PC-98�V���[�Y�� CPU
�� 4���� CPU (386�݊� CPU) ��
NEC���p�\�R���APC-98�V���[�Y�ɊW���� CPU�ɂ��ĉ摜�Ƌ��ɓK���ɉ�����Ă��܂��B
2016/ 2/ 23 �X�V
�� 4���� CPU (386�݊� CPU) ��
CPU�A�N�Z�����[�^�u�[���̉����B
- Cyrix Cx486DLC
- Cyrix Cx486SLC
- Cyrix Cx486DRx2
- Cyrix Cx486SRx2/ Cx486SLC2
- Texas Instruments 486SXL/ 486SXL2
- Texas Instruments 486SXLC/ 486SXLC2
- IBM 486SLC/ SLC2
- IBM 486DLC2/ DLC3 (BLUE LIGHTNING)
- IIT XC87SLC, XC87DLC
- IIT 487DLX
- Intel Rapid CAD
| ���� | Cx486DLC | �������[�J�[ | Cyrix�A�e�L�T�X�E�C���X�c�������c (TI)�A�i�V���i���E�Z�~�R���_�N�^�[ |
|---|---|---|---|
 |
���\�N���� | 1992/6 | |
| �`�� | 132pin PGA | ||
| �o�X�� | 32�r�b�g | ||
| �g�����W�X�^�� | 600,000 | ||
| �����Z�p | �| | ||
| �Ή��\�P�b�g | 132pin PGA�\�P�b�g | ||
| ����N���b�N (MHz) |
25/ 33/ 40 | ||
| �V�X�e���N���b�N (MHz) |
25/ 33/ 40 | ||
| �ꎟ�L���b�V�������� | 1KB | ||
| �L���b�V�������� | �Ȃ� | ||
| ����d�� | 5V | ||
| ���߃Z�b�g | 32�r�b�g���� (IA-32) | ||
| PC-98�{�� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| PC-98�I�v�V���� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| CPU�A�N�Z�����[�^ �ł̗̍p�� |
I-O DATA �@PK-486D (20MHz: PC-9801DA/RA,PC-98RL�Ή�) (�ꕔ TX486DLC)�@PK-A486/87DW3 (32MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DA/RA�Ή�) �@PK-A486/87DW4 (40MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DA/RA21/RA51�Ή�) �@PK-A486DW3 (32MHz: PC-9801DA/RA�Ή�) �@PK-A486DW4 (40MHz: PC-9801DA/RA21/RA51�Ή�) �@PK-Cx486/87D (40MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DA/RA21/RA51�Ή�) �@PK-Cx486DE (40MHz: PC-9801DA/RA21/RA51�Ή�) �@PK-EP486D (32MHz: PC-386G/GS/S/V�Ή�) �@�� �^�Ԗ����Ɂu-L�v���t�����͉��i����i Buffalo/ MELCO �@HDA-20W (20MHz: PC-9801DA/RA�Ή�)�@HDA-C20W (20MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DA/RA�Ή�) �@HDL-16W (32MHz: PC-9801DA/RA, PC-98RL�Ή��BPC-9801RA2/RA5�ȊO�̋@��� 16MHz���̂ݑΉ�) �@HDL-20W (40MHz: PC-9801DA/RA, PC-98RL�Ή�) �@HRX-12T (36MHz: PC-9801DX/EX/RX�Ή�) �@HRX-12W (24MHz: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX�Ή�) �@HRX-12WY (24MHz: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX�Ή�) �@HRX-C12T (36MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DX/EX/RX�Ή�) �@HRX-C12TY (36MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DX/EX/RX�Ή�) �@HRX-C12W (24MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX�Ή�) �@HSP-32D (32MHz: PC-9801DA/RA, PC-98RL�Ή�) �@HSP-DL (20MHz: PC-9801DA/RA, PC-98RL�Ή�) �@HSS-DL7 (25MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: �{�� CPU�Z�b�g) �A�b�v�O���[�h�e�N�m���W�[ (UGT) (Kingston��) �@UGT1000C (20MHz: PC-9801DA/RA�Ή�)�@UGT1100C (20MHz: PC-9801RL�Ή�) �@UGT1200C (25MHz: PC-386G/S�Ή�) �@UGT10x2C33 (32MHz: PC-9801DA/RA�Ή�) �@UGT10x2C40 (40MHz: PC-9801RL�Ή�) �@UGT10x2C50 (50MHz: PC-386G/S�Ή�) �A�Z�b�g�R�A �@Cobra 486C (32MHz: PC-9801DA/RA�Ή�)�@Cobra 486CF (32MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DA/RA�Ή�) �@Cobra 486CFL (32MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-98RL�Ή�) �G���R�� �@UP486DLC25 (20MHz: PC-9801DA/RA, PC-98RL�Ή�)���ɂ���������B |
||
| ���l | L1�L���b�V�������������B | ||
| ��� |
�@Cx486DLC�͍����\�ȃR�v���Z�b�T�uFasMath�v�Œm���x�̗L�����t�@�u���X�����̊�Ƃ� Cyrix�� Intel�� i386DX�����o�[�X�G���W�j�A�����O�ʼn�͂��ĊJ������ x86�n 32�r�b�g CPU�Bi386�ƃs���݊��� i386�̕��i��v�𗬗p���Ē�R�X�g�� 486���̍����\�ȃp�\�R���Y�ł���Ƃ����R���Z�v�g�ŊJ�����ꂽ�B����_�͗ǂ��������A���o�[�X�G���W�j�A�����O�̂� AMD���ɔ�ׂ� Intel���i�Ƃ̌݊��������Ⴂ�B �@�����Ƃ��Ă� i386DX�ƃs���݊��ł���Ȃ���i486���l�ɃL���b�V���������� 1KB������ 486���߃Z�b�g��lj����� 486�݊��� CPU�œ��N���b�N�� i386DX�ɔ�ׂč����ȏ������������Ă���B �@�܂��A�{ CPU�����̃L���b�V���������́A1KB�Ə��Ȃ��Ȃ��� i486�ɂ͖�����i�̃��C�g�o�b�N�@�\�ɑΉ����Ă���A���Z��������x�ɃL���b�V���������̃f�[�^�����C���������ɏ������ނ̂ł͖����A���Z�������I���܂ł̓A�N�Z�X�������ȃL���b�V�����������̃f�[�^���������������A������̃^�C�~���O�ł܂Ƃ߂ă��C���������ɏ����߂����Ƃ� CPU�̊O�ɗL���r�I�x�����C���������Ƃ̃A�N�Z�X���������Ƃŏ��Ȃ��L���b�V�����������t���Ɋ��p���Ă���B �@�������A���C�g�o�b�N�@�\�ɂ����_������ DMA�A�N�Z�X�Ɖ]���� CPU���W���Ȃ��o�H�Ń������̃f�[�^�������������Ă��܂��Ə����߂��̍ۂɕs�������N���ăf�[�^��j�Ă��܂����ꂪ����B���ہADMA�A�N�Z�X���� FDD��o�X�}�X�^�]���� I/F�ŃA�N�Z�X����������ƌ듮�삷��B �@����āA�n�[�h�E�F�A�Ƃ��Ă� i386���痬�p�ł�����̂� BIOS���̃\�t�g�E�F�A�ł́A�{�� i386DX�ɂ͓����L���b�V���������𐧌䂷��@�\�͖����̂ŁA���̃L���b�V����������K�ɐ���ł���悤�ɐv�������K�v���L�����B�����L���b�V���������̏�Ԃł̉��Z���x�́Ai386DX�Ɠ��������Ⴂ�B �@BIOS�� Cx486DLC�ɑΉ����Ă��Ȃ��ꍇ�ł������ɃL���b�V���������̐ݒ��ύX���邱�Ƃ��ł���̂ŁA�N����ɕʓr�\�t�g�E�F�A (�h���C�o) �Őݒ��ύX�����䂷��ō��̃p�t�H�[�}���X�������ł���悤�ɂȂ�B �@�Ȃ��ATX486DLC�́ACyrix���v���� CPU�̐����𐿂������Ă����e�L�T�X�E�C���X�c�������c���ACx486DLC�����Ѓu�����h�Ƃ��Đ����������̂ŃR�A�͓���ł���BCyrix�͌� TI�̎Ј����ݗ�������Ђł�����ATI�Ƃ͕��ꉏ�Ńg���u�����x�X�N���Ă����B �@���� CPU�͍����ł͉��i������ i386DX�ƍڂ��ւ��ē����L���b�V�����������\�t�g�E�F�A�Ő��䂷�邾���ŁAi486�ɂ͋y�Ȃ����̂� 20���` 30�����x�̍��������ł�����ɕ֗��� CPU�Ƃ��čL�܂����B�����A�����ɂ͑㗝�X�������������߂Ɍl�A���Ȃǂɂ���ē��肷��ȊO�ɓ��肷����@�������������A���[�U�Ԃ̌������i�݃L���b�V���������𐧌䂷��c�[���Ƃ��ăt���[�̕����������o�ꂵ IPL�N����uHSB�v�Ƃ������ċN���c�[���� OS���킸�L���b�V�������L���ɂł���l�ɂȂ����B���̌��ʂƂ��� Cyrix (�T�C���b�N�X) �̖��O�����[�U�[�̊ԂōL���m��n��悤�ɂȂ����B �@���� CPU�̓o��ɂ��A�ȑO�͋Z�p�̗͂L��R�A�ȃ��[�U�Ɍ����Ă��� CPU�����ɂ��A�b�v�O���[�h�Ƃ�����@����ʂ̃��[�U�ɂ���r�I�e�Ղɍs����悤�ɂȂ�A�����̎��Ӌ@�탁�[�J�[�������� 286�@�� 386�@�p CPU�A�N�Z�����[�^�������B����ɂ���ꎟ CPU�A�N�Z�����[�^�u�[�����K���B(^-^) �@Cx486DLC�̕]���́A���{�����ł͗����Ŏ�y�ȃA�b�v�O���[�h��i�� CPU�A�N�Z�����[�^�Ƃ��čL�܂����ׂɔ�r�I�D�ӓI�Ȉӌ����������A�č����ł́A���o�[�X�G���W�j�A�����O�� 486��搂��Ȃ���� i486SX�ɋy�Ȃ����Z�̏������x�AIBM�� 486�݊� CPU�Ɨގ����鐻�i���ACyrix�� TI�̊m���Ȃǂ���A���Ȃ�ے�I�ȕ]���ɂȂ��Ă���B �@CPU�A�N�Z�����[�^�Ƃ��Ďg�p����Ƃ��́Ai386DX��蔭�M���������ߍ��N���b�N�œ��삷�鐻�i�ɂ��Ă͕��M�p�Ƀq�[�g�V���N�����t���������ǂ��B |
||
�@����2��g�b�v�� Back�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y�[�W�g�b�v�� Top�@
| ���� | Cx486SLC | �������[�J�[ | Cyrix�A�e�L�T�X�E�C���X�c�������c (TI)�A�i�V���i���E�Z�~�R���_�N�^�[ |
|---|---|---|---|
 |
���\�N���� | 1992/5 | |
| �`�� | 100pin QFP | ||
| �o�X�� | 16�r�b�g (���� 32�r�b�g) | ||
| �g�����W�X�^�� | 600,000 | ||
| �����Z�p | �| | ||
| �Ή��\�P�b�g | �| | ||
| ����N���b�N (MHz) |
20/ 25/ 33 | ||
| �V�X�e���N���b�N (MHz) |
20/ 25/ 33 | ||
| �ꎟ�L���b�V�������� | 1KB | ||
| �L���b�V�������� | �Ȃ� | ||
| ����d�� | 5V 3.3V(��d���� 486SLC/e-V) |
||
| ���߃Z�b�g | 32�r�b�g���� (IA-32) | ||
| PC-98�{�� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| PC-98�I�v�V���� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| CPU�A�N�Z�����[�^ �ł̗̍p�� |
I-O DATA �@PK-V486/87SW2 (24MHz: PC-286V�Ή�)�@PK-VF486/87SW2 (24MHz: PC-286VF�Ή�) �@PK-VG486/87SW3 (32MHz: PC-286VG�Ή�) �@PK-X486SG (20MHz: PC-9801VX�Ή�: PGA�p) �@PK-X486SL (24MHz: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX�Ή�: PLCC�p) �@�� �^�Ԗ����Ɂu-L�v���t�����͉��i����i Buffalo/ MELCO �@HSL-25 (25MHz: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX�Ή�)(�ꕔ TX486SLC����)�@HSL-C25 (25MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX�Ή�)(�ꕔ TX486SLC����) �@HSP-4SD25 (25MHz: PC-9801DX/EX/RX/UX�Ή�) �@HSP-4SD33 (33MHz: PC-9801DX/EX/RX�Ή�) �@HSP-4SV25 (25MHz: PC-9801RX/VX, PC-98XL�Ή�) �@HSS-4S7V25 (25MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801RX/VX, PC-98XL�Ή�) �@HSS-4S7D25 (25MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DX/EX/RX/UX�Ή�) �@HSS-4S7D33 (33MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DX/EX/RX�Ή�) ABM �@486GT-NSE/C (32MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801NS/E�Ή�)�@486GT-R(24MHz: PC-9801DX/EX/RX/UX�Ή�) �@486GT-X �@486SLGT-MK�U �A�b�v�O���[�h�e�N�m���W�[ (UGT) (Kingston��) �@UGT2425xC-E286 (25MHz: Kingston 386SX Now)�@UGT2425xC-N98 (25MHz: Kingston 386SX Now) �@UGT2433xC-E286 (33MHz: Kingston 386SX Now) �@UGT2433xC-N98 (33MHz: Kingston 386SX Now) �A�Z�b�g�R�A �@VIPER(20MHz: PC-9801CS/DS/ES/FS/FX/RS, PC-9821modelS1/S2, PC-98GS�Ή�)�@VIPER 486(20MHz: PC-9801CS/DS/ES/FS/FX/RS, PC-9821modelS1/S2, PC-98GS, PC-386M/VR�Ή�) �@VIPER 486-e (16MHz: PC-386P/GE�Ή�) �@VIPER 486-r (16MHz: PC-9801US/LS, PC-386LS/LSR�Ή�) �@VIPER 486-s �@VIPER 486-t (25MHz: PC-9801NC�Ή�) �@VIPER 486-t Rev.B (20MHz: PC-9801NC�Ή�) ����d�@�Y�� �@EP48633HC�@LS486C �@RX486C (24MHz: PC-9801RX�Ή�) �@VX486C (24MHz: PC-9801VX�Ή�) ���ɂ���������B |
||
| ���l | L1�L���b�V�������������B | ||
| ��� | �@Cx486SLC�� Cyrix�� Intel�� i386SX�����o�[�X�G���W�j�A�����O�ʼn�͂��ĊJ������ x86�n 32�r�b�g CPU�B�{ CPU�́Ai386SX�ƃs���݊��� i386SX�̕��i��v�𗬗p���Ē�R�X�g�� 486SX���̍����\�ȃp�\�R�� (��Ƀ��o�C���^�C�v) �Y�ł���Ƃ����R���Z�v�g�ŊJ�����ꂽ�B32bit CPU�ł͂��邪�Ai386SX�ƃs���݊��̂ɊO���f�[�^�o�X�͔����� 16bit�ƂȂ��Ă���B�{ CPU�ł� i486SX���l�ɃL���b�V���������� 1KB�������Ă��邪�A���̓����L���b�V���������� Intel���i�ƈႢ�����Ƃ��Ă͐�i�̃��C�g�o�b�N�@�\�𓋍ڂ��Ă���B�ڍׂ́ACx486DLC�̍����Q�Ƃ̂��ƁB �@���� 486SLC�̖��̂����� CPU�Ƃ��Ă� IBM���i�����݂��邪�ACx486SLC�� IBM 486SLC�Ƃ͌q����͂Ȃ��ACyrix���i�̃L���b�V���������̗e�ʂ� 1KB�Ə��Ȃ��B�܂��A1993�N 11���� Cx486SLC�̌�p�Ƃ��ē�{������� Cx486SLC2���o�ꂵ�����A������� IBM 486SLC2�Ƃ͕ʕ��� CPU�ŃL���b�V���������� 1KB�Ə��Ȃ��̂Œ��ӂ̂��ƁB���̂�����킵�������� Cx486SRx2�ɕύX����Ă���B �@���_�Ƃ��ẮA���o�[�X�G���W�j�A�����O�̂� AMD���ɔ�ׂ� Intel���i�Ƃ̌݊��������Ⴂ���ƂƁA��i�̃��C�g�o�b�N�Ή��L���b�V���������̈��萫��������������ƁA�W���d���ł͔��M����������������������B �@�Ȃ��ATX486SLC�́A�`�b�v�̐����𐿂������Ă��� TI�� Cx486SLC�����Ѓu�����h�Ƃ��Đ����������̂ŃR�A�͓���ł���B �@Cyrix�́A�{ CPU�� i386SX�̐v���قڂ��̂܂܂� i486SX�����̃p�\�R��������Ɗe�p�\�R�����[�J�[�ɔ��荞�݂��|�����B���o�[�X�G���W�j�A�����O�� i486���݂̐��\��搂��c�Ƃ̎�@�ɖ�肪����A�č����ɉ����ăf�X�N�g�b�v PC��A�A�b�v�O���[�h�̗p�r�ł͍̗p���L����Ȃ��������̂̒�d���� Cx486SLC�̓o����L�胂�o�C�� PC�ł͍̗p���L�������B �@����A���{�����ł̓��[�J�[���p�\�R���ɍ̗p����鎖�͖w�ǂȂ��������̂́A�p���[���[�U�[�B�� i386SX�s���݊��Ɖ]���_�ɒ��ڂ��]���p�\�R���� i386SX��u����������̂ł͂Ȃ����Ɖ]���l������A�������s�� i386SX�Ɠ\�芷���ăh���C�o�\�t�g�ƕ��p���ē��삳���邱�Ƃɐ����������Ⴊ�G���ŏЉ���Ɩ��������� Cx486SLC�͈�����ڂ𗁂т鎖�ƂȂ����B �@���������ł́ACyrix�̔̔��㗝�X�������l�A���⋤���w���ɂ��ꊇ�����ɗ���ȊO�ɓ��肷����@�͂Ȃ��������A�p���[���[�U�[�� PC�p�[�c�V���b�v�̋��͂ŏH�t���𒆐S�ɏ��X�ɗ��ʗʂ����������̃��[�U�[�ɍL�܂����BQFP�� i386SX�̓}�U�[�{�[�h�ɒ��ڔ��c�t������Ă��蔼�c�W���g�p���Ȃ��ƌ������鎖���ł��Ȃ��̂ŁACPU�ɔ킹��^�C�v�� CPU�A�N�Z�����[�^���o�ꂷ��܂ł́A���͂Ō��������ݐ����̔����ɐ��������ҁACPU�����łȂ��p�\�R���܂ł�����������ҁA�悤�₭���������ߓ\�芷���̉������s����V���b�v�ɔߊ�̈˗����͂����҂Ɣߊ삱�������̃h���}�����������ŌJ��L����ꂽ�B �@���āA286�@�� 486���������������̂͂��� CPU�̂������Ƃ����ĊԈႢ�����BCx486SLC�� i386SX�ƃs���݊��� i386SX�̕��i��v�𗬗p���Ĉ��� 486�@�Y�ł���Ƃ������̂����A�����悤�ȃR���Z�v�g�� i386SX�� 80286�̊W������B���̓_�ɒ��ڂ���� Cx486SLC�� i386SX�ƒu���������Ai386SX�� 80286�ƒu����������̂ł���ACx486SLC�� 80286�ƒu����������Ƃ����}�������藧�B���҂͒��ڃs���݊��ł͂Ȃ����A�L���b�V������������̕K�v���L���Ď��ۂɂ͂����ȒP�ɂ͂����Ȃ������̂����A��i�I�ȃ��[�U�[�Ǝ��Ӌ@�탁�[�J�[�����͂��Ď������d�˂����ʂƂ��Ēu�������ɐ����BCx486SLC�� 286�@�p CPU�A�N�Z�����[�^�ɍL���̗p����ACx486SLC�͈�ۂ̔������� 286�@�̋~����ƂȂ����B �@����� 286�@�p�� CPU�A�N�Z�����[�^�� CPU���{�[�h�ɓ��ڂ��A�}�U�[�{�[�h�̃V�X�e���N���b�N���{�[�h��� 2�{���ɂ��镨��A�{�[�h��̃N���X�^�����g�p���}�U�[�{�[�h�Ƃ͓Ɨ������N���b�N�œ��삷�镨�Ȃǂ�����A�p�t�H�[�}���X�͂��ꂼ������ɈقȂ�B80286�͗l�X�ȃp�b�P�[�W�^�C�v��������̂� i386SX�Ƃ͈Ⴂ�\�P�b�g�ɍڂ��Ă�����O�����Ƃ��ł���̂ŁALCC�^�C�v�������� CPU�A�N�Z�����[�^�̎��t�����e�ՂƉ]�������L���Ă�����͈�ʂ̃��[�U�[�ɂ��L���Z�������B �@����CPU�́ACx486DLC���l�Ƀt���b�s�B�f�B�X�N�ɂ�� IPL�N���ŃL���b�V�������L���ɂł���c�[��������̂� OS���킸�֗��ł���B80286 12MHz�� Cx486SLC 24MHz���r����� 35�����x���Z�����������������B �@���Ȃ݂ɁA�M�҂����߂Ďg���� CPU�A�N�Z�����[�^�͂���CPU���g���� I-O DATA���� PK-X486SL�ŁAPC-9821Xa16/W30��V�i�ōw������܂Œ������Ɨ��p���Ă����B(^-^) |
||
�@����2��g�b�v�� Back�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y�[�W�g�b�v�� Top�@
| ���� | Cx486DRx2 | �������[�J�[ | Cyrix�A�e�L�T�X�E�C���X�c�������c (TI) |
|---|---|---|---|
 |
���\�N���� | �| | |
| �`�� | 132pin PGA | ||
| �o�X�� | 32�r�b�g | ||
| �g�����W�X�^�� | �| | ||
| �����Z�p | �| | ||
| �Ή��\�P�b�g | 132pin PGA�\�P�b�g | ||
| ����N���b�N (MHz) |
33/ 40/ 50/ 66 | ||
| �V�X�e���N���b�N (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33 | ||
| �ꎟ�L���b�V�������� | 1KB | ||
| �L���b�V�������� | �Ȃ� | ||
| ����d�� | 5V | ||
| ���߃Z�b�g | 32�r�b�g���� (IA-32) | ||
| PC-98�{�� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| PC-98�I�v�V���� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| CPU�A�N�Z�����[�^ �ł̗̍p�� |
I-O DATA �@PK-Cx486DRX2 (40MHz: PC-9801DA/RA, PC-98RL, PC-386/V/GS�Ή�) |
||
| ���l | L1�L���b�V���������A�N���b�N�_�u���[���ځB | ||
| ��� | �@Cx486DRx2�� Cyrix���J������ x86�n 32�r�b�g CPU�� Cx486DLC�R�A�ɃN���b�N�_�u���[��������� i386DX�s���݊��� CPU�B486���߂ւ̑Ή��� 1KB�̃��C�g�o�b�N�Ή��L���b�V���������̓����ɂ��Ă͕ύX�͂Ȃ��B �@�N���b�N�_�u���[�Ƃ́ACPU�̃R�A�����ŃV�X�e���N���b�N (�O���N���b�N) �� 2�{���Ɉ����グ����̂ŁA�V�X�e���N���b�N���Ⴂ�܂܂ł����Z�������x���グ����@�Ƃ��Č��݂ł͈�ʓI�ɂȂ��Ă���B �@���� CPU�́A�ቿ�i�Ɖ]������������{�����ł� CPU�A�N�Z�����[�^�Ƃ��Ď��v���L�����B�]���̃V�X�e���N���b�N�̒Ⴂ�{�̂ł��N���b�N�A�b�v���̊댯�ȉ����������� CPU���ڂ������邾���ō��N���b�N����ɂ��p���[�A�b�v���o����B �@���C�g�o�b�N�Ή��L���b�V���������̃R���g���[���ɂ� BIOS�ɂ��T�|�[�g���K�v�Ȃ̂ŁA���̋@�\�������p�\�R���Ŏg�p����ɂ͉��炩�̃\�t�g�E�F�A�œ����L���b�V����L���ɂ��Đ��䂷��K�v������B �@����N���b�N�̏㏸�ɂ��]���� Cx486DLC��蔭�M���������߁A�K�{�ł͖������̂̍��N���b�N�œ��삷�鐻�i�ɂ��Ă͕��M�p�Ƀq�[�g�V���N�����t���������ǂ��B |
||
�@����2��g�b�v�� Back�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y�[�W�g�b�v�� Top�@
| ���� | Cx486SRx2/ Cx486SLC2 | �������[�J�[ | Cyrix�A�e�L�T�X�E�C���X�c�������c (TI) |
|---|---|---|---|
 |
���\�N���� | 1993/12/27 | |
| �`�� | 100pin QFP | ||
| �o�X�� | 16�r�b�g (���� 32�r�b�g) | ||
| �g�����W�X�^�� | �| | ||
| �����Z�p | �| | ||
| �Ή��\�P�b�g | �| | ||
| ����N���b�N (MHz) |
33/ 40/ 50 | ||
| �V�X�e���N���b�N (MHz) |
16/ 20/ 25 | ||
| �ꎟ�L���b�V�������� | 1KB | ||
| �L���b�V�������� | �Ȃ� | ||
| ����d�� | 5V | ||
| ���߃Z�b�g | 32�r�b�g���� (IA-32) | ||
| PC-98�{�� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| PC-98�I�v�V���� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| CPU�A�N�Z�����[�^ �ł̗̍p�� |
I-O DATA �@PK-Cx486SRX2 (40MHz: PC-9801DS/ES/FS/FX/RS, PC-9821modelS1/S2�Ή�) |
||
| ���l | L1�L���b�V���������A�N���b�N�_�u���[�A�o�X�ϊ���H���ځB | ||
| ��� | �@Cx486SRx2�ACx486SLC2�� Cyrix���J���� Cx486SLC�̃R�A�ɃN���b�N�_�u���[��������� i386SX�s���݊��� x86�n 32�r�b�g CPU�B486���߂ւ̑Ή��� 1KB�̃L���b�V���������̓����ɂ��Ă͕ύX�͂Ȃ��B�����̃��C�g�o�b�N�Ή��L���b�V���������̓p�\�R���� BIOS���Ή����Ă��Ȃ��ꍇ�́A�ʓr���炩�̃\�t�g�E�F�A�Ő��䂷��K�v������B �@�N���b�N�_�u���[�Ƃ́ACPU�̃R�A�����ŁA�V�X�e�� (�O��) �N���b�N�� 2�{���Ɉ����グ����̂ŁA�V�X�e���N���b�N���Ⴂ�ꍇ�ł������ɓ��삳���邱�Ƃ��ł���Ƃ������_�����B����ȍ~ CPU�̓��쑬�x���グ���@�Ƃ��Ĉ�ʓI�ɂȂ��Ă���B �@���� Cx486SRx2�� i386SX�@�� CPU�����p�ɏd�ꂽ�B286�@�� 386DX�@�ł� CPU���\�P�b�g�ɓ��ڂ���Ă���̂���ʓI�Ȃ̂Ŏ�芷���鎖���o���邪�Ai386SX�n����CPU�̓}�U�[�{�[�h�Ƀn���_�t������Ă���̂� Cx486DRx2�̂悤�ɂ͊ȒP�ɍڂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�����ŁAQFP�� i386SX�̏�ɒ��ڔ킹�ACPU�̎���ɂ킸���ɘI�o���Ă���s������{�̂�������^�C�v�� CPU�A�N�Z�����[�^���������ꂽ�B �@���� CPU�A�N�Z�����[�^���g���ꍇ�ɂ́A���� i386SX�� C�X�e�b�v�ȍ~�łȂ���i386SX���~�����邱�Ƃ��o���Ȃ��̂Ŏg���O�Ɏ��O�ɒ��ׂĂ����K�v������B���Ȃ݂ɁAI-O DATA�ł͂���� DOS�ォ�画�ʂ���v���O������z�z���Ă����B |
||
�@����2��g�b�v�� Back�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y�[�W�g�b�v�� Top�@
| ���� | 486SXL/ 486SXL2 | �������[�J�[ | �e�L�T�X�E�C���X�c�������c�A�A�i�V���i���E�Z�~�R���_�N�^�[ |
|---|---|---|---|
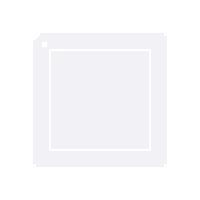 |
���\�N���� | �| | |
| �`�� | 132pin PGA | ||
| �o�X�� | 32�r�b�g | ||
| �g�����W�X�^�� | �| | ||
| �����Z�p | �| | ||
| �Ή��\�P�b�g | �| | ||
| ����N���b�N (MHz) |
16/ 20 /33 /40 /50 (486SXL) 33/ 40/ 50/ 66 (486SXL2) |
||
| �V�X�e���N���b�N (MHz) |
16/ 20 /33 /40 /50 (486SXL) 33/ 40/ 50/ 66 (486SXL2) |
||
| �ꎟ�L���b�V�������� | 8KB | ||
| �L���b�V�������� | �Ȃ� | ||
| ����d�� | 5V | ||
| ���߃Z�b�g | 32�r�b�g���� (IA-32) | ||
| PC-98�{�� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| PC-98�I�v�V���� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| CPU�A�N�Z�����[�^ �ł̗̍p�� |
486SXL���� Buffalo/ MELCO �@HRD-PC12T (36MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DX/EX/RX�Ή�)�@HDA-PC20W (40MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DA/RA�Ή�) �@HDA-PC20WJ (40MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DA/RA�Ή�) 486SXL2���� �A�Z�b�g�R�A �@VIPER X TypeP (40MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DA/RA, PC-386S/V�Ή�) |
||
| ���l | L1�L���b�V���������A�N���b�N�_�u���[ (TX486SXLC2�̂�) �o�X�ϊ���H�����B | ||
| ��� | �@486SXL�� Cyrix�� CPU�����Ă����e�L�T�X�E�C���X�c�������c (TI) �� Cx486DLC���x�[�X��CPU�ɓ�������Ă���L���b�V���������� 8KB�ɑ��������� x86�n 32�r�b�g CPU�B486���߂ւ̑Ή��A���C�g�o�b�N�Ή����A�����L���b�V���������̑��ʈȊO�ɕύX�͂Ȃ��B�����L���b�V�������������ʂ���Ă��镪�A���N���b�N�� i386DX�� Cx486DLC�ɔ�ׂăp�t�H�[�}���X�������B �@����A486SXL2�́A486SXL�ɃN���b�N�_�u���[��������� CPU�ŁACPU�����ł̓V�X�e���N���b�N�� 2�{���œ��삷��B����ɂ��V�X�e���N���b�N�̒Ⴂ�]���̃}�U�[�{�[�h�ł����̂܂܂̐v�ō�����������������p�\�R�������邱�Ƃ��ł���B�܂��A�����L���b�V���������̓��쑬�x���R�A�N���b�N�ɓ�������̂ł���Ƀp�t�H�[�}���X�����シ��B �@������� CPU�ł� BIOS���{ CPU�ɑΉ����Ă��Ȃ��ꍇ�́A�{���̐��\�������o�����߂ɓ����L���b�V���������̓�������炩�̃\�t�g�E�F�A�Ő��䂷��K�v������_�͋��ʂ��Ă���B���� CPU�͏]���� i386DX���ڂ����V�X�e���ɉ����� CPU�A�N�Z�����[�^�Ƃ��ăp���[�A�b�v��ړI�Ƃ�����u�������p�r�ɂ����p���ꂽ�B �@�e�L�T�X�E�C���X�c�������c�� 486�݊� CPU�ɂ́Ai486SX�s���݊��� 486SXL��486SXL2�����݂���Bi386DX�s���݊��̖{���i�Ɩ��O�������Ȃ̂Ŕ��ɂ�₱�����B(^ ^;; |
||
�@����2��g�b�v�� Back�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y�[�W�g�b�v�� Top�@
| ���� | 486SXLC/ 486SXLC2 | �������[�J�[ | �e�L�T�X�E�C���X�c�������c |
|---|---|---|---|
 |
���\�N���� | �| | |
| �`�� | 100pin QFP | ||
| �o�X�� | 16�r�b�g (���� 32�r�b�g) | ||
| �g�����W�X�^�� | �| | ||
| �����Z�p | �| | ||
| �Ή��\�P�b�g | �| | ||
| ����N���b�N (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33 /40 (486SXLC) 33/ 40/ 50 (486SXLC2) |
||
| �V�X�e���N���b�N (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33 /40 (486SXLC) 16/ 20/ 25 (486SXLC2) |
||
| �ꎟ�L���b�V�������� | 8KB | ||
| �L���b�V�������� | �Ȃ� | ||
| ����d�� | 5V | ||
| ���߃Z�b�g | 32�r�b�g���� (IA-32) | ||
| PC-98�{�� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| PC-98�I�v�V���� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| CPU�A�N�Z�����[�^ �ł̗̍p�� |
486SXLC2���� �A�Z�b�g�R�A �@VIPER P-28 (40MHz: PC-9801DS/ES/FS/FX/RS, PC-9821modelS1/modelS2�Ή�)�@VIPER P-28r (32MHz: PC-9801US�Ή�) �@VIPER X TypeS (32MHz: PC-9801CS/DS/ES/FS/FX/RS, PC-9821modelS1/modelS2, PC-98GS, PC-386GE/M/VR�Ή�) Evergreen (�����ł̓A�b�v�O���[�h�e�N�m���W�[ (UGT) ���̔�) �@REVTO486 386SX2+ |
||
| ���l | L1�L���b�V���������A�N���b�N�_�u���[ (TX486SXLC2�̂�) �o�X�ϊ���H�����B | ||
| ��� | �@486SXLC�� Cyrix�� CPU�����Ă����e�L�T�X�E�C���X�c�������c (TI) �� Cx486SLC���x�[�X��CPU�ɓ�������Ă���L���b�V���������� 8KB�ɑ��������� x86�n 32�r�b�g CPU�B486���߂ւ̑Ή��A���C�g�o�b�N�Ή����A�����L���b�V���������̑��ʈȊO�ɕύX�͂Ȃ��B�����L���b�V�������������ʂ���Ă��镪�A���N���b�N�� i386SX�� Cx486SLC�ɔ�ׂăp�t�H�[�}���X�������B �@����A486SXLC2�́A486SXLC�ɃN���b�N�_�u���[��������� CPU�ŁACPU�����ł̓V�X�e���N���b�N�� 2�{���œ��삷��B����ɂ��V�X�e���N���b�N�̒Ⴂ�]���̃}�U�[�{�[�h�ł����̂܂܂̐v�ō�����������������p�\�R�������邱�Ƃ��ł���B�܂��A�����L���b�V���������̓��쑬�x���R�A�N���b�N�ɓ�������̂ł���Ƀp�t�H�[�}���X�����シ��B �@������� CPU�ł� BIOS���{ CPU�ɑΉ����Ă��Ȃ��ꍇ�́A�{���̐��\�������o�����߂ɓ����L���b�V���������̓�������炩�̃\�t�g�E�F�A�Ő��䂷��K�v������_�͋��ʂ��Ă���B �@���� CPU�́Ai386SX�n����CPU��u��������ۂɏd�ꂽ���Ai386SX�̓\�P�b�g���ł͂Ȃ��ׁACx486DRx2�̂悤�ɊȒP�ɍڂ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̂��߁AQFP�� i386SX�̏�ɒ��ڔ킹�ACPU�̎���ɂ킸���ɘI�o���Ă���s������{�̂������� CPU�A�N�Z�����[�^���������ꂽ�B �@�Ȃ��A���� CPU�A�N�Z�����[�^���g���ꍇ�ɂ́A���� i386SX�� C�X�e�b�v�ȍ~�łȂ��� i386SX���~�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂Ŏg���O�Ɏ��O�ɒ��ׂĂ����K�v������B���Ȃ݂ɁAI-O DATA�ł́A����� DOS�ォ�画�ʂ���v���O������z�z���Ă����B |
||
�@����2��g�b�v�� Back�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y�[�W�g�b�v�� Top�@
| ���� | 486SLC/ 486SLC2 | �������[�J�[ | IBM |
|---|---|---|---|
 |
���\�N���� | 1992 | |
| �`�� | 100pin QFP | ||
| �o�X�� | 16�r�b�g (���� 32�r�b�g) | ||
| �g�����W�X�^�� | 1,349,000 | ||
| �����Z�p | 0.8microne CMOS process | ||
| �Ή��\�P�b�g | �| | ||
| ����N���b�N (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33 (486SLC) 33/ 40/ 50/ 66 (486SLC2) |
||
| �V�X�e���N���b�N (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33 | ||
| �ꎟ�L���b�V�������� | 16KB | ||
| �L���b�V�������� | �Ȃ� | ||
| ����d�� (�R�A��/ I/O��) |
3.6V/ 5V | ||
| ���߃Z�b�g | 32�r�b�g���� (IA-32) | ||
| PC-98�{�� �ł̗̍p�� |
�Ȃ� | ||
| PC-98�I�v�V���� �ł̗̍p�� |
�Ȃ� | ||
| CPU�A�N�Z�����[�^ �ł̗̍p�� |
486SLC2���� I-O DATA �@PK-X486S50 (48MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX)�@PK-X486S50-L (48MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX) Buffalo/ MELCO �@HRX-C12Q (48MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX)�A�Z�b�g�R�A �@VIPER jet Type1 (40MHz: PC-9801FS/FX, PC-9821modelS1/modelS2�Ή�)�@VIPER jet Type2 (40MHz: PC-9801DS/ES/RS�Ή�) �@VIPER jet Type3 (32MHz: PC-386GE�Ή�) �A�b�v�O���[�h�e�N�m���W�[ (UGT) �@360PBN-S3 (48MHz: PC-386GE�Ή�) |
||
| ���l | L1�L���b�V���������A�N���b�N�_�u���[�A�o�X�ϊ���H�����B | ||
| ��� | �@486SLC�́AIBM�����А��p�\�R����p�� Intel�Ɛ����ɒ�g���ĊJ������ CPU�� 386SLC���x�[�X�� 486���߂ɑΉ������� ���ǔł� x86�n 32�r�b�g CPU�B�O���f�[�^�o�X�� 16�r�b�g�A�����f�[�^�o�X�� 32�r�b�g�A16KB�̓����L���b�V���Ƃ�������{�I�ȕ����͏]���ƕς��Ȃ����AIntel�Ɛ����Ɍ_�ĊJ�����Ă��鎖���L���Ă������x�͍����A���̎�� 486�݊� CPU�Ƃ��Ă̓g�b�v�N���X�̐��\�œ��N���b�N�� i486SX�ɕC�G���鍂�����Z�����\�͂����B �@�܂��A486SLC2�́A486SLC�ɃN���b�N�_�u���[��������A��荂���N���b�N�œ��삷��悤�ɉ��ǂ��ꂽ���́BCPU�����ł̓V�X�e���N���b�N�� 2�{���œ��삷��B �@����d���̓R�A���� 3.6V�ɉ������Ă��邾���łȂ��ABIOS���瓮�쒆�ł��ׂ�������ݒ肪�ύX�ł��邽�ߏ]���� CPU�ɔ�ׂēd�͏���}�����Ă���B �@�`�b�v�ɂ� 486SLC2�Ƃ����\�L�ł͂Ȃ��A���b�g�i���o�[���Ƌ��ɁuIBM 14 PQ�v���Ə�����Ă���B���� INTEL�̖��̂����L����Ă���_�����̃��[�J�[�̌݊� CPU�ɂȂ��O�ϓI�ȓ����ł���B �@���� CPU�� IBM���p�\�R����p�Ƃ��ďo�ׂ��ꂽ���A�ꕔ�ł� CPU�A�N�Z�����[�^�Ƃ��Ă̎��v���L�����B�{ CPU�� i386SX�Ƃ̓f�[�^�o�X�����ʂł��镨�̃s���݊��ł͂Ȃ��ׂɏ]���̃p�\�R���ɒP���ɍڂ������ē��삳���鎖�͂ł��Ȃ����Ai386SX�� 80286�̃o�X�ɕϊ��ł���Z�p���m������� CPU�A�N�Z�����[�^�ɂ��̗p���ꂽ�B���̎�� 486�݊� CPU�Ƃ��Ă͍ŋ��ŁA���� 286�@�� 386SX�@�ł͂��� CPU���̗p���Ă���A�N�Z�����[�^���ŋ��ɂȂ�B������L���� I-O DATA�̐��i�� 1999�N 11���܂ł̒������ԃJ�^���O�ɍڂ��Ă����B �@CPU�A�N�Z�����[�^�Ƃ��Ă̌��_�́ACx486SLC�ƃL���b�V������̎d�l���قȂ�̂Ń��[�J�[���p�ӂ�����p�̃h���C�o���K�v�ɂȂ�Ƃ���ŁACyrix�Ō�����悤�� IPL�N�����o���Ȃ��B���̂��ߓ����L���b�V����L���ɂł��� OS���AMS-DOS�� Windows�Ɍ����Ă��܂��̂Ő�p OS�̃Q�[�����ɂ͌����Ȃ��B �@�܂��A����d�����Ⴂ����ɔ��M�������q�[�g�V���N�͕K�{�ł͖������̂̎��t���������ǂ��B(^ ^;; �@���Ȃ݂ɁAPK-486S50-L (4�{��) �𓋍ڂ��� PC-9801RX21 (80286�A12MHz) �ł́A�������Z�����̃p�t�H�[�}���X�Ɍ���� i486SX 40MHz�����ɍ����������B |
||
�@����2��g�b�v�� Back�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y�[�W�g�b�v�� Top�@
| ���� | 486DLC2/ 486DLC3 | �������[�J�[ | IBM |
|---|---|---|---|
 |
���\�N���� | 1994 | |
| �`�� | 132pin QFP | ||
| �o�X�� | 32�r�b�g | ||
| �g�����W�X�^�� | 1,400,000 | ||
| �����Z�p | 0.8microne CMOS process | ||
| �Ή��\�P�b�g | �| | ||
| ����N���b�N (MHz) |
40/ 50/ 66 (486DLC2) 60/ 75/ 100 (486DLC3) |
||
| �V�X�e���N���b�N (MHz) |
20/ 25/ 33 | ||
| �ꎟ�L���b�V�������� | 16KB | ||
| �L���b�V�������� | �Ȃ� | ||
| ����d�� (�R�A��/ I/O��) |
3.3V/ 5V | ||
| ���߃Z�b�g | 32�r�b�g���� (IA-32) | ||
| PC-98�{�� �ł̗̍p�� |
�Ȃ� | ||
| PC-98�I�v�V���� �ł̗̍p�� |
�Ȃ� | ||
| CPU�A�N�Z�����[�^ �ł̗̍p�� |
486DLC3���� I-O DATA �@PK-A486BL60 (60MHz: PC-9801DA/RA, PC-98RL�Ή�)�@PK-A486BL60-L (60MHz: PC-9801DA/RA, PC-98RL�Ή�) �@PK-A486BL75 (64MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DA/RA, PC-98RL�Ή�) �@PK-A486BL75-L (64MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DA/RA, PC-98RL�Ή�) Buffalo/ MELCO �@HDA-C20TJ (60MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-9801DA/RA�Ή�)�@HRL-20TS (60MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-98RL�Ή�) �@HRL-20TY (60MHz�A�R�v���Z�b�T�t��: PC-98RL�Ή�) Evergreen (�����ł̓A�b�v�O���[�h�e�N�m���W�[ (UGT) ���̔�) �@REVTO486 386SX3+ (60MHz: 386SX�@�Ή�)�@REVTO486 386DX3+ (60MHz: 386DX�@�Ή�) |
||
| ���l | L1�L���b�V���������A�N���b�N�_�u���[�iDLC2)�A�N���b�N�g���v���[���� (DLC3)�B | ||
| ��� | �@486DLC2/ 486DLC3�́AIBM�� Intel�ƒ�g���ĊJ������ 486SLC�� ���S�� 32�r�b�g�ł� CPU�B���̑��� 486���߂ɑΉ��A16KB�̓����L���b�V���Ƃ�������{�I�ȕ����͕ς��Ȃ��B486SLC���l�� 486�݊� CPU�Ƃ��Ă̓g�b�v�N���X�̐��\�œ��N���b�N�� i486SX�ɕC�G���鍂�����Z�����\�͂����B����̂ɕʖ��Ƃ��āuBlue Lightning BLX2/ BLX3�v�Ƃ������O�����B �@486DLC2 (BLX2) �̓N���b�N�_�u���[��������V�X�e���N���b�N�� 2�{���ŁA486DLC3 (BLX3) �̓N���b�N�g���v���[��������V�X�e���N���b�N�� 3�{���œ��삷�邪�AiDX2���̓���{���Œ�̈�ʂ� 486�n CPU�Ƃ͈قȂ����͈͓̔��� BIOS��\�t�g�E�F�A����A�N�e�B�u�ɓ���{���̕ύX���\�ɂȂ��Ă���B �@�`�b�v�ɂ� 486SLC2���l�ɕi���̕\�L�ł͂Ȃ��A���b�g�i���o�[���Ƌ��ɁuIBM 14 PQ�v���Ə�����Ă���B���� INTEL�̖��̂����L����Ă���_�����̃��[�J�[�̌݊� CPU�ɂȂ��O�ϓI�ȓ����ł���B �@�}�U�[�{�[�h�����Ă��� ETEQ MICROSYSTEMS�Ђ́AIBM�ƒ�g������ CPU���x�[�X�Ƃ��� PC/AT�݊��@�̎��Ӄ`�b�v����荞�� CPU ET486DLC2���J�����Ă���B �@���� CPU�� IBM���p�\�R����p�Ƃ��ďo�ׂ��ꂽ���A��� i386DX�ւ̒u��������Z�p���m������� CPU�A�N�Z�����[�^�ł��̗p���ꂽ�BI-O DATA�̐��i�ł́A���� CPU�̓����ł��铮��{�����\�t�g�E�F�A�ŕύX�ł���������������āu���Z�b�g�R���g���[���@�\�v�Ə̂��p�\�R���{�̂̃��Z�b�g�̉œ���N���b�N��ύX�ł��鐻�i�������B486DLC3�����g�p���������̐��i�ł� CPU�̓����N���b�N�������ł��Ȃ�̃p�t�H�[�}���X�A�b�v��̊��ł��邪�A����ŕ��������_���Z�ł͊O���ɐݒu����CPU�����Ⴂ�N���b�N�̃R�v���Z�b�T�ɗ����Ă��邽�߂ɁACPU�R�A���x�Ɠ����� iDX2�ɔ�ׂăR�v���Z�b�T�������Ђ��ς��ʂ��������������_���Z�𑽗p���� Windows�n OS�ł͎v���قǃp�t�H�[�}���X���L�тȂ������B �@���̌�Ai386�s���݊� 486CPU�̏I���Ƌ��� i386DX�� 32�r�b�g�o�X�� iDX2�ɒu���������@���m������� i386DX�@�p CPU�A�N�Z�����[�^�ł� i486�n CPU�ɐ�ւ���Ă������B �@�Ȃ��ACPU�A�N�Z�����[�^�ł́A�{�� BIOS���s���ׂ��L���b�V������⓮��{���ݒ��ʓr�\�t�g�E�F�A (�h���C�o) �Ő��䂵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�K�ȃh���C�o���C���X�g�[�����Ȃ��ƌ��� i386DX���x�̃p�t�H�[�}���X�ɂȂ��Ă��܂������łȂ�����N���b�N�� 1�{������̂܂܂Ȃ̂ŗv���ӁBMS-DOS�AWindows�ȊO�� OS�Ŏg�p����ꍇ�ɂ́uHSB�v�Ƃ��������ݒ�\�t�g�E�F�A���g�����̈�H�v���K�v�ɂȂ�B �@IBM�� Intel�Ƃ̒�g���I������� Cyrix�� x86�n CPU�`�b�v�̐������e�L�T�X�E�C���X�c�������c�ɑ����Đ����������BIBM 486DX2�� Blue Lightning DX2�́A�{ CPU�Ɩ��O�͎��Ă��邪 Cyrix�̋����� IBM�̃u�����h�ŏo�ׂ��� Cx486DX2�̂��Ƃ� 486DLC2/ DLC3�͂������ iDX2�Ƃ��S���̕ʕ��ł���B |
||
�@����2��g�b�v�� Back�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y�[�W�g�b�v�� Top�@
| ���� | XC87SLC�AXC87DLC | �������[�J�[ | IIT (Integrated Information Technology), LC Technology |
|---|---|---|---|
 |
���\�N���� | �| | |
| �`�� | 68pin PGA (XC87DLC) 68pin PLCC |
||
| �o�X�� | 32�r�b�g (XC87DLC) 16�r�b�g (���� 32�r�b�g) (XC87SLC) |
||
| �g�����W�X�^�� | �| | ||
| �����Z�p | �| | ||
| �Ή��\�P�b�g | 68pin PGA�R�v���\�P�b�g (XC87DLC) 68pin PLCC�R�v���\�P�b�g |
||
| ����N���b�N (MHz) |
20/ 25/ 33/ 40 (XC87DLC, XC87SLC) 50 (487DLX25/50) |
||
| �V�X�e���N���b�N (MHz) |
20/ 25/ 33/ 40 (XC87DLC, XC87SLC) 25 (487DLX25/50) |
||
| �ꎟ�L���b�V�������� | �Ȃ� | ||
| �L���b�V�������� | �Ȃ� | ||
| ����d�� | 5V | ||
| ���߃Z�b�g | x87�A3C87�Ǝ��g������ | ||
| PC-98�{�� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| PC-98�I�v�V���� �ł̗̍p�� |
�@�Ȃ� | ||
| CPU�A�N�Z�����[�^ �ł̗̍p�� |
�@�s�� | ||
| ���l | �N���b�N�_�u���[���� (487DLX25/50) | ||
| ��� |
�@IIT XC87SLC�́A�č� IIT (Integrated Information Technology, Inc.) �� IBM 486SLC�� Cyrix Cx486SLC�Ɖ]���� 386�s���݊� 486�v���Z�b�T�����ɔ̔������R�v���Z�b�T�BIBM 486DLC�ACyrix Cx486DLC�����ɂ�XC87DLC������B �@�]���� 3C87 (i387DX�݊�)�A3C87SX (i387SX�݊�)�Ƃ̈Ⴂ�͖��݂̂̂Ǝv����B486�Œlj����ꂽ���߂ɑΉ����Ă��邩�͕s���B486SLC/ DLC�����ƌ����Ă����ۂ� i387�݊��Ȃ̂� 386�@�ł���薳���g�p�ł���B �@�R�A�� IIT�Ǝ��̐v�ɂȂ��Ă��� i387�ɔ�ׂĉ��Z�����\�͂������A���N���b�N����ɑΉ����Ă��邾���łȂ������ IIT�Ǝ��̒lj����߂𓋍ڂ��Ă���B��� 3D CAD�����ɉ��Z�����̍�������⏕���镨�ł������� IIT�Ǝ� (Cyrix�� ULSI���i�ɂ͖���) �Ɖ]�������L���ĕ��y�͂����c�O�Ȃ��痘�p�ł���s�̂̃A�v���P�[�V�����͖w�ǂȂ������B�p�b�P�[�W�łɂ̓h���C�o�����[�߂�ꂽ�t���b�s�[�f�B�X�N���t�����Ă����B �@XC87DLC�AXC87SLC�͌��4C87DLC�A4C87SLC�Ɩ��̂��ύX���ꂽ�B�p�b�P�[�W�� 486SLC�����͒ʏ�� PLCC�A����� 486DLC�����̐��i�̓R�X�g�_�E�������ʂ̃Z���~�b�N�ł͖����������p�b�P�[�W�̑��� PLCC�^�C�v�A����ɂ͂��� PLCC�� PGA�ϊ��\�P�b�g�ɔ��c�t���������̂܂ł���B �@IIT�� 486SLC/ DLC�����R�v���Z�b�T���i�Q�̒��ł����ڂ��ׂ��͍ŏI���i�� 487DLX25/50�ŃR�v���Z�b�T�ł���Ȃ� Cx486DRX2�̗l�ɓ����ɃN���b�N�_�u���[�𓋍ڂ��V�X�e���N���b�N 25MHz�ɑΉ�����{���� 50MHz�œ��삷��Bx86�n�̃R�v���Z�b�T�Ƃ��Ă͍ō���Ƃ�������B �@���ۂ� 286�@�� 386�@�ŃN���b�N�_�u���[��������� 486�݊�CPU + �R�v���Z�b�T�̑g�ݍ��킹��A�R�v���Z�b�T���� CPU�A�N�Z�����[�^�Ɍ������ăx���`�}�[�N�����ƕ��������_���Z�����̓R�A�N���b�N���x���O���N���b�N�Ɉˑ�����̂ő����ĕ��������_���Z�֘A�̐��l���Ⴍ�p�t�H�[�}���X��������X���ɂ���B �@IIT�̃R�v���Z�b�T�͎�ɕč����ŗ��ʂ����{�����ɗA���㗝�X������������A�����œ��肷��ɂ́A�C�O�Ōl�A�����邩���R�W�����N���̓X��Ō�����ȊO�ɓ���ł����i�͖����̂ŁA�m��l���m�郌�A�ȑ��݂ƂȂ��Ă���B���A�ŗL���Ă����v���������ߓ���͂قڕs�\�ƌ����Ă悢�B �@�R�v���Z�b�T�Ƃ͐��l�f�[�^�v���Z�b�T�Ƃ����� CPU�Ƌ������ē��삵�A�����Z���̕��������_���Z�̏�������ɒS�����ĉ��Z�����������������B������ CPU�̉��i�����ɍ������������_���Z�𑽗p����A�v���P�[�V������ CAD��w�p�v�Z���̓���ȕ��Ɍ����Ă��������L���āA�}�U�[�{�[�h�ɐ�p�̃\�P�b�g��݂��������ŕʔ���̃I�v�V�����Ƃ��ċ�������鎖����ʓI�������B �@�����ACPU�̉��Z�����\�͂����߂��@�Ƃ��ẮA�V�X�e���N���b�N (����F�x�[�X�N���b�N) �����������鎖���B��̕��@�ŗL�������A50MHz�ȏ�ň��肵�ē��삳���邱�Ƃ��Z�p�I�ɓ���������߁A���P�̍�Ƃ��� CPU�R�A������������������Ƃ�����@�������悤�ɂȂ����B����I�Ȏ�@�Ƃ��č̗p���L���� IBM 486SLC2�ACyrix Cx486DRx2�ATexas Instruments TX486SXLC�Ɖ]�����R�A�N���b�N (�����N���b�N) ���V�X�e���N���b�N�̓�{�œ��삷��N���b�N�_�u���[��������� CPU�����X�o�ꂵ�n�߂�ƁA�V���Ȗ��_�Ƃ��� CPU�̃R�A�N���b�N�ƃR�v���Z�b�T�̓���N���b�N���� (2:1) �ɂȂ�A����N���b�N�����������ĉ��Z�����������ɂȂ��� CPU�̍����p�t�H�[�}���X���A����N���b�N�̒x���R�v���Z�b�T���������������Ă��܂����u�g�[�^���Ƃ��Ẵp�t�H�[�}���X���ቺ���Ă��܂��Ƃ������_����������ƂȂ����B �@���ۂ� 486�݊� CPU + �R�v���Z�b�T�̑g�ݍ��킹�Ńx���`�}�[�N�����ƕ��������_���Z�����̓R�A�N���b�N���x���O���N���b�N�Ɉˑ�����̂ő����ĕ��������_���Z�֘A�̐��l���Ⴂ�B���̌X���� IBM 486DLC3�� �R�v���Z�b�T�̑g�ݍ��킹�Ō����ɂȂ�B �@Intel�͂�������z���� CPU�P�����オ���Ă��܂����� i486 (i486DX�Ai487)�ł́A�R�v���Z�b�T�̋@�\�� CPU�R�A�Ɠ����œ��삷��悤�� FPU (���������_���Z���j�b�g) �Ƃ��ăR�A�ɓ��������B���̐헪�͑听���� ��{���œ��삷�� i486DX2 (iDX2) �ł́A�����N���b�N�Ɠ������鍂���ȕ��������_���Z������ x86�݊� CPU���[�J�[��傫�������������|�I�ȍ����p�t�H�[�}���X�����������B �@�܂��A���� GUI (Graphical User Interface) �� OS�Ƃ��� Microsoft�� Windows�����y���n�߂������ł�����A�]���͓���̃��[�U�[�݂̗̂p�r�ł��������������_���Z������ OS�̉摜�����ň�ʃ��[�U�[����������߂���悤�ɂȂ����������y�ɔ��Ԃ������鎖�ƂȂ� iDX2�͑�q�b�g�A�����ʂ�������ɂ�R�X�g���ቺ���]�� CPU����̍ڂ������̎��v�����܂�A���ɂ�Intel�����ł͐��Y���Ԃɍ���Ȃ��Ȃ��Ē�g��� IBM�ɐ������O��������̃x�X�g�Z���[�ƂȂ����B����ȍ~�͂قڑS�Ă� CPU�ŃR�v���Z�b�T�� CPU�R�A�ɓ�������邱�ƂƂȂ�Ax86�n CPU�̃R�v���Z�b�T�͏I�����}���鎖�ƂȂ����B �@���̗���� Cyrix�AIIT�AULSI�Ȃǂ̃R�v���Z�b�T����ɐ����̔����Ă������[�J�[�̐�s���ɑ傫�ȉe����^���鎖�ƂƂȂ��Ă��܂��B������� Cyrix�̓t�@�u���X (���O�̍H��������Ȃ�) �̃R�X�g�̈����ƒ����d�͂�� x86�n CPU�Ɋ��H�����o���AIIT�̓l�b�g���[�N�̕��y�Ƃ������������z���ăe���r��c�p�`�b�v��v���Đ����c���}�����B���̌�ACyrix�̓i�V���i���Z�~�R���_�N�^�[�ɂ�锃�����o�čŏI�I�ɑ�p�� VIA�ɔ������ꂽ���̂̍��͐��������AIIT�� 8x8, Inc.�ɎЖ����ς�������̂� VoIP�̃T�[�r�X�v���o�C�_�ƋƑԂ�ς��������Ă���BULSI SYSTEMS (�����n�̉�ЂƂ͕ʂ̃A�����J�̊��) �ɂ��Ă͒肩�ł͖����B �@���Ȃ݂ɁACPU�̃R�v���Z�b�T�͋ߔN�����̂̂낵���グ����B���Ă̊w�p���Z�����͌��� HPC (High Performance Computing) �ƌĂ�A�����ȕ��������_���Z�������s���摜�����p�̃`�b�v�� GPGPU (General Purpuse GPU) �Ƃ��ăO���t�B�b�N�����ȊO�̉��Z�����ɗ��p���悤�Ƃ������ꂪ����B��������Z�����ɓ��������� CPU�̃R�v���Z�b�T�ɂ���Ɖ]�����̂� nVidia�́uTesla�v�AIntel�́uXeon Phi�v�Ȃǂ��o�ꂵ�Ă���B |
||
�@����2��g�b�v�� Back�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y�[�W�g�b�v�� Top�@
PC-98, PC-9801, PC-9821, PC-H98, PC-9800, FC-9801, FC-9821, FC-9800, SV-98, 98SERVER, VALUESTAR, CanBe, 98NOTE���́ANEC�Ђ̏��W�܂��͓o�^���W�ł��B
i486, Pentium/Pro/II/III, MMX, ODP, Celeron�́Aintel�Ђ̏��W�܂��͓o�^���W�ł��B
Windows, MS-DOS�� Microsoft�Ђ̏��W�܂��͓o�^���W�ł��B
���̑��A���i���A�^�ԓ��́A��ʂɊe���[�J�[�̏��W�܂��͓o�^���W�ł��B
