PC-98シリーズと CPU 第 3世代 CPU編
PC-98 series and CPU. The volume 3rd generation CPU
NEC製パソコン、PC-98シリーズに関係する CPUについて画像と共に適当に解説しています。
2017/ 4/ 10 更新
第 3世代 CPU
この世代で x86系 CPUの基礎が固まった。
- Intel i386DX
- Intel i386SX
- Intel i386SL (PC-98)
- Intel i387DX
- Intel i387SX
- Intel i387SL
- AMD Am386DX/DXL
- AMD Am386SX/SXL
- IBM 386SLC
- VM Technology VM386SX+
- Cyrix 83D87, 87DLC
- Cyrix 83S87, 87SLC
- IIT 3C87, 3C87SX
- ULSI US83C87, US83S87
| 名称 | i386DX (i80386) | 製造メーカー | Intel |
|---|---|---|---|
 |
発表年月日 | 1985/10/17 | |
| 形状 | 132pin PGA, 132pin QFP | ||
| バス幅 | 32ビット | ||
| トランジスタ数 | 275,000 | ||
| 製造技術 | 1.5microne process 1microne process |
||
| 対応ソケット | 132pin PGAソケット | ||
| 動作クロック (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33 | ||
| システムクロック (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33 | ||
| 一次キャッシュメモリ | なし | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||
| PC-98本体 での採用例 |
PC-9801DA/RA PC-98RL/XL^2 PC-H98model60/U60/70 FC-9801A OP-98X/20H |
||
| PC-98オプション での採用例 |
PC-98XL2-07 (16MHz: PC-98XL2機能拡張プロセッサ) PC-98XL2-07L (16MHz: PC-98XL2機能拡張プロセッサ) |
||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
京都マイクロコンピュータ Turbo-386シリーズ (PC-9800シリーズ対応) |
||
| 備考 | − | ||
| 解説 |
i80386は 80286の後継として Intelが開発した CPUで、バス幅が従来の倍の 32ビットに拡張され 32ビットデータセットを扱う 初の x86 CPUとして登場した。演算処理能力は 80286に比べ 40%〜 50%程度向上している。当時は 1個あたり数十万円という極めて高価な CPUであったため、外部データバス幅を半分に削減した廉価版の i386SXが登場し、商標権の保護 (数字のみでは登録できない) と製品を区別するため i386DXと名称が変わった。 i386ではバス幅の拡大と共に使用できるメモリの容量も 32ビットの最大 4GBまで拡張された。この i386から 32ビット命令セットが加わり現在の CPUの基礎となった。また、速度の遅いメインメモリと CPU間の速度差を埋めるために当時は非常に高価では有ったが、最大 64KBの SRAMキャッシュメモリの接続をサポートし、これを搭載する事でさらなる処理速度の向上を可能にした。コプロセッサはこちらも 32ビットに対応した i387DXをサポートする。 i386で追加された機能の中でも特に仮想 86モード (CPU一つの中に 8086がいくつもあるように動作させる) という機能は、Microsoftの Windows等マルチタスク OSでは欠かせない物となっている。ちなみに、Windows 95は i386でも非常に遅いながら動作する。(^ ^;; 良く K6-IIIや Celeron等の CPUで内蔵している一次キャッシュメモリを切ると 386相当の動作になると言うのは、x86系 CPUの基礎ともなったこの CPUに由来する。 なお、初期の i80386には 32ビット命令 (仮想 86モード) にバグの有るものが存在した。その為、32ビット命令を使用しないように CPUの表面に「16 BIT S/W ONLY」と刻印されたものがある。また、初期ロットに於いて「ΣΣ」と刻印のある物はバグが無い事の証となっている。 この CPUは、製造プロセスが途中で 1.5μ (ミクロン) プロセスから 1μプロセスに変更されダイサイズが縮小化された。参考写真のように動作クロック表示の後に「IV」と刻印されている物は、1μプロセスで製造された物となっている。一般に製造プロセスが微細化すると消費電力が下がり発熱も少なくなる他、ダイの面積が小さくなる事で一つのシリコンウェハからより多くのコアを作れるようになり歩留まりが良く製造コストが下がる。 Intelは 80286まではセカンドソース品の生産を許可していたが、製造に余力が出てきた事からこの i80386からは一変して認めない方針を取る。よって、同じ 386を謳っていても AMDや Intelと正式に提携した IBMであってもインテルのコアとは同一ではない。これによって互換性に問題が出る事もあるが、逆に製造メーカー各社の個性が出るようになった。 PC-9800シリーズでは、当時の最上位機として 1987年 10月に登場した PC-98XL^2 (ダブル) に初めて搭載された。この機種はハイレゾモードとノーマルモードを持った特殊なマシンで、非常に高価であった為に企業ユーザが中心で一般には影が薄い存在となっている。しかし、搭載していた i80386は 32ビット命令にバグが有るものだったので、翌年の 10月に PC-98XL2機能拡張プロセッサ「PC-98XL2-07」としてバグの無い i80386がオプション扱いで発売される事となった。事実上の有償アップデートである。 PC-9800シリーズで i386搭載マシンが普及する切っ掛けとなったのは、筺体デザインをベージュ基調からアイボリーに一新して 1988年 7月発売された PC-9801RA2/ RA5で 386搭載マシンとしては手ごろな価格だったので大きな注目を集め PC-9800シリーズと i386マシンの普及に一役買った。 さて、ここで登場する PC-H98 (ハイパー 98) シリーズは、まさにバブル絶頂期の 1990年 1月に新しい拡張バスの 32ビットバスマスタの NESAバス (Cバスは 16ビット) や最高級の CPUを搭載したハイレゾモード搭載の最上位シリーズとして PC-H98 model70が初登場した。最上位機らしく横長の巨大な本体が特徴で、オフィスコンピュータ N5200シリーズが基になっている。 H98シリーズでは、AGDCや、E^2GCを搭載し、従来の 4,096色中 16色の画面モードに加え、1677万色中 256色 (初期のモデルではオプションの 256色ボードが必要) の画面モードが追加され、PC-9800シリーズで、初めて 14.6MBのメモリの壁 (80286時代の名残) を破るなど注目を集めた。 ところが、コネクタ類が従来の PC-9800型番のパソコンと異なるうえ、本体価格が極めて高いなどの理由によって、業務用途ではそれなりに支持があったが、一般層までには普及に至らなかったという言わば幻の PC-9800シリーズ。この NECの H98シリーズ推進戦略は裏目に出てしまい、アンチ NECユーザの増加や EPSON製 PC-98互換機にシェアを奪われる一因にもなる。 SV-H98、OP-98シリーズは、ハイパー 98を PCサーバ用途として企業ユーザ向けに売り出したもの。他にも、オフィスコンピュータ用に N5200 model98シリーズ等、一言に H98といっても多くのバリエーションが存在する。 ちなみに、H98シリーズの i386DXモデルではキャッシュメモリを内蔵しているため、ノーマルモード専用機よりパフォーマンスが高い。 この CPUを採用した CPUアクセラレータとしては、幾つかのメーカーから Cバススロットに取り付ける CPUボードとして存在する。Cバス接続の製品はいずれもデータの転送に 16ビットバスを介するため処理能力は向上するが i386本来の性能を活かせない。どちらかと言うと i386の新機能を使う物と割り切った方が良い。 |
||
| 名称 | i386SX | 製造メーカー | Intel |
|---|---|---|---|
 |
発表年月日 | 1988/6/16 | |
| 形状 | 100pin QFP | ||
| バス幅 | 16ビット (内部 32ビット) | ||
| トランジスタ数 | 275,000 | ||
| 製造技術 | 1.5microne process 1microne process |
||
| 対応ソケット | 132pin PGAソケット | ||
| 動作クロック (MHz) |
12/ 16/ 20/ 25/ 33 | ||
| システムクロック (MHz) |
12/ 16/ 20/ 25/ 33 | ||
| 一次キャッシュメモリ | なし | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||
| PC-98本体 での採用例 |
PC-9801CS/DS/ES/FS/FX/RS/T/US PC-9801LS, NC, NS, NS/E, NS/EZ, NS/L PC-9821model1/2 PC-98GS FC-9801F/S RC-9801 |
||
| PC-98オプション での採用例 |
なし | ||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
ABM 386SXGT (10MHz: 286機対応) |
||
| 備考 | バス変換回路搭載。 | ||
| 解説 |
i386SXは Intelの戦略として当時非常に高価だった32ビット CPUの i80386の普及を後押しし、AMD等のセカンドソース品の高クロック版 80286の普及を阻止するために、コア部をそのままにして外部アドレス幅を24ビット、外部データバスを 16ビットに削減した廉価版として開発された。CPUのコスト削減の意味合いもあるが、従来の 16ビット CPU 80286用の設計や部品を流用できて安価に 32ビットパソコンを製造できるという大きなメリットを持つ。 一方で、外部とのデータのやり取りにバス変換回路を通す為にタイミング合わせにウェイトが入るので処理速度が低下したり、動作クロックをあまり上げられないというデメリットがある。演算処理能力は、i386DXを 100%とすると i386SXは 80%〜 90%程度になる。コプロセッサは、i387DXとは別に i387SXと i387SLをサポートする。 後期ロットから Cステップという物が登場し、CPUのピンを制御することにより CPUの動作を止められるようになった。i386SX用の CPUアクセラレータを搭載する場合には Cステップ以降の i386SXのみに対応しているので注意を要する。Cステップ品を判別するためには、I-O DATAが提供した判別ツールを実行する方法がベストだが、外観から見分ける方法としては「C STEP」と表記がある物、「i386 SX」のロゴが入っている物は、C STEP品とみて間違いない。 i386SXのコアをベースとする派生製品は幾つかあり、省電力管理機能を充実させたノートパソコン向けの i386SLや、省電力管理機能に加え組み込み機器向けに制御関連の周辺チップをセットにした i386EX、省電力管理機能とメモリ管理ユニット (MMU)を内蔵した i386CXなどバリエーションが多いのも i386SXの特徴となっている。 前述の通り、i386SXは 80286と外部データバス幅が 16ビットと同じで互換性が高く登場した当時に、実際に 80286を i386SXに置き換えるという改造がコアなユーザの間で流行った。ピン互換ではない為に単純には成功しなかったものの試行錯誤によって成功。その実験結果を受けて ABMから i386SXを搭載した 80286機用の 386SXGTという CPU置き換え型 CPUアクセラレータが登場した。 80286から 386SXへの載せ換えでは演算処理速度はほぼ変わらないが、仮想 86モードや、386命令が使用できると云うメリットが有った。高価な半面、目に見えて処理速度が向上する訳でもないので一般のユーザーにはそれ程の広がりも見せなかった。この時点では、CPUアクセラレータブームの序章に過ぎなかったのだが、その後、米国のファブレス半導体企業であるサイリックス (Cyrix)が 386とピン互換の 486系 CPUをリリースすると事態は一変し CPUアクセラレータブームが巻き起こることとなる。 実際に 80286を i386SXに交換しても演算処理能力の向上と言う意味では微々たるものだったものの仮想 86モードが使えるようになる事で Windows3.1を動作させる事が出来るようになるメリットが大きかった。 ちなみに、PC-98で Windows95が動く最低ラインは、80286を検出すると停止する仕様なので i386SX 12MHzと言われている。なお、EPSON製の PC-98互換機では、動作中に CPUの動作速度を変更できるため、Windows95起動後に V30モードに切り替えるという荒業を使ってもっと遅く動作させることができる。(爆 |
||
| 名称 | i386SL (PC-98) | 製造メーカー | Intel |
|---|---|---|---|
 |
発表年月日 | 1990/10/15 | |
| 形状 | 196pin QFP | ||
| バス幅 | 16ビット (内部 32ビット) | ||
| トランジスタ数 | 855,000 | ||
| 製造技術 | 1microne process | ||
| 対応ソケット | − | ||
| 動作クロック (MHz) |
20 | ||
| システムクロック (MHz) |
20 | ||
| 一次キャッシュメモリ | なし | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||
| PC-98本体 での採用例 |
PC-9801NS/T | ||
| PC-98オプション での採用例 |
なし | ||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
なし | ||
| 備考 | バス変換回路、省電力機能搭載 (SMM) | ||
| 解説 |
i386SL (PC-98)は Intelが NECと共同開発し i386SXをベースに PC-9800シリーズのメモリコントローラや拡張バスといった周辺回路を集積、省電力を目的としたシステムマネジメントモード (SMM) を追加したノートパソコン向けの x86系 32ビット CPU。 バッテリ駆動時の電力消費節減に有効なレジュームやサスペンド機能が使用できる。演算能力や省電力以外の機能は i386SXと変わらないが、CPU周辺回路や SMM機能の追加により集積するトランジスタ数は 3倍にも増加した。 i386SL (PC-98)は、i386SX同様にコプロセッサもサポートしており i387SLが対応する。 演算処理能力としては、i386SXベースとなっているが周辺回路をコアに統合したためか処理速度は速く、I-O DATAのベンチマークソフト「INSPECT」で i386SL(98)搭載の PC-9801NS/Tと i386SX搭載の PC-9801NS/Lの整数演算 (Dhryston) テストを比較すると同じ動作クロックでありながら NS/Tの方が 40%程度高い数値を示す。これは、i386DXの PC-9801DAをも 20%上回る数値である。 一方、省電力性能は i386SX 16MHzで同じバッテリパックを使用する先代の PC-9801NS/Eと比べ目を見張るほどの向上はないものの動作クロックの上昇の割には、パワーセーブモードにすることで 30分程度長くバッテリ駆動ができるようになっていることから省電力機能もなかなかの物を持っている。 ちなみに、本来の i386SLは IBMと共同開発し PC/AT互換機専用に設計されていて ISAバスをサポートしている。この 「i386SL (PC-98)」 は、NECの ノートパソコン PC-9801NS/Tの開発に当たって、Intelに作らせた (共同開発した) PC-9800シリーズ専用 CPUで、CPU表面に 「PC-98」 のロゴが入っていて当時の NECの強さを物語っている。(^ ^;; この CPUを搭載した PC-9801NS/Tは、先述の通り演算処理能力がデスクトップパソコン並みに高く動作が軽快でバッテリの持ちも良いとあって大成功し出荷台数も多く 98NOTEの普及と知名度のアップに功を奏した。 |
||
| 名称 | i387DX (i80387) | 製造メーカー | Intel |
|---|---|---|---|
 |
発表年月日 | 1986 | |
| 形状 | 68pin PGA | ||
| バス幅 | 32ビット | ||
| トランジスタ数 | 120,000 | ||
| 製造技術 | 1.5microne process 1microne process |
||
| 対応ソケット | 68pin PGAコプロソケット | ||
| 動作クロック (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33 | ||
| システムクロック (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33 | ||
| 一次キャッシュメモリ | なし | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | x87 | ||
| PC-98本体 での採用例 |
なし | ||
| PC-98オプション での採用例 |
PC-9801-65 (16MHz) PC-98RL-03 (20MHz) PC-98XL2-03 (16MHz) PC-H98-E01 (33MHz) PC-H98-E01U (33MHz) |
||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
なし | ||
| 備考 | − | ||
| 解説 | i387DXは x86系 32ビット CPU i386DX用の Intel純正コプロセッサ。i386DXに合わせてこちらも 32ビットに拡張されている。これも当初は i80387と呼ばれていた。これを取りつけることで CPUと協調して動作し関数演算等を専門に行い浮動小数点演算処理が高速化される。 大きさは i386DXよりも若干小さく PGAパッケージの 80286と同じ大きさである。この i387DXの隣に Pentiumを並べるとまるでミニチュアのようである。(^ ^;; i387DX登場以降しばらくして、Cyrix、IIT、ULSI SYSTEMS、Chips and Technologies (C&T) 等互換 CPUメーカーも i387DX互換コプロセッサを販売し始め、同じクロックでも演算処理能力が高く、値段の安い製品が登場してきた為にそちらが注目を集めるようになった。 国内では CPUアクセラレータブーム以降、サイリックス (Cyrix) の知名度が上がると i386ピン互換の 486CPUである Cx486DLCとコプロセッサ Cx38D87のセット販売が功を奏し、i386用コプロセッサとしては Intel純正品よりも Cyrix製品の方が普及が進み i387DXは影が薄い存在となてしまった。 |
||
| 名称 | i387SX | 製造メーカー | Intel |
|---|---|---|---|
 |
発表年月日 | 1990/7 | |
| 形状 | 68pin PLCC、68pin QFP | ||
| バス幅 | 16ビット (内部 32ビット) | ||
| トランジスタ数 | − | ||
| 製造技術 | 1.5microne process 1microne process |
||
| 対応ソケット | 68pin PLCCコプロソケット | ||
| 動作クロック (MHz) |
12/ 16/ 20/ 25/ 33 | ||
| システムクロック (MHz) |
12/ 16/ 20/ 25/ 33 | ||
| 一次キャッシュメモリ | なし | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | x87 | ||
| PC-98本体 での採用例 |
なし | ||
| PC-98オプション での採用例 |
PC-9801-64 (16MHz) PC-9801-64U (16MHz) PC-9801LS-03 (16MHz) |
||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
なし | ||
| 備考 | − | ||
| 解説 |
i387SXは x86系 32ビット CPU i386SX用の Intel純正コプロセッサ。コプロセッサは CPUと協調して動作し関数演算等を専門に行い浮動小数点演算処理が高速化される。i386SXと同様に外部データバスは 16ビットに削減されている。i386DX用の i387DXとは形が違うだけでなく対応バスが異なり全く互換性が無いので購入の際には注意を要する。 なお、CPUアクセラレータでシステムクロックをボード上で 2倍以上に引き上げるタイプの製品にコプロセッサを搭載する場合は、Intel純正 i387SXは 20MHzや 25MHz品が多く 33MHz以上の動作クロックには対応していないので、オーバークロックとなってしまい故障の原因となる可能性がある。この様な用途には、Cyrix等の互換メーカー品を使用した方が良い。 |
||
| 名称 | i387SL | 製造メーカー | Intel |
|---|---|---|---|
 |
発表年月日 | 1992/9 | |
| 形状 | 68pin PLCC、68pin QFP | ||
| バス幅 | 16ビット (内部 32ビット) | ||
| トランジスタ数 | − | ||
| 製造技術 | 1microne process | ||
| 対応ソケット | 68pin PLCCコプロソケット | ||
| 動作クロック (MHz) |
12/ 16/ 20/ 25/ 33 | ||
| システムクロック (MHz) |
12/ 16/ 20/ 25/ 33 | ||
| 一次キャッシュメモリ | なし | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | x87 | ||
| PC-98本体 での採用例 |
なし | ||
| PC-98オプション での採用例 |
20MHz版 PC-9801-66PC-9801-66U PC-9801-66R |
||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
なし | ||
| 備考 | − | ||
| 解説 |
i387SLは、i386SX、i386SL用の Intel純正コプロセッサ。CPUと協調して動作し関数演算等を専門に行い浮動小数点演算処理が高速化される。i386SLと同様に外部データバスは 16ビットに削減されている。i386DX用の i387DXとは形が違うだけでなく対応バスが異なり全く互換性が無いので購入の際には注意を要する。 i387SXとの違いは殆どないので、i386SL搭載の PC-9801NS/Tにはどちらでも使用できる。実際にインテルのコプロセッサのカタログでは、PC-9801NS/Tには i387SX-20が対応する旨の記述がある。 |
||
| 名称 | Am386DX/DXL | 製造メーカー | AMD |
|---|---|---|---|
 |
発表年月日 | 1991/4 | |
| 形状 | 132pin PGA, 132pin QFP | ||
| バス幅 | 32ビット | ||
| トランジスタ数 | 161,000 | ||
| 製造技術 | 1.5microne process 1microne process 0.8microne process |
||
| 対応ソケット | 132pin PGAソケット | ||
| 動作クロック (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33/ 40 | ||
| システムクロック (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33/ 40 | ||
| 一次キャッシュメモリ | 不明 | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||
| PC-98本体 での採用例 |
なし | ||
| PC-98オプション での採用例 |
なし | ||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
不明 | ||
| 備考 | 低消費電力 (Am386DXL) 。 | ||
| 解説 |
Am386DX/DXLは AMD製の i386DX完全互換の x86系 32ビット CPU。コプロセッサは Intel i387DXおよび互換品に対応する。AMD自体は 386用コプロセッサを製造していない。 CPUの性能的には Intel製品と特に変わらないと思われる。Am386DXには Intel製品に無い 40MHzの高クロック版があり、その演算処理能力は i486SX-25MHzに相当すると言われている。40MHz版はコストパフォーマンスの高い製品として低価格パソコンのメーカーに受け入れられた。 消費電力の低い製品があるのも特徴で Am386DXLは低消費電力版で 40MHz版でも 2.1Wの消費電力となっている。また、Intel製品同様に組み込み機器向けに Am386DEという製品も用意されている。 80286以降 Intelは、製造キャパシティの増強が進んだことも有りセカンドソースを認めない方針に転換した。これにより多くの x86互換 CPUメーカーは撤退を余儀なくされたが、AMD、Cyrix等の一部のメーカーは x86系 CPU製造で生き残りを模索し始める。 そこで AMDは、独自に Intel i386DXを解析して i386互換 CPUを作ることに成功したが、マイクロコードを巡ってインテルと紛争状態になりこの結果 Am386を販売できなくなってしまう。 後に販売を再開する事が出来たが、その時点で既に 486が普及し始めていた事も有り、販売の機会を喪失するという大きな痛手を負った。これ以降 AMDは Intelと袂を分かち、抜きつ抜かれつの激しいバトルが展開されるようになる。そして 2012年現在も AMDはやや息切れ感 (CPU内蔵グラフィック機能は秀逸だが) が有るがいまだにバトルは続いている。 日本国内では流通量が少なくマイナーな存在で、PC-9800シリーズでも採用例はないが、価格が Intel製品より安いため CPUアクセラレータに採用された例がある。 ちなみに、他の i386DX互換 CPUとしては、ファブレス半導体企業の Chips and Technologies (C&T) がマイクロコードの著作権を回避するクリーンルーム設計技術で設計した Super386 J38600DX等が有った。しかし、既に AMDや Cyrix等の知名度のあるメーカーが多く参入し互換 CPUを製造していた事も有って事業としては成功しなかった。 その後に C&Tは VGA互換ビデオチップで名を馳せたのだが、何の因果かグラフィックス技術獲得のために 1997年に Intelに買収されてしまった。 |
||
| 名称 | Am386SX/SXL | 製造メーカー | AMD |
|---|---|---|---|
 |
発表年月日 | 1991 (Am386SX) 1991/4/29 (Am386SX/SXL) |
|
| 形状 | 100pin QFP | ||
| バス幅 | 16ビット (内部 32ビット) | ||
| トランジスタ数 | 161,000 | ||
| 製造技術 | 0.8microne process | ||
| 対応ソケット | − | ||
| 動作クロック (MHz) |
20 /25/ 33/ 40 | ||
| システムクロック (MHz) |
20/ 25/ 33/ 40 | ||
| 一次キャッシュメモリ | 不明 | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||
| PC-98本体 での採用例 |
なし | ||
| PC-98オプション での採用例 |
なし | ||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
ABM 386SXGT-MARKIII (25MHz: PC-9801DX/RX対応)アップグレードテクノロジー (UGT) UGT2325xC-E286 (25MHz: PC-286 model0/C/US/UX/X/V/VE/VF/VG/VJ/VS対応)UGT2325xC-N98 (25MHz: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX, PC-98XA/XL対応) UGT2333xC-E286 (33MHz: PC-286 model0/C/US/UX/X/V/VE/VF/VG/VJ/VS対応) UGT2333xC-N98 (33MHz: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX, PC-98XA/XL対応) Kingston SX NOW 50 (PC/AT互換機用)SX NOW 60 (PC/AT互換機用) |
||
| 備考 | バス変換回路搭載、省電力機能搭載 (Am386SXL)。 | ||
| 解説 |
Am386SX/SXLは、AMD製の i386SX完全互換 x86系 32ビット CPUで Intel製品よりも高クロックで動作する製品があるほか、消費電力も 35%程度削減されている。Am386SXLはインテルの i386SL同様の高度な消費電力管理機能が追加されている。 コプロセッサは Intel i387SX、i387SLおよび互換品に対応する。AMDは 386用コプロセッサは製造していない。 80286以降、AMDは Intelの CPUをライセンス生産することができなくなったため、Am386SXはそれまでの CPUとは違い、AMDが i386SXを独自で解析し開発したものとなっている。この経緯については Am386DX/DXLの項目を参照の事。 演算処理能力は Intel製品と特に変わらないと思われる。消費電力の低さ、価格の安さから低価格ノートパソコンなどで採用された。 しかし、Cyrixから i386SXピン互換の 486 CPU Cx486SLCが発売されるとそちらの知名度が一気に上がり、影の薄い存在になってしまった。 日本国内では流通量が少なくマイナーな存在で、PC-9800シリーズでも採用例はないが、価格がインテル製品より安いため CPUアクセラレータに採用された。 ちなみに、CPUアクセラレータの UGT2325xC-N98/E286は、キングストン (Kingston) の 286機用 CPUアクセラレータ SX NOWシリーズを輸入したもので製品に「UGT」のシールが貼られている。また、キャッシュメモリが 16KB載っていた高級モデルもある。 |
||
| 名称 | IBM 386SLC | 製造メーカー | IBM |
|---|---|---|---|
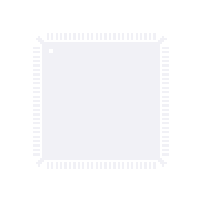 |
発表年月日 | 1991 | |
| 形状 | 100pin QFP | ||
| バス幅 | 16ビット (内部 32ビット) | ||
| トランジスタ数 | − | ||
| 製造技術 | − | ||
| 対応ソケット | − | ||
| 動作クロック (MHz) |
16/ 20/ 25 | ||
| システムクロック (MHz) |
16/ 20/ 25 | ||
| 一次キャッシュメモリ | 8KB | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||
| PC-98本体 での採用例 |
なし | ||
| PC-98オプション での採用例 |
なし | ||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
不明 | ||
| 備考 | バス変換回路、省電力機能搭載。 | ||
| 解説 |
IBM 386SLCは 米 IBM (International Business Machines) が Intelと正式に提携し i386SXベースで開発した i386SX互換の x86系 32ビット CPU。 コア内部は 32ビット、アドレスバス 24ビット、外部データバス 16ビットと i386SX同様でありながらコアと等速で動作する 8KBのキャッシュメモリを内蔵、性能的には Intelの i386DX同等クラスの処理能力と言われている。 また、消費電力が 25MHz版でも 2.5Wと少なく同社の ラップトップパソコンで採用された。 この CPUは、NECと共同開発した i386SL (PC-98) と同様に、IBMが自社のパソコン用に設計したもので i386SXとピン互換では無いので CPUのアップグレード用途として使用することは難しい。 本 CPUは直接 PC-98とは関わりが無いが、CPUアクセラレータとして採用された 486SLC2や 486DLC3の基になった CPUとしては重要な製品である。 |
||
| 名称 | VM386SX+ | 製造メーカー | VM Technology |
|---|---|---|---|
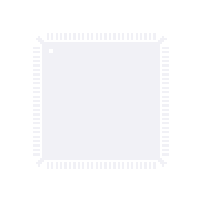 |
発表年月日 | 1991 | |
| 形状 | 100pin QFP | ||
| バス幅 | 16ビット (内部 32ビット) | ||
| トランジスタ数 | 275,000 | ||
| 製造技術 | − | ||
| 対応ソケット | − | ||
| 動作クロック (MHz) |
40 | ||
| システムクロック (MHz) |
40 | ||
| 一次キャッシュメモリ | 不明 | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | 32ビット命令 (IA-32) | ||
| PC-98本体 での採用例 |
なし | ||
| PC-98オプション での採用例 |
なし | ||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
不明 | ||
| 備考 | バス変換回路搭載。 | ||
| 解説 |
VM386SX+は、日本の企業ブイ・エム・テクノロジーが開発した i386SX互換の x86系 32ビット CPU。この他に 386ピン互換の486互換 CPUとして VM486DLC2も存在するようだが詳細は不明。 当時パソコンの CPUと言うと Intel製品の知名度が圧倒的に高く、国内メーカーのパソコンで採用されたという例はないので、国産でありながらパソコンユーザーの間でも印象が非常に薄い CPUである。 このブイ・エム・テクノロジー社は 1986年に、Intel 4004の設計開発者であった嶋 正利氏が設立した企業である。Intel x86互換の CPUとして 16ビットの VM860、32ビットの VM8600を開発し主にワードプロセッサに採用された。 国内開発としては最後となる x86系 CPU。NECが V30をめぐって Intelに訴訟を起こされたことから、それ以降、日本の半導体メーカーは巨額な開発コストと訴訟のリスクが付きまとう x86系 CPUの開発からは完全に撤退、RISCプロセッサや DRAM、液晶パネルの開発にシフトしていった。 |
||
| 名称 | Cx83D87、Cx87DLC | 製造メーカー | Cyrix、Texas Instruments |
|---|---|---|---|
 |
発表年月日 | 1989 | |
| 形状 | 68pin PGA (Cx83D87) 80pin QFP (Cx87DLC) |
||
| バス幅 | 32ビット | ||
| トランジスタ数 | − | ||
| 製造技術 | − | ||
| 対応ソケット | 68pin PGAコプロソケット | ||
| 動作クロック (MHz) |
25/ 33/ 40 | ||
| システムクロック (MHz) |
25/ 33/ 40 | ||
| 一次キャッシュメモリ | なし | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | x87 | ||
| PC-98本体 での採用例 |
なし | ||
| PC-98オプション での採用例 |
なし | ||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
Cx83D87搭載 I-O DATA PK-A486/87DW3 (33MHz: PC-9801DA/RA対応)PK-A486/87DW4 (40MHz: PC-9801DA/RA21/RA51対応) PK-Cx87D (33MHz、コプロセッサ単体: PC-9801DA/RA, PC-98RL, PC-386/G/GS/S/V対応) PK-Cx87D4 (40MHz、コプロセッサ単体: PK-A486DW4対応) ※ 型番末尾に「-L」が付く物は価格改定品 Buffalo/ MELCO HRX-C12T (36MHz、コプロセッサ付属: PC-9801DX/EX/RX対応)HRX-C12W (24MHz、コプロセッサ付属: PC-9801DX/EX/RX/UX/VX対応) HSC-40 (40MHz、コプロセッサ単体) HSC-D7 (25MHz、コプロセッサ単体) Cx87DLC搭載 アセットコア Cobra 486CF (32MHz、コプロセッサ付属: PC-9801DA/RA対応)Cobra 486CFL (32MHz、コプロセッサ付属: PC-98RL対応) |
||
| 備考 | − | ||
| 解説 |
Cx83D87は米サイリックス (Cyrix) が開発した i387DX互換のコプロセッサで「FasMath」という商品名で販売された。コアは Cyrix独自の設計になっているためインテル純正の i387DXに比べ演算処理速度が 20%〜 50%ほど速いとされている。実際に PC-9801RA21で I-O DATAのベンチマークソフト INSPECTで実測し Whetstoneの点数を i387DXと比較たところ約 20%高かった。他に 40MHzといった Intelのラインナップに無い高クロック動作に対応している点が特徴。 パッケージは 68pin PLCC以外に、組み込み機器や CPUアクセラレータ向けに基板搭載用に i486 CPUソケットの真ん中の空きスペースに収まるサイズの QFPパッケージの Cx87DLCがある。このコプロセッサは、Intel純正品よりも価格が安くコストパフォーマンスが良かったので、国内では CPUアクセラレータに良く利用されただけでなく、386機向けのオプションとして単品でも発売された。これらによって Cyrixの知名度向上と従来高価だったコプロセッサの普及に一役買った。 ちなみに、本コプロセッサは製品名表記にバリエーションが有り Cx487DLCは、Cyrixの 386ピン互換 486プロセッサとセットで販売された物。387DXは恐らく欧州向けの製品。いずれも表示は異なるが Cx83D87とコアは同一で性能も変わらない。 コプロセッサとは、数値データプロセッサともいい CPUと協調して動作するもので、関数演算等の浮動小数点演算の処理を専門に担当し演算処理が高速化される。次の世代の i486DXや i486DX2以降の CPUでは、浮動小数点演算ユニット (FPU) として始めから内蔵されるようになり、以降この方式が定着した。 Cyrixは、1988年に創立したチップベンダーで、80287互換のコプロセッサ「FasMath」はデビュー作となった。このメーカーの特徴は、チップの設計のみを行い生産部門を持たないファブレス企業で、チップの生産はテキサスインスツルメンツ (Texas Instruments) や IBM、SGSトムソン (現 STマイクロエレクトロニクス) に発注するという形で製造していた。自社で工場の設備を持たない分、多大な設備投資が不要となり低コストで製品を出荷できるというメリットがある。 この為に 83x87には Cyrixブランド以外にも Texas Instrumentsブランドの製品もある。同じ CPUアクセラレータでもロットによってブランドの違うチップを搭載している事があるが、コアは同一なので性能や機能に違いはない。 PC-98としてこのコプロセッサを採用することは無かったが、後に登場する 486互換 CPUアクセラレータでは、上位モデルで採用されている他に下位モデル用のオプションとして I-O DATAや MELCO (現 Buffalo) と云ったサードパーティーから単品での販売も行われた。 |
||
| 名称 | Cx83S87、Cx87SLC | 製造メーカー | Cyrix、Texas Instruments, Xtend |
|---|---|---|---|
 |
発表年月日 | 1989 | |
| 形状 | 68pin PGA (Cx83S87) 80pin QFP (Cx87SLC) |
||
| バス幅 | 16ビット (内部 32ビット) | ||
| トランジスタ数 | − | ||
| 製造技術 | − | ||
| 対応ソケット | 68pin PLCCコプロソケット | ||
| 動作クロック (MHz) |
25/ 33 | ||
| システムクロック (MHz) |
25/ 33 | ||
| 一次キャッシュメモリ | なし | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | x87 | ||
| PC-98本体 での採用例 |
なし | ||
| PC-98オプション での採用例 |
なし | ||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
Cx83S87搭載 I-O DATA PK-486/87SG (24MHz、コプロセッサ付属: PC-9801VX: PGA用)PK-486/87SL (24MHz、コプロセッサ付属: PC-9801DX/EX/RX/VX: PLCC用) PK-X87S (25MHz: コプロセッサ単体) ※ 型番末尾に「-L」が付く物は価格改定品 Buffalo/ MELCO HSC-S725 (25MHz: コプロセッサ単体)HSC-S733 (33MHz: コプロセッサ単体) HSL-C25 HSS-4S7V25 (25MHz、コプロセッサ付属: PC-9801RX/VX, PC-98XL対応) HSS-4S7D25 (25MHz、コプロセッサ付属: PC-9801DX/EX/RX/UX対応) HSS-4S7D33 (33MHz、コプロセッサ付属: PC-9801DX/EX/RX対応) Cx87SLC搭載 I-O DATA PK-V486/87SW2 (24MHz、コプロセッサ付属: PC-286V)PK-VF486/87SW2 (24MHz、コプロセッサ付属: PC-286VE/VF) PK-VG486/87SW3 (33MHz、コプロセッサ付属: PC-286VG) PK-X486S50 (48MHz、コプロセッサ付属: PC-9801RX/DX/EX/VX: PLCC用) ※ 型番末尾に「-L」が付く物は価格改定品 ABM 486GT-NSE/C (32MHz、コプロセッサ付属: PC-9801NS/E対応)S87-R (24MHz: 486GT-R対応サブボード) |
||
| 備考 | − | ||
| 解説 |
Cx83S87は、Cyrixが設計した i387SX互換のコプロセッサで、特別に「FasMath」という商品名が付いている。コアは Cyrix独自の設計になっているためインテル純正の i387SX/ SLに比べ演算処理能力が 20%〜 50%ほど高く、動作クロックも 40MHzといった高クロック動作に対応している。 パッケージは 68pin PLCC以外に、基板搭載用の小型で QFPパッケージの Cx87SLCがある。このコプロセッサは、価格が安くコストパフォーマンスが良かったので、CPUアクセラレータに良く利用された。 ここで気を付けなければならないのが、ボード上でシステムクロックを 2倍にして供給する CPUアクセラレータボード上に搭載する場合で、Intel純正品の i387SXでは 25MHz以上に対応するものが少ないため、必ず Cx83S87を利用しなければならない。 ちなみに、本コプロセッサは製品名表記にバリエーションが有りREVEAL TM BY Cyrix 387SXまたは単に 387SXと表記されている製品は恐らく欧州向けの製品と思われる。表記は異なるもののコアは同一なので性能は変わらない。 コプロセッサとは、数値データプロセッサともいい CPUと協調して動作するもので、関数演算等の浮動小数点演算の処理を専門に担当し演算処理が高速化される。次の世代の i486DXや i486DX2以降の CPUでは、浮動小数点演算ユニット (FPU) として始めから内蔵されるようになり、以降この方式が定着した。 Cyrixはチップの設計のみを行うファブレス企業のため、チップの生産はテキサスインスツルメンツ (Texas Instruments) や IBM、SGSトムソン (STマイクロエレクトロニクス) に発注するという形で製造していた。 このため、83x87には Cyrixブランド以外にも Texas Instrumentsブランドのものもある。同じ CPUアクセラレータでもロットによってブランドの違うチップを搭載している事があるが、コアは同一なので性能や機能に違いはない。 PC-98として採用することは無かったが、後に登場する 486互換 CPUアクセラレータでは、上位モデルで採用されている他に下位モデル用のオプションとしてサードパーティーから単品での販売も行われた。 |
||
| 名称 | 3C87、3C87SX | 製造メーカー | IIT (Integrated Information Technology) |
|---|---|---|---|
 |
発表年月日 | 1988 | |
| 形状 | 68pin PGA (3C87) 68pin PLCC (3C87SX) |
||
| バス幅 | 32ビット (3C87) 16ビット (内部 32ビット) (3C87SX) |
||
| トランジスタ数 | − | ||
| 製造技術 | − | ||
| 対応ソケット | 68pin PGAコプロソケット (3C87) 68pin PLCCコプロソケット (3C87SX) |
||
| 動作クロック (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33/ 40 | ||
| システムクロック (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33/ 40 | ||
| 一次キャッシュメモリ | なし | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | x87、3C87独自拡張命令 | ||
| PC-98本体 での採用例 |
なし | ||
| PC-98オプション での採用例 |
なし | ||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
不明 | ||
| 備考 | − | ||
| 解説 |
IIT 3C87は、米国 IIT (Integrated Information Technology, Inc.) が開発した i387DX互換のコプロセッサ。コアはメーカー独自の設計になっていて i387DXに比べ演算処理能力が高く、高クロック動作に対応している。実際に PC-9801RA21で I-O DATAのベンチマークソフト INSPECTで実測し Whetstoneの点数を i387DXと比較たところ、約 15%高かった。他にも i386SX互換の3C87SX (16〜 33MHz) がある。 変わったところでは、Cyrixが設計した 486DLC/SLC向けのコプロセッサのラインナップが有った点がユニーク。486SLC向けの XC87SLCや、486DLC向けのXC87DLC、4C87DLCといったラインナップが有った。なお、486SLC/ DLC向けと言っても実際は 387互換なので 386でも問題無く使用できる。 コプロセッサとは数値データプロセッサともいい CPUと協調して動作し、関数演算等の浮動小数点演算の処理を専門に担当して演算処理が高速化される。 IIT製 387互換コプロセッサの大きな特徴は、他のメーカー製コプロセッサとは異なり、幾つかの独自の追加命令が用意されている点があげられる。主に 3D CAD向けに演算処理の高速化を補助する物であったが IIT独自 (Cyrixや ULSI製品には無い) と言う事も有り残念ながら利用できるソフトは殆どなかった。 IITのコプロセッサ製品群の中でも注目すべきは 487DLX25/50と言う製品でコプロセッサでありながら、Cx486DRX2の様に内部にクロックダブラーを搭載しシステムクロック 25MHzに対応し 50MHzで動作する。x86系のコプロセッサとしては最高峰ともいえる。また、486DLC向けの製品はいずれもパッケージが金属製と言う外見も変わった製品だった。 これらのコプロセッサは主に米国内で流通し日本国内に輸入代理店も無い事から国内ではかなりマイナーな存在となっているが、かつて秋葉原のラジオデパート地下に有った某銘店 (迷店?) には箱入りの新品が残っており 2014年現在でも通販にて入手が可能である。 他にも、多くのメーカーが 387互換コプロセッサを製造していたが、i486DXや i486DX2以降の CPUでは、浮動小数点演算ユニット (FPU) として、始めから CPUに内蔵されることが一般化したため、387を最後に殆どのメーカーが撤退した。 ちなみに、2012年現在 グラフィックチップも似たような状況になっている。かつては Cirrus Logic、Trident、3Dlabs、Weitek、3dfx、S3等多くのメーカーが存在したが、生き残ったのは NVIDIA、AMD (ATI)、Intel、Matroxぐらいとなった。今後は、AMD、Intel共にグラフィックチップを CPUに統合する方向に進んでいるので、他のメーカーの動向が気になるところである。 IITは、1987年 2月に発足し 286、386、486用コプロセッサを製造していたが、1996年 12月に 8x8に社名を変更、テレビ会議用チップを残しコプロセッサの製造を停止した。その後の 2003年には半導体製造を停止し VoIPのサービスプロバイダに業態を変えた。 |
||
| 名称 | US83C87、US83S87 | 製造メーカー | ULSIシステムズ |
|---|---|---|---|
 |
発表年月日 | 1988 | |
| 形状 | 68pin PGA (US83C87) 68pin PLCC (US83S87) |
||
| バス幅 | 32ビット (US83C87) 16ビット (内部 32ビット) (US83S87) |
||
| トランジスタ数 | − | ||
| 製造技術 | − | ||
| 対応ソケット | 68pin PGAコプロソケット (US83C87) 68pin PLCCコプロソケット (US83S87) |
||
| 動作クロック (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33/ 40 | ||
| システムクロック (MHz) |
16/ 20/ 25/ 33/ 40 | ||
| 一次キャッシュメモリ | なし | ||
| 二次キャッシュメモリ | なし | ||
| 動作電圧 | 5V | ||
| 命令セット | x87 | ||
| PC-98本体 での採用例 |
なし | ||
| PC-98オプション での採用例 |
なし | ||
| CPUアクセラレータ での採用例 |
不明 | ||
| 備考 | − | ||
| 解説 |
US83C87は、米 ULSIシステムズ (ULSI Systems、日立の子会社とは無関係) が開発した x86系 32ビット CPU i386DX対応の i387DX互換コプロセッサで、コアはメーカー独自の設計になっているため i387DXに比べ演算処理能力が高く、高クロック動作に対応している。i386SX用の i387SX互換のコプロセッサは US83S87。両者ともに日本国内では非常にマイナーな製品である。 このコプロセッサは当初「Math-Co DX」(i386DX用)、「Math-Co SX」(i386SX用) というブランドで出荷していたが、後に「Advanced Math Coprocessor DX/DLC」、「Advanced Math Coprocessor SX/SLC」という名称に変更された。 このコプロセッサは、性能、機能共に他のメーカーと目立った特徴は無いが、メーカー独自の施策として永久保証で動作不良が発生した場合でも 3回まで無償で交換が受けられるという保証規定で販売されていた。 US83S87の演算処理能力は、実際に PC-9801USで I-O DATAのベンチマークソフト INSPECTで実測し Whetstoneの点数を i387SXと比較たところ約10%高かった。 コプロセッサとは、数値データプロセッサともいい CPUと協調して動作するもので、関数演算等の浮動小数点演算の処理を専門に担当し演算処理が高速化される。次の世代の i486DXや i486DX2以降の CPUでは、浮動小数点演算ユニット (FPU) として始めから内蔵されるようになり、以降この方式が定着した。 他にも i387互換コプロセッサとしては、ファブレス半導体企業の草分け的存在の米 Chips and Technologies (C&T) 製の Super Math J38700DXや、米 Weitek製 Abacus 3167があった。Abacus 3167は独自のバス設計で i387DXとはピン互換では無いが i387DXに比べて 2.5倍演算処理が高速だった。 いずれのメーカーも後にグラフィックチップメーカーとして名を馳せるが、グラフィック技術の獲得のため C&Tは 1997年に Intelに、Weitekは 1996年末に Rockwell Internationalに買収されている。 |
||
PC-98, PC-9801, PC-9821, PC-H98, PC-9800, FC-9801, FC-9821, FC-9800, SV-98, 98SERVER, VALUESTAR, CanBe, 98NOTE等は、NEC社の商標または登録商標です。
i486, Pentium/Pro/II/III, MMX, ODP, Celeronは、intel社の商標または登録商標です。
Windows, MS-DOSは Microsoft社の商標または登録商標です。
この他、製品名、型番等は、一般に各メーカーの商標または登録商標です。
