| |
|
●遺跡要覧と情報源 ●周辺の地形 ●遺跡の時空間 ●調査区全体図 ●大形加工材 ●多様な木製品 ●漆と朱 ●律令の祭祀空間 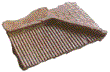
瓦塔 ※2000年制作です ※2002年4月の見学会 ┗東京考古系i | 水辺の作業場・水辺の祭祀空間 |
|
縄文時代の集落傍の水辺が埋没した遺跡は、保存環境の良さと、加工場としてのユニークな遺物の出土で注目されています。特に台地・丘陵の集水域から低平な谷地に流れ込む付近は、立地として好まれたようです。 貯水地で知られる狭山丘陵の、多摩湖の作られた谷あい(北川)の下流に、下宅部(しもやけべ)遺跡は位置しています。埋没流路から、加工された大形材、トチの実のアク抜き、木製品の素材処理、粗加工、漆液や朱の調整、分銅型打製石斧の製作、シカ・イノシシの解体と儀礼など、様々な生業活動の痕跡が発見されています。時期的に主体となるのは、堀之内式、加曽利B式の縄文時代後期と、安行3式頃の晩期になります。飾り弓10点を含む34点の弓、土偶数十点、漆塗りの杓子柄、網代なども出土しています。 また、1000年以上の時を経て、8〜9世紀の律令期(奈良平安時代)に水辺祭祀を意図したと思われる、長径12mの池状遺構が構築されています。金属製品や農耕具、櫛、墨書のある坏(須恵器)などが見つかっています。調査区内からは他に瓦塔(須恵質の陶製五重塔、隣のNo.2遺跡資料と接合)も出土しています。  遺跡の現況(1999年11月28日)下流方向を望む | |
| ※遺構遺物写真は東村山市遺跡調査会下宅部遺跡調査団提供。なお本サイト内のコメントは1999年までの情報を元に独自に構成したもので、公式な見解ではありません。 | |