 ATELIER Z “CUB” Elite 到着で、
ATELIER Z “CUB” Elite 到着で、ペグはGotohのクルーソン型上級モデルGB-2 SPECIAL (ギターで言うスロッテッドヘッド・タイプ・ペグ)…
分厚いベースプレートからシャフト受けまで一体成形で、トルク調整も可能な、かなりしっかりした造りだが…
何故か逆巻き。
Fender Jazz Bass等にも逆巻きがあるが…
何故だろう?
慣れないと、チューニングが一寸怖い。
と、書いたが…

R & Bell Electric Upright Bass UB-S ヘッドと見比べて欲しい。
チューニングマシン(ペグ)の取り付け方法が上下(左右?)逆になっているのだ。
巻き取り軸とつまみ軸の関係から見れば「上下逆」。
ペグそのものから見れば「左右逆」に取り付けられている。
 こちらはFender Precisionのヘッド裏。
こちらはFender Precisionのヘッド裏。通常、ギターやエレクトリックベースのペグ取り付けはこの方向である。
これで回転順方向(ねじを締める方向:時計回り)につまみを回せば、巻き取り軸は弦を巻き取る方向に回り、ピッチがあがる。
Fender Bassで希に逆巻きのペグを装着した物があるが、それはギアの回転そのものが逆になっているはずである。(ペグの取り付け外観は変わらない)
つまり、このまま巻き取り軸を「上下逆」に取り付け(Fenderの場合、片側一列配置なので、左利き用に交換という事になる)れば、巻き取り軸とつまみの位置関係も逆になり、回転順方向では弦は緩み、ピッチが下がる、すなわち逆巻きという事になる。
 これはコントラバスのヘッド部分。
これはコントラバスのヘッド部分。あちこち調べてみたが、ウッドベースでの標準的なペグの配置は、この写真のように、エレクトリックベースから見るとギア(巻き取り軸)とつまみ軸の位置が上下反転した形になっている物が一般的なようである。
学生時代所有していたコントラバス(COINと言うメーカー製の合板楽器だった)は、安物だったのでエレクトリックベース用ペグが装着されていたため、これとは逆の位置関係だったが、ギターから入った身には違和感がなかった。
 一般的なコントラバス・ペグ。
一般的なコントラバス・ペグ。つまみ軸は巻き取り軸の下側に位置する配置である。
学生時代の練習場所には恐らく鈴木製であったと思われるコントラバスもあって、このタイプの大型プレート付きのペグが付いていたが、その楽器でも逆巻きを意識した記憶がない。(巻き取り軸とつまみ軸の関係も記憶にないが…)
現在のたまり場にもコントラバスが置いてある(一番下写真参照)が、この楽器でも逆巻きを意識した事はない。
 一番上の写真を参照して頂きたいが、最初にこのペグの「上下逆取り付け」に気づいたときは、「単にペグのベースプレートがヘッドの取り付け部分よりも上下幅があり、Fender Bass式につまみ軸が上に来るように取り付けるとペグのベースプレートがはみ出してしまう」からではないかと想像した。
一番上の写真を参照して頂きたいが、最初にこのペグの「上下逆取り付け」に気づいたときは、「単にペグのベースプレートがヘッドの取り付け部分よりも上下幅があり、Fender Bass式につまみ軸が上に来るように取り付けるとペグのベースプレートがはみ出してしまう」からではないかと想像した。…のだが、同メーカーのスクロールヘッドを持たないモデルでも、ペグ取り付け部に余裕があるにもかかわらず「上下逆取り付け」になっている。
何故こんな形で逆巻きになっているか…これは伝統的コントラバスの外観仕様をデザインに取り込んだがペグの巻き方向をオーダーする事までは考えなかったと想像するしかない。
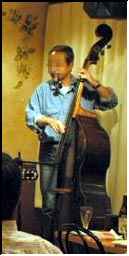
このCUBシリーズに装着されるペグはGotoh製であり、そもそもスロッテッド・ヘッド用の物はカタログに載っていない。
故に、メーカーがオーダーすれば「上下逆取り付け」したときに逆巻きにならない「構造的逆巻き仕様」の発注は可能なはずだからである。
一般的なベースペグはFenderスタイルの「片側一列配置」が多く、また、製品には左利き仕様もあるはずなので、このCUBシリーズも右利き半分、左利き半分の組み合わせを使っていると思われる。
つまり、わざわざ製作するまでもなく既製の製品の組み合わせで構成できるのである。
順巻き仕様にして欲しかったなぁ…
 アップライトベース
アップライトベース これまでのお話
これまでのお話 順路へ戻る
順路へ戻る 国産ギター大好き!目次へ戻る
国産ギター大好き!目次へ戻る トップページへ戻る
トップページへ戻る