CINE ART 4
Home
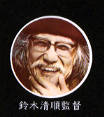
鈴木清順の二本---「ツィゴイネルワイゼン」と「陽炎座」
--夢と現の彼岸・・フイルム歌舞伎--
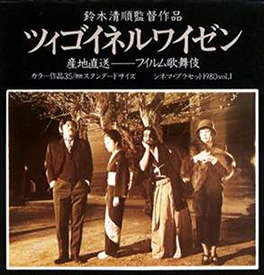 「ツィゴイネルワイゼン」
「ツィゴイネルワイゼン」
「生きているひとは死んでいて、死んだひとこそ生きているような
むかし、 男の旁には そこはかとない女の匂いがあった。
男にはいろ気があった。」
プロデューサー:荒戸源次郎 企画:伊東謙二 脚本:田中陽造 撮影:永塚一栄 照明:大西美津男 美術:木村威夫・多田桂人 スチール:荒木経惟 音楽:河内紀 録音:岩田広一 編集:神谷信武 助監督:山田純生
●出演:原田芳雄 大谷直子 藤田敏八 大楠道代 樹木希林 他
当時、この映画が上映されたのはシネマ・プラセットと名付けられた半円形の銀色のテントドームのなかだった。
ぼくの住んでいた街のパルコの屋上に設置されたドームの中は百人以上は入れたのかどうか・・ちいさなテント小屋のようなドームという印象の記憶しかない。それは映画館に入るというより、少し以前に唐十郎主催の演劇集団で存在した赤テントに入る時の気分に近かった。
それはともかく、映画流通の革命とも言われたそのドームもろとも移動しながら長期に渡って上映され続けた映画が、この「ツィゴイネルワイゼン」だ。
 正直言えば座席は小さく堅く快適とは言えず、ゆうに三時間に及ぼうとするこの映画を観るのは身体には酷だったが、それでも最終日の近くに、もう一度そのドームの中で堪能したほどの、それは映画だった。
狭いドームの中にいるのは、特別な映画ファンと言うべきか・・、その時は俳優の数人や大島渚監督なども同じ椅子に観客と混じって腰掛けていた。
正直言えば座席は小さく堅く快適とは言えず、ゆうに三時間に及ぼうとするこの映画を観るのは身体には酷だったが、それでも最終日の近くに、もう一度そのドームの中で堪能したほどの、それは映画だった。
狭いドームの中にいるのは、特別な映画ファンと言うべきか・・、その時は俳優の数人や大島渚監督なども同じ椅子に観客と混じって腰掛けていた。
今のロードショー館のように快適な設備はないが、上映が準備され照明が消えると場内は真っ暗の暗の・・漆黒の闇に変えることができた。その中で 「ツィゴイネルワイゼン」を観るという贅沢は、もう今では叶わぬ夢の様な出来事だろう。
ビデオでは不可能な映画体験の極みというものがあるとすれば・・、この1980年のシネマ・プラセットのドームのなかで観る「ツィゴイネルワイゼン」 だと言うしかない。
 映画は、大正ニヒリズムの余韻のこる昭和初期が舞台である。「ツィゴイネルワイゼン」とは、サラサーテの曲だが、サラサーテ自身演奏のSPレコードから微かに聴こえる、その録音中に紛れ込んで入っている声に、奇妙に、また執拗に惹かれたふたりの男が辿る、摩訶不思議なるあの世とのラブシーンに満ちた旅の道ゆき・・。
映画は、大正ニヒリズムの余韻のこる昭和初期が舞台である。「ツィゴイネルワイゼン」とは、サラサーテの曲だが、サラサーテ自身演奏のSPレコードから微かに聴こえる、その録音中に紛れ込んで入っている声に、奇妙に、また執拗に惹かれたふたりの男が辿る、摩訶不思議なるあの世とのラブシーンに満ちた旅の道ゆき・・。
同行するのは細君か、はたまたあの世の使者か・・、 熟した色香の女たちを交えて、この世とあの世の境を行ったり来たりしているような話である。
いやこれは、むしろその彼岸へ渡るための、夢の芝居なのかもしれない。
鈴木清順は「今度の映画は、生きている人間は本当は死んでいて、死んでいる人が本当は生きているんだ。という一種の怪談ですね。
情念や因縁は何ひとつない、現代風のノッペラボウな怪談を、やさしく、面白く、極彩色の娯楽映画に仕上げてみるつもりなんです」と制作に先んじて語っている。
それは、その通りの出来映えとも言え、それ以上に、謎めいたあの世との親近感とでもいうべきような、そんな深さが作者の予想を超えてフイルムに潜んでいるような気もする。
 あまりに幻想的なのに生々しい・・そんな濡れた手で背筋を触られるような官能と静寂の無限螺旋な夢の数々。
あまりに幻想的なのに生々しい・・そんな濡れた手で背筋を触られるような官能と静寂の無限螺旋な夢の数々。
日本に映画としてのシュルレアリスムの文法が仮にあるとすれば、断じてこの映画がそれであるとぼくは思う。
鈴木清順には熱烈な信奉者がいると聞くが、ぼくが観た最良の数本は「ツィゴイネルワイゼン」と「陽炎座」。 それに昔テレビで観た「1966年作:けんかえれじぃ」の青春映画らしいのに、やはり不思議な雰囲気とその映像美で語られた浪漫だ。
残念だけど「1981年:陽炎座」の後の「1985年:カポネ大いに泣く」「1991年:夢二」は物足りなさを覚え、楽しめなかった。その時のぼくには多分、この人のユーモアとナンセンスが、生の世界に終始していたと感じたからかも知れないし、この二本に遊んだ鈴木清順は「死」の「あの世」の静寂をあえて考慮しなかったのだとも思われた。
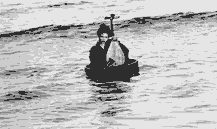 鈴木清順の世界とは多分、ある種の演劇の世界を好む人は必ずや魅了される世界だろうと思う。
鈴木清順の世界とは多分、ある種の演劇の世界を好む人は必ずや魅了される世界だろうと思う。
ぼくとしては自分の体質とはどこか異質だと感じながらも、なにか懐かしいゾーンへと、前世の記憶のようにと・・ぼくを引込こむ世界が「ツィゴイネルワイゼン」の映画の闇のなかの時間にはあるようだ。
だからそれは夢の出所を覗くような怖い映像でもあり、とても楽しくスリリングなものでもある。そんな実に独特な映画体験である。
しかしそれは誰かが・・「死をもてあそぶ」と表現したように、この映画に語られてあるものには必ずユーモアが地下水のように浸透しているという、そういった奇妙なバランスのなかで成立している、ということなのだ。
それはあたかも夢よりも、熟した夢のようだと言えるかも知れない・・。
SP盤レコードにはじまり、当時のモダンな建物や装飾品、また女と共に語られる「腐る前が一番うまい」という熟れた桃、エロチックな蟹、干物・・と小道具も艶かしい存在に使われて本望であろうか・・。
二役となる大谷直子の落ち着いた美しさが印象的だし、亡くなった監督でもあった藤田敏八の渋さ、大楠道代のモダンな可憐さと色気(大楠道代はこの後の「陽炎座」では驚くべき美しさだ)、原田芳雄のワイルドさが生きた男臭さと不気味さ。脇役もすべて印象的な後味を残す作品だ。
 ところで・・、ぼくが一番怖かったのはラストシーンに至る、橋の向こうから見える少女の手招きからの御案内だ。・・ぼくの夢のなかにある二本の足は、あの小さな案内人には逆らいがたいと・・、ひょこひょことついていくのかも知れない。
ところで・・、ぼくが一番怖かったのはラストシーンに至る、橋の向こうから見える少女の手招きからの御案内だ。・・ぼくの夢のなかにある二本の足は、あの小さな案内人には逆らいがたいと・・、ひょこひょことついていくのかも知れない。
貴方も彼岸へのご案内はいかが・・。
夏よりも・・秋にふさわしい怪談として、この一本・・ということです。
(写真はモノクロームですが、映画はカラーです)
「陽炎座」
--TAISHO 1926 TOKYO--
「三度びお会いして、四度目の逢瀬は恋になります。死なねばなりません。それでもお会いしたいと思うのです。」
製作:荒戸源次郎 企画:伊東謙二 原作:泉鏡花 脚本:田中陽造 撮影:永塚一栄 照明:大西美津男 美術:池谷仙克 音楽:河内紀
●出演:松田優作 大楠道代 加賀まりこ 楠田枝理子 大友柳太朗 原田芳雄 中村嘉津雄 他

続く年の1981年に上映された「陽炎座」。
渋谷まで期待に胸膨らませ観に行ったことを覚えている。 制作は同じシネマ・プラセットだったが配給は日本ヘラルドに変って、これは通常の映画館で上映された。
(当時の関係者の方からメールをいただきました。・・「陽炎座」は確かにヘラルドの配給でしたが、 シネマ・プラセットが新ドームにて2ヶ月間、新宿の三井ビルの下で先行ロードショーをしています、
そして、そのドームにて、名古屋、大阪、札幌、博多の4ヶ所で、有料試写会というイベントをしています。」ということです。 御指摘と情報を感謝いたしますと共に、間違いをおわびいたします。)
主演のひとりの松田優作というと、この映画と夏目漱石原作・森田芳光の「それから」には日本の男の色気を感じた人も多いかも知れない。
「それから」ともある意味共通するかも知れない・・。夢幻の登場人物たちに迷宮に翻弄されるような主人公の頼り無さも、 松田優作の独特の味になった。
 絢爛たる豪華な色彩の着物と舞台セットが大楠道代の妖艶なる美しさを際立たせていた。
絢爛たる豪華な色彩の着物と舞台セットが大楠道代の妖艶なる美しさを際立たせていた。
淀川さんは泉鏡花の世界の女ではないフランス美人的な大楠道代の、鏡花おんなにけんめいにいどんだ(心がけ)が出した芸の姿を誉めていた。
ともかくまずもって、ぼくにはこの大楠道代を観ているだけでも、とりわけ満足というところもあったほどなのだが・・。
「ツィゴイネルワイゼン」に続いて、この「陽炎座」もあの世からの引力を全編のトーンに充満させた怖い絵巻物でもあるのだが、もうその爛熟の果てに到達したかのようなその映像の、全編に息をもつかせぬ美しさが充満していて、あらためて日本文化の美術感覚と映画の様式美という言葉を思い出させた映画だ。
 原作は泉鏡花。
原作は泉鏡花。
ぼくはこの有名な作家のお話を映画でしか接したことがないのが、ちょっと未だに恥ずかしいのだが、淀川さんの話にも、よく登場する名前でもあり、映画では玉三郎の「外科室」や寺山修司の「草迷宮」などでも出会い、気になっていて、その美学になんとかもう少し接近してみたいものだとは思いつつ・・ついぞ、本を捜して開いてみるということを忘れている。
 登場する人物がすべてどこか現世的でない空気を持っているのだが、ただひとり加賀まりこは生身の生命力をかもし出していたのは許されたものか意図されたか・・知るよしもないのだが、あれは加賀まりこというひとのつよい役者の性だったのだろうか。
登場する人物がすべてどこか現世的でない空気を持っているのだが、ただひとり加賀まりこは生身の生命力をかもし出していたのは許されたものか意図されたか・・知るよしもないのだが、あれは加賀まりこというひとのつよい役者の性だったのだろうか。
逆にテレビでは司会などで元気な切れるテンポで押しまくるような楠田枝理子が、この映画では着物を着た静かな人形の風情で佇んでいる姿が怖い・・。
 陽炎座の舞台小屋崩壊のスペクタルといい、そして、まるで映画の背景としての壁紙のように・・徐々に妖しく増殖していく殺戮地獄絵図が過剰なほどにめくるめく・・、男女のあの世へのみちゆきの舞台を、そんな大道具セットたちが華麗に演出している。
陽炎座の舞台小屋崩壊のスペクタルといい、そして、まるで映画の背景としての壁紙のように・・徐々に妖しく増殖していく殺戮地獄絵図が過剰なほどにめくるめく・・、男女のあの世へのみちゆきの舞台を、そんな大道具セットたちが華麗に演出している。
「清順流フイルム歌舞伎」とはよく表現した言葉で、贅沢な日本の美術文化に充分に浸された気分になる。
ほうずきのみごとな朱色を生かして、水中のマジックを魅せたシーンも特に印象的だ。
前作と違って、目に見えるモノにすべて映画芸術の魅力を投影させようとしたかのような、ある意味で余裕のようなものが感じられるのは、前作「ツィゴイネルワイゼン」の絶大な成功に支えられたものと言えるかも知れない。
それはその分、この「陽炎座」という映画は、誰にも感情移入を試みることができないというほどの美術仕掛けの映画・・ ともいえるだろうか。
(この特集に掲載されている写真はすべて当時のパンフレット・チラシから取り込んだものです)
|
映画監督 : 鈴木清順
大正12年東京生まれ。 1980年「ツィゴイネルワイゼン」で、キネマ旬報ベストワン。 他、国内の各賞多数受賞。ベルリン映画祭審査員特別賞。 1981年「陽炎座」でキネマ旬報第3位。 |
Home | 1.ビクトルエリセ | 2.大林宣彦 | 3.トリュフォー
pageの上へ戻る