
また、マカフェリもどき、Paradise PDR-900である。
あまりにごつすぎて気になっていたテールピースだが、セルマー/マカフェリ・タイプのレプリカが輸入されているという情報を手に入れた。
Paradise、他はまぁまぁだが、ココだけは一寸バランスが悪い気がする。
贅沢を言えばペグもオリジナルとは全く違うのだが、オリジナル・マカフェリのカバードタイプはそう簡単には手に入らない。(もしかしたら不可能?)
 作りから言えば、この見るからに頑丈そうなクロームメッキのテールピースは、実際、しっかりしている。
作りから言えば、この見るからに頑丈そうなクロームメッキのテールピースは、実際、しっかりしている。オリジナルセルマーやセルマーレプリカのテールピースは(恐らく)真鍮のペナペナ板をプレスしただけの物に見える。
実際、Stringphonicの商品説明には…
DR Tailpiece For Maccaferri
多くのマカフェリのコピーメーカーが採用しているDR製のテールピース。コイツに変えただけで雰囲気も随分と変わります。おまけにボールエンド弦もループエンド弦も両方使える様になるので、選択の幅も広がります。
今このDRのテールピースが付いているギターでも、いつ壊れるか分からなくて不安に思っている方、予備として一個ストックしておきましょう。木ネジx3コ付。
とあり、暗に華奢で壊れやすいことを示唆したような記述もある。
しかし、その儚さがまたセルマー/マカフェリ・タイプのイメージであるように感じるのは私だけ?
ループエンド弦も使える、と言うのは優れものの様な気もするが、現実問題としては国内ではループエンドのギター弦入手は非常に困難である。
Paradise PDR-900が使用しているテール・ピースは、Paradiseよりもずっと高価な、※ルシアーの製作モデルでも採用されている例があるようなので、特性的には悪くはない物なのだろうが…
テールピースの場合、剛性も含め材質等の変更で音質は果たして変るのであろうか?
少々興味深い。
- ※ルシアー
- 「元はリュートを作る人」から転じて「少量生産手工ギター制作者」の様な意味で使われているようである。
ここ数年よく見られる言葉だが、言葉の意味をきちんと定義してから使っている例はまず見たことがない。
こんな、極めて非一般的なカタカナ語を、前後の文脈で意味を理解しろと言うのだとしたら、物書きとしてあまりに不親切で投げやりな態度ではないかと思う。
物知らず、と言われればそれまでだが、実は私自身、この間まで意味が分からなかったのだ。
ずっと調べていたが、リュートに当たるまでにかなりの時間を費やしてしまった。
- リュート:Rute
- 「楽器の王」等と呼ぶ人もいる。
ギターの元となったとも言われ、音色はクラシックギターに近いと言えなくもないが、どちらかというとマンドリンにイメージが近い。
リュートのために書かれたバロックやルネサンスの曲は多数がギター用に編曲され、クラシックギターの重要な演目になっている。
年代や目的によって色々な種類があり、複弦で6コースや10コースと言った多弦楽器
我が家のにセルマー/deマカフェリ、Paradise PDR-900は、購入時のレポートで
表板は普通の針葉樹である。スプルースか?一応単板のようだ。と書いたが、オリジナルのセルマー/マカフェリは殆どが側裏板が合板仕様だったようである。
(表単板と言うのが衝動を最終決定した要因)
サイド/バックは勿論合板だろうが、ローズのようである。バインディングもくすんだローズのような木目の木材。(オリジナルのSelmer/Maccaferriもモデルによってはサイド/バックは合板だったようだ)
当時の技術では単板よりも合板の方がコストが掛かったらしく、あえて、表板以外は合板で製作された様な節もあり、この仕様もあの独特の音色を生んでいるのかも知れない。
このParadiseも、作りは決して誉められたモノではないが、音の方はそこそこ、それらしい物なのだ。
オリジナルは20年間、1000本そこそこしか作られなかった楽器である。
現存する物は殆どレプリカと言って良いだろう。
(価格はピンからキリまでではあるが…)
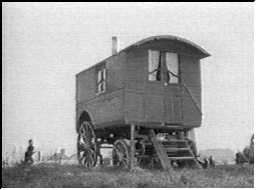
商品到着後に、続く…
 珍品入手-続き:3
珍品入手-続き:3 扱いは
扱いは 展示順路へ戻る
展示順路へ戻る 次へ
次へ GB楽器博物館
目次へ戻る
GB楽器博物館
目次へ戻る
 トップページへ戻る
トップページへ戻る