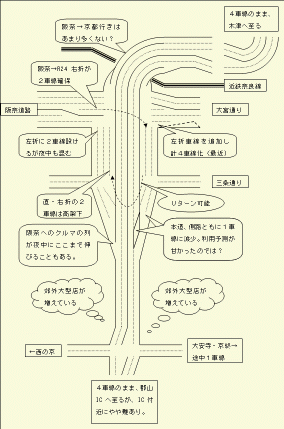横田<miskij>萬や 奈良
ちょっと風向きが変わったのかな?
大和北道路有識者委員会
が、第7回、第8回の有識者委員会を実施し、早々と結果を公開してますが、特に注目したいのは
資料-2-2 文化財保護の観点から京奈和自動車道に関するご意見等をいただいた団体一覧(PDF)。
反対意見かそれに類する見出ししか列挙されてないのも壮観と変に感心してしまいますが、
それだけでなく
資料-6 PIプロセスキャンペーン報告(PDF) でも住民の生の意見を公表されるなど、
反対意見があることも紹介したことは賞賛できるかもしれません。
こういう反対意見が多数あることは、団体一覧の日付が平成12年から始まっていることから、
奈良国道側も判っていらっしゃるはずなのに、今頃?、という感も少々あります。
もし、最初から先見性のある人々による反対意見を示していれば、
それらの理路整然とした説明でもっと早いうちに流れが決まっていたのかもしれません。
つまり1000億円クラスの超大型事業という予算が得られなくなるのを歓迎しない向きとの板挟みに遭い、
やむなくこういう意見が出ていますよ、という一種のポーズのような気もしています。
なんにせよ、事務的に対応せざるを得ないのかもしれないのだけど、それならば、それらの対応の中で、
PI本来のありかたとして情報などが漏れている点、奈良国道側では対応できない領域を私が勝手に補ってみたいと思います。
第二阪奈道路の阪奈トンネルはシールド工法だった?
(注:一部、未確認点もあるので、その点はご了承ください)
奈良県道路建設課のweb siteにて、問い合わせのフォームが用意されているので、
阪奈トンネル部分の事業費を問い合わせたところ、1260億円との回答をいただきました。
つまりキロ当たり200億円ちょい、と山岳トンネルの10倍にもなっています。
むしろ、随所で聞くシールド工法のキロあたり単価に近づいてる感があります。
東京新聞>
みやこ新聞>
外環道で大深度地下利用構想
によると、各シールド工法のキロあたり単価が下記のように記されています。
| 場所 | メートル単価 | キロ単価 | 備考 |
|---|
| アクアライン | 8190万円 | 819億円 | 2階建てトンネル2本 |
| 地下鉄・大江戸線 | 3420万円 | 342億円 | 1車線相当の内径が狭いトンネルが2本 |
| 中央環状線 | 9300万円 | 930億円 | アクアライン並になるのでしょう |
この記事では、事業費はもとより、他の問題についても触れています。
- 掘削工事で排出される大量の残土処理問題。
- 防災対策。
- 維持費。
残土処理問題はちょっと考えたくない(高架工事ならほとんど出ないのに…)のでわきにおいて、防災対策について…
アクアラインのサイトでは、トンネル自体を2階建ての構造にして、1階を車両も通行可能な非常用通路に割り振っています。
それでもなお、日本坂トンネルの火災事故のようなことが発生しない保証はどこにもないと思われます。
地中深くで、このような火災が発生した場合、周囲の地層への影響はどれくらいあると予想されてるのでしょう?
万が一、トンネル自体が使用不能になれば、もう1本、となるんでしょうか?
地上式なら、上空や側路からの消火活動などが容易に行えるし、また一部区間が破損したとしても、
例えとして挙げるにはちょっとツライのですが、阪神高速のように復旧も早いと思われます。
R169の大滝ダム関連の周辺道路工事でも、仮設道路をしゃかしゃか組み上げて通行に支障のないようにしたりできるのに対し、
地中だったらほとんどお手上げ、と思われます(こうしてみると阪奈トンネルは大切に使いたいものです)。
ちなみにシールド工法が、キロあたり200億円と仮定した場合、1キロの事業費だけで、高架道路を10キロ、それより安くできる地上道路なら20キロも作れる計算になります。
木津ICから郡山ICまでは15キロほどありますが、大ざっぱにキロあたり30億円掛けるとして450億円。
平城京跡の下を完全にトンネルで迂回すると、シールド工法が必要な区間が5キロになるといわれますが、
そうすると事業費は1000億円にもなります。(前後の傾斜したトンネル部分は含まない)
それだけあれば、今の15キロほどを景観を考慮して盛土方式+交差点の立体化をすべてこなせるだけでなく、
お釣りで他の地域の未完成な立体化区間や、渋滞ポイントの改良に回せると思うのですが・・・
維持費については詳しくないのですが、盛土方式(名阪国道・伊賀上野付近、郡山〜天理東)なら橋脚・橋桁の劣化の心配をしなくて済むでしょうか。
トンネルについては、青函トンネルを検索してみると、相当な額が掛かっているのが伺えます。
東山間部を迂回するとした場合
 委員会が提示している東山間部コースについて、トンネルを設けるとしたら、R369のA地点(標高270m)あたりから南に下って、
県道80号・名張線のB1地点(標高350m前後)あたりでしょうか。入り組んだ峡谷に出ます。
委員会が提示している東山間部コースについて、トンネルを設けるとしたら、R369のA地点(標高270m)あたりから南に下って、
県道80号・名張線のB1地点(標高350m前後)あたりでしょうか。入り組んだ峡谷に出ます。
春日山原始林を含むバッファゾーンぎりぎり、東へ弓なりに迂回させて全長5キロに納めています。
原始林すぐ近くにトンネルの出入り口を作るのを避けるとしたら、B2地点(同435m),B3地点(同350m)があります。
B2地点は標高の点で後述する深刻な問題がでてきます。
B3地点だと全長が5キロを超えてしまうので、A地点側の入り口をずらす必要が出てきます。
1キロほど進むと標高が350mになりますが、そこまでが8%の勾配になり、高速道路には出来なくなります。
それでR369が標高を稼ぐためにかなり蛇行しているのも判ると思います。
工法は、とりあえず山岳トンネル方式、2車線1キロあたり20億円で、100億円くらいでしょうか。
B1案では勾配が抑えられ、キロあたり1.6%と緩い勾配になりますが、B2案では3.36%と高速道路としてはぎりぎりになります。
どのみち、ずっとアクセルをふかした状態で登るので、バイクだとトラックの後ろにはとても付きたくないです。
さて、南に出たところで、どうやって郡山につなぐの?というもっと厳しい問題がでてきます。
西には住宅地、天皇陵、皇女墓…を避けると、西南方面でも正暦寺があるので心苦しいです。
一応、200mくらいあけて(寺から見ると東の山の向こうになる)、C地点の高樋町(標高100m)を経て…
と思うのですが、ここまでの距離が5km、B1案およびB3案で5%、B2案で6.76%という急勾配になります。
とても実用的ではないので、勾配を稼ぐためにどこかで距離を稼ぐ必要があるのですが、
そうすると名阪国道の天理Ωカーブのような蛇行路が必然的に必要になってしまいます。
それでもなお、C地点では標高がすとんと落ちる形なので、平地に至るまでの区間は法隆寺なみの高さの橋脚の連続になるでしょう。
これは南阪奈道路を見れば判ります。
また、まっすぐ南に伸ばして名阪国道につなごうとすると、B2案では標高差が解消できません。
結論:北半分は名張方面には妥当だが、南半分は郡山へ向かうには無理があると思われる
現在のR24バイパスの事業費およびいくつかの問題点
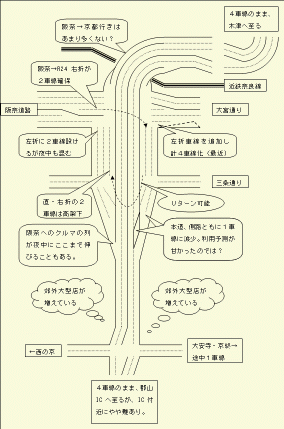 R24バイパスは、木津からR24分岐点(大和郡山市伊豆七条町)までの15キロほどを指していますが、
190億円という回答をいただいています。
R24バイパスは、木津からR24分岐点(大和郡山市伊豆七条町)までの15キロほどを指していますが、
190億円という回答をいただいています。
高架部分は地図上の測定で2.6キロくらいです。現在の高架工費でいえば50億円と仮定して、
残り140億円が地上区間に使われたと推定するとキロあたり10億円くらいになります。
肝心の車線の配分地図を見かけないので、MS-Wordで作図してみました。
一部、記憶に頼っていて事実と合わない所があるかもしれませんが、大体においてこのような構造です。
南行きについて見てみましょう。本線と、阪奈道路から来る側路はそれぞれ2車線ありますが、
合流地点で強引にそれぞれ1車線に減らして合流し、ずっと2車線の構成になっています。
2車線一杯のクルマの通行量が発生している状況で、このような絞り込みを食らうと、
一遍でクルマが動かなくなるのは誰が見ても明らかでしょう。
実際、R24の渋滞は、並行するJR関西・奈良線、平城山駅付近の車窓から見ることができます。
同様に、阪奈道路から南に行く車線も2車線でぎりぎりになっているのに、絞り込みを掛けているんですから、
阪奈道路にまで渋滞が及んでしまうのです。
そこから先は、通常の平面交差による信号待ち渋滞、程度になります。
ここは素直に本道、側路ともに各2車線を用意していくのが妥当と思うのです。
交差点では、本道を立体交差にするのは当然として、景観および埋蔵遺物などを考えると土盛り工法でしょうか。
そして、上記のような車線数の故意的な減少による渋滞の発生については、
奈良国道のパンフレット
(PDF形式/6.3MB)の3〜6ページでは、明確には触れていらっしゃらないようです。
本来は、ここまで詳しく分析して掲載するものだと思うのですが…
結論:試験的に6〜8車線化を行ってはどうでしょうか?
近鉄西大寺駅の地下通路で見た地下水の水位
たまたま、近鉄西大寺駅を北から南へ移動する時に見つけたのですが、
地下通路の壁面から地下水が染み出ているのに気付きました。

地下通路の壁からの滲出模様
|
これをどう受け止めるかは皆さんにお任せします。

2003.Apr.17 R24立体交差の詳細図を一部修正(大宮通り西行き、左折車線を追加し4車線)
TOP|
奈良めぐりに戻る|
PIを比較してみる|
公述会に行きました
※Web Page以外のメディア(雑誌・放送・CDなど)に掲載する際は連絡乞う。
Copyright by YoKota MItSuhiro <miskij>2003. All Rights Reserved.
 委員会が提示している東山間部コースについて、トンネルを設けるとしたら、R369のA地点(標高270m)あたりから南に下って、
県道80号・名張線のB1地点(標高350m前後)あたりでしょうか。入り組んだ峡谷に出ます。
委員会が提示している東山間部コースについて、トンネルを設けるとしたら、R369のA地点(標高270m)あたりから南に下って、
県道80号・名張線のB1地点(標高350m前後)あたりでしょうか。入り組んだ峡谷に出ます。