









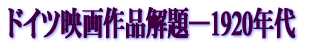
| 1920 | |
| 1920 �w�X�L�[�̋��� Wunder des Schneeschuhs�x �A���m���g�E�t�@���N�ē� 1920 �w�}���A�E�}�O�_���[�i Maria Magdalena�x ���C���z���g�E�V�����c�F���ēA�V�i���I�F�i�t���[�h���q�E�w�b�x���̃h���}�ɂ��j �y�L���X�g�z���C���z���g�E�V�����c�F���A���V�[�E�w�[�t���q�A�p�E���E�n���g�}�� 1920�i���{����1921.11.9�j �w�J���}�]�t�̌Z�� Die Brüder Karamasoff�x �J�[���E�t���[���q�ēA�V�i���I�F�J�[���E�t���[���q�i�h�X�g�G�t�X�L�[�̏����ɂ��j�A�B�e�F�I�b�g�[�E�g�[�o�[�A���u�F�n���X�E�]�[���� �y�L���X�g�z�t���b�c�E�R���g�i�[�i�V�J���}�]�t�j�A�x�����n���g�E�Q�c�P�i�C�����j�A�G�~�[���E���j���O�X�i�f�B�~�g���j�A�w���}���E�e�B�~�q�i�A���N�Z�C�j�A���F���i�[�E�N���E�X�i�X�����W���R�t�j�A�t�[�S�E�t���[���q�i�O���S���[�j�A�O�����t�B�b�c�E�~�����X�J�i�O���V�F���J�j�A�n�i�E�����t�i�J�^���[�i�j�A���h���t�E���b�e�B���K�[�A�p�E���E�J�E�t�}���A���[�t�B�[�l�E�h�[���A�C�����K���g�E�x�����A�h���[�E�A�C�q�F���x���N�A�J�[���E�c�B�b�N�i�[�A�t�����c�E�R���l���E�X�A�n���X�E�[�[�j�E�X�A���h���t�E�[�[�j�E�X�A�t�F���f�B�i���g�E���[�x���g �y����z���V�A�̘V�n��Ƃ��̎O�l�̑��q�A�f�B�~�g���A�C�����A�A���N�Z�C�̔ߌ��I����B 1920�i���{����1922.10.6�j �w�e�����ւ�j Der verlorene Schatten�x ���[�t�X�E�O���[�[�ēA�V�i���I�F�p�E���E���F�[�Q�i�[�A�B�e�F�J�[���E�t���C���g�A���u�F�N���g�E���q�^�[ �y�L���X�g�z�p�E���E���F�[�Q�i�[�i�Z�o���_�X�F���y�Ɓj�A�����_�E�U�����m���@�i�o�[�o���F�ނ̈��l�j�A���F���i�[�E�V���b�g�A�O���^�E�V�����[�_�[�A���B���w�����E�x���h�E�A�A�f�[���E�U���g���b�N�A�w�[�g���B�q�E�O�[�g�c�@�C�g�A���I���n���g�E�n�X�P���A�n���l�X�E�V���g�D���� �y����z���y�ƃZ�o���_�X�̓��@�C�I�����̖��킪�~��������ɁA�e�G�ŋ��̖��@�����̌��Ԃɏ���āA����������̉e����������B�ނ̈��l�o�[�o���́A���̌��ɏƂ炵�o���ꂽ�ނ̎p�ɉe���Ȃ��̂����āA�C�������Ƃ����̂����[�B�h�C�c�E���}���h��ƃA�[�_���x���g�E�t�H���E�V���[�~�b�\�[�̗L���ȁw�y�[�^�[�E�V�����[�~�[���̕s�v�c�Șb�x��|�Ă�����i�B 1920.2�� �w���F�̎� Der gelbe Tod�x ��ꕔ�F�J�[���E���B���w�����ēA�B�e�F�A�N�Z���E�O���[�g�N���[�G�� �y�L���X�g�z�O�X�^�t�E�A�h���t�E�[�����[�A���[�U�E���@���b�e�B�A�O�C�h�E�w���c�t�F���g�A���h���t�E�N���C�������[�f���A�n���l�E�u�����N�}�� 1920.2.3 �w�����S�i�u���̏����߂���l�l�v�j�x �t���b�c�E�����O�ēA�V�i���I�F�e�A�E�t�H���E�n���u �y�L���X�g�z�J���[���E�g�G���A���[�g���B�q�E�n���^���A�w���}���E�x�b�g�q���[�A�A���g���E�G�g�z�[�t�@�[�A���h���t�E�N���C�������b�Q�A���[�x���g�E�t�H���X�^�[�������i�K �y����z�x�������́u�}�������n�E�X�v�ŕ���B 1920.2.6 �w�w偁iDie Spinnen�j�x��w�_�C���̑D (Das Brillantenschiff�j�x �t���b�c�E�����O�ēA�V�i���I�F�t���b�c�E�����O�A�B�e�F�J�[���E�t���C���g�A���u�F�w���}���E���@�����A�I�b�g�[�E�t���e�A���[�g���B�q�E�N�����[�A�n�C�����q�E�E�����E�t�A����F�f�[�N���E�t�B���� �y�L���X�g�z�J�[���E�f�E�t�H�[�N�g�i�J�C�E�z�[�N�j�A���b�Z���E�I�����i���I�E�V���[�j�A�Q�I���N�E���[���i�w偂̌��Ђ̎�́j�A���h���t�E���b�e�B���K�[�i�W�����E�e���[�F�_�C�������h���j�A�e�A�E�c�@���_�[Thea Zander�i�G�����F�ނ̖��j�A���C�i�[�E�V���^�C�i�[ Reiner-Steiner�i�_�C���̑D�̑D���j�A�t���[�h���q�E�L���[�l�i�A�����n�u���}�[�F���K�s�ҁj�A�G�h�K�[�E�p�E�� Edgar Pauly�i�l�{�w�̃W�����j�A�}�C���n���g�E�}�E�A�[ Meinhard Maur�i�����l�j�A�p�E���E�����K���i���_���l�j�A�j�E�`�E���[�}�[�A�M���_�E�����K�[�B �y���炷���z�u�w偁v�̌��Ђ̎҂����͈ˑR�Ƃ��āA�_��I�ȃ_�C����T���Ă���B�A�W�A�Ŕނ�͈�l�̃��K�s�҂ɏo��B����Ɣނ͌��Ђ̎҂����ɁA���̃_�C���̓����h���̃_�C�������h���A�W�����E�e���[�������Ă���Ɛ�������B���̊ԃJ�C�E�z�[�N�̂ق��́A�ň��̍Ȃ��E�Q�����u�w偁v�̌��Ђ̎҂�����ǂ�������B�����Ĕނ͌x�@�ɁA���I�E�V���[�̏Z��������ꂳ����B���I�E�V���[�͂��܂���������B�������J�C�E�z�[�N��Ԃ�ŏo�ė���悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B�ނ͂���L�^�����������A����̓`���C�i�E�^�E���̉��ɂ���n���s�s�ւ̓��ē��ł��邱�Ƃ��킩�����B�����Ŕނ͂��̒n���s�s�ɔE�э��݁A���I�E�V���[���ޏ��̉��S�҂����ƊJ���Ă�����c�𓐂ݕ�������B�����Ďl�{�w�̃W�����Ƃ�炢���j�Ƀ_�C�������h���̉��~��T�点�悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��m��B���̏�ނ��m�Ƌ��R�̂������ŁA�d�|����ꂽ㩂��瓦���B �@�u�w偁v�̌��Ђ̎҂����̓_�C�������h���̖��A�G�����E�e���[��U������B�����ă_�C�������h���ɁA�_�C�������h��n���G�������ɉ������Ƃ�����Ă�����B�e���[�̓J�C�E�z�[�N�ɏ��������߂�B�J�C�E�z�[�N�͑D���������e���[�̐�c�̎c�������ނ���A�_�C�������h�̉B���ꏊ�ɂ��Ă̔閧��ǂݎ��B����͑吼�m�̃t�H�[�N�����h�����ɂ���B�e���[�̉��~���Ď����Ă����l�{�w�̃W���[���A���̔閧��m��A�`�����̒ʐM�ł�������I�E�V���[�ɓ`�B����B���̌��ʃt�H�[�N�����h�����ŁA�J�C�E�z�[�N�ƃ��I�E�V���[���Ō�̑���������B�܂��ŏ��ɃJ�C�E�z�[�N���_�C�������h�̂��铴���ɓ��B����B�������ނ́u�w偁v�̌��Ђ̎҂����Ɏ�艟��������B������ɉΎR�̃N���[�^�[����L�ł̏��C������o�āA���荞��ł����u�w偁v�̌��Ђ̎҂���������ł��܂��B���т��ɂȂ���Ė������o�܂��Ă����J�C�E�z�[�N�����́A�E�o���邱�Ƃ��ł����B �@�T���t�����V�X�R�ɖ߂����J�C�E�z�[�N�́A�Ƃ��Ƃ��u�}�C�X�^�[�v�Ə̂���u�w偁v�̌��Ђ̖��m�̎�̂ɏo��B���̌��ЂɃ_�C���T�����ϑ����Ă����C���h�̔閧���@�ւ��A����ނɕs�M�̔O������A�ނ��Ď�������B�ނ͓����悤�Ƃ��邪�A�C���h�̔閧���@�ւɎE�����B�C���h�l�͂���ɃG�����E�e���[���E�����Ƃ���B�������J�C�E�z�[�N�Ɣޏ��̕��e���A�Ō�̏u�Ԃɔޏ����~�����Ƃ��ł���B 1920.2.26�i���{����1921.5.13�j �w�J���K�����m Das Kabinett des Dr.Caligari�x ���[�x���g�E���B�[�l Robert Wiene�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[�A�n���X�E���m���B�b�c�A���u: �w���}���E���@�����A���@���^�[�E���C�}���A���@���^�[�E���[���q�A�B�e�F���B���[�E�n�[�}�C�X�^�[ �y�L���X�g�z���F���i�[�E�N���E�X Werner Kraus�i�J���K�����m�j�A�R�����[�g�E�t�@�C�g Conrad Veidt�i�`�F�[�U���j�A�����E�_�[�S���@�[ Lil Dagover�i�W�F�[���j�A�t���[�h���q�E�t�F�[�A�[ Friedrich Feher�i�t�����V�X�j�A �n���X�E�n�C�����q�E�t�H���E�g���@���h�t�X�L�[ Hans Heinrich von Twardowski�i�A�����j�A���[�h���t�E���b�e�B���K�[ Rudolf Lettinger�i�q�����J��I���t�@�[�X�j�A���[�g���B�q�E���b�N�X Ludwig Rex�A�G���U�E���@�[�O�i�[ Elsa Wagner�A�w�����[�E�y�[�^�[�X Henri Peters�A�A���m���c Arnolds�A�n���X�E�����U�[�����h���t Hans Lanser-Ludolff�B �y���炷���z���_�a�@�̊��҂̃t�����V�X���A�a�C���Ԃƈꏏ�Ɏ{�݂̒�̃x���`�ɍ����Ă���B�_��I�ȑ̌��ɂ��Ă̔ނ̕���Ɏ����X���Ă���B�����ߑ��̏����W�F�[�������S�����悤�ɔނ�̑���ʂ肷�������A�ނ́u���ꂪ���̍Ȃł��B�����ޏ��ƈꏏ�ɑ̌��������Ƃ��A���Ȃ����̌��������Ƃ��ꡂɊ�Ȃ��Ƃł��v�ƌ������B�����Ĕނ͔ނ̕����b���͂��߂�B������z���X�e�����@���ɍ̎s������ė���B��������̋��s�t������ė������A���̒��ɂ̓J���K�����m�Ǝ��̂��Ă����Ȓj�������B�ނ͍̎s�Ɏ����̏ꏊ�����蓖�ĂĂ��炤���߂ɁA�����̎������ɂ���ė������A�������Ƒ҂�����A��������{���Ă��܂��B����Ɣނ̖����Ăꂽ�B�ނ͖����̏��L�̎������ɔ�э���ōs�������A���L�͔ނ��Ђǂ����\�Ɉ����A���ꂩ�當���ʂ����o���B���̖�ɖ����̏��L�͎E�����B�t�����V�X�Ɣނ̗F�B�̃A�����́A�������W�G�[���������Ă���B��������l�͂ǂ�Ȓ��荇�����f�O���āA�ꏏ�ɔM�����Ă���ޏ��ɑI���̎��R���䂾�˂邱�Ƃ𐾂��Ă���B�̎s���J�����ƁA��l�̓J���K�����m�̏�����K���B�ނ̓`�F�[�U���Ƃ������̖��V�a�҂𐁒����A���܂�Ĉȗ��A�Q�R�N�������Ă��āA������\���ł���ƌ����B�t�����V�X�ƃA�������`�F�[�U�������Ă���B�����ăt�����V�X���x�������ɂ�������炠���A�A�����͖��V�a�҂ɁA�u�l�͂ǂꂭ�炢�������邩�v�Ǝ��₷��B�`�F�[�U���������J���A�u�����̒��܂Łv�Ɠ�����B���ɂȂ��ăt�����V�X�́A�A��������ӎh���E���ꂽ�ƕ����m��B�t�����V�X�̓J���K�����m�ɋ^����������B�������x�@�͉��̏؋��������ł��Ȃ��B�����đ�R�̎E�l���N���A���x�͔Ɛl�������߂܂��āA�߂��ؖ������ƁA�����͂������������Ǝv���B�����Ď����͓�l�̎E�l�ɍ߂͂Ȃ��Ƃ������̒j�̐������A�M�p���悤�Ƃ��Ȃ��B�������t�����V�X�̓J���K���̔��n�Ԃ���A�����ڂ𗣂��Ȃ��B�ނ͎Ԃ̒������������B�`�F�[�U���͊������悤�ȗe��̒��ɐg���났�������ɉ�������Ă���B�������̒��Ƀ`�F�[�U���̐l�`����������Ă���ԂɁA�{���̃`�F�[�U���͖��̃W�F �[���̐Q���̐N�����Ă���B�W�F �[�����ڂ��o�܂��B�ޏ��͌��m��ʒj�̎p�����āA���юn�߂�B��ȓ���S�ɖW�����āA�`�F�[�U���͔ޏ����E�����Ƃ��Ȃ��B�����Ĕނ͔ޏ����x�b�h�����������o���āA�ޏ��ƈꏏ�ɑ��苎��B���e�Ƌߏ��̐l�X���ނ�ǂ��B�t�����V�X�����͒ǐՎ҂̒��ԂɂȂ��Ă���B�`�F�[�U���͏����𗎂Ƃ��āA����ɓ����A���ɏo�ē|���B�t�����V�X�̓J���K���̔��n�Ԃɋ}���ōs���B���x�͌x�@���ނɓ��s����B�x�@���������J���Đl�`��������B�J���K�����m�͂��̊Ԃɓ�����B�t�����V�X�͔ނ̐Ղ�ǂ��A���鐸�_�a�@�ɒ����B�t�����V�X�̓x����炷�B���l�̈�t���ނ��@���̂Ƃ���֘A��čs���B�����ċ��������ƂɁA�ނ͉@���ƃJ���K�����m������l�����Ƃ������Ƃ�����B�J���K���̋��Ȃ��Ƃ���ŁA�t�����V�X�͏���̈�t������������āA�ނƈꏏ�ɃJ���K���̔閧�̏��ނ�O��I�ɒ��ׂ邱�Ƃ��ł���B�ނ�͉@�����J���K���Ƃ������̖��p�t�̕���Ɏ��g��ł������Ƃ�����B�J���K���͂P�W���I�ɖ��V�a��}��ɂ��āA��������̎E�l��Ƃ��Ă����̂������B�`�F�[�U�����a�@�Ɉ����n���ꂽ���A�@���͔ނ��E�l�̔}�̂ɂ��悤�ƌ��ӂ����B���̔����Ǝ��`�F�[�U����˂�����ƁA�@���͓|��Ă��܂��A�S���߂𒅂�����B�t�����V�X�͔ނ̕�����I�����B�`�F�[�U�������Z���Ă���{�݂̐������A���̂܂ܐi�s����B�E�ϋ����@������������Ă��鎞�A�t�����V�X���ނɏP���������āA�ނ��������E�l�҂��ƙ�߁A�ނ��i�ߎE�����Ƃ���B�u�������݂͂�ȁA�l�������Ă���Ǝv���Ă���B��������Ȃ��@���������Ă���̂��I�I�ނ̓J���K�����A�J���K�����A�J���K�����I�v�ނ͉��������܂�A�Ƌ����Ɉ��������čs���B�@�����ނ�f�@���A���ꂩ�珕�肽���ɐ�������B�u�Ƃ��Ƃ����͔ނ̖ϑz��c�������B�ނ͎������̐_��I�ȃJ���K�����Ǝv���Ă���I�@�����č��⎄�͔ނ��������@���킩�����v�B �y����z�x�������́u�}�������n�E�X�v�ŕ���B�u�\����`�f��v�Ƃ��ē��قȃZ�b�g�����̐S����f�������āA�h�C�c�f��̉���������J��������I��i�B�W�[�t���[�g�E�N���J�E�A�[����Ɏ���̌`�p�ɖ͔͗�I�\�N��F�����A�ނ̉f��j�����Ɂw�J���K������q�g���[�ցx�i1947�j�Ƃ����^�C�g����^�����B�i�N��L39�j �y�f��]�z���u�L�l�}�g�O���t�v�i1920�j��686���\�\�u�c�c�x�������͂�����V�炵���L���b�`�t���[�Y���������B�u�N�̓J���K���ɂȂ�˂Ȃ�ʁv�Ƃ����̂ł���B���T�ԑO����A���̂��킭���肰�Ȓ茾�I���߂��A������L��������A�l�ɂ�߂����āA����������V���̗������яo���B�����ʂ����́u���Ȃ��͂����J���K���ł����H�v�ƁA�����˂�B�ȑO�u���Ȃ��͑����}�m�[���m���F�^�o�R�̏��W�n�Ƃ����˂��̂ƁA�قړ����悤�ɁB�����āu�f��ɂȂ����\����`�v�Ƃ��u���C�v�Ƃ����A���킳�̎�ƂȂ����B���č��₻�ꂪ�A���̍ŏ��̕\����`�f�悪��f����Ă���B�����Ă��ꂪ���_�a�@�ʼn�������Ƃ����_�������A�������C�̗v�f�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�l������|�p�ɑ��Ăǂ̂悤�ȑԓx����낤�Ƃ��A���̏ꍇ�͂���́A���m�ɂ��̎��i������B���������_�̕a�I�Ȗϑz�́A�����̂䂪�A��Ȍ��z�I�f���̒��ɁA�ō��x�ɂ܂ō��߂�ꂽ�\�������o���Ă���B���E�͋��l�̓��̒��ł͈�����l����悵�A�ނ̌��z�̐l���������A�����I�ɂ͗H��̂悤�Ȍ`������Ă���悤�ɁA�ނ炪���̒��œ����Ă�������A����ȑ��e��悷��B�O�p�`�̑���h�A������c�����A���I�ɋȂ��肭�˂����ƁA���Ԃ̂悤�ȉ����c�c�B�n���h�����O�͐l���n���n�������A�����̃V�[���͒��ړI�ɐl�̐S�𖣘f���A���Â܂�悤�Ȍ��ʂ����Ȃ��Ă���B�Ⴆ�ΎE�l�̃V�[���B���̏ꍇ����g�ݍ����Ă���l�������̉e���������Ȃ��i���łȂ��炻��́A�Z�p�I�ɂ����炵�����������f���ł���j�B���邢�͋��l�̉ԉł̖��̑̌��B���̒��Ŕޏ��͖��V�a�҂Ɏ�艟�������A�߂܂�����قNj��������A�����z���Ɉ���������čs���B���_�a�@�̒���̍ŏI��ʂ��A���Ɉ�ې[�����ʂ������B�����ł͋��l�͋����̔�����N�����A�S�֕��ŗ}������B�t���b�c�E�t�F�[�G���͂��̋��l���A���炵���g�U�艉�Z�ʼn����Ă���B��ʂɋ����ґS���Ɖ��Z�̏o���f���͂܂��������Q�ł���B�J���K�����m�̌��z�I�ȕ������������F���i�[�E�N���E�X�A����͂����ȒP�ɂ͐^���̂ł��Ȃ��悤�Ȉ�i�ł���B�N���E�X�ƕ���ŁA�܂������s�C���Ȉ�ۂ�^���閲�V�a�҂ɕ������A�R�����[�g�E�t�@�C�g�̈����I�ȗތ^�B�_�o���Ȑl�Ȃ�A���̂��߂ɖ��̒��ł��Ȃ���邩������Ȃ��B���l�̉ԉł́A�₳���������������Ȃ��������E�_�[�S���@�[�������Ă���B���܂�d�v�Ȗ��ł��A���h���t�E���b�e�B���K�[�ƁA�L���Ȏ��l�ł���N�ǎ҂ł���n���X�E�n�C���c�E�g�D���@���h�t�X�L�[�́A���炵���B���[�x���g�E���B�[�l�́A�����̂悤�Ɏ��ꂽ�ēԂ�������A��ƃ��@�����A���C�}���A���[���q�ƈꏏ�ɁA�P�������ʐ^�ɂ��`�ʂɎx�����āA������ۂݏo���Ă���B�u�f�[�N���v�f���Ђ͂��̍ŐV��i�ɂ���āA�f��|�p���܂��s���l�܂��Ă͂��炸�A����ɔ��W����V�炵���A���m�̉\���Ɍ������ĊJ����Ă��邱�Ƃ��ؖ������B �@�u���̉f��̔������o�����̂́A�V�N���A�v��������_���̕��͋C�A�s�ӑł��̖��͂ȂǁA������v�������͂��Ĕ������ꂽ�����I�G�l���M�[�ł���B�M�a�̖����A�g���Â���Ă��Ȃ��A�܂������V�炵����i�ɂ���āA�ӎ��I�Ɍ|�p�����ɑg�ݓ������B���\�Ȏ���ɕ���ꂽ���̉f��́A�܂�ŔM�a���̌��ʂ�����B�Â��X�H�A���Ȃ����狿���Ă��閽�ߒ��̍��߁A�ǂ�������̊X�������Ƃ̍b�������с[�[�����Ĕw�i�ɂ́A�X�̒����̒n�悪�[���ł��畂���т�����A�}�i�I�Ȑ�҂����ɂ���Đ�̂���A�e�̔j�A��A�̕����A���ォ��̎ˌ��A��֒e�c�c�B �@���̍��Ղ����̉f��̒��ɂ���B���̃J���K�����m�́AE�E�s�EA�E�z�t�}���̖����������Ă���B�ނ͌̋����ړI���Ȃ��_��I�Ȓj�ŁA���������ɂ��āA�l�ԂɈ����̖���������߂�B���錈�肵���ӎu�̂Ȃ��f�����ł���A�ЂƂЂƂ̐g�U��ɉ����s���Ȑ��̕s���Ȃ��̂�����A�ЂƂЂƂ����V�����Ȃ����߂̃|�P�b�g�ɖ����Ă���Ŗ�ɉ��ڂ��g���Ă���B�����ėd���I�ȗH��ɁA�����ȏb������̉�����Ă���B����f�r���҂̖��V�a�I�Ȑ��m���A������|�p�T�O���z�����ފ݁A�����A�肪����A�����s�ׂ�����A�����ЂƓ˂������邾�����B�ē��[�x���g�E���B�[�l�́A�l�����A�\���̘g�ɐ��_�I�ɓK������悤�ɂƂ߂Ă���B���Ȃ킿�A�S���̂Ȃ��l���A���@���������Ȃ��s���ҁA�P���Ɍ�������͂ł����Ă��A���̎��Ԃ����]�̂Ȃ��Ɍ����Ȃ��l�Ԃɂ��Ă���B �@���B�[�l�́A�ނ̋��͎҂����������Z�p�I�ɍ\�����ꂽ���E�̒��ɗL�@�I�ȍޗ���g�ݍ��ޓw�͂��Ă���B�ނ́A�o�D�̗L�@�I�Ȍ`�̂��A����Ό��z�̌`�������̂��Ƃ���p���鉼�ʂŌ��킷�Ƃ���܂ł́A���Ȃ������B���������āA�������������ɂ���č\�����ꂽ�Q�̐��E���Փ˂��Ă���B�L�@�I�Ȃ��̂��A���w�I�Ɍ`�����ꂽ���̂ƐڐG���Ă��̓���͕s�\�ɂ݂���̂ł���B���B�[�l�̉��o�́A���̕���̂��т�����a�炰��ƓI�ȃj���A���X�����o���āA��ʂ̋C���Ńo�����X���Ƃ��Ă���B �@���̋C���Ɋ�Â��ĉ�Ƃ����́A���`���Ă���B�\����`�̑����I���ʂ��A���ɐ��m�Ɋ����Ƃ��Ă���v�i�w�\����`�̉����E�f��x�͏o���[�A320�y�[�W�ȉ��j�B �����b�e�E�g�E�A�C�X�i�[:�w�\����`�f��|�p�̒a���x�\�\�u�\����`���w�ɂ����āA���ꂬ��̌�����C�܂܂ȕ��@�I�|�u�Ƃ��ĕ\����Ă���A����߂��������R���g���X�g�ւ̌X����A������_��̏d���e���h�C�c�l�̐��܂���̐����́A�V�����f��|�p�ɂ����Ă��̗��z�I�ȕ\���������o���ɈႢ�Ȃ������B���h��s�����Ăяo�������e�́A�f��ł͔��͖����I�Ȏp�ŁA���͋�̓I�ȃ��A���e�B��ттāA�h���Ă���B��������悤�Ƃ��鐸�_���͂̎��݁A���ׂĂ̐S���w�ɓG�ӂ�����\����`�I���E�ς̔M�����A�����鎞��̒��ł����Ƃ����ׂƂ������̎���ɂ����āA���}����`�̗H��̐��E�̌����Ċ��S�ɂ͖Y����Ă��Ȃ������_���`�Əo��B�����ł̂��ɂȂ��āA�\����`�I�ȗl���ӎv�����łɉߋ��̂��̂ƂȂ������ɁA�S���ł��邱�Ƃ���������f��ēE�Ⴆ���[�x���g�E���B�[�l�̃P�[�X������ł���E���A���ɗ͋��������̉f������Ƃ������Ƃ��A�N���肤��B�E�Ɩ��ɐ��ʂ��������ȃv���f���[�T�[�ł���G�[���q�E�|�}�[�́A��{��҂������A�A���t���[�g�E�N�[�r�����f��̃Z�b�g�̍쐬�̂��߂Ɋl���������Ƃ����Ӑ}�������Ă����ƌ���Ă���B�N�[�r���Ȃ炫���ƁA�S�����̉f����a���������ł��낤�B�@���̊댯�Ȑ[������Ƃ�āA�ʂ̕��@�ŁA�����\����`�f��ɓ��݂��Ă���A���o�������铯�����ɒB�������Ƃł��낤�B�N�[�r���̓��m���B�b�c�Ɠ������A���̐_��I�ȃS�[�����̒��A�v���n�̏o�g�������B�����ă��m���B�b�c�̂悤�ɔނ́A�s�C���Ȓ��Ԑ��E�̋��|��m���Ă����B�E������芪�������̃f���[�j�b�V���ȑn���҂ł���N�[�r���ɁA�w�J���K���x�̑��u���l�Ă��邱�Ƃ�������Ȃ������̂́A�c�O�ł���B������ɂ��Ă��J�[���E�}�C���[�̌|�p�����Őq��łȂ����̂Ƃ��������^���Ă������̉f��̃X�^�C���ɂƂ��āA��ې[���\����`�̑��u�͌���I�ł������B���������[�x���g�E���B�[�l�̉��o���ꡂɌ���I�ł�����!�@�����G��̒��Ɉ��E���ꂽ�v���̔����������邱�Ƃ̂ł����h�C�c�A�o�Ϗ�Ԃ������Ă��̐l�X�̐��_��ԂƓ��l�ɕs����Ɍ������h�C�c�ɂ����ẮA�l���̎������_�Ȋv�V�ɂ͑S���D�s���ȕ��͋C���������v�B 1920.2.27 �w�֕��\�\��̐���s�� Der Reigen�x ���q�����g�E�I�U���@���g Richard Oswald�ēA�V�i���I�F���q�����g�E�I�Y���@���g�i�A���g�D�[���E�V���j�b�c���[�̏����w�֕��x�ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�z�t�}���A�A�N�Z���E�O���[�g�N���[�G�� �y�L���X�g�z�A�X�^�E�j�[���[�� Asta Nielsen�i�G���i�j�A�R�����[�g�E�t�@�C�gConrad Veidt�i�y�[�^�[�E�J�����@���j�A�G�h�D�����g�E�t�H���E���B���^�[�V���^�C��Eduard von Winterstein�i�A���x���g�E�y�[�^�[�X�j�A�e�I�h�[���E���[�X Theodor Loos�i�t���b�c�E�y�[�^�[�X�j�A�C���[�E�t�H���E�^�b�\�[�������g Ilse von Tasso Lind�i��j�A���[�j�E�l�X�g Loni Nest�i�q���j�ȂǁB �y���炷���z�G���[�i�͑������疳�O���ɂȂ������������B�p��͔ޏ����Ƃ���ǂ��o���Ă��܂����B�Ƃ����͔̂ޏ�������s�A�m���t�ɍ���Ă��܂������A�ނ͌�������Ƃ��Ă͕n�����������炾�����B�ޏ��͂��̃s�A�m���t�̗F�l��ʂ��āA�y�[�^�[�E�J�����@���ƒm�荇���B�ނ͔ޏ��̈��l�ƂȂ�A�ޏ����L���o���[�̉̎�ɂ��悤�Ƃ���B�����Ŕޏ��̓J�����@�����玩�R�ɂȂ邽�߂ɁA����㗬�K���̉Ƃ̉ƒ닳�t�ɂȂ�B���̉Ƃ̎�l���ޏ��ɋ߂Â��A�Ȃ�����ɔޏ��ƌ�������B����ƃG���[�i�͎����̋`���̌Z��A�A���x���g�E�y�[�^�[�X�ɍ��ꍞ�݁A�ނ̂ق����ޏ������߂�B�y�[�^�[�E�J�����@�����Ăюp�������A�������ċ�����������B�����ăG���[�i�Ǝ����Ƃ̂��Ă̊W�Ɣޏ��̂���܂ł̕���\�I����B�y�[�^�[�X�͔ޏ����Ƃ���ǂ��o���B�G���[�i�͍��x�́A�J�����@���ƈꏏ�ɁA�Ƃ���ᑭ�Ȏ���ɓo�ꂷ��B�����ăJ�����@���̊�A�d�ŁA�Z�팖�܂ɂȂ�B����ƃA���x���g�E�y�[�^�[�X�͋����̂��܂�A�����̔�����N�����ē|���B�G���[�i�̓y�[�^�[�E�J�����@�����ˎE���A�������ł��������B��͂�ޏ��������Ă���t���b�c�E�y�[�^�[�X������ė����Ƃ��ɂ́A�����łɒx���A�ޏ��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �y�f��]�z���u�f�A�E�t�B�����v���A1920�N��10���\�\�u�c�c���e�����łȂ��A�l�������ތ^�I�ł���B���̒��̈��̂悤�ȏ��A�����炵�A�����ĕv�A�s�K�ȗ��l�B�}�S�̐V��̒����炱�̉f����ۗ������Ă���̂́A�I�X���@���g�̂����ꂽ�ē̉��ŁA���Z���\���Ȑ��ʂ�����������ł���B�܂��ǂ����u�ʖځv�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ�����̃A�X�^�E�j�[���[���ɁA�I�X���@���g�͐V���Ȍ��ʂ���@���^�����B�܂��R�����[�g�E�t�@�C�g����͐h煂ȃE�C�b�g�������o�������A����̓t�@�C�g�̌`�p�ɐV�����j���A���X��Y�������̂������B�܂����B���^�[�V���^�C���̖��^�̉��Z��l�Ԑ��L���Ȃ��̂ɍ��߁A���[�X�ɂ͓���̂���ӂꂽ�̌����A�ߌ��I�ȏɂ܂Ő���グ�������B�f���Ƒ��u���A�o�D�w�̉��Z���l�A���炵�������v�B ���u�L�l�}�g�O���t�v���A1920�N��686���\�\�u�c�c����ӂꂽ���f��B����ȏ�̂��̂ł͂Ȃ��B���q�����g�E�I�X���@���g�ɂ͂����Ɨǂ���i�����邵�A���N���N�����o�āA�Ăщߋ��̖��y����p���������A�X�^�E�j�[���[�����A���҂͂��ꂾ�����c�B�����Ƃ����Z�͈�т��Ă��炵�������B�R�����[�g�E�t�@�C�g�͂����̂悤�ɔ��Q�ŁA�����Ԃꂽ���y�Ƃ̖��ɁA�^�̐����𐁂�����ł���B���܂�L���Ȃ��̃G�[�h�D�����g�E�t�H���E���B���^�[�V���^�C���ƃe�I�h�[���E���[�X���A�őP��s�����Ă���B�q���̏����ȃ��[�j�E�l�X�g���A�����ׂ����̂�����v�B �y����z����ǂ��j���������X�ɂ��ǂ�v���Z�X��`�����V���j�b�c���[�̃h���}�Ɋ�Â��f��B 1920.3�� �w���F�̎� Der gelbe Tod�x��� �J�[���E���B���w�����ēA�B�e�F�A�N�Z���E�O���[�g�N���[�G�� �y�L���X�g�z�G�����X�g�E�h�C�b�`���A�}���K���[�e�E�V�F�[���A�O�X�^�t�E�A�h���t�E�[�����[�A�O�C�h�E�w���c�t�F���g�A�n���l�E�u�����N�}���A�I���K�E�����u���N�A�G���f�����[�E���r�E�X�A���h���t�E�N���C�������[�f���B 1920.3.9�i���{����1921.12�j �w�����o�� Kohlhiesels Töchter�x �G�����X�g�E���r�b�`�� Ernst Lubitsch�i��1920�N3��12���j�ēA�V�i���I�F�n���X�E�N���[�� Hanns Kräly�A�G�����X�g�E���r�b�`��E. Lubitsch�A�B�e�F�e�I�h�[���E�V���p�[���N�[�� �y�L���X�g�z�w�j�[�E�|���e���AHenny Porten�i����F�O���[�e���^���[�[���j�A�G�~�[���E���j���O�X Emil Jannings�i�y�[�^�[�E�N�T���F��)�A�O�X�^�t�E�t�H���E���@���Q���n�C�� Gustav von Wangenheim�i�p�E���E�[�b�v���j�A���[�R�v�E�e�B�[�g�P Jacob Thiedtke�i�}�e�B�A�X�E�R�[���q�[�[���j �y���炷���z�h���̎�l�}�e�B�A�X�E�R�[���q�[�[���ɂ́A��l�̖�������B�o�̃��[�[���͂��悻���h���̂��Ȃ��A�K�~�K�~���̂������ł���B���̃O���[�e���͔��ɐl�D���̂���A���f�I�ȁA�݂��݂����������ł���B��҂����݂͂�ȃO���[�e���̐K��ǂ������邪�A���ɂ����܂����N�T���F���ƍT���߂ȃ[�b�v���́A�ޏ��ɔM�S�ɋ�������B �@�����ăN�T���F���ƃO���[�e���͂Ђ����Ɏv�������킷�B���������e�̃}�e�B�A�X�͔_���̕��K�ɏ]���āA�o������Ɍ���������łȂ���A�O���[�e���̌������������Ƃ��Ȃ��B���[�[���̌��炵����ł����l����ƁA�����Ȃlji�v�ɂł��Ȃ���������Ȃ��B�����������̎ア�N�T���F���ɑ��āA�[�b�v���͂܂����[�[���ɋ������邪�����A��������ΊԈႢ�Ȃ��O���[�e�����l���ł���Ɛ������A���܂��܂Ɛ�������B �@�N�T���F���̓[�b�v���̒����ɏ]���āA�ˑR���[�[���ɋ�������B�������Ă���ޏ��̐l�t�������̈����𗝗R�ɗ������A���ɃO���[�e�����Ȃɂ��悤�Ƃ�������ł���B���낢��Ɩʓ|�Ȍ����̏����̌�A�������������Ȃ���B���ꂩ��N�T���F���͂��Ⴖ��n��炵���J�n���A�܂��Ƃ̉Ƌ��S�����������o���Ă��܂��B����Ƀ��[�[��������Ƃ��A���ꂩ�玟�X�Ɏ����悤�Ȏ�r�ȍs�ׂ�����B����ƈӊO�Ȃ��ƂɁA���[�[���͗r�̂悤�ɂ��ƂȂ����Ȃ�A����������炵���Ȃ��āA���z�I�ȍȂɕϐg����B�����ăN�T���F���̈������߂āA�����炵���g������n�߂�B�N�T���F�������͂������胊�[�[���̂ق����ǂ��Ȃ�A�����������悤�Ƃ͎v��Ȃ��Ȃ�B�������ē�l�͂������莗�����̕v�w�ɂȂ��Ă��܂����̂ŁA�[�b�v���̓O���[�e���ƈꏏ�ɂȂ�A�����ڏo�x���ƂȂ�B �y����z�w�j�[�E�|���e������������������̔_���쌀�ɂ��āA�G�����X�g�E���r�b�`���͂��������Ă���B�u�����h�C�c�����������쌀�f��̒��ŁA��Ԑl�C���������̂́A�w�����o���x�������B����́u���Ⴖ��n��炵�v���o�C�G�����̎R�n�ɈڐA�������̂ɑ��Ȃ�Ȃ������B����͓T�^�I�Ƀh�C�c�I�ȏo�����������v�B�m���ɂ���̓h�C�c�I�ȁA���������������Ȃ����[���A�̊쌀�ł���A���X�����������B �@�w�����o���x�̕���͐�̒��ł���B�Ƃ����̂̓��r�b�`�����E�C���^�[�X�|�[�c�ɔM�����Ă������炾�����B����ɔN�Ɏl�{�T���ܖ{�Ƃ����n�[�h�Ȑ���X�P�W���[�������Ȃ��Ȃ���A�����ɃX�L�[�x�ɂ����Ƃ����w�����������邽�߂ɂ́A���B�e�̎d�����E�C���^�[�X�|�[�c�̉\�͏��ł�鑼�͂Ȃ������B�����Ń��r�b�`���ɂ͐�̉f�悪�������邱�ƂɂȂ����B�w�����[�W���̃i�C�g�x�A�w�����o���x�A�w��̃����I�ƃ����A�x�A�w�R�L�����V�J�x�ȂǂȂǁB �@�����ă��r�b�`���͂��������w�i��l���I�Ɏg�����Ȃ�����̓_�ł́A�ǐ��������Ȃ������B�Ⴆ�T���߂ȃ[�b�v�������~�̖̏��̉��ɓn�����̏�ɍ����āAꡂ����̉����ɗ����Ă���N�T���F���Ɛe�����Θb�����킷��ʂ�����ł���B���̕���ŗ���{�̃��~�̖́A�V�܂łƂǂ��قǍ����A�������Ă���܂ł�������ނ��o���ł���B���܂��܂������ނ��Ă����ł���ɂ��Ă��A�܂�ł���͈�̗l���I�ȃZ�b�g�Ƃ��āA���̕��i�̒��ɐA����ꂽ���̂悤�Ȉ�ۂ�^����B �@���邢�͌������̌�̃_���X�̏�ʁB�_���X�E�t���A�̑傪����ȃZ�b�g�́A������j���A���X�̑f���炵���Z�W�̏Ɩ��ɏƂ炵�o����Ă���B���̗l�������ꂽ������A�G�~�[���E���j���O�X������V���̃y�[�^�[���A���������悤�ɋ��\�ɉ~��`���Ȃ���A�ނ̂��Ⴖ��n�V�w���|���J�ň�������B�ނ͎��͂ɗ����Č������Ă���l�������Čジ���肵�Ă����^�ցA���݂Ȃ炵�Ȃ���ːi���čs���B�_���̗x�肪�A�ϋq�̎��o�����o����Ⴢ��Ă��܂��قǂɌ������U��t�����A�l����������Ă���B �@�������������T�^�I�Ƀh�C�c�I�ȃR���f�B�[�ɂ����Ă���A�q���C��������h�b�y���Q���K�[�i��d�l�i�j�ł��邱�Ƃ́A���ڂɒl����B����̓w�j�[�E�|���e��������������邱�Ƃɂ��A�P�Ȃ�쌀�I���ʂȂǂł͂Ȃ��B�w���g�x�A�w�v���[�O�̑�w���x�ȗ��A�h�C�c�f��̖{���I�����Ƃ������ׂ��u�����ꂽ��̍��v�Ƃ����ݒ肪�A�R���f�B�[�ɂ����Ă��瓥�P����Ă���̂ł���B��̍��������Ă���̂́A�w���g�x�̃n���[�X���m��w�v���[�O�̑�w���x�̃o���h�D�C���Ƃ������j�������ł͂Ȃ��B���������܂���̍��Ɉ�����Ă���̂ł���B�����ɂ͓����̃h�C�c�̏W�c�I���ӎ��ɍ��������A�[���R���v���b�N�X������B��������w�j�[�E�|���e���̓�����A�쌀�I���ʈȏ�̈�ۂ�^����̂ł���B�쌀�f��ł��獰�̋T�����ՂƂ��Ă���Ƃ���ɁA�Ƃ̐[��������ƌ�����B �@���̂��߂��ǂ����͕ʂƂ��āA���̑f�ނ̓h�C�c�ł͐����ԈႢ�Ȃ��e�[�}�ƕ]������A�ĎO�ɂ킽���čĉf�扻���ꂽ�B1930�N�ɂ̓n���X�E�x�[�����g�ēŁA���łɎl�\�ɂȂ��Ă����w�j�[�E�|���e�����A�܂�����q���C�����������B1943�N�ɂ́A�N���g�E�z�t�}���ēA�w���[�E�t�B���P���c�F���[�剉�A1955�N�ɂ́A�Q�[�U�E�t�H���E�{�����@���ēA�h���X�E�L���q�i�[�剉�A�����ĂP962�N�ɂ��A�A�N�Z���E�t�H���E�A���x�b�T�[�ēA���[�[���b�e�E�v���t�@�[�剉�Ń����C�N���ꂽ�B 1920.3.12 �w��̃����I�ƃ����A Romeo und Julia im Schnee�x �G�����X�g�E���r�b�`���ēA�V�i���I�F�n���X�E�N���[���A�G�����X�g�E���r�b�`���A�B�e�F�e�I�h�[���E�V���p�[���N�[�� �y�L���X�g�z���[�R�v�E�e�B�[�g�P�A���b�e�E�m�C�}���A�O�X�^�t�E�t�H���E���@���Q���n�C���A���[�t�B�[�l�E�h�[���A�����E�X�E�t�@���P���V���^�C�� �y����z�����������Ƃ�������Ȃ���l���ӎu��ʂ��R���f�B�[ 1920.4.16 �w�S���f���n���̖� Die Nacht auf Goldenhall�x �R�����[�g�E�t�@�C�g�ēA�V�i���I�F�}���K���[�e�E�����_�E���V�����c�A�w���}���E�t�F���i�[�A���y�F�p�E���E�N���V�� �y�L���X�g�z�R�����[�g�E�t�@�C�g�A�O�V�[�E�z���A�G�X�^�[�E�n�[�K���A�n�C�����q�E�y�[�� 1920.4.30 �w�A�b�J�[�X�̖� Das Ma*dchen aus der Ackerstrasse�x ���C���z���g�E�V�����c�F���ēA�V�i���I�F�{�r�[�EE�E�����g�Q�A�A���c�F���E�t�H���E�`�F���s�[�i�G�����X�g�E�t���[�h���q�̏����ɂ��j�A�B�e�F�N���g�E�N�����g �y�L���X�g�z�I�b�g�[�E�Q�r���[���A�����[�E�t���[���A���C���z���g�E�V�����c�F�� �y����z��s�s�h���}�B 1920.5.12 �S���f��@�iREICHSLICHTSPIELGESETZ�j���z �y����z���ׂẲf��͌��J�O�ɉf�挟�{�ǁiPrufstelle�j�ŋ����˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����K��B�{�݂̓x�������ƃ~�����q�F���ɐݒu�B���C�q�̓����Ȃ̉����g�D�i�N��L38�j 1920.7.8 �w���ނ��̒j�Ɨx��q Der Bucklige und die Tänzerin�x �t���[�h���q�E���B���w�����E�����i�E�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[�i�ނ́w�̐ڕ��x�Ƃ������e�ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�t���C���g�A���u�F���[�x���g�E�l�p�b�n �y�L���X�g�z�U�b�V���E�O�[���i�M�[�i�F�x��q�j�A���[���E�S�b�g�E�g�i�W�F�[���Y�E�E�B���g���F���ނ��̒j�j�A�p�E���E�r�[���X�t�F���g�i�X�~�X�F�������̓Ɛg�j�j�A�A���i�E�t�H���E�p�[�����i�X�~�X�̕�e�j�A�A�����E�y�[�^�[�X���A���m���c�i�p�[�V�[�j�݁j�A�x���E�|���[�j�i�x��q�j �y���炷���p���i�ƕ��Q�̕���B�n���Ƃ��ނ��̑̂ɑł��̂߂���Ă����W�F�[���Y�E�E�B���g�����A�������ނ̕x�Ɛ_��I�Ȕ��e�̗�t���g���āA�W���������s����߂��ė���B�����ėx��q�̃M�[�i�Əo����A�ޏ��͔N�y�̈��l�X�~�X�ƒ��Ⴂ���Ă����B�����ŃE�C���g���͔ޏ��ɂ��̗�t��^����B�M�[�i�̓X�~�X�Ƙa�����A�ނƍ���B������t���g�����Ă��܂����̂ŁA�ޏ��͂��ނ��ɗ�t�������Ɨ^���Ă���Ɨ��ށB���i�ɋ��ꂽ�E�C���g���́A�V������t�ɓł̕���������B����͔ޏ��̐O�ɐG�ꂽ�҂͒N�ł�����ł��܂��ł������B���̂��߃X�~�X�͊���z�����N�����Ď��B�M�[�i�͋^�O��������B�ޏ��̎��̈��l�p�[�V�[�j�݂ɂ����ł̏Ǐ��ꂽ�Ƃ��A�ޏ��͋}���ŃE�B���g���̂Ƃ���֍s���B����ƃM�[�i�ɑ��ď�M�̗��ɂȂ��Ă������ނ��́A�ޏ����疳���ɐO��D���A���ꂩ���ō܂œł𒆘a���悤�Ƃ���B�������M�[�i�͔ނ̎肩�炳���ƕr��D�����A���l�̂Ƃ���}���B�E�B���g���͎��ʁB 1920.8.26�i���{����1923.2.8�j �w�W�F�L�����m�ƃn�C�h���i���k�X�̓��jJanuskopf�x �t���[�h���q�E���B���w�����E�����i�E�ēA�V�i���I�F�n���X�E���m���B�b�c�i���C�X�E�X�e�B�[�����\���̏����w�W�F�L�����m�ƃn�C�h���x�ɂ��A�B�e�F�J�[���E�t���C���g�J�[���E�z�t�}�� �y�L���X�g�z�R�����[�g�E�t�@�C�g�A�}���K���[�e�E�V�����[�Q���A���B���[�E�J�C�U�[���n�C���A�x�[���E���S�W�A�}���K���[�e�E�N�b�v�t�@�[�A�O�X�^�t�E�{�b�c�A���[���E�t�����g�A�}�O�k�X�E�V���e�B�t�^�[�A�}���K�E���C�^�[�A�����U�E���h���t�A�_�j�[�E�M�����^�[ �y����z�����̎��ӂł̔ߌ��i�x�������́u�}�������n�E�X�v�ŕ���j�N���J�E�A�[p79 1920.12.14�i���{����1924.12.5�j �w���P�Y������Sumurun�x �G�����X�g�E���r�b�`���ēA�V�i���I�F�n���X�E�N���[�� Hans Kräly�A�G�����X�g�E���r�b�`�� Lubitsch�i�t���[�h���q�E�t���N�U�̃I���G���^�����p���g�}�C���ɂ��j�A�B�e�F�e�I�h�[���E�V���p�[���N�[���A�Z�p�w���F�N���g�E�V�����@�l�b�N�A���p�F�N���g�E���q�^�[�B���� �F�E�j�I�����E�[�t�@ �y�L���X�g�z�|�[���E�l�O�� Pola Negri�i�x��q�j�A�C�G�j�[�E�n���X�N���B�X�g Jenny Hallesqvist�i�Y���C�J�j�A�A�E�g�E�G�Q�f�E�j�b�Z�� Aud Egede Nissen�i�n�C�f�[�j�A�p�E���E���F�[�Q�i�[ Paul Wegener�i�V�����j�A�n���[�E���[�g�P Harry Liedtke�i�k�����f�B���j�A�J�[���E�N���[���B���O Carl Clewing�i�Ⴂ�����j�A�G�����X�g�E���r�b�`�� Ernst Lubitsch�i���ނ��j�A�}���K���[�e�E�N�b�v�t�@�[ Margarete Kupfer�i�V�w�l�j�A���[�R�v�E�e�B�[�g�P Jacob Tiedtke�i�����j�A�p�E���E�r�[���X�t�F���g Paul Bienfeldt�i�A�N���b�h�j�A�p�E���E�O���[�c Paul Graetz�i���g���j�A�}�b�N�X�E�N���[�l���g Max Kronert�i���g���j �y���炷���z�ꏊ�͂X���I�̃o�O�_�b�h�B�����Ƃ̈�c�����ւ���ė���B���P�i�|�[���E�l�O���j�A���ނ��̓����t�i�G�����X�g�E���r�b�`���j�A�V�k�i�}���K���[�e�E�N�b�v�t�@�[�j�Ƃ������ʁX�ł���B���ނ��͗x��q�������Ă��邪�A���P�͔ނ̎��i�S���������ĂāA�ʔ������Ă��邾���ł���B�����ĕ��P�́A�V�����i�p�E���E���F�[�Q�i�[�j�̂��߂ɐV�������P�Y��������T���Ă���z�ꏤ�l�A�N���h�i�p�E���E�r�[���X�t�F���g�j�̌�ɂ��čs���B���݂̒��P�Y�������i�C�F�j�E�n�b�Z���N���B�X�g�j�́A�Ⴂ�D�����l�k���E�A���E�f�B���i�n���[�E���[�g�P�j�������Ă���̂ŁA�������玩�R�ɂȂ肽���Ɩ]��ŁA�z�ꏤ�l�̃A�N���h�ɁA�V�������P�T���𗊂̂ł���B �@�Ƃ��낪���P���܂������̋{�a�ɒ����Ȃ������ɁA�����̑��q�i�J�[���E�N���[���B���N�j�Əo����Ă��܂��B�����ɑ��q�͈�ڌ��Ă����ɂ��̕��P�ɍ��ꍞ�݁A�k���E�A���E�f�B����ʂ��āA�ޏ��ɍ����ȑ��蕨������B���������P�͂��̑��蕨���A��������Q�����k���E�A���E�f�B���̕��ɊS�������B�����ނ͌���������ޏ����瓦��A����ɂ���Ă��ނ����犴�ӂ����B����V�����́A���P�̃Y�������ɕs��̋^���������A���Y�̔����������B����Ƒ����̑��q���A�Y�������Ɍ���������͎̂������������A�ޏ��͎������͂˂����Ɛ������āA�ޏ����~���B �@�Ƃ��낪�V�����͕��P�̗x�������ƁA��������C�ɓ����Ă��܂��A�ޏ���V�������P�ɂ��Ă��܂��B�ޏ��������Đ�]�������ނ��́A�ۖ������ʼn�����ԂɊׂ�B�V�k���ނ������āA���́u���[�v��܂ɋl�ߍ��ށB������k���E�A���E�f�B���̌ق��l�������A�������ڂ̂��̂������Ă�����̂Ǝv������ŁA����ł����Ă��܂��B���̑܂̓k���E�A���E�f�B���̑q�ɂ���A�V�����̂��߂̑傫�Ȕ[�i�ƈꏏ�ɁA�{�a�ɉ^�э��܂��B�X�ɂ�����ʂ̔��ɂ́A�k���E�A���E�f�B�����g���Ђ���ł���B �@�V��������A���荞��ł��܂��ƁA�ނ̑��q�����╃�̒��P�ƂȂ������P�̂Ƃ���֔E��ł���B��l�����i���A���������Ă���ƁA���̌�������������V�����́A�{�苶���ē�l���E���Ă��܂��B�����������Ԃ���ڊo�߂����ނ����A�Ȃ����ׂ��Ȃ����߂Ă���B���̂�����ŘV�����́A���x�̓Y�������ƃk���E�A���E�f�B�������������Ă��邢��̂������āA���R�Ƃ���B�ނ̓k���E�A���E�f�B�����P���āA�E�����Ƃ���B���̏u�ԁA�w�ォ�点�ނ��̂����������ނ��h���B���ނ��͈����镑�P�̎E�Q�ɕ��Q�����̂ł���B�\�N�͎��B�Y�������ƃk���E�A���E�f�B���́A�i���Ɍ����B������ނ��͋{�a�̖���J���āA�n�����̏���������������A����͍Ăѕ��Q�̗��|�l�̐����ɖ߂��Ă����B �y����z�A���u�̑����ƃo�U�[���̃G�L�]�V�Y���̐��E�ł̗x��q�̕���i�x�������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŕ���j�B �@���̉f��́A1910�N�ɓ����h���}���o�̒鉤�������}�b�N�X�E���C���n���g���A�x�������́u�J���}�[�V���s�[���v�őn�n�����p���g�}�C���E�o���[�u�Y�������v�Ɋ�Â��Đ��삳�ꂽ�B�o���[�̂ق��́u���X�����A���i�̂Ȃ��A�_���_�������������ƍ��]���ꂽ�ɂ�������炸�A�ϋq�ɂ͑�Ɏđ听���������߁A���̓��O�ł����Ζ͕�㉉���ꂽ�B�J��Ԃ��ꂽ�㉉�̔z���ɂ́A���ނ��ɕ��������r�b�`���������Ă����B����Ƀ��C���n���g�̉��o�́A����𐳊m�ɖ͕킵�悤�Ƃ�����O�̌��ꂩ��̗v�]�ŁA���䂻�̂܂܂ɎB�e���ꂽ�B����䂦�r�E�N���J�E�A�[���A�u1910�N�ĂɁA���C���n���g�̃p���g�}�C���w�Y�������x���f�扻���ꂽ���A�����2000���[�g���̒����ɂ킽���āA���̕���ł̏㉉�̐��m�ȕ�����^���邱�Ƃɂ���āA�ϋq��ދ��������v�Əq�ׂĂ���̂́A���������I�͂���ł���B �@�Ƃ���Ń|�[�����h�̃����V�����̑匀��ł̏㉉�ł́A�A�|���[�j�A�E�J���y�b�c�����P�ɕ����āA�M���I�Ȋ��т𗁂т��B�ޏ��ɒ��ڂ������C���n���g�́A�ޏ����x�������ɌĂ�ŁA�����̃I���W�i���̕���ɓo�ꂳ�����B�����Ă��̃|�[�����h�����́A�h�C�c�ł̓|�[���E�l�O���Ƃ������ő�X�^�[�ƂȂ����B�܂肱�̉f��́A����́u�Y�������v�ł̓�l�̃X�^�[���A��l���ē��o�D�Ƃ��āA��l�͖��f�I�ȕ��P�Ƃ��āA������X�N���[���Ɉڂ����f�悾�����B�����X�j���������r�b�`�����o�D���u�肵���Ƃ��A�ږ��͖������ƁA�ŏ�����A�B��������Ă����B�����ė^����ꂽ��Ԃ̑�����A�u�Y�������v�̂��̂��ނ��j�������B���r�b�`���Ƃ��Ă͈������������킯�ł���B �@����f�揗�D�ƂȂ����|�[���E�l�O���́A���r�b�`���f��ɋN�p���ꂽ���ƂŁA�X�^�[�ƂȂ����B�w�J�������x�i1918�j�A�w�̊�x�i1918�j�A�w�p�b�V�����x�i1919�j�ɂ��剉���āA��������l�C���D�ƂȂ����B���̌��ʔޏ��́A1923�N�Ƀ��r�b�`�����X�A�����J�ɏ�����A�n���E�b�h�ł��X�^�[�Ƃ��đ傢�ɂ��Ă͂₳�ꂽ�B �@�f�掩�̂͂�����C���n���g�̕������b�Ƃ��Ă��邪�A���r�b�`���̃R�X�`���[���E�v���C���̖��t���ɂ���āA�j�q���ȋC���̕Y�����̂ƂȂ�A�����̊ϋq�̐S���Ƃ炦���B���C���n���g���烋�r�b�`���́A�u���ǂ������z�A�F�ʖL���ȑ啑���A����̋Z�I�A���\�������@�O�Ȍ��z�I�V�[���̔×��Ȃǂւ̕Έ��v���p�����B���������S�ȉf���Ƃ��������r�b�`���́A�f��I�����Ɩ��f�͂�����ޓƎ��̎����ŁA�l����摜�𑨂����B�w���x���g�E�C�G�[�����O�́u�x���[���N�[���[���v���ɁA�����������B�u���r�b�`���͓�����ڍs���������A�G�X�J���[�g�����A�����ČX�̗���𒆒f����B��Q�W�̂����߂��p�B�����ł͔ނ͊����ł���A���ӂ�����̗���Ƒ���������B�X�̓_�ł̓��r�b�`���́A�쌀�f��ēƂ��Ă���߂Ē��z�ɕx��ł���B�ނ������⏢�g����z�ꏗ���f���I�ɏ�������Ƃ��ɂ́A�܂��Ƃɋ@�q�ł���A���̉f���͊y�����v�B �@���ۂ��̉f��̊j�S�́A�V���[�Ƃ��Ă̖ʔ����ł���A���̓_�ł͍����ł��F�����Ă͂��Ȃ��B�v�z�I�ȈӖ��ƂȂ�ƁA�₤�������Ƃ������̂ł��邪�A�r�E�N���J�E�A�[�͐^���ʂ��炱�������Ă���B�u���r�b�`���̉f��̐^�̈Ӌ`���������킹���̃q���g���A�w���P�Y�������x�̒��ŁA���r�b�`�������ނ��������Ă��鎖���̂����ɗ^�����Ă���B�����̔ނƂ��ẮA�ގ��g������ďo������̂́A�܂�������O�I�Ȃ��Ƃł������B�������h���E���āA�n�����̏����������ׂĉ���������ƂŁA���ނ��́A��E�C�̏�ʂ��琷���̌����������A���ė���B�q�ނ͂܂��x�����蒵�˂��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���O�͏������߂Ă��邩��r�ƁA�E�[�t�@�̉�����͏q�ׂĂ���B���|����k�ɂ܂���킹�Ă��܂���i�t�������Ɠ��ꉻ���邱�Ƃɂ���āA���r�b�`���́A�ނ�����đn��o�������̗��s���A��ƃ����h���}�I�Ȋ������̔z�����甭���Ă���Ƃ�����ۂ��A���ӎ��̂����ɐ[�߂Ă���B�����h���}�̖��t���́A�f���Ɋ܂܂ꂽ���̃V�j�V�Y���̌��������ǂ�����̂ɖ𗧂��Ă���B���̍������Ȃ��Ă���̂́A���̒��̏o�����ɑ��鋕���I�Ȋϓ_�ł���B����́A���r�b�`���̉f��₻�̈������A�×~�Ȏx�z�҂��E���Ă��܂�����ł͂Ȃ��A�l���ɂ����ĉ��l�������ׂĂ��\����Ⴂ���l���������j�ł����Ă��܂��悤�ȁA���т��������^���Ă��邱�Ƃ�����m�邱�Ƃ��ł���v�B �y�G�s�\�[�h�z�u���r�b�`���͐��N���A�����ŋ�������Ă��Ȃ��B�ނ͓X�����[���b�c���A���������Ă��Ȃ��B���ƌ����Ă����r�b�`���́A�����������ɂ͂������X����肷���Ă���B�Ƃ������Ƃ͂Ƃɂ��������Ă��A�E�[�t�@�̊ē����̖����܂�����������̂́A���ۖ��Ƃ��Ă��A�܂������Ƃł����낤�B�ނ͂������܂�30�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��������A������������҂ł��Ȃ��B�ނ͂����������a�m�ŁA���������t�����z���Ă���B�ނ͍����ēł���B �@�ނ͔o�D���ǂ̂悤�ɉ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������A���玦���Ă݂���p���A�N�ɂ��Ђ������Ȃ��قǗǂ��S���Ă���B���������Č�����Ƃ��A�ނ͋H�ɂ݂�قǂ̕ϐg�̍˔\�������Ă����B���Ƃ����̂ɁA�ނ͉��̂܂������ʼn����Ȃ��̂��H�@�o�D�����ɉ�����������Č����Ă���ނ��A���̑�ϏO�ɁA�܂�����������Č����悤�Ƃ��Ȃ��̂��H�����Ŕނ́A���ނ��̒j�̖���������B�����Ă���͎��s�������B �@�ǂ̂悤�ɖ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ǂ��m���Ă���ށA�o�D���炠����]�v�Ȃ��̂���菜���ނ��A�������g����͂܂�������������苎�炸�A�܂����������������悤�Ƃ��Ȃ��B�ނ͎v�������\���B�ނ͈�l�̎��i�[�����ނ��j��������B�ނ͊������났��낳����B�ނ͎�^���Řb���B�ނ͎B�e���u�̒��𑖂���B�ނ̔o�D�����́A�����������Ȗʂ����Ŋώ@����B�̑�ȏ��j���r�b�`���́A�ނ�ɋւ��Ă��邱�Ƃ������͑S������Ă��邱�Ƃ��A��̂킩��Ȃ��̂��낤���H�@�ނ͖��ߐ��ɁA�܂��Ɍ����܂����֒����ĉ����Ă��邱�Ƃ��H�@�ނ͂Ƃɂ����A�f�ʎ��Ńt�B����������̂��I�������A�ނ͂����炭�A���̔o�D������悤�ɂ́A���������邱�Ƃ��Ƃ͂��Ȃ��̂��낤�B�ނ̓|�[���E�l�O���ɂ��������B�q�l�͂��Ђ܂��f��ɏo�悤�c�c�{���͖l�ɂ́A���̂ق����ē�������ʔ����I�r �@�l�O���͋V���ă��r�b�`�������߂�B�G�����X�g�E���r�b�`���͂����鎞���ʂ��čő�̉f��ē��ƁA�ޏ��͊m�M���Ă���\�\���̊m�M��ޏ��́A30�N�o���Ă��Ȃ����������Ă����\�\�B�ނ́A��l�̔o�D�̒��ɉ����Ђ���ł��邩�A���̔o�D���g�����悭�m���Ă���B���������ɑ��Ă����́A�ނ͂������ᔻ�Ȃ̂��B���r�b�`���͑����Č����B�q�˂��A�{���͖l�͂����o�D�ł������Ǝv���Ă����B�{���ɂ����ȂB�ē���͖̂ʔ����B�m���ɖl�͂��ꂪ�D�����B�������A�����ʼn�����A����͂܂������ʕ�������ˁI�r �@�x���������́u�E�[�t�@�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ł̕���́A���ׂĂ̐l�X�ɂƂ��đ听���ł���B�Ƃ�킯�G�����X�g�E���r�b�`�����A�ϋq����A���R�[������B�o�D�����݂͌��Ɋ�������킹��B�M�����邩�H�@��̊ϋq�ɂ͂킩��Ȃ��̂��H�@�ϋq���A���̂悤�ȓc�ɏL���A�傰���ȉ��Z�ɂ��܂����Ƃ�����A�S�g�S����X���ĉ��Z���邱�ƂɁA�܂��Ӗ�������̂��낤���H�@�q���r�b�`���I�@���r�b�`���I�r�ƁA�l�X�͋��ԁB�����ĉ��x�����x���A�|�[���E�l�O���ƃn���[�E���[�g�P���A�J�[�e���̑O�����B���r�b�`���͘e�ɗ����Ă���B�q�����A�o�čs����A�N�����I�r�ƁA�ނ͌����B�������[�g�P�������B�q�����ǁA�ނ�͂����Ă�ł���I�r�@���r�b�`���͐^���ł���B�q�N�����ɂ����v���邾�����r�B�����ϋq�͋���ł���B�q���r�b�`���I���r�b�`���I�r�q��̂��ɂ́A���ꂪ�������Ȃ��́H�r�ƁA�l�O�����ނ��ĂԁB�q���Ȃ��͈ꏏ�ɏo�Ȃ�������Ȃ���r�B�������r�b�`���͂Ԃ₭�B�q�l�͂��̋C�͂Ȃ��c����͖��Ӗ����c�r�B�����ēˑR�A�ނ͓{���������B�q�N�����͈�́A�l���ǂ�ȂɂЂǂ��������A�킩��Ȃ��̂��ˁH�r �@�J�[�e���̌��Ŕނ͒��ق��Ă���B�q���r�b�`���I���r�b�`���I�r�ƁA�ϋq�͔M�����ČĂԁB���r�b�`���͎S�߂ȋC�����ł���B�q�Ȃ�قǁA�l�̔o�D�����͂����������̂��r�B�ނ͊z�̊���@���B�����Ĕނ́A��x�Ɩ��������悤�Ƃ͂��Ȃ������v�i�N���g�E���[�X�w�h�C�c�f��̈̑�Ȏ���x�j�B 1920.9.2�i���{����1922.10.20�j �w�Q�j�[�l Genuine�x ���[�x���g�E���B�[�l�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[�A�B�e�F���B���[�E�n�[�}�C�X�^�[ �y�L���X�g�z�t�F�����E�A���h���A�G�����X�g�E�O���[�i�E�A�n�����g�E�p�E���[�� �y����z��ȉƂɕ����߂�ꂽ���̔ߌ��B�w�J���K���x�̊ē̉f��Ƃ������ƂŒ��ڂ��ꂽ���A���҂͂���B�N���J�E�A�[p98 1920.9.3 �w�G�J�`�F���[�i���� Katharina die Grosse�x ���C���z���g�E�V�����c�F���ēA�V�i���I�F�{�r�[�EE�E�����g�Q�A���C���z���g�E�V�����c�F���A�B�e�F�J�[���E�t���C���g �y�L���X�g�z���f�B�[�E�w�[�t���q�A�Q���g���[�g�E�f�E�����X�L�[�A���C���z���g�E�V�����c�F���A�C���J�E�O�����[�j���O�A���[�c�B�G�E�w�[�t���q �y����z���V�A����̕���B 1920.9.24 �w�[�\��\�� Abend... Nacht... Morgen�x �t���[�h���q�E���B���w�����E�����i�E�ēA�V�i���I�F���h���t�E�V���i�C�_�[���~�����w���A�B�e�F�I�C�Q���E�n�� �y�L���X�g�z�u���[�m�E�c�B�[�i�[�i�`�F�X�g���j�A�Q���g���[�g�E���F���J�[�i���[�h�F�Ԗ��E�̍������w�j�A�R�����[�g�E�t�@�C�g�i�u�����o�[���E�ޏ��̒�j�A�J�[���E�t�H���E�o���i�v�����X�F�q���D���j�A�I�b�g�[�E�Q�r���[���i�E�I�[�h�F�T��j �y����z�����i�E�ē̒T��f��B 1920.10.13 �w�T�����A�̐R���� Der Richter von Zalamea�x ���[�g���B�q�E�x���K�[�ēA�V�i���I�F���[�g���B�q�E�x���K�[�i�X�y�C���̌���ƃJ���f�����̋Y�Ȃɂ��j�A�B�e�F�A�h���t�E�I�b�g�[�E���@�C�c�F���x���N�A���u�F�w���}���E���@�����A�G�����X�g�E�}�C�t�@�[�X �y�L���X�g�z�A���x���g�E�V���^�C�������b�N�i�y�h���E�N���X�|�j�A�����E�_�[�S���@�[�i�C�U�x���j�A�n�C�����q�E���B�b�e�i�h���E�A�����@���j�A�A�O�l�X�E�V���g���E�v�i�L�X�p�j�A�G�����X�g�E���[�g�����g�i���{���h�j�A���[�^���E�~���[�e���i�t�@���j�A�G���[�U�x�g�E�z�����i�C�l�X�j�A�}�b�N�X�E�V�����b�N�i�h���E�����h�j�A�G�����X�g�E���[�K���i�R���j�A�w���}���E�t�@�����e�B���i�h���E���[�y���R�j �y���炷���z�h���E�A�����@����т��_�v�y�h���E�N���X�|�̉Ƃɏh�c����B�N���X�|�͎����̖��C�U�x���ƖẪA�����@������̊K�ɉB���B�����h���E�A�����@���̓C�U�x���𓐂���B�����Ĕޏ��̕����ɐN�����悤�Ƃ��邪�A�N���X�|�Ɣނ̑��q�ɖW������B�h���E���[�y���R�͑�тɃN���X�|�̉Ƃ��痧���ނ����A�邪��������U�����A�𗧂�����悤������B�A�����@���͂������C�U�x����U�����āA��������B�N���X�|���U�����A�̍ٔ����ɑI�o�����B�A�����@�����C�U�x���ƌ������邱�Ƃ����Ƃ��A�N���X�|�͔ނ�ߕ߂���B�h���E���[�y���R�̓A�����@�����R�@��c�̐R���Ɉς˂��������Ɗ�]����B����ƃN���X�|�͑����̏W��̔����J������B�����ɂ̓A�����@�����i�E����Ă���B�t�@�����ނ��ق����̂������B�����̓N���X�|���������s����������ƌ��肷��B�����ĉ��߂Ĕނ��I�g�̐R�����ɔC������B�C�U�x���͏C���@�ɓ���B�t�@���͏��R�̋��ɋΖ�����B�����������̖��_������Ă��ꂽ�B 1920.10.29�i���{����1923.10.23�j �w���l�S�[���� DER GOLEM, WIE ER IN DIE WELT KAM�x �J�[���E�x�[�[�A�p�E���E���F�[�Q�i�[�����ēA�V�i���I�F�p�E���E���F�[�Q�i�[�A�w�����b�N�E�K���[���A�B�e�F�J�[���E�t���C���g�A���u�F�n���X�E�y���c�B�q�A����F�E�j�I���f��� �y�L���X�g�z�p�E���E���F�[�Q�i�[ Paul Wegener�i�S�[�����j�A�A���x���g�E�V���^�C�������b�NAlbert Steinrück�i���r�E���[�t�j�A�����_�E�U�����m���@ Lyda Salmonova�i�ނ̖��~���A���j�A�G�����X�g�E�h�C�b�`�� Ernst Deutsch�i���[�t�̊w�l�j�A�n���X�E�V���g�D���� Hanns Sturm�i�V���r�j�A�I�b�g�[�E�Q�r���[�� Otto Gebühr�i�c��j�A���[�^���E�~���[�e�� Lothal Müthel�i�t�����A�����݁q�����J�[�r�j�A���[�j�E�l�X�g Loni Nest�i�����ȏ����j�A�}�b�N�X�E�N���[�l���g Max Kronert�A�h�[���E�y�b�c�H���g Dore Paetzold�A�O���^�E�V�����[�_�[ Greta Schröder �y���炷���z16���I�̃v���n�̒��̃��_���l���Z��̐��_�I�w���҂ł��郉�r�i���@�w�ҁj�̃��[�t�́A��������ɐ��C���ώ@���Ă���B�ނ͌����B�u���ɂ��ΊԂ��Ȃ��A�傫�ȍЂ�������ꃆ�_���l�̐g�ɍ~��|���낤�Ƃ��Ă���v�B�����Ă܂��ɍc�邪���_���l�ɑ���z�����悤�Ƃ��Ă����B�u���_���l�ɑ��Đ\�����Ă�ꂽ�������̍��i�Ɋӂ݂āA���͋��Z��̃��_���l��x�Ȃ����O�ɒǕ����邱�Ƃ𖽂���v�B �@���r�̃��[�t�́u�����~�����߂ɂ́A���̋��낵���喂���A�X�^���g�̌�����A���ЂƂ��y�ō��ꂽ�l�ԃS�[�����ɁA�V���������𐁂����ގ������o���˂Ȃ�ʁv�ƌ����B�����֍c��̎g�҂̃t�����A�����݂��A���_���l���Z��̒��V�ɔ����Ă���ė���B���[�t���������āA��x���c����Ж�����������̂��߂ɁA�c��ւ̓��X�̌���𗊂ށB���[�t�̖��~�������̔������ɂ�������Q�������݂́A�������藊�݂�������B�߂��Ă����ނ́A�u�����̒��N�̌��тɖƂ��āA���ɖڒʂ�������B���̐܂�A�����̖��@��������x������悤������v�Ƃ����A�c��Ɏ莆�������ė���B �@���̊ԂɃ��[�t�͑喂���A�X�^���g���Ăяo���A���낵��������^���錾�t���B�����Ă��̎w���ɏ]���āA�S�y���̋��ɖ��@�̎������������아��u���ƁA���l�S�[�����͖ڂ��o�܂��B�����ċ���ȗ͂���������g���Ƃ��āA���[�t�Ɏd����B�o���Ղ�̓��ƂȂ�A���[�t�̓S�[������A��ċ{�a�ɏo������B�t�����A�����݂̓~�������ɁA�u�N�̂����オ����ɒ�������A�l�͂������蔲���o���ČN�̉Ƃɍs���B�ڈ�ɌN�̕����̑��Ƀ����v���Ēu���Ă��炢�����v�Ƃ����莆��͂���B�{�a�ł̓��[�t���c����b�ɃS�[�������Љ�A�݂ȋ����̖ڂ�������B�t�����A���͏���o���A�~�������̎�����ł��̕����ɉB���B �@�c�邩�疂�@��������Ƌ��߂�ꂽ���[�t�́A�u���B�̉����c��̍s��������ɓ���܂��B���B�̖������A���ǂ��������Ē����������߂ł��B���̑���A�ǂȂ������𗧂Ă���A�����肵�Ă͂Ȃ�܂���v�ƌ����āA�r�����s�����_���l�̌���������B�Ō�ɉi���̃��_���l�A�n�X�t�@�G���X���o�ꂷ��ƁA�{��͌x����Y��ę��ɕ�܂��B����ƌ��������A�ǂ��U�����A����������B�����đ�L�Ԃ̓V�䂪�����Ă݂�ȉ����Ԃ��ꂻ���ɂȂ�B�c�邪�u���������Ă���A����������̖���������ی�v���ł��낤�v�Ƌ��ԂƁA���[�t�̓S�[�����ɖ����ēV����x��������B�c��͊��ӂ��ă��_���l�̒Ǖ����������B �@����[�t�͋}���ŋA��A�u�c�邪���̖����̕ی����ꂽ�B��т̊p�J��炵�A�킪���E�肩��N�������悢�v�ƍ������B�����āu�S�[������A���O�̎g���͏I�����������B���O�͍Ăѓy��ɖ߂�˂Ȃ�ʁv�ƌ����āA�S�[�����̋��̌�䊐����O���B�S�[�����͍ĂєS�y���ɋA��B���[�t�̊w�l�̓~�������̕�����@���A�u���삳��A���N���Ȃ����B�ꏏ�ɏW���ɍs���܂��傤�v�ƗU���B�Ƃ��낪������t�����A�����݂̐�����������B���i�ɋ������w�l�͔S�y���Ɍ�䊐��ĂāA�S�[�����̐������Ăёh�点��B�����āu�~�������̕����ɒN�����E�э���ł���B���O���s���Ēǂ������̂��v�Ɩ�����B �@�����ēx�h�������S�[�����̓R���g���[���������Ȃ��B�˂�j���ĕ����ɓ������S�[�����̓t�����A����͂܂���ƁA�Ƃ̓��̏ォ�瓊�����Ƃ��ĎE���Ă��܂��A�Ƃɉ�t���ĔR���オ�点����A�~�������̔��̖т�͂�ŁA�O�֘A��o���Ă��܂��B�V�i�S�[�O�Ŋ��ӂ̋F�������Ă����l�X���A�u�Ύ����I�v�̋��тŊO�֏o�Ă݂�ƁA�̓��_���l���Z��ɏP���������Ă���B�Q�O�̓��[�t�ɁA�u�ǂ������������~���ĉ������B�������������������ĉ������v�ƍ��肷��B���[�t�͊肢�ʂ����߂�B�����S�[�����̓��_���l���Z����͂ފR�̉��ɍs���A�����ɋC�₵���~����������������B�����ċ��Z��̐���Ɍ������čs���āA�����j��B��̑O�ŗV��ł����q���B�͋����ē����čs�����A���c���ꂽ�������̎q�́A�S�[�����ɋ߂Â��ă����S�������o���B�S�[�������ޏ�������グ��ƁA�ޏ��̓S�[�����̋��̌�䊐��ɖڂ�t���āA�S�����C�ɂ�����O���Ă��܂��B�S�[�����͋��̂�O��ɗh�邪���A���̎q�͔ނ̘r���犊�藎����B���ꂩ��S�[�����͋����ɂ�����|���B �@�W�����A�������[�t�́u�S�[�����͂ǂ����v�ƒT�����A���ꂪ���̔S�y�ɖ߂��Ă���̂������āA�_�Ɋ��ӂ���B�u�����A�O�x�܂ʼn��̖������~�������ꂽ�G�z�o�̐_�Ɋ��ӂ̋F�������܂��v �y����z��Ԗڂ̃S�[�����A�x�������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŕ���i�n���X�E�y���c�B �q�ƃN���g�E���q�^�[���e���y���z�[�t�̃E�[�t�@�E�Q�����f�ɁA�����̃v���n��������B���_���l�`�����h�C�c�E���}���h�ƌ��z�I�Ȃ��̂ɂ��Ẵ��F�[�Q�i�[�̃��B�W�����ݏo�����j �@�J�o���̔�@�ɂ���Đ����𐁂����܂��S�y���S�[�����̃��_���`���́A�����I�ł͂܂�1908�N�ɁA�����L�͂���������ƃA���g�D�[���E�z�[���`���[�ɂ���Č�������ď㉉���ꂽ�B���w�j����������Ă��܂����z�[���`���[�̂��́u�S�[�����v���́A�O�X�^�t�E�}�C�����N�̏����u�S�[�����v�ƁA���F�[�Q�i�[�ƃw�����b�N�E�K���[���̉f��w�S�[�����x�ݏo���G�}�ƂȂ����B�����Ɖf��͂ǂ����1914�N�ɓ����ɍ��ꂽ���A���݂ɂ܂������W���Ȃ������B�������܂������ʎ�ނ̍�i�ł͂����Ă��A����͓`�������㉻���đh���������_�ł́A�����Ӌ`�������Ă���B�}�C�����N�̏����́A�����̃v���n��Ƃ��Ă���B�����Ĉ�l�̂Ɍ���́A���̒��ŕ�Β����t�A�^�i�W�E�X�E�y���i�[�g�ƂȂ邪�A�y���i�[�g�͂܂��S�[�����ƈ�v����B����́u���_���̓`���ƁA�e���p�V�[��I�J���e�B�Y���Ɋւ��铖���̕A�v���n�̃A���_�[�O���E���h��n���I����Ƃ��������̂̐�[�ŁA���ʂɐD�萬���ꂽ�A����̕������ł���v�B���������Ă���́A�`���̃S�[��������Ƃ͈������ނ̍�i���ƌ�����B �@�������ł�1913�N����̉f��w�v���[�O�̑�w���x�ɂ���āA�v���n�̃��_���l�Q�b�g�[�̊���`���ɐe����ł����p�E���E���F�[�Q�i�[�́A���̔ނ̍ŏ��̃S�[�����f��ŁA16���I�̃��r�E���[�t�ƃS�[�����Ƃ̕�����ނɂ��悤�Ƃ����B�������v���f���[�T�[���ًc�������A�o�ϓI���R����A�u����I�ȁv�h���}�����߂�ꂽ�B���̌��ʏo���オ�����f��́A�v���n�̃��_���l���Z��Ō@��̎d�������Ă����J���҂��A����ȔS�y�������A�Õ����̂Ƃ���֎����čs���Ƃ����A���㕨�ɕύX����Ă��܂����i1936�N�Ƀt�����X�̃W�����A���E�f�����B���B�G���A���̃g�[�L�[�ł�������j�B����͂���A1920�N�́w�S�[�����x�f��́A���̌������ł���B �@�������Č������̌�ɁA1920�N�ɁA����ΑO�����ꂪ����邱�ƂɂȂ����킯�ł��邪�A���̕��������Ɛ[�݂̂����i�ƂȂ����B�O��ł͌���ɒu��������ꂽ�~�������ƃt�����A���̖��ʌ����O�ʂɏo�āA�����h���}�����Z�����������A���x�͂͂�����Ƒz���͂̐��E������ɂȂ����B�u�s�C���Ȃ��́v�Ɓu���I�Ȃ��́v�̗́A�w�v���[�O�̑�w���x�Ŏ����ꂽ�����̃v���n�̒��̕��͋C�̖��͂��A�V�炽�Ȍ`�ōč\�����ꂽ�B�Ȃ��Ȃ炱�̉f��̃v���n�̒��́A�w�v���[�O�̑�w���x�̂悤�ɁA���ۂ̒��̃��P�ł͂Ȃ��A�\����`�̌��z�ƂƂ��ėL���ȃn���X�E�y���`�q�̍�����Z�b�g����������ł���B�����̂قƂ�ǂȂ��A�ΐ��ƋȐ��Ƃ��������̊p�Ƃ����A�܂�ŕ\����`�̃��f���̂悤�Ȑ��ɂ���č\�����ꂽ�A���́u���\�v�̒����̃����w�����E�́A�h�C�c�̃T�C�����g�f��̃Z�b�g�̖͔͂ƂȂ����B �@�p�E���E���F�[�Q�i�[�͕���̑O�ɁA�������������B���̗F�l�A���z�Ƃ̃y���`�q���\�������̂́A�v���n�ł͂Ȃ��B����͈�̒��̎��A��̖��A�S�[�����Ƃ����e�[�}�ւ̌��z�w�I�ȃp���t���[�Y�ł���B���̉�����L��́A���猻���I�Ȃ��̂�z�N��������̂ł͂Ȃ��B����̓S�[�������ċz���Ă��镵�͋C����낤�Ƃ�����̂ł���v�B�����Č��z�ɂ�鎍�Ƃ��Ẳf��̂��̃��B�W�����́A���̉f��ɂ���Ď��Ɍ����Ɏ������ꂽ�̂ŁA�w���x���g�E�C�G�[�����O�͂�����]�����\�\�u�p�E���E���F�[�Q�i�[�́w�S�[�����x�̊ēƂ��āA�g�U�艉�Z�I�Ȃ��̂Ƌ�ۓI�Ȃ��̂Ƃ̊Ԃ̋ύt�������B�n���X�E�y���`�q�͔ނ̂��߂ɁA�v���n�̃Q�b�g�[�����S�ɍ��グ���B�����Ă���ɂ���Ĕo�D��n���I�ɂ���w�i��������B���F�[�Q�i�[�ƃy���`�q�́A���R�̂�������R����r�������A�����ɍ\�����ꂽ�f���������A�f��ɂƂ��Ė����������Ƃ��ؖ������B���ۂ̒��A���ۂ̕��i�̎B�e�́A�������A�����[���ł��낤�B�o�D������i�̃Z�b�g�ɑg�ݍ��ޗL�@�I���o�́A����̉f��̂��߂ɍ��ꂽ�A�����ɗ��������ꂽ�f�����������e���邱�Ƃ��ł���B�V�炵���w�S�[�����x�����̂��Ƃ��w�J���K���x�̌�ɁA�w�Q�k�C�[�l�x�̌�Ɋm�F�������Ƃ́A����I�������B���F�[�Q�i�[�̓h�C�c�f��̂��߂ɁA���̒N�����ȏ�̂��Ƃ������B�w�S�[�����x�͒����̕���ɑł������āA���̕��͋C��^�����ŏ��̉f��ł���v�B�����Ƃ������ł͂��̉f��́A�y���`�q�̃Z�b�g�����܂߂āA�P�ɕ\����`�I�Ȃ��̂Ƃ͌��Ȃ���Ă��Ȃ��B���[�Q���g�V���e�B�[���̗v�f���w�E����Ă���B�y���`�q�ƃX�y�C���̌��z�ƃA���g�j�I�E�K�E�f�B�Ƃ̐e�ߐ����w�E����Ă���B������ɂ��Ă����̉f�悪�A����I�Ȃ��̂��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B �y�f��̃Z�b�g�ƌ��z�Ɓz��ꎟ���E���̔敾�̂��߂ɁA�{���̌��z�̈˗����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����h�C�c�̌��z�Ƃ́A���Ȃ��Ƃ����z�ɊW������悤�Ɍ����郁�f�B�A�ɊS��������B���̍ۉf��͂��܂��܂ȗ��R�ŁA�������镪�삾�����B��ɂ͉f�悪�u���O�v�𑨂��Ă������Ƃł���B���O�Ƃ̐G�ꂠ�������߂�҂́A�v���I���z�Ƃ��܂߂āA�f����ł��Ȃ������B�����ăp�E���E���F�[�Q�i�[�̂悤�ȉf��l�̗U��������āA�f��Ƒ��`�ƃO���t�B�b�N�ƕ��w�Ƃ̊Ԃ��Ȃ��ւ���낤�Ƃ���A���̕����v�V�̉^�������܂ꂽ�B����ɂ̓y�[�^�[�E�x�[�����X��u���[�m�E�^�E�g�Ƃ������h�C�c�H��A���̃����o�[���܂܂�Ă����B �@�����ău���[�m�E�^�E�g����A�f��������̃��[�g�s�A�I�ȃK���X�����𐁂����ނ��߂߂̔}�̂Ƃ��Ďg�����Ƃ��l�������Ƃ��������B�������f��Ƃ̊W�����肠����̂ɂ����̂́A�n���X�E�y���`�q�̂ق��������B�w�S�[�����x�͂��̐��ʂł���B�y���`�q�̓x�������̃e���y���z�[�t�̖쌴�ɁA�⋭�������������ō������̒��S�̂��Z�b�g�����B�Q�b�g�[���͂ޏ�ǁA��A������54���̉ƁB�Ȃ��肭�˂����H�n�̉ƁX�̓˂��o�����o���A�X������ȁA�������Ȃ���̕��������[�[���̊���̓y���`�q���x�������ɍ�����u�匀��v�̗��V�ɂ���āA�ߓ��Ε��̈ӏ��ŏ����Ă����B�J�^�c�����̊k�̂悤�ɏd�Ȃ��āA���邮����Ȃ���㏸����X�p�C�����I�K�i�A�Ђǂ�����A�f�t�H���������ꂽ�ו��́A�o�D�����Ȃ��Ă��A���ꎩ�g���������Ă����B�y���`�q�́A�u���������_���Ȃ܂�ł���ׂ����v�ƌ������B �@���̃R�[�i�[�ɂ��閧������ł���悤�Ɍ������B�����ɂ���̓A�N�V�����̂��߂Ƀf�U�C�����ꂽ�\�z���������B�܂�d�Ȃ荇�����t�@�T�[�h�A�ٗl�ȒʘH�A�ˑR�̍���̕ω��A�K�i�A�x���A����Ƃ������Z�b�g�́A�^����U�����̂������B�����w�S�[�����x�ɂ������Ԃ̈������́A�J���o�X�̔w�i�Ƃ�����@����A�z�����w�J���K���x�̎�@�Ƃ́A�܂������قȂ��Ă���B�w�S�[�����x�̃Z�b�g�͊��S�ɎO�����ł��邪�A�w�J���K���x�����ۓI�Ɂw�S�[�����x���L���ɂȂ������߁A�l�X�͎O�����̂ق�����O�ł���ƐM�����B�������w�J���K���x�̊ē��[�x���g�E���B�[�l���g���A�w�߂Ɣ��i���X�R���j�R�t�j�x�ɂ����ẮA�O�����̃Z�b�g�ɗ����Ԃ��Ă���B�܂���͓����O�����ɂ���̂ł͂Ȃ��B�w�J���K���x�̏ꍇ���A�w�S�[�����x�̏ꍇ���A���ꂪ���z���̖L���ȋ�Ԃ�n�o���邱�Ƃɐ������Ă��邱�Ƃ��A�d�v�Ȃ̂ł���B �@���̌��ʂƂ��ăZ�b�g�̓T�C�����g�f��Ȃ�ł͂́A���ʂɍۗ������������ʂ������ƂɂȂ����B�܂�Z�b�g�͔o�D�ƑΓ��ɂȂ�A���@���Ă��錾��̑���ɁA���^�t�@�[�Ƃ��Ă̖����������邱�ƂɂȂ����̂ł���B�w�S�[�����x�̃Z�b�g�́A�����������^�t�H���b�N�ȋ�Ԃ̓T�^�ƌ��邱�Ƃ��ł���B 1920.12�� �w�X�L�[�̋��� Das Wunder des Schneeschuhs�x �A���m���g�E�t�@���N�ēA�B�e�F�[�b�v�E�A���K�C���[�A�A���m���g�E�t�@���N �y�L���X�g�z�n���l�X�E�V���i�C�_�[�A�G�����X�g�E�o�[�_�[�A�[�b�v�E�A���K�C���[�A�A���m���g�E�t�@���N�A�x�����n���g�E���B�����K�[�B �y����z�A���m���g�E�t�@���N�Ɠ��̎R�x�f��̒a�����L�O����t�@���N�ŏ��̒��ڍ�i�B 1920.12.14�i���{����1923.4.27�j �w�f�Z�v�V�����i�A���E�u�[�����jAnna Boleyn�x �G�����X�g�E���r�b�`�� Ernst Lubitsch�ēA�V�i���I�F�t���[�g�E�I���r���O Fred Orbing���ƃm���x���g�E�t�@���N Norbert Falk�A�n���X�E�N���[�� Hans Kräly�A�B�e�F�e�I�h�[���E�V���p�[���N�[�� �y�L���X�g�z�w�j�[�E�|���e�� Henny Porten�i�A���E�u�[�����j�A�G�~�[���E���j���O�X Emil Jannings�i�w�����[�����j�A�p�E���E�n���g�}�� Paul Hartmann�i�w�����[�E�m���X���j�A���[�g���B�q�E�n���^�E Ludwig Hartau�i�m�[�t�H�[�N���݁j�A�A�E�h�E�G�[�C�G�[�E�j�b�Z�� Aud Egede Nissen�i�����W�F�[���E�V�[���A�j�A�w�[�g���B�q�E�p�E�� Hedwig Pauly�i���܃L���T�����j�A�q���f�E�~�����[ Hilde Müller�i�������A���[�j�A�}���A�E���C�[���z�[�t�@�[ Maria Reisenhofer�i���f�B�E���t�H�[�h�j�A�t�F���f�B�i���g�E�t�H���E�A���e�� Ferdinand von Alten�i�}�[�N�E�X�~�[�g���j�A�A�h���t�E�N���C�� Adolf Klein�i�E���W���@���j�A�p�E���E�r�[���X�t�F���g Paul Biensfeldt�i�{�쓹���t�j�A���B���w�����E�f�B�[�Q���}�� Wilhelm Diegelmann�i�J���y�b�W�����@���j�A�t���[�h���q�E�L���[�l Friedrich Kuhne�i�N���C�}�[��i���j�A�J�[���E�v���[�e�� Karl Platen�i��tArzt�j�A�G�������O�E�n���]�� Erling Hanson�i�p�[�V�B���݁j�A�]�t�B�[�E�p�K�CSophie Pagay�i���c���Ō�w�j�A���[�[�t�E�N���C�� Josef Klein�i�E�C���A���E�L���O�X�g�����j �y���炷���z�p�����w�����[�����͓��y�҂ő�H���A���ɊႪ�Ȃ������B�m�[�t�H�[�N���݂̖ÃA���E�u�[�����́A�w�����[�E�m���X���ƈ��������Ă������A������A���R�w�����[�����̖ڂɂƂ܂�B��ڂŃA�����C�ɓ��������́A�ȗ��@����閈�ɁA�����̗���������悤�ɂȂ�B�A���͉����Ȃ��������A���l�̃m���X�������ƃA���̊W���א����Ĕޏ���a���̂ŁA��ނ����̋����ɉ�����B �@�������w�����[�����ɂ͂��łɉ��܃L���T�����Ɖ������A���[�������B�A���ƌ������邽�߉��܃L���T�����𗣍��������́A�����F�߂Ȃ����[�}�@���ɔ��R���āA�A���O���J���E�`���[�`��n�݂��āA���炻�̎ɂƂȂ����B�����ăE�G�X�g�~���X�^�[���@�ŁA���̓A���Ɖ₩�Ȍ��������������B���Ɍ�������l�����ɏW�܂��āA���Ă���Q�O�̔g�B �@�������ăA���͉��܂ƂȂ������A�K���͒��������Ȃ������B���ɂ͒j�q�����Ȃ������̂ŁA���p���̉��q�ނ��Ƃ����҂���Ă����B�A���̉��D������́A���܂ꂽ�̂����q���������߁A�������莸�]���Ă��܂��B�����֏����̃W�F�[���E�V�[���A���A���ɑR����悤�Ɏp�������A���̒��̓A���𗣂�ăW�F�[���Ɉڂ��Ă����B����ɔ䕐�ŏd�������m���X���ƃA���Ƃ̓��Ȃ�ʊW���掂��鐺�����̎��ɒB�����B�{�������̓A���������h�����ɗH���āA�ٔ��ɂ���������B�m���X���͔ޏ��̖������،����邷��O�Ɏ��ʁB�ޏ��͏f���ł���m�[�t�H�[�N���Ƃ��ĊJ����Ė@��́A�ޏ��ɕs��̍߂Ŏ��Y�̔����������B�������ĞۉԈ꒩�̖��̂̂��A�A���͒f����̘I�Ə�����B �y����z�G�����X�g�E���r�b�`���͑�ꎟ���E���O�́A�y���ȃh�^�o�^�쌀�f��̃R���f�B�A���Ƃ��Đl�C���Ă����B�Ƃ��낪����́A�s��ƋQ��̒��ŋꂵ�������𑗂��Ă����h�C�c�����ɁA���؈�ࣂ��閲�邱�ƂŐ������˂�����E�[�t�@�f��Ђ̃_�[�t�B�g�]���ɋN�p����āA������w�p�b�V�����x�삷�邱�ƂɂȂ����B����̓t�����X�v����w�i�ɁA�t�����X���̒��P�f���o���[�v�l�̉h�Ɩv����`�������j���̍��؉f�悾�����B�����Ƃ��Ă͔j�V�r�Ȑ��̃G�L�X�g���ƍ��Ȉߏւ�Z�b�g���g���Đ��삳�ꂽ���̍�i�́A���������łȂ����O�ł���q�b�g�����B�˂炢�����������_�[�t�B�g�]���́A���̉��̂ǂ��傤���˂���āA�t�����X���̋{����C�M���X���̋{��ɕς��āA������{���j���̒�����삷�邱�Ƃ��A���r�b�`���Ɏ����������B�������ďo���オ�����̂��w�f�Z�v�V�����x�������B���r�b�`���͂���ɂP�X�Q�P�N�Ɂw�t�@���I�̗��x�삵�Ă���A���ꂪ��ʂɃ��r�b�`���̗��j���O����ƌĂ�Ă���B �@���̎O��i�ł́A���C15���A�w�����[�����A�t�@���I���������剉�j�D�́A�G�~�[���E���j���O�X��l���������A�剉���D�͂����������Ă����B�f���o���[�v�l���������d���ȃ|�[���E�l�O���́A�X�^�[�Ƃ��ē��̏o�̐����������B�����Łw�f�Z�v�V�����x�̃A���E�u�[�����ɂ́A�w�j�[�E�|���e�����N�p����A����C�M���X�Ƃ������������ŁA�|�[���E�l�O���̃f���o���[�v�l�Ƌ������ƂɂȂ����̂������B �@���r�b�`���́w�p�b�V�����x�����̂���|����ȃZ�b�g�������炦�A�u850���}���N���₵�āA�w�����[�����̐������ׂɕ`�ʂ��A�{��̉A�d�A�����h�����A���l�̃G�L�X�g���A���̑�����̗��j��̃G�s�\�[�h�Ȃǂ�D�荞�₩�Ȕw�i�ɂ���āA��������藧�Ă��v�B�����āw�p�b�V�����x�ƈ���āA�u�^����ꂽ�j�������܂�c�߂邱�ƂȂ��A���j��ꐧ�N��̎������̗~�]�̒f�R�̂悤�Ɍ����邱�Ƃ��ł����B�����ł��A��͂�A�ꐧ�N��̗~�]���D����������߂���߂���ɂ��Ă��܂��B�\�\�ق�ꂽ�R�m���A���E�u�[�����̈��l���E���B�����čŌ�ɂ́A�ޏ��݂�����f����ɂ̂ڂ��Ă䂭�B���S�ȕ��͋C�����߂邽�߂ɁA����̃G�s�\�[�h���}������Ă��邪�A���������̂̔�]�Ƃ́A�q�����̋��|�Ɩ���Ȏ��̌Y�߂̊Ȍ��ȕ\���r�ł���ƌĂv�B �@��ʂɔ�]�Ƃ́A�w�p�b�V�����x�Ɓw�f�Z�v�V�����x���r�����ꍇ�A�w�p�b�V�����x�̂ق��ɌR�z��������B���������j���O�X�̓t�����X�����C�M���X���̂ق����҂����肵�Ă����B�����č��ȈߏւƐ������ꂽ�f���̍\���̓_�ł́A�w�f�Z�v�V�����x�͂܂��Ƃɖڂ�D�����̂��������B�ǂ����������A�����ɂ��̉f��̊�ڂ��������B���b�e�E�A�C�X�i�[�́w�f���[�j�b�V���ȃX�N���[���x�̒��ŁA���������Ă���B�u���r�b�`���ɂƂ��Ă͗��j�́A���̎���̍��Ȉߏւʼnf����B�邽�߂̐�D�̋@��ȊO�̉����ł��Ȃ��B���A�r���[�h�A�L���Ȏh�J���A�ȑO�������X�����������r�b�`���̔삦���ڂ��A�L���V�ɂ����̂ł���B���̏ケ�̐��܂���̃V���[�}���͎��㌀�ɂ����āA�Z���`�����^���ȗ���������A�����h���}���̌Q�W�̓�����A�˂��Ȃ���ꂽ���j�I�����ƍ������킹�錋�\�ȉ\�����������v�B�܂�L���ȑՊ����̍s��̏�̌Q�W�V�[�����A���������\�����ő���ɔ��������邽�߂ɐݒ肳�ꂽ�ڋʂ������̂ł���B �@����䂦�w�p�b�V�����x���邢�́w�f�Z�v�V�����x�́A���G���̉p�����Ђ����ɔ�掂�����̂��Ƃ����A���蓖���̍��O�̔����́A���r�b�`���Ɋւ������A���悻�I�͂��ꂾ�����ƌ�����B���̖��ɂ��ẮA�C�F���c�B�E�e���v���b�c�����́w�f��j�x�̒��ŁA���������Ă���B�u�^���͒��Ԃɂ���B�q�E�j�I���E�E�[�t�@�r�Ђ��f��w�p�b�V�����x����悵���Ƃ��A�`�[�t�̃p�E���E�_�[�t�B�g�]���́A���̉f�悪�S���E�ŏ�f����邱�Ƃ��A�܂�t�����X��펞�����h�C�c�����ɑ����Ă������̍��X�ł���f����邱�Ƃ��A�v�Z�ɓ���Ă����B���̗\�z�͓��������B�E�[�t�@�Ђ̋��Z�{�X�ł��镧���ʂ̃A���t���[�g�E�t�[�Q���x���N�́A���̉f����I���Ȕ����v���p�K���_�ƕ]�������B�����ăt�����X�����łɕs���Ȍ���Ă��Ă���Ƃ��ɁA�ǂ����ăC�M���X���������悤�Ɉ����Ă������Ȃ��킯�����낤�B�������ă`���[�_�[�����̐������������f��w�f�Z�v�V�����x���B��Ƃ����A�C�f�A�����܂ꂽ�v�B �y�G�s�\�[�h�z�u���l�̃G�L�X�g���́A���l�̎��Ǝ҂ł���B���͗ǂ�����ł͂Ȃ��B�s��̂����炵�����ʂ́A�N�̖ڂɂ����炩�ł���B�l�X�͋ŁA�E���Ȃ��B���̌��ʒ����͈����B��x�ƃE�[�t�@�́A���̂悤�Ȉ����G�L�X�g���g�����Ƃ͌����ĂȂ����낤�B�����ă��r�b�`���͔ނ���A�܂��܂���������K�v�Ƃ���B�Պ����̍s��̂��߂ɔނ́A���j���O�X�ƃw�j�[�E�|���e���Ɋ��Ă�������ܐ�l���̒j����v������B�Պ����̍s��͑s��Ȍ����Ȃ̂ŁA�E�[�t�@�̐�`�S���҂́A���{�̃����o�[�𐔐l�A���̎B�e����������悤���҂����B��b��́A�悭����悤�ɏ��X�x��A������͓�����҂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����Ɛa�m���������Ȃɍ������B�����Ń��r�b�`���͊J�n�̍��}��������B�Ƃ��낪�s��͓����Ȃ��B�����N�������̂��H�@���Ǝ҂����́A��b�����ɋC�������̂������B���ꂪ�ނ�ɂ́A�܂������f���s�i�ɗ��z�I�ȋ@��Ǝv��ꂽ�B�Պ����̍s���g�ޑ���ɁA�ނ�͑����\���āA���{�Ɍ������Đi�ށB���j���O�X�ƃw�j�[�E�|���e���Ɍ������Ċ��Ă������ɁA�ނ�͐��{�̃����o�[�������Č��J�𐁂��āA���W���Ƃ��B���ꂩ��V���v���q�R�[���A�u�d�����悱���I�d�����悱���I�v �@���{�̐a�m���́A������Ⴄ���ɍl�����B�ނ�͌����Ȃ��炠���ӂ��Ɠ�������B���̌シ���A�ނ���悹�āA�Ԃ��X�^�[�g���鉹����������B�����s���Ă��܂����B���̐l�X�������Ă��܂����B���r�b�`���Ɣނ̏��肽���A���j���O�X�ƃw�j�[�E�|���e���̏��������Ă��锪�l�̏��������B�����w�j�[�E�|���e���͓����Ȃ��̂ŁA�������Ȃ��B�ޏ��̒��Ă��镞�́A�����ւ�d�����E�j�q�łł��Ă���B����͔ޏ����g�����d���B�ޏ��͔��l�̂����������Ȃ��ɂ́A����������Ȃ��B�����Ŕޏ��͗��������Ă���B�q���O�r�͔ޏ��Ɍ������ĎE�����邾�낤���H�@�ޏ��͕G��������������B�����Ɠ{�����炪���͂݁A���Ԃ����Њd�I�ɐU��グ����B�ޏ��͖ڂ����B���Ă͂����Ȃ��I���̂Ƃ��A���{�̎肪�ޏ��̌��ɒu�����B�q�|�����ŁA�w�j�[�B���ɂ͉�������B���͉����A��������ȏ��̎q���I�r�B�b���ɕ��������l�����A�n�ʂ���ޏ��̏��������グ���̂ŁA�w�j�[�E�|���e���͂悤�₭�̂��ƂŁA�����̊y���ւ��ǂ蒅�����Ƃ��ł����v�i�N���g�E���[�X�F�w�h�C�c�f��̈̑�Ȏ���x�j�B �@�f��́u�x�������E�V���A���v�̎��P���s�Ƃ��āA�x�������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�Ńv���~�A�������Ȃ��A���y�Ԃɂ͑����̋M������Ȃ����B�Ō�ɃA���E�u�[�����̎]�����ʂŃG���h�ƂȂ����i�N��L38�j�B 1920.12.25 �w���܂悦�鑜 Das wandernde Bild�i�u��̒��̐���vMadonna im Schnee�j�x �t���b�c�E�����O�ēA�V�i���I:�e�A�E�t�H���E�n���u�A�t���b�c�E�����O�A�B�e�F�O�C�h�E�[�[�o�[ �y�L���X�g�z�~�A�E�}�C�i�C�����K���g�E���@���f���n�C�g�j�A�n���X�E�}�[���i�o�q�̌Z��Q�I���N/���[���j�A���h���t�E�N���C�������[�f���m�N���C�������b�Q�n�i���B���E�u�����g�F�o�q�̌Z��̏]�Z��j�A���j�E�l�X�g�A�n���[�E�t�����N �y����z���[���͑o�q�̌Z��̂��߂Ɉ����鏗������g�������āA�R�n�̌ǓƂ̒��ɉB������B������ނ͒ʂ肷����ɐ��ꑜ�����āA����̑��������o�����Ƃ��ɖ߂��ė���Ɛ����B���̂̂�����̑��͐���̂��߂ɗ������B���̓�������̒��ŃC�����K���g�͖��q���~���B�l�X�͐��ꎩ�g�����Ɗ�Ղ��������̂��Ǝv���B���[���͂��܂悦�鐹��̑��̂Ƃ���߂�_�@������B�x�������́u�^�E�G���e�B�[���p���X�g�v�ŕ���B |
|
| 1921 | |
| 1921�i���{����1923.6.4�j �w�����̉��� Der Mann ohne Namen�x �Q�I���N�E���R�[�r�ēA���N�����F�t�B�������L�V�R��p173 1921 �w�}�m���E���X�R�[ Manon Lescaut�x �t���[�h���q�E�c�F���j�[�N�ēA�V�i���I�F�x�A�[�e�E�V���b�n�A�J�[���E�O���[�l�i�A�x�E�v�����H�[�̏����ɂ��j�A���u�F�A���g�D�[���E�M�����^�[ �y�L���X�g�z�����A�E�}���i�}�m���E���X�R�[�j�A�A���}�E�O�����[���P�i�}�m���̕�e�j�A���@���^�[�E�Q�[�x���i�}�m���̌Z��j�A�G�h���B���E�V�F�[�t�@�[�i�e�B�x���W���j�A���q�����g�E�Q�I���N�A�����E�X�E�u�����g�B 1921 �w�R�Ƃ̐킢�� Im Kampf mit dem Berge�x �A���m���g�E�t�@���N�ēA�V�i���I�F�A���m���g�E�t�@���N�A�B�e�F�[�b�v�E�A���K�C���[ �y����z�L�^�f��B 1921.1.21 �w��̃v�����i�[�h Gang in die Nacht�x �t���[�h���q�E���B���w�����E�����i�E�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[�i�f���}�[�N�̃n���G�b�g�E�u���b�z�̉f���{�i�w�����ҁx�j�̎��R�ȋr�F�A�B�e�F�}�b�N�X�E���b�c�F �y�L���X�g�z�I�[���t�E�t�F���X�i�A�C�M���E�x���l�����j�A�G���i�E�����i�i�ނ̍���҃w���[�l�j�A�R�����[�g�E�t�@�C�g�i�Ӗڂ̉�Ɓj�A�O�h�����E�u���[���E�V���e�b�t�F���Z���i�����[�A�x��q�j�A�N�������e�B�[�l�E�v���X�i�[�B �y���炷���z����҃w���[�l��A��āA�Ƃ���L���o���[�ɓ������Ƃ��A�x���l�����́A�������䂵���̂��Ă���x��q�����[�̂Ƃ���Ă��B�ޏ��͂������Ȃ�O����A���̈�t�̒��ӂ������Ɍ��������悤�Ƃ��Ă����B�����Ĕޏ��̓x���l�����܂��āA�U�f���邱�Ƃɐ�������B�ނ̓w���[�l���̂ĂāA�����[�ƌ������A�ޏ��ƈꏏ�ɂ��鋙���Ɉ������ށB�U���̓r���œ�l�́A���т��ш�l�̎Ⴂ�Ӗڂ̉�Ƃɏo��B�x���l�͎�p������A�ނ̊���������Ƃ��ł���Ǝv���B�����Ď�p�����������̂��A���������邽�߂ɔނ������̉ƂɌ}����B�w���[�l���d���a�C�ɂ������Ă���ƕ����ƁA�ނ͔ޏ��̂Ƃ���}�����A�������Ƃɓ���Ă͂��炦�Ȃ��B�A�r�ɔނ̓����[�Ƃ��̎Ⴂ��Ƃɏo����A��l�͂��łɐe���Ȉ���Ō���Ă��邱�Ƃ��킩��B�����Ńx���l�̓����[�ƕʂ�āA���֖߂�B����������[�́A�����L���Ȋ�Ȉ�ɂȂ��Ă����x���l��K�ˁA�Ăю���������Ƃ������Ă����悤���ށB�������x���l�̓����[�ɁA�ޏ����������Ȃ��Ƃ�����ԂȂ�A��Ƃ̎��Â����Ď����Ă�낤�ƁA�⍓�Ɍ������B�����ނ����ɋA�����Ƃ��A�����[�͂����p�������Ă����B�����[�Ɍ������ē����������t���v���o�����ނ́A�����\��������Ĕޏ��̂Ƃ���}���B�����������x�������B���l���~�����߂ɁA�����[�͎��疽�����Ă����B�����ĖӖڂ̉�Ƃ̓x���l�̏��������Ƃ�����B�����[�����ł́A�ނɂ͐l���͂������̉��l���Ȃ����炾�����B�����ăx���l�������A�����̏��������ɓ˂������Ď���ł���̂����������B �y����z�x��q�̗U�f�ɋ����čȂ��̂Ă���Ȉオ�A�ڂ̌����Ȃ���Ƃɗx��q������A�Ăю���������Ƃ̎�p������œ�l�����ɒǂ����A���������ʂƂ������̔ߌ��́A�w���ނ��̒j�Ɨx��q�x�̌�́A�����i�E�Ƌr�{�ƃJ�[���E�}�C���[�Ƃ́A��Ԗڂ̋�����i�ł���B����̓��B���[�E�n�[�X����i�]�ł������悤�ɁA�O�I��������I���B�W�����ɕϗe�����āA���ʓI�ȃ��Y�����ŗ��ł�������i�ƂȂ��Ă���B�����ĕ\����`����q�������f��r�ֈڍs�����h�C�c�f��̖G������ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł���B�}�����ꂽ���Z�ɂ�������炸�A�����ْ����ɖ������f���́A��ʂɃ����i�E���̂��Ɍ��o�����ēɂȂ邱�Ƃ��A���łɎ������Ă���ƕ]������Ă���B �@�����Ƃ�����͉ߑ�]���ł����āA���̍�i�͓��e�I�ɂ͒ʑ��I�Ȍ����݂ł����Ȃ��A�`���I�ɂ̓T�C�����g�f����L�́A����ĕt�����悤�ȃp�g�X�ɂ͂܂荞��ł���Ƃ������]������B�����������������]����A���R�`�ʂ̂����炷���Y���̗͋����͔F�߂Ă���B���Â̋���ȃR���g���X�g���琶����f�����͂��炵���B �@����̃I�[���t�E�t�F���X�ɂ��ẮA�u�f�A�E�t�B�����v���������A�u�ނ̗}�����ꂽ�\����@�͒��ڂɒl����v�Ə^���Ă����B������������T�C�����g�f�掞��ɓ��L�̉��Z�̌^�ɉ߂��Ȃ��Ƃ����]��������B�Ƃ��������̉f��́A�]�����r����������Ă����i�ł���B �y�f��]�z1920�N12��14���t���u�t�B�����N�[���[���v���\�\�u�c�c���̉f������āA�ǂ�Ȉ�ۂ��c�������H�@���ɂ��炵�����y�I�Ȃ��̂��c�����B�����n�߂���l�̒j�ƈ�l�̏����݂��Ɍ��������āA���������ނƂ��A�����ē�l���Ȃ��₩�ȕ����̋�C�̒��ŁA�K�X���̋��Ő[���Â��ċz���A���̊ԊO�ł͉J���~��A���������Ă���Ƃ��������ł���B���邢�͔ނ����̌�ŁA�ޏ��̎�ɃL�X����Ƃ��A�����Ĕޏ������ɂ�����A�k���Ȃ���r���L����Ƃ��������ł���B���邢�͂�����l�̏����A�̂Ă�ꂽ���ł��A�Ԗ͗l�̃\�t�@�ɉ��ɂȂ��Ă���Ƃ��A���A�a��ŁA�܂�����������߂đ�ϐÂ��ɁA�����ċ��łɊւ��鍱�ׂȋL�����ڂ��Ă��鏬���ȐV���̒Z�M���A�J��Ԃ����̉�������o���Ƃ��������ł���B���邢�͖ڂ̌�����j���Ӗڂ̒j�̑���ʂ�߂��A�吺�Łu�l�͌N�̉�������E�����I�v�Ƌ��ԂƂ��[�[�������Ӗڂ̒j�́A�߂��݂̂��߂ɓ���t���Ă��܂�������ŁA�����ɂ����Ɨ��������Ă���c�B�����ł͂����͒���Ƃ̌|�p���ǂ��ŏI���A�ē̂��ꂪ�ǂ��Ŏn�܂�A�o�D�����̂��ꂪ�ǂ��Ŏn�܂�̂��A����͂킩��Ȃ��B���ׂĂ����荬�����ĉf���炵���̂��B���ׂĂ��݂��ɍ����荇���Ă���B���ׂĂ��������Ă��āA���̕\���͂ł��͂��Ȃ��B�J�[���E�}�C���[���������X���v�g�́[�[��̕��|��i�ł���c�c�ނ��ǂ����Ă�悤�ɁA����点�āA��l�̈Ӗ����Î����Ȃ���A�}���ň�߂��삯�����Ă����Z�ʂ́A�M�����������̂�����c�c�B�����i�E�̉��o�́H�@���ہA�f��̍˔\�ɂ��Č��Ƃ��ɂ́A�����͂ǂ��ł��A�����i�E�̂�����l���Ă����ƌ����Ă悢�c�v�i���B���[�E�n�[�X�j�B 1921.2.3 �w�키�S Ka*mpfende Herzen�i�����߂���l�l Die Vier um die Frau�j�x �t���b�c�E�����O�ēA�V�i���I�F�e�A�E�t�H���E�n���u�A�t���b�c�E�����O�i�q�E�d�E���@�����[�̃h���}�ɂ��j�A�B�e�F�I�b�g�[�E�J���g�D���b�N�A���u�F�G�����X�g�E�}�C���F���X�A�n���X�E���R�[�r �y�L���X�g�z�J���[���E�g�����i�t�������X�E�C�P���v�l�j�A���[�g���B�q�E�n���^�E�i�n���[�E�C�P�����F�̔��l�j�A�w���}���E�x�g�q���[�i�t�������X�E�C�P���v�l�̕��e�j�A�A���g���E�G�g�z�[�t�@�[�i���F���i�[�E�N���t�g�F�t�������X�̂��Ă̍����/�E�C���A���E�N���t�g�F�ނ̂��傤�����j�A���h���t�E�N���C�������b�Q�i�A�v�g���F���i����߂�Ƃ��Ă���ҁj�A���[�x���g�E�t�H���X�^�[�������i�K�i���[�j�G�j�A�����[�F���[���[�i���̎����j�A�n���[�E�t�����N�i�{�r�[�j�A���I���n���g�E�n�X�P��/�p�E���E���[�R�b�v�i��l�̂₭���j�A�S�b�g�t���[�g�E�t�b�y���c�i���d���j�A�n���X�E�����v�V���b�c�i�Ȃ炸�ҁj�A���[�U�E�t�H���E�}���g���i�}���S�b�g�j�A�G�[���J�E�E�����[�i���t�w�j�A�p�E���E�����K���i�Ȃ炸�ҁj�A�G�h�K�[�E�p�E���i�ڗ����Ȃ��l�j�A�Q���n���g�E���b�^�[�o���g�i�V������̏��N�j 1921.2.9�i���{����1922.12.3�j �w���n�����b�g Hamlet�x �X���F���E�K�c�F�iSvend Gace�j�A�n�C���c�E�V�����iHeinz Schall�j�ēA�V�i���I�F�G�����B���E�Q�p���g�i�V�F�C�N�X�s�A�ł͂Ȃ��A�m���E�G�[�̓`���ɂ��j�A�B�e�F�N���g�E�N�����g�A�A�N�Z���E�O���[�g�N���[�G�� �y�L���X�g�z�A�X�^�E�j�[���[���A�p�E���E�R�����[�g�A�}�e�B���f�E�O�u�����g�A�����[�E���R�u�\�� �y����z�ƒ대�B�A�X�^�E�j�[���Z�����n�����b�g���������f��v���~�A�i��]�͂悻�悻�����u���҂̂��߂̉f��v�ƍ��]�������A�������听���������j�i�N��L40) 1921.4.7 �w�t�H�[�Q���b�g�� Schloss Vogelöd�x �t���[�h���q�E���B���w�����E�����i�E�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[�i���h���t�E�V���g���b�c�̓����̏����ɂ��j�A�B�e�F�t���b�c�E�A���m�E���@�[�O�i�[ �y�L���X�g�z�A���m���g�E�R���t�i�t�H�[�Q���b�g��̏��t�H���E�t�H�[�Q���V�����C�j�A�����E�L���[�U�[���R���t�i�c�F���^�A�ނ̍ȁj�A���[�^���E���[�l���g�i���n���E�G�b�`�����݁j�A�p�E���E�n���g�}���i�y�[�^�[�E�p�E���E�G�b�`�����݁j�A�p�E���E�r���g�i�U�b�t�F���V���e�b�g�j�݁j�A�I���K�E�`�F�z���@�i�U�b�t�F���V���e�b�g�j�ݕv�l�j�A�w���}���E�t�@�����e�B���i�ސE�n���ٔ��������j�A�����E�X�E�t�@���P���V���^�C���i�C�̏������a�m�j�A�Q�I���N�E�c�@���@�c�L�[�i���K���R�b�N�j�A���[�x���g�E���t���[�i�Ɨ߁j�A���B�N�g���E�u�����[�g�i�[�i�t�@�������g�_���j�A���@���^�[�E�N���g�E�N���[�i���g���j�A���[�j�E�l�X�g�i�q���j �y���炷���z�t�H�[�Q���b�g��Ŏ�̉�Â����B�����J�̑���10���̓V�C�̂��߂ɁA�܂����o���ł��Ȃ��B�v�����������n���E�G�b�`�����݂���Ɏp�������B�U�b�t�F���V���e�b�g�j�ݕv�l���v�ƈꏏ�ɗ��邱�ƂɂȂ��Ă���̂ŁA���͔��݂ɏo������悤���߂Ă݂邪�A���ʂł���B�j�ݕv�l�́A�G�b�`�����݂̎E���ꂽ�Z��̕v�l�������̂ł���B�G�b�`�����݂ɂ́A�����̌Z���E�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�����������Ă���B�o�������邽�߂ɁA�j�ݕv�l�͓�����A�����ɏo�����悤�Ƃ���B�ޏ��̍ŏ��̕v�̉������҂ł���t�@�������g�_�������邱�Ƃ��āA�͂��߂Ĕޏ��͗��܂錈�S������B�_����m���Ă���҂͒N�����Ȃ��B�^�����������悤�Ǝv���Ă���G�b�`�����݂́A�t�@�������g�_���ɕϑ����Č����B�j�ݕv�l�͔ނɍ��������傤�Ƃ���B�ޏ��͂܂��ނɁA�y�[�^�[�E�p�E���Ƃ̌��������ɂ��Č��B�p�E���͂��闷�s����A���ė���ƁA�܂������l���ς���Ă��܂��Ă����B�ނ͎����̑S���Y��n�����l�����ɕ��z���悤�Ƃ��A���̂��ߔނ̌Z�ƌ��_�ɂȂ����B�����Ŕޏ��͘b�𒆒f���A�����ɂȂ��Ă�����b�����Ƃ���B��A�ޏ����_�����Ă���ƁA�ނ͎p�������Ă���B��̈�s���o������ہA�ޏ��̓G�b�`�����݂�ӂ߂āA�ނ��Z��̃p�E�����E�����̂��ƌ����B�t�@�������g�_�����p�����������Ƃ��A�ސE�n���ٔ��������́A�G�b�`�����݂ƊW������Ƃ���B�������_�����Ăюp�������A�j�ݕv�l�͍����𑱂���B������ƁA�_���͉���������āA�G�b�`�����݂Ƃ��Đ��̂����킵�A�j�ݕv�l���ɂ��̃t�@�������g�_���ł���ނɑł����������Ƃ��A�j�݂ɍ�����B�j�݂́A�K�������ޏ������W�Ƃ͌����Ȃ��s�K�Ȏ��Y�̂��߂ɁA�y�[�^�[�E�p�E�����݂��ˎE�����̂������B�j�݂͎��E����B���̎��A�{���̃t�@�������g�_�����A���[�}���瓞������B �y����z���̍�i�͓����h�C�c�ōL���ǂ܂�Ă����ʑ��I�ȁu�x�����i�[�E�C���X�g���[���e�v���Ɍf�ڂ��ꂽ�̂��A�u�E���V���^�C���E�u�b�N�v�̈���Ƃ��āA����ȕ����������h���t�E�V���g���b�c�̏������f�扻�������̂������B�Ƃ������Ƃ̓����i�E�����̐��I�ȉf�挾��ɂ���āA�ގ��g�̗����W�ł�����A�f��j��̌ÓT�̈ʒu���߂�悤�ȍ�i����邽�߂̌���Ƃ��ẮA���������n��ȏ����������Ƃ������Ƃł���B �@�������w�m�X�t�F���g�D�x����邱�ƂɂȂ郀���i�E�́A�������邱�Ƃ��Ȃ����̃X�����[��������u���C���Ȃ��́v�������Ă��镵�͋C�����ݎ�邱�Ƃɐ������Ă���B����ɂ��Ă������i�E�́A���̉f����͂�16���ԂŎB��グ���̂�����A�����ł���B�V�������E�W���~���[�͂��̉f��ɂ��āA���������Ă���B�u���̍�i�́A�����i�E�ē��A�A�܂������O�ʓI�ȃt�@���^�W�[�i�w�W�F�L�����m�ƃn�C�h���x�j�A���R��`�I�ȃh���}�i�w���ނ��Ɨx��q�x�j�A�T��f��i�w�[���c��c���x�j�A�����Ď������i�w�}���b�c�@�x�j�Ƃ������C�y�Ȉ��K�I�앗�ɔw���������A�ŏ��̉f��ł���悤�Ɍ�����B���̂��߂ɂ͌��݂����Ă̓]�����������B �@����1911�N�ł���B�����i�E�̐��E���`�𐬂��Ă����B�h�C�c�̔��v���ɂ���ē��h������ꂽ���̃T�����̋��܂������͋C�́A���ɂ́A�܂������ʂ̑Ό��̌����ƂȂ��Ă���悤�Ɏv����B���u�́A��M��}����ꂽ���l�����������S�ە��i�́A���f���Ƃ��Ă̖����ʂ����Ă���v�B���ہA�w���}���E���@�����̍쐬�����t�H�[�Q���b�g��̃Z�b�g�́A���͋C���o���̂ɑ�ϖ𗧂��Ă���B �@����ɃJ�[���E�}�C���[�̃V�i���I���A���������C�������炩���ߍו��Ɏ���܂Œ蒅�����Ă���B�Ⴆ�u�����v�Ƃ����V�[���́A���̓T�^�ł���B���B���[�E�n�[�X�́u�t�B�����E�N�[���[���v���ɁA���������Ă���B�u���̉f��ɂ́A�q�����r�Ƃ����^�C�g���̃V�[��������B�q����ȁA�V��̍����z�[���ɁA���̂��߂ɐl�E���������E�l�҂��A���̗��l�ƈꏏ�ɂ���B��l�͂܂����������Ȃ��B�܂�Œ����̂悤�Ɂj�[�[�f�悪�n�܂��Ĉȗ��A���̂悤�ȏ�ʂ������ꂽ���Ƃ͋H�ł���v�B �@�u����Ɍ����A�����i�E�̗l���̒��œƓ��Ȃ̂́A�{���̍s�ׂ��̂��̂Ƃ͂��܂�Ȃ���������Ă��Ȃ��O���e�X�N�ȃV�[�����A�Ƃ��Ƃǂ���ɑ}������邱�Ƃł���B��̑䏊�Ń{�[�C�͂܂ݐH�����������߂ɁA�R�b�N�ɕ���ł������炤�B����ƃ{�[�C�͂��̖�A�������䏊�ɂ��ăt�@�������g�_������A�܂ݐH�������邽�߂̌������炢�A���̒��Ɏw�����邽�тɃR�b�N�̖j���Ђ��ς����A�Ƃ�����������B�����ЂƂ̃V�[���ł́A���Â߂̂����肪�����畔���ɓ����Ă��āA�������J�̒��ɘA��o�����Ƃ��鈫���ɔY�܂������̏ꍇ�ł���B�����̃V�[�����t���C�f�B�Y���̉e���Ǝw�E����͈̂Ղ������A�����i�E�̏ꍇ�A�������ꂾ���łȂ��̂́A�����̃O���e�X�N�ȃV�[���������錻���̎��ԂƂȂ��܂��ɂȂ��Ă��܂��āA�ЂƂ̐��E�����肾���Ă��܂��V�^�̍˔\�̂��邱�Ƃł���v�i�w�h�C�c�\���h�f���ڏ�f��4�E5���p���t���b�g�x�A�T�y�[�W�j�B�@���̌����̔閧�\�I�̔ߌ��́A�x�������́u�}�������n�E�X�v�ŕ���ꂽ�B �y�f��]�z1921�N�u�L�l�}�g�O���t�v��739���\�\�u�c�c���Ȃ�ʐS�I�Ȃ��̂�\�����A�O�ʓI�ȃZ���Z�[�V������������邱�ƂɁA�e�E�v�E�����i�E�̉��o�������������ƁA���ꂪ���̉f��̓��ʂȋ��݂ł���B���o�͂��܂��܂ȋC���Ƃ܂��������q�������Ă���B���z�ƉJ�Ɨ������O�ʂ̕��͋C�́A��ɏ�̏Z�l�����̊Ԃ��x�z���Ă���C�����Č����A�邻�̂��̂Ɠ����悤�ɁA����߂Ĕ����ȐS�̓�����}��Ă���B�����ď�͖��邭�Ƃ炵�o���ꂽ���ʂɂ���āA���ɂ͊y����ł����s���A���ɂ͖�̈ł��Ƃ炵�Ă��邽������̑��ɂ���āA�S�z���d���̂��������Ă��鎞�Ԃ���������B�����ł́A���炵�����ʂ�����V�炵���\����i����������Ă���B�����Ƃ��Ă��鎞�ɏo�����A���̌シ���y���~��̉J�̒����A���ė����̈�s�̉f���́A���ɂ��炵�������c�c�B��̓����̋�Ԃ͍T���߂ȉ₩���ƋC�i�̂���f���������Ă��邪�A���ɍ\����ɂ����Ă����������B�����Ĉ�ʓI�ɉf��S�̂��A�f���ɂ����Ă����Z�ɂ����Ă��A�f��̂ǂ�Ȃ܂₩���̋P�����������Ă���c�c�v�B 1921.4.12�i���{����1925,1.30�j �w�R�L���V�J Die Bergkatze�x �G�����X�g�E���r�b�`���ēA�V�i���I�F�n���X�E�N���[���A�G�����X�g�E���r�b�`���A�B�e�F�e�I�h�[���E�V���p�[���N�[�� �y�L���X�g�z�|�[���E�l�O���i�����V�J�F�����c��̖̂��j�A�p�E���E�n�C�f�}���i�A���N�V�X���сj�A���B�N�g���E�����]���i�v�ǎi�ߊ��j�A�G�f�B�b�g�E�����[�i�����[�F�i�ߊ��̖��j�A���B���w�����E�f�B�[�Q���}���i�N���E�f�B�E�X�F�����c�̎�́j�A�p�E���E�r�[���X�t�F���g�i�_�t�R�F�����c�̈ꖡ�j�A�G�����B���E�R�b�v�i�g���|�F�����c�̈ꖡ�j�A�p�E���E�O���[�c�i�c�H�t�@�m�E�����c�̈ꖡ�j�A�}�b�N�X�E�N���[�l���g�i�}�W���I�F�����c�̈ꖡ�j�A�w���}���E�e�B�~�q�i�y�|�F�����c�̈ꖡ�j�A�}���K�E�P�[���[ �y���炷���z�v�t�B�t�J�i�C���̖q�̓I�ȎR�n�ɂ���g�b�Z���V���^�C���v�ǂł́A�i�ߊ����������K���ŕ��m��������ߏグ�Ă���B�����ɔނ͕��m�������ە����邪�A�ނ��w���������ۂ�A���m�����݂͂�ȐQ���ɖ߂��Ă��܂��B���������v�ǂ֗L���ȏ����炵�A���N�V�X���т��]�C���ė���B�i�ߊ��̖������[�͂�����ē���A���e�͑傢�ɐS�z�ɂȂ�B������̎R�̉��ɂ̓N���E�f�B�E�X����̂Ƃ���A�_�t�R�A�g���|�A�c�H�t�@�m�A�}�W���I�A�y�|�Ƃ������R���̈ꖡ�����āA������̕��a�𗐂��Ă���B��̖̂������V�J�́A���������R�������̊ԂŁA�܂�ŏ����̂悤�ɐU�镑���Ă���B �@���ăA���N�V�X���т͗v�ǂ֕��C����r���A���̎R���̈ꖡ�ɏP���A�g����ݔ�����Ă��܂��B���������т͎����𗇂ɂ��������V�J�ɍ��ꍞ�ށB����Ɨv�ǂɒH�蒅�������т́A�v�ǂɔE�э���ł��������V�J���������߂āA�ڕ�����B�����[�͂��̏�ʂ�������ʂ��Č��Ă��܂��A��������x�������B�����V�J�͐g����������Ȃ��B �@���̃����V�J�������ɂȂ��Ă���̂��������̃N���E�f�B�E�X�́A���̌��z���₷���߂ɁA�ޏ����艺�̃y�|�ƌ��������悤�Ƃ���B�����v�ǎi�ߊ��̖������[�̓A���N�V�X���тƌ������邱�ƂɂȂ�B������������V�J�͂�����x�v�ǂɔE�э��ށB�A���N�V�X���т������[�Ƃ̌����������A�C�����̓����V�J�̂ق��ɌX���Ă���B�����[�͂��������]���Ă��܂��B�������������[�̎p�����������V�J�́A�S������āA�����������������тɂӂ��킵�����ł͂Ȃ����Ƃ����B�����Ŕޏ��͒��тɌ������āA�킴�Ɖ��i�ȐU�镑�������Ă݂���B�����������т͉��₩�ȃ����[�̕��ցA��������S���ڂ��B�����V�J�͎R���̃y�|�̂Ƃ���֖߂��čs���B �y����z�����̊쌀�f��̑��l�҃��r�b�`�����A�X�^�[���D�̃|�[���E�l�O�����Ăуq���C���ɋN�p���ĎB�e�������̉f��́A���R�Ƃ�����悤�ȕ��䑕�u�A�l�p�����ʂ̌`���ނ����O�ł���悤�ȁA�ٗl�ȏ�ʂ̎B�e�̎d���ɂ���āA���h�쌀�f��Ƃ����ɂ͗]��ɑO�q�I�ȍ�i�ƂȂ��Ă����B���h���t�E�N���c�͂��̒��w�\����`�Ɖf��x�̒��ŁA���������Ă���B�u�h�C�c�ōŏ��̎����т����l���I�f�悪�A�t���I�Șb�ł��邪�A�G�����X�g�E���r�b�`���ɂ���ĉ��o���ꂽ���Ƃ́A���ڂɒl����B�n���X�E�N���[���̃X�N���v�g�ɂ��w�R�L�����V�J�x������ł���B���̊쌀���Ӑ}�I�ɁA���������牓�����z�I�O���e�X�N�l����ڎw���ĉ��o����Ƃ����̂��A���r�b�`���������ɂ����Ε\�������Ӑ}�������B��Ƃ̃G�����X�g�E�V���e�����́A���r�b�`���̒�Ă��A�����т����\���Ɉڂ��ւ����B�t�H�����̓p���f�B�[�����ꂽ�o���J���n���̊�����ʂ�����A���ׂĂ�����ɘc�߂��A�傰���ɖc��܂��ꂽ�B�\���̓��A���Ȍ����̔ޕ����u�����A�������̓o���J���I�ؔ��A�����̕��K��ڕW�Ƃ���A�C���j�[����肵�Ă���v�B �@�f��̂��߂Ɉ�̗l�������o���Ƃ����n���I���ӂɂ���āA���r�b�`���͂��炩���߁A���łɌ��܂����f���ʂ̃T�C�Y��ł��j�낤�Ƃ����B�l�p�̃X�N���[����ɁA�f�����悤�ɕ`���͖̂��Ӗ����ƌ�������ɁA�ނ̓X�N���[�����A�����̉f���̓��e�ɂӂ��킵���t�H�����ƃT�C�Y�ɍ����悤�ɐؒf�����B �@���̌��ʂƂ��āA�ۂ��ʂ�߂̖ʁA�ׂ������̖ʂ␂���̖ʂ����ݏo���ꂽ�B�ۂ��ʁA�L�X���Ă�����̂悤�Ȍ`�̖ʁA�[�ŏ���ꂽ����M�U�M�U���̖ʂ��x�����B�ȑO�ɂ͂���Ǝ������͉̂����Ȃ������B�̂��ɂ�ꡂ��ɑ�_�Ȏ����������Ȃ�ꂽ���A���h�I�o�[���X�N�̂��߂ɁA���̂悤�ɋɒ[�ȗl���������݂�ꂽ���Ƃ͋H�ł���A���ꂾ����w���̉f��͒��ڂɒl����B �@���������̗l�������A�f��̋��s�I�����̖W���ƂȂ����B�\����`�ƃ��[�Q���g�V���e�B�[���ƃI���G���g���̃����w���I�ؗ킳�����z�I�ɍ��������Z�b�g�ł́A�^�������Ȑ��͉������A���ׂĂ��Ȃ��肭�˂�A�A���̂悤�ɖ�������Q�����͗l�ɉ�������B��������̊��S�Ș����́A�n�b�s�[�G���h�̖���������O�ꂵ���R�l�̃J���J�`���A���Ƒ��ւ��āA�����̊쌀�f��̏펯���z�������̂������B���R���r�b�`���f������ɗ���ϋq�̃Z���X�ɍ����͂��͂Ȃ������B �@��������N�̃n���E�b�h�ł̃��r�b�`���f��Ƃ̊֘A�Ō���A���̉f�悪�������Ă���R���̕s�𗝐��̖\�I�́A�̂��ɂ͈�w�z���ɊJ�Ԃ��邱�ƂɂȂ郋�r�b�`���̕��h�������������A���łɖG��ɂ����Ď����Ă���B����͒��̓_�Ă̂��߂Ƀ��b�p�𐁂����m�̏�ʂŎn�܂�B�ނ͉E��Ƀ��b�p�������A����Ƀ\�[�Z�[�W�������A�����̂ƐH�ׂ�̂����݂ɂ����Ȃ��̂ł���B���̊ԂɋN�����b�p�ɉ��̔������������ɖ����Ă��镺�m�����̃J�b�g���}�������B��������l�̕��m���N���オ�邪�A�ނ͕��A�����̂��A�܂��x�b�h�ɂ����荞��ł��܂��B�Ƃ��Ƃ���ʈ�t�ɑ傫�ȓ�������A�u�������Ȃ���Ή�����܂��s����̂��I�v�ƙႦ�Ȃ���A���m�������x�b�h����@���o���B���ꂩ�瑾�����i�ߊ��ɗ������ė�������s�i���镺�m�������Ƃ炦��J�����́A���c�̌P���̉ʂĂ����Ȃ��i���Z���X���������f���o���B�����Ďi�ߊ����g���A�������ɂ����Ă͍ȂƖ��ɓz��̂悤�Ɉ�����A���a�ȋ��Ȓ���ł����Ȃ��B �@�܂�N�������݂����m�A��܂����C�������������ɏ��������Ƃ̂ł���A���r�b�`���̏��̖��͂������ɂ���B�����P�X�Q�P�N�̃h�C�c�̊ϋq�́A�܂����̂悤�ȏ��ɁA�S�̏������ł��Ă��Ȃ������B���r�b�`�����g�A��ɂȂ��Ă��炱�������Ă���B�u���̉f��ɂ́A���̑��̉f����������̑n���͂ƁA���h�I�ȉf���̋@�m������ł����ɂ�������炸�A�܂������̕s�]�������B����͐�シ������ꂽ�B�����ăh�C�c�̊ϋq�́A�R����`��푈�𒃉����f�����Ԃ悤�ȋC���ł͂Ȃ������v�B 1921.4.27 �w��i�P�x ���@���^�[�E���b�g�}���ē� �y����z���ƐF�ʂƊw�I�}�`�̃��Y���Ƃ��������ۉf�� 1921.5.5�i���{����1924.6.26�j �w�����_���g�� Danton�x �f�B�~�g���E�u�R���F�c�L�[ Dmitri Buchowetzki�ēA�V�i���I�F�f�B�~�g���E�u�R���F�c�L�[�A�J�[���E�}�C���[�i�Q�I���N�E�r���[�q�i�[�̃h���}�w�_���g���̎��x�ɂ��j�A�B�e�F�A�[���p�[�h�E���B���[�O�A���u�F�n���X�E�h���C���[ �y�L���X�g�z�G�~�[���E���j���O�X�i�_���g���j�A���F���i�[�E�N���E�X�i���x�X�s�G�[���j�A���[�[�t�F���[�j�b�`���i�J�~�[���E�f�������j�A�t�F���f�B�i���g�E�t�H���E�A���e���i��l�̋M���j�A�G�[�h�D���@���g�E�t�H���E���B���^�[�V���^�C���i���F�X�^�[�}�����R�j�A�V�������b�e�E�A���f���i�����V�[���E�f�������j�A�}���[�E�f���V���t�g�i���w�j�A�q���f�E���F���i�[�i�o�x�b�g�j�A�t�[�S�E�f�[�u���[���i�A�����I�b�g�j�A�t���[�h���q�E�L���[�l�i�t�[�L�G���^�����B���j�A���[�x���g�E�V�����c�i�T���E�W���X�g�j�A�A���x���g�E�t���[���[�g�i��ҁj�A�G���[�E���[�����c�B �y����z���j�h���}�B���x�X�s�G�[�����_���g����㩂ɂ�����B�v���ٔ����ł̍ŏI�٘_�ŁA���łɑߕ߂��ꂽ�_���g�����ނ����������҂�������������B���O�͔ނɊ��Ă���B���x�X�s�G�[���͋}���Ŕނ�A�s�����A�M���`���ɂ���������B �@�r�E�N���J�E�A�[�͗��j��c�Ȃ����_�ł́A�w�p�b�V�����i�}�_���E�f���o���[�j�x�ȏゾ�Ɣ����i�N��L45�j 1921.5.27 �w�j�� Scherben�x ���[�v�[�E�s�b�N�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[�A���[�v�[�E�s�b�N�i�Q���n���g�E�n�E�v�g�}���̏����w���ؔԃe�B�[���x�ɂ��j�A�B�e�F�t���[�h���q�E���@�C���}�� �y�L���X�g�z�x���i�[�E�N���E�X�i���ؔԁj�A�w���~�[�l�E�V���g���}���E���B�b�g�i�ނ̍ȁj�A�G�f�B�b�g�E�|�X�J�i���j�A�p�E���E�I�b�g�[�i�S���ē��j �y���炷���z�Ƒ������H�̂��߂Ƀe�[�u���̎���ɏW�܂����Ƃ��A���ؔԂ͓d��ŁA�S���ē�������ė���Ƃ����m�点�����B�˕��ő����������悤�ɊJ���A���K���X������B�����K���X�̔j�Ђ�O�|���ɏE���W�߂�B�����A�ē�����������B�����Ė����K�i��|�����Ă���Ƃ��A�ē����~��Ă��Ė��Əo��B�ق�̈�u��l�͌��ߍ����B�c�ɖ��͂����܂������痈�����Ȓj�ɍ��ꍞ�ށB��A�ނ͖��̕����ɔE��ōs���B���ؔԂ͂����̂悤�Ɏ����̋Ζ��ɏA���A�������NJ�������H��Ԃ��A�~�̊����钆�ɕ����Č��ĉ��B�Ƃł͕�e���ڂ��o�܂��A�����ɋC�Â��Ēǂ��čs���ƁA����͊ē��̕������畷�����Ă���悤�Ɏv�����B���̕����̃x�b�h����Ȃ̂���������A�ޏ��͕��Ŕ���j���Ċē��̕����ɓ���B�����Ă����ɖ�������̂�������B�ޏ��͂��̒j�̍s�ׂ���邪�A�ނ͂����₽���ނ���B��]������e�́A���[�̏\���ˑ��̑O�ɍs���A��������ĈԂ߂����߂�B�ē��͋C����������������āA�ޏ��̕����։^��ōs���B �@�����A�ڊo�܂����v�������Ƃ��A�Ƃ̒��͂܂������Â܂肩�����Ă���B���͖ڂ��o�܂��A�䏊�Œ��̎x�x�Ɏ�肩����B���ؔԂ͋Ζ�����߂�A�Ȃ̃x�b�h����ɂȂ��Ă���̂�������B���̊�́A�钆�ɉ����N������������Ă���B�ނ͌ˊO�̐X�̒���{�����A��̒��œ�������ł���Ȃ�������B�ނ͍Ȃ̎��̂��Ƃ։^�ԁB�ē��͂��̔ߌ��ɑ��āA���������߂邾���ł���B���ؔԂ͍Ȃ̈�̂�����ɏ悹�āA��n�։^�ԁB���̊Ԃɖ��͊ē��ɁA�������ꏏ�ɘA��Ă����Ă���ƍ��肷�邪�A�ނ͗₽����������ށB��藐���ċA������e�ɁA���͒j�ɔƂ��ꂽ���Ƃ�������B���e�͊ē��Ɏߖ������߂邪�A�ނ̍����ȑԓx�ɕ��𗧂Ăċt�サ�A���Y��Ĕނ��E���Ă��܂��B �@���ꂩ��ނ̓J���e����͂݁A�w�̂Ȃ����H��ŗ�Ԃ��~�߂āA���������B�u���͐l�E�����v�B �y����z�x�������́u���[�c�@���g�E�z�[���v�ŕ���ꂽ�A���̃��[�[���Q�r���Q�n���̉Ƒ��ߌ��f��́B�����͍Ō�́u���͐l�E����ICH BIN EIN MÖRDER�v�����ł���B�܂肻��͉f�����̂Ɍ�点�悤�Ƃ���A�����閳�������@�ƌ�����h�C�c�E�T�C�����g�f��̌���̈�ł���B�����ē����ɂقƂ�njˊO���P�̖����A�u�������f��v�̒a�����Ӗ�����_�ŁA�G�|�b�N���[�L���O�ȍ�i�������B�����ȉf��j�ƃ��b�e�E�A�C�X�i�[�́A���̒��w�f���[�j�b�V���ȃX�N���[���x�̒��ŁA���������Ă���B �@�u���[�v�[�E�s�b�N���ނ̉f��w�j�Ёx�ɂ���Đ��ݏo�����������f��́A�Ƃ�킯�S�����f��ł���B����͂Ƃ�킯�A����I�Ȋ��̒��œ�������Ă��鏭���̐l�ԂɁA�œ_�Ă邱�ƂɌ��肵�Ă���B�����ĒP�������邽�߂ɁA���A�ꏊ�A�̓���Ƃ����\���Ɋ�b��u���Ă�B���������ăs�b�N�͂�����\����`�̏������ƁA�ӎ��I�ɑΗ�����B�Ȃ��Ȃ�\����`�҂����͎��m�̂悤�ɁA�����̐S���w�A������l�I�A���s���I�ߌ��A�������g��̐S�����͂��A�J��Ԃ����f���Ă��邩��ł���v�B �@���������S���̕\�������������ɒB�����邽�߂ɁA�s�b�N�͑����̃V���{�����g�����B�f��̃^�C�g�������łɏے��I�ł���B�s�b�N�͉f��̎n�߂ƏI���Ɂu�j�Ёv�̎R���������ƂŁA������������Ă���B���邢�̓��[���X�d�M�@���ē��̓�����������Ƃ��A��������j��B�����ē˕������a�ȕ����̒��𐁂��߂���B���邢�͊ē��͕�e�̎��̂������̂��A�����̕����ɍs���Ď��B�������������ŋ̐��ڂ��r�������P��������A����u�T�^�v�ɊҌ������B �@�����Ƃ��ے��I��@�̂��ׂĂ��������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�r�E�N���J�E�A�[�͂��������Ă���B�u�m���ɑ����̕��̂��A���������ۂ��ے��̖ړI�Œ���Ă���悤�Ɍ�����B�w�j�Ёx�̒��ɌJ��Ԃ������A����ꂽ�R�b�v�̃N���[�Y�A�b�v�́A�^���ɒ��ʂ����Ƃ��́A�l�Ԃ̈Ӑ}�̂��낳��\������ȊO�̖ړI�͎����Ă��Ȃ��B����͂��ꎩ�g�Ƃ��ẮA���̈Ӗ����Ȃ��B�������������������Ȏ��s�́A�����Ȑ��ʂ݂������̂Ɠ�������\�\�܂�}�C���[�̕��̂ɑ����M����\�\���������̂ł���B�f��̂��߂ɕ��̗̂̈�𐪕����邱�Ƃɂ���āA�ނ͉�ʂ̌�錾�t���P�v�I�ɖL���ɂ����̂ł���B���̐����́A���������ׂĖ��E���悤�Ƃ���ނ̓w�͂Ƒ��ւ��āA�^�ɉf��I�Ȍ�@�̂��߂̓����J�������̂ł������v�B �y�f��]�z���u�f�A�E�t�B�����v���\�\�u�c�c���ؔԂ̂悤�ɁA�d�݂ɉ����Ԃ���ĕ������F���i�[�E�N���E�X�B�ŋ��͔j�Ђ̂悤�ɍӂ���ނ̈�Ƃ̍K�����߂����Đi�s����B�w�J���K�����m�x�̋r�{�ƃJ�[���E�}�C���[�́A���́u�ܓ��Ԃ̃h���}�v�ɑ��A��Ȃ܂łɉA�T�ȃV�i���I���������B���[�v�[�E�s�b�N�́A�ނ̂����̑@�ׂ��Ŋē����B��ʂ̒��֓˓����ė�����C�@�֎Ԃ̃N���[�Y�A�b�v��A���̏����̕��Q�����ɍs�����e�́A�Â��^���̂悤�ɔ����ė��ċ������e�ȂǁA�X�ɂ͖Y�ꂪ�����d���Ől�̐S�ɍ�p����ӏ�������B���͂��܂�ɓO��I�Ɏ�����������Ă��܂������߂ɁA�����ł��Ȃ��܂܂ł���B��e�������ƂŁA���͊ē����牽��]�ނ̂��H�@������x�����Ă���ƁA�ނɂ������̂��H�@������ǂ�ł͂��߂āA�s�C���Ȃ��̉Ƃ���A�������ꏏ�ɘA��čs���Ă���Ɣނɗ���ł���̂��Ƃ������Ƃ��킩��B�G�f�B�b�g�E�|�X�J�ȏ�ɑ傫�ȍ˔\�������Ă��Ă��A���̉ۑ�͏����ł��Ȃ��������낤�B�ޏ��͂����Ɖ��̊������^�����ɂ����킯�ł͂Ȃ��B���ɔޏ��́A���ʂ̂Ȃ��₽���p�����獂�܂��āA�k�����̂̂��l�Ԑ��̐[�݂ɒB����B���������̎c�悪�A�~���悤���Ȃ�������p���̎c�悪�A���̌��ɗ���ł���B���Ƃɂ��Ǝ����Ƃ������̂́A�ʗᑽ���̂��̂��A���������Ă��܂��Ƃ������ƂɂȂ�̂�������Ȃ��B�Ƃ����̂͌��Ď��Ƃ������ƂɊւ��ẮA�����̂ق��������Ɖs�����̂�����ł���B���e���̃��F���i�[�E�N���E�X�́A�݊��Ŗ��m�ȋ`���̓z��Ƃ��āA���ׂĂ����m���~�܂邱�ƂȂ��A���Q�Ɍ������ďd�������ŕ����čs���B�����������N���E�X�͔��͂�����A��̎��R�͂ł���B�p�E���E�I�b�g�[�̊ē��́A���̉��Z��̉��l�̓_�ŁA�K��������l�ł͂Ȃ��B�V���ؔԂ̎�����O�ɂ��āA�ނ̎肩�牌�������藎�����ʂ͂��炵���B�w���~�[�l�E�V���g���X�}���E���B�b�g�̕�e���́A����C�̂Ȃ��p��掦���Ă���B����߂Ĕ������A���炵���N�������������f���ƁA���������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��������d�ȉf���Ƃ��A�����荇���Ă����BA�EF�v�B ���u�L�l�}�g�O���t�v1921�N��746���\�\�u�c�c�g�U��̂��\���\�͂������������Ȃ��o�D�����̏�������A���i�̓_�ł͂��炵���K�Ȕw�i�����܂��I���ƂɎx�����āA�f�p�Ŋ����I�ȉf��̋ؗ��Ă��A�����ɂ����������ɃX�N���[����ɓ��e����Ƃ��������́A�]���Ƃ���Ȃ����������c�c�v�B 19219.9�i���{����1925.4.17�j �w���ԃT�b�t�H�[ Sappho�x �f�B�~�g���E�u�R���F�c�L�[�ēA�V�i���I�F�f�B�~�g���E�u�R���F�c�L�[�A�B�e�F�A�[���p�[�h�E�t�B���t�A���u�F���[�x���g�E�l�p�b�n �y�L���X�g�z�|�[���E�l�O���A���n�l�X�E���[�}���A�A���t���[�g�E�A�[�x���A�A���x���g�E�V���^�C�������b�N�A�w���K�E�������_�[�A�I�b�g�[�E�g���v�g�E�A�G���U�E���@�[�O�i�[�A�G���m�[���E�M�����g �N���J�E�A�[��106�� 1921.9.19 �w�n�Q�^�J�̃��@�� Die Geier-Wally�x �G�[���@���g�E�A���h���E�f���|���ēA�V�i���I�F�G�[���@���g�E�A���h���E�f���|���i���B���w���~�[�l�E�t�H���E�q�������̏����ɂ��j�A�B�e�F�A�[���p�[�h�E���B���[�O�A�J�[���E�n�b�Z���}�� �y�L���X�g�z�w�j�[�E�|���e���A���B���w�����E�f�B�[�e�����A�A���x���g�E�V���^�C�������b�N�A�I�C�Q���E�N���b�p�[�B �y����z�Ԉ���������Ƌ��h�Ɛ^�̈����߂��鋽�y�f��B�x�������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŕ���i���i�`�����1940�N8��13���A�n���X�E�V���^�C���z�t�ēA�n�C�f�}���[�E�n�b�g�n�C���[�剉�̃����C�N����j�B 1921.10.7�i���{����1923.3.30�j �w���ł̒J Der müde Tod Ein deutsches Volkslied�x �t���b�c�E�����O Fritz Lang�ēA�V�i���I�F�e�A�E�t�H���E�n���u Thea von Harbou�A�B�e�F�t���b�c�E�A���m�E���@�[�O�i�[�i���F�l�`�A�A�I���G���g�A�����̕��j�A�G�[���q�E�j�b�`���}���A�w���}���E�U�[���t�����N�i�Ãh�C�c�̕��j�A���u�F���[�x���g�E�w�����g�A���@���^�[�E���[���q�A�w���}���E���@�����B����F�f�[�N�����r�I�X�R�[�v�ЁB �y�L���X�g�z�����E�_�[�S���@�[ Lil Dagover�i�Ⴂ�����j�A�x�����n���g�E�Q�b�P Bernhard Goetzke�i���_�j�A���@���^�[�E�����Z���i���l���m�j�A�n���X�E�V���e�����x���N�i�s���j�A�G�����X�g�E�����b�P���g�i���E�ҁj�A�}�b�N�X�E�A�[�_���x���g�i���ؐl�j�A�G�[���q�E�p�v�X�g�i���t�j�A�p�E���E���[�R�b�v�i���j�j�A�G�h�K�[�E�N���b�`���i��t�j�A�w���}���E�s�n�i�d�����j�A�Q�I���N�E���[���i��H�j�A�}���A�E���B�X�}�[���i�V�k�j�A�A���C�W�A�E���[�l���g�i��e�j ���I���G���g�̕��F�����E�_�[�S���@�[�i�]�x�C�f�j�A���@���^�[�E�����Z���i�t�����N�l�j�A�x�����n���g�E�Q�c�P�i��t�F�G���E���g�j�A���h���t�E�N���C�������b�Q�i�C�X�������̑�m�j�A�G�h���@���g�E�t�H���E���B���^�[�V���^�C���i�J���t�j�A�G�[���q�E�E�����[�i�A�C�V���j �����F�l�`�A�̕��F �����E�_�[�S���@�[�i�t�B�A���b�^�j�A���h���t�E�N���C�������b�Q�i�W�����[���j�A���C�X�E�u���f�B�i���[�A�l�j�A���[�i�E�p�E���[���i����j�B �������̕��F���@���^�[�E�����Z���i�������j�A�x�����n���g�E�Q�c�P�i�|�p�Ɓj�A�p�E���E�r�[���X�t�F���g�i�A�q�A���p�t�j�A�J�[���E�t�X�c�@�[���i�c��j�A�}�b�N�X�E�A�[�_���x���g�i�呠��b�j�A�m�C�}�����V���[���[�i�Y���j �y���炷���z18���I�͂��߁A����Â��h�C�c�̒��ցA���������Ă���Ⴂ�j��������ė���B�r���ň�l�̌��m��ʒj���n�Ԃɏ�荞��ł��āA��l�����낶�뒭�߂�B�̂��ɓ�l�͖ړI�n�̗��قŁA�Ăт��̒j�ɏo��B�ނ͒��̗L�͎҂����ɂƂ��Ă��A�s�C���Ȑl���ł���B���炭�O�ɔނ͒��Ɍ���A��n�̋߂��̓y�n������A���̓y�n�̎���Ƀh�A�������Ȃ������ǂ��߂��炵���̂ł���B �@���ė��قɔ��܂��������q���B�ƗV��Ŗڂ����炵�Ă���ԂɁA���l�̎�҂͂��̒j�ɘA�ꋎ���Ă��܂��B��]�����ޏ��͗��l��{���ĕǂ̂Ƃ���֗��āA�C�������B�����t���ޏ��������āA�Ƃ֘A��ċA��B�����Ŕޏ��͂���{�̒��Ɂu���͎����������v�Ƃ������͂�ǂށB�����ēŔt���������Ƃ���B �@�����O���R�b�v�ɐG��悤�Ƃ����u�ԁA�ޏ��͓ˑR���̋���ȕǂ̑O�ɂ���B�����ɂ͓����������B�ޏ��͂�����ʂ�A�����K�i���オ���Ă����ƁA��ԏ�ɂ��̌��m��ʒj���҂��Ă���B����͎��_�������B�ޏ��͔ނɎ����̗��l��Ԃ��Ă���Ɨ��ނƁA���_�͔ޏ���傫�Ȃ낤�����ň�t�̋���ȉ�ɘA��Ă����B�낤�����͂��������l�̐l�Ԃ̑��肾�����B���_�́u���͐l�Ԃ̋ꂵ�݂��ꏏ�Ɍ��Ă���̂ɔ�ꂽ�B���͎��̐E�Ƃ�ł���v�ƌ����A�ޏ��Ƀ`���`���h�炢�ł���O�{�̂낤�����������B����͎����̔����Ă���O�l�̎�҂̐����̂낤�����������B �@�ނ���ޏ��̗��l���l�A�Ⴂ���Ɉ�����Ă����B���_�͔ޏ��ɁA���̎O�{�̒��̈�{��R���s���Ȃ��悤��邱�Ƃ��ł�����A�ޏ��̗��l�̐����͏����邾�낤�ƌ����B�������ĎO�̕��ꂪ�n�܂�B �@���̂낤�����̕���ł́A�ޏ��͂X���I�̃o�O�_�b�h�̒��̃J���t�̖��]�x�C�f�ƂȂ�A�Ⴂ�t�����N�l�������Ă���B�ޏ����ً��k�ƊW���Ă��邱�Ƃ��I������ƁA���̃t�����N�l�͑ߕ߂����B��]�I�Ƀ]�x�C�f�͔ނ̐������~�����Ǝ��݂�B�J���t�͒�t�̃G���E���g�ɖ����āA�ނ����߂ɂ�����B�]�x�C�f������ė����Ƃ��́A���łɒx�������B�ޏ��̓G���E���g�̊��m���Ă����B����͎��_�������B �@���̂낤�����̕���ł́A�ޏ���14���I�̃��F�l�`�A�̖��t�B�A���b�^�ł���B�ޏ��͎Ⴂ�t�����`�F�X�R�������Ă��邪�A�������Ӓn�̈����V�W�����[���ƍ��Ă���B�W�����[���͔ޏ��ɁA�u���͂��Ȃ�������ł��邱�Ƃ�m���Ă���B����������������Ȃ��́A���������邱�Ƃ��w�Ԃ��낤�v�ƌ����B�����ăW�����[�����t�����`�F�X�R�̖���_���Ă��邱�Ƃ��킩�����̂ŁA�t�B�A���b�^�͒����ȃ��[�A�l�������̂����āA�ޏ��ƈꏏ�ɃW�����[������Ȃɂ����A�ł�h�������ŎE�����Ɗ�Ă�B�����W�����[���͂��̉A�d�����j��A�t�����`�F�X�R���ł�h�������̋]���ɂȂ�悤�ɁA���Ƃ��^�ԁB�@�Ñ㒆���ʼn��������O�̂낤�����̕���ł́A�ޏ��͖��p�t�A�q�̖��e�B�A�I�`�F���ł���B�����ď���̃������ɗ����Ă���B���p�t���{��ł��̖��p�����������A�c��̓e�B�A�I�`�F���ɋ����������B�������D�������Ă��A�͐s���ł��A�ޏ��͉����Ȃ��B�c���{�点���e�B�A�I�`�F���́A�Ƃ��Ƃ��������Ƌ��ɏۂɏ���ē����o���B�c��̔h�������R���͂������ǂ����Ȃ��B�����ōc��́A�A�q�����������@�̔n���|�p�Ƃɗ^���A�����ɂ�����炸�ޏ���A��A��悤������B �@���_�̊�������|�p�Ƃ͓V����삯�A��u�ɂ��ē�l�ɒǂ����B�����Ńe�B�A�I�`�F���͕�����K�������p���g���Ē����ɕϐg���A���������Ղɕς���B�|�p�Ƃ͌Ղ�|���B�����̖j���猌�̗܂������B�������ĎO�{�̂낤�����̉͏����Ă��܂��B �@�������ǂ����Ă����l�����Ԃ������ޏ��́A������x���_�̎��߂����肷��B�����Ŏ��_�͔ޏ��ɍŌ�̋@���^����B�����ޏ������̐l�Ԃ̖��������Ă�����A���Ŕޏ��̗��l�̖���Ԃ��Ă�낤�Ƃ����̂ł���B�����ő��̊Ԃ̖����I���B �@�V��t���ޏ��̌�����Ŕt�������ƒD�������Ă��܂��B�����Ĕނ͎����͂����l���ɉ}���ʂĂĂ���ƌ������炷�B�����Ŋ�ޏ������Ȃ��̖������̗��l�̂��߂ɋ]���ɂ��Ă���Ȃ����Ɨ��ނƁA�ނ͓{���Ĕޏ���@���o���Ă��܂��B���ʂĂ���H���A�a�@�ɂ����ڂ�ڂ̘V�k�B���A�]���ɂȂ��Ă���Ȃ����Ɛq�˂�ƁA�܂��҂炾�ƒf��B �@���̎��a�@�ɉΎ����N����B���@���҂������Ă��܂��Ă���A�Ԃ�V����l���c����Ă��邱�Ƃ��킩��B��e�̔߂��݂ɑł��ꂽ�ޏ��́A���̒��ɔ�э���ł����B�ޏ����Ԃ�V������グ���u�ԁA���_���ʂ���L���āA���̖�����낤�Ƃ���B�������ޏ��͖�j��B�����̗��l�̖��������Ȃ��̂��~�߂āA�Ԃ�V�𑋂̊O�ɍ��������A��e�Ɏ�n���Ă��B�Ă������錚���̔R���オ��̐^�ŁA���_�͔ޏ��������l�̂Ƃ���֓����Ă����B�����ē�l�𐫂̗̉��̏�։������B �y����z1921�N10��7���ɁA�x�������̉f��فuU.T.�N�[�A�t�����X�e���_���v�Ɓu���[�c�@���g�E�U�[���v�ŕ���ꂽ�A���́u���͎���苭�����ǂ����ɂ��Ă̕���v�́A�f���Ƃ����V�炵���}�̂�ʂ��āA�_�b�ƒʑ��I�n���h�����O�����̂����A����\���Ƃ͈قȂ�ʑ��Ɂu����̐_�b�v���N�����f�悾����( �N��L45)�B�����Ă���̓t���b�c�E�����O���A�T�C�����g����̃h�C�c�f��E���\����ē̈�l�Ƃ��Ă̖������m������̂ɁA����I�ȈӖ����������ŏ��̍�i�������B�����ɂ̓��}���e�B�b�N�ȋC���Ɠ����ɁA�h���ς��x�z���Ă���B���̗��`���̂��߂ɁA��ʂɂ͂��̉f��̌����́A�r�E�N���J�E�A�[���͂��߁A�����̐l�X�ɂ���āA�u�i���Ɉ�ƂȂ�����l�̍��́A�ԍ炭�u���z���ď��V���čs���v�Ɖ��߂���Ă���B�t���b�c�E�����O�̉f���̗͂́A�܂��ɂ����������`�I���߂������A���r���@�����X�̒��ɂ���B���łɁu��ꂽ���_�v�Ƃ������薼���A�C���j�J���ł���B�l�Ԃ̉^�������ɂ���Ē��f����Ƃ�����ڂɁu��ꂽ�v���_�́A��l�̗��l��V���Ō����邱�Ƃɂ����̂��A����Ƃ�����������ڂ�������āA�Ȃ����̖�ɉ�������̂��A�ǂ���Ȃ̂��낤���H �@�t���b�c�E�����O�͑�ꎟ���E���ɏ��Z�Ƃ��ďo�����A�������Ė��a�@�ŁA�����ς玀���������V�i���I�������n�߂��B���������̌�������������̒���Ƃ����̑������������̂́A���a��`�I�E�\����`�I�Ȑ⋩�������B�������t���b�c�E�����O�͍ŏ�����t���b�c�E�����O�������B�ނ͉f������Ƃ́A��̐_�b����邱�Ƃ��Ƃ��������Ƃ�m���Ă����B�V�炵�����o���͔ނ̏ꍇ�A�Â��_�b�w�̒��ɓ��荞�݁A���ꂻ�v�V����͂�^�����B �@�ނ͂����Ǝ��Ə����̖��������Ă����B�܂�w���ł̒J�x�́A������ꎟ���E���̑O���̌��ɂ���āA�˔@�Ƃ��ďo���オ������i�ł͂Ȃ��B���t�@�G���������̃}�h���i����͍����āA���܂��܂ȉ摜���c�����悤�ɁA�t���b�c�E�����O�������̃e�[�}�����܂��܂ɓW�J����v���Z�X��H���Ă����̂ł���B��ꎟ���E���̌o���́A����߂ĒP���������e�[�}�̏����̎d�����Aꡂ��ɖL�ɂ���̂ɖ𗧂����B����䂦���̉f������l������̂ɂ��Ă���̂́A��{�I�ɂ͓����u���Ɖ����v�̃e�[�}�ł͂Ȃ��āA���I�ȉf���ɂ���Ċ��N�����C���̑��l�ȐF���ł���B���C�X�E�u�j���G���́A�t���b�c�E�����O�́w���ł̒J�x���ނɑ��āA�f��̎��I�\���͂ւ̖ڂ��J�����Ă��ꂽ�ƁA�q�ׂĂ���B�w���x���g�E�C�G�[�����O�́A�t���b�c�E�����O�͂��̉f��ɂ���āA�f��̂��߂ɝR��I�o���[�h�Ƃ����W�������������Əq�ׂ��B���̉f��̏h���ς𐭎��I���S�ɒʂ�����̂Ƃ����r�E�N���J�E�A�[�ł����A�u�w���ł̒J�x�̔�g�I�\�����ۂ������������͂́A���ׂĂ��ړ��ł��Ȃ���̃J�����ŏ������˂Ȃ炸�A����ɖ�ԎB�e�͂܂��s�\���������Ƃ��l����ƁA���ꂾ����w���Q�ɒl����B�����̉f���̃��B�W�����́A����߂Đ��m�Ȃ̂ŁA���Ƃ��āA���݂̂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������o���N��������قǂł���B�w�h��������ꂽ�X�P�b�`�x�Ƃ������ׂ��x�j�X�̃G�s�\�[�h�́A�����ȃ��l�T���X���_��h�点�A�Ⴆ�A�J�[�j���@���̍s���X�^���_�[����j�[�`�F���́A�P�������c�E�ȓ썑�̏�M�U����A�₩�ȓ��{�̏�ʂ�ʂ��āA����������Ă����B�����̃G�s�\�[�h�ɂ́A�܂��s�v�c�ȗ���Ƃ����Ă���B�_�O���X�E�t�F�A�o���N�X���A���̏�ʂ̖��@�̔n��A�����p�b�g�̌R�������O�~�Ɏh������āA�����悤�Ȗ��@�̃g���b�N���g�����X�y�N�^�N���E���r���[�w�o�O�_�b�h�̓����x����������Ƃ́A�悭�m���Ă���v�Ə^���Ă���B�G�s�\�[�h�����ł͂Ȃ��A�{�̃n���h�����O���A����߂Ĉ�ۓI�ł���B�h�C�c�̏����Ȓ��̌Õ��Ȃ������܂��Ǝ��_�̊ق̏d�X�������͋C�A�����ĉ������A���̋���ȕǂ̈��|�I�Ȕ��́B���̓_�ł́w�J���K���x�̃Z�b�g����������@���^�[�E���[���q�A�w���}���E���@�����A���[�x���g�E�w�����g�̃g���I�̎�ɐ���Z�b�g�̐▭�Ȍ���̌��ʂ��A�傫�ȈЗ͂����Ă���B�ނ�͂����ł��w�J���K���x�̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA�����ꂽ�d���������ƌ�����B �@�f������ې[���̂ɔ�ׂāA�f�悪�������Ă���_�b�w�̂ق��́A�͂Ȃ͂��B���ł���B�h�C�c�I�ȏh���ςƔ��R�Ƃ����J�g���b�N�I�_���`�̍����́A�`����w�Ƃ��Ă͒ʑ��I�ł���B�������t���b�c�E�����O�ƃe�A�E�t�H���E�n���u�D�v�Ȃ̌l�I���ȂƂ������ׂ��A���������ʑ��I�_�b�w�́A�͂Ȃ͂��������Ȃ��̂ł���ɂ�������炸�A�f������Ƃ��Ă͂����������ʓI�������B�f���\���͏�������y���Ƃ͈�����_�b�����z�I�Ȕ��������B�W�����ɕϗe���邱�Ƃɐ��������̂ł���B �y�G�s�\�[�h�z�t���b�c�E�����O�̓��F�B�ނ͉f����ē���̂ł͂Ȃ��B�ނ͐V�炵�����E��n������̂ł���B����ɂ͋���������B���̂�����H���̂͑�|����ȃZ�b�g�ł͂Ȃ��A�ʂĂ����Ȃ��������ƁA�ʂĂ����Ȃ��O����Ɏd������t���b�c�E�����O�ł���B�ނ͈�̃V�[����10��A���邢��20����B�e����B���������������ނ̋C�ɓ���Ȃ��B���ׂĂ͂����Ɨǂ��A�����Ɗ��S�Ȃ��̂ɂł���͂����B�ނ̋��͎҂����́A�����ɍ��܂������ɂȂ�B�������ނ�͉A�ň����������Ă��A��͂�t���b�c�E�����O�ɋ��Q���Ă���̂��B�ނ͓Ɠ��̐l�Ԃł���B�ނ͑��̊ē����Ƃ͂܂�ň���Ă���B�ނ̓G�����X�g�E���r�b�`���̂悤�ɉ����o�g�ł͂Ȃ��B�ނ̓W���[�E�}�C�̂悤�ɁA�����ɂ͋������Ȃ��B�ނ͎����̌��z�ɐ����𐁂��������Ƃ���B�������ނ��z�����Ă�����̂ƈ���Ă͂Ȃ�Ȃ��B �@�ނ͜߂���Ă���B�ނ͑Ë����Ȃ��B�����ׂ����Ƃ́A�ނ�����̎�舵����S���Ă��邱�Ƃł���B�l�Ԃ��ˑR�������ꂽ��A���肪����Ζ�������o���ꂽ�肷��l�q�B��̃x�j�X���o�Ă���l�q�\�\�����ȘH�n�A���邢�͉^�͂̎G�����f���o�����Ƃɂ���Ăł͂Ȃ��B���r�b�`���ł������������������Ȃ��B����ƂăT���E�}���R�L������������邱�Ƃɂ���Ăł͂Ȃ��B�W���[�E�}�C�������炻��������������Ȃ��H�@�����ł͂Ȃ��A���ɒ��ސ��i�̐Βi�ɂ���Ăł���B��{�̂��܂��^�͂̒��ɏ����Ă����S���h���ɂ���Ăł���B �@�t���b�c�E�����O�͖���Q���ɍl�����g���b�N���g�����A����͂̂��ɏ펯�ƂȂ�B�Ⴆ�A�����ł̃G�s�\�[�h�̒��ɁA���l�����̓�����ʂ�����B���l�����͏ۂɏ���ē����悤�Ƃ���B�c��͎ˎ�ɁA�ނ�ɒǂ����Ɩ�����B�ˎ�͔n�ɏ��A�_��˂������đ���B�����Ď��̖�j���h���т��c�c�B���ׂĂ����������Ƃ́A�����͐V�炵���A�Z���Z�[�V���i���������B�������t���b�c�E�����O�ɂƂ��āA�Z���Z�[�V���i���Ȍ��ʂ������邱�Ƃ́A�܂��������ł͂Ȃ��B�ނ͉���]��ł���̂��H�@�ނ͍ő�ɂ��čō��ْ̋��x�̂���X�g�[���[����肽���̂ł���B�ނ͎����̓o��l���������A�X�N���[�����z���Ċϋq�̒��֓����čs���̂�]��ł���B�ނ͔ނ炪�ϋq�̐S���A�������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�قǑ����Ă��܂����Ƃ�]��ł���B�w�J���K�����m�x�Ɠ��l�A�剉���D�͍Ăє����������E�_�[�S���@�[�ł���B���_��������̂́A�o�D�x�����n���g�E�Q�c�P�ł���B�ނ͂���Ȍ�A�t���b�c�E�����O�f��ɂ͕K���o������悤�ɂȂ�B �@���̉f��̓x�������ŕ���ꂽ�Ƃ��ɂ́A����قǐ����͂��Ȃ��B����x�������̐V���̔�]�̌��o���ɞH���A�u�ދ��Ȏ��_�I�v�B�p���ł͂�����̉f��̓Z���Z�[�V�����ɂȂ�B�u�^�Ƀh�C�c�I�v�ƁA�p���̔�]�Ƃ����͕]����[�[�܂�A�u�[���v�Łu�|�p�I�v���Ƃ����̂��B��������ƃh�C�c�ł���������B���̐����͉��N���̊ԑ����B33�N��1954�N�ɁA���̉f��̓x�������́u�f���t�H�C�p���X�g�v�ł�����x��f�����B�e�A�E�t�H���E�n���u�D���O�u����b���B�f��ق�����Ƃ��A�ޏ��͑������点��B������A�ޏ��͎q�̓]�|�������Ŏ��ʁB���ꂪ�A�u��ꂽ���_�v���������A�傢�ɘ_�c���Ăf��̖{���̏I��肾�����B 1921.10.20�i���{����1923.6.29�j �w���̃l���]�� Lady Hamilton�x ���q�����g�E�I�Y���@���g�ēA�V�i���I�F���q�����g�E�I�Y���@���g�i�n�C�����q�E�t�H�����[�g�E�V���[�}�b�n�[�̏����ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�z�t�}�� �y�L���X�g�z���A�[�l�E�n�C�g�A�R�����[�g�E�t�@�C�g�A���F���i�[�E�N���E�X�A���C���z���g�E�V�����c�F�� �y����z�p���C�R�̉p�Y�l���\���̈��l�̕���A�ޏ��̓l���]���̎���Ђǂ������Ɋׂ�B 1921.10.22 �w�C���h�̕�W Das indische Grabmal�x �W���[�E�}�C�ēA�V�i���I�A�e�A�E�t�H���E�n���u�A�t���b�c�E�����O�A�B�e�F���F���i�[�E�u�����f�X �y�L���X�g�z�I�[���t�E�t�F���X�A�~�A�E�}�C�A�R�����[�g�E�t�@�C�g�A�G���i�E�����i�A���A�E�f�E�v�e�B �y����z���j�������^���ȃG�L�]�V�Y���̖`���f��B�x�������̃��H���^�[�X�h���t�Ƀ}�C�͐_�a�s�s�����݂������B2000�Ȃ���2400���}���N�����̃X�y�N�^�N���f��̂��߂ɔ�₳�ꂽ�ƌ����Ă���B��ꕔ�w���K�s�҂̎g�� Die Sendung des Yoghi�x�̓x�������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŕ���B��w�G�V���i�v�[���̌� Der Tiger von Eschanapur�x��11��19���ɁA�u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŕ���B 1921.10.21 �w�g���O�X�\�\�Ό� Verlogene Moral (Brandherd)�x �n���X�E�R�[�x�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[�i����Â��A�C�X�����h�̃o���[�h�ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�t���C���g�A���u�F���[�x���g�E�l�p�b�n �y�L���X�g�z�I�C�Q���E�N���b�p�[�i�����E�l�g���O�X�j�A�w���~�[�l�E�V���g���X�}�������B�b�g�i�Y�k�O���A�[�F�ނ̕�e�j�A�A�f�[���E�U���g���b�N�i�~�X�E�g�D�[���h�F���َ�j�A�Q���g�E�t���b�P�i�����F�ޏ��̉��j�A�t�F���f�B�i���g�E�O���[�S���i�N�i���E�G�b�Q���g�F�ނ̌㌩�l�j�A�P�[�e�E���q�^�[�i�O�[�h���[���F�ނ̖��j�A�}���[���E���C�R�i�A���i�F�����j�A�v�E�n�����i�N���X�`�����F�Ǘ��l�j �y���炷���z�A�C�������h�̂���_��̋���ȐՌp�������́A�ӎu�̋����f��̃~�X�E�g�D�[���h�Ɉ�Ă���B�ނ͏����̃A���i�������Ă���A�ޏ��͔ނ̎q���݂������Ă���B�~�X�E�g�D�[���h�̓A���i��ǂ��o���B�����ă����͊w�Z�֍s�������B�A���i�͊����E�l�g���O�X�Ɣނ̕�e�ŎY�k�̃O���A�[�̂Ƃ���ɁA����������B�����͔ނ̌㌩�l�̖��O�[�h���[���Ɩ����������������B�A���i�͎q�����Y�ނ��A�~�X�E�g�D�[���h�̓����̑���ɁA��������Ă����Ȃ̂ŁA�ޏ�����q�����グ��B�A���i�̓�������̕ւ��҂��Ă��邪�A���ʂł���B�����̂��߂̍��炪�n�܂����Ƃ��A�A���i�͏d���Y��M�ŐQ�Ă���B�g���O�X�̓A���i��������悤�ɂȂ��Ă���A�ޏ��̍Ō�̎��ɁA���ɂ��Ă��B�g���O�X�͎��A���i���A��������։^�ԁB�����͑����݂ɋ���ďf��ɒ��т�����A�ޏ����i�ߎE���B �y��i�]�z�u�f�A�E�t�B�����v���A1921�N��11���\�\�w�Ό��x�u�c�F���^�E���f��v�̐V�����T�����̔_�����́A���i�Ȍ|�p��i�ƒʑ��I�Ȍ��ʂƂ̊ԂŁA���f����낤�Ǝ��݂āA�������Ă���B�n���ȐE�l�������������ɓ���āA���蕨�Ƃ��Ĕ_�ꑊ���l�̌������̏�ɉ^�ԂƂ����A�n���h�����O�̃N���C�}�b�N�X�́A�^�����Ȃ�������ۂ��c�����A����ɂ�������炸���̉f��́A�ϋq�Ɋ�ɔ߂���������������B�f��̂��т����P��̉��ŁA�����Ă����Ȃ����ƌ������A����O�ɂ��Ă͂��߂āA�������ꂵ�߂��f����i�ߎE�����̔_�ꑊ���l�A������j�ƕʂꂳ�����Ă��A�����̎q��������邱�Ƃ����ޏ����A�ނ�݂͂�ȁA�ؒ���̂��т��������������鋭�łȐ��i�ɂ���āA���ʂ����Ă���B �@�n���X�E�R�[�x�̉��o���A��̂ɂ����Ă��̃X�^�C�����������Ă���B����������Ɠ����ɁA�����\����`�I�ȗ]�C�������Ă͂��Ă��A�K��������l�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���Z�͑S�̂Ƃ��čŌ�܂ł��炵�������B�������̃}���[���E���C�R�́A�n�߂̂����̓V�i���I�����߂Ă���قǂɂ́A�K�������l�̐S�𖾂邭���鉉�Z�͂��Ă��Ȃ��B�_�ꑊ���l�̖��n�ȏ��N�炵�����A�Q���g�E�t���b�P�͕��тł����Z�ł��A���炵���\�����Ă����B�A�f�[���E�U���g���b�N�A�t�F���f�B�i���g�E�O���[�S���A�I�C�Q���E�N���b�p�[�́A�ނ�̉�����l�����ɁA�Ǝ��̐�����^�����B��ʂ͊T���ėǍD�ł��邪�A�Ɩ����ʂ̏����̌��ׂ��A�����I�ȉf���̏ꍇ�ɂ́A��Q�ƂȂ��Ă���BA�EF�B 1921.12.11 �w����q�\�\�������f�� Hintertreppe--Ein Film-Kammer-Spiel�x ���I�|���g�E�C�G�X�i�[ Leopold Jessner�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[�A�B�e�F�J�[���E�n�b�Z���}���A�Z�b�g�\���Ɣ��p�F�p�E���E���[�j�A����F�t�����A�f��ƃw�j�[�E�|���e���f�� Henny-Porten-Film �y�L���X�g�z�w�j�[�E�|���e�� Henny Porten�i�����j�A���B���w�����E�f�B�[�e���� Wilhelm Dieterle�i�ޏ��̍���ҁj�A�t���b�c�E�R���g�i�[ Fritz Kortner�i�X�֔z�B�j�B �y���炷���z���钆�Y�K���̉ƒ�Ɍق��Ă��閺���A�l�v�Ƃ��ĊO���œ����Ă���{�[�C�E�t�����h�̎莆��҂��ł���Ă���B�����ޏ��͗X�֔z�B�ɐq�˂�B�ނ͂��̖��ɂЂ����ȏ�M������Ă���B�ނ͔ޏ��̔߂��݂�a�炰�邽�߂ɁA�ɂ��̎莆�����A�����l�v����̎莆�Ƃ��ēn���B���ӂ̋C��������ޏ��́A�|���`�����̂ڂ�ނ̒n���̏Z���Ɏ����čs���B��������̕\�̕��ł́A�ޏ��̎�l�̈�Ƃ��p�[�e�B���J���Ă���B�ޏ��͗X�֔z�B�������������Ă���̂������A�ӂ����Ĕނ��炻�̎������グ��B�M�Ղ���ޏ��́A���ꂪ����������莆�̏����肾�Ƃ������Ƃ�m��B����܂ł̎莆���������̂́A�ޏ��̃{�[�C�E�t�����h�ł͂Ȃ��B�X�֔z�B���ޏ��ւ̈����A�����̎莆���U�������̂��Ƃ������Ƃ��A�ޏ��ɂ킩��B���̂Ă�ꂽ�C�����Ŕޏ��́A�܂��ޏ��̂��Ƃ��C�Ɋ|���Ă����B��̐l�ԂɐS�������A�[�H�̏��҂������B�������s���s���̒j�̎v���ł̂ق����A�����Ƌ����B�S���d���ޏ��́A�X�֔z�B�̂Ƃ��������B�ʂ�Ō��m��ʒj���҂��Ă���B����͔ޏ��̃{�[�C�E�t�����h���Ƃ킩��B�ނ͔ޏ��ɂ����莆���������ƁA�����Ēf������B�X�֔z�B���莆������肵���̂ɈႢ�Ȃ��B�l�v�͗X�֔z�B��Nj�����B���̓h�A�̂Ƃ���ɖ߂��čs���A���_�𗧂���������B�ޏ��͏������ĂԁB�X�֔z�B�͐l�v���A�蕀�őł��E���Ă��܂����B�ߏ��̐l�X���h�A��j��J���āA�l�v�͎��ɁA�X�֔z�B�͋������ڂ������āA�܂������������܂���z�������Ă���̂����߂�B��l��Ƃ̓X�L�����_�����ƁA�����Ƃ���ǂ��o���B�ޏ��͍D��̊፷���������Ă���l�X�̑���ʂ�߂��āA�K�i������Ă����A�Ƃ̉�������[�����g�𓊂���B �y����z����͋r�{�ƃJ�[���E�}�C���[�́u�������f��v�O����A�w�j�Ёx�A�w����q�x�A�w����̔ߌ��x�̐^�Ɉʒu�����i�ŁA�h�C�c�E�T�C�����g�f��̃X�^�[�A�|���e���剉�̌���ł���ɂ�������炸�A�����̔�]�͔ے�I�������B����ꂽ�̂�1921�N12��11���ł��邪�A����ɂ��ăN���g�E�s���g�D�X�́A�u�^�[�Q�u�[�t�v����ŁA���������Ă���B�u���̓��t�̓h�C�c�f��j�Ɏ�M�ŏ������܂��ł��낤�B���Ƃɂ��Ƃ��̉f��́A�܂����N����������������Ȃ��B����͎O�l�����o�ꂹ���A��s�s�̉ƂƂ���������̏ꏊ���������Ȃ��f��ł���B�����������łȂ��A��_�ȍ�i�ł���B��ƁA�o�D�A��Ƃ����ĉ��y�Ƃ��A�f��ɂ����Ă���قǗF���������ĘA�т������Ƃ��A���Ă��������ǂ����A�킩��ʂقǂł���B����܂ʼnf��Ō������ł����Ƃ��l�ԓI�ȉf��B�C�G�X�i�[�͂���܂ł̂ǂ�ȉf��ē��ȏ�ɁA�w�j�[�E�|���e�����g�����Ȃ����B���̈��������ւ̊�]��Ƌ��̐�]��\�����Ă���ޏ��̗�����|���́A����߂ė͋����g�U��\���̗͂���Ă���B�������҈ꗥ���͏��������A���ׂĂ̓��������C�Ɉ��Ă���B�X�֔z�B��������̂̓R���g�i�[���ł���B�܂������������Ƃ��������B���̊ɖ����͍��}�Ɏ��Ă���B���ӂ���A�����̂��Ă��邱�Ƃ͈Ӗ��[�����Ƃ��B�C�G�X�i�[�͌����ɐ����𐁂����B�\����`�H�@�ہA�S����`�B�p�E���E���[�j�̃Z�b�g�̗���͌��z�I�ɍ���A�Ƃ炵�o����Ă��āA�l�C���Ȃ��A�߈��ɖ����A�J�̒��Ɍ��̂Ă��Ă���B�S���̍D��S�ɖ��������͉B��Ă��邪�A�ˑR�Nj��҂̕S���̓��Ő�߂���B�ǂ����̂���������Ȃ�A���̉f��͐��E���ɍL�܂�ɈႢ�Ȃ��B����͗A�o�����ɍ��ꂽ����ł͂Ȃ��A���_�[�X�̐l�X�̌��g�I�ȋ�����Ƃ�����ł���v�B �@���̉f�����������I�|���g�E�C�G�X�i�[�́A�����x�������̍�������̊ēƂ��āA�����̏ꍇ�t���b�c�E�R���g�i�[������Ƃ��āA�ÓT��\����`���ɑ�_�ȉ��o�����邱�ƂŁA�����j��ɋP���������Ղ��c���������l�ł���B���̉f��͂��������o�������C�G�X�i�[���A����o�������č�����ŏ��̉f��ł���B�������ނ͑��ɂ͂P�X�Q�R�N�ɁA�A�X�^�E�j�[���[�����g���āA���@�[�f�L���g�̋Y�Ȃ��J�[���E�}�C���[���r�F�����w�n��x������������Ȃ̂ŁA�ނ̉f��Ƃ��Ė��ɂ����̂́A���́w����q�x�����ł���B�����Ĕނ́A�J�[���E�}�C���[�ɂ��\����`�I�ȃV�i���I�����o�������A�����̂���]�Ƃ̒��ڂ��������̂́A���̉f�悪�\����`�I�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ������B�Ⴆ�A���t���[�g�E�P���́u�x�����i�[�E�^�[�Q�u���b�g�v����ŁA�u���̉f��͕\����`�Ƃȉ��̊W���Ȃ��B�ނ���S���I�ɓ��O��������ł���v�ƁA�^�����B�t���I�Ɍ����A���̉f��͕\����`�����ɂ͍l���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A��\����`�I��i�ł���B���h���t�E�N���c�ɂƂ��ẮA�����20�N��O���̒��ڂɒl���邷�ׂẴh�C�c�f��́A���ʂ̓����ł���B�ނ́w�\����`�Ɖf��x�̒��ŁA���������Ă���B�u�ē����R�����y���z�����u���������Ă���Ƃ���ł́A�ǂ��łł��\����`�I�v�f���w�E���邱�Ƃ��ł���B�C�G�X�i�[�́w����q�x�ɂ́A�����ł̓�l�����̗����̏u�Ԃ������V�[��������B�Z�b�g�͊m���ɕ\����`�ł͂Ȃ��B����������͕\����`�����ɂ͍l�����Ȃ��B�f����Ԃ𖬗��̂Ȃ��A����C�܂܂Ȗʂɕ������Ă������̔z���̎d���́A���̗R����ے肵�Ă��Ȃ��B�����ăC�G�X�i�[�͉��o�ɂ����āA�\����`�I�ȏ�i�\���̏��`�����f��Ɉڂ��悤�ȉ��o�̎d�����A�ڂɌ�������̂ɂ��悤�Ƃ����B�g�U��̐S���I�\���͐�߂��āA�͋����A�ߖꂽ�d���ƂȂ��Ă���B�ނ͂��ׂĂ����S�ɋ����������ɁA�����I�Ɏd�������Ă���v�B �y�f��]�z���u�f�A�E�t�B�����v���A1921�N��51���\�\�u���I�|���g�E�C�G�X�i�[�̂��̍ŏ��̉f��́A�����̕���Ŕނ̗͂̂����������o�����Ă����l�X�݂�Ȃ��A���������Ƒ҂��Ă������̂ł���B�r�{�Ƃ̃J�[���E�}�C���[���g���A������u�������v�ƌĂ�ł���B�S�̂Ƃ��Ă͂����������́A�����킴�Ƃ炵���X�^�C���ɒ��q�����킹�Ă��邱�̉f��́A���������܁A���Ȃ�ʂ��������l�������ꂽ���̂���Ƃ�Ă���Ƃ��ɁA��ɐl�̂�����𑨂���c�c�B�C�G�X�i�[�̉��o�ɂ���āA�S�̂������ŁA�������痣��A��ɍ��߂�ꂽ�̈�ɉ^�э��܂��B�Z�b�g��C�Ƃ��Ẵp�E���E���[�j�́A���`�I�ȍ\�}�ƃ^�b�`�̈�i����肾�����B�����̖������̂��A���������܂����ے���p�����ɉʂ����Ă���A�Ɠ��̈Ӗ��������������͒��ڂɒl����B�ڊo�܂����v�A��A�Ăї�̂Ђ��B�䏊�̓���I�Ȏd���܂ł��A�f����⍲������̂ƂȂĂ���B �@�z���F�������̃w�j�[�E�|���e���A�X�֔z�B�̖��̓t���b�c�E�R���g�i�[�A�l�v���̓��B���w�����E�f�B�[�e�����B�����̉��Z�̓|���e���̐��n�����\�͂̂��ׂĂ̖��͂������Ă��邪�A��������т��đS�͂��X���Ă���킯�ł͂Ȃ��B�t���b�c�E�R���g�i�[�͔ނ̖��́A���������悤�ɒ��ݍ���ł����������A���ܔY�܂����قǍd�����������ɂ܂ŃG�X�J���[�g������B�f�B�[�e�����͂��܂�d�����Ȃ��Ă��Ȃ��B���ł̂悤�ɃU�b�Ƙe�����������鈵�����́A�Ⴆ�Έ�̃V�[���ŁA�h�A�̃K���X�z���Ɍ����邨�q�������A�s���K���̂悻�悻�������A�s�C���Ȃ܂ł̐��m���ŏ������鈵�����c�c�v�B ���N���J�E�A�[�w�J���K������q�g���[�ցx�i1958�j�\�\�u�c�c�J�[���E�}�C���[�̉f��ł́A�S���̓������ɒ[�ɒP��������āA���肠��ƕ����яオ���Ă���B���ꂼ�ꂠ�����Ȗ{�\��̌����Ă��鐔�l�̓o��l�����A�����ɍ\�����ꂽ�̉^�т̒��֑g�ݍ��܂�Ă���B�O���̔�]�Ƃ����́A���̒P������s���R�ŕn�ゾ�Ɣᔻ�������A�h�C�c�̔�]�Ƃ����̑����́A�����ԍ��؉f�����h���������āA�����������Ă����̂ŁA�����̉f����A�l�Ԃ̍��̐[�����̂��̂������Ă����u�������v�ł���Ə^�����c�c�v�B |
|
| 1922 | |
| 1922 �w��i1O pus 1�x ���@���^�[�E���b�g�}���ē� �y����z�����g�Q���ʐ^��z�킹����_�̃_�C�i�~�b�N�Ȕz��ɂ�钊�ۉf��B 1922�i���{����1923.10.12�j �w�V�������[���� Der Graf von Charolais�x �y����z�N���J�E�A�[p112 1922.1.31�i���{����F���A��1928.5.18�j �w���C���ߜƋ� Fridericus Rex�i�t���f���[�N�X�E���b�N�X�j�x �A���c�F���E�t�H���E�`�F���s�[�ēA�V�i���I�F�n���X�E�x�[�����g�A�A���c�F���E�t�H���E�`�F���s�[�i���@���^�[�E�t�H���E���[���̏����w�t���f���[�N�X�x�ɂ��j�A�B�e�F�O�C�h�E�[�[�o�[�A�G�����X�g�E�����g�Q���X �y�L���X�g�z�I�b�g�[�E�Q�r���[���剉 �y����z�t���[�h���q�剤�̐��U���f�扻�����ʑ��f��A�x�������ŕ����A�s��Ɗv���E���v���̗]�o�������Ԃ��Ă��钆�ł̃v���C�Z���]���̉f����߂����Ę_���͌������A�\�͍����ɂ܂łȂ����B�E���͌N�吧�ւ̎]�̂Ɋ��Ă����B��O���E��l�������1923�N3��31���B 1922.2.2�i���{����1922.11.3�j �w���ݗߏ�@Fräulein Julie�x �t�F�[���N�X�E�o�b�V���ēA�V�i���I�F�}�b�N�X�E�����N�A�����E�X�E�E���M�X�i�A�E�O�X�g�E�X�g�����h�x���Ƀh���}�ɂ��j�A�B�e�F�����E�X�E�o���e�B�q�A���u�F���[�x���g�E�w�����g�A���@���^�[�E���[���q �y�L���X�g�z�A�X�^�E�j�[���[���i�W�����[�j�A���B���w�����E�f�B�[�e�����i�W�����j�A�A���m���g�E�R���t�i���݁j�A���[�i�E���b�Z���i���ݕv�l�j�A�P�[�e�E�h���V���A�I�[���t�E�V���g�����A�G�����X�g�E�O���[�i�E�A�Q�I���N�E�V���l���B �y���炷���z�߂��Ⴍ����ɂȂ����������琶�܂ꂽ�W�����[�́A��̔��ݕv�l�ɂ���āA�j�̎q�̂悤�Ɉ�Ă���B�������l�Ƃ̌����Ŏ��]�����o������A���ݕv�l�͖��ɁA�����Ēj�̓z�ꏗ�ɂ͂Ȃ�Ȃ����Ƃ𐾂킹��B���ꂩ��ޏ��͊قɉ����A���̒��ŏĎ�����B�W�����[�͂��̌�A�R��������ق���ޏ����~���o���Ă��ꂽ���g���̃W�����ɍ��ꍞ�ށB�ނ͔ޏ���U�f���A���ꂩ��c���Ȑl���ɕϐg����B�W�����[�͓������J���āA�����@����B�i�N���J�E�A�[p108�j 1922.2.21�i���{����1923.5.18�j �w�t�@���I�̗� Das Weib des Pharao�x �G�����X�g�E���r�b�`���ēA�V�i���I�F�m���x���g�E�t�@���N�A�n���X�E�N���[���A�B�e�F�e�I�h�[���E�V���p�[���N�[���A�A���t���[�g�E�n���[���A���u�F�G�����X�g�E�V���e�����A�A���E�t�[�x���g�A�G���l�E���b�c�i�[�A���y�F�G�h�D�A���g�E�L���l�b�P �y�L���X�g�z�G�~�[���E���j���O�X�i�t�@���I�F�A���l�X�j�A�A���x���g�E�o�b�T�[�}���i�]�[�e�B�X�j�A�n���[�E���[�g�P�i�����t�B�X�j�A�p�E���E���F�[�Q�i�[�i�U�����N�j�A�_�O�j�[�E�[�����F�X�i�e�I�j�X�j�A�����_�E�U�����m���@�i�}�P�_�j�A�t���[�h���q�E�L���[�l�i�Վi���j�A�p�E���E�r�[���X�t�F���g�i���m���j�A�G���U�E���@�[�O�i�[�A�}�f�B�[�E�N���X�`�����X �y���炷���z�i�G�W�v�g�A�G�`�I�s�A�A�k�r�A�ƃM���V���Ƃ̊Ԃ̐푈�ƕ��a�j�B �@�G�`�I�s�A�̉��U�����N�́A�G�W�v�g�̃t�@���I�̃A���l�X�������K�₵�A�����������Ă��A���̃}�P�_��܂Ƃ��Ē��邱�Ƃ�\���o��B�}�P�_�̏����g���ŃM���V���l�̃e�I�j�X�́A�G�W�v�g�̐_�a�q���z�Z�t�]�[�e�B�X�̑��q�̃����t�B�X�ɗ����Ă���B�����ă����t�B�X���x�������ɂ�������炸�A��Ђ����ɁA���������ċւ����Ă���ɂɔE�э��ށB��l�͕߂炦��āA�t�@���I�̑O�Ɉ����o�����B����ƃt�@���I�͍����G�`�I�s�A���痈���ԉł�Y��āA���������e�I�j�X���Ȃɂ������Ɩ]�ށB�e�I�j�X�̓����t�B�X�̖����~�����߂ɁA��������m������Ȃ��B�ޏ��̓G�W�v�g�̉��܂ƂȂ�B�G�`�I�s�A�̉��U�����N�͕��J���ꂽ�Ɗ����A�G�W�v�g�ɐ��z������B�A���l�X�͐��ɕ����O�ɁA�����t�B�X�ւ̑z������A�ނɉi���̒�߂𐾂����Ƃ��Ȃ��e�I�j�X���A�ɂɕ����߂�����B�����Ă�����l�ɂւ̔閧�̒ʘH��m���Ă��錚�z�Z�t�]�[�e�B�X�̊�����蔲������B �@�G�`�I�s�A�ƃG�W�v�g�̌R���͍����ő�������B�G�W�v�g�R�͑ł��j���A�����o������Ȃ��B�t�@���I�̃A���l�X�͐펀�����ƍ�������B�s�k�����G�W�v�g�R�������t�B�X���đg�D���A�G�`�I�s�A�R�ɏ�������B�����ĖӖڂɂ��ꂽ���e�ɂ���āA�����߂�ꂽ���l�e�I�j�X�̂Ƃ���֓������B�A���l�X��\�N�Ƃ��đ���ł������O�̓����t�B�X�����Ă��Č}����B�e�I�j�X�͏����q�X����p�Y�����t�B�X���A�����̐V�����v�ł���A�G�W�v�g�l�̃t�@���I�ł���Ɛ錾����B�������퓬�ŕ������A���Ǝv���Ă����A���l�X���߂��ė���B�ނ͍ȂƉ��������Ԃ����Ƃ���B�����t�B�X�́A�A���l�X���e�I�j�X��f�O����Ȃ�A������f�O����ƌ����B�A���l�X�͂���������B���������]�������O�̓����t�B�X�ƃe�I�j�X��őł��E���B�A���l�X�̉������A�ނ������߂ɍ��܂���B 1922.2.23 �w���ꂽ�҂��� Die Gezeichneten�x �J�[���E�e�I�h�[���E�h���C���[�ēA�V�i���I�F�J�[���E�e�I�h�[���E�h���C���[�i�A�[�Q�E�}�[�f�����O�̏����ɂ��j�A�B�e�F�t���[�h���q�E���@�C���}�� �y�L���X�g�z�|���i�E�s�q�����X�J���A�E���f�B�[�~���E�K�C�_���t�A���n���l�X�E�}�C���[�A�g�����C�t�E���C�X �y����z�v���O�̃��V�A�ɂ����郆�_���l���Q�B�f���}�[�N�̃h���C���[�ē��h�C�c�̉f���Ђ̂��߂ɐ��삵���ŏ��̉f��B 1922.3.4 �w�m�X�t�F���g�D�[�E���|�̃V���t�H�j�[ Nosferatu--Eine Symphonie des Grauens �x �t���[�h���q�E���B���w�����E�����i�E F.W. Murnau�ēA�V�i���I�F�w�����b�N�E�K���[�� Henrik Galeen�i�u�����E�X�g�[�J�[����́w�z���S�h���L�����x(�n���������ɁA�������j�ɂ��j�A�B�e�F�t���b�c�E�A���m�[�E���@�[�O�i�[�A����F�f�[�N���E�r�I�X�R�[�v�� �y�L���X�g�z�}�b�N�X�E�V�����b�N�i�I�����b�N���݁\�\�m�X�t�F���g�D�j�A�O�X�^�t�E�t�H���E���@���Q���n�C�� Gustav von Wangenheim�i�g�[�}�X�E�t�b�^�[�j�A�O���^�E�V�����[�_�[�i�G�����A�ނ̍ȁj�A���[���E�S�b�g�E�g�i�o�����@�[�����j�A�O�X�^�t�E�{�b�c�i�W�[�t�@�[�X�F����j�A�A���N�T���_�[�E�O���[�i�n�i�N�m�b�N�F�Ɖ��������j�A�Q�I���N�E�g�E�V���l���i�n�[�����O�j�A���[�g�E�����c�z�t�i�A�j�[�F�ނ̍ȁj�A���H���t�K���O�E�n�C���c�i���v�P�j�A�A���x���g�E���F�m�[���i���v�Q�j�A�M�h�E�w���c�t�F���g�i����j�A�n�[�f�B�E�t�H���E�t�����\���i�a�@�̈�t�j�B �y���炷���z�u���[�����ōȃG�����ƍK���Ȍ��������𑗂��Ă���t�b�^�[�́A���ς��ȉƉ��������N�m�b�N�̂Ƃ���̏]�ƈ��ł���B������A�ނ̓m�X�t�@���g�D�Ə̂����_��I�ȃI�����b�N���݂̂Ƃ���ցA�����_������Ԃ��߂ɔh�������B�u���Ȃ��͂���ő����̋����҂���B����ɂ͂�����X��J���v��c���X�̊��ƂЂ���Ƃ���Ə��X�̌����v�B�t�b�^�[�͊�ȋ����������邪�A���������Ǘ��̊�тɂ͏��ĂȂ��B�ނ͎Ⴂ�Ȃ����ʂ̗F�l�ɑ����āA���ɏo��B �@�������̓r���ł����t�b�^�[�́A��ȗH��̏o���ɏo��B�h�����V�����@�j�A�n���̏Z�������́A���̖��m�ȗ��s�҂ɁA�u���̍��v�ɗp�S����悤�x������B �@�x�b�h�Ŕނ͋z���S�ƗH��ɂ��Ă̖{��������B�ނ͂��̐��s��ǂށB���ꂩ����M���݂��n���������e������������B�����A�ނ͂��������̖{�𗷍s�J�o���ɂ��܂����ށB�h�̒���̌x���́A�ނɗ��̌p�����v���Ƃǂ܂点�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������̔��Ō�҂͂���ȏ��֍s�����Ƃ����ށB �@��ނ��t�b�^�[�����炭�k���ōs���ƁA��ȕ����̌�҂��ڂ�U����Ă��鍕���n�Ԃ��K�^�s�V�Ƃ���ė���B����ɏ��Ɣn�Ԃ͖җ�ȃX�s�[�h�ŃI�����b�N���݂̏�ɔނ��^��ōs���B��̖�͋����Ă���t�b�^�[�̊�O�ŁA�H��̎�ɂ���Ă̂悤�ɁA�S���ЂƂ�łɊJ���A�A�C�Ȕ��݂��ނ��o�}����B���݂̎p�͔n�Ԃ̌�҂Ǝ��Ă���B���ꂩ��ނ̓I�����b�N���݂̈��A���A���ĂȂ�����B�H���̂Ƃ��ނ��w���ƁA���݂͔ނ̌����z�����Ƃ���F�ނ̓m�X�t�F���g�D�A�z���S�������B �@���݂̓t�b�^�[�̍Ȃ̊G�����āA����ɏo�Ă���Ƃ����傤�ǃt�b�^�[�̉Ƃ̐^���������Ƃ������Ƃ�m��ƁA�S�O�����ɍw���̌_������ԁB���̖锌�݂��t�b�^�[�̕����ɗ��āA�ނ̎猌���z���B���̎��u���[�����̉Ƃɂ���Ȃ̃G�������A�����ɂ��Ȃ���Ėڂ��o�܂��A�v�̖����ĂԁB�ޏ��̋��ѐ��͋z���S�m�X�t�F���g�D�ɔ���A�ނ͎����̋]���҂���������͂Ȃ��B �@�����t�b�^�[�͎������Q���ɕ����߂��Ă���̂�����B�t�b�^�[�������牺�̒��������ƁA�Ԃɉ��ꂽ�y����t�ɋl�߂�������ςݍ���ł���B�ςݏI���Ɣ��݂͈�ԏ�̊����ɉ������A�Ԃ͗H��̎�ɓ����ꂽ�悤�ɁA��������삯����B�t�b�^�[�͑����瓦�������A���|�ɓ��]���Č̋��ւ̋A�r�ɏA���B �@�ނ͔M�ɕ�������Đl���s�ȂɂȂ邪�A���ߐ[���l���������ʂĂ��ނ������A�Ō삵�Č��C�����߂��Ă��B�m�X�t�F���g�D�͊�����D�ɍڂ��ďo�q����B�����D���Ƀl�Y�~���������Ă��āA��g���͎��X�Ɏ��ɒǂ������B�����t�b�^�[�̓u���[�����}�����A��l�D�Ɏc�����m�X�t�F���g�D�̂ق�����ɒ����Ă���B�������A�u���[�����ł̓��@���E�w���W���O���m�����R�̔閧�Ɛl�Ԑ����Ƃ̊�ȑΉ��ɂ��ču�`���Ă���B �@�m�X�t�@���g�D������ė���Ƌ��ɁA�u���[�����̒��Ƀy�X�g�����s��B���ǂ��Ă����t�b�^�[���A�悤�₭�u���[�����ɒ����B�Ȃ̃G�����͔ނ̎�ו��̒��ɋz���S�̖{�������A�ǂ�Ȃ��Ƃ��N��������m��B ���̖{�ɂ́A���炩�ȐS�������������Ȃ�z���S�ɖ閾���̍ŏ��̃j���g���̖����ɋC�Â��̂�Y�ꂳ���A�z���S���Q���ɂ��Ă��鉘�ꂽ�y�̊����̂Ƃ���ցA�閾���O�ɖ߂�Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��ł���ƁA�����Ă������B�G�����͐g���]���ɂ��ċz���S���Ăъ悤�ƌ��S����B �@�����ăm�X�t�F���g�D�������̑��Ɍ����������Ƃɓ������̂������G�����́A���̉��������҂��Ď����̂Ƃ���֗������A�ނɎ�������o���B�m�X�t�F���g�D�������Ō����z���Ă��邤���ɓ�������B�u���[�����ɂ̓m�X�t�F���g�D�̋��C�̉Ɨ��N�m�b�N�����āA�Ŏ��ɓ�����Ă������A�ނ͓��̏o�ɋC�Â��āu����l�A����l�A�C��t���āI�v�ƌx������B�������Ԃɍ���Ȃ��B�������˂��ċz���S�̐g�̂�����A�o�ɖ߂��B������A��ċ}���ŃG�����̂Ƃ���֗����t�b�^�[�́A�����₦�₦�̍Ȃ�������B������ �m�X�t�F���g�D�̉e������������ƁA�Ȃ̕a�C�͊�Ղ̂悤�ɏ�����B�����ăm�X�t�F���g�D�̉Ɨ����e���Ɠ������Ɏ��ʁB �y����z���̉f��̃V�i���I�́A�w�v���[�O�̑�w���x�A�w���l�S�[�����x��w�d�ԃA���E�l�x�Ƃ������A�h�C�c����z�f��̌���̃V�i���I��ēɊ֗^�����w�����b�N�E�K���[�����A�u�����E�X�g�[�J�[�̏����w�z���S�h���L�����x�����~���ɂ��ď��������̂������B����͂܂��ɁA�A���O���E�T�N�\���n�̋��|���w�ƃh�C�c�n�̌��z���w�����āA�u�f��v�Ƃ����V�����}�̂Ɉڂ��A�f��Ƃ����W���������������������̕\���ɂ���߂ēK�����}�̂ł��邱�Ƃ���������i�������B���̈Ӗ��ł͂��̉f��́A�����܂ʼn��X�Ɛ��삳�ꑱ���Ă��鐢�E�̉���z�f��̌����̈�ƂȂ����A�L�O���ׂ���i�ƈʒu�Â��邱�Ƃ��ł���B�����ɂ���͊ē����i�E���A1920�N��h�C�c�E�T�C�����g�f��̋����̈�l�ɂ̂��オ��ߒ��ŁA�w�t�H�[�Q���b�g��x�ɑ����Ĕ��\�����A�ނƂ��Ă��d�v�Ȉʒu���߂��i�ł���B �@�u�h���L�����v�����łȂ���ʂɋz���S�́A��Ƃ��ăC�M���X�E�A�����J�f��̂��C�ɓ���̃e�[�}�ŁA�قƂ�ǖ����ɉɂ��Ȃ��قǂ̐����U��ŁA�ʐ������r�����������B�ɂ�������炸�p�ĂŁA���̃����i�E�́w�m�X�t�F���g�D�x�����̂���i�����܂ꂽ�Ƃ͌�����B���F���i�[�E�w���c�H�[�N�ēɂ�郊���C�N���A�����i�E�̌���𒉎��ɂȂ�������i�ł���B�����Ƃ��p�Čn�́u�z���S�v�f��ɂ́A�قƂ�ǃ}�j�A�I�ȃt�@���������B�Ⴆ�G���u�f���ɁvNo.11�́u�h���L�����G�w�ʐ^���T�v�Ȃǂ́A�A���������X�����\���Ă���B�����ʑ��I�ȋz���S�f�悪�A�C�M���X�E�A�����J�ő�O�̈��|�I�x�����Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B �@�����i�E�́w�m�X�t�F���g�D�x�Ɋւ��ẮA�h�C�c�f����t�����ɂ��������u�L�[�m�E�u�[�t�v��ҏW���āA�f��̖��������������N���g�E�s���g�D�X���A���̉f��̌��z������ɏ^���āA�����q�ׂĂ���B�u�R���g���X�g�Ƃ��ĝR��I�ȗv�f�Ət�̒��̂悤�ȏ���A����߂Đ��N�Ȉ�͂�^����B�����i�E�͂��̉f��ŎႢ�l�X�������g�����B���ꂪ�ނ̉f��ɁA�_�炩���Ə����^���Ă���v�B���������Ӗ��ł́A�����i�E�͋z���S���ނƂ��Ȃ�����A�ʂ��Ղ̉����f��Ƃ͈قȂ鎟���̍�i�ݏo�����ƌ�����B �@�h�C�c�\����`�f��ɂ��Ă̑�z�����_�l�w�f���[�j�b�V���ȃX�N���[���x�����������b�e�E�A�C�X�i�[�́A���̒��Ń����i�E�ɂ��āA���������Ă���B�u�h�C�c�f��ő�̉f��ēt���[�h���q�E���B���w�����E�����i�E�̉f��̍\���́A�����ĒP�Ȃ鑕���I�l�������Ӑ}�������̂ł͂Ȃ��B�ނ̓h�C�c�f��S�̂̒��ŁA�����Ƃ����|�I�ŁA�����Ƃ��ɗ�ȃC���[�W��n�������l���ł���B�ނ͌|�p�j�̌P�����Ă����B�t���b�c�E�����O���L���ȊG��𒉎��ɍĐ����悤�ƈӐ}�����̂ɑ��āA�����i�E�͂��������G��ɂ��Ď����������Ă���L���A����������l�̃��B�W�����ɕϊ�����B�����i�E�͎������g���瓦��悤�ƈӐ}���Ă����̂ŁA�t���b�c�E�����O�̂悤�ɁA�|�p�I�Ȉ�ѐ��ɂ���āA�������g��\�����邱�Ƃ����Ȃ������B�������ނ̉f��̂��ׂẮA�ނ̓��I�R���v���b�N�X�̋L���ƂȂ��Ă���B�܂�ނ̉f��́A�ނ���]�I�ɖ����ȑ��݂ɗ��܂��Ă��鐢�E�ɑ��ẮA�ގ��g�̓����ł̓����̋L���ƂȂ��Ă���B�Ō�̉f��w�^�u�[�x�ɂ����Ă����A�ނ͕��a�Ǝ�̍K�������o�����悤�Ɍ�����v�B �y�f��]�z�����h���t�E�N���c�w�\����`�Ɖf��x�i1926�j�\�\�u�c�c���j���O�X���g�����w�Ō�̐l�x�ŁA�͂�����Ɨl�������ꂽ�����n�����������i�E�́A���Ƃɂ��Ƃ܂��ӎ��I�ȕ\����`�ł͂Ȃ����A���̌`���ɋ߂Â��Ă���悤�Ɍ����鏔�v�f�ɂ���āA�ނ̋z���S�f��w�m�X�t�F���g�D�x�̒��ŁA�S�̕��͋C�̏����o���s�C���Ȉ�ۂ�n��o�����Ǝ��݂��B�w�����b�N�E�K���[�����������肵���V�i���I�ō\���������̋��|�ɖ������`���ɂ����ẮA�l�Y�~��y�X�g�D��A�z���S�ǂ���A�ۓV��̍L�Ԃ�A��Ȃ̂悤�ɑ���n�Ɉ����ꂽ�����הn�ԂȂǂɂ���Đ��ݏo�����d�Ȃ荇�������z���A���݂ɍ�p�������ăf���[�j�b�V���Ȍ��ʂ������Ă��邪�A����͎n�߂��玩�R��`�I�`�ʂ�����Ă����B�����i�E�͔��I���i���������A��̂��郔�B�W��������邱�Ƃ�ڎw���ĉ��o�����B�����Ď��R�̂܂܂̃t�H�����łłė^���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A���̋��|�̌��ʂ�B�������c�c�v�B ��1922�N9��11���t���́u�t�B�����E�N�[���[���v���\�\�u�c�c�ނ̌��z�I�ȃm�X�t�F���g�D�f��́A���l�|�ɂ���ăZ���Z�[�V�����������N�������B���̖��l�|�ɂ���Ă����ł́A�������f���̖����̌��ꂪ�A���̔��͂���N������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��悤�ȗ͂�U����Ă����c�c�B�ǂ�ȏꍇ�ł������i�E�̉f��ł́A�����͂���߂ċ���Ȍ��Ɋւ�邱�ƂɂȂ�B������ƌ����āA�ړI�̂��߂ɂ͎�i��I�ʖ�S�ƂƊւ���Ă���̂ł͂Ȃ��B�܂����������ɍ��ʂ��Ă��܂��A�܂Ƃ���i�߂Ȃ��Ȃ��Ă���h�C�c�f����A�ǂ��������~�����Ƃ��ł��邩�ɂ��ē���ɂ߂Ă���A�v������l�Ɗւ���Ă���̂ł���B�ނ͈�Ȃ�ʓ_�ŁA�����̉f��̐��E�̘g���͂ݏo���B�f��l�̊ԂŔ��������̃t���[�X�����h�l�̎p�ɏo����Ƃ��A���łɈٗ�ł���B�ނ͂���A�u�f��̍��̉ǖقȐl�v�̈�l�ɐ����邱�Ƃ��ł���i�t���b�c�E�I�����X�L�[�j�B �Ȃ��A�w�m�X�t�F���g�D�i�z���S�j�x�̃g���b�N����g�������u�́A�A���r���E�O���E��������B 1922.3.8�i���{����1926.4.30�j �w�R����n Der brennende Acker�x �t���[�h���q�E���B���w�����E�����i�E�ēA�V�i���I�F�e�A�E�t�H���E�n���u�ƃ��B���[�E�n�[�X�A�A���g�D�[���E���[�[���A�B�e�F�t���b�c�E�A���m�[�E���@�[�O�i�[ �y�L���X�g�z���F���i�[�E�N���E�X�A�I�C�Q���E�N���b�p�[�A�E���f�B�[�~���E�K�C�_���t�A���A�E�f�E�v�b�e�B�B �y����z���������y�n����Ζ����o��Ƃ����\�z�ŋN������S�ƕ��~�̔_���ƒ�̎������B����͎��E�ƕ��̂����܂��������ɔ��W���邪�A�ߌ��̌����͂��������̍K���ŏI���B�����͌Z�킪�܂����������̐��E�ς������Ă��邱�ƁA�_���ƋM���Ƃ̊Ԃ̎Љ�I����̒���⎑�{��`�I��肪�����ł��邱�ƂŁA��i�����������Â�����̂��炵�߂Ă���B 1922.4.27�i���{����1923.5.1�ꕔ�Z�k�Łj �w�h�N�g���E�}�u�[ DR, MABUSE, DER SPIELER�x��ꕔ:�u��q���t�E����̉f�� Der grose Spieler. Ein Bild der Zeit�v �t���b�c�E�����O�ēA�V�i���I�F�e�A�E�t�H���E�n���u Thea von Harbou�i�m���x���g�E�W���b�N�̏����ɂ��j�B�e�F �J�[���E�z�t�}���A���p�F�V���^�[���E�E�[���n�i��ꕔ�B�e���Ɏ����j�A�I�b�g�[�E�t���e�A�G�[���q�E�P�b�e���t�[�g�i��j�A�J�[���E�t�H���u���q�g�i��j�A����F�f�[�N���E�r�I�X�R�[�v�� �y�L���X�g�z���h���t�E�N���C�������b�Q Rudolf Klein-Rogge�i�}�u�[���m�j�A�x�����n���g�E�Q�b�P Bernhard Goetzke�i���F���N�����j�A�A���t���[�g�E�A�[�x���i�g���g���݁j�A�A�E�g�E�G�[�C�F�[�E�j�b�Z�� Aud Egede Nissen�i�J���E�J���b�c�@�A�x��q�j�A�Q���g���g�E���F���J�[�i�g���g���ݕv�l�j�A�p�E���E���q�^�[�i�G�h�K�[�E�t���A�S�����҂̑��q�j�A���x���g�E�t�H���X�^�[�������i�K�i�V���y���A�鏑�j�A�n���X�E�A�[�_���x���g�E�t�H���E�V�����b�g�E�i�Q�I���N�A�}�u�[���m�̉^�]��j�A�Q�I���N�E���[���i�y�V���j�A�J�[���E�t�T�[���i�n���@�V���j�A�O���[�e�E�x���K�[�i�t�B�t�B�A�����j�A�����E�X�E�t�@���P���V���^�C���i�J���X�e���A���F���N�̗F�l�j�A�����f�B�A�E�p�`���q�i�i���V�A�w�l�j�A�����E�X�EE.�w���}���i�V�������j�A�J�[���E�v���[�e���i�g���g���݂̏��g���j�A�A�j�^�E�x���o�[�i�x��q�j�A�p�E���E�r�[���X�t�F���g�i�s�X�g�����������j�j�A�����E�X�E�u�����g�A�A�E�O�X�e�E�u���b�V�����O���[�t�F���x���N�A�A�f�[���E�U���g���b�N�A�}�b�N�X�E�A�[�_���x���g�A�O�X�^�t�E�{�b�c�A�n�C�����q�E�S�[�g�A���I���n���g�E�n�X�P���A�G���i�[�E�q���v�V���A�S�b�g�t���[�g�E�t�b�y���c�A�n���X�E�����J�[�}���A�A�h���t�E�N���C���A�G�[���q�E�p�v�X�g�A�G�h�K�[�E�p�E���A�n���X�E�V���e�����x���N�A�I�[���t�E�V���g�����A�G�[���q�E���@���^�[ �y���炷���z����T���u��q���t�E����̉f���v�\�\�}�u�[���m�͑�ϐ����������_���͊w�҂Ƃ��āA�Љ�ɒm���Ă���B�����ނ͓�d�����𑗂��Ă���A�������̉��ʂ̉��ŁA�Ö��p�̔\�͂𗘗p���āA�ƍߓI�Ȃ����ō��Y�ƌ��͂̊g��ɓw�߂Ă���B�@ �@���傤�Ǎ��ނ́A�X�C�X�ƃI�����_�̊ԂŃR�[�q�[�̎���Ɋւ���o�ϋ�������s���Ă��邱�Ƃ�m�����B�ނ͗�Ԃ̒��ł��̎g�҂��E�����A���菑�𓐂܂���B����ɓd�C�H���l�ɋU���������Ǝ҂���̕ŁA�����̌��������������Ƃ��}�u�[�͒m��B�����Ŕނ͐^�ʖڂȎ��ƉƂ̉��ʂ̉��ɁA������ɍs���B�����Ĕ鏑�̃V���y���ɖ����āA���菑����ꂽ���ފ����A������̊J�������Ԍ�ɃX�C�X�̎��قɎ�n�����悤�ɂ���B�}�u�[��������ɓ���ƁA���菑�̋L�^���������Ƃ����m�点�����āA������870����120�ɉ�����B�}�u�[�͔����B����ƋL�^�����������Ƃ����m�点�����āA�����980�ɏオ��B�}�u�[�͔����āA����Y���B �@�[���ނ͐��_���͂ɂ���Đl�Ԃ̓��]����e���ɂ��āA�u������B���̊Ԃɔނ͍s���l�ɕ����āA�n���X�ɂ���ނ̋U�D�H���サ����A��s�ƃt�[�S�[�E�o�����O�ɕ����āA�u�t�H���E�x���W�F�[���v��K�ꂽ�肷��B�����ɂ͗x��q�J���E�J���b�c�@���o�ꂷ�邪�A�ޏ��̓}�u�[�̒����ȋ��Ǝ҂ł���B�ޏ��͎��̋]���҂Ƃ��āA��������̍H���̑��q�G�h�K�[�E�t���ɁA�}�u�[�̒��ӂ�����������B�}�u�[�͍Ö��p���g���āA�t���������ƈꏏ�Ƀ��@���G�e����A��o���A�g�����v�N���u�u174�v�Ɉē�����B�����čÖ���Ԃ̃t�����s�����A15���}���N�Ƃ���������A�����z�e���E�G�N�Z���V�I�[���̃t�[�S�[�E�o�����O�̕����Ɏ����Ă���悤�Ɍ����B �@�����t�����z�e���ɕ����ɍs���ƁA�����Ŕނ̓J���b�c�@�ɏo��B�����܂��ޏ��ɖ��f���ꂽ�t���́A�ޏ��Ɍ������A�ޏ��͎w�߂��ꂽ�Ƃ��肻��������B������t�����ƂŃJ���b�c�@��҂��Ă���ƁA�t�H���E���F���N�������K�˂ė���B�����́u�t������A���͂��Ȃ�����������x�@�̒��ڂ̕ی�̉��ɂ��邱�Ƃ������邽�߂ɗ��܂����v�ƌ����B�ނ͍X�ɂU�T�ԑO���炢�����ܓq���̔�Q�����Ƃ����i�������ǂɊ��Ă���A���Ȃ����Ȃ��߂����o�����O���ɓq���ő�s�����ƕ������̂ŁA���͂𗊂݂ɗ����̂ł��ƌ����B����͂ǂ���瓯��l���炵���Ƃ������B �@��������������ƁA�}�u�[�ɋ�������ăJ���b�c�@������ė���B�����Č����̖��h��������ƁA����Ȋ댯�Ȃ������͂��Ȃ��悤�ɂƌx������B���F���N�͗F�l�̃J���X�e���ƈꏏ�Ɂu�V�������E�O�����v�ɍs���ĐH�����������ő{���𑱂���B�ނ̓��X�g�����̗������ŁA�g���g���ݕv�l�ɏo��B�ޏ��͓q���҂̊Ԃł́A�u�s�������q�v�Ƃ��Ēm���Ă����B�ޏ����g�͓q���ɉ����Ȃ���������ł���B�ޏ��͔��p���W�Ƃ̕v�ɑދ����āA�q����́@���͋C�������Ă����̂ł���B�����Ń��F���N�͔ޏ���������āA���m�̑啨�̑{���ɋ��͂�����B �@���̊ԂɃ}�u�[�͐V���ɔ����̘V�l�ɕϑ����āA�ׂ̓q����ɍ���A���V�A�w�l�Ƃ��̂T���h���̐^��̃l�b�N���X��q���ď������A�����̃g���b�N�ŁA����������̂��̂Ƃ���B������F���N�����̓J���b�c�@����A�閧�̓q���N���u�̃��X�g����ɓ����B�����Ŕނ͉��ʂ�t���āA�܂��͂��߂Ƀ}�u�[���������u�A���_���V�A�v�̓X��K���B�����ăG�L�]�`�b�N�Ȉ�ۂ�^����V�l���A�������Ƃɂ�ށB�}�u�[�̓��F���N�ɍÖ��p�������悤�Ƃ��邪�A�͂��߂Ē�R�ɂԂ���B�}�u�[�̓��F���N�̉������������A�����Ԃœ����o���B�����ă}�u�[�̒��Ԃ����F���N�������~�߂悤�Ƃ��邪�A���F���N�̓}�u�[�̐Ղ�ǂ��āA�z�e���E�G�N�Z���V�I�[���܂ōs���B�������}�u�[�͋��d�ɉ����Ďp������܂��B �@�}�u�[�͍���t���ƃ��F���N��ЂÂ��悤�Ƃ���B�ނ̎w�߂ŃJ���E�J���b�c�@�̓t���̉Ƃɍs���A�V�����q���N���u�u�v�`�E�J�W�m�v�̊J�X�ɏ����B���̍ۃ}�u�[�̎莆�𗎂Ƃ��āA�C�Â����ɋA��B���F���N�̓J���b�c�@���^�O������Ȃ��悤�ɁA���C�ɐU�镑���悤�ɂƃt���ɂ����߁A�������Ȃ��̑O�ɂ����ɍs������A���̊댯���Ȃ��ƈ��S������B�q�����n�܂����Ƃ���Ń��F���N�͌x�@�ɓd�b�������A������������B�����������̒��Ń}�u�[�̈ꖡ�̓t�����ˎE���Ă��܂��B�J���E�J���b�c�@���ߕ߂����B �@���ăg���g���ݕv�l�͂���S��p�̃T�[�N���ŁA�L���Ȑ��_�Ȉ�}�u�[���m�ɏo��A�ނ𗂓��̃g���g�@�ł̃p�[�e�B�ɏ��҂���B���F���N�̓g���g���ݕv�l��K��A���̋��͂���B�u���Ȃ��͓q���N���u�ňꏏ�ɂ�����ꂽ���̂悤�ɁA�����I�ɃJ���b�c�@�̓Ɩ[�ɓ����ĉ������B���͂��Ȃ����A�J���b�c�@�Ɍ������点�邱�Ƃɐ�������Ɗm�M���Ă��܂��v�ƌ����B�����鎞��ł����Ƃ��댯�Ȕƍߐl�̈�l�̎肪�����͂ނ��߂ł��ƌ����āA���Ƀg���g�v�l�͏��m���A�x�@�̗��u���ɓ���B�����ăJ���b�c�@�Ɂu�E�l���s��ꂽ�Ƃ��A���Ȃ��͋߂��ɂ����́v�ƒT�������ƁA�J���b�c�@�͕v�l�̉��Z�����j���Ă��܂��B�����ŕv�l�̓t�����}�u�[�ɎE���ꂽ���Ƃ������邪�A�J���b�c�@�́u�}�u�[�͈̑�Ȑl�Ԃł���A�����������Ă���B���̂�����l�̐l�𗠐邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƌ����B���ݕv�l�́u���߂�Ȃ����A�J���b�c�@����A���͂��Ȃ����ނ������Ă��邱�Ƃ�m��܂���ł����v�Ǝӂ�A����ȏ�T��o�����Ƃ��~�߂�B �@���Ƀg���g�@�Ńp�[�e�B���J�����B�}�u�[���m������B�ނ͔��݂ɍÖ��p�������A�J�[�h�V�тł��q�B�ɂ������܂��d�|���A���������j���Ă��܂��悤�Ɏd������B���҂�����l���������܂������Ƃ����̂ŁA�X�L�����_���ɂȂ�A�p�[�e�B�͐������ł��܂��B�}�u�[�͍����𗘗p���āA�ޏ���A�ꂾ���A�����̉Ƃ̈ȑO�J���E�J���b�c�@�����������ɕ����߂�B �y����z��ꎟ���E����̐����̋L�^�ƕs�C���ȓƍَ҃}�u�[���̑n���B�x�������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŕ���B 1922.5.26 �w�h�N�g���E�}�u�[ DR, MABUSE, DER SPIELER�x���:�u�n���E�����̎���̐l�Ԃ��߂��錀 Inferno-Ein Spiel um Menschen unserer Zeit�v �y���炷���z����U���u�n���E�����̎���̐l�Ԃ��߂��錀�v�\�\���������藐�����g���g���݂̓��F���N������K��āA�u���͂������ܓq��������Ă��܂��܂����B����苭�������ɋ������Ă��������̂ł��v�ƍ������A���������P�[�X��C���邱�Ƃ̂ł���V���Ȑ��_�Ȉ��m��Ȃ����Ɛq�˂�B���̂Ƃ������킹���q�̒��ŁA�v�ȂɂƂ��Ďn�߂Ă̋q�̓}�u�[���m�������������Ƃ������F���N�́A�}�u�[���m�ɐf�@�����߂�悤�Ɋ��߂�B �@����}�u�[�͔��ݕv�l���荞�߂ɂ��悤�Ƃ��Ă���B�����֔��݂���d�b���������āA�v�f�@�����߂���B�}�u�[�͗����̂P�P���ɖK���Ɠ�����B�������݂�K�˂��}�u�[�́A��ϖʔ����P�[�X�Ȃ̂Ŏ��Â������܂��傤�Ɩ��邪�A����������ƌ����B�u���Ȃ��͎������Â����Ă���ԁA�Ƃ��o�邱�Ƃ��A�l�ɉ���Ƃ����Ă͂Ȃ�܂���v�B�����Ŕ��݂͂��̎w���ʂ�ɁA���g���Ɂu����v�l�̂��Ƃ�q�˂�ꂽ��A���炭���ɏo�Ă��܂��ƌ����v�Ɩ�����B���F���N����d�b��������A���g���͖�����ꂽ�Ƃ���u���v�Ȃ͗��s���ł��v�Ɠ�����B���F���N�͕s�v�c�Ɏv�������A���ݕv�Ȃ̊댯�ȏ�Ԃɂ͋C�Â��Ȃ��B�ނ̓J���b�c�@�������Y�����ɑ����āA�܂��܂��������q�₷��B�ޏ����������肻���ɂȂ����ƒm�����}�u�[�́A�Ŏ�Ƃ��ČY�����ɐ��荞�܂��Ă���艺��ʂ��āA�J���b�c�@�ɓł̃A���v���𑗂�B �@�J���b�c�@�͂��ƂȂ������������Ŏ��ʁB�����}�u�[�̎q���̈�l�y�V�����A���F���N�����������Ɛ���������Ƃ��Ď��s���A�ߕ߂����B����ƃ}�u�[�͍����A�W�e�[�^�[�ɕϑ����ĘJ���Ҏ���ɍs���A�ߕ߂��ꂽ�v���̏}���҂��ڑ����ɒD�҂��悤�ƃA�W��B �������D�҂���������ƁA�}�u�[�͎艺�̈�l�Ƀy�V�����ˎE�����A�閧���R���̂�h���B �@�������Ă����ă}�u�[�̓g���g���ݕv�l����������B�u���͂��̒��Ƃ��̍����������ł��B���͋M�������ɓ��s���������ǂ��������ɗ����̂ł��v�B�����Ĕ��ݕv�l���ނɂ��̂ɂȂ邱�Ƃ�����ŁA�u���͕v�̂Ƃ���֍s���̂ł��v�ƌ����ƁA�}�u�[�́u�����Ȃ��͂��Ȃ��̂���l�Ɏ��Y�̔������������̂ł��v�ƌ����B�����Ĕ��݂Ɍ������Ắu���Ȃ��̕v�l�͂��Ȃ��_�a�@�֑��낤�Ƃ��Ă��܂��B���Ȃ��̐l���͂����܂��ł��v�Ɛ������ށB��]�������݂͍������Ă��܂��A�Ƃ��Ƃ����݂���ōA����Ď��E���Ă��܂��B �@���݂̎���m�������F���N�͔��ݓ@��K��A���g���ɔ��݂͂ǂ��ɂ��邩�ƕ����B���g���́u���̕s�K�ȓq���̖�ȗ��A���͔��ݕv�l�ɂ����Ă��܂���v�Ɠ�����B���̂Ȃ��߂���������{�����邽�߂Ƀ��F���N���������ɋA��ƁA�}�u�[���m���҂��Ă���B�����ăg���g���݂̎��͖��p�t�U���h���E���F���g�}���̍Ö��p�̉e�����Ɛ����A���F���g�}���̎����̋��Ƃ�K��āA�����̖ڂŊm���߂�悤�ɂƊ��߂�B �@�����̔ӂɖK�ꂽ���F���N�́A���F���g�}���A���̓}�u�[�ɗU�����ꂽ����ɏオ��B�����Ĕނ����ɂ����uTSI-NAN FU�v�Ƃ�����������A���F���g�}�����}�u�[�ł��邱�Ƃ����������A���x�̓}�u�[�̍Ö��p�ɂ������Ă��܂��B�������������̒��ɏ�����Ă���Ƃ���ɁA�u�ϋq�Ȃ𗣂�āA�ˌ��̑O�Ɏ~�܂��Ă���Ԃɏ��A�t���X�s�[�h�Ńx���N�X���o�āA�V���^�C���u���b�N�E�����I�[���ցv���������F���N�́A�����Ŋ낤���Ď��������ɂȂ�B�����ނ͕����ɁA��������ڂ𗣂��ȂƗ���ł����̂ŁA�Ԉꔯ�̂Ƃ���ŕ����ɋ~����B �@���F���N�̓}�u�[�̉Ƃ��͂�����B�E�o�ł��Ȃ��ƒm�����}�u�[�́A��������R���Č��������B���F���N�͓d�b�Ń}�u�[���Ăяo���A��R���~�߂�悤�������邪�A�}�u�[�́u���͎������v���Ƃ̒��̍��Ƃ��Ɗ����Ă���B�����~�����Ȃ�A����A��ɂ��邪�����v�Ƌ��ۂ���B�����āu�g���g���ݕv�l�����̉Ƃɂ��邱�Ƃɒ��ӂ���v�ƌ����B�v�l�̖����댯���ƒm�������F���N�́A�R���̏o�������߂�B�R�����˓�����ƁA�}�u�[�͔��ݕv�l��A��ē����悤�Ƃ��邪�A�v�l�͒�R���ă}�u�[���瓦���B�}�u�[�͒n���̃g���l����ʂ��āA�U�D�H��ɓ������ށB�������̍H��̌������������F���N�́A�}�u�[�������֓��S�����Ɛ������A�����Ƌ��ɍH��ɋ}�s����B�}�u�[�͍H��̓����̌��������Ă��Ȃ������̂ŁA�O�֏o���Ȃ��B �@�Ƃ��Ƃ��ނ͋C�������Ă��܂��A�ނ̋]���ƂȂ����t���A�J���E�J���b�c�@�A�g���g���݁A�y�V���̖S���ɓq��������B�ނ͕�����B���F���N���H��ɓ��ݍ��Ƃ��A�ނ͂����Ɋ��S�ɋ����Ă��܂����j�A�u���ă}�u�[���m�������j�v�����������������B �y����z�w���ł̒J�x�ɑ����t���b�c�E�����O�ḗA���̃T�X�y���X�ɕx�����h���}�́A�w���ł̒J�x�ȏ�ɒ��ړ����ُ̈�Ȑ����̋�C���ċz���Ă���B�������猩����������w�i�́A���ׂĂ��̋}���������Y���̖��؋��Ƃ����`���ݏo���̂ɖ𗧂��������ł��邪�A����̉Q���ɂ������ϋq�́A���ړI�ȑ̌��Ƃ̏Ɖ��ɐ�ɂ����ł��낤�B�t���b�c�E�����O�ƃn���u�̂˂炢���A�����ɂ������킯�ŁA�ϋq�̔����͓�l�̎v���ڂ������B�����Ńt���b�c�E�����O���g�A�̂��ɂ��̉f����u�h�L�������^���[�f��v���Ə̂��Ă���B��������̍Č��Ƃ����Ӗ��ɂ����Ăł͂Ȃ��A�����̃h�C�c�l���{�\�I�Ɋ����Ă������̋��Ђ��A�}�u�[�Ƃ�����l�̐l�����ɋ����Ă��邿���Ӗ��ŁA����̃h�L�������^���[�������Ƃ����̂ł���B�m���ɓ�����̊ϋq�ɂƂ��ẮA�f�������ꂽ���܂��܂ȗv�f���A�����������Ђ̉��I�ȋL���������B�o�D�̕\���L���ȉ��Z�A�S�\�̈��Ƃ������ہA����ƈł̕s�C���͌����A���E�̂��Ȃ��Ȃ�������̐��_�����o�����Ă���\����`�I���u�\�\������������Ă̌��ʂ͖��_�������B�����̃J�^���O�͂��������Ă���B�u�푈�Ɗv���Ƃɂ���đ|�����A���݂���ꂽ�l�Ԃ́A�~�]���狝�y�ցA���y����~�]�ւƋ}�����Ƃɂ���āA��Y�ɖ������ߍ��ȔN���ɕ��Q���Ă���v�B �@�f�悾���ł͂Ȃ��B�m���x���g�E�W���b�N�̌���ɂ����łɁA������������̋C�������삵�Ă����B�u�푈�̋A���͑z���͂𒾐Â������A�ނ��낻����������Ă��B���\���l�Ƃ����҂������A����ɖ��ׂ̐����ɓ��Ă��܂��Ă����B�l���͂��̉��N�Ԃ�ʂ��āA�������߂�����I�M�����u���ȊO�̂��̂ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B���]�ƐS��͈ꂩ�����ɓ��Ă��܂��Ă����v�B�܂蓖���̃h�C�c�l�̐S��́A�T�X�y���X�ɕx�j�q���ȃ����h���}�ɂ҂�����̏ɂ������B �@�����Ƃ��m���x���g�E�W���b�N�̌���́A�K�������������������̍�i�ł͂Ȃ������B�����t���b�c�E�����O�ƃe�A�E�t�H���E�n���u���A�����Ɠ��̋^���_�b�I�����h���}�Ɏd���ďグ�Ȃ������Ƃ���A�Ƃ��̐̂ɖY�p����Ă������Ƃ��낤�B����̎�l���́A���̃J���X�}�I���݂Ƃ͎��Ă����Ȃ����s���ɉ߂��Ȃ��B�G���̃��F���N�������^�ʂ�̔\���ŁA�����I�S��̐l���ł���B�����̕�������E�I��s�s�x�������ł͂Ȃ��āA�c�ɂ̃~�����w���ł���B�����G���`�b�N�ȕ`�ʂ́A��ƃn���X�E�n�C���c�E�G�[���@�[�X���A�����̃h�C�c��y���w�ɓ��������ʑ��\����`�̈��ȃX�^�C���P���邱�ƂŁA����̌X���������Ă����B �@���̂悤�ɉf��̂ق����������ꡂ��Ɏ���̊���ɓY���Ă������A�\����`�̎������[�h�����N���g�E�s���g�D�X�́A����ɂ��Ď��̂悤�ɕ]�����Ă���B�u���̂悤�ɒʗ�i�ʑ��I�ȁj�w�E���V���^�C���E�u�b�N�x�V���[�Y�̍�i��ǂ܂Ȃ��҂́i����䂦�m���x���g�E�W���b�N�̏�����m�炸�ɃE�[�t�@�E�p���X�g�f�抻�ɗ���҂́j�A�f��w�h�N�g���E�}�u�[�x�ɂ���āA�O�̃Z���Z�[�V������̌����邱�Ƃ��ł���B���ɁA�h���I�Ȕƍߎ���������B�܂�^���Ɛl�Ԃ𑀂邱�Ƃ��l���̕K�v���ł���悤�ȁA����ȃX�P�[���̋��M�I�Ȕƍߎ҂����邱�Ƃ��ł���B���ɁA�J�[���E�z�t�}���̕��O��čI�݂ȁA�悭�b���ꂽ�A�i���͊����Ă��������������j����߂Č|�p�I�Ȏʐ^�ɂ���āA�ڂ����f����A�����Ƃ肳������B�Ⴆ�Ζ�̊X�H��ʂ�s�d�ŁA�Èł�����肪���삵�A�h��A�R����V�[���B�����̋������悤�ȉe���A�\������悤�ɉ�ʂɓ����Ă���V�[���B����͂���܂Ō������Ƃ̂Ȃ��ʐ^�Z�@�̊v�V�ł���B�����đ�O�ɁA�ē̃t���b�c�E�����O���A���C���݂������̎�����A�����I�ȃ^�C�v�Ɗ��ɔZ�k���悤�Ɠw�߂Ă��邱�Ƃł���B�m���x���g�E�W���b�N�̏������ƍߎ҃}�u�[�̑����A��葽�������Ă���̂ɁA���炪�s����ȑ��݂ł��郉���O�́A�����̍ˁA�@�m�A�����ĉf���\���ɂ���āA�f�����e���|�Ŏ��㑜���J��L���悤�Ƃ��Ă���B�W���b�N�̏����ɂ�����ȏ�ɁA���̉f��̐l�����͐��I�ɍ��グ���āA��̌^�ɂȂ��Ă���B�����Ă��ׂĂ̌^�̐l�������A�r�ꋶ���A�������A���s�������ォ�琶�ݏo����A�Ăт��̐��E�̒��ɗn�����ށB�Ⴆ�Ύ����̏�i�Ȋ�����A��]�I�ɃA���@���`���[�������߂Ă���M���̏��������Ă��炢�����B���邢�͕\����`�ŏ[����������̎��悤�ȕ����ŁA���y�C���Ō|�p�̃h�O�}�ɂӂ����Ă���A���ׂ̗D�_�s�f�Ȓj�A�����p�̔ƍߎ҂ɓz��̂悤�ɕ����Ă���x��q�����Ă��炢�����B���ꂩ��t���b�c�E�����O�ḗA�ŋ߂̔N�����ߓx�̋����A���A�Z���Z�[�V�����A���@�Ƃ����`�ł����ɂ����炵�����ׂĂ̂��̂��A���k���悤�Ƃ��n�߂�B�Ȋw�I�ɏn�����ꂽ�ƍ߁A���������鑊�ꑛ���B�G�L�Z���g���b�N�ȓq���N���u�A�Ö��p�A�R�J�C���A����������������������Ȏ���A���_�I�ɂ����I�ɗꑮ�I�ȁA�Ў�Ȑl�ԁB�ǐS�̖����̂����R�ł���悤�ȁA���̋��菊���������l�X�v�B�N���g�E�s���g�D�X�̔�]���̂��A����̋�C���̂��̂̕\���ł���B �@�\����`�͎���̃V���{���������B�t���b�c�E�����O�͉f��̒��ŁA�u�\����`���ǂ��v�����v�Ƃ�����ɑ��āA�}�u�[�ɂ������������Ă���B�u�\����`�͗V�Y�ł��B���������ꂪ�ǂ����Ă����Ȃ��̂ł��傤�B�����ł͂��ׂĂ��V�Y�ł��I�v�܂肱�̉f��͂��ׂĂ��V�Y�ɂȂ��Ă��܂������E���e�[�}�Ƃ��Ă���B�V�Y�i�q���j����l�Ƃ��Ẵ}�u�[���m�́A�V�Y�ɂ��Ė��ĂȌ����������B�u���Ȃǂ͂���܂���B�~�]�����邾���ł��I�@�K���Ȃǂ͂���܂���B���͂ւ̈ӎu�����邾���ł��I�v �@���������ۂɂ͂��̉f��ł́A�u���͂ւ̈ӎu�v���}�u�[�̓��@�Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B��ɂȂ�Ȃ�قǁA�V�Y�i�q���j���̂��̂����ȖړI�ƂȂ�A���삷�邱�Ǝ��̂̉��y�ɂӂ����Ă���B�J���҂��A�W���Ď艺��D�҂�����Ƃ��A�ނ̋]���҂̐��������Ă����ԂƂ��A�ނ͑���̖��l�|�ɂ���ĕ��^���ꂽ���͂��y����ł���B���̉f��̊�Ȗʔ����́A�܂��ɂ����ɂ���B�����}�u�[���u���͂ւ̈ӎu�v�����ؖ����������鈫���I�Ȑl�����ɉ߂��Ȃ��Ƃ�����A���̉f��͕s�C���Ńf���[�j�b�V���Ȃ��̂ƂȂ����ł��낤�B�}�u�[����i��ړI�ƍ������邱�Ƃɂ���āA�ނ̒��l�I�\�z�̔�l�Ԑ����A�����ׂ��l�ԓI�Ȃ��̂ɕς��B���ꂪ���̉f�������ł�����̂ɂ��Ă���B���邢�̓t���b�c�E�����O���g���A���������ʔ��������Ă����̂�������Ȃ��B �@������ɂ��Ă�����̃v���O�����������悤�ɁA�u���̃}�u�[���m��1910�N�ɂ͑��݂����Ȃ������ł��낤���A�����炭1930�N�ɂ͂��͂⑶�݂����Ȃ��ł��낤�B�����͂����v�������B������1922�N�̍��́A�ނ͎���ɐ����ʂ��̏ё��Ȃ̂ł���v�B�u���Ȃ݂ɂ���́A����܂łɎB�e���ꂽ�ŏ��̖{���̃M�����O�f��ł���B���̌�10�N���o�Ă悤�₭�n���E�b�h���A�l�Ԃ��Ԃɉ����Ԃ��ꂽ��A�ƍߎ҂�������@�֏e�Ō������肷��f����A�����ɍ��̂ł���B�����āA�����̉f�悪���[���b�p�֗���ƁA�l�X�͌����B�q�A�����J�̓T�^���I�r�����ăt���b�c�E�����O�����������f���10�N���O�Ƀh�C�c�ō�������ƁA�ނ̉f��Ɠ����悤�Ɍ��z�I�ŁA�r�����Ȃ����I�ȃx�������ō�������Ƃ��A�Ƃ����ɖY��Ă��܂��Ă���v�i�w�h�C�c�f��̈̑�Ȏ���x�j�B �@���̉f��̑�ꕔ�Ƒ�́A���݂ɕ₢�����W�ɂ���B���������ĘA���f��̂悤�ɁA���ɂ킯�ď�f����̂��A�����Ƃ������킵�������������B�������A�����J�ł͓��ꕔ�ɒZ�k���ď�f�������߂ɁA����łȂ��Ă�����ɓn�邱�̉f��́A���������������ɂ������̂ɂȂ����B���{�ł̕�����Z�k�ł������B���ꂪ���̉f��̕]�������������錋�ʂƂȂ����B�ɂ�������炸�f��͐��������B���̂��߃t���b�c�E�����O���g��1933�N�ɓ�Ԗڂ́u�}�u�[�v������������łȂ��A1960�N�ɂ��w�}�u�[���m�̐�̊�x��������B1962�N�ɂ́A33�N�́w�}�u�[�x�����F���i�[�E�N�����K�[�ɂ���čĉf�扻����A�u�}�u�[���m�v�́u�z���S�h���L�����v�̂悤�ɁA��̌^�Ƃ��Ă̐l�ԑ��̈ʒu���߂�悤�ɂȂ����B��������������ے�����l�ԑ��Ƃ��Đ���������ł��낤�B �y�f��]�z���u�x�������̃��[�����g�v�A1922�N5��4���\�\�u���̉f��̐����̗��R�͂��̃v���b�g�ɂł͂Ȃ��A�G�s�\�[�h�I�ȃf�B�e�[���ɂ���B�S�̂Ƃ��Ă̎����̘A���ɂł͂Ȃ��A��̎���������ƕ\�����Ă���X�̎����ɂ���B����̓��Y���ƃX�s�[�h�ɂ���āA�X�^�C���ƕ��͋C�ɂ���Č��т����Ă���B�����ɂ͕����Ɣƍ߁A�q���̏�M�ƃR�J�C����p�A�W���Y�ƌx�@�̎����̔Z�k������B���̏d�v�Ȓ���ň�Ƃ��Č����Ă�����̂͂Ȃ��B����������A�����A�I�J���g�̂������܁A���t�ƖO�H�A���A�A�Ö��p�A�\����`�A�\�́A�����ĎE�l�I �@��l�ԓI�Ȑl�Ԃ̂��̃f���[�j�b�V���ȍs���́A���̖ړI���A���̃��W�b�N���Ȃ��[�[���ׂĂ��V�Y�ł���B�������̐l�X���q�����y����ł���̂ɁA�}�u�[���m�͐l�Ԃ̐����A�l�Ԃ̉^�������Ă�����ł���v�i�u�x�����i�[�E�C���X�g���[���e�v�j�B �@�u���̉f��͌��݂��A���ؖ����f���o���ꂽ����j�������Ă���B�m���x���g�E�W���b�N�̏����̓e�A�E�t�H���E�n���u�ɂ���āA�I�݂ɉ��삳�ꂽ�B���������F�[�f�L���g�I�Ȍ��肪�A�s���a�Ńq�X�e���b�N�Ȑ����̊ԑ����Ă�����Ր��̎��̕����̏�ɁA�O���e�X�N�ȔA���e�B�́A���肷�锒�M�𓊂�������悤�ɔR�₳�ꂽ�̂́A�܂������t���b�c�E�����O�̉��o�̂������ł���B�ނ̎�ɂ��ʐ^�ɂ���āA����܂ŕ��������Ƃ��Ȃ��悤�ȕ\���͂��B�����ꂽ���Ƃ́A�����ׂ����Ƃł���v�B ���u�L�l�}�g�O���t�v�A1922�N5��7���\�\�u���̃}�u�[���m�́A�����̎���̈��̗��z���ł���B�ނ͑e��Ȃ���������ߋ��̃M�����O�̉��Ƃ͈Ⴄ�B�ނ����m�ł���̂́A���R�ł͂Ȃ��B�����Ĕނ͎����̃A�J�f�~�b�N�ȋ���œ����m�I�ȗ͂̂��ׂĂ��A�ނ̋��l�I�Ȍv����������邽�߂ɓ��������v ���u�a�E�y�v���\�\�u�o�ꂵ���l�����������̎���ɂƂ��ēT�^�I�ł��邾���łȂ��A�ނ�̐����̎d���Ɣނ�̒u����Ă�����������I�ł���B����䂦�f��̏�i�ʁA���̃Z�b�g�\�\���z�ƃV���^�[���E�E���b�n�ƃI�b�g�[�E�t���e�̋����ׂ����ʁ\�\���A�d�v�ȈӖ������v�B 1922.10.6 �w���N���`�A�E�{���W�A Lucrezia Borgia�x ���q�����g�E�I�Y���@���g�ēA�V�i���I�F���q�����g�E�I�Y���@���g�i�����n���[�E�V�F�t�̏����A�u���J���h�D�X�i���̓��L�̋L�q��O���S�����B�E�X�Ȃǂ�f�ނƂ��āA���R�ɋr�F�j�A�B�e�F�J�[���E�t���C���g�A�J�[���E�t�H�X�A�J�[���E�h���[�t�X�A�t���f���b�N�E�t�[�O���U���g�A���u�F���[�x���g�E�l�p�b�n�A�{�[�g�E�w�[�t�@�[ �y�L���X�g�z���A�[�l�E�n�C�g�i���N���`�A�E�{���W�A�j�A�R�����[�g�E�t�@�C�g�i�`�F�[�U���E�{���W�A�j�A�A���x���g�E�o�b�T�[�}���i���h���S�E�{���W�A�F�@���A���N�T���h���U���j�A�p�E���E���F�[�Q�i�[�i�~�P���b�g�j�A�n�C�����q�E�Q�I���Q�i�Z�o�X�e�B�A�[�m�j�A���^�[���E�~���[�e���i�W���A���E�{���W�A�j�A�P�[�e�E���@���f�b�N�E�I�Y���@���g�i�i�I�~�j�A�A���t�H���X�E�t�����[�����g�i�A���t�H���\�E�t�H���E�A���S���j�A�A���N�T���_�[�E�v�O���[�i�n�i���l�j�A���B���w�����E�f�B�[�e�����i�W�����F���j�E�X�t�H���c�@�j�A�����[�_�E�U�����m���@�i�f�B�A�{���F�Ւ����t�̏��j�A�A�j�^�E�x���o�[�� �y����z���[�}�@���A���N�T���_�[�Z���̖����N���`�A�E�{���W�A�̐��U�����������j���f��B �y���炷���z�@���A���N�T���h���U���͎����̓�l�̉��A�`�F�[�U���ƃW���A���A�����ĖẪ��N���`�A�ɔ��Ɉ������Ă���B�ނ̓��[�}�����\���Ă���`�F�[�U���̈��s��M���悤�Ƃ��Ȃ��B�������W���A�����E���ꂽ�Ƃ��A�E�����̂̓`�F�[�U�����ƒm��A�ނɒǕ���\���n������Ȃ��B���N���`�A�̓W�����F���j�E�X�t�H���c�@�ƌ������Ă͂��邪�A����͐����I���R����ł����āA�����ł͂Ȃ������B�`�F�[�U���̓��N���`�A�ɂ��̏�M�ŋ����ɔ����āA�ޏ���Y�܂��B�����ĔނƔޏ��Ƃ̊Ԃ��ז�����҂͒N�ł��A���ʉ^���ɂ���B�������N���`�A�́A�W�����F���j�����ʂ��Ƃ�]�܂Ȃ��B�����Ŕޏ��͔ނ̓��S��������B�ޏ��͔ނƗ�����������B �@��Ԗڂɔޏ��̕v�ƂȂ����̂̓A���t�H���\�E�t�H���E�A���S�����������A�ޏ��͔ނ����ɂ��܂��Ĉ�����悤�ɂȂ�B�����Ń`�F�[�U���͔ނ��E������B���N���`�A�͕��Q�����ӂ��A�W�����F���j�E�X�t�H���c�@�̏�A�y�U�[���}���B�`�F�[�U���̋]���ɂ���鎟�̒j�́A���R�ނ��낤�Ǝ@�������炾�����B�W�����F���j�E�X�t�H���c�@�̂ق����A���ł����N���`�A�������Ă����B�ޏ��́u���Ȃ����`�F�[�U�����E���Ă��ꂽ��A���͂��Ȃ��Ɉ�������܂��傤�v�Ɩ���B �@�W�����F���j�E�X�t�H���c�@�̓`�F�[�U���̌ق����b���̍U�������ނ��Ă��܂�����ŁA�`�F�[�U���Ƃ̌����̏���������B�����đ��ݍ����Ă����l�̋w�G���m�́A���̌����Ō݂��ɑ�������ɒǂ�����Ă��܂��B�Z�o�X�e�B�A�[�m������l�̖S�[���y�U�[���邩��^�яo���A��ɂ̓��N���`�A��������l���c�����B �y�f��]�z���u�f�A�E�t�B�����v���A1922�N��44���\�\�u�c�c���Z�̓_�ł͂��̉f��́A���|�I�ɂ��炵���B�ϋq�ɂ����Ƃ�������ۂ�^����̂́A�@���A���N�T���h���U���ɕ������o�b�T�[�}���ł���B�₯���ς��̈���̎�����Ƃ��Ẵ`�F�[�U����������R�����[�g�E�t�@�C�g���A���l�ɂ����ꂽ���Z��傢�Ɍ����Ă��邪�A���܂��̉��Z�S�̂ꂷ�郉�C�����������̂��c�O�ł���B�W���A���E�{���W�A�ɕ��������^�[���E�~���[�e���́A�����ȋC�i��������Ă���A�܂��������������R���b�N�ł���B�����ăf�B�[�e�����̃X�t�H���c�@�́A�����ΔނƑΏƓI�ł���B���D�w�ɂ��Č����ׂ����Ƃ́A���܂�Ȃ��B���A�[�l�E�n�C�g�͎��܁A�����ăA�j�^�E�x���o�[�͓�A�O�J���A�ǂ��B�ꂽ��ʂ����邪�A������j�D�����̉��Z�̗��h�ȏo���f���ɂ́A�����y�Ȃ��c�c�v�B ���u�L�l�}�g�O���t�v���A1922�N��828���\�\�u�c�c�I�Y���@���g�͋^���Ȃ��A�l�������������Ƃ����ŁA�����Ƃ������͎�i����g���Ďd���������B�܂��ނ́A���ŗ��h�ȍ�i����邽�߂ɁA�ǂ�ȉӏ��ł����������A������낻���ɂ��Ȃ������̂ŁA���̍�i�͋Z�p�I�Ȗʂł́A�f��̂�����\�������ݐs�����Ă���B�r�����Ȃ��s��ȕ��䑕�u�A�I�蔲���ꂽ�ō��̔o�D�����A�J��L������ߏւ⏬����̉ؗ킳�A�L���ȑz���͂��l�Ă����Z�b�g��⏕��i�[�[�����������ׂĂ��ꏏ�ɂȂ��āA���|�I�ɔ������A���h�ȉf�������o���Ă���c�c�v�B 1922.10.6 �w���@�j�i�\�\�i���̌��� Vanina--Die Galgenhochzeit�x �A���g�D�[���E�t�H���E�Q�[�����n�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[�i�X�^���_�[���̏����w���@�j�i�E���@�j�j�x�ɂ��j�A�B�e�F�t���f���b�N�E�t�[�Q���U���O�A���u�F���@���^�[�E���C�}�� �y�L���X�g�z�p�E���E���F�[�Q�i�[�i�g���m�̑��j�A�A�X�^�E�j�[���[���i���@�j�i�j�A�p�E���E�n���g�}���i�I�N�^�[���B�I�j�A�x�����n���g�E�Q�c�P�i�i�Ձj�A���E�[���E�����Q�i�i�Y���j�A���B�N�g���E�u�����i�����j�B �y���炷���z�\�N�I�ȑ��ł��镃�e�̃h���}�B�g���m�Ŕ������u������B����������͎x�z�҂̑��ɂ���āA�c���ɑł��j����B���̖����@�j�i�́A�����̎w���҂ƌ������邱�Ƃɂ���āA���̖����~�����Ƃ���B���͌�����F�߂�B���������ꂩ��V�����`���̑��q���i��Y�ɂ�����B�Ƃ����͍̂��Ɨ����͈��ɗD�悷�邱�Ƃ��A��ۓI�Ɏ������Ƃ������炾�����B 1922.11.13�i���{����1924.3.7�j �w�t�@���g�� Phantom�x �t���[�h���q�E�����i�E�ēA�V�i���I�F�e�A�E�t�H���E�n���u�B�g�E�g�E�g���@���h�t�X�L�[�i�Q���n���g�E�n�E�v�g�}���̓����̏����ɂ��j�A�B�e�F�A�N�Z���E�O���[�g�N���[�G���A���u�F�w���}���E���@�����A�G�[���q�E�`�F�����H���X�L�[�A���y�F���I�E�V���s�[�X �y�L���X�g�z�A���t���[�g�E�A�[�x���i���[�����c�E���{�^�F�s�s�������j�A�t���[�_�E���q�����g�i�ނ̕�e�j�A�A�E�h�E�G�Q�f�E�j�b�Z���i�����j�[�A�ނ̎o���j�A�g�E�g�E�g���@���h�t�X�L�[�i�t�[�S�A��j�A�J�[���E�G�g�����K�[�i���{�H�̃}�C�X�^�[�j�A�����E�_�[�S���@�[�i�}���[�A�ނ̖��j�A�O���[�e�E�x���K�[�i�V�����@�[�x�v�l�F�����j�A�A���g���E�G�g�z�[�t�@�[�i���B�S�`���X�L�[�j�A�C���J�E�O�����[�j���O�i�j�ݕv�l�j�A���A�E�f�E�v�e�B�i�ޏ��̖������b�^�ƃ��F���j�J�E�n�������j�A�A�h���t�E�N���C���i�S�폤�n�������j�A�I���K�E�G���Q���i�ނ̍ȁj�A�n�C�����q�E���B�b�e�i�p�����j �y���炷���z�s�s�������Ǝ��l�̈��̌��z�̕���B �@���[�����c�E���{�^�͓s�s�������ł���B�ނ͕�e�Ƃ��傤�����̐��b�����Ă���B�ނ͖��z�ƂŁA��������Ǐ����A���������Ă���B�ނ͗T���ȓS�폤�̖����F���j�J�E�n�������������Ă��邪�A����̉Ԃł���B�������{�H�̃}�C�X�^�[���ނ̎��̂��߂ɏo�ŎЂ������Ă�낤�Ɩ��Ă��ꂽ���ƂɗE�C�Â����āA�ނ͎����������厍�l�ɂȂ����悤�ȋC�ɂȂ�B�����Ŕނ͎����̃L�����A�����藧�Ă邽�߂ɁA�������c��ł���f��̃V�����@�[�x�v�l����A���������B���ꂩ��ނ͓S�폤�̂Ƃ���ɍs���āA����������Ă��郔�F���j�J�ɋ�������B�������C�ł������Ă���̂��ƁA����o�����B���C������Ŕނ̓����b�^�ɏo��B�ޏ��̓��F���j�J�E�n�������ɉZ��ł���悤�Ɍ�����B�����Ŕނ͔ޏ��̂��߂ɂ��������������A����Ŏ����̗��̃t�@���g����Y��悤�Ƃ���B���̂�����ނ͏f�ꂩ�������Ă����B���B�S�`���X�L�[�Ƃ������҂��ނ�������āB�f��̃V�����@�[�x�v�l�̂Ƃ���ɉ������邱�Ƃ��v�悷��B�����������Ƃ��A��l�͎v���������v�l�Əo��A���B�S�`���X�L�[�͕v�l���E���Ă��܂��B��l�͑ߕ߂���A�Y�����Ń��[�����c�E���{�^�͂���ƌ����ɖڊo�߂�B�ߕ������Ɣނ́A�����Ɣނɑ��Đ��������Ă����A���{�H�̖��}���[�ƌ�������B �y����z�f��̓Q���n���g�E�n�E�v�g�}��60�̒a�������L�O���āi��1922�N11��15���A60�Βa�����j�A�u���X���E�Ńv���~�A��f����A��T�Ԍ�x�������ŋL�O��f���ꂽ�B���]�̑�䏊�A���t���[�g�E�P�������A�����B 1922.12.3 �w������钆�܂� Von Morgen bis Mitternacht�x �J�[���E�n�C���c�E�}���e�B�� K.H.Martin�ēA�V�i���I�F�w���x���g�E���g�P�A�J�[���E�n�C���c�E�}���e�B���i�Q�I���N�E�J�C�U�[�̃h���}�ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�z�t�}���A���u�F�A���x���g�E�l�p�b�n �y�L���X�g�z�G�����X�g�E�h�C�b�`���i�o�[�W�j�A�G���i�E�����i�i�ނ̍ȁj�A���[�}�E�o�[���i���m��ʏ����j�A�n���X�E�n�C�����q�E�t�H���E�g���@���h�t�X�L�[�A�t���[�_�E���q�����g�A�G���U�E���@�[�O�i�[�A�G�[�x���n���g�E�����[�f�A���[�E�n�C���A�t�[�S�E�f�[�u���[���A���b�e�E�V���^�C���ƃ}���[�E�c�B���}�[�}���E�o���[ �y���炷���z�������A�E����炸�A���~�������Ȗڂ��ŁA�o�[�W����s�̃J�E���^�[�ɍ����Ă���B�����ł͑�ׂ��������ە����A�l�������Ă���B���̔w��ɂ́A��ꂽ���ƕn���ɓ�����ꂽ��e�ƒ������̑c������������A�o�[�W�݂̂��߂Ȑ���������B�s�ς́A�i���ɓ����L���B�o�[�W�̓��ɉΉԂ�����B�ނ͋�s�̋��𒅕����A�p�������B�Ƒ��͗��ɑł��ꂽ�悤�ɋ������A�x�@���ނ̍s����ǂ��B�o�[�W�͂����������Ȑ��������߂ď��炷��B�����A���w�A����P�����E�̒����A����o�[�W�͂�イ�Ƃ����g�Ȃ�ŕ������A�u�Z���Ԏ��]�ԋ����v�̃M�����u���ɁA�����̂悤�ɘQ���B�����Ċy�����M���I�Ȗ��̌����悤�Ƃ��邪�A�ؗ�Ȑ����͔ނ̐S�����ނ��݁A�������̎p�͂���ꂱ���ׂƂȂ�B�[���̉��Ŕނ͎����̉e�ɂނ��ł���āA�ނ͋~���R���P�}�V�[���̂Ƃ���}���B���̖钆�A�ނ�d���̒��Ɏ��_������āA�ǂ������w�������B�����o�[�W�ɂ͎��_���ǂ����w���Ă���̂��킩��Ȃ��B�x�@�̎肪����B�ǂ��߂�ꂽ�ނ́A���Ƀu���[�j���O���e�ŁA�u���̕Ԏ��������̋��̃V���c�̒��ɑł����ށv�B�ނ͘r���Ђ낰�āA��������Ď��ʁB�u������钆�܂Łv�̃h���}�͏I���B �y����z�f��͓��{�ł�����f���ꂽ�B |
|
| 1923 | |
| 1923�i���{����1924.7.4�j �w�������� Alles für Geld�x ���C���z���g�E�V�����c�F���ēA�V�i���I�F�n���X�E�N���[���A���h���t�E�V���g���b�c�A�B�e�F�A���t���[�g�E�n���[���A���[�g���B�q�E���b�y���g �y�L���X�g�z�G�~�[���E���j���O�X�iS. I. ���b�v�j�A�w���}���E�e�B�~�q�i�t���[�g�E���b�v�j�A�_�O�j�[�E�[�����F�X�i�A�X�^�j�A�w���x���g�E���B���^�[�V���^�C���i�t�H���E���[���v�l�j�A���@���^�[�E�����i�w�����[�E�t�H���E���E�t�F���j�A�N���g�E�Q�b�c�i�G�[���n���g�j�A�}���A�E�J�����f�[�N�i�V�V�[�j�A�p�E���E�r�[���X�t�F���g�A�t�F���[�E�W�[�N���A�E�����q�E�x�^�b�N�A�G�����X�g�E�V���^�[�����i�[�n�o�E�A�[�A�n�C�����q�E�V�����[�g�A���C���z���g�E�V�����c�F���A�}�b�N�X�E�N���[�l���g �y����z��������̍H�Ɖ�S.I.���b�v�͗��܂�Ƃ����m��Ȃ��×~�ŁA�����Ɩ��̂��Ƃ�O���ɒu���Ă���B�����ނ͎������ł͂܂����B�ނ̑��q�ŗL���ȃ��[�T�[�̃t���[�g���A���e�ɐӔC������Ǝv�킹�鎖��ŁA���̎�����B���e�͖@��ɗ��������B�����Ė��߂ɂ͂Ȃ������A�a�C�̕�e���ŕa����̂ɕK�v�Ȃ������H�ʂ���ړI�����Ŕނƌ��������Ȃ̃A�X�^�́A�ނƗ�������B�i�N���J�E�A�[p131���j 1923�i���{����1924.6.27�j �w�G�N�X�v���[�W���� Explosion�x �J�[���E�O���[�l�ēA�B�e�F�J�[���E�n�b�Z���}�� �y�L���X�g�z���A�[�l�E�n�C�g�A�I�C�Q���E�N���b�p�[�A�J�[���E�f�E�t�H�[�N�g�i�N���J�E�A�[249���j 1923�i���{����1924.11.14�j �w�v�Џo Alt-Heidelbeg�x �n���X�E�x�[�����g�ēA�V�i���I�F�n���X�E�x�[�����g�i���B���w�����E�}�C���[���t�F���X�^�[�̃h���}�ɂ��j�A�B�e�F�O�C�h�E�[�[�o�[ �y�L���X�g�z�p�E���E�n���g�}���i�J�[���E�n�C���c�F�c���q�j�A�G�[�t�@�E�}�C�i�P�e�B�[�j�A���F���i�[�E�N���E�X�i���b�g�i�[���m�j�A�I�C�Q���E�O���N�A�t���b�c�E���F���g�n�E�[���A���B�N�g���E�R���[�j �y���炷���z������������̐̂̃h�C�c��ɁA�n�C�f���x���N��w�ɗ��w���Đt��搉̂��Ă������q���A�����̎��ŗ��w��ł�����A�A�����ĉ��ʂ��p���A��������Ȃ����X���߂��������ɁA�����̔O�ɋ���Ă�����x�v���o�̃n�C�f���x���N��K�˂邪�A���łɐ�t�̖��̐Ղ͏��������Ă����B �y����z�Z���`�����^���Ȓʑ��h���}�Ƃ��Ĕ��Ȑl�C�����̂ŁA�ĎO�Ďl�ɂ킽���ĉf�扻���ꂽ�B�@ 1923�i���{����1924.3.7�j �w���R�m Der Steinerne Reiter--Eine Filmballade�x �t���b�c�E���F���g�n�E�[���ēA�V�i���I�F�t���b�c�E���F���g�n�E�[���i�e�A�E�t�H���E�n���u�̃A�C�f�A�ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�z�t�}�� �y�L���X�g�z���h���t�E�N���C�������b�Q�A�i�R�̎�j�A���[�c�B�G�E�}���n�C���i�r�������j�A�O�X�^�t�E�t�H���E���@���Q���n�C���i��l�j�A�t���b�c�E�J���p�[�X�A�Q�I���N�E���[���A�G�~�[���A�E�E���_�A�O���[�e�E�x���K�[�A���B���w�����E�f�B�[�Q���}�� �y���炷���z�u�R�̎�v�͋���ȗ͂����\�N�Ƃ��āA�_����������悵�Ă���B�_�������͗����オ�邪�A�u�R�̎�̕����ɑł��j����B�����ŗr����������ɔE�э���ŁA�ނ��h���E�����Ƃ���B�Ƃ��낪�u�R�̎�v�������Ȑl���ƒm���āA�ޏ��͔ނɍ��ꍞ�ށB�����Ĕ_����������ɉ����ė���ƁA�ނ������ē��������Ƃ���B�u���������K���ł�����́A�ނƋ��Ɏ���邱�Ƃ��I�v�Ɣޏ��͌����B����Ɨ�����l�̏�ɗ����A��l�͉��Ɖ����B�i�N���J�E�A�[p112�j 1923 �w�G���K�f�B���̌ώ�� Fuchsjagd im Engadin�x �A���m���g�E�t�@���N�ē� �y����z�t�@���N�́u�R�x�f��v�̂͂���B�i�N���J�E�A�[p112�j 1923�i���{����1925.5.29�j �w�ܔM�̏ Die Flamme�x �G�����X�g�E���r�b�`���ēA�V�i���I�F�n���X�E�N���[���i�n���X�E�~�����[�̌���ɂ��j�A�B�e�F�e�I�h�[���E�V���p�[���N�[���A�A���t���[�g�E�n���[�� �y�L���X�g�z�|�[���E�l�O���i�C���F�b�g�j�A�w���}���E�e�B�~�q�i�A���h���j�A�A���t���[�g�E�A�[�x���i���E�[���j�A�q���f�E���F���i�[�i���C�[�Y�j�A�t���[�_�E���q�����g�i�}���[�E���@�U���j�A���[�R�v�E�e�B�[�g�P�i�u���W���A�j�A�}�b�N�X�E�A�[�_���x���g�i�W���[�i���X�g�j�A�t�F���f�B�i���g�E�t�H���E�A���e���i�Ќ�a�m�j�A�C�G�j�[�E�}���o�i�A���h���̕�e�j �y����z�����O���I�̃p���ɂƂ����A���C�ȎႢ��ȉƂƁA�����ȍ��������Ă��鏩�w�Ƃ̗�������B��ȉƂ͏��w�̋��ɑ��������̂́A�����̃u���W���A�I�}���S���̂Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̂��ߔނ̐V�����͖ʓ|�Ȃ��̂ƂȂ�A��������ނ͏��w�̋����瓦���o���A���i�ł͂��邪�����Ă����e�̂Ƃ���֖߂�B 1923. ? �w���e�@�̃~�X�e���[ Mysterien eines Friseursalons�x 1923.2.1 �w��t�̐� Ein Glas Wasser�x ���[�g���B�q�E�x���K�[�ēA�V�i���I�F���[�g���B�q�E�x���K�[�A�A�h���t�E�����c�i���[�W���[�k�E�X�N���u�̊쌀�ɂ��j�A�B�e�F�M�����^�[�E�N�����v�A�G�[���q�E���@�V���l�b�N �y�L���X�g�z�}�f�B�E�N���X�`�����X�i�A���i�F���܁j�A�w���K�E�g�[�}�X�i�A�r�K�C���j�A�n���X�E�u���E�[���F�b�^�[�i�W�����E�E�C���A���E���T���j�A���[�c�B�G�E�w�[�t���q�i�}�[���o�����ݔ܁j�A���h���t�E���b�g�i�[�i�w�����[�E�{�����O�u���[�N���j�A�t�[�S�E�f�[�u���[���i�g���E�b�h�j�A�n���X�E���@�X�}���i���`���[�h�E�X�R�b�g���j�A�u���[�m�E�f�J�����i�g�[�V�B��݁j�A�}�b�N�X�E�M�����X�g���t�i�g���v�\���j �y���炷���z�p���{��ł̗������߂���A�d�쌀�B�X�y�C���p���푈����̃����h���B�A�������̓�l�̏d�v�ȕ⍲���͂܂��������̖ړI���\���Ă���B�{�����O�u���[�N���̓t�����X�Ƙa�������Ԃ��Ƃ�~���A�}�[���o�����܂͂����]�܂��A���̂��߃t�����X���g�ɉy���������̂��A�J��Ԃ��W���悤�Ƃ���B�{��ɃW�����E�E�C���A���E���T���Ƃ������̎Ⴂ�j������ė������A�����͂₪�Ĕނɑ�ύD�ӂ������悤�ɂȂ�B���̂��ߔނ͂����܂��̒��Ɂu���[�h�E�W���[�i���v�̘N�ǎ҂ɏ��i����B�}�[���o�����܂����T���ɏH�g�𑗂�B�����ĂƂ��Ƃ������̎Ⴂ�����̃A�r�K�C���܂ł��A���������T���ɗ�������B���̍����������C�o���W���������A����������̖ړI�̂��߂ɗ��p���邱�Ƃ�S���Ă���̂́A�{�����O�u���[�N��������l�ł���B�ނ͑�σX�����̕x�V�Y�ɏ�肾���A���C�o���W�a�ɂ����߂������łȂ��A���T���ƃA�r�K�C���̂��߂̍K�������v���Ă�����B 1923.2.22 �w�n�� Erdgeist�x ���I�|���g�E�C�G�X�i�[�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[�i���F�[�f�L���g�̍ŏ��́w�����x���ɂ��j�A�B�e�F�A�N�Z���E�O���[�g�N���[�G�� �y�L���X�g�z�A�X�^�E�j�[���[���A�A���x���g�E�o�b�T�[�}���A���h���t�E�t�H���X�^�[�A�A���N�T���_�[�E�O���[�i�n�A�n�C�����q�E�Q�I���Q �y����z�ܐl�̒j�̊Ԃɗ��~�]�Ɏx�z���ꂽ���̕���A�O�l�����ʁB 1923.2.26 �w�\�\���Ɨ����߂���Â��h���} Der Schatz--Ein altes Spiel um Gold und Liebe�x �f�E�v�E�p�v�X�g�ēA�V�i���I�F�f�E�v�E�p�v�X�g�A���B���[�E�w�j���O�Y�i���h���t�E�n���X�E�o���`���̕���ɂ��j�A�B�e�F�I�b�g�[�E�g�[�o�[�A���u�F���[�x���g�E�w�����g�A���@���^�[�E���[���q�A���y�F�}�b�N�X�E�h�C�b�`�� �y�L���X�g�z�A���x���g�E�V���^�C�������b�N�i�o���^�U�[���j�A���[�c�F�E�}���n�C���i�x�A�g���b�c�j�A�C���J�E�O�����[�j���O�i�A���i�j�A���F���i�[�E�N���E�X�i���[���E�X���F�e�����c�j�A�n���X�E�u���E�[���F�b�^�[�i�A���m�[�j �y���炷���z�����t�o���^�U�[���͍Ȃ̃A���i�A���̃x�A�g���b�c�A����ɏ���̃��[���ƈꏏ�ɁA����I�[�X�g���A�̐X�̉��ɂ���Â��ƂɏZ��ł���B���킳�ɂ��A���̉Ƃ̊�b�ǂ̉��ɁA�g���R�푈����̕����߂��Ă���B�����Ń��[���͂Ђ����ɂ��̕����悤�Ƃ���B�Ⴂ���H�t�A���m�[������ė��āA�x�A�g���b�c�Ɍ��z����B�����Ĕނ�������B�A���i�ƃ��[���́A�ז��ȃA���m�[���n�����悤�Ƃ��邪�A�×~���炨�݂����m�ő����n�߂�B�����ăA���m�[�ƃx�A�g���b�c���O�o���Ă���ԂɁA�~���������[���͖����ɂȂ��āA�Ƃ̊�b����w�[���@�艺����B���̂��߂Ƃ��Ƃ��Ƃ��|�A�Z��ł����҂݂͂ȁA���̉��ɖ��܂��Ă��܂��B�O�o���Ă��Ė��E�������A���m�[�ƃx�A�g���b�c�́A�V�����������n�߂邽�߂ɁA�����𗧂�����B 1923.3.21 �w�p�K�j�[�j Paganini�x �n�C���c�E�S���g�x���N�ēA�V�i���I�F�n�C���c�E�S���g�x���N�i�p�E���E�o�C���[�̃��e�B�[�t�ɂ��j�A�B�e�F�V���e�t�@���E���[�����g �y�L���X�g�z�R�����[�g�E�t�@�C�g�A�G�[�t�@�E�}�C�A�O���[�^�E�V�����[�_�[�B �y����z�V�˓I���@�C�I���j�X�g�A�p�K�j�[�j�̗�������B 1923.3.31 �w���C���ߜƋ� Fidericus Rex�x�i��O���E��l���j �A���c�F���E�t�H���E�`�F���s�[�ē� �y�L���X�g�z�I�b�g�[�E�Q�r���[���A�G���i�E�����i�A�G�h�D�����g�E�t�H���E���B���^�[�V���^�C�� �y����z��ꕔ�E���1922�N1��31����f�B 1923.5.25 �w�V���y�b�T���g�̗��ĉ� Das Wirtshaus im Spessart�x �y����z���B���w�����E�n�E�t�̃����w���w�₽���S�x�ɂ��f��A�x�������E�N�[�A�t�����X�e���_���̉f��فu�A���n���u���v�ŕ���B1957�N�Ƀ����C�N���ꂽ�B 1923.6.12 �w�H�T�̐l Der Mensch am Wege�x ���B���w�����E�f�B�[�e�����ēA�V�i���I�F���B���w�����E�f�B�[�e�����i���I�E�g���X�g�C�̕���ɂ��j�A�B�e�F���B���[�E�n�[�}�C�X�^�[ �y�L���X�g�z�n�C�����q�E�Q�I���Q�A�A���N�T���_�[�E�O���[�i�n�A���B���w�����E�f�B�[�Q���}���A�G�~�[���G�E�E���_�A�}���[�l�E�f�B�[�g���q �y����z�E�l�̌��^����������C�����߂��鑺�����B�f�B�[�e�����ŏ��̊ē�i�ŁA�}���[�l�E�f�B�[�g���q���x��q�Ƃ��ăf�r���[�B 1923.8.24 �w���B���w�����E�e�� Wilhelm Tell�x ���h���t�E�h�D�I���X�L�[�ēA�V�i���I�F���B���[�E���[�g�i�t���[�h���q�E�V���[����̃h���}�ɂ��j �y�L���X�g�z�R�����[�g�E�t�@�C�g�A�P�[�e�E�n�[�N�A�I�b�g�[�E�Q�r���[���A�G�[�h�D�����g�E�t�H���E���B���^�[�V���^�C���A�G���i�E�����i�E �y����z�x�������̉f��فu�}�������n�E�X�v�ŁA����f��Ƃ��ĕ���B 1923.8.31 �w�t�̖ڊo�� Frühlings Erwachen�x �k�E�R�����A�i�E�t���b�N�ēA�V�i���I�F�i�t�����N�E���F�[�f�L���g�̌���ɂ��j �y�L���X�g�z�w���^�E�~�����[�A�i�E�G�b�v �y����z�x�������̉f��فu�A���n���u���v�ŕ��� 1923.8.31 �w�u�b�f���u���[�N�Ƃ̐l�X Die Buddenbrooks�x �Q���n���g�E�����v���q�g�ēA�V�i���I�F�A���t���[�g�E�t�F�P�[�e�A���C�[�[�E�n�C���{�������P���r�b�c�i�g�[�}�X�E�}���̏����̃��e�B�[�t�ɂ��j�A�B�e�F�G�[���q�E���@�V���l�b�N�A�w���x���g�E�V���e�t�@�� �y�L���X�g�z�y�[�^�[�E�G�b�T�[�A�A���t���[�g�E�A�[�x���A�q���f�K���g�E�C���z�t�A�}�f�B�[�E�N���X�`�����X �y����z�g�[�}�X�E�}���̍�i�̍ŏ��̉f�扻�B�x�������́u�^�E�G���e�B�[���p���X�g�v�ŕ���B 1923.9.27 �w���ꂳ��A���Ȃ��̎q�����Ă�ł��� Mutter�ADein Kind ruft�x �y����z�V���e�t�@���E�c���@�C�N�̏����w�R�炵�����Ȃ�閧 Das brennenes Geheimnis�x�ɂ��f��A�x�������́u�}�������n�E�X�v�ŕ��� 1923.10.16 �w�킭�e�\�\��̌��o SCHATTEN---Eine nächtliche Halluzination�x �A���g�D �[���E���r�]���ēA�V�i���I�F���h���t�E�V���i�C�_�[�A�A���g�D�[���E���r�]���i�A���r���E�O���E�̃A�C�f�A�ɂ��j�A�B�e�F�t���b�c�E�A���m�[�E���@�[�O�i�[�A���y�F�G�����X�g�E���[�Q�A���u�ƈߏցF�A���r���E�O���E �y�L���X�g�z�t���b�c�E�R���g�i�[�i�v�j�A���[�g�E���@�C���[�i�ȁj�A�O�X�^�t�E�t�H���E���@���Q���n�C���i���l�j�A�A���N�T���_�[�E�O���[�i�n�i�e�G�ŋ��t�j�A�t���b�c�E���X�v�i���g���j�A�����[�E�w���_�[�i�����j�A�}�b�N�X�E�M�����X�g���t�A�I�C�Q���E���b�N�X�A�t�F���f�B�i���g�E�t�H���E�A���e���i��l�����j �y���炷���z�i����a���w�҂��ϑz�̎��i�ɂ����镨��j�B�c�ɂ̍��s�ȉ��~�B�[���̔����̒��ŁA��l�̒j�����납��A��̊K�̑��ӂʼn��~�̎�l�Ǝ�w�����i���Ă���p������B���̏�����ŁA�ނ͐H���ɏ��҂���Ă��q��������������̂�����B���~�̒��ɓ���ƁA�����͂��q�����Ǝ�l���̐l�Ԃ��A��w�߂�����m�邱�ƂɂȂ�B�܂�v�Ȃ͎�w�̈��l�����Ƃ���ɎO�l�̎^���҂������}���Ă���B�v�͂��ݏグ�Ă��鎹�i�̔O�ɋ���āA���l�����������̍Ȃ̉��Ō������A�ȂƗx��p����Œǂ��B���m��ʊώ@�҂͌��ւ̂Ƃ���Ɏp�������āA�����𗷂̉e�G�ŋ��t���Ǝ��ȏЉ��B�e�G�ŋ��t������Č����������H�����肰�Ȍ|�ɋ����A�������Ȃ�����A���~�̎�l�͉e�G�ŋ������������邽�߂ɁA�ނ��������ꂽ�B�H���̌エ�q�����̓T�����ɏW�܂����B�������e�G�ŋ��̎�������Ă���ԁA�ނ�͏�̋����B�G���X�̂ւ̊��҂����S�ɔނ�̐S���߂Ă����B����Ɖe�G�ŋ��t�͔ނ�ɍÖ��p�������āA�N���ނ������ӎ��̗~�]�����R�Ɋy����ł���Ƃ������z����������B�v�͈��l�ƕ��i���Ă���Ȃ�͂܂��A���i�ɋ����ď��g���ɍȂ����т��ɂȂ����A�l�l�̏�l�����ɁA�Ȃ����Ŏh���т����A����Ƃ����玀�����邩�A�I���𔗂����B��l�����͖��͂Ȕނ̍Ȃ����Y�����B����ƕv�͂����苃���Ȃ��炭���܂ꂽ�B��l�����͂������ނ�e�͂����A���������ɋ������ꂽ�s���̏����Ƃ��āA�ނ𑋂�����蓊�����B�ނ͓]�����Ď��B�e�G�ŋ��t�͂��q�����ɁA���̋���ׂ��h���}���A�ނ�̃t���X�g���[�V�������炫���Փ��̎����Ƃ��đ̌������Ă���A�ނ���Ăѐ��C�ɋA�点���B �@�����č��₷�ׂĂْ̋����͏����������B��w�͍��∤�炵�������ŁA�]���ȍȂɕϐg���Ă����B���͂������i���闝�R�̖����Ȃ����v�́A�e�G�ŋ��t�ɂ����Ղ��V��^�����B��l�����͂͊ق�����A�e�G�ŋ��t������ɑ������B�ق̎�l�Ɣނ̍Ȃ͈���̂����������i�����Ȃ���A���������čs�����q�������A�����猩�������B �y����z�x�������́u�m�����h���t����v�ŕ���ꂽ���̍�i�́A�A���r���E�O���E�̃A�C�f�A�ƃZ�b�g�ɂ��A�\����`�̓T�^�ƌ�����f�悾�����B 1923.10.23 �w�����P�� Austreibung�x �t���[�h���q�E���B���w�����E�����i�E�ēA�V�i���I�F�e�A�E�t�H���E�n���u�i�J�[���E�n�E�v�g�}���̌���ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�t���C���g �y�L���X�g�z�J�[���E�Q�b�c�i�V���^�C���[�F���e�j�A�C���J�E�O�����[�j���O�i�V���^�C���[�F��e�j�A�I�C�Q���E�N���b�p�[�i�V���^�C���[�F���q�j�A���[�c�B�G�E�}���n�C���i�A���l�j�A�A�E�h�E�G�Q�ŁE�j�b�Z���i���h�~�[���j�A���B���w�����E�f�B�[�e�����i���E�A�[�F��l�j�A���[�x���g�E���t���[�i�q�t�j�A�G�~�[���G�E�N���c�i���j�q�j�A���[�R�v�E�e�B�[�g�P �y���炷���z���炳�т����_��Ŕ_�v�̃V���^�C���[�́A�V�������e�ƍŏ��̌����Ő��܂ꂽ���A���l�ƕ�炵�Ă���B�ނ͔������Ⴂ���h�~�[���ƍč����邪�A���h�~�[���̖ړI�͔ނ̋��������B�ޏ��͂����ɎႢ��l�̃��E�A�[�ƒʂ���B�����Ĉ��l�ƈ�w�߂Â����߂ɁA�v�̃V���^�C���[��������āA���̑��̗������킹��B�ނ͏��m���āA�_��蕥���B�����ނ͂����Ɋ�݂ɋC�Â��āA���E�A�[��ł��E���B �y����z�x�������E�N�[�A�t�����X�e���_���́u�E�[�t�@����v�ŕ���B 1923.10.29 �w���@ Das alte Gesetz�x E.A.�f���|���ēA�V�i���I�F�p�E���E���[�m�i�n�C�����q�E���E�x�̉�z�L�ɂ��j�A�B�e�F�e�I�h�[���E�V���p�[���N�[�� �y�L���X�g�z�w�j�[�E�|���e���A�G�����X�g�E�h�C�b�`���A���F���i�[�E�N���E�X�A�A�������E�����t�X�L�[ �y����z���̈ӎu�ɔ����āA�o�D�ɂȂ邽�߂ɃQ�b�g�[�����������r�̑��q���A�����̈�����烔�B�[���́u�u���N����v�̔o�D�ƂȂ�A���Ƃ��a�����镨��B 1923.10.29�i���{����1925.1.28�j �w�߂Ɣ��@Raskolnikow�x ���[�x���g�E���B�[�l�ēA�V�i���I�F���[�x���g�E���B�[�l�i�t���[�h���E�h�X�g�G�t�X�L�[�̏����w�߂Ɣ��x�ɂ��j�A�B�e�F���B���[�E�S���g�x���K�[�A���u�F�A���h���C�E�A���h���C�G�t �y�L���X�g�z�O���S���[�E�t�}���i���X�R���j�R�t�j�A�~�q���G���E�^���V���m�t�i�}�������h�t�j�A�}���A�E�Q���}�m���@�i�}�������h�t�̍ȁj�A�p�[���F���E�p�����t�i�\�R�����j�A�}���A�E�N���V���m�t�X�J���i�\�[�j���j�A���F���E�g�[�}�i�A�����[�i�j �y���炷���z�S���I�ƍ߉f��B�w���̃��X�R���j�R�t�͎����̃A�����[�i�̓X�ŁA�����E�l�̍߂�Ƃ����B���̍ۃA�����[�i�̖��ɏo��������A�ޏ����E�����B���炭�o���Ă���ނ͈����Ă��閺�ɂ�������������B����̓A�����ő�������l�Ƃ��̂��߂ɋC�Ⴂ�ɂȂ�����e�Ƃ̖��\�[�j���������B�����̉𖾂��ϑ����ꂽ�\�R�����̓��X�R���j�R�t���^�����B�������@���I���M�ƂƂ��āA����������č߂̏��������悤�Ƃ����w���́A����������Ă���悤�Ɍ������B�������\�[�j�����ނ̐S�����āA�����̍߂�F�߁A���̏����������ɉۂ���C�����ɂ������B 1923.11.5 �w�C�����i�L���X�g�̈ꐶ�jI.N.R.I.�x ���[�x���g�E���B�[�l�ēA�V�i���I�F���[�x���g�E���B�[�l�A�B�e�F�A�N�Z���E�O���[�g�N���[�G���A���[�g���B�q�E���b�y���g�A���C�}�[�E�N���c�F �y�L���X�g�z�O���S�[���E�N�}���A�w�j�[�E�|���e���A�A�X�^�E�j�[���[���A���F���i�[�E�N���E�X �y����z�����ɂ�郂�j�������^���f��B2000�l�̃G�L�X�g�����F�����B�����ɎR�����ꂽ�B�i�N��L54�j 1923.11.6 �w���̔ߌ� Trago*die der Liebe�x �W���[�E�}�C�ēA�V�i���I�F���I�E�r�����X�L�[�A�A�h���t�E�����c�A�B�e�F�]�[�t�X�E���@���Q�[�G�A�J�[���E�v���[�e�� �y�L���X�g�z�~�A�E�}�C�A�G�~�[���E���j���O�X�A�C�_�E���X�g�B ����F�t�����X�M�����E�̔ƍߒT�㕨��B 1923.11.29�i���{����1925.9.18�j �w���f�̊X�\�\�����̉f�� Die Strasse --Der Film einer Nacht�x �J�[���E�O���[�l�ēA�V�i���I�F�J�[���E�O���[�l�A�����E�X�E�E���M�X�i�J�[���E�}�C���[�̍\�z�ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�n�b�Z���}���A���u�F�J�[���E�Q���Q �y�L���X�g�z�I�C�Q���E�N���b�p�[�i�j�j�A���[�c�B�G�E�w�[�t���q�i�ނ̍ȁj�A�A�E�h�E�G�Q�f�E�j�b�Z���i���w�j�A���I���n���g�E�n�X�P���i�c�Ɏҁj�A�A���g���E�G�g�z�[�t�F�[�i���w�̃q���j�A�}�b�N�X�E�V�����b�N�i�Ӑl�j�A�n���X�E�g���E�g�i�[�Ǝq���U�b�V�� �y���炷���z����錘���ȋ�s�o�[�W ���Ȃ̂Ƃ���������āu�X�v�ɏo�邪�A����������Ė߂��ė���Ƃ����A���R���Ă����ǂ͓���̐����ɓK������b�B �@�X�H�͒�����ӂ܂ŁA�����̕����̓V��ɉe�̂悤�ɉf���Ă���̂����Ă����l�̏��s���̐S��U���B�����̕����ɂ͂��яL�����͋C���x�z���Ă���B�X�H�̃��B�W�������A���藧�Ă��������ނ̑f���炵�����̂ŗU�f����B��������߂�Փ��ɋ�藧�Ă��āA�����Ȃ����s���̑����́A���̋l�܂�Ƃ̏����E���o�āA���p�I�ȊX�H�֓��ݏo���B�����ɂ́A�J�[���E�O���[�l�̉f���̃g���b�N�Z�p�����ݏo�����A�_�_�C�Y���I�ȑ�s�s�����̃��B�W�����A���E�[���E�n�E�X�}�����������������B�W�������x�z���Ă���B �@���s���̑����͂����}���B�X�p�ɏ��w�������Ă���B���̏��w�ɗU���Ĕނ́A�_�_�I�C���t���l���ŏ���ꂽ�_���X����ɘA�ꍞ�ށB�����Ŕނ͔ޏ��́u�F�����v�Ə̂����l�ɒj�ɏЉ���B��l�͂��̏��̃q���B������l�͂��̑��_�ł���B�ނ炪�������A�g�����v�̂������ܓq���ŁA�y�e���ɂ����悤�Ƃ��Ă���Ƃ���ցA�����łӂ���D����C�Ɍ����т炩���Ȃ���A��l�̓c�Ɏ҂�����ė��āA���Ԃɉ����B���҂͑���������c�Ɏ҂�����A��������ނ����낤����B�����čŌ�̓y�d��ŁA���҂͓c�Ɏ҂��E���Ă��܂��A���ꂩ�珩�w�����Ƃ�ɂ��āA���ȃT��������o�Ă����������E�l�҂Ǝv����悤�Ɋ�ށB�x�@�ɘA�s���ꂽ�����͓r���ɕ��Ă��܂��A������i���邱�Ƃ���v�����Ȃ��B��l�Ɩ[�ɓ����ꂽ�ނ͐�]���āA�l�N�^�C���������A����Ŏ��݂낤�Ƃ���B�������^�Ɛl�������������߁A�ނ͎ߕ������B�ނ͋ł̊X�H�����߂������B�l�e���Ȃ��A���ɐ�����Ď��������܂��������Ɠ����Ă��邾���ł���B�Ƃɖ߂����ނ����Ԃɓ���ƁA�ނ̍Ȃ͒g�߂��X�[�v�������ƃe�[�u���̏�ɒu���B�j�͍���A�����Ƒ����X�[�v���܂߂āA���ʼnƒ�̊Ǘ��ɏ]���C�ɂȂ�B�K�^�ȋ��R���������~���Ă��ꂽ�Ɗ��ӂ��Ă���ނ́A�����X�̗U�f�ɗU���邱�Ƃ͂Ȃ��B �y����z�X�H�����ׂ��Q�����O�̐��E�A�ƒ�������̏�Ƃ���u�X�H�f��v�̓T�^�B�i�N��L54�j 1923.12.5 �w����ꂽ�C Der verlorene Schuh�x ���[�g���B�q�E�x���K�[�ēA�V�i���I�F���[�g���B�q�E�x���K�[�i�����w���u�D���Ԃ�v��E�ET�EA�E�z�t�}���ƃu�����^�[�m�̃��e�B�[�t�ɂ��j�A�B�e�F�M�����^�[�E�N�����v�A�I�b�g�[�E�x�b�J�[�A���u�F���h���t�E�o���x���K�[�A�}���A�E���B�����c�A���y�F�O�C�h�E�o�M�[�� �y�L���X�g�z�w���K�E�g�[�}�X�i�}���[�j�A�p�E���E�n���g�}���i�A���[�����E�t�����c�j�A�}�f�B�E�N���X�`�����X�i���B�I�����e�j�A�I���K�E�`�F�z���@�i�G�X�e���j�A�w���}���E�e�B�~�q�i�V���^�C�X���V���g���X�����O�j�݁j�A���I���n���g�E�n�X�P���i��݁F�n�o�N�b�N��\�Z���j�A�G�~�[���G�E�N���c�i�A���C�W�A�����j�A�p�E���E�R�����[�g�E�V�������^�[�i�A�i�X�^�[�V�������j�A���F���i�[�E�z���}���i�G�[�P���}�����݁j�A���[�c�B�G�E�w�[�t���q�i�x�����[�g���ݕv�l�j�A�}�b�N�X�E�M�����X�g���t�i�N�R���j�݁j�A�t���[�_�E���q�����g�i���j�A�Q�I���N�E���[���i�����j�A�Q���n���g�E�A�C�]�C���g �y���炷���z �@����j����߂���x�ڂ̌����������B��������x�ڂ̍Ȃ͐����ŁA��x�ڂ̌����Ő��܂ꂽ�ނ̎q���ɂƂ��ẮA�炢�����̎n�܂肾�����B�Ƃ����̂͑P�ǂȕ��e�͎�X�����A���̎q�����p�ꂩ��\���Ɏ���Ă��Ȃ��������炾�����B�����ŕ��e�Ǝq���͂��̋�Y��Â��ɐS�̒��ɂ��܂����B���������̋�Y�̓��S�̐Â����́A���ق̐��E�ɒʂ��铹�̓����������B��n�̕�e�̕�̂Ƃ���ő�ꂪ�҂��Ă����B���͂Ђ����ɁA��ɂ�������Ǝ��������Ă��āA����ł��܂��܂ȖԂ�a���ł������A���̖Ԃ͂��܂��܂Ȏ����▂�p�I�ȋ����ɖ����Ă��āA�������������ƁA���Ƌ�Y���I����āA�K���ւ̔������̂��ƒ��ˏオ��̂������B �y����z�����w���f��B |
|
| 1924 | |
| 1924�i���{����1925.9.28�j �w���̒��̏� Die Frau im Feuer�x �y����z�N���J�E�A�[p131�� 1924�i���{����1925.7.7�j �w���C���� Helena�x�i��ꕔ�w�w���i�̗��D Der Raub der Helena�x�A��w�g�����̖v�� Der Untergang Trojas�x �}���t���[�g�E�m�A�ēA�V�i���I�F�n���X�E�L���[�U�[�A�B�e�F�M���X�^�[���E�v���C�X�A�G�[���@���g�E�_�E�v �y�L���X�g�z�G�f�B�E�_���N���A�i�w���i�j�A�E���W�[�~���E�K�C�_���t�i�p���X�j�A�n�i�E�����t�A�A�f�[���E�U���g���b�N�A�A���x���g�E�V���^�C�������b�N�A�J�[���E�f�E�t�H�[�N�g�A�A���x���g�E�o�b�T�[�}�� �y����z�M���V���_�b���ނƂ������j�������^���ȗ��j���f��B�i�N���J�E�A�[131���j 1924�i���{����1925.12.4�j �w顁i����jDie Perücke�x �x���g���g�E�t�B�[�A�e���ēA�V�i���I�F�x���g���g�E�t�B�[�A�e���A�B�e�F�q�����}�[���E�����X�L�[ �y�L���X�g�z�I�b�g�[�E�Q�r���[���A�C�G�j�[�E�n�b�Z���N���B�X�g�A�w�����[�E�X�`���A�[�g�A�J�[���E�v���[�e���A�t���[�g�E�[���o���Q�[�x���A���[���E�t�����g�A�����A���E�C�G���l�t�F���g �y����z�����l������̏����āA����̐����ɓ��邱�Ƃ��邪�A�܂������������ɂ��܂��ꂽ������A���C���Ƃ���āA�Ƃ��Ƃ����E���镨��B�i�N���J�E�A�[p127�j 1924�i���{����1926.2.26�j �w���͋P���A���x��� Arabella�x �J�[���E�O���[�l�ēA�V�i���I�F�n���X�E�L���[�U�[�A�B�e�F�J�[���E�n�b�Z���}���A���u�F�J�[���E�Q���Q�A�G���l�E���b�c�i�[ �y�L���X�g�z���[�E�}�[�V���i�A���x���j�A�A���t�H���X�E�t���[�����h�A�t���b�c�E���X�v�A���[�R�v�E�e�B�[�g�P�A�t���b�c�E�J���p�[�X�B �y���炷���z���n�n�̕���B�n�͖��ȏ̒��Ŏ�����~��ꂽ�T�[�J�X�̗x��q�̖��ɂ��Ȃ�ŁA�A���x���ƌĂ�Ă����B���n�̃��[�X�Ő��X�̏����𐋂����A���x���͂������A�V���ĖY����A�����[�S�E���E���h�̔n�ɗ����Ԃ�A����ɒҔn�Ԃ���������邱�ƂɂȂ邪�A�Ō�ɐS�D�������P�Ƃɋ~����B �y����z�N���J�E�A�[�Q�ƁB 1924�i���{����1927.5.6�j �w�|�p�Ǝ�p�\�\����|�p�Ƃ̋��̓� Orlacs Hände�x ���[�x���g�E���B�[�l�ēA�V�i���I�F���[�g���B�q�E�l���c�i���[���X�E���i�[���̓����̏����ɂ��j�A�B�e�F�n���X�E�A���h���V���A���p�F�V���e�t�@���E���F�Z���A����F�p���f�抔����� �y�L���X�g�z�R�����[�g�E�t�@�C�g�i�p�E���E�I�����N�F�s�A�j�X�g�j�A�A���N�T���h���E�]���i�i�C���H���k�F�I�����N�̍ȁj�A�t���b�c�E�R���g�i�[�i�G�E�[�r�I�E�l���j�A�t���b�c�E�V���g���X�j�i�p�E���E�I�����N�̕��j�A�p�E���E�A�X�R�[�i�X�i�V�I�����N�̏��g���j�A�J�������E�J���e���G���i���M�[�l�j�� �y���炷���z�C���H���k�ƃp�E���E�I�����N�͍K���ȕv�w�ł���B�p�E�������t���s����A���ė���̂ŁA��l�Ƃ����̎���҂����˂Ă���B�C���H���k���p�E�����w�Ɍ}���ɍs�����Ƃ���ƁA���Ԏ��̂��N����B���̍ۃp�E���͏d�������̂ŁA�a�@�ł́A���S�ɍӂ��Ă��܂����ނ̎���A���Y���ꂽ����̎E�l�ƃ��@�Z�[���̎���ڐA���āA���ւ��悤�Ǝ��݂�B�I�����N�͎����̎�ɂ��Ă̐^�����ƁA�C����������ɂȂ�B�ނ͂����ȂɐG��悤�Ƃ����A�s�A�m���e���Ȃ��B�I�����N�Ƃ͋ꋫ�Ɋׂ�B��]�����C���H���k�́A���đ��q�Ƃ��̍Ȃ�ǂ��o�����V�I�����N�ɉ�ɍs���B�����C���H���k�͉��̏��͂������Ȃ��B�ޏ��̓p�E���ɁA�ނ̕��̂Ƃ���֍s���悤�ɗ��ށB�o�|���Ă������p�E���́A�����h���E����Ď���ł���̂�����B�x�@�͋��킪�A�E�l�ƃ��@�Z�[���̒Z���ł��邱�ƂɋC�Â��B�ȑO�̊Ō�l�G�E�[�r�I�E�l���́A�I�����N����������B�Ƃ����̂͘V�I�����N���h���E���ꂽ�Z���Ƀ��F�Z���̎w�䂪����A���@�Z�[���̎�͍��ł́A�I�����N�̎肾����ł���B�x�@�͍���A�p�E�����E�l��Ƃ����̂��Ƌ^���B�ނ͖������咣���A�l���������������������Ƃ�b���B�l�����p�E����������Ƃ�������̋������т��낤�Ƃ����Ƃ��A�x�@�͔ޏ�����Ȃɂ�����B�ޏ��͋����͔F�߂邪�A�E�l�͔F�߂��A�����������̂̓p�E�����ƌ����B���M�[�l�̓C���H���k�ɁA�l���Ƃ̊W����������B�x�@���̑O�Ŕޏ��́A�l���ɕs���ȏ،�������B�����̍߂ŏ��Y���ꂽ���@�Z�[���̎�ɋA�����Ă����E�l�ƁA�I�����N�̕��e�ɑ���E�l�́A����l�����Ƃ������̂��������Ƃ���������B �y�f��]�z���u�L�l�}�g�O���t�v��922���\�\�u�c�c����͑S���ԑR����Ƃ���̂Ȃ���i�ł���B�V�i���I�A���o�A���Z�A�B�e�A�Z�b�g�A��������\�����Ȃ��B�ƍߎ҂̎���������I�����N�ɕ������R�����[�g�E�t�@�C�g�́A�Ƃ��Ă����킵�������قǂ̋��|�ɖ������V���t�H�j�[��t�łĂ���B�ނ͓��������f�B�[�̃��@���G�[�V�������A�S���炢���t�ł邪�A������Ƃ����Ċϋq�̐_�o�ɑދ��Ȏv����������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�I�����N�̍Ȃɕ�����������̃]���i��́A�Ђǂ������Ƃ����t�@�C�g�̃m�b�|�̎p�ƒ��a�����邽�߂ɂ́A�����ƌy���Ɍ�����O�����]�܂����������낤�c�c�v�B ��1925�N2��2���t���u�t�B�����E�N�[���[���v���\�\�u�c�c�܂������O�ꂵ�ēƑn�I�Ȃ̂́A�ނ̎�̉��Z�ł���B��̗Y�ق����ŁA�S�̃h���}��W�J���邱�Ƃ��\�ł���B�t�@�C�g�̓h�C�c�f��̐����Ȃ��I�蔲���̐l�ԕ\���҂̈�l�ł���c�c�v�B ��1925�N2��3���t���u�����[���v�\�\�u�c�c�t�@�C�g�͕s�K�Ȑl�Ԃ̂����Ƃ���悤�Ȏp���A�_�o�ׂ̍����|�p�ƓI�Z�ʂŎ������邱�Ƃɐ��������B�l�����m�ɂ���_�ŁA�t�@�C�g�̈��|�I�ɂ����ꂽ�Z�ʂ́A�e�[�}�̎�������\���������o���c�c�v�B �y����z�N���J�E�A�[p157���Q�� 1924.1.3�i���{����1927.11.25�j �w����̔ߌ� Sylvester--Tragödie einer Nacht�x ���[�v�[�E�s�b�N�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[�A�B�e�F�J�[���E�n�b�Z���}���A�O�C�h�E�[�[�o�[�A���u�F���[�x���g�E�`�E�f�B�[�g���q�A�N���E�X�E���q�^�[�A���y�F�N���E�X�E�v�����O�X�n�C�� �y�L���X�g�z�I�C�Q���E�N���b�[�p�[(�i���X��j�A�G�f�B�b�g�E�|�X�J�i�ȁj�A�t���[�_�E���q�����g�i��j�A���h���t�E�u�����[�}�[�i�����ς炢�j�A�J�[���E�n���o�b�q���[�A�����E�X�E�d�E�w���}�� �y���炷���z�N���A�l�X�͑�A�����j���Ă��邪�A����i���X�ł́A��e�ƍȂƂ̊Ԃ̎��i�̑����ɁA���݂ƂȂ������傪�A��]���Ď��ɋ~�������߂�B �y����z�u�h�C�c�f�悪��ΓI�f��|�p�ɂ���قNj߂Â������Ƃ͂Ȃ��v�i�w���x���g�E�C�G�[�����O�j�B 1924.1.7 �w����݂̍��� Die Finanzen des Grossherzogs�x �t���[�h���q�E���B���w�����E�����i�E�ēA�V�i���I�F�e�A�E�t�H���E�n���u�i�t�����N�E�w���[�̏����ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�t���C���g�A�t�����c�E�v���[�i�[�A���u�F���[�t�X�E�O���[�[�A�G�[���q�E�`�F�����H���X�L�[ �y�L���X�g�z�}�f�B�E�N���X�`�����X�i�I���K�F����܁j�A�n���[�E���[�g�P�i����F�������j�A���[�x���g�E�V�����c�i�I���K�̌Z��j�A�A���t���[�g�E�A�[�x���i�t�B���b�v�E�R�����Y�j�A�A�h���t�F�E�G���Q���X�i�h���E�G�X�e�o���E�p�P���R�j�A�w���}���E�t�@�����e�B���i�r���c�@�[���^�x�b�J�[�j�A�����E�X�E�t�@���P���V���^�C���i�C�U�[�N�X�F��s�Ɓj�A�O�E�C�h�E�w���c�t�F���g�i�}���R���B�b�c�j�A�C���J�E�O�����[�j���O�i�A�E�O�X�e�B�[�l�j�A���@���^�[�E�����i���C�E�t�F���i���f�X�j�A�n���X�E�w���}�����V���E�t�[�X�i���ނ��̉A�d�Ɓj�A�Q�I���N�E�A�E�O�X�g�E�R�b�z�i�댯�ȉA�d�Ɓj�B �y���炷���z�I�y���b�^�̒��ł̗����ƉA�d�Ɗv���B �@��]�I�ȂقNj��z��w�������~�j���Ƃ̎Ⴂ�x�z�҃���������́A�������Ē����̖ړI�ł����Ȃ����O�����s�ŁA���V�A�M���̑���܃I���K�ƒm�荇���B��l�Ƃ��݂��ɑ卼�\�t���Ǝv���Ă��邪�A����������͓�l�̃��u�̖W���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�I���K�͔ޏ��̌Z���ޏ��������Ȓj�����������悤�Ƃ��Ă���̂ŁA�ꋫ�Ɋׂ�B����̂ق��́A�b�������ƍ����̊�@�ɒ��ʂ��Ĕ�������Ă��̂ŁA�ꋫ�Ɋׂ�B��l�݂͌��ɏ��������ċꋫ������B�����ė������������͋P�������x�z�ҕv�Ȃ��}�����B 1924.2.10�i���{����1924.10.3�j �w�����N�w The Marigge Circle�x �y����z�G�����X�g�E���r�b�`���ēi��1928�N9��10���Q�Ɓj�̓n�č�i�B�܂��f�p�������A�����J�Ƀ\�t�B�X�e�B�P�[�g���ꂽ�j���W�̉f���ŁA�u���r�b�`���E�^�b�`�v�̖������߂��f��B 1924.2.14�i���{����1924.3.20�j �w�j�[�x�����Q�� Die Nibelungen�x�i��ꕔ�w�W�[�N�t���[�g Siegfried�x�j �t���b�c�E�����O�ēA�V�i���I�F�e�A�E�t�H���E�n���u Thea von Harbou�A�B�e�F�J�[���E�z�t�}���A�M�����^�[�E���b�^�E�A���@���^�[�E���b�g�}���A�A�j���[�V�����F�u��̖��v�S���A���p�F�I�b�g�[�E�t���e�A�G�[���q�E�P�b�e���t�[�g�A�J�[���E�t�H���u���q�g�A�ߑ��F�p�E���E�Q���g�E�O�f���A���A�G���l�E���B���R���A�n�C�����q�E�E�����E�t�i�t�����̈ߑ��A�b�h�A����S���j�A���y�F�S�b�g�t���[�g�E�t�b�y���c�A����F�f�[�N���E�r�I�X�R�[�v�� �y�L���X�g�z�p�E���E���q�^�[ Paul Richter�i�W�[�N�t���[�g�j�A�}���K���[�e�E�V�F�[�� Margarete Schön�i�N���G���q���g�j�A�n�i�E�����t Hanna Ralph�i�u���[���q���f�j�A�n���X�E�A�[�_���x���g�E�V�����b�g�E Hans Adalbert Schlettow�i�n�[�Q���E�t�H���E�g�����C�F�j�A���h���t�E�N���C�������b�Q Rudolf Klein-Rogge�i�G�b�c�F�����j�A�e�I�h�[���E���[�X Theodor Loos�i�O���e�����j�A���g���[�g�E�A���m���g�i�E�[�e��@�j�A�n���X�E�J�[���E�~�����[�i�Q�[���m�[�g�j�A�G�����B���E�r���X���@���K�[�i�M�[�[���w���j�A�x�����n���g�E�Q�b�P�i�t�H���J�[�E�t�H���E�A���c�@�C�j�A�n���f�B�E�t�H���E�t�����\���i�_���N���@���g�j�A�Q�I���N�E���|���i�b�艮�̃~�[��/�ˎA���x���q/�u���I�f���j�A�t���[�_�E���q�����g�i���[�l�̉����j�A���h���t�E���b�g�i�[�i�����[�f�B�K�[�E�t�H���E�x�q�������j�A�Q�I���N�E�����t�X�L�[�i�_���j�A�C���X�E���[�x���c�i�����j�A�t�[�x���g�E�n�C�����q�i���F���x���j�A�t���b�c�E�A���x���e�B�i�f�B�[�g���q�E�t�H���E�x�����j�A�Q�I���N�E�A�E�O�X�g�E�R�b�z�i�q���f�u�����g�j �y���炷���z��ꕔ�F�w�W�[�N�t���[�g�x �@�l�[�f�������g���W�[�N�����g�͌��q�W�[�N�t���[�g���A�H��̖�����b���邱�Ƃ��w���邽�߂ɁA�b��̗_�ꍂ���j�[�x���̓C���̑����~�[���̏Z�ށA�[���X�̉��̓����ɑ������B���錕��b����d���ɂ������W�[�N�t���[�g�́A�����������܂�����҂Ɉ�����B����ނ̓~�[���ɕʂ�������A���n�ɂ܂������āA�\�ɕ������P�N���G���q���g�̏Z�ރu���O���g�̃O���e�����̋{���K�˂邽�߂ɏo������B�₪�ă��H�����X�̐[���J�ɂ��ǂ蒅�����W�[�N�t���[�g�́A�ʼn��𐁂�����ȉΗ��ɓ���j�܂��B �@�ނ͌������킢�̌�A�����o�������N��U����ė����E���B�قƂ���������O�ɓ��Ă�ƁA�s�v�c�ɂ����钹�̐��������ł����B�u���𗁂т��܂��A���̌����A�Z�̔@���g�����A�n���ʂ�ʐg�ƂȂ������v�B�W�[�N�t���[�g�͊��ŗ��ɂȂ�A���𗁂т����A���̎������̗t���ꖇ�ނ̔w���ɗ���������B���̏ꏊ�������s���g�̃W�[�N�t���[�g�̎�_�ƂȂ�B �@���ă��C����ɋ߂��u���O���g�̍��̃��H�����X�̏�ł́A�N���G���q���g���Z�̃O���e�����A�E�[�e��@�A�����Ėd�b�n�[�Q���E�t�H���E�g�����C�F���Ƌ��ɁA���̊y�l�t�H���J�[�̌�镨����B����͗E�m�W�[�N�t���[�g���Η���ގ�������A�����ŕ��Z�������ď����A����P�Q�l�̉Ɛb�𗦂��Ă��邱�Ƃ���A���̍��ɏZ�ރj�[�x�����Q�����̘ˎA���x���q���ނ��E�����Ƃ����̂����炵�߁A�j�[�x�����Q�����̌v��m��Ȃ��قǂ̕�ƁA�A���x���q�̉B�ꖪ����ɓ��ꂽ�Ƃ������ꂾ�����B �@���̎���ǂ̔ޕ�����p�J�̉��������A�P�Q���̉Ɛb��A�ꂽ�W�[�N�t���[�g�̓�����������B�ނ͊��}����A�N���G���q���g��܂Ɍ}�������Ɛ\���o��B�N���G���q���g���W�[�N�t���[�g���炸�v�����A���̒��œ�H�̃��V���莔���̃^�J���P���ĎE�������Ƃɕs���������āA�E�[�e��@�ɑł�������B�O���e�����̓n�[�Q���̌��ɂ���āA���˂Ă������Ă���A�C�X�����h�̏����u�����q���g��܂Ɍ}���邽�߂̎菕�������Ă����Ȃ�Ƃ��������ŁA���̃N���G���q���g���W�[�N�t���[�g�ɗ^���邱�Ƃ����m����B�W�[�N�t���[�g�̓N���G���q���g�̕�����u�ɂ���āA���ɐ����B�����ĉ��̂��������ăA�C�X�����h�ɍs���B �@�A�C�X�����h�ɌN�Ղ���҂������������u�����q���g�̓O���e�����ɕ��Z�����ނ��A�B�ꖪ��t�����W�[�N�t���[�g�ɏ�����ꂽ�O���e�����́A���ɔޏ�������������B���͔ޏ������H�����X�ɘA��Ă���B�����ċ{�a�ŃO���e���ƃu�����q���g�A�W�[�N�t���[�g�ƃN���G���q���g�́A��̌��������₩�ɋ��s�����B�O���e�����͍ĂщB�ꖪ�𒅂��W�[�N�t���[�g�̏�������āA�u�����Ƃ͂Ȃ邪�܂Ƃ͂Ȃ�ʁv�Ƃ����u�����q���g���A�������ɔ܂Ƃ���B�����W�[�N�t���[�g�̓N���G���q���g�ƍK���ȏ���̌�ŁA�B�ꖪ�̔閧�ƁA����ɐg�̂̏����ꏊ�̔閧��ł�������B �@�����m�����N���G���q���g�̓u�����q���g�ƒ��荇�����Ƃ��A��ώv���オ����������M����B�{�����u�����q���g�͎����̔s�k�̐^�������Â��A���Q�̂��߃n�[�Q���E�t�H���E�g�����C�F�ɋ߂Â��B�n�[�Q���̓W�[�N�t���[�g�̖������O���e�����𗽂��悤�ɂȂ����̂�J�����Ă����̂ŁA���̈Öق̗����̂��ƂɁA�W�[�N�t���[�g�̎E�Q���v�悷��B�����ĕv���C�����N���G���q���g�̐S�z���t�p���A�W�[�N�t���[�g����邽�߂Ə̂��āA�ނ̐g�̂̋}�����o���B �c�c �@������Ȃ�ƂȂ�A�W�[�N�t���[�g�͊�����������߂ɐ������ށB���̋@������������Ă����n�[�Q���́A�W�[�N�t���[�g�̎�_��_���A�����𓊂����Ŏh���т��ĎE���B �@�W�[�N�t���[�g�̈�̂��x��������������Ɏ���ď�ɉ^���B�O���e�������u�����q���g�ɕ��Q�̐�����������ƁA�ޏ��͉����������ނ悤�Ɍ���B�n�[�Q�����W�[�N�t���[�g�̈�̂ɋ߂Â��ƁA�������猌�������o���B����������N���G���q���g�̓n�[�Q���ɑ���^�O���m�F���ꂽ�Ǝv���A�O���e�����Ƀn�[�Q�����߂���Ɣ��邪�A���́u�n�[�Q���͗]�̒��b����v�Ƃ͂˂���B���̌Z��Q�[���m�[�g��M�[�[���w���⑼�̉Ɛb�B���A�N��l�Ƃ��ăN���G���q���g�̖����ł͂Ȃ������B�ޏ��͍��݂���g�ɕ����Ăނ��ы����A���Q�̔O��S�ɕ����B�u�����q���g�̓W�[�N�t���[�g�Ɋ��z���ƕ��Q�𐋂����v���̈����̒��ŁA���玀�ɏA���B 1924.4.26�i���{����1925.9.4�j �w�j�[�x�����Q�� Die Nibelungen�x�i��w�N���G���q���g�̕��Q Kriemhilds Rache�x�j �y���炷���z��F�w�N���G���q���g�̕��Q�x �@�g���ɗ���ꂽ�N���G���q���g�́A�W�[�N�t���[�g�����@�����X�ɉ^�����j�[�x�����Q���̕�̏����ŁA�V�����������l�����悤�Ǝ��݂�B�n�[�Q���͕������肵�āA��������C����ɒ��߁A���̏ꏊ��N�ɂ������Ȃ��B�N���G���q���g�͈�w���������Q�𐾂��B �@����Ɖ����t�����̍����烊���[�f�B�K�[�E�t�H���E�x�q������������ė��āA�ނ̉��G�b�c�F���̂��߂ɃN���G���q���g�ɋ�������B�n�[�Q�����|�~�����ɂ�������炸�A�O���e�����͂��̋��������m����B�N���G���q���g�̓����[�f�B�K�[�ɂ��čs�����A�W�[�N�t���[�g�̕悩���Ɉ�t�̓y���g���čs���B�����ăG�b�c�F�����ޏ��̓G�ւ̕��Q�������邱�Ƃ𐾂����̂ŁA�G�b�c�F���ƌ�������B�Ԃ��Ȃ��ޏ��͒j�̎q���Y�ށB�G�b�c�F���ƃN���G���q���g�̓u���O���g�̈ꑰ���t�����̋{��ɏ��҂���B�N���G���q���g�̈Ӑ}�����������n�[�Q���͍Ă��|�~�������A�O���e�����ƉƐb�B�͏��҂���B �@�G�b�c�F���̋{��ł̓u���O���g�̕o�q���}���邽�߂ɁA����ȉ���J�Â����B�N���G���q���g�̓G�b�c�F������������āA�n�[�Q�����E�����悤�Ƃ���B�������G�b�c�F���́v�Ȃɐ������ɂ�������炸�A�q���ڑ҂��錠���̕������_��������B�������̍L�Ԃŏj�����s���Ă���ԂɁA�t�����ƃu���O���g���̏]�ҒB���y����ł���n���̓����ł́A�N���G���q���g����t���������̂��߂ɁA��̓}�h�̊ԂɌ��Ȃ܂������Η����N����B �@�t�������u���O���g���̏]�ҒB���E�C���āA���ꂩ�牤�̍L�ԂɐN������B�~���ĕ����������̒��Ńn�[�Q���́A�G�b�c�F���ƃN���G���q���g�̎q�����E���B����t�����̉������Q�𐾂��B�u���O���g�̈ꑰ�͍L�Ԃ̒��ɗ��Ă�����A�t�����ɂ���ĕ�͂����B�N���G���q���g�̓u���O���g�̈ꑰ�ɁA�����n�[�Q���������n���Θa���ɉ����悤�Ɠ`����B����Ȃ��Ƃ�������͈ꑰ���F�������܂����ƁA���ۂ����B�����ĉ�����ꂽ�L�Ԃ́A���ɕ�܂��B�N���G���q���g�̌Z��B�͑��̃u���O���g�̋M���B�ƈꏏ�ɁA���X�ɎE�����B�Ō�܂Ő������т��O���e�����ƃn�[�Q���́A���т��ɂȂ���ăN���G���q���g�̑O�Ɉ����o�����B�ޏ��̓O���e�����E�����A�n�[�Q�����j�[�x�����Q���̕�߂��ꏊ���������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�ނ�����E���B�����ăN���G���q���g���A�ޏ��ɍŌ�܂Œ����������q���f�u�����g�ɂ���ĎE�����B�ނ͔ޏ����t�����ɂ����炵���Ж�ɋ������āA���ɃN���G���q���g�ւ̒������̂Ă��̂ł���B�G�b�c�F���͔ޏ��̎��̂�����āA�R����{�a�ɓ����Ă����A���I�̒��Ɏ��疄�܂�B�������Ĉ��ߌ��͖������B �y����z�w���ł̒J�x�A�w�h�N�g���E�}�u�[�x�̎��Ƀt���b�c�E�����O�����グ���̂́A�Q���}���̉p�Y�������w�j�[�x�����Q���̉́x�������B�����O�̖��𐢊E�I�ɗL���ɂ������̉f��́A�������p�Y�������̉f�扻�ł͂Ȃ������B����͓`�������ɂ��ď������e�A�E�t�H���E�n���u�́A�ʑ��I�Ɍ��㉻���ꂽ�V�����_�b�̉f�����������B�u����ȃe�[�}���D�e�A�E�t�H���E�n���u�́A�Â������ɂ���Ď��R�ɑ�{���\�����A����Ɍ���I�ȈӖ�����ݍ��܂��悤�ƈӐ}�����B�������Ėk���_�b�́A�v���~�e�B���ȏ�M�Ɏ���ꂽ�`����̐l����`���A�A�T�ȕ���ƂȂ��Ă��܂����v�B �@���̌��㉻���ꂽ�L�b�`���Ƃ��Ẵj�[�x�����Q������́A�t���b�c�E�����O�̉f���ɂ���āA�f��I�ɂ͌���ƂȂ����B�����Ɂu�f��v�Ƃ����}�̂̊�Ȑ��i������B�u�L�b�`���v��y��Ƃ�������[�[���R�u����v�Ƃ��Ắu�p�Y�������v�ƈ���āA�f��̓A�C���j�J���ȓ�d���������ƂƂȂ����B�����O���g�̌����Ƃ���ł́A���̉f��Ŕނ��Ӑ}�����̂́A�l�̈قȂ������E��`�����Ƃ������B�u���O���g�����́u࣏n���������v�A�Ⴂ�W�[�N�t���[�g�́u�H�삶�݂��d���̂悤�ȁv���E�A�u�����q���g�̃A�C�X�����h�́u���߁A���������C�v�A�����āu�A�W�A�l�v�G�b�c�F���̐��E�ł���B�����Ă��̐��E�̃C���[�W��\�����邽�߂ɁA�A�C�X�����h�ƃ��H�����X�ɂ́A�ɓx�ɑ����I�ɗl�������ꂽ�Z�b�g���g�����B���̌��ʃI�b�g�[�E�t���e��̍��������ȃZ�b�g���X�N���[�����x�z���A�l�Ԃ̌Q���܂ł��l�������ꂽ�B���ꂪ���̉f��̒B���������j�[�N�Ȑ��ʂł���A������߂��鑽�l�ȉ��߂́A���ׂĂ��́u�l�����v�ɑ���Ӗ��Â��ł���B�Ⴆ���b�e�E�A�C�X�i�[�͒����w�t���b�c�E�����O�x�̒��ŁA���������Ă���B �@�u�A�[�P�[�h��ǂ������������A�l�����͎��ۂɁA����ɍ��킹�āA���̘g�̒��ɂ͂ߍ��܂�Ă���B�l�����͂����Α��u�̈ꕔ�ƂȂ�B�Ⴆ�Ε��m�̗�͑O�i�̒��Ɏ��Ă���A�݂ȓ����w�I�ȏ����g�ɂ��Ă���B�����Ă��̓��̂̍�̔w����A����p�Y�����̍s�A�������Ƒ剾���ɋ߂Â��Ă����B�����O�͂����ŕ��m�������A�u���O���g�ꑰ�̐�ΓI�ȗ͂��ے����邽�߂Ɏg���Ă���v�B�ߏւ����܂߂Đl�������V�����g���J���Ȍ��z�I�\�}�̒��ցA���S�Ɋw�I�ɑ��������ꂽ���ʐ������A�܂��Ƃɑs��ȋL�O��I�f���́A����ɍ��v�������A��������߂������B����ȏ�̈Ӗ��͂Ȃ��B������ƌ����Ė�����ł͂Ȃ��B�e�A�E�t�H���E�n���u���g���������b�g�[�A�u�h�C�c�����̂��߂Ɂv�Ƃ����A���Ǝ�`�I���߂�A�N���J�E�A�[�̗^�����l�ԓI�Ȃ��̂ɑ��鑕���I�Ȃ��̂̊��S�ȏ����A���Ў�`�ɋ������鑕���Ƃ��Ă̑�O�Ƃ������߁A���邢�͐_�b�ɑ���A�C���j�[�ƚ}�Ƃ����������̉��߁[�[�����������l�ȉ��߂̍���ɂ��錻��̏������̊����A�n���u�[�����O�͂���ɑ���ނ�̊��o���A���̂悤�Ɉ�ۓI�ɗl���������̂ł���B �@�������蓖���̃h�C�c�ł͑�ނ���ނȂ����ɁA���������l�����̐��I����]��������́A�����ς爤����`�I�g����S�����f��Ƃ��ď^���鐺���A���|�I�������B�Ⴆ�u�t�B�������H�b�w�v���͂��������Ă���B �u���ăj�[�x�����Q���̉̂��L�����E�ɍL�߂邽�߂ɁA�t�B�[�f����t�ł���V���l�A�t�@���J�[�E�t�H���E�A���c�@�C�̂悤�ɁA�����t���b�c�E�����O�͐��E�̊�ɁA�\���ɖ������ߋ��̈Â��ٓ��ɋx��ł������̂��������߂ɁA�f��Ƃ������ق̌���������B�ނ̓h�C�c�̉p�Y��������h��������B�s�퍑�������̏����̉p�Y�����̂��߂ɁA���E�������܂ł܂��قƂ�nj������Ƃ̂Ȃ��悤�ȏ��������A�f���őn�삷��[�[����͈�̈̋Ƃł���I�@�t���b�c�E�����O�������������B�����Ĉꖯ���S�̂��ނ�������B�ꖯ���S�́B�Ȃ��Ȃ�t���b�c�E�����O�����̖����̂����Ƃ������̐S��͂�ł��邩��ł���c�c�����͍Ăщp�Y��K�v�Ƃ��Ă���I�v �@���̂悤�Ȗ�����`�I�ȑԓx�́A�����ł͗��s��Ȃ��B������ƌ����Ă��������x��ƕЂÂ��邾���ł͍ς܂Ȃ��B����E����ƈ���āA�i�V���i���Y���͂܂��v���X�̉��l�C���[�W�������Ă��Ȃ������B�����������ゾ�����̂��Ƃ������Ƃ��A�F������K�v������B �@����䂦���̉f��̕���̎��A���傤�ǁw���̓��X�x�Ƃ����t���[�h���q�剤���������{���o�ł������肾�����u���[�m�E�t�����N���A�|�c�_���̎��������̕揊��K�ꂽ�B�����ăt���[�h���q�剤�̕�ɁA����ȃ��{������������ȉԗ֕������Ă���̂������B���{���ɂ́u�j�[�x�����Q���f��̕���ɓ������āA�t���b�c�E�����O�v�ƋL����Ă����B���ۂɂ͂��̉ԗւ�������̂́A�e�A�E�t�H���E�n���u�������Ɛ�������Ă���B�����둽�K�ǓI�����𑗂��Ă����ʑ��I��{�쐬�̖���n���u�́A���~�I�œ����I�ȌX���Ɠ������炢�A�����I�ő��d�ȌX�����D��ł����̂�����B����䂦�t���b�c�E�����O�[�e�A�E�t�H���E�n���u�̃R���r�́A�����O�f��̕����\���̖��f�͂Ƃ������킵���Ƃ̗������A���ݏo���Ɠ��̍������݂������B�n���u�͂P�X�R�R�N�̃q�g���[�̐����l���ȑO�ɁA���łɃt�@�V�Y���ɌX���Ă����B���̂��߃q�g���[�̃h�C�c��郉���O�́A�n���u�Ɨ������邱�ƂɂȂ邪�A����܂ł͂��̊�ɂ˂��ꂽ��l�O�r�́A���@�C�}������̃h�C�c�f����\�����i����葱���Ă����B�A���t���[�g�E�|���K�[�͉f��w�j�[�x�����Q���x���A�u�����̂��߂ɕs����Ƃ��Ñ�Q���}���̕��K�ɑ��鑑�d�ȉ�́v�ƌĂ��A����͂��̂܂܃����O�[�n���u�̃R���r�̐��i�K��ł�����B�@ �@�׃������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŕ���B��ł́A��ꕔ�̑����I�����́A�ꖳ���̍��ׂɕς��A�����̑�s�E��45���������B 1924.2.26 �w�J�����X�ƃG���[�U�x�g Carlos und Elisabeth�x ���q�����g�E�I�Y���@���g�ēA�V�i���I�F���q�����g�E�I�Y���@���g�A�B�e�F�J�[���E�n�b�Z���}���A�J�[���E�v�[�g�A�J�[���E�t�@�X�A�e�I�h�[���E�V���p�[���N�[�� �y�L���X�g�z�R�����[�g�E�t�@�C�g�A�I�C�Q���E�N���b�p�[�A�A�E�h�E�G�Q�f�E�j�b�Z���A���B���w�����E�f�B�[�e���� �y����z�u�N��̔ߌ��v�B�t���[�h���q�E�V���[�̃h���}�w�h���E�J�����X�x�̃��@���G�[�V���� 1924.5.10 �w�A���v�X���� Der Berg des Schicksals�x �A���m���g�E�t�@���N�ēA�V�i���I�F�A���m���g�E�t�@���N�A�B�e�F�A���m���g�E�t�@���N�A�n���X�E�V���l�[�x���K�[�A�[�b�v�E�A���K�C���[�� �y�L���X�g�z�n���l�X�E�V���i�C�_�[�A�G���i�E�����i�A�t���[�_�E���q�����g�A���C�X�E�g�����J�[ �y����z�A���v�X�ł̗����h���}�B 1924.6.16�i���{����1926.5.7�j �w�ł̗� Die Macht der Finsternis�x �R�����[�g�E���B�[�l�ēA�V�i���I�F���|�x���g�E���B�[�l�i���t�E�g���X�g�C�̌���ɂ��j �y�L���X�g�z�u���X�N���|�p���v�̃����o�[ �y����z�x�������́u���[�c�@���g�E�z�[���v�ŕ���B�N���J�E�A�[p108 1924.9.26 �w�~�q���G�� Michael�x �J�[���E�e�I�h�[���E�h���C���[�ēA�V�i���I�F�e�A�E�t�H���E�n���u�A�J�[���E�e�I�h�[���E�h���C���[�i�w���}���E�o���O�̏����w�~�J�G���x�ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�t���C���g�A���h���t�E�}�e�[ �y�L���X�g�z���@���^�[�E�X���U�[�N�i�~�q���G���j�A�x�����~���E�N���X�e���[���i�N���[�h�E�c�H�[���g�j�A�m���E�O���[�S�A�i���`�A�E�U�~�R�t��ݕv�l�j�A�A���N�T���_�[�E�}���X�L�[�i�A�[�f���X�N���C�g�j�A�O���[�e�E���X�n�C���i�ނ̍ȁj�A���[�x���g�E�K���\���i�`���[���Y�E�X�E�C�b�g�j�A�}�b�N�X�E�A�E�c�C���K�[ �y���炷���z�f�O�̕���B�L���ŋ������̉�ƃN���[�h�E�c�H�[���g�́A�ނ̋C�ɓ���̃��f���̎�҃~�q���G����{�q�ɂ���B��������뗎�������A�������U�~�R�t��ݕv�l���c�H�[���g�ɕ`���Ă��炢�A�~�q���G����U�f����B�c�H�[���g�́A�F�l�̃W���[�i���X�g�̃X�E�C�b�g���ނ̖ڂ��J�����Ă����܂ŁA����ɋC�Â��Ȃ������B����ނ̓~�q���G���̑ԓx�ɐ�]���A�܂��Ȃ̕s��̑���������ŎE�����F�l�A�[�f���X�N���C�g�̉^���ɔߒQ���āA�s���̏d�a�ɂȂ�B�����Ď��ʑO�ɂ�����x�~�q���G���ɉ�����Ƃ����ނ̊肢�����Ȃ����Ȃ��B�ɂ�������炸�ނ̓~�q���G�����A�P�Ƒ����l�Ɏw�肷��B 1924.11.5 �w�Ίp�������y Diagonal Sinfonie�x �y����z���B�L���O�E�G�b�Q�����O�̐��I�Ȓ��ۉf��B 1924.11.7 �w�_�l�����ݕv�l Gräfin Danelli�x �Q�I���N�E���B���w�����E�p�v�X�g�ēA�V�i���I�F�n���X�E�L���[�U�[�A�B�e�F�O�C�h�E�[�[�o�[ �y�L���X�g�z�w�j�[�E�|���e���A�A�p�E���E�n���[���A�t���[�h���q�E�J�C�X���[�A�G�[�x���n���g�E���C�g�z�t�A�t�F���f�B�i���g�E�t�H���E�A���e���A�����e�����E�h�D�����A�J�[���E�G�g�����K�[ �y����z�x�������̉f��فu�v�����X�p���X�g�v�ŕ���B 1924.11.13�i���{����1925.9.25�j �w���X�̉��V�A Wachsfigurenkabinett�x �p�E���E���[�j�ēA�V�i���I�F�w�����b�N�E�K���[���A�B�e�F�w���}�[���E�����X�L�A���u�F�p�E���E���[�j�A�G�����X�g�E�V���e�����A�t���b�c�E�}�E���V���[�g�A����F�l�v�g�D���E�t�B���� �y�L���X�g�z�G�~�[���E���j���O�X�i�n�[�����E�A���E���V�b�h�j�A�R�����[�g�E�t�@�C�g�i�C��������j�A���F���i�[�E�N���E�X�i��W���b�N�j�A���B���w�����E�f�B�[�e�����i�����鎍�l�^�A�T�h�^�Ԗ��j�A���[���E�S�b�g�E�g�i�X�l�`�ق̎�����j�A�I���K�E�y���C�F�t�i�ނ̖��^�c�A���^�ԉŁj�A�G�����X�g�E���[�K���A�Q�I���N�E���[�� �y���炷���z�i���l�����o���X�l�`�ق̋��|�̐l�����̕���̉f�����j�B �@���钬�̒���s�ɁA��l�̎Ⴂ���l������ė��āA�u�W����̐�`������������l�������ށv�Ƃ����L���Ɋ���Ƃ߂�B�ނ͑������̘X�l�`�̌����������ɍs���B�����ɂ̓n�[���[���E�A���E���V�b�h��C����������W���b�N�▂�p�t���i���h�E���i���f�B�[�j�Ȃǂ̘X�l�`���A�����ƕ���ł���B�X�l�`�ق̎�����͎Ⴂ���l�ɁA�����̘X�l�`�ɂ��Ă̕���������悤�˗�����B�X�l�`�ق̎�����̔��������G�[�t�@���A�ނ̑z�����������āA�M���X���[�Y�Ɋ��点��B�ނ̓n�[���[���E�A���E���V�b�h�̘X�l�`�̕Иr����ꂽ�̂ɂ������āA�܂��ŏ��Ƀn�[���[���E�A���E���V�b�h���Иr������������������B �@�o�O�_�b�h�̃J���t�A�n�[���[���E�A���E���V�b�h�́A��σ��}���`�b�N�Ȏx�z�҂ŁA�ދ��������āA������������������Ă���B�������̏����̒N��l�Ƃ��āA�p�����̃A�T�h�̍ȁA�c�@���قǂɔ������҂͂��Ȃ��B������J���t����b�ƃ`�F�X�����Ă��ĕ�����ƁA�p�����̉��������}���Ă���悤�Ɍ�����B�{�����J���t�͑�b�ɁA�p�������E���Ɩ�����B�����p�����̍ȃc�@���̔��e�ɂƂ납���ꂽ��b�́A�A�T�h���E�����ɋA���Ă��āA���̂��Ƃ��J���t�ɍ�����B �@�b���ƈ����ȃJ���t�́A�ϑ����ăc�@����U�f���ɏo�|����B����p�����̃A�T�h�́A������̂������Ƒi����c�@���ɁA�J���t�̋{�a�ɔE�э���ŁA�ǂ�Ȋ肢�ł����Ȃ��Ă����J���t�̖��@�̎w�ւ��A����ł��Ă��Ɩ��ďo�|����B���̗���ɃJ���t�̓c�@���̏��ɔE�э���ŁA�ޏ���U�f���A�L���ȉ��̎w�ւ������т炩���B�{�a�ɔE�э��A�T�h�́A�J���t���g����ɐQ���ɒu�����X�l�`���h���A���̘r����ċU�̎w�ւ�D���B�������ԕ��Ɍ������Ă��܂��A����Ƃ̎v���ʼnƂɓ����A��B �@�J���t�Ɍ�������Ă���Ƃ���ցA�A�T�h���A���Ă������ƂɋC�Â����c�@���́A�J���t���p���Ă����̒��։B���B�A�T�h�́u����̓J���t���E���Ă����v�ƌ����āA���@�̎w�ւ�������B�����֔ԕ�����������ė��āA�J���t�E���̍߂ŁA�A�T�h��ߕ߂���B�������c�@���̓A�T�h�������A�����r����w�ւ����A�u���͎E���ꂽ�J���t���A�����ɐ����Ďp���������Ƃ��肤�v�ƌ����B����ƃJ���t���p���Ă����̒�����p�������B�c�@���͂����ɂ܂��A�u�����Ď��́A���̈�����A�T�h���J���t�̃p���Ă��ɂȂ邱�Ƃ��肤�v�ƌ����B�J���t������������A��l�͖ڏo�x���J���t�̋{�a�ɓ���B �@���̕���̓��V�A�̃C��������ƈ����B���������̖\�N�̓N���������{�a�̒n���ɍ~��čs���A�ł�ꂽ�]���҂̒f�����̋��߂āA�ق�����ł���B�ނ̋C�ɓ���̊ߋ�́A���̗����邱�Ƃŋ]���҂̍Ō�̎������ލ����v�ł���B���̍����v�ɖ��O���������܂��ƁA����͎��̋]���҂��Ӗ�����B�Ƃ��낪�ł̒��t�͗��邪�������E���̂ł͂Ȃ����Ƃ��������������B�ނ͂����h�����߂ɁA�t�ɍ����v�ɗ���̖��O���L�����ƍl����B���s�����萯�p�t�ɂ��̂��Ƃ��x�����ꂽ����́A�Ђǂ��s���ɂȂ�B �@������l�̋M�����N���������{�a�ɂ���ė��āA�ނ̖��̌������ɁA������o�Ȃ��ė~�����Ɨ��ށB�p�S�[���C�����́A�ԉł̕��e�ƈߏւ��������ďo�|����B�r���ňÎE�c���P���Ă��āA�ԉł̕��e�𗋒邾�Ǝv���ĎE���B�C�����́u�c��͎����������v�ƌ����āA�������ɕ����B�����č����𗘗p���ĉԉł����炢�A�Ԗ����S�����āA���⎺�ɑ��点��B�����ꂽ�ԉł̓N���������{�a�ɘA�ꍞ�܂��B�ޏ��͍c��̎��āA�n�����֍s���B�����ł͔ޏ��̉Ԗ������₳��Ă���B���邪�ޏ��̌��ǂ��ė���B �@���̎��萯�p�t������ɁA�u���Ȃ��͓ł�ꂽ�v�Ƌ��ԁB���������邪�A�u���Ƃǂꂭ�炢�������邩�v�ƕ����ƁA�萯�p�t�́u���̍Ō�̗�����ɗ�����܂Łv�Ɠ����āA����̖��O���L���������v�������B�ł�ꂽ�ƐM��������́A�C�������Ă��܂��B�����Đ��U�̍Ō�̓��܂ŁA�����v���x�݂Ȃ��Ђ�����Ԃ�������B �@��O�̐�W���b�N�̕�����ǂ����邩�A���ꂱ��ƍl���Ă��邤���ɁA�Ⴂ���l�͔��Ė��荞��ł��܂��B���̒��Ŕނ́A�X�l�`�ق̎�����̖��ƈ��������B�ˑR��l�͐�W���b�N�ɏP����B�����Ăǂ�Ȃɓ����Ă��A��W���b�N�͂ǂ��܂ł���l��ǂ��Ă���B���|�̃N���C�}�b�N�X�ŁA�Ⴂ���l�͖��肩��ڊo�߂�B���ɂ͖��̒��ł̗��l�G�[�t�@�����āA��l�͖{���Ɉ����n�߂�B �y����z���̉f��͕���̍ۂɂ́A�P�C��������̕���A�Q��W���b�N�̕���A�R�n�[���[���E�A���E���V�b�h�̕���̏��ŏ�f���ꂽ�B�����������ɏ������ς����A���̂ق��������ƌ��ʓI�ł��邱�Ƃ��킩�����B�ȗ����̏����ŏ�f����Ă���B�����p�E���E���[�j�͔��p�ēƂ��ėD�ꂽ�d�������Ă��������ɁA���̍�i�̓Z�b�g�A�Ɩ��̂�����̖ʂ��猩�Ă��A�Ō�̐^���̕\����`�f��̈�ł���B�ނ͈ӎ��I�ɁA�l������n���h�����N�̎�������C�����A�Z�b�g��J�����̃p�[�X�y�N�e�B����ʂ��ĕ\�����邱�Ƃ�ڎw�����B�Ⴆ�C��������̎c�s���́A���ߕt����悤�Ȍ����̈�������A�l�Ԃ��̈ꕔ�ɊҌ�����悤�ȏ����@�ɂ���āA��W���b�N�̗H�삶�݂��s�C�����́A��������ƃt�H�����ō\�����ꂽ�悤�Ȍ`�p�ɂ���ĕ\������Ă���B���������������\����`���L�̎�@�́A��ꎟ���E����̃A�i�[�L�[�Ȑ����̒��ł����A���ʂ��������A���܂�Ɍ֒����ꂽ�ǂ����́A����Ɉ�a����^����悤�ɂȂ�A�h�C�c�f��̕\����`�́A���̍�i���Ō�Ƃ��āA�嗬����͂���Ă������ƂɂȂ�B�����t�����N�E���@���V���E�A�[�́A�u���E����i���F���g�r���[�l�j�v���ŁA������]���Ă����B �@�u�w���X�̉��V�A�x���ē��Ă����Ƃ̃p�E���E���[�j�́A�|�p�Ƃ̓��Z��f�O����悤�ȋC�͂Ȃ��A�Ǝ��̐��i����������Ԃ⎖����n�������B�ނ͂��������߂čI�݂ɁA�����ĖړI�ɓK���������t���������Ă����Ȃ����̂ŁA���炵�����ʂ�B�������B�O�̕���̊e�X�́A�Ǝ��̒��q�ʼn�������B�R�����[�g�E�t�@�C�g���C��������ɕ��������̕���́A�o���[�h���ɕs�C���ŁA�����I�ɑs��ł���B���̕���͖S��̂悤�ɒʂ�߂��čs���B��O�̕���̓o�[���X�N���̊쌀�ł���B�����ł̓G�~�[���E���j���O�X�́A���镨��̊y�����p���f�B�[���琶�ݏo���ꂽ�A�Ђǂ��������A����ȂЂ����������A�Ђǂ����m�ȃ����w���̃J���t�ł���B �@�p�E���E���[�j�ē���Ƃł���Ƃ��������Ƃ́A�f���̋Z�p�I�\���ɂ���߂ėL���ɓ����Ă���B�ނ̓J�����̉\���𗘗p���s�������Ƃ�S���Ă���B�Ⴆ�ΓƎ��ɕω����A�����̂���f���ݏo���悤�ȃA���O���A�����ނ̉f���͂����Ε��G�߂��āA���ʂ��������Ȃ��B��ɒP�������ɁA�͂��̗v�f�ō\�����ׂ����Ƃ������Ƃ��A�킪���ł͊ȒP�ɖY�ꋎ���Ă��܂��v�B �@�������j�I�ɉ�ڂ��Ă݂�ƁA�������w�����b�N�E�K���[�����V�i���I�E���C�^�[�Ƃ��č\�z�����A��N�O�́w�m�X�t�F���g�D�x���A���ۓI�ȋ��|�f��̐��I��i�ƌ��Ȃ���Ă���悤�ɁA���̉f��͋��|�R���f�B�[�f��Ƃ����W�������̐��I��i�ł���B�����ăp�E���E���[�j���g�w���X�̉��V�A�x�̐����ɂ���āA�n���E�b�h�ɏ�����A������1927�N�A���������̃W�������̌ÓT�I��i�w�L�ƃJ�i�����x��������B������1929�N��44�Ŏ��ʂ܂ŁA����ɎO�{�̃X�����[�f��A�w���j�x�w�V�i���_���x�w�Ō�̌x���x��������B �@�����ɂ��̉f��́A�������ꂽ�h�C�c�f��Ɩ��ڂȊW�������Ă���B�n�[���[���E�A���E���V�b�h�̕���́A���r�b�`���́w���P�Y�������x�Ȃǂ����������Ƃ��āA���N�O�h�C�c�ŗ��s�����A���r�A���Ƃ����W���������A���Ă����������h�ł������B�C�����������W���b�N���A�Ǝ��̐l�����ł͂Ȃ��B��W���b�N��20�N��h�C�c�̃����h���}�f��́A�قƂ�ǃX�^���_�[�h�Ȑl�����ŁA�̂��Ƀp�v�X�g�́w�p���h���̔��x�ŁA�ɂߕt���̌`�p�ƂȂ�B �@���̍�i�̏o���f������l�łȂ����Ƃ́A�̂���w�E����Ă������A����͐�������̈����̂����ł��������B����ɂ��Ď���̃��B���w�����E�f�B�[�e�����́A��N���������Ă���B�u�p�E���E���[�j�́w���X�̉��V�A�x�̊ēł���Ɠ����ɁA���u�Ƃ������B�ނ͂��̉f��ł͑�ϕs�^�������B�Ƃ����̂͂��̊��̃X�|���T�[�ƂȂ����̂́A���Ƃ��������V�A�l���������A���������Ȃ��Ă��܂����B�Ō�̃G�s�\�[�h�́A����Ƃ̂��Ƃłł����グ�邱�Ƃ��ł����A�h�����ĉf���ɏo�����B����͖{���ɒQ���킵�����Ƃ������B�Ȃ��Ȃ�������T�ԁA���邢�͂�������}���N����Aꡂ��ɗǂ��f�悪��ꂽ���낤����ł���B�ɂ�������炸���̉f��́A���Ȃ�傫�Ȑ��������߂��B�����炭���̎�̂��̂Ƃ��Ă͍Ō�ł��낤�B�ϋq�̑啔���́A�\����`�Ȃǖ��ɂ��Ȃ������B�l�X�͒P�ɖʔ����X�g�[���[�����߂��B�h�C�c�ɂ͎R��ԁA�����Ŋ����I�Ȏ����荞�A��A�̋��y�f�悪�������B���������f��͐������A���_���ȗl���̉f��̂�����D���Ă����B�w���X�̉��V�A�x�̂悤�ȍ�i�ł���A�����Ė�薳���ɁA��ʊϋq�̔�������킯�ł͂Ȃ��̂ł���B��̕���̃Z�b�g�ƃJ�������[�N�́A���ꂼ��Ɠ��ł��邪�A���̕���ł̃t���b�c�E�}�E���V���[�g�̃Z�b�g�̖��͂ƁA���̕���̃p�E���E���[�j�̃Z�b�g�̈�ۂ́A���������Ă���B��O�̕���ł́A�����I�ȕs�C���ȕ��͋C�������o���Ă���J�������[�N���ڗ����Ă���B�Ȃ����̉f��ł̓G�~�[���E���j���O�X�A�R�����[�g�E�t�@�C�g�A���F���i�[�E�N���E�X�Ƃ����A�����̃h�C�c�f��E�̎O�喼�D���������Ă��邪�A�������L�̂��Ƃ������B �y�f��]�z���h���t�E�N���c�w�\����`�f��x�\�\�u�J��Ԃ��m�F����˂Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�\����`�ł̓X�^�C���ւ̊G��I�ӎu���A�e�ՂɊ���I�ȕ\���̏[���𑨂���Ƃ������Ƃł���B�q�X�l�`�̔��r�̍�ҁA�p�E���E���[�j�͂��̊W����ɕq���ɑ̌������B �@�q�X�l�`�̔��r�ŕ\����`�I�ł�����̂́A���̑ԓx�̕K�R���琶�܂�Ă���̂ł͂Ȃ��A�������\�����@�ł���B���[�j�͑�_���m�Ɏ��R�����A�ʂƐ��̉��o�ɂ����āA�f��̋C������肷��悤�Ȍ`���ɉ�������B�ނ͂��낢��Ȍ`����c��܂���B�ނ͂��낢��Ȍ`�������ł�����B���m�̕��ł͔ނ́A���������߂Ċ�ԂȁA�ʔ������@�œ����͗l�����A�܂����V�A�̕��ł́A�u�r�U���`���I�ɓ��X�ƁA���炩�ɉ����ق����Ă���B�����Ĕ����Ȏw��ŁA�^���̃G�l���M�[���������A��W���b�N�I�g�ƃv���t�B����^����s�C���ȃV�[���̘A���̂����ɁA�\����`�I�����̊�������Ă���B�\����`�I�`���̗v�f���A�t�B�����̂�����Ƃ���ɕ����яオ���Ă͂��Ă��A���̎d���̓����ł́A�����Ō�̕����ɂ��Ă����������Ƃ͂Ȃ��B���̔��ɒZ�����X�g�̌��т́A���m�ȃR���|�W�V�����ƁA�����I�A���Z�I�ȉ��o�̖������������Ă���A�\����`�f��̒Z�����j�̒��ŁA���̏d�v�Ȓn�ʂ��߂Ă���ƌ����Ă悢�B�c�c������Ɏ��R�Ȍ`�͎̂Ă��A���т���ꂽ���R�ȖʂƐ��Ƃ��A�܂������\����`�I�ŁA�ǂƓ��́A�O�i�Ƙp�ȂƂɋ�̉�����Ă���B��ɂ����A�������悤�Ƃ����͂�����A��Ԃɂ����邫��߂Č����I�Ȕ��p�v�̋��\���ł���A�×~�ł���A�K�i���ڂ܂�������Ăł���B �@���j�́A���̖����ɓ������ꂽ���p�v���A����Ό����ő��������B��̌��������h�߂��ꂽ�����͋�ԂɔM�a�̖�������o���A���ׂẴJ�[�u����ʂ��A���₳�ꂽ���𑖂点�A�w�i�̂Ȃ��[�������ݏo���A�߂̕ǂɈÕ��̖��͂��o���A���ꂪ�����L�т邪���Ƃ�������B���u�̋Z�p�I�ȉ\�����Œ肳��A���݂ɓ��肱�݁A�܂��͏d�ˍ��킳��ĎB�e����Ă��āA��Ԃɂ����邢���Ȍ`��̉^�����l�����K�I�ȑ�������������Ă��āA�`����w�I�ȗ̈�ɂ܂ō��߂��Ă���B����قǐ��m�Ɏ�i�ƍޗ�������ɑ����I�Ȉӎu�ɏ]�����Ă��邩�炱���A��O�́A���̔��ɑ����A�����ȃV�[���𑽑�̊��т������Ď��ꂽ�̂��B�\����`�́A���ꂪ��i��S���I�ړI�ɏ]�������邱�Ƃɂ���āA���̐��ʂ��Ȃ��Ƃ����v�i�u�\����`�̉����E�f��x�A�͏o���[�A332�y�[�W�ȉ��j�B 1924.11.24�i���{����1931.4.15�j �w�j���[ Nju--Eine unverstandene Frau�x �p�E���E�c�B���i�[�ēA�V�i���I�F�p�E���E�c�B���i�[�i�I�V�b�v�E�f�����t�̌���ɂ��j�A�B�e�F�A�N�Z���E�O���[�g�N���[�G���A���C�}�[���E�N���c�F�A���u�F�p�E���E���[�g�A�S�b�g���[�v�E�w�b�V���A�L���X�g�F�G���[�U�x�g�E�x���N�i�[�i�j���[�j�A�G�~�[���E���j���O�X�i�v�j�A�R�����[�g�E�t�@�C�g�i���l�j�A�~�[�S�E�o���g�i�x�r�[�V�b�^�[�j�A�j���X�E�G�g���@���i�q���j�A�}���K���[�e�E�N�b�p�[�A�J�[���E�v���[�e���A�}�b�N�X�E�N���[�l���g �y���炷���z�P�ǂł͂��邪�A����ӂꂽ�����҂ƌ������A���ƂȂ�����ɋQ���Ă���j���[�́A�@�ׂȊ��o�̊O���l��Ƃƒm�荇���A�����̂�����ĕv��q�����̂ĂāA���̒j�̕����Ɉڂ�B���̕����͔ޏ��ɂ́A�����̉ƒ�Ɣ�ׂĊy���悤�Ɍ�����B���������炭���邻�̊O���l�͔ޏ��ɉ}���Ă��܂��A�v�Ǝq���̋��ɋA��悤�ɂƂ����߂�B�������j���[�͂�邹�Ȃ��ɁA�g�������Ė����ق���I�ԁB 1924.12.23�i���{����1926.1.28�j �w�Ō�̐l Der letzte Mann�x �t���[�h���q�E���B���w�����E�����i�E�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[Carl Mayer�A�B�e�F�J�[���E�t���C���g�A ���p�F���[�x���g�E�w�����g�A���@���^�[�E���[���q�A����F�E�[�t�@�f��� �y�L���X�g�z�G�~�[���E���j���O�X Emil Jannings�i�h�A�}���j�A�}���[�E�f���V���t�g�i�ނ̖Áj�A�}�b�N�X�E�q���[�i�Ԗ��j�A�G�~�[���G�E�N���c�i�f��j�A�Q�I���N�E���[���i��x�j�A�n���X�E�E���^�[�L���q���[�i�x�z�l�j���B �y���炷���z�z�e���E�A�g�����e�B�N�̑O�ɋ����[���̂��������𒅂��A�N������h�A�}���������Ă���A���q������]�ƈ��������������ڒu����Ă���B�ނ̐����́A�d�����I������ɔނ��A���Ă�������̂Ђǂ��A�C�Ȑ��E�ɁA���P�������炷�B����Ђǂ����V��̎��A�d���g�����N�����낷�̂ɁA�ނ̗͂ł͂������ɗ����Ȃ��Ȃ��Ă����B����������x�z�l�́A�ނ̃|�X�g�������ƎႢ�͂̂���j�ɏ���悤�����A���N�̐����Ȏd���Ԃ�̂��߁A�ނ����ق͂����A�g�C���̔Ԑl�̎d������^���邱�ƂɌ��߂�B�V�l�̌ւ�͂����ӂ��ꂽ�B�ނɋ����[���̐�����E������x�z�l�̑O�ɁA�ނ͂��������藐���ė����Ă���B���̎��ނ́A�����J����邱�ƂɂȂ��Ă���Â̌������̂��Ƃ��v���o���B�����ŒN�̖ڂɂ����܂�ʂ����ɁA�ނ͒E�����ꂽ�����̐����̓����Ă���˒I�̌��������Ǝ��B���ꂩ��ł��Ђ�����āA�ނɐV�����d�������蓖�Ă鏗�����̌ォ��A���߂��Ȃ�����čs���B �@��ɂȂ��Ĕނ̓z�e���ɖ߂�A�E�����ꂽ�����𓐂ݏo���B�Ƃ����͉̂Ƃō���̏j���̎��ɁA�N�ɂ��ٕςɋC�Â��ė~�����Ȃ�����ł���B�j���̐Ȃł������������ς�����ނ́A���ł��݂�Ȃ��瑸�h����Ă���h�A�}�����Ƃ������ȋ\�ԂɐZ��B���������ɂȂ��Ĕނ́A�Ăю����̎S�߂����ӎ�����B�[���A��̍ۂɒ��邽�߂ɁA�ނ͐������w�̎�ו��������ɗa����B�Ƃ��낪�f�ꂪ�ނɐe���������ŁA�����ɒg�����H�������āA�z�e���̃h�A�̏��֎����čs�����A�����ɂ���V������̒j�����āA�т�����V����B�����ăg�C���ɍs���悤�Ɍ����āA�V���������A�����̏������ē����o���B�[���V�l�������p�ł����Ɨ�����z���Ă����ƁA�݂�Ȃ��ނ�}��̖ڂł��낶�댩��B�����݂�Ȓm���Ă���B�Ƒ��͔ނɏo�Ă����ƌ����B��A�ނ̓z�e��������Ԃ��ɍs���B�N�������x�������A�ނɑ��ėF���ۂ��Ă���A�ނ��Ԃ߂�B �@�������^���͕ς��B����Ƃ�g�̋������̂��q���ނ̘r�̒��Ŏ��ɁA�����ɂƂ��āu�Ō�̐l�v�Ɉ�Y���c���Ƃ������Ƃɂ��Ă������̂ŁA�ނɂ͋������̍��Y����Y�Ƃ��ē������̂ł���B�ނ͎����ɐe��������x�ƈꏏ�ɁA�߂Ă����z�e���ŏj����B�����Ĉ��̒Ҕn�Ԃ����̓�l�̔N������F�l���A�����Ɣ����������։^��ōs���B �y����z���z�e���̃h�A�}�����V�������߂Ƀg�C���̔Ԑl�Ɋi��������A�����̐�����E������Đ�]����Ƃ������̖��������@�̌��ɂ��āA���B���[�E�n�[�X�́u��������A��������A�L�l�}�g�t���t�B�[�̐V�������オ�n�܂�v�Ə������B�x�������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŕ���B �y�f��]�z��1925�N1��6���t���́u�f��T�ԁv���\�\�u�c�c�O��I�Ɋw�ђ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�f��ɂ͉����̖@�������̂܂ܓ��Ă͂܂�A���̖@�������o�I�\���\�̖͂��ɗ��Ă邱�Ƃ́A�ē��Ƃ�o�D������J�����}���̍˔\�ɔC����Ă���̂��Ɗm�M���Ă����҂́A12��23���ȗ��A�h�C�c�Ɏ��o��̎p���݂̂Ɉˑ����A��������o�Ă��āA��ۂ�`�B����̂Ɋ��S�ɔ[����������̂����������o�I�͂ւƓ����A�f��|�p���̂��̂����݂��Ă���Ƃ������Ƃ�m�����B���Ƃɂ��Ƃ���12��23���́A�f��|�p��ʂ̒a�����ł���B�����Ă���܂ŋN���������Ƃ͂��ׂāA���̈̋Ƃ̒P�Ȃ�i�K�ɉ߂��Ȃ������̂ł���c�c�v�B ��1924�N12��24���t���w���x���g�E�C�G�[�����O�̔�]�\�\�u�c�c�w�Ō�̐l�x�̓h�C�c�̍ŗD�G�f��Ȃ̂ŁA�C���^�[�i�V���i���ł���B����̓A�����J�̂��̂��A�A�����J�̍ŗD�G�f��ł���C���^�[�i�V���i���ł���̂Ɠ����ł���B�J�[���E�}�C���[�́A�������ēł͂Ȃ��̂ɁA�ēƂ��āA���邢�̓J�����}���Ƃ��ăV�i���I�������A�B��̉f��V�i���I���C�^�[�ł���B���Ȃ�ʂ��̎��ۓI�Ȋ���ړ��̔\�͂��A���Ƃɂ��Ǝ��܁A���܂�ɕ��w�I�ɁA���邢�͂��܂�ɍ��{�I�ɋ�������߂�����������Ȃ��B�}�C���[�̔��W�ɂƂ��ďd�v�ȃV�i���I�́A���Ƃɂ��Ɖf��̂��Ƃ�\���������m�ƁA���ۓI�Ȃ��Ƃ�\�������f��l�Ƃ̊Ԃ́A��������������������Ȃ��c�c�B�V�i���I���C�^�[�Ƃ��ẴJ�[���E�}�C���[�ƁA�ēƂ��Ẵ����i�E�Ƃ��A���Ɉ�̑S�̂��\�����Ă��邱�Ƃ́A�w�Ǖ��x�Ȍ㖾�ĂɂȂ����B���̍�i�ŁA���҂̒�g�̉��l���ؖ����ꂽ�B�����i�E�͉��Ƃ��炵�������������Ă��邱�Ƃ��낤�B�h�A�}���ƈꏏ�Ɉړ�����J�����́A�ނ��牓����������A�ނɋ߂Â����肵�āA����ւ����l�����A���Ƃ��炵�����Ε����֗h�ꓮ���A�N�V�����Ƃ��Ĉ����Ă��邱�Ƃ��낤�B�����Ă��̃A�N�V�����̒��ł́A�������Ɩ��̃A�N�Z���g���A�e���|�̏I������A���ׂĂ悭�l���s������Ă����[�[����͊��S�����̌���ł���A�J�����}���̃t���C���g�́A����ɔ��Q�̘r�ŎQ�^���Ă���c�v�B 1924.12.29 �w�����ǂꏗ Bacchantin�x ���[�g���B�q�E�K���O�z�[�t�@�[����A �y�L���X�g�z�I���K�E�`�G�z���@�A�p�E���E���F�X�^�[�}�C���[ |
|
| 1925 | |
| 1925 �w���̉� Liebesfeuer�x �o�E�k�E�V���^�C���ē� �y����z�N���J�E�A�[215�� 1925�i���{����1927.4.27�j �w�F���̋��� Wunder der Schöpfung�x �y����z�N���J�E�A�[�A156 1925�i���{����1928.5.25�j �w���͖Ӗځ@Liebe macht blind�x �y����z�p����Ƃ��������f��B 1925�i���{����1928.4.21�j �w�슛 Die Wildente�x ���[�v�[�E�s�b�N�ēA�V�i���I�F�e�E�J�[���Z���A���[�v�[�E�s�b�N�i�w�����b�N�E�C�v�Z���̃h���}�ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�f���E�X �y�L���X�g�z���F���i�[�E�N���E�X�A���`�[�E�w�[�t���q 1925.2.11�i���{����1926.10.1�j �w�����j Zur Chronik von Grieshuus�x �A���g�D�[���E�t�H���E�Q�����n�ēA�V�i���I�F�e�A�E�t�H���E�n���u�i�e�I�h�[���E�V���g�����̏����ɂ��j�A�B�e�F�t���b�c�E�A���m�[�E���@�[�O�i�[�A�J�[���E�h���[�t�X�A�G�[���q�E�j�b�`���}���A���u�F���[�x���g�E�w�����g�A���@���^�[�E���[���q�A�n���X�E�y���c�B�q �y�L���X�g�z�p�E���E�n���g�}���i�q�����b�q�j�A���h���t�E�t�H���X�^�[�i�f�[�g���t�j�A�����E�_�[�S���@�[�i�O���^�j�A�A���g�D�[���E�N���E�X�l�b�N�i�O���[�X�t�[�X�̗̎�j�A�Q���g���[�g�E���F���J�[�i�I�����~�����f�j�A���h���t�E���b�^�[�i�I�[���F�E�n�C�P���j�A�n���X�E�y�[�^�[�E�y�[�^�[�n���X�i�����t�j�A�Q���g���[�g�E�A���m���g�A���[�[�t�E�y�[�^�[�n���X �y���炷���z�i��l�̌Z�킪����̑������߂����đ�������B�s�g�Ȓ����`���̕��͋C���Y���j�B �@�O���[�X�t�[�X�̗̎傪�S���Ȃ����̂��A�ނ̓�l�̑��q�̊Ԃʼn�ȑ����������N����B�����l�̃q�����b�q�͕��̈ӎu�ɔ����āA�܂�ʉ��l�̖��O���^�ƌ������Ă����B�������Ƒ��̒��ْ̈[�҂�������̃f�[�g���t�́A�M���̖��I�����~�����f�ƌ������Ă����B�����Ŕނ͑����̌������咣���đ������B�Ό��������Ă��邤���ɁA�O���^�̓f�[�g���t�ɋ�������Ă���Ɗ����āA���E��ԂɊׂ�A�q�����Y�ۂɎ���ł��܂����B�q�����b�q�͒�̃f�[�g���t��㩂��d�|���A�����Ŕނ��E���Ă��܂��B�������ނ̓O���^�̎��ɋ������A�܂�����E���Ă��܂������ƂɉՂ܂�āA�O���[�X�t�[�X�̏�������āA���ɏo��B���̊Ԕނ̏����ȑ��q�����t�́A�����Ɉ�Ă���B�q�����b�q�͔��N��ɖ߂��ė��āA�͂��߂đ��q�����t�ɉ�B�ނ͂��傤�Ǘǂ��Ƃ��ɋA���������̂ł�����B�Ƃ����̂̓I�����~�����f�������t��U���o���ė{�q�ɂ��A����ɂ���ăO���[�X�t�[�X�������̂��̂ɂ��悤�Ƃ��Ă������炾�����B�������ĕ��Ƒ��q�͂���ƃO���[�X�t�[�X�̎�ƂȂ邱�Ƃ��ł����B 1925.3.3 �w�������\�t Heiratsschwindler�x �J�[���E�x�[�[�ē� �y�L���X�g�z�P�[�e�E�n�[�N�A���[�U�E���@���b�e�B 1925.3.16�i���{����1926.10.22�j �w���Ɨ͂ւ̓� Wege zu Kraft und Schönheit --Ein Film uber moderne Körperkultur�x �ēF���B���w�����E�v���[�K�[�B�V�i���I�F���B���w�����E�v���[�K�[�B�|�p�E�w�p�ږ�F�A�E�O�X�g�E�P�X�^�[���m�A�A���g�D�[�A�E�J���v�����A�t���b�c�E�N�����V�������A�J�[���E�G�r���O�n�E�X�����B�B�e�F�t���[�h���q�E���@�C�}���A�I�C�Q���E�t���q�A�t���[�h���q�E�p�E���}���A�}�b�N�X�E�u�����N�A�N���g�E�m�C�x���g�A���[�R�v�E�V���b�c�H�[�A�G�[���q�E�V���e�b�J�[�B���u�F�n���X�E�]�[�����A�I�b�g�[�E�G���g�}���B���y�F�W���[�[�b�y�E�x�b�c�F�A����F�E�[�t�@�f�敶���f�敔 �y�L���X�g�z�v���C�Z���̈��w�A���Y���E���y�E�̈�̂��߂̃w�����E�E�X�N�[���i�_���N���[�Y�j�A���[�G�����g���x�w�Z�A�{�[�f�E�X�N�[���A�A���i�E�P���}�������E�̈�X�N�[���A�}���[�E�E�C�O�}�����x�O���[�v�A���o���E�X�N�[���A���̑�������X�|�[�c����̐��E�L�^�ێ��ҁA��ҁA�j���̃_���T�[�i�j�f�B�E�C���y�R�[�t�F���A�^�}���E�J���T���B�[�i���j�A�u���[�}�̌��O����v�̃V�[���Ƀw���^�E�t�H���E���@���^�[�A���j�E���[�t�F���V���^�[���A�G�[�t�@�E���[�x���x���N �y����z�x�������ő�̉f��فu�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�Ńv���[�K�[�ē̃E�[�t�@�����f�敕��B�u���O�����IVolksbildend�v�Ƃ����]�_�i�v���f�B�J�[�g�j��^����ꂽ�B �@�̑��I��║�x�Ƃ��ĂяW�߂ăv���[�K�[�́A�k�[�f�B�Y���^������슴���f��삵���B���̒��ɂ͓����ɐ��E�I�ȏ^���Ă������V�A�̃o�����[�i�̃J���T���B�[�i���������A�h�C�c�Ő���ȁu�m�C�G�E�^���c�v�̐l�C�ҁA�j�f�B�E�C���y�R�[�t�F���������B����͌ÓT�Ñ�̃M���V���̑̈���[�}�̌��O����i���[�t�F���V���^�[���̏o���V�[���j����A����̃X�|�[�c�E�V�[���A�����I�̑��║���Ɏ���܂ł̓��̂̏C����`���A��G���e�B�V�Y���I�k�[�h�́A�ϐ��̎�ꂽ�͋����l�Ԃ̎p�𗝑z�������B����́u�Z�I�I�ȃ|�[�Y����I�ȃZ�b�g���g���āA�Ñ�̗L���ȁu���S�Ȃ�g�̂Ɍ��S�Ȃ鐸�_���h���ė~�����v�Ƃ������b�g�[�̉f������ڎw�����B���̃��b�Z�[�W�͌ÓT�Ñ�̐��_�ɂ�錻��̃h�C�c�̎�҂̓��̂̍Đ��ł���A���̖ړI�ɉ������`�p�m�ɒ掦�����B ���̊܈ӂ@�����t�����N�E���@���V���E�A�[�́A�l����\�����t�́u���E����v���ɘ_�]���ڂ��A�u�w���Ɨ͂ւ̓��x�́m�R�l�哝�́n�q���f���u���N�ɁA�����F���ɒʂ��邩������Ȃ��ƐS�z����Ă���̂́A�܂��Ƃɂ����Ƃ��ł���B�Ȃ��Ȃ炱�̑f���炵���A����߂ċ���I�ȃX�|�[�c�f��́A�c�O�Ȃ��瑼�̂��ׂĂ��A�P�ɐV�����R����`�ւ̏����ƌ������˂Ȃ��ŏI��ʂ������Ă��邩��ł���B�c�c�v�Ə������B�u�ÓT�Ñ�̐��_�ɂ�錻��h�C�c�̎�҂̓��̂̍Đ��v�[�[�P�X�R�U�N�̃x�������E�I�����s�b�N�́A�i�`�ȑO�̏����i�K�ł��łɁA���������u�����Ƃ��Ă����B 1925.4.24 �w��Ƃƃ��f�� Der Maler und sein Modell�x �y����z�p���ƃs���l�[�R�n�ŎB�e���ꂽ�ƕ�����f��A�x�������̃N�[�A�t�����X�e���_���ŕ��� 1925.5.3 �u��Ήf��v��f �y����z�x����������N�[�A�t�����X�e���_���́u�E�[�t�@�E�e�A�[�^�[�v�ŁA�}�`�y�ѓ��������́u��Ήf��v�������̊ϋq���W�߂ď�f�B�v���O�����ɂ̓��B�L���O�E�G�b�Q�����O�A���b�g�}���A�t�F���i���E���W�F �A���l�E�N���[���A�q���V���t�F���g- �}�b�N�A�n���X�E���q�^�[�̎����f�悪�ڂ��Ă����B 1925.5.12 �w���� Lebende Buddhas�x �p�E���E���F�[�Q�i�[�ēA�V�i���I�F�p�E���E���F�[�Q�i�[�A�n���X�E�V���g�D�����A�B�e�F�O�C�g�E�[�[�o�[�A���C�}�[���E�N���c�F�A���u�F�n���X�E�y���c�B�q�A�{�[�g�E�w�[�t�@�[ �y�L���X�g�z�p�E���E���F�[�Q�i�[�A�A�X�^�E�j�[���[���A�P�[�e�E�n�[�N�A�O���S���[�E�t�}�� �y����z��l�̉p���̋������`�x�b�g�����̐Ղ����ǂ�B 1925.5.18�i���{����1928.9.28�j �w��тȂ��X Die freudlose Gasse�x �Q�I���N�E���B���w�����E�p�v�X�g�ēA�V�i���I�F���B���[�E�n�[�X�iWilly Haas�j�m�t�[�S�E�x�b�^�E�A�[�̏����w��тȂ��X�x�ɂ��j�A�B�e�F�O�C�g�E�[�[�o�[�A�N���g�E�G���e���A���u�F�n���X�E�]�[�����A�I�b�g�[�E�G���h�}���A����F�]�[�t�@�f�� �y�L���X�g�z�O���^�E�K���{ Greta Garbo�i�O���[�e�E�����t�H���g�j�A���[���E�t���g Jaro Furt�i�����t�H���g�{���ږ⊯�j�A���[�j�E�l�X�g�i�}���A���h���E�����t�H���g�j�A�A�X�^�E�j�[���Z���i�}���A�E���q�i�[�j�A���F���i�[�E�N���E�X�i�����j�A�C�A�����E�n���\���i�f�[���B�X���сj�A�}�b�N�X�E�R�[���n�[�[�i�}���A�̕��e�j�A�W�����B�A�E�g���t�i�}���A�̕�e�j�A�J�[���E�G�g�����K�[�i���[�[�m�t�j�A�C���J�E�O�����[�j���O�i���[�[�m�t�v�l�j�A�A�O�l�X�E�G�X�e���n�[�c�B�i���M�i�E���[�[�m�t�j�A�A���N�T���_�[�E�����X�L�[�i���C�g���m�j�A�^�}���E�g���X�g�C�i���A�E���C�g�j�A���[�x���g�E�K���\���i�h���E�A���t�H���X�E�J�l�X�j�A�w�����[�E�X�`���A�[�g�i�G�S���E�V���e�B���i�[�j�A�}���I�E�N�X�~�q�i�A�[���B���O�卲�j�A���@���X�J�E�Q���g�i�O���C�t�@�[�v�l�j�A�g���X�g�C���ݕv�l�i�w�����G�b�e��j�A�G�I�h�i�E�}���N�V���^�C���i�����P���v�l�j�A�w���^�E�t�H���E���@���^�[�i�C���[�j�A�O���[�S���E�t�}���i���d�j�A���X�J�g�t�i�g���[���B�b�`���j�A�N���t�g�����b�V�q�A�I�b�g�[�E���C�����B���g �y���炷���z�i��ꎟ���E����̃C���t������̃��B�[���̊X�̃G�s�\�[�h�j �@��ꎟ���E����A�s��̒����B�[���͂Ђǂ��C���t���ɏP��ꂽ�B���Y�K�������鍑�̍��������I�[�X�g���A�̓s�s�M�����A�������j�ǓI�C���t���ɉ���������āA�ꂵ��ł����B����ł��ނ�̖͐̂̑ʂ�ۂ��Ƃɋ��X�Ƃ��Ă����B�������Ƃ̒��ł͐�]�ƋQ���ɋ�������Ă����B�����������ł́A�ߍ��Ȍ������D�@�Ƃ��āA���Ԉ�ʂ̋����𗘗p���āA�t�ɗ��v���V���������K��������Ă����B���̒��ł��A�ȑO�r�[���b�c�ŗm�������������[�[�m�t�́A���͒������[���b�p��s�̎x�z�l�Ƃ��āA��Ԓ����Ƃ������������B�ނ͌l�I�ɂ͔�̑ł����̂Ȃ��P�ǂȐl�����������A�����l�Ƃ��Ă͊C��R�炾�����B�����ē����͊X�H�ł��i���X�ł��A���鏊�œ��@�I�Ȏ���������Ȃ��Ă����B�v�����鋌���������w�̓T�^�ł��郈�[�[�t�E�����t�H���g�{���ږ⊯�܂ł��A����������ʂ̓��@�M�̂Ƃ肱�ƂȂ��Ă����B �@�ނ͎����I�ɑސE���A�⏞�����H�Ɗ��ɓ����������A����͊ԈႢ�Ȃ��|�Y����悤�Ȋ�Ƃ������B�����đ��Ȃ�ʃ��[�[�m�t������ɖڂ����A����A���[���`���l�Ƒg��ŁA������߁A���̊�Ƃ������B�����t�H���g�͎����������ׂĎ����������łȂ��A���̏㍷�z�̕�U�܂ł��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������B�����Ă��Ă͗T���������n��S�̂��A�n���������B�����t�H���g�̏Z��ł��������q�I�[���������A���̈�������B �@���₱�̊X�͉��\�ȓ����Ɨm�����̃O���C�t�@�[�v�l���H�U��𗘂����X�������B�����~��O�ɂ��āA�Z�����Q���Ɠ�����Ƃ�邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����́A�ނ炪�i�����Ă���邩�ǂ����ɂ������Ă����B�����ނ�͂����������͂̍����A����߂Ĉ�煂ɗ��p���s�������B�����͓����a�ɂ��ď������������B�O���C�t�@�[�v�l���Y��ȏ��̎q�ɂ́A���Ŋ|�����肵�����A����ɂ͎v�f���������B�ޏ��̎d����̌��ɂ͏����ȃT����������A�����Ŕޏ��͈��������̈��������Ă����̂������B�S�g���ɋQ���Ă������̒n��̎Ⴂ�������́A���̋U��̋P���̗U�f�Ɏ��X�ɋ������B �@�v�����đ������l�X�̗���ƁA�s�i�s�Ȑ��������̂Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ����y�B�������������͋C�̒��ŁA�ˑR�A���̂̒m��Ȃ����낵���E�l�������N�����B���̊X�̏����ȁA�������킵�����قŁA���[�[�m�t�E�R���c�G�����̖@���ږ�̍ȂŁA�������𗬂��Ă������A�E���C�g���E����Ă���̂����������̂ł���B���^�̓R���c�G�����̋�s���G�S���E�V���e�B���i�[�Ɍ�����ꂽ�B�ނ͔ޏ��Ƒ�ϐe���ȊW������ł������炾�����B�ނ͑ߕ߂���A�۔F�����ɂ�������炸�A�����Y�ɏ����ꂽ�B �@��������t�H���g�ږ⊯�̉Ƃ́A�ߎS�ȏ�Ԃ������B�ږ⊯�͂�������ł��̂߂���Ă����B�Ƒ��̒��ł́A���������̃O���[�e�������A������l���Ȃ��ɂ��A�ꋫ��蔲���悤�ƌ����ɂȂ��Ă����B�~���̐_�̓A�����J�̋~���R�̏��Z�f�[���B�X���A�Ԏ�l�ɂȂ��Ă��ꂽ���Ƃ������B�ނ̓h���Ŏx�������B����͂������藎���Ԃ�Ă��܂����Ƒ��ɂƂ��ẮA��ςȉ��b�������B�������g���ӎ��ɋÂ�ł܂��������t�H���g�ږ⊯�́A���̐l�D���̂����҂��A�c����j�ł������G�Ƃ������Ȃ������B�Փ˂܂��ՓˁB������ʂĂ��f�[���B�X�́A���̊ԂɃO���[�e��������悤�ɂȂ��Ă͂������A������Ƃ��Ƃ��o�Ă����Ă��܂����B �@����ʂĂ��O���[�e�́A�O���C�t�@�[�v�l�ɗ���ق��Ȃ������B�ޏ��͐M�p�Ŕ����A����ɋ����肽�B����ƃO���C�t�@�[�v�l�͖{�����ނ��o���A���t�̎�莝�������āA�ޏ���j�łɒǂ��������Ƃ����B�����������ŗ�̎E�l�������v��ʓW�J�𐋂��āA���������B���w�̃}���A����������o�����āA�������E�����Ǝ��������̂������B�P�ǂł͂��邪�y���Ȕޏ��́A�ȑO�G�S���̏�w�������B�����Ń��A�ƃG�S�����ӂ��������Ă���̂������ޏ��́A���A�̂����Ŏ����͎̂Ă�ꂽ�̂��Ǝv�����݁A�Ђ����Ƀ��A���E���āA���^���G�S���ɂ�����悤�Ɏd�������̂������B �@�O���[�e�������悤�ɓ]�������˂Ȃ��������A�ޏ����ˑR�Ƃ��Ĉ��������A�����锽�ɂ�������炸�A�ޏ���M�������Ă����f�[���B�X���A�ޏ����~�����B�����ē�l�͌��ꂽ�B���̊ԂɌx�@�̓O���C�t�@�[�v�l�̉Ƃ̉������ȏɖڂ������B���������ɑ���X�̏Z�l�����̑����́A��]�I�ȍs�ׂƂȂ��Ĕ��������B�呀���]���ɂ��Ď����Ǝq���̘I�����Ȃ��ł�������ȕ�e�̈�l���A�ނ��h���E�����̂ł���B �y����z�A�����J�ŃX�^�[�ƂȂ�O���^�E�K���{���o���B �@�\����`�̔g���ޒ����āA�������q�ϓI�Ɍ���V�����X���̎���ƂȂ����Ƃ��A���̎咪�ƂȂ�X���́A������u�V������`�v�������B���̒��ő��̊ēƈꖡ��������݂Ƃ��Ē��ڂ��ꂽ�̂��A�p�v�X�g�������B�ނ͊X���f���[�j�b�V���ȉ^���̏ꏊ�ƌ���\����`�̊X�H�f��Ƃ͈�������_����X�������B�܂�u��l�̐l�Ԃ̋��R�Ȑ����ł͂Ȃ��A�T�^�I�Ȑ�����W�]����f��v�̎���̌�������B���ꂪ���́w��тȂ��X�x�ł���A�ނ͂���ɂ���āA�u���[�_�[�I�ȃh�C�c�̃��A���Y���ēv�Ƃ����������邱�ƂɂȂ����B�����ނ̃��A���Y���́A���}���I�E�����h���}�I�X�����A�l���I�ɔ۔F������̂ł͂Ȃ������B�u�^�̐��͂���߂ă��}���I�ł���v�Ƃ����̂��A�ނ̍l���������B �@�����ނ��u���قȁv���A���Y���ēƏ̂����̂́A���������M�O�ɂ���Ăł͂Ȃ��B�����܂ł��f��\���̓��ِ�����Ăł���B���̉f��̓h�L�������^���[�ł͂Ȃ������B�p�v�X�g�̓X�^�W�I�Ɂu��тȂ��X�v��������B�����Ă�����I�݂ȏƖ��̌��ʂŁA�\��L���ȉf���Ƃ��đ������B����������@�ɂ���āA�ނ͑���̃��B�[���Ƃ����A����̎Љ�̏�`�����B�������ނ̑��������A���e�B�ɂ́A�����Ȕނ̚n�D���������B�Z�b�b�N�X�ł���B�u�ނ̍�i�ł͔��t�A�́A�퐔�Ƃ��Ă̈Ӗ��������Ă����v�B �@���̍۔ނ͏����ɑ�����ʂɉs�����o�ɂ���āA����߂ăA�g���N�e�B���ȉf���\���ݏo�����B���̉f��ɂ����ẮA�O���^�E�K���{���f�r���[���A�A�X�^�E�j�[���[�������w���œo�ꂵ�A�O�q�I�\�����x�̌��c���@���X�J�E�Q���g���A���t�������œo�ꂵ�A�܂��ƂɌ��ʓI�Ȉ�ۂ�^���Ă���B�܂��w�C�G�X�^�E�x���k���x�̃x����������̂��߂ɁA�f��ē}�E���b�c�E�X�e�B���������A��Ă��������̃O���^�E�K���{�����āA�p�v�X�g�͒����ɃK���{�[�j�[���Z���̑g�ݍ��킹�������̂������B���C�̗d���Ƃ��ẴK���{�̓o��ł���B����j�[���Z���͋������̘V���ƉƂ̏�w�����A�ɐƌ����Ă悢�\���͂ʼn������B���g��⌦�̈ߏւŋɊy���̂悤�ɏ��藧�Ă����̏��w�̖ڂɂ́A���낵���قǂ̋�����������Ă���B�����Ă��ׂĂ�j����I�Փ��ɋ�藧�Ă�ꂽ���̂悤�ɁA�ޏ��̈ȑO�̈��l�̐V�������l���E���B���ꂩ��ޏ��͊O�ʓI�����𓊂��̂ĂāA�ޏ��̃p�g�����̑����ɂЂꕚ���B����قǗ��`�̐^�����f�������ꂽ���Ƃ́A�܂��Ȃ������B�A�h�E�L���[�́u���Ƃ��ꂪ������̎Љ�I�R���e�N�X�g�̒��Ŏ��Ǝ��̉��l�́A�p�v�X�g�̎�v�ȃe�[�}�ł���A�ނ̓W���[�W�E�O���X�̃X�P�b�`�ɉe������āA�ނ̐l�����̉��ʂ����A�ނ�̂���߂ĉ������Ȋ��\��\�I����v�Əq�ׂĂ���B �@�p�v�X�g�̃��A���Y���͕��ՓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���������肳�ꂽ�g���ł́A�e�[�}�͕��Ă����ɂ�������炸�A�\�I�I�͉��ؖ����������Ă����B�����Ƃ��L���Ȃ̂́A�N���������Ƃ���A�����̓X�̑O�ɕ��A���ʂĂ��������̒�����̑O�ŁA���̂������傫�Ȍ���A�ꂽ�֖҂ȓ������A�⍓�ɓX������ʂł���B�p�v�X�g�̂���������i�`�ʂ̂����܂����́A��Ɉ�т����ނ̓��F�ł���A�ނ̎Љ�I���͂̎����l�ł���B�R��������ɏƂ炳�ꂽ�X�H��Â������ƁA�����ґ�ȃz�e���̂�����悤�Ȍ���̃R���g���X�g�����ݏo���A�ۗ������������[�[����͔ނ̉��Ȃ����̖\�I�Ɠ���̚n�D�ɗR��������̂������B���̈Ӗ��ł́A�u�����̓X�̑O�ɍs�Ă��鏗�̋q�����̑����A���n�����̑����璭�߂Ă�������̗~��ɘc�炱���A���̉f��̊��o�I�������A���S�ɖ��炩�ɂ�����̂ł���v�B 1925.5.19 �w�C���s�G�g�� Pietro,der Korsar�x �A���g�D�[���E���r�]���A�V�i���I�F�A���g�D�[���E���r�]���i���B���w�����E�w�[�Q���[�̏����ɂ��j�A�B�e�F�t���b�c�E�A���m�[�E���@�[�O�i�[�A���h���t�E�}�e�A���u�F�A���r���E�O���E �y�L���X�g�z�A�E�h�E�G�Q�Q�E�j�b�Z���A�p�E���E���q�^�[�A���h���t�E�N���C�������b�Q �y����z�C���̊Ԃł̃��u�Ǝ��i�̕��� 1925.6.26 �w�f��̒��̉f�� Der Film im Film�x �t���[�h���q�E�|���Q�X�ēA�V�i���I�F�t���[�h���q�E�|���Q�X�A�V���e�t�@���E���[�����g �y����z�t���b�c�E�����O�A�p�E���E���[�j�AE�EA�E�f���|���ē��̉f���L�^���܂������A�f��̔��W�ɂ��Ă̋���f��B 1925.8.29�i���{����1926.12.10�j �w��܊K�� Die Verrufenen--der fünfte Stand�x �Q���n���g�E�����v���q�g Gerhard Lamprecht�ēA�V�i���I�F���C�[�[�E�n�C���{�������P���r�b�c�A�Q���n���g�E�����v���q�g�i�x�������������`������ƃn�C�����q�E�c�B���ɂ��Ȃc�B���iZille�j�̑̌��ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�n�b�Z���}���A���u�F�I�b�g�[�E�����f���n�E�A�[ �y�L���X�g�z�x�����n���g�E�Q�c�P�i���[�x���g�E�N���[�}�[�j�A�A�E�h�E�G�Q�f�E�j�b�Z���i�G���}�j�A�G�h�D�����g�E���[�g�n�E�U�[�i�ʐ^�t�j�A�}�f�B�E�N���X�`�����X�i�Q���_�j�A�A���g�D�[���E�x���Q���i�Z�t�j�A�t���[�_�E���q�����g�i�}���K���[�e�E�N�b�p�[�A�p�E���E�r���g�A�Q�I���N�E���[�� �y���炷���z���ł��������߂ɁA�U�̍߂�Ƃ����Z�t�̃��[�x���g�E�N���[�}�[���A�Y��������o�������B�ƂɋA��ƁA���e�́u���V�����肵���悤�ȓz�ɂ́A�킵�̉Ƃɋ��ꏊ�͂Ȃ��v�ƌ����āA�ǂ��o���Ă��܂��B���ł��ނ����ށB�����Ԃꂽ���[�x���g�͕��Q�Ҏ{�݂ɓ���B�d���ɂ��Ԃꂽ���Ӗ������Q�҂́A����Œa�������j���Ă��A�u���߂łƂ��A�����ǒ���������Ƃ͌���Ȃ���v�ƈ��A�����n���ł���B �@��]�������[�x���g�͎��E����Ă邪�A�S�D�������t�w�G���}�Ɏ~�߂���B�ނ̓G���}�̂Ƃ���֔��A�d����������B�̖ʂ��d��g���́A���[�x���g���ǂ��ɂ��邩��m��ƁA�p���āA�ނ��A�����J�֍s�����悤�Ƃ���B���Ă̋��ł����̎g���ɂ���ė���B�ނ̃G���}�̕��S���āA�ޏ���ǂ��Ԃ��B �@�������ˑR���[�x���g�ƃG���}�Ƃ̊Ԃ͈������B�G���}�̌Z����������ŁA���[�x���g�ƈꏏ�ɕ������Ă������A�V�����������N�����A����ɃG���}�����������߁A�Z�Ǝo��l�͓��S���邱�ƂɂȂ�B �@���[�x���g�̓x�������ɏo�āA���̘J���҂Ƃ��ē����B��������[�x���g�ɍK�^���K���B�H��̋@�B���̏Ⴕ�Ď~�܂��Ă��܂��A�@�B���C���ł���f���b�Z���h���t�ɓd�b������A�呛���ɂȂ��Ă��܂��B�o�c�҂͒����ɊԂɍ��킹�邽�߁A�@�B�������ɂł������������B����ƃ��[�x���g���C�����ďo�āA��������B�o�c�҂��ނ��Z�t�����������Ƃ�m��ƁA�ƂɌĂ�Ŗ��ɏЉ��B���[�x���g�͉ߋ������A�u�Ăя㏸�������Ƃ�����]�I�Ȉӎu�������A���ɂ��̕M��ɐs�����������߂��������������E�����̂ł��v�ƌ����B�o�c�҂͔ނ��Ǘ��E�Ɉ����グ��B �@��N���߂�����B�G���}�͎��̏��ɏA���Ă���B�����Ď��ʑO�ɂ�����x�ނɉ�����ƌ����B�ޏ��͌����B�u���͂�������̒j�ɕ�����͂����ɂ��Ă��A����ł����[�x���g�������Ă���̂ł��v�B����ƃ��[�x���g������ė���B�ޏ��̓��[�x���g�ɕ�����Ď��ʁB �@�u�n���ƔߎS�A�����ƃA���R�[�����A�l�X���܊K���ƌĂ����̂ɂ���v�Ƃ����̂��A���̃c�B���f��̌��_�������B �y����z���̉f��́u�c�B���f��v�Ə̂�����i�̑�\�ł���B�n�C�����q�E�c�B���̓x�������̋��y��ƂŁA�u�~�����[�v�ƌĂ��x�������̕n���n����A�Ɠ��̈��D�����߂��M�v�ŕ`�����Ƃɐ�O���Ă����B���p�j��ł͖��ɂȂ��Ƃł͂Ȃ����A�x�������̂���Ή�����̌����Ƃ������ׂ����݂ŁA�����̃x�������q�ɂ́A���������ɑi����������̂������Ă���B�����āu�ނ̕`�����h�{�s�ǂ̎q�������A�J���ҁA���t�w�A�݂��ڂ炵������̎�I���K���e���A�̂炭�玞�Ԃ����Ă���S�߂ȏ��ƁA���̂̒m��Ȃ��A���̎p�́A�h�C�c�l�����ɑ傢�ɐl�C�����v�B �@���̃c�B���́u�~�����[�v���f�扻���悤�Ƃ��铮�����A1925�N�����琷��ɂȂ����B�����͂܂��V�l�ē����������v���q�g�́A���̐�ڂ����Đ������A�h�邬�Ȃ��n�����l�������B�ނ̓c�B������A�{���ɂ������b���B����ɂ���ăV�i���I���������B�c�B���͂����ǂ�Ŋ������A�B�e�ɗ���������B�����v���q�g���C�ɂ������̂́A���ׂĂ��ł������{���ɂ��邱�Ƃ������B�����Ŕނ̃A�V�X�^���g�����́A�����y���̖�Ԏ��e���A���݉��A�V�����[�W�G���w�̈Â����Ȃǂ��A����݂Ԃ��ɒT��������B�����łƂ��Ƃ��X�^�W�I�̒��ɁA���t�w��q��������ꂪ�A���悤�悷�邱�ƂƂȂ����B�����v���q�g�͖{���̃u�����f�[���o���{���̎���A��l���������̒a�������j����������Ă������B �@���̂悤�ɂ��āw��܊K���x�͏o���オ�����B����͖����߂ȉf�悾�����B�������������f�悾�����B�܂��Ƀh�C�c�Łu�����̐l��v���ꂾ�����B��l�����~�����G���}�́A�o��������l���Ɏ̂Ă��Ă��A����͌���Ȃ��B�����Ď��̏��ɋ삯������l���̃��[�x���g�̘r�ɕ�����Ď��ʁB�܂��ɗ܂̃����h���}���̂��̂ł���B����䂦�O�ꂵ���v�V�I���_�ɗ��r�E�N���J�E�A�[�́A�����ᔻ�����B �u���̋̉��~���ɂȂ��Ă�������́A��̗v�f�̍����ł���B����ʼnf�搻��҂́A�v�����^���A�[�g�̋��ɂ��āA�������Ƃ����ǂ��njJ��Ԃ����Ƃɂ���āB�Љ�I���Ɏ��g��ł���U�������B�����ň�l�̓��ʂȘJ���ҁi�{���͑S�R���̊K���̐l�Ԃł͂Ȃ��j�ɁA�K�^�ȏ��i�̋@���^���邱�Ƃɂ���āA�Љ�I�����������B�������Ċϋq���q�̐��r�ɖ���������̂ł���B�����K���̍��ق����ǂ̂Ƃ���A�����I�Ȃ��̂Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��A���̕���͂ق̂߂����v�B �@�m���ɎЉ�ᔻ�Ƃ��Ă͂��̉f��́A�܂��������ɐ^���Ɏ��g�ގp���������Ă���B �c�B���f��̎��_�́A�����܂œ����̃x�������̉����́A���j�I�ɌŗL�̕��͋C�������o���A��I�ȖʂɊ�b��u�����̂ŁA�K�������̎��_�ł͂Ȃ��B���̑��肻���ɂ́A�x�������q���ނ�̕����Ō����悤�Ȃ��̂̂��ׂĂ�����B�܂�c�B���́u�~�����[�v�������ɉf��������Ă���B�K���I���_�ƌ������邱�̏�I�Ȗʂ́A�u���̎��v�u���̏�v�Ő�����l�ɂƂ��ẮA��ԐS�ɑi����ʂł���B���ꂪ�ǂ�Ȃ��̂ł��邩���������̂ɂ́A���̉f��͑ł��Ă��ł���B �@�f��̃v���͓����A�����v���q�g���c�B���f�����낤�Ƃ��Ă���ƕ������Ƃ��A����U�����B�����̏펯�ł́A�f��قł���Ȃ��̂���������҂́A����͂����Ȃ������B����ȏ�Y��邽�߂ɂ����A�l�X�͉f������ɍs���̂��B���������l�����l�́A�c�B���f��̖{�������Ⴆ�Ă����̂ł���B�u�n���ƔߎS�v�Ƃ����������̂��̂��A���ł͂Ȃ��̂������B����́u�����҂����v�ł���B�܂�G�L�X�g���Ƃ��Čق�ꂽ���t�w��q����A���������ɁA���̂��̂���̕W���^�����̂������B����̓c�B���̈ӂɔ������W�肾�����B�����Ŕނ́u�����݂͂�Ȃ����Ȃv�Ƃ���������t�����v���J�[�h���X�P�b�`�����B���_�̂̂��A�f��́w�����҂����i��܊K���j�x�Ƃ����A��d�^�C�g���Ō��J����邱�ƂɂȂ����B�v���~�A�E�V���[�͑听���ŁA��Ȃ����c�B���ɔ��芅�т������A�M�������ϋq�ɖW�����āA�����Ԕނ͉f��ق���o�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�y�ē����z��w�Ŕ��p�j�Ɖ����j���w�Ԃ������A�����̌P�����A�f��̃V�i���I�������Ă����B�����ɉf��ēƂȂ�A�g�[�}�X�E�}���̍�i�̍ŏ��̉f�扻�A�w�u�b�f���u���[�N�Ƃ̐l�X�x��������B����ɑ����āw��܊K���x�삵���A�f��ēƂ��Ă̒n�ʂ��m�������B1931�N�A�G�[���q�E�P�X�g�i�[�̏��N���̌���w�G�~�[���ƒT�ソ���x�̉f�扻�A�w���N�T��c�x����������A����͔ނ̂����Ƃ��L���ȍ�i�ł���B�w���R�m�x�i1932�j�A�w�[�g�̗��x�i1933�j�A�w�{���@���[�v�l�x�i1937�j�Ƃ�������i�����������̂��A����E����A�Ō�̏d�v��i�w�x�������̉������Łx�i1946�j�삵���B����̓c�B���f��̗����������i�������B�ނ͂܂��c��ȉf��W�̎Q�l�i�����E���āA�u�h�C�c�E�L�l�}�e�[�N�v�̊�b�����A���珊���ƂȂ����B�����Ĕގ��g���f��j�ƂƂ��āA�w�h�C�c�E�T�C�����g�f��P�X�O�R�|�P�X�R�P�x�Ƃ����A�c��ȃJ�^���O�����������B�ȗ����̃J�^���O�́A���̎����̃h�C�c�f��́A�X�^���_�[�h�Ȗژ^�ƕ]������Ă���B 1925.9.17 �u�E�[�t�@�T�ԃj���[�X UFA-WOCEHNSCHAU�v�̍ŏ��̏�f �y����z�h�C���q�T�ԃj���[�X�ƃ��X�^�[�T�ԃj���[�X�iMESTER-WOCHE�j���������ďo�����u�E�[�t�@�T�ԃj���[�X�v�̍ŏ��̍���f�B����߂Ă��܂��܂ȏo������m�点���B 1925.10.22 �w�e�N�T�X�̔_��� Der Farmer aus Texas�x �W���[�E�}�C�ēA�V�i���I�F�W���[�E�}�C�A�����t�EE�E���@�����[�i�Q�I���N�E�J�C�U�[�̊쌀�w�R���|���^�[�W���x�ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�h���[�t�X�A�A���g�j�I�E�t�����Q���A���u�F�p�E���E���[�j �y�L���X�g�z�����A���E�n�����f�[���B�X�A���B���[�E�t���b�`���A�}�f�B�E�N���X�`�����X �y����z�g���Ⴂ�ł������肢���Ȃ������̕���B 1925.10.23 �w�A�W�A�̓��� Die Leuchte Asiens�x �t�����c�E�I�X�e���ēA�V�i���I�F�j���������E�p���A�B�e�F���B���[�E�L�[���}�C���[�A���[�[�t�E���B���V���O �y����z���ƒ��O���߂���S�[�^�}�E�u�b�_�̓����̕���B�ƁE������f��B 1925.11.16�i���{����1927.5.20�j �w���@���G�e Variete�x �G�[���@���g�E�A���h���E�f���|�� Ewald Andre Dupont�ēA�V�i���I�F���I�E�r�����X�L�[�A�G�[���@���g�E�A���h���E�f���|���B�i�t�F�[���N�X�E�z�����_�[�̏����w�V���e�t�@���E�t���[�̐����x�ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�t���C���g�A���u�F�I�X�J�[�E�t���[�h���q�E���F�����h���t�A����F�E�[�t�@�f��� �y�L���X�g�z�G�~�[���E���j���O�X Emil Jannings�i�u�{�X�v�E�t���[�j�A���A�E�f�E�v�e�B Lya de Putti�i�x���^���}���[�j�A�E�I�[�E�C�b�N�E�E�H�[�h�i�A���e�B�l���j�A�}���[�E�f���V���t�g�i�t���[�̍ȁj�A�Q�I���N�E���[���i���v�j�A�N���g�E�Q�����i�`�p�J���ҁj�A�`���[���Y�E�����J�[���i�o�D�j�A�A���X�E�w�q�A�p�E���E���[�R�b�v���тɃR�h�i�X�E�g���I�u�O�l�u�����R�v�Ɠ����t���X�e�� �y���炷���z�i�d���ȏ����̖��͂ɓM��A�Ԓj���E���T�[�J�X�|�l�̕���B �@�u�{�X�v�t���[�͂����Y�����ɓ����Ă���10�N�ɂȂ�B�ނ̍Ȃ͉��͂悤�Ɠw�͂���B�t���[�͂���܂ŁA�Y�������������H�ڂɂȂ����߂ɑ��鎩���̋C�������A��x����낤�Ƃ��Ȃ������B�������ނ͌Y�������ɂ��̕�������B �@���ċu�����R�Ȍ|�t�������t���[�́A�p�[�g�i�[�̏��[���V�������߂Ɉ��ނ��A���͌����������̎�����Ƃ��āA����Ə��[�q����{���Ă���B�Ƃ��낪������A�n���u���N�̗V�Z��ŁA�ނ͐g���̂Ȃ��G�L�]�`�b�N�Ȕ������A�x���^���}���[�ƒm�荇���B�����čȂ̔����������āA�����̃V���[�ɏo�������邽�߂Ɉ������B�����Ԃ��Ȃ��ނ͔ޏ��̗d�������͂ɁA������������ɂȂ�B�����Ă������菊�т�ꂵ�āA�畆�̂���Ï��[���̂ĂāA�x���^���}���[�ƈꏏ�Ƀx�������ɍs���B �@�����Ŕނ̓u�����R�Ȍ|�t�̃A���e�B�l���Ɍق��A�����������ĎO�l�ŁA���|���b�p�ő�̃��@���C�G�e�B����u���B���^�[�K���e���v�ɁA�V�����ԑg�ŏo������B�g���I�͐�������B�����v���[�{�[�C�̃A���e�B�l�����A�x���^���}���[�̐K��ǂ�������B�ޏ��̂ق����N���Ⴍ�A�n���T���ȃA���e�B�l���̂ق��Ɉ�����A����t�̍Ղ�̎��ɐڕ������킵�Ă���Ƃ�������Ƃ��߂���B���킳�b����ь����A�Ȍ|�̃p�[�g�i�[�B�́A�Q���ꂽ�t���[�����炩���B�t���[������ɋC�Â��A��������x���^�ɂ̂߂荞��ł����̂ŁA�t�サ�ē{��ɉ��Y���B �@�����ċȌ|�̌����̎��ɁA�A���e�B�l����]�������Ă��܂����Ƃ����Փ��ɋ���邪�A���̎��͂���Ƃ��̋C������}����B���̑���ނ̓A���e�B�l����㩂ɂ����A�s�`�̌������������B�ނ̓A���e�B�l���ɉʂ����������������A�h���E���B���ꂩ��ނ͌x�@�ɏo������B�ٔ����͔ނɖ���������鍐����B �@�������ĕ������Ă���10�N�o�����ނ́A���n�߂āA���������ƍs�̔w�i������̂������B������������ނ͉��ߕ������B �y����z���̉f��͂d�E�`�E�f���|���ē̑�\��ł���A�قƂ�ǗB��̐�����ł��邾���łȂ��A�T�[�J�X�|�l���������f��Ƃ��āA�����̗ގ���i��K�ڂɁA�ǐ��������Ȃ����͂������Ă���B�t�F�[���N�X�E�z�����_�[����́w�V���e�t�@���E�t���[�̐����x�́A1912�N�ɂ͂��łɃ��B�S�E�����\���ēE�剉�ɂ���āA�܂�1919�N�ɂ̓��C���n���g�E�u���b�N�ēA�A���g���E�G�g�z�[�t�@�[�A�n�j�[�E���F�C�Z�剉�ɂ���āA����ʂ�̃^�C�g���ʼnf�扻����Ă������A�t�F�[���N�X�E�z�����_�[�Ƃ����A���@���G�e��J�o���b�g�̑嗧���̍�i���A�{���ɓK�C�̉f��ē����o�����̂́A��͂�f���|���ɂ����Ăł������B �@����̓W���[�i���X�g�Ƃ��ďo�������f���|�����A���@�K�{���h�I�Ɉ�N�Ԃӂ��ƃ��@���G�e�̊ē��߁A���̌o�����I�݂ɐ��������V�i���I�����������ł���B���@���G�e�̊ē���������߂ɁA�ނ͂����̂ق��͑呹�������A�x�������֖߂����Ƃ��A��������E�[�t�@�f��Ђ���A�u���@���G�e�f�������Ă݂܂��H�v�ƁA�����������邱�ƂɂȂ����B���̌��ʁA���@���G�e�̏�������̔w��ʼn�������|���A����܂łɂȂ������قǐ��ʂ�������`�ʼnf��������A���f��ł���ɂ�������炸�A��^�����ƂɂȂ����̂������B �@����ɂ́w�Ō�̐l�x�̖��J�����}���A�J�[���E�t���C���g�̂����ꂽ�B�e�Z�p���A�傢�ɍv�������B���ۂɓ����x���������̃��@���G�e�u���B���^�[�K���e���v�ɏo�����Ă����u�R�h�i�X�E�g���I�v�́A�ډB���R��]���Ԃ���B�e�����A�ٔ������f���̃��A���e�B�́A����Ȍ�̂ǂ�ȃ��@���G�e�f����������ł����B�ނ�͎剉���D���j���O�X�̑�����������킯�ł��邪�A��ς����Ƃ����̊i�ŁA���j���O�X�ɏ��������Ă��Ȃ������B�ɂ�������炸�f���̃C�����[�W�����̗͂́A���ɋ��͂������̂ŁA�����ւ��ɂ�邲�܂������A�ϋq�̒��ӂ��������Ƃ͂Ȃ������B����䂦�r�E�N���J�E�A�[�͂��������Ă���B �@�u�f���|���͉��v�҂ł͂Ȃ��������A�ċA�c���̉��p�Ƃł������B�w�Ō�̐l�x�̃J�����}���ł��������[���E�t�����g�̋��͂̂��ƂɁA�f���|���͑�ꎟ�������̕\����`�̎�@���A������`�I�ȃh�[�Y�Ă̋ٔ������ɉ��p�����̂ł������v�B �@�x�������̃��@���G�e����u���B���^�[�K���e��Wintergarten�v�̏�ʂŁA�u�����R�̖��Z����I���ꂽ�B�w���x���g�E�C�G�[�����O���u�ēA�ʐ^�A���Z�̏����v�Ǝ]�����B �y�f��]�z���u�f�Ќ�v�v�ے����\�\�u�c�c�{���O�����Ƀ����i�E�̂��Ƃ������āA�w�Ō�̐l�x��l�̌����f��̒��̑�P���Ƃ��Ēu������A���̍��̏o��ɐ旧���āA�����ȁw���@���G�e�x�������A���������]�͂�������ŏ㋉�̌��t�ɖ����Ă���̂ŁA�V�͂͂▭�Ȕj�ڂɂȂ����킢�Ƌ��鋰��̂����Ă݂���A�K�ɂ��Ă����s�K�ɂ��Ă����A�l�̎����Ă�����̂����ł͂������Ƃ���ɂ��ƁA��͂�w�Ō�̐l�x�̕�����قǂ܂����Ă����̂ŁA�ق��ƈ��S��������ł���B �@�������Ĉق𗧂Ă�킯�ł͂Ȃ����A�w���@���G�e�x�ɂ́w�Ō�̐l�x�قNJ������͂Ȃ��悤�Ɏv���B���̌y�Ƃ��납�����Ɠ������A���̉f�悻�̂��̂����낢�|�������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�������𐔂����Ă�ΐF�X�����邪�A�����͑����̂�����A�l�͈�[���ɉ���Ēu�����Ǝv���B�Ђǂ�������������Εs���ȂƂ��������B�ς炳��Ă��Ȃ��B�Ƃ����_�ŁA�l�́w�L�[���x�Ɠ����l�Ȋ��������B�S�̂ɖ��̏����������̂����₾�����B���`����Ă������j���O�X�̉��Z���A�ڂ��́u���㕞�𒅂��I�Z���v�Ƃ��������B�w�Ō�̐l�x�̃|�[�^�̂悤�ȃ��j�[�N�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B �@���e���w�Ō�̐l�x�قǒ����ł��݂��݂����Ƃ��낪�Ȃ��B�������݂��݂�����肪�����킯�łȂ����A���͖l��̍D�݂Ȃ̂��낤���A�Ƃɂ������́w�Ō�̐l�x�́w�N�V�����邪�̂ɐE��D���Ă��̂��߁c�x�Ƃ����悤�ȋC���ɂ���ׂāA�w���@���G�e�x�́A�����ł͍Ȏq���̂ĂĒu���Ȃ���A���Ă��̎Ⴂ�����ǂ������Ƃ����āA�Ђ�������̂悤�ɖʂ��ӂ��炵�Ăɂ�݂����g�剽�̔��Ȃ��Ȃ��i�I�j�j���E���Ă��܂��Ƃ����C�����́A�l�ɂ͉���������B �@�A�����J�l�͂��̃|�[�^���w�����x�ȂǂƂ������Ƃɂ�����������̂ɓ����ł��ʂ炵���B���������܂�w�����x�Ƃ������Ƃ̊O�ʂ���ɂƂ���Ă���l�ł͂Ȃ��낤���H�@�l�͎v���ɁA����͐l�Ԃ̋��h�Ƃ������̂̏ے��Ƃ�����ׂ����̂ŁA�������������̃|�[�^����������w�����x�ł������̂ŁA���ꂪ�����A�����J�̐a�m�ł���i���ł�������A����͂����ʂȌ`���Ƃ��Ă����ꂽ�����ʂ̂ł͂Ȃ��낤���B�����ċ��炭�����ƒ��x���Ђǂ��̂ł͂���܂����B�Ƃɂ����l�͂��̋����ɂ����Ắw�����x�ɑ��邠�̂�������ɂ́A�[�������ł���B�݂̂Ȃ炸���̃|�[�^�͒P�Ȃ鋕�h����łȂ��A�Ƒ��̂��̂ɑ���ڗ��Ɖ]���l�Ȃ��̂��܂܂ꂽ�������コ�Ȃ̂ł͂���܂����B�ܘ_�����]���コ�̓A�����J�l�ɂ͂Ȃ���������Ȃ��B �@�w�Ō�̐l�x�̎���������B�\�\���̃n�s�E�G���f�B���O���֑��Ɖ]���悤�Ȑ����ȑO�啪�������悤�����A�l�͂����͎v��Ȃ��B�����������S����o���̂ł����Ƃ��A�A�����J�ɂ������悤�Ƃ����̂��낤�Ƃ��A�]���邱�Ƃ͖ܘ_�����A�`����]���Ă�����͐����n�C�J���ȋC���Ŗʔ����Ǝv���B��Ԃ̓����~���̂悤�ɗ��тĐ��҂̔@�����Â��܂�|�[�^�̎p�ōi���Ă��܂��ẮA���܂�Z���e�B�����^���߂���B�����œ������Ă����Ƃ��܂��Ă��������̂ł͂���܂����B�����]���_�ŁA���̂��֒��������������ĕs���a�łȂ��B�Ƃɂ����}�S�̃A�����J�f��̃n�s�E�G���f�B���O�Ƃ͎��̂��������̂ł͂���܂����B�v�i�u�f��]�_�v��R����P���j 1925.12.17 �w�����}�b�`������������ Das Mädchen mit den Schwefelhölzer�x �y����z�E�[�t�@�E�g�[���t�B�����̑����i�A�Z�p�I���ׂ̂��߁A���s�B 1925.12.18�i���{����1929.5.16�j �w�����c�̖� Ein Walzertraum�x ���[�g���B�q�E�x���K�[�ēA�V�i���I�F���[�x���g�E���[�v�}���A�m���x���g�E�t�@���N�i�n���X�E�~�����[�����w�����̕v�N�k�b�N�X�x�ƃt�F���b�N�X�E�f���}���A���I�|���g�E���R�u�\���A�I�X�J�[�E�V���g���E�X�̃I�y���b�^�w�����c�̖��x�ɂ��j�A�B�e�F���F���i�[�E�u�����f�X�A���u�F���h���t�E�o���x���K�[�A���y�F�G���l�E���y�[�i�I�X�J�[�E�V���g���E�X�ɂ��j �y�L���X�g�z�}�f�B�E�N���X�`�����X�i�v�����Z�X�E�A���b�N�X�j�A���B���[�E�t���b�`���i�k�b�N�X�Ə̂���j�R���E�X�E�v���C�����݁j�A���[�R�v�E�e�B�[�g�P�i�G�[�x���n���g��\�O�����j�A�J�[���E�x�b�J�[�U�N�X�i�v�����X�E�y�[�^�[���t�����c�j�A�����E�X�E�t�@���P���V���^�C���i���b�N�z�t�E�t�H���E�z�t���b�N�j�A�}�e�B���f�E�Y�V���i�R�P���b�c��j�A�����f�B�A�E�|�g�`�i�i�V���e�t�B�j�A�N�Z�j�A�E�f�X�j�i�t�����c�B�E�V���^�C���O���[�o�[�j �y���炷���z�u�k�b�N�X�v���ƃv���C�����݂̓��B�[���̐V���Ղ̂Ƃ��ɁA�v�����Z�X�E�A���b�N�X�E�t�H���E�O�����[���g�D������U�f����B�A���b�N�X�͖{���v�����c�E�t�����c���y�[�^�[�ƌ����������邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A����Ȃ��Ƃ͔ނɂ͂Ƃ�ł��Ȃ��b�������B�ނ͐V������̏����y���t�����c�B�E�V���^�C���O���[�o�[�̂Ƃ���ɁA�Ԉ������߂��B����Ȃ��ƂƂ͒m�炸�A�A���b�N�X�͂��̃t�����c�B�����y���t�Ƃ��Čق����B�Ƃ����͔̂ޏ��̓��B�[�����y�̒m���ŁA�v�ɂ����ƋC�ɓ����Ă��炢�����������炾�����B�����t�����c�B�́A�k�b�N�X�����͔ނ̃A���b�N�X���������Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɁA�C�Â����B�����Ĕޏ����v�����X�ƌ�������ȂǂƂ����̂́A�u�����c�̖��v�ɉ߂��Ȃ��ƒm�����B |
|
| 1926 | |
| 1926�i���{����1927.7.21�j �w�����m�̓G���f�� Kreuzer Emden�x 1926 �w�Y��ɗ��͂��܂� Man spielt nicht mit der Liebe�x �Q�I���N�E���B���w�����E�p�v�X�g�ē� 1926.1.25�i���{����1927.11.11�j �w�^���`���t Tartuff�x �t���[�h���q�E���B���w�����E�����i�E�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[�i�����G�[���̓����̊쌀�ɂ��j�A���u�F���[�x���g�E�w�����g�A���@���^�[�E���[���q�A����F�E�[�t�@�f�� �y�L���X�g�z�G�~�[���E���j���O�X�i�^���`���t�j�A���F���i�[�E �N���E�X�i�I���S���j�A�����E�_�[�S���@�[�i�G���~�[���F�ނ̍ȁj�A���[�c�B�G�E�w�[�t���q�i�h���[�k�j�A�w���}���E�s�n�i�g����̒��̂����j�A�A���h���E�}�g�[�j�i���j�A���[�U�E���@���b�e�B�i�Ɛ��w�j �y����z�V�i���I���C�^�[�̃J�[���E�}�C���[�̓����G�[���̃R���f�B�[�ɘg����������B�f��̒��̉f��B �y���炷���z�N������f���́A�ꏟ�Ԃ����Ɛ��w����A�s�\���Ȑ��b�������Ă��炦�Ȃ��B�ޏ����ނ̂��߂ɍ���܂�̂́A�����ނ̎���A�������Y����ɓ���邽�߂ł���B���̖ړI�̒B���邽�߂ɁA�ޏ��͏f���ɉ��̂��Ƃ����������A�܂�܂Ɣނ�p��������B����Ƃɓ��邱�Ƃ��ւ���ꂽ���́A�f�����Ɛ��w�̈�����㩂���~���o�����߂ɁA���̂����ʼnƂɂ��܂����荞�����ƌ��S����B�ނ͌������t�ɕϑ����A�ړ��f��قŃ^���`���t���̕������f����B�I���S���͐M�S�̌����j�ł���^���`���t�ƒm�荇���B�^���`���t�͈�����������A�~���邽�߂ɑS���Y��n�����l�X�Ɉ②����悤�ɁA�I���S���������̂����B�I���S���͐��q����悤�ɂƁA�I���S���������̂����B�I���S���͐��q����^���`���t���A�����̉Ƃ֘A��čs���B�������G���~�[���v�l�����̃h���[�k���A�^���`���t���́u�����v��[�����悤�Ƃ��Ȃ��B�I���S�����n�����l�X�̂��߂Ɉ⌾�����쐬���A�^���`���t�ɂ��̐l�����̂��߂ɁA�Ǘ����Ă��炨���Ƃ�����Y�̖��`�̏������������悤�Ƃ����Ƃ��A�G���~�[���v�l�́A�v�ɂ��̗F�l�̈��ӂ��m���ɂ킩�点����@���l���o���B�^���`���t�Ƃ̃��u�V�[����ޏ��͏������A������I���S���ɃJ�[�e���̉A�ɉB��Ėڌ������悤�Ƃ����̂ł���B �@�^���`���t�̓I���S���������A�����㩂��ƐM����B�I���S���͗F�l�̗�V����������������M�����݁A�����グ�čs���āA�⌾�����ŏI�I�Ɋ������悤�Ƃ���B���̎��h���[�k���ނ���������B�����č��̓G���~�[���Ɠ�l���肾�Ǝv���Ă���^���`���t���A�Ȃɋ߂Â��ĕs�����Ȑ\���o������̂��A�����z���Ɍ���悤�ɃI���S����������B����I���S���͔[�����A�����F�l���Ƃ���ǂ��o���B�f���f�̂̂��A�Ɛ��w�͂��������莩���̈Ӓ���R�炵�Ă��܂��B�ޏ��͑܂̒��ɁA���͓Ŗ�̕r��������B�ޏ��͔N�������l�̈��ݕ��ɁA���̕r���疈�����H�Â���Ă����̂������B��҂͎����̉��������A���̈��҂̐��̂������B�f���͉Ɛ��w���Ƃ���ǂ��o���B �y����z���b�e�E�A�C�X�i�[�ɂ���āA�ޏ��̒����w�����i�E�x�̒��Ɉ��p���ꂽ�A�J�[���E�}�C���[�̃V�i���I�̎w���́A���̂悤�ł���B �S�i�@���̎��Ȑl���^���̐l���͂���炵������ƃh�A�̕���ނ��čs���B �@�@�@���A���̐l���͗����Ă���B �g��@�̌C�����Ă��� �ő���@�̂̋M�l�̂悤�ɁA�����Ƃ����ɗ��B �@�@�@�@�����č��I �g��@�@���̑����C�̕Ј�����ق���o���^�{�苶���āB �@�@�@�@�����č����̐l�͕��� �y�f��]�z�����b�e�E�A�C�X�i�[�w�f���[�j�b�V���ȃX�N���[���x�\�\�u�c�c�����i�E�̂��̉f��ɂ����āA���Q�ɒl����̂́A�ߏւƎ��͂̒��a�ł���B���܃^���`���t�̍�����s�m�̈ߏւ��A�Ȃ߂炩�牓�i����ۗ����Č����Ă���B���邢�͂��̕��i�̑O�ɁA�����ۂ����[�X�ɂ���Č`��^����ꂽ�T�e���̕����A�݂�����B�����Ƃ��납�牺�����Ă��āA���������Ղ����Ă���J�[�e���̃r���[�h�̋P���̑O�ŁA�x�b�h�J�o�[�̋���H�������o�Č����A�������̏_�炩�������ʓI�Ɍ����Ă���B�����Ă����������C�̂��ׂĂ��A�Ȃ���w�͂����肷��̂́A�^���`���t�������郄�j���O�X�̓c�ɏL�����������A�ˑR�����j��A���[�X�̂����x�b�h�̏�ŁA�s��@�ɂ̂т�����Ƃ��ł���c�c�v�B ���u�f��Z�p�Ɖf��Y�Ɓv1926�N��4���\�\�u�c�c�ނ̓t�����X�쌀�̃n���h�����O���A�G�s�\�[�h�I�ȂƂ���͂��ׂĖ������A�{���I�ȗv�f�͉ߓx�ɋ������āA�f��I�ɂ����Č���I�Ȍ��ʂ����悤�ɉ������Ă��܂��Ă���B�ނ͑S�̂��ސ�����������A���̂��߂ɑS�̂�����I�ɂނ��������Ȃ�A�����I�Ȕނ̃��Y���ɁA�����e����^���Ă��܂����悤���c�c�����������ł����������ƂɊS�������̂́A��̎��ɂ��ׂ��ł���B�Ƃ����͍̂ŏI�I���ʂ̓_�ł͕s�m���Ȃ��̏����̎d���́A�O�����Ĉӎ������A�����I���i�������Ă����炵������ł���B�ނ́[�[���f��ɂ����Ă͂��߂Ĕ��ɖ��ĂɁ[�[��̌X�����A���邢�͍�҂ɂ���ẮA�͂�����q�ׂ�ꂽ���P���A���W�J���ɋ������ׂ��������B���������Ĕނ́A�f��|�p��i�̎�ϓI�ȉ\�������A�͂�����Ƌ������ׂ��������B����̓J�[���E�}�C���[�̑n�삩��A����ɂ͂�����ǂݎ���A�������ɑ��d�ɉ������̈Ӑ}�ł���c�c�v�B ���u�L�l�}�g�O���t�v1926�N��989���\�\�u�c�c���{�I��肵���c����Ă��Ȃ��B���̍�i�́A����J�[���E�}�C���[�̉f��ł��邩�̂悤�ɁA�t�����X�̎��l�̗��O�ɏ]���Ď��R�ɁA�f�����̂��̂Ƃ��Č���̂��悢�B���肵�Č����A����͑�����f��ł͂Ȃ��A���s�̓I��i�ł��Ȃ��A���Ɖf��ł��Ȃ��A�����炭�S���Ɠ��Ȍ`��^����ꂽ�|�p��i�ł���B�قƂ�ǐg����ȍ����ƌ����������炢�ł���B����ΌÓT�I�h���}������l���ɖ|�����̂ł���A�\���A���䑕�u�A���߂��A�܂���������I�Ȃ̂ł���c�c�v�B 1926.2.15 �w�}�m���E���X�R�[ Manon Lescaut�x �A���g�D�[���E���r�\���ēA�V�i���I�F�A���g�D�[���E���r�\���i�A�x�E�v�����H�[�̏����ɂ��j�A�B�e�F�e�I�h�[���E�V���p�[���N�[���A���u�F�p�E���E���[�j�A���y�F�G���l�E���y�[ �y�L���X�g�z���A�E�f�E�v�e�B�i�}�m���E���X�R�[�j�A�E���f�B�[�~���E�_�C�_�m�t�i�f�E�O�����[�j�A�G�h�D�A���g�E���[�g�n�E�U�[�i�f�E�O�����[�����j�A�t�[�x���g�E�t�H���E�}�C���[�����N�i�u���j�A�t���[�_�E���q�����g�ƃG�~�[���G�E�N���c�i�}�m���̏f�ꂽ���j�A�����_�E�|�e�`�i�i�V���U���k�j�A�e�I�h�[���E���[�X�i�e�B�x���W���j�A�W�[�N�t���[�g�E�A���m�[�i���X�R�[�j�A�g���[�f�E�w�X�^�[�x���N�i�N���[���j�A�}���[�l�E�f�B�[�g���q�i�~�V�����[�k�j �y���炷���z�C���@�ɓ�����邱�ƂɂȂ��Ă����c�ɂ̏������A���̔������̂��߂ɁA���Ő����l�ƎႢ�M���f�E�O�����[�𖣘f���A�p���ɘA��čs�����B�����������ŘV��݂̈��l�ɂȂ邱�Ƃ����������B����ƃf�E�O�����[�̂Ƃ���֖߂�A�ނƑ傫�ȍK����̌�����B��������̊ԁA�����Ԃ�ė��Y�ƂȂ�B�Ō�Ɏ��R�āA���l�̎�ɕ�����Ď��ʁB �y����z�t���[�h���q�E�c�F���j�[�N��1921�N�ɁA�Ȃ̃����A�E�}�����q���C���ɋN�p���ĎB�����ŏ��̉f�扻�́A�S�߂Ȏ��s�ɏI������B���̓�x�ڂ̉f�扻�̓h���}�I�ɂ͋��������A�������q���C���̃}�m���̉ƔR���錃������M�͌����Ă����B 1926.3.10 �w�t���[�����X�̃��@�C�I�����e�� Der Geiger von Florenz�x �p�E���E�c�B���i�[�ēA�V�i���I�F�p�E���E�c�B���i�[�A�B�e�F�A�h���t�E�V�����[�Y�B�A�A�[���p�[�h�E���B���[�O �y�L���X�g�z�R�����[�g�E�t�@�C�g�A�m���E�O���[�S�A�A�G���[�U�x�g�E�x���N�i�[�A���@���^�[�E���� �y����z�{�[�C�b�V���Ȗ�����Ƃɗ�������B 1926.3.22 �w�V�F�����x���N�Z�� Die Brüder Schellenberg�x �J�[���E�O���[�l�ēA�V�i���I�F���B���[�E�n�[�X�A�J�[���E�O���[�l�i�x�����n���g�E�P���[�}���̏����ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�n�b�Z���}���A���u�F�J�[���E�Q�I���Q�A�N���g�E�J�[���A����F�E�[�t�@�f��� �y�L���X�g�z�R�����[�g�E�t�@�C�g�i���F���c�G���E�V�F�����x���N�ƃ~�q���G���E�V�F�����x���N�Z��̓���j�A�����E�_�[�S���@�[�i�G�X�^�[�E���E�t�A�C�[���j�A�w�����[�E�h�E�t���[�X�i�V���E�t�A�C�[���j�A���A�[�l�E�n�C�g�i�C�F�j�[�E�t�����A���j�A���F���i�[�E�t���b�e���[�i�Q�I���N�E���@�C�f���o�b�n�j�A�u���[�m�E�J�X�g�i�[�i�J�`���X�L�[�j�A�����E�X�E�t�@���P���V���^�C���i�G�X�^�[�̑��̐��q�ҁj�A���B���w�����E�x���h�E�i�G�X�^�[�̑��̐��q�ҁj�A�G�[���q�E�J�C�U�[�i�G�X�^�[�̑�O�̐��q�ҁj�A�p�E���E�����K���i�ʼn��j�A���[���E�t�����g�i�����݂��j�A�t���[�_�E���q�����g�i�뗎�������S�l�j �y���炷���z�i���R�o�������l�̏������߂���A��l�̌Z��̃h���}�j�B �@�V���E�t�A�C�[���͔���H��̏��L�҂ł���B�V�F�����x���N�Z��͔ނ̂Ƃ���Ɍق��Ă���A���F���c�G���̂ق��͔鏑�Ƃ��āA�~�q���G���̂ق��͎�C�Z�t�Ƃ��ē����Ă���B������A������200�l�̘J���҂����ʁB���������E�t�A�C�[���͈⑰�╉���҂ɁA���̓���������Ȃ��B����������V�F�����x���N�Z��͎��E���肢�o��B���E�t�A�C�[�����瑽���̂��Ƃ��w�ю���Ă������F���c�G���́A�������@������Ă݂�B�����Ă����܂��̂����ɔނ͑����̍��Y�����グ��B����ɑ��ă~�q���G���̂ق��́A���������l�������悤�A�����ǂ�Ȕj��̓�����J�����Ȃ��悤�ɂ��悤�ƁA�����ɐ����B�����Đl�Ԃ̔ߎS��a�炰�邽�߂ɁA�ނ͎��Ǝ҂����̂��߂̒c�n�����B �@���F���c�G���͂��鋣���̂Ƃ��ɁA�������C�F�j�[�E�t�����A���ƒm�荇���B�ޏ��͔����̎��d�������J���ҁA�Q�I���N�E���@�C�f���o�b�n�̍���҂������B���F���c�G���͔ޏ��������̈��l�ɂ��A���D�ɂ��Č㉇����B�����������ɔޏ��ɉ}���Ă��܂��B�ނ͂��Ă̌ق���̖��G�X�^�[�ɐS�������A�ޏ��̃G�L�]�`�b�N�Ȕ������ɖ��������B�����G�X�^�[�̂ق��͎R�t�̃J�`���X�L�[�������Ă����B�G�X�^�[�͂����������̈��l�̎�`�U���ɂ���č�������Ɋׂ�B����ƃ��F���c�G���́A�ޏ��������ƌ������邱�Ƃ������Ƃ��āA������\���o��B�G�X�^�[�͓��ӂ���B�C�F�j�[�͐�]���āA�������э~���B�~�q���G���͏d�a�̏����������̉ƂɈ�������ĊŌ삷��B���F���c�G���̌����͕s�K�Ȍ��ʂƂȂ�B�G�X�^�[�͂��ꂩ��������ƁA�����̓J�`���X�L�[�̈��l�̂܂܂��낤�ƁA��炳���B���������s�ƂȂ��Č������{��ɋ��ꂽ���F���c�G���́A�Ȃ��i�ߎE���Ă��܂��B���ꂩ�狶�C�Ɋׂ��āA�Ȃ̎��̂̑��ɂ��������B�Q�I���N�ƃC�F�j�[�͍Ăь݂��ɔF�ߍ����B�~�q���G���̒c�n�ŁA��l�͍K���Ȗ����Ɍ������Đi�ށB �y�f��]�z�u�f�A�E�t�B�����v��1926�N��13���\�\�u�c�c�`�ʂ̓R�����[�g�E�t�@�C�g�̈��|�I�Ȉ�ۂ̉e�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B�ނ͂��̓�l�̌Z������S�ɉ��������Ă���A�ԓx�A�g�Ԃ�A���^���A�ڂ��܂ŁA�S�R�ʂɂȂ��Ă���B�ނ́u���z�Ɓv�Ɓu���K�S�ҁv�̃C���[�W���A�����I�ɁA���������I�ɑn�o���āA���������߂ċ���ɕ\�����Ă���B���̐��ʂ́A�R�����[�g�E�t�@�C�g������܂łɉ��������̒��ł��A�����炭�����Ƃ����n�������̂ł���B�ނ������̐l���̎p�ʼn�ʂɌ����V�[���́A�Z�p�I�ɋ����[���A�f�l���т����肳�����c�c�v�B 1926.3.24�i���{����1928.4.6�j �w�S�̕s�v�c Geheimnisse einer Seele�x �Q�I���N�E���B���w�����E�p�v�X�g�iPabst�j�ē� �y�L���X�g�z���F���i�[�E�N���E�X�剉 �y����z�S�I�����̉f���̓J�����}���̃O�C�h�E�[�[�o�[�ɂƂ��Ă������������B 1926.4.1 �w�l�ԂĂ����� Menschen untereinander�x �Q���n���g�E�����v���q�g�ēA�V�i���I�F���C�[�[�E�n�C���{�������P���r�b�c�A�G�h�D�����g�E���[�g�n�E�U�[�A�Q���n���g�E�����v���q�g�A�B�e�F�J�[���E�n�b�Z���}���A���u�F�I�b�g�[�E�����f���n�E�A�[ �y�L���X�g�z�A���t���[�g�E�A�[�x���A�A�E�h�E�G�Q�f�E�j�b�Z���A�p�E���E�r���g�A�G���U�E���@�[�O�i�[�A�P�[�e�E�n�[�N �y����z�x�������̈��A�p�[�g�ł̂��܂��܂ȉ^���B 1926.4.15 �w�v�����Z�X�E�g�D�������x �t���[�h���q�E�V�F�[���t�F���_�[�ē� �y�L���X�g�z�����A���E�n�[���F�C�A�n���[�E�n���� �y����z�x�������̉f��فu�A���n���u���v�ŕ���B 1926.4.29�i���{����1959.2.21�j ���V�A�f��w��̓|�`�����L�� Panzerkreuzer Potemkin�x �y����z�G�C�[���V���e�C���́w��̓|�`�����L���x���x�������̃A�|������ŊC�O�����J�B�ߌ�ɂ̓v���C�Z���A�x�������x�����Ă��f������āA��f�����F�B�������ړI�ӎ��I�Ȓ����̌�A�f��͂V��12���ɋ֎~�B7�������삵���łōĊJ�B�w�|�`�����L���x���_�̓��@�C�}�����a���̕��������I���S�����������B�v�����^���A�Q�W�f��ƃ����^�[�W�����_�Q�Ɓi�w�x�������E�xp328�j�B1927�N�̃c�F���j�[�N�ḗw�D�H�x�ɂ��e����^�����B 1926.5.2 �w�A�N���h���q�̖`�� Die Abenteuer des Prinzen Achmed�x ���b�e�E���C�j�K�[�ēA���́F���@���^�[�E���b�g�}���A�x���g���g�E�o���g�V���A�A���N�T���_�[�E�J���_���B �y����z�A���W���̃����v�A�J���t�̖��A���@�̓��̏��x�z�ғ��̕���ō\�������A�ŏ��̒��҉e�G�ŋ��g���b�N�f��B 1926.9.6 �w���o�̎q������ Die Unehelichen--Eine Kindertragödie�x �Q���n���g�E�����v���q�g�ēA�V�i���I�F���C�[�[�E�n�C���{�������P���r�b�c�A�Q���n���g�E�����v���q�g�i�u�������E�s�Җh�~�A���v�̌����f�ނɊ�Â��j�A�B�e�F�J�[���E�n�b�Z���}���A���u�F�I�b�g�[�E�����f���n�E�A�[ �y�L���X�g�z�����t�E���[�g���B�q�i�y�[�^�[�j�A�A���t���[�g�E�O���b�T�[�i�p�E���j�A�x�����n���g�E�Q�c�P�i���[�����c�j�A�}���S�b�g�E�~�b�V���i���b�e�j�A�t�F�[�E���@�N�X���[�g�i�t���[�_�j�A�}���K���[�e�E�N�b�p�[�i�c�B�[���P�v�l�j�A�G�h�D�����g�E���[�g�n�E�U�[�A�P�[�e�E�n�[�N�A�p�E���E�r���g�A�G���[�E���@�[�O�i�[ �y���炷���z����Ȑe�̋��ŋꂵ�߂��Ă���n���Ȋ��̎q���������߂���h���}�B �@�y�[�^�[�A�p�E���A���b�e�A�t���[�_�͂�������������ŁA��������Ɉ�ĂĂ��炦�Ȃ��s�K�Ȏq�������ł���B���̒��̈�l�p�E���́A���łɈ��̓D���ɗ�������ł��āA�e�\�ȕ��Ǝ����ȕ�Ƃ̈�`��w����������H���Ă���B���̎O�l�͈�����̗{���e�́A�����߂Ȏ�ɋ}�����Ă��Ȃ���A���킵���l���𑗂��Ă���B �@�{��̃c�B�[���P�v�l�͎O�l�̗{���q���A���\�Ȏ������Ƃ������Ă����B13�̃y�[�^�[�͊X�։҂��ɍs���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�U�̂̂��ア���̎q���b�e���A���炵�Ȃ����c�B�[���P�̂��߂ɁA�ΒY�^�т܂ł��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���炵�����j���A���̐l�X�͊y����������߂����Ă���Ƃ����̂ɁB�S�̃t���[�_�͐ΒY���̑O�ł������������ĉ߂����Ă���B�O�l�̎q�������̗B��̊�т́A�t���[�_�̐e�F�A�u���b�L�[�v�Ƃ������̃E�T�M�ł���B���������ς�����c�B�[���P�́A�E�T�M�������Ă��锠���A�����璆��֓������Ƃ����B�{��ɉ��Y�ꂽ�y�[�^�[�̓c�B�[���P�ɒ��т����邪�A���ʂقǂԂ��̂߂����B�ߗׂ̐l�X�������ē����āA�u������x�����q���������Ȃ�������A�x�@�ɑi�����v�Ƌ����B�����ăy�[�^�[�͒x��Ȃ��悤�ɑ�����������Ȃ���w�Z�֍s���B�����ނ̓��b�e�ƈꏏ�ɁA�S�~�̂ď�ɃE�T�M�̕���@��B11���̕X�J����l�����Ԃʂ�ɂ���B�����Ă��̖郍�b�e���M���o���B�u��҂��Ă�ł��Ȃ��Ắv�ƌ����Ă��A�c�B�[���P�́u�����ɂ͗ǂ��Ȃ��v�ƁA��荇��Ȃ��B���������������A���j���ɂȂ��Ă���ƌĂꂽ��҂́A�u���̂����Ƒ����ĂȂ������̂��A������x�ꂩ������Ȃ��v�ƌ����B���ǃ��b�e�͈�҂̎�̒��Ŏ��ʁB���̊Ԃɂ���ƌx�@�́A�c�B�[���P�̎q���s�҂ɖڂ�������B�u�܂��Ԃɍ��������ɑ��̎q�����������̂Ƃ���֍s����悤�ɂ��Ă��Ȃ��Ắv�B�c�B�[���P�͗{�猠�����グ���āA�@��ɏ��������B�t���[�_�͎����ی�A���̐��b�ŁA�e�Ȑ��ԉ��̏��[�Ɉ�������āA�c�ɂ֍s���B�a�@�ɑ���ꂽ�y�[�^�[���A���̌�A�������̕w�l�Ɉ��������B�����āu���܂�Ă͂��߂āA�a�������j���Ă��炤�v���ƂɂȂ�B �@�������ăy�[�^�[�̉^�����D�]�����悤�Ɍ������B�����ނ͓ˑR�̍K�����M����ꂸ�A�v���͂����A�݂̂̂��ڂ炵���Z���ƃ��b�e�̕�Ɍ������B������A�ނ̌��O�������ƂȂ�B��D�̑D���������ނ̕��e���A��`���������悤�Ɣނ�{�q�ɂ����̂������B�u�@���ɂ��A���e�͎������ɑ���v�����͂Ȃ��v�ƍR�c�����ƁA�ނ́u���͂��̎q��{�q�ɂ����̂��v�ƌ����āA�q���̖@�I�㗝�l�ł���Ƃ����ٔ����̏ؖ����������B�x�������s�S�̊ȍقŌ��肪����B�u���͂������O���������Ȃ��B���C�łˁA�y�[�^�[�v�ƁA�������̕w�l�͕ʂ��������B�V�����z�[���ŁA�y�[�^�[�͕��e�̎d������`�킳���B�u�����o���Ȃ���v�ƌ����Ă��A�u���������A��������v�Ɠ{����B��������ӁA�D���̃e�[�u���̏�ɉΎ��̕r������̂������y�[�^�[�́A���������ς���Ă����c�B�[���P�̎p���v���o���A�s���ɋ���āA�͂������瓦���o���B������20�L���ȏ�������āA���̐e�ȕw�l�̉ƂɒH�蒅���B �@���e�͗��������y�[�^�[�̓��S���x�@�ɓ͂���B�@���͍Ăуy�[�^�[�Ɉ����n���悤������B�u�������͏]��˂Ȃ�Ȃ��B���͂��O�������ŕ��e�̂Ƃ���֘A��߂��Ɩ��܂����v�B�����āu���O�͂����ɂ���̂��v�ƕ��e�Ɍ���ꂽ�y�[�^�[�́A�D�̏��~���̊K�i���삯�̂ڂ��āA���̒��ɔ�э��ށB�������������Ă�����D�̎Ⴂ�A�����A�ނ������グ��B�y�[�^�[�̋~���́H �y����z��{�I�ɂ͂��̉f��ł��A�����v���q�g�ē̎p���́A�w��܊K���x�̏ꍇ�Ɠ����ł���B���������u�c�B���f��v�ƌ����Ă��A�ނ͂��������ɐi�B�܂肱���ł͔ނ́A�O��I�Ɏq���̗���ɗ����Ă���B�h�C�c�Ŏ������̎q������������̉f�悪���ꂽ�̂́A���ꂪ�͂��߂Ă������B���́u�q���̔ߌ��v�i�w���w�̔ߌ��x�ƒʒꂵ�Ă���j�ł́A��l�͊��S�ɘe���ł���B �@�w��܊K���x�̏ꍇ�Ɠ������A���̉f��̃��A���e�B��ۏ��Ă���̂́A�f�l�o�D�Ɗ��f���Ƃ̗͂ł���B�y�[�^�[���̃����t�E���[�g���B�q���������̎q�������́A�S���̑f�l�ł���B�������͒��������Ƃł͂Ȃ��B�v�̓����v���q�g���A�q���̐S�̋�Y���A�I�݂ɉ��������邱�Ƃɐ����������Ƃł���B���̉f��̉��l�͂����ɂ���B �@�u�������E�s�Җh�~�A���̌��I�f�ނɊ�Â��v�X�N���v�g���������̂́A�w��܊K���x�̃X�N���v�g�����������C�[�[�E�n�C���{�������P���r�b�c�ł���B�x�����������̎�������`�ɂ����f��ƌ����A�G�[���q�E�P�X�g�i�[�́w�G�~�[���ƒT�ソ���x���f�扻�����w���N�T��c�x���L���ł��邪�A�����x�������̎q���������Ȃ���A���̑ɂɂ���u�q���̔ߌ��v��`���o�������̉f��́A�����ƒm���Ă悢��i�ł���B 1926.10.1 �w���̏\���R�i���}���ꂴ��q�������jKreuzzug des Weibes�x �}���e�B���E�x���K�[�ēA�V�i���I�F�h�[�W�I�E�R�t���[�A�}���e�B���E�x���K�[�A�B�e�F�]�[�t�X�E���@���Q�[�G�A�`�EO�E���@�C�c�F���x���N �y�L���X�g�z�R�����[�g�E�t�@�C�g�A�}���[�E�f���V���t�g�A���F���i�[�E�N���E�X�A�n���[�E���[�g�P �y����z�@�̔D�P������֎~����Y�@��218���ɔ�����X���f��B 1926.10.14�i���{����1928.3.1�j �w�t�@�E�X�g Faust�x �t���[�h���q�E���B���w�����E�����i�E�ēA�V�i���I�F�n���X�E�L���[�U�[�B�i�i�A�v�A�Q�[�e�A�N���X�g�t�@�[�E�}�[���[�A���тɌÂ��t�@�E�X�g�`���ɂ�������[�g���B�q�E�x���K�[�̃V�i���I�w����ꂽ�p���_�C�X�x���g�p�j�B�B�e�F�J�[���E�z�t�}���A���p�F���[�x���g�E�w�����g�A���@���^�[�E���[���q�A����F�E�[�t�@�f��� �y�L���X�g�z�Q�X�^�E�G���N�}�� Gosta Erkmann�i�t�@�E�X�g�j�A�G�~�[���E���j���O�X Janinngs�i���t�B�X�g�j�A�J�~���E�z���� Camilla Horn�i�O���[�`�q�F���j�A�t���[�_�E���q�����g�i�O���[�`�q�F���̕�j�A���B���w�����E�f�B�[�e���� Wilhelm Dieterle�i���@�����e�B���j�A�C���F�b�g�E�W���x�[�� Yvette Guilbert�i�}���e�E�V�����F���g���C���j�A���F���i�[�E�t���b�e���[�i��V�g�j�A�G�[���N�E�o�[�N���i�p���}���j�A�n�i�E�����t�i�p���}���܁j�A���^�[���E�~���[�e���i�C���m�j�� �y���炷���z���t�B�X�g�͐��E�̎x�z������ɓ���悤�Ɠw�߂�B��V�g�K�u���G���Ƃ̑����ŁA�ނ͂ǂ�Ȑl�Ԃɂ����݊O�����Ĕj�ł֓������Ƃ��ł���ƁA�咣����B�K�u���G���͔ނƓq�����A���t�B�X�g�͐l�ԒB���A�_�ւƓ��������痣�����邱�Ƃɂ͐������Ȃ��Ƃ������ɓq����B�t�@�E�X�g�ɂ���ă��t�B�X�g�͂��̗͂��������ƂɂȂ�B�܂����t�B�X�g�͂��鍑���y�X�g�ŋꂵ�߂�B�V�w�҂̃t�@�E�X�g�́A�ނɈꐶ�������������߂ĒQ���l�X��O�ɁA�ׂ����ׂ��Ȃ������Ă���B�����_���ނ������Ă���Ȃ��Ȃ�A����������ƈ����������Ă���邩������Ȃ��ƁA�t�@�E�X�g�͌����̒��̏\���H�̂Ƃ���ŁA�������Ăяo���B�������l�X�͔ނ̔w��̒n��������Ă���̂ŁA�����̖��������Ă��Ă��A �t�@�E�X�g�̓y�X�g��������Ƃ͂ł��Ȃ��B��]�����ނ͂����œŎ��ɓ����������߂�B����ƃ��t�B���g���ނɉi���̎Ⴓ�̎p���o���ėU�f���A���̏�ނɂ��̐��̂��ׂĂ̕��^���邱�Ƃ����B��������������ł���B�t�@�E�X�g�͓��ӂ���B �@�����Ĕނ̓��t�B�X�g�̃}���g�ɏ���āA������ăp���}�֔�ԁB�����ł͂��傤�nj��������s���Ă���B���t�B�X�g�͌��݂��E���A�����t�@�E�X�g�͔��������܂����炤�B���������̓��͏I���B�t�@�E�X�g�͏���\���Ɋ��\���邽�߂ɁA�����̉�����ɖ]�݁A���t�B�X�g�ɍ���n���B�����͍���ނ�������ւƂ��������A�ނɌ����̕�����\������B�������t�@�E�X�g�͌̋����������B�ނ̖]�݂����t�B�X�g�͂��ׂĖ������˂Ȃ�Ȃ��B�̋��̒��ɖ߂����t�@�E�X�g�́A����̓����̑O�ŃO���[�`�q�F���ɏo��A�ޏ��̐������ɐS��ł����B���̎����傤�ǔޏ��̌Z�̃��@�����e�B�����A�������I����ċA���Ă��Ă���B���t�B�X�g�̓O���[�`�q�F���̔��̒��ɁA���@�ŋ��̍������Ă����B�����ޏ��͂�����̃}���e�E�V�����F���g���C���̂Ƃ���Ɏ����čs���Ă��܂��B�t�@�E�X�g�́A�q���B�ƗV��ł���O���[�`�q�F���̒��Ԃɓ���A�������t�B�X�g�̓V�����F���g���C���v�l�Ɍ�������āA�U�f�̂Ă����������B�t�@�E�X�g�̓O���[�`�q�F���Ɉ�����������B�����Ė�A�ނ͔ޏ��̕����ɔE�э��ށB���t�B�X�g�͈��݉��Ń��@�����e�B�������A�ނ��E���B��e�̓O���[�`�q�F���̕����Ɍ��m��ʒj�����錻��������āA�ߒQ�̂��܂莀��ł��܂��B�t�@�E�X�g�ƃ��t�B�X�g�͓�����B �@�O���[�`�q�F���͂��炵�҂ɂ���A�ǂ��o�����B�ޏ��͊����~��̉��Ŏq�����Y�ނ��A�l�X�͖�˂�߂āA�ޏ��ɉ��̏������^���Ȃ��B�ޏ��͎q�����̐������܂�̒��ɐQ������B�b���B����e�Ǝ��q����������B�O���[�`�q�F���͍ٔ��Ɋ|�����A���Ԃ�̌Y��\���n�����B���������߂�ޏ��̐��̓t�@�E�X�g�ɓ͂��A���t�B�X�g�͔ނɂ�����x��d���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����t�@�E�X�g�͔߂��݈ȊO�����̂����ݏo���Ȃ��i���̎Ⴓ���B�����Ń��t�B�X�g�͔ނɔN������p��Ԃ��B �@�������Ĉ�l�̘V�l�ɕԂ����t�@�E�X�g�́A�O���[�`�q�F���Ɏ͂�������߂ɁA���߂��Ȃ���ޏ��̌Y��ɕ����Ă����B���̏u�ԁA�ޏ��͍��̎����̗��l�̎p��F������B���t�B�X�g�̂ق��͂���ŁA���������E�̎x�z������ɓ��ꂽ�ƐM����B�t�@�E�X�g�ɐl�ς̓��݊O�����邱�Ƃɐ�����������ł���B�������V�g�K�u���G���͔ނɑ��āA�V���ւ̓�������B�Ȃ��Ȃ獡��^�ɐ������̂ƂȂ����t�@�E�X�g�ƃO���[�`�q�F���̈���A�����̖ژ_�������ׂĔj�Ă��܂�������ł���B �y����z�Q�[�e�́w�t�@�E�X�g�x�ł͂Ȃ��A���ԓ`���ɂ���i�ŁA�g���b�N�Z�p����g�����B�O���[�`�q�F�����̃J�~���E�z�����̐V�N�Ȗ��͂��������B�j�T�v���~�A�̏��ҋq�̒��ɂ̓��B���w�����E�}���N�X�A�V���g���[�[�}���O���A���C�q�X�o���N���كV���n�g�A�}�b�N�X�E���C���n���g�A�G�[���b�q�E�N���C�o�[�A���I�|���g�E�C�G�X�i�[�������B�i�w�x�������E�xp366�j �y�f��]�z�u�f��T�ԁv1926�N��44���\�\�u�h�C�c�̕���́A�I�蔲���̊ϋq��O�ɂ��āA�u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�I�[�v�ŊJ�Â��ꂽ�\�\�����̔��芅�т�����ꂽ�\�\�A�����J�ɗ��s�������������ґS���ɑ����āA�J�~���E�z���������ӂ̈ӂ�\�����c�c�B�܂����ɃJ�~���E�z�����͊ϋq�����]�����Ȃ������\�\�A�������ɂ͂��Ƃ₩�ȐU�镑���������A�܂��������C�ŁA�萶���n�߂�����̓���Ƌ��ۂƂ�\�������ޏ��O���[�g�q�F���́A���܂��܂Ȏ���������قǍI�݂Ƀ}�X�^�[�����A���炵���o���f���ł���A�\�\�ޏ��͂��Ƃɂ��ƑS�A���T���u���̒��ŁA���̉f��̒��Ő����Ŗ��ĂȐl�Ԑ����ɂȂ����A�B��̑��݂�������������Ȃ��B�{���̐S���̌����A���̎p�̒��ɖ��ł��Ă���B�����Ŕޏ��̓t�@�E�X�g�`���ɁA���{�I�ɂ͂���قǏd�v�łȂ��v�f��t�����Ă��邾���ł��邪�A�����̑��݈�ʂ̏h���I�Ȃ��̂𒆐S�ɐ����Ă��镶�w��i�����A�����Ɉ�w�Ǝ��̊�����^���Ă��ꂽ�B�����������ׂĂ��J�~���E�z�����́A�����ς�ȏW���͂ŒS�����B�ޏ��͂��̉f��̒��ŁA�܂��ɐl�Ԃł���B�\�\���t�B�X�g���̃��j���O�X�A�قƂ�ǖ��l�|�ɋ߂��ӂ�����������ނ̎���̂킴�A���ׂĂ��\���ɍl�����A�Ӑ}����A�d�グ���Ă���B�ނ͕��䂩�痈���o�D�ł͂��邪�A�ނ̃��t�B�X�g�͂��͂▯�O�{�ɍ������Ă͂��Ȃ��B�܂����������ׂ����\�t�ŁA�ŋ��̍ŏ��ƍŌ�ł����A���l�D���̖��甲���o�āA������������A�܂������ڗ�ȓz�ɂȂ�B�\�\�t�@�E�X�g�D�X���m���̃O�X�^�E�G�N�}���B�V�l�Ƃ��ĂƂ��Ă͐��ʂ��Ȃ����A�Ⴂ���m�Ƃ��Ă͍D�܂������͓I������A�\�\�z��ɂȂ��������ɑ��ẮA��l�̒n�ʂ��������������郆���J�[�̂悤�ȋC���B���̂��ׂĂ̔o�D���������h�ŁA���炵���A�����ł���B�ē����i�E�͉�������邪���ɂ����A�X�^�b�t��M�S�ɒ������A�₦�ԂȂ��ŋ���@�����B�f���̓s�J�s�J����悤���Y��ŁA�����̓_�ŋZ�p�I�ɔ��Q�ł���B�Ⴆ�A�h�C�c����A���v�X���z���ăp���}�s���A���t�B�X�g�ƃt�@�E�X�g�̔�s�́A�I�݂ɂȂ����f���\�\�ォ��̃p�[�X�y�N�e�B���͂��炵���B��s�̍����̕ω��A�C�^���A�̕��n�ւ̉��~�������ł���B�����ăp���}�̊قł́u��ȋq�����v�̏o���́A�܂��������قł���B���̉f��́A���������������̃����w���ɐڂ��Ă���Ƃ���ɁA�����Ƃ��������ӏ��Ƃ����Ƃ����d���ׂ�����������B�����Ă��������ӏ��́A����Ȃ�����𑗂邾���̉��l������B�ًc�A���邢�͋^�O���������_�́A�e�[�}�̉����_�I�Ȉ������ł͐������Ă�����̂́A���̍�i�̒����R�I�Ȃ��̂��A�_���I���ϗ��I�Ɍ`���A���p���s�������Ƃ���h���}�g�D���M�[�ł���iIckes)�v�B 1926.10.28 �w�\�}���N�����̖`���@Die Abenteuer eines Zehnmarkscheins�x �x���g���g�E�t�B�[�A�e���ēA�V�i���I�F�x�[���E�o���[�W���A�B�e�F�w���}�[���E�����X�L�[�A���[�x���g�E�o�[�x���X�P �y�L���X�g�z�A�O�l�X�E�~�����[�A�I�X�J�[�E�z�����J�A���@���^�[�E�t�����N�A���F���i�[�E�t���b�e���[ �y����z�u�\�}���N���������X�ɕʂ̐l�Ԃɓn���Ă����A�C�܂���ȗ����L�^������������̃G�s�\�[�h�ō\������Ă���B���̎����̈ē��ŁA�f���͔N���̖��H�̒������˂�����A�����Ȃ���Ή��̊W���Ȃ��l�����������グ�A�H��A��̎���A�����A�C���t�������҂̉��y�T�����A�E�ƏЉ�A�����̑��A�a�@�Ƃ������ꏊ����˂���B�o���[�������g�̌��t�ɂ��A�͂��������u���܂��܂ȉ^���̐ڍ��_���A���I�Ɍ��т��Ȃ���A�l���Ƃ����D���̒��������Ă�������ǂ��Ă���v���̂悤�ł���v�i�r�E�N���J�E�A�[�j�B�x�������E�N�[�A�t�����X�e���_���̉f��فu�E�[�t�@����v�ŕ��� 1926.11.2 �w���p�̐l�Ԃ��� Uberflüssige Menschen�x �A���N�T���_�[�E���Y���j�[�ēA�V�i���I�F�A���N�T���_�[�E���Y���j�[�i�A���g���E�`�F�z�t�̏����ɂ��j�A�B�e�F�I�b�g�[�E�J���g�D���b�N�A�J�[���E�A�b�e���x���K�[�A���u�F�A���h���C�E�A���h���C�G�t �y�L���X�g�z�I�C�Q���E�N���b�p�[�A�J�~���E�t�H���E�z���C�A�n�C�����q�E�Q�I���Q�A�A���x���g�E�V���^�C�������b�N �y����z���V�A�̏��s�s�ł̂��܂��܂ȉ^���B�h�C�c�E�\�A�Ԃ̍ŏ��̋��������i�B 1926.11.10 �w��߂ȃY�U���l Die keusche Susanne�x �y�L���X�g�z�����A���E�n�[���F�C�A���B���[�E�t���b�`�� �y����z�x�������̉f��فu�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŕ����A�听���B 1926.12.17�i���{����1928.9.28�j �w���R Der heilige Berg�x �A���m���g�E�t�@���N Arnold Fank�ēA�V�i���I�F�A���m���g�E�t�@���N�A�B�e�F�[�b�v�E�A���K�[���[ Sepp Allgeier�A�n���X�E�V���l�[�x���K�[ Hans Schneeberger�A�A���m���g�E�t�@���N�A�w���}�[���E�����X�L�A�A���x���g�E�x�[�j�b�c�A���u�F���I�|���g�E�u�����_�[ Leopold Blonder�A�J�[���E�x�[�� karl Bohm�A���y�F�G�g�����g�E�}�C�[�� Edmund Meisel �y�L���X�g�z���j�E���[�t�F���V���^�[�� Leni Riefenstahl�i�f�B�I�e�B�[�}�j�A�G�����X�g�E�y�[�^�[�[�� Ernst Petersen�i�t�����c�E���B�[�S�j�A���C�X�E�g�����J�[ Luis Trenker�i���[�x���g�F�A���s�j�X�g�j�A�t���[�_�E���q�����g Frida Richard�A�t���[�h���q�E�V���i�C�_�[ Friedrich Schneider�A�n���l�X�E�V���i�C�_�[ Hannes Schneider �y���炷���z�i��l�̎R�j����l�̏��𑈂������h���}�j�B �@�A���s�j�X�g�̃��[�x���g�Ɗw���̃t�����c�͗F�l�ł���B��l�͂�����ꏏ�ɁA����Ńf�B�I�e�B�[�}�̃_���X�����Ė�������B�t�����c�͋��̉Ԃ�ޏ��ɗ^���A����ɃX�J�[�t�����炤�B�ޏ��̓��[�x���g��K�ˁA�R�ւ̓�������A�ނ͔ޏ��������������Ă���Ǝv���B���[�x���g�̓X�L�[�̃R���e�X�g�ɂ��Q�������A�댯�ȓ~�̓o�R��ڎw���B�����Ă����ăt�����c��U���B��̒��œ�l�͗����������A�t�����c�͘[�֖߂낤�ƌ����B�u�Ȃ��v�Ƃ����₢�ɔނ́u�f�B�I�e�B�[�}���l��҂��Ă��邾�낤�v����Ɠ�����B������ă��[�x���g�́A�F�l�����C���@�����������Ƃ�m���ċt�サ�A�Փ��I�ɋl�ߊ��B���Ƃ����肵�����B�[�S�͓]������B���[�x���g�͕K���ɂȂ��ē�l���q���ł���U�C����ێ���������B���E�ł̓f�B�I�e�B�[�}������ŗx���Ă���Ƃ���ցA��e�����āA���[�x���g�������[�H�܂łɋA��Ƃ����������c�����܂܁A�܂����R���Ă��Ȃ��ƍ�����B�{�������o������B���[�x���g�͈�Ӓ��U�C����ێ����Ă��邪�A�������{���������ꂽ���A���o�ł����낤�ƂȂ�A�f�B�I�e�B�[�}�̎p�����đ̂����B�����ē]�����郔�B�[�S���щz���āA�ނ��[���ɗ�����B�[�ɋA�����{�����̈�l���f�B�I�e�B�[�}��K�˂āA��l�̎���������B�ޏ��͋A�����A�v���o�ɐ�����B �y����z�R�x��ʂ̉f���ƁA���o��ʂ̕X�̋{�a�����蕨�B |
|
| 1927 | |
| 1927 �w�j�������x���N�̃}�C�X�^�[ Der Meister von Nurnberg�x ���[�g���B�q�E�x���K�[�ē� 1927�i���{����1928.8.7�j �w�O�̈� Manege�x �y����z�N���J�E�A�[p144 1927 �w�����������R Der frohliche Weinberg�x �y����z�N���J�E�A�[p144 1927�i���{����1928.6.15�j �w���X�^�[ Laster der Menscheit�x �y�L���X�g�z�A�X�^�E�j�[���[�� 1927�i���{����1929.2.28�j �w���[�x Liebe�x 1927 �w���܃��C�[�[ Konigin Luise�x �i��ꕔ�wDie Jugend der Konigin Luise�x�A��w:Konigin Luise�x�H�j �J�[���E�O���[�l�ē� 1927�i���{����1928.9.6�j �w�T�����C�Y Sunrise�iSonennaufgang�j�x �q�E�e�F�v�E�����i�E�ēA�V�i���I�F�J�[���E�}�C���[�i�w���}���E�Y�[�f���}���̏����w�e�B���W�b�g�ւ̗��x�ɂ��j�A�B�e�F�`���[���Y�E���[�W���[�A�J�[���E�V���g���X �y�L���X�g�z�W���[�W�E�I�u���C�A���W���l�b�g�E�Q�C�i�[�A�}�[�K���b�g�E�����B���O�X�g���A�{�[�W���E���[�W���u �y����z�����i�E�̃n���E�b�h��i�B 1927.1.10�i���{����1929.4.3�j �w���g���|���X Metropolis�x �t���b�c�E.�����O�ēA�V�i���I�A�t���b�c�E�����O�A�e�A�E�t�H���E�n���u�A�B�e�F�J�[���E�t���C���g�A�M�����^�[�E���b�^�E�A�i����B�e�j�I�C�Q���E�V���t�^���A���u�F�I�b�g�[�E�t���e�A�G�[���q�E�P�b�e���t�[�g�A�J�[���E�t�H���u���q�g�A�ߑ��F�G���l�E���B���R���A���y�F�S�b�g�t���[�g�E�t�b�y���c�A����F�E�[�t�@�f��� �y�L���X�g�z�u���M�b�e�E�w���� Brigitte Helm�i�}���A�^�l���l�ԁj�A�O�X�^�t�E�t���[���q Gustav Frohlich�i�t���[�_�[�E�t���[�_�[�[���j�A�A���t���[�g�E�A�[�x���i���[�E�t���[�_�[�[���j�A���h���t�E�N���C�������b�Q Rudolf Klein-Rogge�i���[�g���@���O�j�A�t���b�c�E���X�v�i�₹���j�j�A�e�I�h�[���E���[�X�i���U�t�@�[�g�^���[�[�t�j�A�G�����B���E�r�X���@���K�[�i�i���o�[11811�j�A�n�C�����q�E�Q�I���Q�i�O���[�g�j�A�I�[���t�E�V���g�����i�����j�A�n���X�E���I�E���C�q�i�}���k�X�j�A�n�C�����q�E�S�[�g�i�i����j�A�}���K���[�e�E�����i�[�i�����Ԃ̏����j�A�}�b�N�X�E�f�B�[�c�F�A�Q�I���N�E���[���A���@���^�[�E�L���[���A�A���g�D�[���E���C���n���g�A�G�����B���E�v�t�[�^�[�i�J���҂����j�A�O���[�e�E�x���K�[�A�I���E�x�[�n�C���A�G�����E�t���C�A���U�E�O���C�A���[�[�E���q�e���V���^�C���A�w���[�l�E���@�C�Q���i���q�J���҂����j �y���炷���z�i��̒��ɏZ�ޏ�w�K���Ɖ��̒n�����E�œz��̂悤�Ɏg�������J���҂̋@�B��������̑�s�s�C���[�W��w�i�ɁA�����ɐ�������ċ@�B��j�A�n���̒��𐅐Z���ɂ���J���҂ƁA���q�̖����낤���Ȃ��ĉ��S�����̒��̃{�X�A�u��v�Ɓu���v���a�����ďI���h���}�j�B �@���g���|���X�͖����̓s�s�ł���B����͒n��ƒn���̓�̓s�s���琬��B�J���҂̒��͒n���̒��ł���B�����ɂ͋���ȋ@�B���������A�J���҂������S���̎��l�̂悤�ɓ�������Ă���B�X�ɂ��̉��ɔނ�̏Z��������B�n��ɂ̓��g���|���X�̎x�z�҂₻�̎q���B�̊y��������B���[�E�t���[�_�[�[�����A���̑S�\�̎x�z�҂ł���B�y���ɂ́u���q�B�̃N���u�v������A������y���݂ɖ����Ă���B�����ł̑��l�҂̓t���[�_�[�[���̑��q�t���[�_�[�ł���B �@������ނ́A�n���̐��E���炽������̎q���B��A��āA�n��̐��E�ɂ���ė����}���A�ɏo��B�ޏ��͎q���B�ɒn��̐��E���ґ�Ȑ����������āA�u�����Ȃ����A��������B�̌Z���v�Ƌ��ԁB�t���[�_�[�̓}���A�����āA�[���S��ł����B�����Ĕޏ��ɂ��Ēn���̐��E�ɍs���B�����Ŕނ͂͂��߂ă��g���|���X�̈Í��ʂ�����B�J���҂���ƒ��Ɏ��̂ŁA���̂悤�ɎS�߂ɓ|��Ă������̂ł���B�ނɂ̓��g���|���X���A�������]���̐l�Ԃ�ۂݍ��ރ����N�_�̂悤�Ɍ������B�ނ͕��̏��ɋA��A���̎��̂̂��Ƃ����B�������́u�����������͔̂������Ȃ��̂��v�Ɨ�R�ƌ��������A�u���̎��̑��q�ɋ@�B���ɓ��邱�Ƃ������v�ƁA�������������B�����āu�n���ɂ����͎̂��B�̒������݂�����ł����B�ނ炪�����M���Ɏ�����������A�ǂ������ł����v�Ƃ������q�̌x���ɂ́A�������������B �@�����֒����Ǘ����̐E���O���[�g������ė��āA�s�R�Ȏ��Ђ��������ƌ����āA�������n���B����ɂ��ăt���[�_�[�[���́A�鏑���牽�̕��Ă��Ȃ��������Ƃ�{�����B�����Ĕ鏑���N�r�ɂ���B�t���[�_�[�͎��E���悤�Ƃ���鏑���~���A���̉Ƃ�����B�t���[�_�[�[���͊Ď��l�Ɍ����������B����t���[�_�[�͘J���ҊX�ɍs���A�ނ�������悤�Ƃ���B����t���[�_�[�[���͒��̐^�ɂ���V�˓I�Ȕ����ƃ��[�g���@���O�̂Ƃ���ɍs���A�s�R�͎��Ђ̈Ӗ����𖾂��Ă���Ɨ��ށB���[�g���@���O�͂��ꂪ�A���g���|���X�̒n���̒n����n�̈ē��}���Ɛ�������B���ꂩ��ނ͘J���҂̑�������郍�{�b�g�J���̎����̐i��������B�X�ɔނ́A�u�n���̂������ŁA�ǂ�Ȃ��Ƃ��J���҂���������ȂɈ������Ă���̂��v�Ƃ��Ԃ���t���[�_�[�[�����ē����āA�n����n�����ʂ���ꏊ�ɁA�ނ�A��Ă����B �@�����ł͘J���҂����̔閧�̏W��J����Ă����B���ɂ̓t���[�_�[�������B�W�܂����J���҂����ɁA�}���A���V�����m�M��^���邽�߂ɁA�o�x���̓��̘b������B���̌��݂��g�Ƃ��āA�ޏ��́u�v�悷�鐸�_�ƍ���̊ԂɁA����҂����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B����͐S�ł��v�ƌ����B�J���҂������u�����̒���҂͂ǂ��ɂ���̂��v�Ɛq�˂�ƁA�}���A�́u���҂��Ȃ����A���̐l�͂����Ɨ��܂��v�Ɠ�����B �@�W��I�������ɁA�t���[�_�[�̓}���A�̂Ƃ���ɍs���A�ޏ��Ɉ�����������B�ޏ����ނɈ��������A��l�͗��������ʼn������B����t���[�_�[�[���̓��[�g���@���O�ɁA�u�N�̃��{�b�g�ɂ��̖��̎p����点��v�ƌ����A�����J���҂����̂Ƃ���֑��荞��ŁA�������Ă��Ƙb���B���[�g���@���O�̓}���A��������āA�����̉ƂɊċւ���B �@�����}���A�����������̏ꏊ�ɗ��Ȃ������̂ŁA�t���[�_�[�͔ޏ���T�����B�Ƃ��Ƃ����[�g���@���O�̉Ƃ���A�u�����āv�Ƃ���������������B�t���[�_�[�̓}���A���~���ɍs�����A�t�Ƀ��[�g���@���O�ɒ͂܂����Ă��܂��B���[�g���@���O�͂��ꂩ��}���A�����f���ɂ������{�b�g�����グ��B�J���҂�����\�͓I�ɒ@���̂߂����������߂Ă����t���[�_�[�[���́A�}���A�ɐ����ʂ��̃��{�b�g��J���҂����̂Ƃ���֑��荞��ŁA�������B���{�b�g�̃}���A�͘J���҂����Ɂu���B�̒���҂͌����ė��Ȃ��ł��傤�B�ƌ����A���g���|���X�̎x�z�҂ɍR���āA���ׂĂ�j��悤�ɒ�������B�t���[�_�[�͘J���҂����ɁA����̓��{�b�g���ƌ����Đ������悤�Ƃ��邪�A���ׂ��ׂɃ��{�b�g�̃}���A�ɒ�������āA�J���҂����̃����`��h�����ē����B �@�J���҂����͋@�B���n�߂�B�E���̃O���[�g�́A�ނɔC����Ă��钆���@�B��j��~�����Ƃ��邪�A���ʂł���B�J���҂����͒����@�B������ƁA���������̎q���B���c���Ă���n���̒����A�^���ɏP���邱�Ƃ�m��Ȃ��B�n���̒��ɍ^��������B���[�g���@���O�̂Ƃ��납�����Ɠ����o�����{���̃}���A�ƃt���[�_�[���A�����Ƃ����Ƃ���Ő������āA�q���B��M������~���B�J���҂����͐^����m��ƁA�{���ă��{�b�g�̃}���A�����Ԃ�ɂ���B�R���鉊�̒��ŁA�s�C���Ȏp�ƂȂ������{�b�g�����āA�J���ҒB�́u�������I�v�Ƌ��ԁB �@�����̃��{�b�g���j�ꂽ���ƂɌ��{�������[�g���@���O�́A�{���̃}���A���ő�����B�t���[�_�[���}���A�������悤�Ƃ��Č��ǂ��ƁA���[�g���@���O�͔ޏ����̓��̏�Ɉ�������グ��B�����ē��̏�̖ڂ�����ނ悤�ȍ����ŁA���͂������苶���Ă��܂������[�g���@���O�ƃt���[�_�[���A��R�ł���������B�t���[�_�[�����������ɂȂ�ƁA�����ȕ��̃t���[�_�[�[�������ɉ��܂��āA�Ђ��܂����āu���q�������Ă���v�ƋF��B���Ƀt���[�_�[�������A���[�g���@���O�͓]��������B �@���X�g�̓t���[�_�[�[�����t���[�_�[�ƃ}���A�̊Ԃɗ����Ă���Ƃ���ցA�E����擪�ɂ����J���҂������߂Â��B�t���[�_�[�ɂ��Ȃ�����āA���͐E���̃O���[�g�ƈ��肷��B�}���A�͍��̓������j������B�u�S�����т���Ƃ������A�l�X�̊Ԃɕ��a�Ɨ����������炳���v�B �y����z�f��Z�p�I�ɂ͌��삾�������A�u�E�[�t�@�v�Ђ́A�J�b�g���A�Z�k���A�荏�B�ɂ������炸���ۓI�����͓���ꂸ�A5300���}���N�̐������͈�������Ȃ������B �@�����Ă��̉f��͕����ē�������A�Z�p�I�Ȃ��炵���ɑ����^�ƁA���m�Ȃقǒʑ��I�ȁu���̒���ҁv�C�f�I���M�[�ɑ��鈫�]�Ƃ����A�A���r���@�����g�ȕ]�����Ă����B�������������猩��A�����̎�����̂��̂��A���r���@�����g�������B������1920�N�㌰�݉�������O�����I���A�l�X�̈ӎ��ɂ̓A�����J�j�Y���Ɗ�����ꂽ�A�����J�Ƃ���A�w���g���|���X�x�͂܂��������������ӎ��̉f�������̂��̂������B�t���b�c�E�����O�̓A�����J�֍s�����̂������B���̗��ŔނɏՌ��I�Ȉ�ۂ�^�����̂́A�j���[���[�N���`�̍ۂ̈�ۂ������B�ˑR�C�����畂���яオ���ė��門�V�O�A����Ƃ��������L���L���ƌ����Ă��鋐��Ȍ����B������f��ɂ��Ȃ��ẮA�ƃ����O�͍l�����B���������ɂƂ��Ă��A���R�̓���I���i�ƂȂ�������s�s�Ɂu���g���|���X�v�I���A���j��͂��߂Ă��̎p���������̂��A�����J�������B�u�A�����J�j�Y���v�Ƃ͂������������ɑ��ė^����ꂽ���̂ł���B�t���b�c�E�����O�͂��̌��z�I�ȑ�s�s���f�������邱�Ƃɂ���āA����̎Љ�I�E�����I�j�S�����������̂������B�\�ʏ������ɓ���A�V�����Y�Ǝ��{��`�̔ɉh�i���Ă��鎞��̒��ŁA����Y�Ƃ̒��ۓI�������Ƒ�O�Љ�Ƃ̊Ԃ��a瀂��A���I�Ɍ`�ۉ�����f�悪���ꂽ�̂́A�܂��ƂɃ^�C�~���O�̂悢�o�����������B �@���̉f��ɂ��ăW�[�N�t���[�g�E�N���J�E�A�[�́A���������B�u�����ŏd�v�Ȃ̂͋ł͂Ȃ��A���i�W���钆�Ɏ������\�ʓI�ȕt�������̕����A���|�I�Ȍ��ʂ����邱�Ƃł���B�c�c��{�X�̃I�t�B�X�A�o�x���̓����݂̌��z�A�@�B��Q�W�̔z�u�A�����������̂��ׂĂ��A�傰���ɏ��藧�Ă�t���b�c�E�����O�̍D�݂������Ă���B�c�����ς瑕���ɑ���S���烉���O�́A���̒��̍^����悤�Ɛ�]�I�Ȏ��݂����Ă���Q�W���A�����I�Ȍ^�ɍ\������قNjɒ[�ɑ���B�f��Z�@�I�ɂ͔�ނ�₵�������ł��邱�̍^���̃V�[�����A�l�ԓI���n����͋���ׂ����s�ł���c�c�v�B���ہu�����O�̂悤�Ȍ|�p�Ƃ́A�{���ɐl�ԓI�ȏ�̗��I�ƁA���̑����I�p�^�[���Ƃ̊Ԃ̑Η������������Ƃ͂łł��Ȃ������B����ɂ�������炸�ނ́A���������p�^�[�����Ō�̍Ō�܂ŕۂ�������B���Ȃ킿�A�J���҂����͌����ɑΏ̓I�Ȃ����ь`�̍s�������Đi�݁A�厛�@�̐��ʊK�i�̏�ɗ����Ă�����ƉƂ̕���ڎw���Ă���v�B �@���ׂĂ����ݐs���������I�@�\�̎��{���I�Ӗ��̕\���Ƃ��āA�w���g���|���X�x�͏ے��I�ȈӖ��������Ă����B�����ăN���J�E�A�[�����łȂ��A���ɂ���������������҂������B���\�A����ɐ�����Ǝ��̖ڐ��Ō��Ă����C���A�E�G�����u���N�ł���B�ނ́w���ꂪ�f�悾�\�\���̍H��x�̒��ŁA��������Ă���B �@�u�V���́w���g���|���X�x�ɃE�[�t�@���Z�S���n���𒍂������Ƃ��X�I�ɕ����B�Ȃ���A���g���́w�x���E�n�[�x�̂��߂ɂ�����R�{�̓����������B���A�A�����J�Ƃ͈Ⴄ�B���[���b�p�l�ɂ́w���g���|���X�x�͘Q����Ӗ������B������f�悾�B���z�I�����̑�s�s�B����͋N�d�@�B�n���̐��E�B����̔o�D�B���[�g�s�A���B�����B�c�c�V���A�r���A�|�X�^�[����Ăɂ��̉f����^����B��̓s�s�B��w�s�s�Ɖ��w�s�s�B�E�[�t�@����}���Ȃ����B�c�c��������Ăя��N�͑̌�����ł��낤�B�������u���M�b�e�̓��ƘZ�S���n���̃Z�b�g�ɏ���ꂽ������������Ƃ��āB�\�\���؊قł̋��s���ςނ�ۂ�S����Ăɏ�f�����ł��낤�B�ޓ��͂ق�̐���������N����������ł���B�ޓ��͋��Ȑ�Ƃ̉����ɁA�����X�����̂������Ȃ������̂��B�ޓ��͋͂������̃p����L���H�����Ƃ�B��̊�]�Ƃ������炢���Ȃ������̂��B �@���̉f�������A�d��Ȃ��Ƃ͏}���҂̏����̓��ƁA���̏����̑I����҂̔������Ƃɂ��邱�Ƃ��ޓ��̂����S����邾�낤�B�����āA�ޓ��́A��w�s�s�̏Z���������L�ׂ�����A��낱�т��ȂĈ���Ԃ��ł��낤�B����͑f���炵���f�悾�B����͋ɂ߂ċ���I���B�E�[�t�@�͂��̂��߂ɂ͂�������K��̋]����ɂ��܂Ȃ������v�i����A�����ЁA�Q�R�O�y�[�W�ȉ��j�B �@�����s�s�̌i�ς���肵���w���g���|���X�x�́A�������Ă��f���͐V�N�ł���B���ꂾ���Ƀt���b�c�E�����O�������j���[���[�N�̖��V�O�́A���R���̃G���p�C���X�e�[�g�E�r���̂悤�Ȓ����w���낤�Ƃ����A���ӎ��I�Ȏv�����݂�����B���o�ł���B�ނ��A�����J�֍s�������́A���w���z�M�͂܂��Ő����ł͂Ȃ������B�j���[���[�N�ł̐Ⓒ����1928�N�������B�G���p�C���X�e�[�g�E�r���̊����́A�����ƒx���1931�N�������B���������āw���g���|���X�x�̖��V�O�́A�܂����������O�̑z���͂̎Y���Ȃ̂ł���B 1927.2.25 �w���̏f�ꂳ��\�\���̏f�ꂳ��x �J�[���E�t���[���q�ē� �y�L���X�g�z�փj�[�E�|���e�� �y����z�x�������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŕ���B�{���̃R���f�B�[�̊y���݁B 1927.4.14 �w�X�̔ߌ� Dirnentragödie�x �u���[�m�E���[���ēA�V�i���I�F���[�g�E�Q�b�c�A���I�E�w���[�i���B���w�����E�u���E���̓����̃h���}�ɂ��j�A���u�F�J�[���E���[�g���B�q�E�L�����[ �y�L���X�g�z�A�X�^�E�j�[���[���i�A�E�O�X�e�F���w�j�A�q���f�E�C�F�j���O�X�i�N�����b�T�F�Ⴂ���w�j�A�I�X�J�[�E�z�����J�A���F���i�[�E�s�b�`���E�i�t�F���b�N�X�F�w���j�A�w�[�g���B�q�E�p�E�������B���^�[�V���^�C���A�I�b�g�[�E�b�N���[���u���K�[�� �y���炷���z�i�V���s�����t�w�̔ߌ���`�����Љ�h�f��j�B �@�A�E�O�X�e�͂������Ȃ�̍́A��ꂽ���w�ł���B�N�����b�T�̕��͂܂��Ⴍ�A���炵���B�w���̃t�F���b�N�X�͐��ӋC����̐�˂ł���B�u���W���A�����̑ދ����ɉ}�����ނ́A���e�ɔ��R���Ă���B�������u�܂������Ă�ˁA�t�F���b�N�X�v�Ǝ�����ƁA�ނ́u�l�͎��R���~�����v�Ƌ���ŁA�Ƃ��яo���B�u�ɂȂ�A�����Ƃ܂��߂��ė���v�Ǝv�������e�̎v�f�͂͂���āA����o���Ă��A�t�F���b�N�X����͉��̉��������Ȃ��B�̂܂ܐ����Ē����ӂ������Ă���t�F���b�N�X�́A���܂������̓꒣�������Ă����A�E�O�X�e�ɂԂ���B�u�l�͗��e�ƌ��܂����B��x�Ɩ߂�Ȃ��v�ƌ����t�F���b�N�X���A�A�E�O�X�e�͎����̕����ɘA��čs���B�����āu�D���Ȃ��������ɋ��Ȃ����v�ƌ����B���ӂ����t�F���b�N�X�́A�A�E�O�X�e�ɂւ���ė���Ȃ��B�����ăA�E�O�X�e�͋����ɂ��A�ނ͎����������Ă���ƐM�����݁A����܂ł̃q����ǂ��o���Ă��܂��B�����Ĕޏ��͔ނɂӂ��킵���l�ԂɂȂ邽�߂ɁA�������͂����āA���َq���̓X����낤�Ƃ���B�������āA�c��͈�N�ȓ��ɂƌ����Ă���ԂɁA�q���m�A���g���̓t�F���b�N�X�ɁA�N�����b�T���Љ��B�ނ͎Ⴂ�N�����b�T�ɐS���ڂ��B�u�l�͗��e�̂Ƃ���֖߂�B���̎��ɂ͌N����������A��o���Ă��v�ƁA�S�ς�肵���ނ͌����B�u�����Ă��̓A�E�O�X�e�̂��̂���Ȃ��v�ƌ����Ă��A�����ނ͘V�������w�Ȃǂɂ͋������Ȃ��B�A�E�O�X�e�͔ނɁu���̂Ƃ���ɗ��܂��āv�ƍ��肷�邪�A�t�F���b�N�X�͗₽���u�l�ɂ͂��̋C�͂Ȃ��B�l�͂����s���Ȃ�����v�Ɠ�����B �@��]�����A�E�O�X�e�̓N�����b�T�ɁA�u���ɔނ�Ԃ��āv�Ɨ��ށB�������N�����b�T�́u�ނ������C�ɓ���������ƈӂ��āA���ɂ͂ǂ����悤���Ȃ��ł��傤�B���͎Ⴂ��ł��v�ƁA��荇���Ă���Ȃ��B�A�E�O�X�e�͐[���S����������B�������ޏ�����Ԕ߂��܂����̂́A�����̎S�߂����́A�ނ���t�F���b�N�X���N�����b�T�ƈꏏ�ɕ�点�A�ނ̖������ʖڂɂȂ邾�낤�Ƃ������ʂ��������B��]�����A�E�O�X�e�̓A���g���������̂����āA�N�����b�T���E������B �@�t�F���b�N�X�͗��e�̂Ƃ���֖߂�A�����̓����e�̕G�ɖ��߂Č����B�u���ꂳ��A�l�̂����Ől�E�����N���Ă��܂����v�B�����ĉ����ɕ���B�V���͂�����B�u���w�̔ߌ��B44�̏��w�A�E�O�X�e�E�O���[�l���g�́A�E�l�����̂��ǂőߕ߂���悤�Ƃ������A���疽�������v�B�u���z�ȃA�E�O�X�e�v�ƁA�����g�̏�̎҂����͔߂��݁A�u�����ɂ��鎄�����݂͂�ȁA����������ȍŊ��𐋂���v�̂��ƒQ���B�������A�E�O�X�e���Z��ł����݂��ڂ炵���A�p�[�g�̃h�A�̏�ɂ́A�������u�ݕ����v�Ƃ����f�����o�Ă����B���ɁB �y����z��ꎟ���E���O��ɑS�������}�����f���}�[�N�o�g�̑受�D�A�X�^�E�j�[���[���́A������߂��Ă���́A��������V�����̔�ނ̂Ȃ��g�U�艉�Z�ŁA�V�������n���J���Ă����B1923�N�́w�]���x�ł́A�Y�����ɓ����Ă�����l��15�N�ԑ҂������Ă���ԂɁA��������V���ė����Ԃꂽ���D���A�o��������l���̑O�ő҂��Ă����̂ɁA�ނ��������������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂����āA�����̘V�������A�����Ɛg���������Z�ŁA���т��͂������B �@���́w�X�̔ߌ��x�ł́A�Љ�̂����ł��鏩�w�̋]���I�Ȉ���̔ߌ����A�▭�̉��Z�ň�ۂÂ��Ă���B���_�I�ɖ��n�Ȏ�҂ƌ��g�I�ȘV���w�Ƃ����A�h�C�c�Łu�֕P�v�̓����́A���ꂪ�u�X�H�v��Ƃ��Ă���_�ɂ���B19���I�̎�s�p���̒֕P�́A�܂��T�����I���͋C�̃q���C���������Ƃ���A20���I�̒֕P�̃T�����͊X���ł������蓾�Ȃ������B20���I�́u���g���|���X�v�́A�����̑�O�̊X������ł���B�u�X�H�f��v�\�\����͒��Y�K���̐l�Ԃ��A�s��`�̑�O�̌Q����s��̊X�H�Ƃ����U�f�Ɉ�����āA�����̒P���ȓ��퐶���̋����������E���o���Ƃ����^�̉f��ɑ��āA�W�[�N�t���[�g�E�N���J�E�A�[���^�������̂ł���B����̓J�[���E�O���[�l�ē�1923�N�ɐ��삵���w�X�H�i�M��薼�w���f�̊X�x�j��A���[�v�[�E�s�b�N�ēw����̔ߌ��x�Ɏn�܂�A1925�N�́w��тȂ��X�x�A�����Ă��́w�X�̔ߌ��x�Ȃǂ��o�āA1930�N���܂ő����A�h�C�c�f����L�̃W�������ł���B���ׂƂ��ēs��̃W�����O������A�u���W���A�Љ�r������������ێ����Ă���ꏊ�܂ŁA�u�X�H�v�������̐����ɂ��Ɠ��̑��e�������A�������琶�N����Ӗ��̕ω��́A�܂��Ɂu����v���̂��̂�����Ă����B �@������ɂ��Ă����������̑�s�s��O�Љ���A�u�X�H�v�ɂ���ĉf���������@���A���̎����ɂ͗��s�̎�@�ƂȂ��Ă����B�|�[���E���[�T�́w�X�̔ߌ��x�ɂ��āA�����q�ׂĂ���B�u�O���O����������̂��X�H�Ɉ����߂��ꂽ�B�y�[�������g�̏���}�����B�q���������B�X�H�̈Â����Ɗp�B�������Ă���X���̖�����v�B��s�s��O�Љ�ɂ����ẮA�X�H����������ł���B����䂦���[���ē̉f��́u���̖ڂ̍����ŎB�e���ꂽ�o�����ɂ���Ďn�܂�B���Ȃ킿�A�j�̑������̑���ǂ��B�����ɉ����āA���ꂩ��K�i�����A����ɕ����̒��֓����čs���v�B�l�Ԃ́u�X�H��������v�ɊҌ�����Ă��܂��B �y�A�X�^�E�j�[���[�������z1883�N�A�f���}�[�N�̃R�y���n�[�Q���ɐ��܂�A�͂��߂͕���Ŗ��𐬂������A1911�N�A�ŏ��̕v�ŏI���̃}�l�[�W���[���������o�Ƃ̃E�A�o���E�K�[�d�ƈꏏ�ɁA�w�f�R�x��������B�����w�M�����x�i1911�j�Ȃǂɂ���āA�k���f��E�ŏ��̐��E�I�f��X�^�[�ƂȂ����B�ޏ��͖��͂Ɉ�����A���̖������m�M�����p�E���E�_�[�t�B�g�]�����A�ޏ���@�O�ȏ����Ńh�C�c�֏������B�ޏ��̕\��L���ȍ�����Ɛg�Ԃ艉�Z�̂��܂��́A��ꎟ���E��풆�A�t�����X���ɂ��h�C�c���ɂ��A�ُ�Ȑl�C���Ă̂ŁA���m�����͚͍���ޏ��̎ʐ^�ŏ��藧�Ă��قǂ������B������1920�N�㖖�Ɏ���܂ŁA�ޏ��̓h�C�c�ł����Ƃ��l�C�̍������D�̈�l�������B�u�h�C�c�̉f�搢�E�́A�T�C�����g����ɃA�X�^�E�j�[���[�����n�������l�������Ȃ���Aꡂ��ɕn�������̂������ł��낤�v�B�����Ƃ��L���Ȃ̂́A�w���ݗߏ�x�i1922�j�A�wINRI�x�i1924�j�A�w�w�b�_�E�K�[�u�����x�i1925�j�̂悤�ȁA�ߌ��I�ȏ������̉��Z�ł���B�w��тȂ��X�x�i1925�j�ł́A�w�X�̔ߌ��x�Ɠ������A���t�w���������B�f�悪�g�[�L�[�ɂȂ��Ă���́A�ޏ��̉f�搶�����I�������������A1932�N�A�B��̃g�[�L�[�f��w�H�̏����x��������B�i�`�����������ƁA�ޏ��̓h�C�c�������āA�f���}�[�N�ɋA�����B 1927.5.14 �w�D�H Die Weber�x �t���[�h���q�E�c�F ���j�[�N�ē�,�V�i���I�F�t�@�j�[�E�J�[���[���A���B���[�E�n�[�X�i�Q���n���g�E�n�E�v�g�}���̓����̎��R��`�Љ�ɂ��j�A�B�e�F�t���f���b�N�E�t�[�Q���U���O�A�t���[�h���q�E���@�C���}���A���u�F�A���h�����E�A���h���C�G�t�i�W���[�W�E�O���X�̋��́m���ʂ̃X�P�b�`�Ǝ����^�C�g���̕����n�̋��Ɂj�A���y�F���B���[�E�V���~�b�g���Q���g�i�[ �y�L���X�g�z�p�E���E���F�[�Q�i�[�i�h���C�V�K�[�F�H���j�A���B���w�����E�f�B�[�e�����i���[���b�c�E�C�F�[�K�[�j�A�_�O�j�E�[�����F�X�i���C�[�[�E�q���[�j�A�e�I�h�[���E���[�X�i�p�����j�A���@���X�J�E�V���g�b�N�i�h���C�V�K�[�v�l�j�A�w���}���E�s�n�i�o�E�����g�j�A�w���^�E�t�H���E���@���^�[�i�G���}�E�o�E�����g�j�A�J�~���E�t�H���E�z���C�i�x���^�E�o�E�����g�j�A�A���g�E�[���E�N���E�X�l�b�N�i�V�q���[�j�A�n���X�E�n�C�����q�E�t�H���E�g���@���h�t�X�L�[�i�S�b�g���[�v�E�q���[�j�A�Q�I���N�E���[���i�A���]���Q�j�A�Q�I���N�E�u���N�n���g�i�L�b�e���n�E�X�F�q�t�j�A�����E�X�E�u�����g�A�G�~�[���E�����g�A�n���X�E�V���e�����x���N�A�G�~�[���E�r�����A���B���[�E�N���X�`���X�L�[�A�Q�I���N�E�K���c �y���炷���z�i19���I�V�����[�W�G���ł̐E�H�X�g���C�L���������h���}�j�B �@�H���h���C�V�K�[�̉Ƃ̑O�ɂ́A�d�グ���D���������n�����߂ɁA��������̐D�H�������������čs�Ă���B�����H���Ɍق��Ă���E���̃p�C�t�@�[�͐����ŁA���������ẮA�J���҂����̘J�������܂������Ƃ����B�ނ͖��x�����l���̕i���������ƌ����āA�J���̔�������x�������Ƃ��Ȃ������B�������E�H�����͋̂��܂���Ղ����Ă��āA�������ɂȂ��Ă���A�^�����ƕs���Ȏd�ł����ÎĂ����B������l�Ⴂ�E�H����R���A�ނ̓p�C�t�@�[�ƏՓ˂����B�����Ńp�C�t�@�[�͍H���̃h���C�V�K�[��A��Ă����B�h���C�V�K�[�͂��̎Ⴂ�E�H���N�r�ɂ��A�|���C�Â����l�X�ɁA�����ɏ��ĂȂ��̂ŁA�J�����ɉ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ����B�V�����H��͂����Ƒ����A�����ƈ������Y���Ă���Ƃ����̂ł���B�E�H�����͌��V�������A�������C�������Ă��܂����B �@�����փ��[���b�c�E�C�F�[�K�[���A�x�������ł̌R���Ζ�����߂��ė����B�ނ͌R���ł͏��Z�̏]���Ƃ��ċΖ����Ă������A�̋��̗F�l�������A���܂�ɂЂǂ�����Ԃꂽ�S�߂ȕ�炵�����Ă��邱�ƂɁA���������B�ނ͎����̗͂�݂����Ɩ���B�����āu�c���͐l����������v�Ƒi�����B���̃X���[�K���̉��ɁA�ނ͖I�N��g�D�����B�E�H������ ���_�ŕ������āA�H���h���C�V�K�̉Ƃ̑O�ɏW�܂�A�V���v���q�R�[���Ŕނɔ��R����X���[�K�������B�h���C�V�K�[�̓��[�_�[�̃��[���b�c�E�C�F�[�K�[���A���F�H�̓k�킽���ɕ߂炦�����āA�ċւ����B���V�����Q�W�̓h���C�V�K�[�̉Ƃ̑O�ɏW�܂��āA���������B�����Čx�����C�F�[�K�[���Y�����Ɍ쑗���悤�Ƃ����Ƃ��A�ޓ��͎E�����ăC�F�[�K�[����������B���ꂩ��x�����ł��炳�ꂽ�B�����璬�ւƖI�N�̒m�点���L�܂����B�����̐E�H�������W�����āA�H��傽���̉ƂɌ������čs�i�����B�����čH��J���҂����ƘA�т��āA�@�B��ł����B�R�����}�s���ė��āA�����ʂɔ��C�������A�J���҂����͓��H�̕ݐŗE���ɖh�킵���B���̂��ߌR���͎�肠�����͓P�ނ�����Ȃ��Ȃ����B �@�I�N�͌��ǂ͒��������ɂ��Ă��A�}���ɍR���ė����オ�����E�H�����̕��N�́A�傫�Ȍx���ƂȂ����B �y����z�f���̓G�C�[���V���e�C���́w��̓|�`�����L���x�̉e�����Ă���B 1927.6.3 �w�ō��w�N���̗� Primanerliebe�x ���[�x���g�E�����g�ēA�V�i���I�F�A���t���[�g�E�V���J�E�A�[�A�N���g�E���F�b�Z�A�B�e�F���B���[�E�S���g�x���K�[ �y�L���X�g�z�t���b�c�E�R���g�i�[�A�A�O�l�X�E�V���g���E�v�A���H���t�K���O�E�c�B���c�@�[�A�O���[�e�E���X�n�C�� �y����z���鍂�Z���̐S���h���}�B 1927.8.20�i���{����30.7.17�j �w�z�[�[ Die Hose�x �n���X�E�x�[�����g�ēA����J�[���E�V���e�����n�C���̊쌀�ɂ�� �y�L���X�g�z�C�F�j�[�E���[�S�A���F���i�[�E�N���E�X�A���h���t�E�t�H���X�^�[�A�t�@�C�g�E�n�[���� �y����z����ŃY�{�������藎���Ă��܂����Ƃ��߂���Љ�h�B 1927.9.19 �w���E�̉ʂ� Am Rande der Welt�x �J�[���E�O���[�l�ēA�V�i���I�F�J�[���E�O���[�l�A�n���X�E�u�����l���g�A�B�e�F�t���b�c�E�A���m�[�E���@�[�O�i�[ �y�L���X�g�z�A���x���g�E�V���^�C�������b�N�A�u���M�b�e�E�w�����A���B���w�����E�f�B�[�e�����A�}�b�N�X�E�V�����b�N 1927.9.23�i���{����1928.11.29�j �w���ё�s������y Berlin.Die Sinfonie der Grossstadt�x ���@���^�[�E.���b�g�}���ēA�V�i���I�F���@���^�[�E���b�g�}���A�J�[���E�t���C���g�i�J�[���E�}�C���[�̃A�C�f�A�ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�t���C���g�A���C�}�[���E�N���c�F�A���[�x���g�E�o�[�x���X�P�A���[�Y���E�V�F�t�@�[�B �y���炷���z�i�ӏt�̕����̃x����������u���f�ʁv�̋L�^�j�B �@�܂��h�ꓮ�����䂪���ۓI�Ȑ��̐��ɂ����A���ꂪ�S�����H�ے����Ă��钼���ƌ����ƁA��ʂ͖閾���̃x�������x�O�B�}�s��Ԃ����i����B�u�x�������A15�L���v�Ƃ����W�����ړI�n���w�����Ă���B���H�A�S���A���ؔԏ����A�V�O�i������ցA��ւƔ�щ߂���B���H�z��̂킫�ɉƉ���H�ꂪ�����B���͂܂�������Ă���B�悤�₭���s������Ԃ̓X�s�[�h�𗎂Ƃ��ďI���́u�A���n���g�w�v�ɋ߂Â��B�v���b�g�z�[�����w�̑�A�[�`�������Ă��āA��Ԃ͐Â��Ɋ��荞�ށB�������܂����͖���̒��ɂ���B�����v�������T���������Ă���B������̒��ɂ����Ƃ����X�H�B�����r���a�̉��ƐV�ẨƂ̃t�@�T�[�h�B���̎����X�H����B����A�ꂽ��ԁA�L�A�ƘH�ɏA����V�ѐl�A�p�g���[�������l�̌x���B��l�̒j���L�����ɓ\��t���Ă���B �@�����Ėڊo�߂����̊������������Ǝn�܂�B�Ԍɂ̔����J���A��Ԃ��o�čs���B�ŏ��̎s�d�ƍx�O�����d�ԁA�n���S�A��荇���o�X�����b�V���A���[�̊J�n��m�点�A����Ɍ�ʂ��������Ȃ�B��Q�̗Y�����{�E��ɋ�藧�Ă���B����̕��m�������s�i���ĉ��K�n�Ɍ������B�����o�����l�g����I���K���e���̘e��ʂ�߂���B�H��̖傪�J���A�]�ƈ������������Ɠ����Ă����B�N�����N����������A�ԗւ���]���n�߂�B�d�����n�܂�B��w�͑��ɐQ���u���A�w���͊w�Z�Ɍ������B�X�֔z�B���X�֕����g���āA�ǂ��o��B�@�W���ɂ͗����X�A���H�X�A���[�h�����X���X���J���B�Ǘ��E���ԂŎd���ɍs���B��Ԃ���������B�O���[�l���@���g�̐X�ł͏�n�𑖂点��҂����B�������ł͒I��o�[�����J�����B�s�O�d�b�����ǂ̎d���̓n�C�X�s�[�h�B �l������B�x�������荇���Ɋ����ē���B�������ł͔��F�������т��Ă���B�}�l�L�����������B�G���K���g�Ȍ�w�l���V���[�E�C���h�߂ĂԂ���B���t�w���������Ă���B���������������y�A�������o�Ă���B�傫�ȊK�i�̑O�Ɋy���B�q���f���u���N���p�������B�Ԋ��𗧂Ăăf���s�i�����c�ƔM�ق�U�邤�َm�B�~���R�̏������m���n�҂̂��߂ɕ�����Ă���B�ؔ��ȑ��������Ԃ���n�Ɍ������B����Ȑl�`�̑���L���B��H�������̋z���k���W�߂Ă���B�x�������̒��Ԏ��̌Ăє���B �@12���B���z�J���҂��p�����p�N���Ă���B�������̃��C�I�������Ђ�ۂݍ���ł���B�r�A�X�^���h�ŁA���z�e���ŁA�\�[�Z�[�W�X�^���h�ŁA�݂Ȃ��������ƌ��ɉ^��ł���B��l�̒j���x���`�̏�Œ��Q���Ă���B�������Ē��x�݂͏I���B �@���[�^�[���Ăт��Ȃ��������B�݂ȍĂъ������n�߂�B�����Ă����[���̈�����n�܂�A�ב��肳��A���������B�܂��l������B������l�����琅�ɔ�э��B�ˑR�̗��B酉J�B���h�����Ԃ��X�H�����čs���B�����ē�������̏I���B�I�ƁB �@�������ނ̌�y�ƃX�|�[�c�̍Â����ւ̎Q�����A�������߂�����B���̂����B�[��ꂪ�E�ъ��B���l���m�̃y�A���������U������B���@���[�[�ΔȁB�����_���B�f��̃X�N���[���ł̓`���b�v�����������グ�Ă���B����ł̓_���T�[�A�o�D�A�̎肪�o�Ԃ�҂��Ă���B�����オ��B��y�Y�Ƃ������J�n�B���@���C�G�e����u���B���^�[�K���e���v�A�u�X�J���v�B�����ăI�y���B�������X�H�ł͘J���҂��s�d�̘H�����C�����Ă���B���X�g�͉ԉB�����Ď���Ɉłɕ�܂�Ă�����s��x�������̏�ɁA����������̌����P���B �y����z��s�s��24���Ԃ̎����I�L�^�f��ŁA�u���f�ʉf��v�Ƃ��Ē��ڂ��ꂽ�B�}�s��Ԃ��x�������́u�A���n�����g�w�v�Ɍ������Ă��i����ŏ��̉f�����A�u�X�s�[�h����v���ے����ē��{�ő傫�Ȕ������ĂB 1927.10.13 �w���̖ڊo�� Das Erwachen des Weibes�x �t���b�h�E�U�E�A�[�ēA�V�i���I�F���@���^�[�E���@�b�T�[�}���A�t���b�h�E�U�E�A�[�A�B�e�F���B���[�E�S���g�x���K�[ �y�L���X�g�z�w���}���E�t�@�����e�B���A�O���[�e�E���X�n�C���A���H���t�K���O�E�c�B���c�@�[ �y����z�Ɖ����L�҂̑��q�Ɩ�Ԃ̖��Ƃ̗����߂���A�x�������̒��݃A�p�[�g�ł̃h���}�B 1927.10.14�i���{����1929.6.23�j �w���E��� Der Weltkrieg�x��ꕔ �y����z�x�������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŁA�h�L�������^���[���g�p�����f�敕��i������1928�N2��9���j�B�N���J�E�A�[p159 1927.12.6�i���{����1928.6.22�j �w�������̔b�� Die Liebe der Jeanne Ney�x �Q�I���N�E���B���w�����E�p�v�X�g�ēA�V�i���I�F�C�����E�G�����u���N�A���f�B�X���E�X�E�E�A�C�_�i�C�����E�G�����u���N�̓����̏����ɂ��j�A�B�e�F�t���b�c�E�A���m�[�E���@�[�O�i�[�A���[�x���g�E���b�n�A���u�F�I�b�g�[�E�t���e�A���B�N�g���E�g���[�t�@�X�A����F�E�[�t�@�f��� �y�L���X�g�z�G�f�B�b�g�E�W���A���k�i�W�����k�E�l�C�j�A�u���M�b�e�E�w�����i�K�u���G���E�l�C�F�ޏ��̖Ӗڂ̏]���j�A�E�[�m�E�w�j���O�i�A���h���A�X�E���{�t�j�A�t���b�c�E���X�v�i�J���r�G�t�j�A�A�h���t�E�G�h�K�[�E���qցi���C�����E�l�C�j�A�n���X�E���[���C�i�|���g���j�A�W�[�N�t���[�g�E�A���m�[�i�K�X�g���j�A�w���^�E�t�H���E���@���^�[�i�}���S�j�A�E���W�[�~���E�\�R���t�i�U�n���L�G���B�b�`�j�A�W���b�N�E�g�����@�[�i�E�H�[���X�E�W���b�N�j�B �y���炷���z�i���V�A�v������̃N���~�A�ŗ����ɗ������t�����X���ƃ��V�A�̊v���Ƃ��A�p���ŋ��������j�B �@�t�����X�̃W���[�i���X�g�A�A���h���E�l�C�́A���V�A�v���ɂ���č������Ă��郍�V�A�ɁA�����I�I�u�U�[���@�[�Ƃ��đ؍݂��Ă���B���̃W�����k�E�l�C�͂����e�ƈꏏ�ɂ���ė������A��l�͑��R���郂�X�N���𗣂�āA��̃N���~�A�֍s���B �@�A���h���̓I�|�`���j�X�g�̎R�t�J���r�G�t����A�{���V�F���B�L�̓����@�ֈ��̈�l�A���h���A�X�E���{�t�Ƃ����N�́A���X�N���ŃW�����k�ƈ��������Ă����ԕ��������B�W�����k�́A�ނ��������������I���ɂ�������Ă���l�Ԃ��Ƃ́A�S���m��Ȃ������B�����A���h���A�X�E���{�t��������Ă���{���V�F���B�L�����́A�A���h����ǂ��āA���̎�ɗ����������@�ֈ��̃��X�g��D���Ԃ����Ƃ���B�����ăA���h�����E���Ă��܂��B �@���c���ꂽ�W�����k�́A�ԌR����������A�A���h���A�X�̌v�炢�ŁA�t�����X�֑��҂���邱�ƂɂȂ�B�J�̍`�ŃA���h���A�X�ɕʂ���������W�����k�́A�t�����X�s���̋D�D�ɏ���ăp���֖߂�B�����E���ꂽ�W�����k�́A����͐�����̎E�Q�������̂�����ƁA�A���h���A�X�������Ă����B �@�p���ɒ������W�����k�́A�����T�㎖�������J���Ă���f�����C�����E�l�C�̐��b���A�����Ń^�C�s�X�g�Ƃ��ē������ƂɂȂ�B�f���ɂ͓V�g�̂悤�ɖ��C�̖Ӗڂ̖��A�K�u���G��������B���炭���Ă���J���r�G�t�ƍX�ɃA���h���A�X���A�p���Ɏp�������B�J���r�G�t�͔��R�̓����@�ֈ����������A�W�����k�̐K��ǂ��A���܂����ׂ��̉\�������߂āA����ė����̂������B�ނ͕x�����Ǝ��̂��Ă��郌�C�����ɋ߂Â��B�����ċ��ނ��Ƃ�m��ʃK�u���G���ɖڂ����A���C�����̋���ړ��ĂɁA�ޏ��ɋ�������B�����I舂ɂ��ׂ�ׂ�ɐ����ς�����Ƃ��A�o�[�̏����̃}���S�ɁA�����͂܂��K�u���G���ƌ������A���ꂩ��E�����肾�Ƙb���Ă��܂��B�}���S�̓K�u���G���Ɍx������B �@�����A���h���A�X�̓\���B�G�g�����@�ւ̓��ʔC����ттāA�p���ɔh������ė����B�W�����k�͂������Ďv���������A���h���A�X�ƍĉ�A�Z���K���̓��X���߂������ƂɂȂ�B�����Ԃ��Ȃ��j�ǂ�����ė���B�������̃A�����J�l�������ȃ_�C�������h������B�����T��͂����T���o���B�����m�����J���r�G�t�͒T�㎖�����ɐN�����āA����𓐂����Ƃ���B�����ă��C�����ɓ��݂̌��������������B����Ɣނ̓��C�������i�E���āA��������B�X�ɃJ���r�G�t�͔ƍs����Ɏc�����Ԑڏ؋��ɂ���āA�E�Q�̌��^���A���h���A�X�Ɍ�������悤�ɂ���B����A���h���A�X�́A�f���ɒǂ��o����Ă��܂��Ă����W�����k�ƁA�z�e���ň����߂����Ă���B�����ăc�[�����R�`�ŁA�t�����X�C�R�̔������A�W��Ƃ����C����ттāA�o�����悤�Ƃ������A�E�l�̌��^�őߕ߂����B �@�W�����k�͗��l�̃A���o�C�𗧏��悤�ƁA�K���ɓw�͂���B��l�̂����z�e���ŁA�ޏ��̓J���r�G�t�����t�w�ƈꏏ�ɂ���̂��������Ă����̂ŁA�ޏ��͉��Ƃ��J���r�G�t�ɏ،������߂悤�Ƃ���B�J���r�G�t�͔ޏ����A�ނɐg���܂�����Ƃ��������ŁA�ޏ��̊肢��e���B�����K���W�����k�́A�J���r�G�t�̂Ƃ���ŁA���̃_�C�������h������B����ɂ���ďf�����E�Q�����̂̓J���r�G�t���Ƃ������Ƃ��������A�ނ͑ߕ߂����B�W�����k�ƃA���h���A�X�́A�����荇���ċ���̍Ւd�̑O�ɂЂ��܂����B �y����z���̉f��̌����́A�G�����u���N�ɂ�錳�̑�{�ł́A�W�����k���A���h���A�X���~�����Ƃ��ł����A��l���j�ł���ߌ��ƂȂ�͂��������B�����������ς���ꂽ�̂́A�P�Ƀn�b�s�[�G���h�ɂ��邽�߂ł͌����ĂȂ������B����̓E�[�t�@�f��Б��Ɗēp�v�X�g�ƁA�����͂܂������̍�Ƃ������G�����u���N�Ƃ̊Ԃ́A���G�ȎO�p�W�f������̂������B���������v���̃��V�A�ƃp���Ƃ�����̏ꏊ��Ƃ���f�悪���ꂽ�Ƃ������Ƃ��A���łɑ�ϋ����[���������̏��Y�������ƌ�����B �@�p�v�X�g���g�����łɁA�A���r���@�����g�ȓ��قȃ��A���Y���̊ē������B�ނ��f������n�߂��̂�1923�N���炾�����B���������đ�ꎟ���E����̑����h�C�c�f��̌X���ł���\����`���A�I��낤�Ƃ��Ă������_����̏o���������B�\����`�I�M���Ƃ͖��W�������̂ł���B�ނ͍ŏ�����u���O�|�p�A���v�ɏ������A�ᔻ�I���A���Y���������Ƃ���f��̉\����͍����Ă����̂ŁA�����̎���ƎЉ�Ƃ�`���Ƃ����A�ނ̓��ӂƂ����̃e�[�}��������i�����グ�悤�Ƃ����̂́A���R�̐���s���������B �@�����E���I�o�ϐl�̑嗧���t�[�Q���x���N�̎P���ɓ������E�[�t�@���A�p�v�X�g�ɋ��Y��`��ƃG�����u���N�̏������f�扻���������R�́A�����̎�����ɂ��Ă͗����ł��Ȃ��B�܂�1926�N4���ɁA�G�C�[���V���e�C���́w��̓|�`�����L���x���A�x�������ŊC�O�����J����A�Z���Z�[�V�����������N���������Ƃ�m��K�v������B�f��j��ō�����̈�ɐ�����ꂽ���̉f��̌��J�́A���V�A�f��u�[���̂��������ƂȂ����B�u�v���|�p�v���ϋq�ɐ[��������^�����킯�ł��邪�A�����ɂ���́A������u�����^�[�W���v�Z�@�ɂ���āA�f�搻��̃v�����V�v���ɐr��ȉe����^�����B�����ăp�v�X�g�͂��łɁA��ꎟ���E��햖���̃L�[���R�`�ł̐����������e�[�}�Ƃ����f������Ƃ����v������Ă�����ł����B����䂦�ނ͂������A�w�|�`�����L���x���͂��߂Ƃ��郍�V�A�f�悩��A�e�[�}�I�ɂ��Z�@�I�ɂ��A�������Ռ������f��ē̈�l�������B�����ăt�[�Q���x���N�P���̃E�[�t�@�ł���A���܂��܂Ȏ����̈Ӗ����������V�A�f��u�[���ɂ��₩�肽���ƍl�����̂������B �@����Ƀ^�C�~���O�ǂ�1926�N4��24���A�x�������œƃ\�F�D����ꂽ�B����͓����̃\�A�̃`�`�G�����O���l���ψ����A���J���m���ɂ���ăh�C�c�������ɌX���̂��������悤�ƈӐ}�������ƂƁA�h�C�c�O���V���g���[�[�}���ɂ��v�f�����������ʏ������Ë��������B����͋ɉE�̑��ɂ���A�����Ƃ����Ƃ��ꏏ�ɂ���čs����Ƃ��������������邱�ƂɂȂ����B�h�C�c���h�R�����V�A�ŐԌR�Ƌ��͂��āA�p�����̋����Ȃ��R���������Ђ����ɐi�߂Ă����Ƃ������Ԃ��A���z���M�I������������Ă����B�܂蓌���̋��Ԃɂ���Ƃ����h�C�c�̒��ԓI�n�ʂ��A�Љ�╶���̌X���ɂ������ȗ��`�I�ȉe�𓊂��Ă����B����䂦�{���V�F���B�L�̕�����f�扻����Ƃ����E�[�t�@�f��Ђ̂������킵���Ӑ}�́A���A���|���e�B�[�N�I�H������o�����̂������B �@���̂����A���������̃C�f�I���M�[�I���O���A�w�|�`�����L���x�I���_�̑f�ނɂ���āA���E�I�q�b�g���˂炤�Ƃ������Ǝ�`�I�v�f�̑O�ɂ́A�������ł��܂����B�����p�v�X�g���g������Ă���悤�ɁA�E�[�t�@�Ђ͊v�����V�A�I���_���������ɂ��邽�߂ɁA�f����u�n���E�b�h�I�l���v�ʼn��o����悤�ɂƎw�������B���̉f��̃A���r���@�����g�ȍ����I���i����������E�[�t�@�̂��������p���ɂ��ẮA�G�����u���N���g����������Ă���B �@�u�w���c�t�F���f���玄�Ɏ莆�������B�w�E�[�t�@�x���w�W�����k�E�l�C�̗��x���f�扻���������Ă���A�ē͗D�G�ȉf��ē̈�l�Q�I���N�E�p�v�X�g����邾�낤�A�Ƃ����̂��B���͐��̍r�p��`�����ނ̉f��w��тȂ��X�x��m���Ă����B���̉f��͍D������������A���́w�E�[�t�@�x�̐\���o����B�p�v�X�g�́A���̏����̋��A���R�Ɓq�ΌR�r�Ƃ̓����A�J���ґ�\�\���B�G�g�̉�c�A�v���ٔ����A�閧������A�Ƃ������G��I�ȃV�[���ŏ��邱�Ƃɂ����B�c�c��R�̃V�[���́A���R���Z�����̎����̏�ʂł���B�p�v�X�g�͂��̃V�[���B�e�̂��߁A���ăf�j�L���R�̏��Z�������A�����������B�c�c�G�L�X�g�������ɂ��܂������Ă��炢���߁A�p�v�X�g�͔ނ�ɂ܂��ďo���������邱�Ƃ�����[�[�P�T�Ԃ����獡�x�͐ԉq��������Ă��炤���A�ߏւ́w�E�[�t�@�x����t���邩��A�ƁB�n�R�ȃG�L�X�g�������͑��т������B���Ă̔��R���Z�������A���Ń{���V�F���B�L������낤�Ƃ��Ă���̂��c�c�ӎ��肱�܂��A���S���̐l�X�𔒒s������f��𗬂��Ƃł���q���̍H��r���ǂ�Ȃ��̂����ɂ킩�����B1927�N��N�ԂɁA�w�l�ӂ̗��x�A�w��̒��̗��x�A�w�x�e�B�[�E�s�[�^�[�\���̗��x�A�w���Ɠ��݁x�A�w���Ǝ��x�c�c�w���Ƌ��x�A�w���������̗��x�A�w�Y���̗��x�A�w���X�v�[�`���̗��x���ϋq�݂͂邱�Ƃ��ł����B����ɂ�����A�w�W�����k�E�l�C�̗��x�Ƃ����ς�킪������ꂽ�킯���v�i�w�킪��z�x�j�B �@����1924�N�Ɂu�x�����i�[�E�x���[���E�N�[���[���v���̘A�ڏ����Ƃ��Č����A�L���ǂ܂ꂽ�G�����u���N�̍�i�̒��ł��A�g�b�v�̃x�X�g�Z���[�ƂȂ�������́A�G�����u���N���g�́u�v������̃��}���`�V�Y���ɑ���������v�Ə̂��Ă��邪�A���ꎩ�̃K�Z���`�����^���ȗ��̕���ƃ{���V�G���B�L�Ɣ��R�̉A�d�Ŗ��t�������A�T�X�y���X�ɕx�ƍߕ���́u�������v�ł����āA�E�[�t�@�̓�d�̎v�f�Ɗ�{�I�ɍ��v�����i�ł������B �@�������E�[�t�@�Ђɂ�錴��̕ύX�́A���́u�������v����˂��Ȃ�����̂������B�����ł̓W�����k�E�l�C�͖{���ɃJ���r�G�t�ɐg��C�����B���������̋]���͖��ʂ������B�A���h���A�X�͎E�l�߂ŏ��Y�����B����䂦�G�����u���N�́u�����̍��͈��E���ꂽ�v�ƍR�c�����B�m���ɂ��̒ʂ�ł��邪�A���̑���f��͌���̃Z���`�����^���Y����r���A������u�s�Εs�}�v�̒������ɂ���āA���ɂ̓T�f�B�X�`�b�N�Ȃ܂łɗ⍓�ȃ��A���Y���ƂȂ��Ă���B�����p�v�X�g�̃��A���Y���͖ړI�ł͂Ȃ��A��i�ł���B����̓����h���}��r��������̂ł͂Ȃ��B�E�[�t�@�Ђ̎v�f�ƃG�����u���N�̍������ɁA�X�Ƀp�v�X�g�̓��قȓ�d�����d�Ȃ��āA���̉f��̓A���r���@�����g�ȕ����̃��f����i�̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B�u���Ȃ��������̂��߂ɓƓ��ł���Ƃ������́A�ނ���Љ�̕a�I��Ԃ̏nj�̓��@�̓_�œƓ��ł���悤�ȁv�w��тȂ��X�x�𗽉킷����̂��������A���Y���Ƃ������킵���Ƃ̋����ł���B �@�u�p�v�X�g�͂����Ŗ{���̌ˊO�B�e���Ŏ����������łȂ��A�o�D�ɂ��N�[���ȕ\����������B�ǂ���́A�W�����k�E�l�C���N���~�A������ۂ́A�A���h���A�X�Ƃ̕ʂ�̏�ʂł���B��l�͟��R���鍋�J�̒��ŁA�r��ʂĂ��p�Ђ̐^�ɗ����Ă���B�����ĕ����������Ƃ��邪�A�ނ�̊Ԃ�ʂ��ĉ��������ւ��������Ȃ���g�~��������l�̌Q��Ɋu�Ă���B���̏�ʂ͂܂����������I�ȒP�����ŎB�e����Ă��āA�����ɔߌ��I�ȏh���_�̃g�[����^����悤�Ȏ��݂͂Ȃ���Ȃ��B���������̃��A���Y���́A�f��̈�̃A�X�y�N�g�ł����Ȃ��B�p�v�X�g�̏����̑n��̓T�^�I�ȍ����̒��ŁA�\����`�I�ȗv�f���������̃V���{���Y��������Ă��邢�����킵���́A����̂������킵���ł�����B����䂦����̃g�[���ɐG���Ƃ����Ӗ��ł́A�p�v�X�g�̂������킵�����A���Y���͋t���I�Ȑ^��������Ă���B��ʂɕ]������A�܂��ޓƎ��́u�������v���A���e�B���A�����ă����h���}������藣���ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���`�����\������s���̗v�f�ƌ���ׂ��ł��낤�B�����āuE�EA�E�f���|���͔ނ́w���@���G�e�x�ɂ����āA���A���ɕ`���Ӑ}�ŁA����Ƃ���ɃJ�������o�v�������@���̗p�����ɂ��Ă��A�ނ̍\�����鐢�E�͌����̋q�ϓI���f�Ƃ������́A�ނ��댻���̗l�������ꂽ�C���[�W�ł������B�ނ̐��҂ƈ���ăp�v�X�g�́A�����̐����̋��R�̌`�Ԃ��B�e���邽�߂ɁA�J�������ړ�������B�w�������b���x�́A�Ȃ炸�҂̃J���r�G�t�̓�����`�ʂ����ʂŎn�܂�B���Ȃ킿�A�ނ̌C�̐悩��J�����͋r�ɉ����āA�T���U�炳�ꂽ�V�����ւƊ����čs���A�e�[�u���̏�̉����̋z���k���ʂ��A�z���k�̈����蕪���Ă���ނ̎��ǂ��A���Ȗ��ɒ��߁A�Ō�ɃJ���r�G�t���\�t�@�ɉ�������Ă���A�z�e���̉��ꂽ�����̈ꕔ�����͂ށB�c�c�ނ͂ق�̎��ɑ���ʈ�ۂ�߂炦�邽�߂ɂ��A���ׂȉf���̐�͂������p����B�����Ă��̂悤�Ȑ�͂���Z�������āA�@�ׂȑg�D�ɍ��グ�A�����ɖ��ڂɊ֘A�������̂Ƃ��Ă̌������ʂ��o���v�B�p�v�X�g���g�͎����̂���������@���A�����������Ă���B�u�ǂ̃V���b�g�������̓����̏�ɍ\������Ă���B�����E�J�b�g�̏I��ł͒N���������Ă���B�����J�b�g�̎n�߂ł́A���̓������p�������v�B�܂�f���I���A���e�B��\������̂ɁA�p�v�X�g�݂͌��ɏՓ˂����������^�[�W���̏Ռ��̌��ʂ𗘗p���郍�V�A�̃X�^�C���Ɣ��ɁA�n���h�����O�̊��S�ȗ�������Nj������̂ł���B�₦���ω�����f���̗^���郊�A���Ȉ�ۂ��A�w�������̔b���x�ŒB�������p�v�X�g�̃��A���Y���̍����ł���B 1927.12.20 �w�傢�Ȃ钵�� Der grosse Sprung�x �A���m���g�E�t�@���N�ēA�V�i���I�F�A���m���g�E�t�@���N�A�B�e�F�[�b�v�E�A���K�C���[�A�n���X�E�V���l�[�x���K�[�A�A���x���g�E�x�[�j�b�c�A���q�����g�E�A���O�X�g�A���u�F�G�[���q�E�`�F�����H���X�L�[�B���y�F���F���i�[�E�q�A�n�C�}�� �y�L���X�g�z���j�E���[�t�F���V���^�[���A�n���X�E�V���l�[�x���K�[�A���C�X�E�g�����J�[�A�p�E���E�O���[�c �y����z����A���v�X�̎R�r�̔Ԑl�̏������X�g���X��a��ł����s�s�̂���}�l�[�W���[�ɁA�X�L�[�������邽�킢�̂Ȃ��R���f�B�[�B 1927.12.22 �w�v���C�Z���̉��܃��C�[�[ Königin Luise�x �J�[���E�O���[�l�ēA�V�i���I�F���[�g���B�q�E�x���K�[�A�B�e�F�A�[���p�[�h�E���B���[�O �y�L���X�g�z�}�f�B�[�E�N���X�`�����X�A�n���X�E�A�[�_���x���g�E�t�H���E�V�����b�g�[ �y����z���C�[�[���܂̎Ⴂ���B |
|
| 1928 | |
| 1928�i���{����1930.11.21�j �w���т̏��� Die Dame mit der Maske�x �n���X�E���q�^�[�ē� �y����z���q�^�[�ē��C���t�����̐����f�Ђ�`���������f��w�g�|�C���t���[�V���� H-Inflation�x�̈ꕔ�B 1928�i���{����1930.3.6�j �w�n���K���A���E���v�\�f�B�[ Ungarische Rhapsodie�x �n���X�E�V�����@���c�ē� �y����z�N���J�E�A�[p197 1928 �w���R���s Freie Fahrt�x �G���l�E���b�c�i�[�ē� �y����z���b�c�i�[���Љ��}�̂��߂ɐ��삵����`�f��B�̒Z���قȂ��������ō\������Ă���B��ꕔ�̓��V�A�f��̖͔͂ɏ]���č\�����ꂽ�A���B���w�����c�鎞��̘J���҂̋ꋫ�ƁA�Љ��}�̑g�D�����ɂ��Ẵh�L�������^���[�I�����^�[�W���A��͓����̓}�����ɕ������A�f��ɂ��}�̃v���p�K���_�������B �i�N���J�E�A�[S191�j 1928 �w�U���N�g�E�p�E���̃J������ Die Carmen von St-Pauli�x �y����z�N���J�E�A�[p162 1928.1.3 �w�V�t���b�c Der Alte Fritz�x �Q���n���g�E�����v���q�g�ē� �y�L���X�g�z�I�b�g�[�E�Q�r���[�� �y����z1��24�����t���[�h���q�E�剤�̒a�����B1��20���f��w�V�t���b�c�x��A�x�������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŕ��� 1928.1.25�i���{����1929.5.1�j �w�d�ԃA���E�l Alraune�x �w�����b�N�E�K���[���ēA�n���X�E�n�C���c�E�G�[���@�[�X�i��1932�N10��14���A�����w�z���X�g�E���F�b�Z���x�j�̏����ɂ�� �y�L���X�g�z�u���M�b�e�E�w�����A�p�E���E���F�[�Q�i�[ �y���炷���z��w�I�y���̋������i��Y�ɂȂ����ߐl�̐��q���g���Ĕ��t�w��s�܂��A���܂ꂽ�d���������������������A���E�l���j��j�ł����A���Ɏ��������o�����������j�ł�����B 1928.2.1 �w�V���_�[�n���l�X Schinderhannes�x �N���g�E�x�����n���g�ēA�V�i���I�F�N���g�E�x�����n���g�A�J�[���E�c�b�N�}�C���[�i�J�[���E�c�b�N�}�C���[�̏����ɂ��j�A�B�e�F�M�����^�[�E�N�����v �y�L���X�g�z�n���X�E�V���g�D�[���F�A�t���[�_�E���q�����g�A�u���[�m�E�c�B�[�i�[�A�A���x���g�E�V���^�C�������b�N�A���V�[�E�A���i�A�t���b�c�E���X�v �y����z�P�W�O�R�N�ɏ��Y���ꂽ���C���n���̓����c�̎�̂̕���B 1928.2.4 �w�f��Ɛl���A�o�[�o���E���E�}���x���s �y����z�A���m���g�E�u�����l���̏����w�f��Ɛl���A�o�[�o���E���E�}���x�A�x�������̃��[���H�[���g���X���犧�s 1928.2.7 �`���b�v�����w�T�[�J�X�x �y����z�x�������́u�J�s�g���v�f��قŃh�C�c����B�听���ŁA�����̏�f��A�x����������̒��S�u���B���w�����c��L�O����v��N�[�A�t�����X�e���_�����ӑ卬�G�ŁA��ʏa�A�V���e����^�B 1928.2.9 �w���E��� Der Weltkrieg�x��� �y����z�x�������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŁA�h�L�������^���[���g�p�����f�敕��i��ꕔ�����1927�N10��14���j�B 1928.3.14�i���{����1969.12.27�j ���V�A�f��w�\�� Oktyabri�x �G�C�[���V���e�C���ē� 1928.3.22�i���{����1930.3.26�j �w�X�s�I�[�l Spione�x �t���b�c�E�����O�ēA�V�i���I�F�t���b�c�E�����O�A�e�A�E�t�H���E�n���u�i�e�A�E�t�H���E�n���u�̏����w�X�s�I�[�l Spione�x�ɂ��j�A�B�e�F�t���b�c�E�A���m�[�E���@�[�O�i�[�A���u�F�I�b�g�[�E�t���e�A�J�[���E�t�H���u���q�g�A���y�F���@���i�[�E���q�����g�E�n�C�}���A����F�E�[�t�@�f��� �y�L���X�g�z���h���t�E�N���C�������b�Q�i�n�MI�^�}�u�[�j�A�Q���_�E�}�E���X Gerda Maurus�i�\�[�j���j�A���B���[�E�t���b�`�� Willy Fritsch�i�h�i���h�E�g�����[���A�T��i���o�[326�j�A�p�E���E�w���r�K�[ Paul Hörbiger�i�t�����c�j�A���[�v�[�E�s�b�N Lupu Pick�i���{�j�A���G���E�_�C���[�X�i�L�e�B�j�A���C�[�Y�E�����t�i�����[���j�A�N���C�O�z�[���E�V�F���[�i�W�F�[�\���j�A�w���^�E�t�H���E���@���^�[�i���f�B�[�E���X���[���j�A�t���b�c�E���X�v�i�C�G���W�b�N�卲�j�A���[���E�X�E�t�@���P���V���^�C���i�z�e���x�z�l�j�A�Q�I���N�E���[���i�@�֎�j�A�p�E���E���[�R�b�v�t�i�V���g�����q�j�A�w���}���E���@�����e�B���A�O���[�e�E�x���K�[ �y���炷���z�i�������ʁE�ʐM��i���t���Ɏg�p�����X�p�C�E�X�����[�f��B���{�̊C�R�m���̏��{�̕����ʂ��b��j�B �@����X�p�C�g�D�����{�̔閧��T�邽�߂ɁA��g�ق��P������A�d�v�ȋ@�����ނ𓐂�A���������E�����肷��B���������̒��ŁA�ԋ߂ɔ������X�y�C���Ƃ̔閧����̈��S����邽�߂ɁA������b���h�������̃o�[�g���E�W�F�[�\���ɁA�����Ɨǂ����̐E�����ʂ����悤�ɂƔ���B�W�F�[�\���͍��ۓI�ȃX�p�C�g�D�̐e�ʂ�T�m���悤�Ƌ�S���Ă������A���̓w�͂͂���܂ł̏��A���l�̗L�\�ȏ����������������������B �@�����ō��x�͈�Ԃ����ꂽ�����̃h�i���h�E�g�����[���i�T��i���o�[326�j���A���̎d���ɓ��Ă��邱�ƂɂȂ�B�����A���̃X�p�C�g�D�̐e�ʂ̃n�M�́A���Ԃɂ͑��s�ƂƂ��Ēʂ��Ă������A�g�����[���ɑR�����邽�߂ɁA�g�b�v�����X�p�C�̃\�[�j���Ă��B�g�����[���ƃ\�[�j�����o��ƁA��l�͂����Ɉ��������悤�ɂȂ����B�����Ń\�[�j���̓n�M�ɁA�����̖�ڂ������Ă����悤�ɗ��ށB�������n�M�͋����Ȃ��B��Ƀg�����[��������ŁA�X�y�C���Ƃ̔閧����̏ꏊ�Ɠ������L���b�`���A���ׂĂ̏d�v�ȋL�^����肷��悤�ɖ�����B �@��ނȂ��\�[�j���́A�g�����[���𗠐炸�Ɏg����B�����悤�Ɠw�͂���B�����g�����[���������Ă����݂̂��߂ɁA�ޏ��̓n�M���������炾������B�����ăg�����[���͂Ƃ��Ƃ����{�̊O�����ŏ����̏��{����A�\�[�j�����X�p�C�ł��邱�Ƃ��m��B������{���g�́A�n�M�̂�����l�̏������L�e�B�̏p���Ɋׂ�B�ޏ��͔ނ�U�f���A�ނ���閧���ނ𓐂ݎ��B�����N��������m�������{�́A�ؕ�����B�L�e�B�͏��ނ��{�X�̃n�M�ɓn���A�J���Ƃ��Ė{���\�[�j���ɗ^�����邱�ƂȂ��Ă����^������炤�B�n�M���g�́A���̐��E�ň�ԋ��͂Ȓj�ɂȂ�Ƃ����A�N���̖��̎������ԋ߂��Ȃ����̂ŁA��������L���V�ɂȂ�B �@�ނ̓\�[�j�����Ō�̎g�����ʂ�������A�Â��ɕ�炳���Ă�낤�ƌ����A����߂ďd�v�ȏ��ނ��O���։^�Ԃ悤������B�\�[�j���̓n�M���A�g�����[���������ז����Ȃ��Ƃ������ŁA����ɉ�����B�n�M�͂��̏�����e��邪�A���ꂩ���R�ƁA�g�����[���̐����ɂ������悤�Ȍv������Ă�B �@�����g�����[���́A���ނ����܂�Ă��܂����ɂ�������炸�A���ʂ̋�����������Ƃ����S�ɂ����Ȃ킳���邽�߂ɁA�h�������̃W�F�[�\���ƈꏏ�ɁA��]�I�ȓw�͂𑱂���B�ނ�̓l���Ƃ������O�ŁA���郔�@���C�G�e�B����ɁA�������Ƃ��ďo�����Ă���ނ�̏����̈�l��K�˂�B�l���͂͋����������邽�߂̔閧�����𐿂������B�n�M�̓g�����[�����D�Ԃŗ��s����̂��˂���āA�ނ̏���Ă���Q��Ԃ��A�g���l���̒��Ő藣���A�㑱�̗�ԂƏՓ˂����ĎE���Ă��܂����Ƃ���B �@���������傤�NJO���֕ۗ{���s�ɏo�|���悤�Ƃ����\�[�j���́A���z���Ɍ��������̗�ԂɃg�����[��������̂����ċ����B��Ԃ͔��Ԃ��A�ޏ��͂��̍Ō�̎ԗ��̔ԍ��R�R�P�R�R��������B�Փ˂��邱�ƂɂȂ�̂́A�ޏ��̏�����D�Ԃł���B�g���l���ɓ���ƁA�n�M�̕����̃����[���Ɨ�Ԃ̃{�[�C���A������͂����A�g�����[���̏�����Q��Ԃ͋t�߂肵�Ď~�܂�B�L���ɏo�ăg���l�����̂������g�����[���́A��Ԃ��ːi���ė���̂����āA�����Čジ���肷��B�����ďՓˁB �@�ԗ��ԍ�33133���g���l���̒��Ŏ��̂ɉ�������Ƃ�m�����\�[�j���́A�g���l�������}���ōs���B���I�̎R����肪��{�˂��o�Ă���̂����āA�\�[�j���͜��R�Ƃ��邪�A�X�ɓˑR�G�̏����Ɏ����̂��߂��݂Ƀs�X�g����˂������āA�ߖ�������B�������̏u�ԁA�˂��o�Ă����肪���̈����̑���͂�œ|���B�g�����[���͐����Ă����̂������B �@���ꂩ��g�����[���ƃW�F�[�\���͐��ɁA���g�s���̂悤�ȋ�s����̃n�M���A���̓V�p�C�g�D�̃{�X�ł͂Ȃ����Ƌ^���B�����X�p�C�g�D�̒����ƂȂ��Ă����s�ł́A�T��i���o�[326�������Ă��邱�ƁA�\�[�j�������������Ƃ�m��B�����Ńn�M�̓\�[�j����������ė������āA��s�Ɋċւ���B�x�@����s�ɋ}�s���A�n�M�̔閧�̕�����{���B�n�M�̓\�[�j�����������A��s���K�X�Ő�������ƌ����B�g�����[���͊낤���Ƃ���Ń\�[�j�����~�����Ƃ��ł������A�n�M�͓����Ă��܂��B �@�n�M��ǂ����x�@�́A�������̃l�����n�M�ɑ��Ȃ�Ȃ����Ƃ�����B�l���̏o�����Ă��郔�@���C�G�e�B����Ɍx�@�����ݍ��ނƁA���͂����Ō�ƊϔO�����l���́A�u�o���h�}�X�^�[�A���y���I�v�Ƌ��сA�܂�ł��ꂪ�~���[�J���̎R��ł���悤�Ɍ��������āA�����Ŏ��E����B�����m��Ȃ��ϋq�����肵�Ă���ԂɁA�������낳���B �y����z�w�X�s�I�[�l�x�̓t���b�c�E�����O�̉f��̒��ł́A���܂�m���Ă��Ȃ���i�������B��ɂ͓������E�ɔz�����ꂽ�̂��A�Z�k�ł��������߁A�w�h�N�g���E�}�u�[�x�̏ꍇ�Ɠ��l�A�d�v�ȓ_����������Ȃ��������߂ł��������B��ɂ́A���̑O�ɍ���āw���g���|���X�x�����ƓI�Ɏ��s�������߁A�����O����������Ԃ����߁A�X�p�C�f��Ƃ����悤�ȍە��̃Z���Z�[�V���i���Y���ɗ������ƌ����Ă��߂ł���B�X�Ƀ����O���g���F�߂Ă���ʂ�A�X�p�C�g�D�͓��������h���ɂ������\���B�G�g�ʏ���\���ɋ[����Ă���A�N���C�������b�Q������n�M�̕����́A�g���c�L�[�Ɏ����Ă��������߁A���\�E�X�p�C���Ƃ����Ό��ō��ꂽ��i�ƌ��Ȃ���A�����Z���Z�[�V���i���Y���������������Ă��܂������߂ł�����B �@�Ƃ��낪1978�N�̃j���[���[�N�f��ՂŁA�t�@�X�r���_�[�A�g�����t�H�[�A�V���u�����Ƃ������A�����̐V�l�f���Ƃ̍�i�ƕ��ׂĂ��̍�i����f�����ƁA�唽�����Ă�ŁA�w�}�u�[�x�A�w�j�[�x�����Q���x�A�w���g���|���X�x�ȏ�Ƃ����]�����邱�ƂɂȂ����B����̓G���m�E�p�^���X�̕�����Ƃɂ���āA���S�ł̏�f���\�ɂȂ������߂ł���B����䂦�W�[�N�t���[�g�E�N���J�E�A�[�̂悤�ɁA���̍�i���u�ȃZ���Z�[�V�����������I�Ӗ����[�����邩�̂悤�Ȍ���������^�����肵�Ȃ���A�A���t���b�h�E�q�b�`�R�b�N�̃X�����[�f��̐^�̐��҂��蓾���ł��낤�v�ƕ]�����ׂ����A�u�t�B�����E�R�����g�v���̃G���I�b�g�E�X�e�C���̂悤�ɁA�u�����O�̍ŗǂ̉f��̈�A���������Đ��E�ň�ԗǂ��f��̈�v�ƕ]�����ׂ��́A�����O�ƃn���u�̉f��̎����قȃL�b�`�������A�ǂ��܂ŏd�邩�ɂ������Ă���B �@�������Ȃ��Ƃ��A�����͌�����B�u�O�O�V�X�p�C�E�V���[�Y�v�͂��납�A�q�b�`�R�b�N����A���|�̐Ⓒ��������ׂ��쌀�}�]���郉���O�̘r�O�𗽉킷��̂́A�e�Ղł͂Ȃ����낤�A�ƁB �y�f��]�z�u�V���s�I�[�l�v���]�i�����x�m�Y�^���c���v�^�g�j�^���X�ؕx���j�^ꠖ{�~�Y�^�ԐΏC�O�j�\�\ �����@���ꂩ��u�V���s�I�[�l�v�̍��]�����܂��B�悸����A�r�F����B �@����̓A�����J�ŕҏS�������̂��B �����@����̊e���̕����̏悶�����ۊԂ̔閧��T�낤�Ƃ���Ԓ��c�̊�����`�������́A���ꂪ���}���X�������Ċ��������I�Ɉ����Ă�B ���c�@�����]���Ƃ����͂̂́A�n���{�E�̃��}���e�B�Y���Ƒ��ւ��Ėʔ����B ꠖ{�@�n���{�E�̍�i�Ƃ��Ă͍��܂ł̂��̂������������I�ȂƂ��낪�������B �����@���G�ȋ��I�݂ɃX�s�[�h�������ēZ�ߏグ���n���{�E�̘V�I���͌h���ɉ�����B �@���߂̕��Ől���̏o�������������Ă�������̓A�����J�ŕҏW�����������낤�B ���c�@�ēt���b�c�E�����O�͎�@�ɉ��ď����̍�i�u�h�N�g���E�}�u�[�v�̖����������B��ɍŌ�̑劈���̃X�s�[�h�ƃ^�C�g���̏o�����ɉ��Ă�����������B �Ԑ@�V������ނ��g���Ă����ɂ͌ÓT���̖̂����o�����Ă�B�R�����ꂪ�����r�����C�ɂȂ�Ȃ��Ƃ���̓n���{�E�̌��тƉ]���悤���B �����@���{�̕����ȂǂɊւ���l�͍��܂ł̂��̂ɔ䂵��ꡂ��ɂ悭�s�͂��Ă���B ���X�@��ɂ��̕��̏�ʂ͈������ˁB �����@��Ԃ̏Փ˂̏�ʁA��s���̍Ō�̊i���̏�ʂ��ǂ��B�S�̂Ƃ��ďd�X�����h�C�c���̂ɔ䂵��ꡂ��ɃX�����ƃT�X�y���X�ƃX�s�[�h�������Ă�B ���c�@���O�i�[�̃J�����̓I�b�g�[�E�t���e�̃Z�b�g�Ƒ��ւ��Č��ʓI���B �Ԑ@�D�Ԃ̏Փ˂̏�ʂ̃J�����E�A���O���Ȃǎ�ɗD��Ă�B ꠖ{�@�n�M�ɕ����郋�h���t�E�N���C�����b�Q�͐̂��烉���O�Ƌ��͂��āA�����O�̋C�����̂ݍ���ł悭�����Ă���B �Ԑ@�n�M�͂͂܂�����B �����@���{���m�����郋�v�E�s�b�N�́A�ގ��g���ē��������āA���m�����_�����������{�l�̖����悭�o���Ă���B ���c�@�s�b�N�̓h�C�c�f��|�p�ƕی싦��̉���B ���X�@�Q���_�E�}�E���X�̓����O�Ɍ��o���ꂽ�������鏗�D���B �@���̑��̔o�D�������O�̖��w���ɂ���ĊF�ǂ��ˁB �Ԑ@�S�̂Ƃ��āA�����O���̂Ƃ��Ă͔��ɋ����{�ʂ̈�ʎ̂����i���B �����@�����]���Ɠ���������̑傫����i�Ń����O�̑��̍�i�ɔ䂵�ď����ė����̂ł͂Ȃ��B��ɏ]���ƕς��ăX�s�[�h�������Ă���B�i�w�f��]�_�x�A���a�T�N�R�����j 1928.4.21 �w�ד� Abwege�x �f�E�v�E�p�v�X�g�ēA�V�i���I�F�A�h���t�E�����c�A���f�B�X���t�E���@�C�_�A�B�e�F�e�I�h�[���E�V���p�[���N�[�� �y�L���X�g�z�u���M�b�e�E�w�����A�O�X�^�t�E�f�B�[�X���A�W���b�N�E�g�����@�[�A�w���^�E�t�H���E���@���^�[ �y����z���������ɑދ����A���̒j�����������n�߂邪�A�Ƃ��Ƃ��ޏ��̕v���v�Ƃ��Ă̋`���ɖڊo�߂�h���}�B 1928.7.14 �w�ߑO�̗H�� Vormittagsspuk�x �n���X�E���q�^�[�̎����f�� �y����z�A�j���[�V�����A�R���[�W���A�t�Ȃǂ��܂������G�`���[�h�B�q���f�~�b�g�ƃ~���[���������Ă���B 1928.8.3 �w���� Zuflucht�x �J�[���E�t���[���q�ē� �y�L���X�g�z�w�j�[�E�|���e���A�t�����c�E���[�f���[�A�}���K���[�e�E�N�b�p�[ �y����z���ł����v���Ƃ̐S�����B 1928.8.29�i���{����1930.4.2�j �w�A�� Heimkehr�x �W���[�E�}�C�ēA���I���n���g�E�t�����N�̏����w�J�[���ƃA���i�x�ɂ�� �y�L���X�g�z�����X�E�n���]���A�f�B�[�^�E�p�����A�O�X�^�t�E�t���[���q �y����z�x�������́u�O�����A�E�p���X�g�v�ŕ���B�V�x���A�ŕߗ������𑗂��Ă�����l�̗F�l�̈�l�����S�ɐ�������B�c���ꂽ��l���悤�₭�A�������Ƃ��A�����̍Ȃ���ɋA�����F�l�̂��̂ɂȂ������Ƃ�m��B�w��������ُ�Ȃ��x�Ȃǂ̐푈���w�̑��̃u�[���Əd�Ȃ����f��B���{���J�ł͉��ł��Ȃ���ʂ����{�ŃJ�b�g���ꂽ�B 1928.9�� �A�����J�f��w�W���Y�E�V���K�[ The Jazz Singer�x �A�����E�N���X�����h Alan Crosland�ēA�A���E�W�����\���剉 �y����z���E�ŏ��̃g�[�L�[�f��x����������B 1928.9.10 �A�����J�f��w�������̃n�C�f���x���N�̊w���v�����X The student prince in Old Heidelberg�x �y����z�}�C���[�t�F���X�^�[�̃Z���`�����^���ȃh���}�w�A���g�E�n�C�f���x���N�i�������̃n�C�f���x���N�j�x�ɂ��A���r�b�`���ē̃A�����J�f�敕�� 1928.9.16 �w���Ԃ�Looping the Loop�x �A���g�D�[���E���r�\���ēA�E�[�t�@�f�� �y�L���X�g�z���F���i�[�E�N���E�X�A�C�F�j�[�E���[�S Jenny Jugo �y����z�G�[���q�E�����f���]�[�����N�[�A�t�����X�e���_���Ɍ��Ă������u���H�[�K�v���z�̒��̉f��فu�E�j���F���Y��Das Univerusum�v�i1763�ȁj�J�Ƃ��A�v���~�A�ɏ�f���ꂽ�B�T�[�J�X�̕��͋C�̒��ł̃����h���}�B 1928.10.8 �u�g�[�L�[�f�抔����Ёv�ݗ� �u�A�[�E�G�[�E�Q�[AEG�v�ЂƁu�W�[�����X Siemens�v�Ђ��u�g�[�L�[�f�抔����� KLANGDILM GMBH�v��ݗ��B���{����300���}���N�B 1928.10.24 �w�Ȃ��ꂽ�� Geschlecht in Fesseln�x ���B���w�����E�f�B�[�e�����ēA�V�i���I�F�w���x���g�E���g�P�A�Q�I���N�E�b�E�N���[�����A�B�e�F���@���^�[�E���[�x���g�E���b�n �y�L���X�g�z���B���w�����E�f�B�[�e�����A�}���[�E���[���]���A�O���i���E�g���l�X �y����z���l�����̐��I���z�Ǝ��i���炭��ϑz�C���[�W�B 1928.12.3�i���{����1929.5.22�j �w�}�b�^�[�z�[�� Der Kampf ums Matterhorn�x �}���I�E�{�i�[���A�k���c�B�I�E�}���\���}�ēA�V�i���I�F�A���m���g�E�t�@���N�i�J�[���E�w���[���̏����ɂ��j�A�B�e�F�[�b�v�E�A���K�C���[�A���B���[�E���B���^�[�V���^�C�� �y�L���X�g�z���C�X�E�g�����J�[�A�n���l�X�E�V���i�C�_�[�A�G�����X�g�E�y�[�^�[�[�� 1928.12.14 �w�l�ނ̐i�� Natur und Liebe�x �y����z�E�[�t�@�̕����f��ŁA�������̏�ʂƐl�ނ̒a���Ɣ��W�̑s��ȏ�ʂƂ������i�N���J�E�A�[S149�j |
|
| 1929 | |
| 1929 �w���\�\�����̊댯�ɒ��� Achtung, Liebe--Lebensgefahr�x �G���l�E���b�c�i�[�ē� �y����z�L�^�f��A�i�N���J�E�A�[201���j 1929 �w�t�̖ڊo�� Fruhlings Erwachen�x ���q�����g�E�I�Y���@���g�ē� 1929 �w��͂����̂��� Die Nacht gehört uns�x �J�[���E�t���[���q�ē� �y����z�N���J�E�A�[p216 1929 �w�x�������̎s�� Markt in Berlin�x ���B���t���[�g�E�o�b�Z�ēA����F�o�b�Z�f�� �y���炷���z�u��s�s�x�������ɂ́A�P�ɑ����e���|�Ɖ������x�z���Ă��邾���ł͂Ȃ��B�x����������̂����Ƃ��ɂ��₩�ȉc�݂̒��ɂ���A�q�̓I�ȏ��s�s���������Â��Ă���B���B�b�e���x���N�L��̏T�s�v�Ƃ����^�C�g���Ŏn�܂�B �@��i�͋���ۂ̃��B�b�e���x���N�L�ꂩ��n�܂�B���ꂩ���l�̐l�����o�ꂵ�A�e���g��X�^���h�̌��݂��n�܂�B���̒����炵���菇�����k���邽�߂ɁA�X�g�b�v���[�V�����E�J�������g�p�����B���䂪��t�ɕ��L��́A���C�Â��Ă���B���Ȕɉ؊X�̍L�ꂪ�A�^�C�g���Ɍ����ʂ�A�q�̓I�ȓc�ɒ��̕��͋C�ɕς��B �@�J�����͍L����߂���ƁX�ŁA�l�X���N���o����i�̕`�ʂɈڂ�B�Q��������J�b�g�A�Ό������ĕE���낤�Ƃ��Ă���j�A�V���b�^�[���オ��A�X���J�����B���̊����̊J�n�ł���B �@�s���n�܂�B�����肵�����̎p���J�������ǂ��B�����̉���A���߂��ĂԂ牺����ꂽ�j���g����A�������܂܂̃j���g���A������̏�ɍڂ��Ă���B�J�����͎��X�ɉ���𑨂��Ă����B�l���Ă����w�����A�������肵���s��̏������A�~�܂��Ă�����̔n�ԁA��l�̎�ɒ͂܂�����A�V�肵�Ă���q������A�����̎R�A�\�[�Z�[�W���Ă���j�A�s��̏�i�����ɐF�ʖL���ɉf���o�����B �ԁX�̓W���B�Ԃ͎s��̏d�v�ȓ_�i�ł���B�Ԃ��������V�k�����A�Ⴂ�����Ԃ��B�̂炭��ƁA���邢�̓Z�J�Z�J�ƒʍs�l����t�ɋl�܂��������������������ĉ�������B�������i������ꂽ�Ă�܂��A�^�N�V�[�惊��܂Ŏs��̕�����Ɏ��Q�����鏗�A�d�Ԃ̏�鏗�A����邨����B�s��͍�������ł���B �@�₪�Ďs��͏I���ɋ߂Â��B���������悤�ɎG���������܂�A�ՎU�Ƃ��Ă���B��̎��Еt�����n�܂�A���������đ|�������n�߂�B���悯��������ŁA��������O���B�����ăJ�����͎T���U�炳�ꂽ�������ʂ��B���݂��������ďE���W�߂������A�܂ɓ���Ď�������V�k�B�L��͍Ăь��̎p�ɂ�����B���|�l�����݂�|���W�߂āA�Ԃɍڂ���B�����T���ĊX�H�̐��|���n�܂�B�f��͂��ꂢ�ɂȂ����ΏA����Ɋ����Ă����N���[�Y�A�b�v�ŏI���B�L��̖q�̓I��i�͏���������B �y����z���̃T�C�����g�f��́A�x�����������̒��S�u���B���w�����c��L�O����v���牄�т�ɉ؊X�A�^�E�G���c�B�[���X�̏I�_�ɂ��邱�̍L��ŁA�T���J�����u�s�v�̖͗l���B�e�����h�L�������^���[�f��ł���B �@����ȏ�ł�����ȉ��ł��Ȃ��B���̉Ȕ����Ȃ��A����Ή��̕ϓN���Ȃ����̉f�悪�A�f��j��̃��A���Y�����Ƃ̊֘A�ŁA���ʂȈʒu��^�����Ă���̂́A���̎����̃h�C�c�Ńh�L�������^���[�f��̐V���ʂ��J����A���̉f����܂��ɂ����������̂Ƃ��āA����߂ĐV�N�Ȉ�ۂ�^��������ł���B �@��s��̐������h�L�������^���[�E�V���b�g�̑g�ݍ��킹�ŕ`���o���A�����̂�����u���f�ʉf��v�́A���V�A�̃W�K�E���F���g�t���w���ꂪ���V�A���x�Ŏn�߂��A�V�����h�L�������^���[�̎�@�Ɏh������Ďn�܂������̂������B�u���W���A�I��@��r���āA�u���̏�łƂ炦���v�v�f�����ō\���������F���g�t�́u�f���v�Ƃ�����@�́A�h�C�c�ł̓��@���^�[�E���b�g�}���ɂ���āA�h�C�c�̐V���������ł���u��s�s�v�̊X�����i�𑨂����@�Ƃ��ĉ��p���ꂽ�B�v���ɂ���ďo�������V�����v�����^���A�Љ�Ƒ����郔�F���g�t�̎p���ƁA�T�����[�}�����ԑw�̔��ɂ���ďo��������s�s��O�Љ�𑨂��郋�b�g�}���̎p���Ƃ̈Ⴂ�́A���҂�����������V���������̈Ⴂ�ɁA���m�ɑΉ����Ă���B�w�x�������̎s��x�́A���b�g�}���̃h�L�������^���[�Ɍ�����u�\���v��r���āA���B�b�e���x���N�L��Ƃ���������̏ꏊ�̎��ԓI���ڂ��A���̒��߂��Ȃ��ɓW�J���Ă���_�ŁA�����̌|�p�X���������u�V������`�v�I�ԓx���A�X�ɓO�ꂳ���Ă���B�w�f���[�j�b�V���ȃX�N���[���x�̒��҃��b�e�E�A�C�X�i�[�́A������]���Ă���B �u���B���t���[�g�E�o�b�Z�́w���B�b�e���x���N�L��̎s��x�ɂ́A�V�����q�ώ�`�����������Ԃ����Ƃ���Ȃ��ɕ\������Ă���B���b�g�}���́w���с[��s������y�x�ɂ����āA�����̃C���v���b�V�����̂��߂ɁA���܂��܂Ȉ�ۂ̉Q���������A�����y�I�ȉ��n����ۗ������邽�߂̃V���{����K�v�Ƃ������A�o�b�Z�͂����������b�g�}�����̃J�����g���b�N�Ȃǂ́A�S�R�K�v�Ƃ��Ȃ��B�o�b�Z�̉f���͑��̊Ԃ̂��́A���������ɂ��邱�Ƃ̋��R����`���B�����ł͉���Ƃ��ĉ��߂͂��ꂸ�A����Ƃ��ĊG��I�ɕ`����Ă͂��Ȃ��B����͑�ϋH�ȕ\���ł���v�B �@�͂�15���̒Z�҂ł͂��邪�A1920�N��̂����Ƃ���ې[�������L�^�f��̈�ł���B 1929 �w�l���͂����̔@�� So ist das Leben�x �J�[���E�����O�n���X Carl Junghans�ēA�V�i���I�F�J�[���E�����O�n���X�A���u�F�G�����X�g�E�}�C���@�[�X �y�L���X�g�z���F�[���E�o���m�t�X�J���A�e�I�h�[���E�s�V���`�F�N�A�}�[�j���E�c�F�j�Z�N���s�V���`�F�N�A�n�C�����q�E�v���n�^�A�G�f�B�b�g�E���[�f���[�A�E�[���E�g���f���X�J���A���@���X�J�E�Q���g�� �y���炷���z�v���n�̒��̕n���X�ɁA��l�̐�����]�I�Ȑ����𑗂��Ă���B���������̗אl�����̐����������悤�Ȃ��̂ł���B�������̍����A�������̂���ԑ厖�Ȃ��Ƃł���B��������ƒj�����͈�����Ŏ������ށB�ΒY���̂Ƃ���ɋ߂Ă���ޏ��̕v�́A�����̂��Ƃ����A�y�j���ɂ͂����T�̉҂������݂Ԃ��Ă��܂��B�ޏ��̖��̓}�j�L���A�t�����ĉ҂��ł��邪�A�ƂĂ���炵�̑����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����Ŕޏ��͉����ނ̐��Ƃ��āA������͂��̉҂��ŁA���Ƃ��Ƒ���{���Ă������Ƌ�J���Ă���B�������v�̋������ɁA���x�̏�Ȃ��ߊ쌀���J��Ԃ��ꂽ�̂��A�ޏ��͔��Ď��悤�ɐQ�Ă��܂��B �@������Γ��j���A�����ޏ��͑��̐l�X�̂悤�ɁA�͔ȂŊy�����V��A�x�肵�Ă���킯�ɂ͂����Ȃ��B���𑐌��ɍL���Ċ������Ȃ���A�����̋x�݂����̂��B�ޏ��̊�ɕ����ق��Ƃ��������A�}�ȉJ�͗l�ɍQ�ĂĐ���������鑛���ɁA�����܂��܂��Ă��܂��B�����ăv���n�̗L���ȃJ���������A������������Ȃ���A������ꂽ�Ԃ������čs���ޏ��̎p�́A���D�ɖ����Ă���B �@������Έ�����̒���ɂƂ��ẮA�u��������ł����邢���j���A�Ӗ��͈����̎n�܂�v�ł���B�ΒY���̓X�ł́A�l�v���ΒY���X�R�b�v�ł����グ�Ă���B��������x�݂������ޏ��̕v�́A�ꐶ��������ɐ����o���ޏ���K�ڂɁA���C�Œx������B�����Ďd�������邳���Ď�����e���ɐΒY���Ԃ���������B�����Č��ǃN�r�ɂȂ��Ă��܂��B�������ނ͉҂������͂����݂�Ȏ����̈��ݑ�Ə��Ɏg���Ă���̂ŁA���[�̐��͕v���N�r�ɂȂ������ƂɋC�Â��Ȃ��B�Ԃ̈������ƂɁA�}�j�L���A�t�̖����A�}�j�L���A�����ɗ��Ďv�킹�Ԃ�ȐU�镑��������v���C�{�[�C�ǂ��̍s�����䖝���悤�Ƃ��Ȃ��������߂ɁA���e�Ɠ��l�N�r�ɂȂ��Ă��܂����̂������B���₷�ׂĂ̏d�ׂ��A���[�̐��̌��ɂ̂��������Ă����B �@�����Ĕޏ��͖Z�����̂��܂�A�����̒a�������������ƂȂǁA�v���o�������Ȃ��B�������ߏ��̐l�����̂ق����A������悭�m���Ă����B�傢�ɂ��ĂȂ��Ă��炤����ł����̂��B�Ƃ��낪�ޏ������ĂȂ��̏����ɒǂ��Ă��邷���ɁA�����������͍��z��{���o���āA�ޏ���������̂��߂Ɏ���Ă����������������˂āA������ɏo�|���čs���A���d���Ƃ�������Ȃ���A�L����������������ł��܂��B�����Ƃ͒m��Ȃ��ޏ��́A�ł�����荋�Ƀe�[�u�����ƂƂ̂��A�ߏ��̐l�������Ă�ŏj�����J�����B�j���̉̂����ޏ��̊�ɂ́A�܂������ԁB�u�^����͎������K���Ȃ�v�B�v���Ԃ�Ƀ_���X������ޏ��̊�́A���������̐l���̊�тɋP���B���������������̂ق����A����ŏ�������ėx���Ă���B�����Đ����ς���āA��r����{�Ԃ牺���ċA���ė���B�͂��ƋC�Â����ޏ��́A�}���ʼnB���Ă��������z�����o���Ă݂�B�����ċ��������Ȃ��Ă���̂�m���āA���������ޏ��̈���Ȏp�B �@�����u���ڂɂ�����ځv�ł���B�����A�䏊�Ŏ�r��T���o���Ĉ���ł������ɁA�A���Ă����ޏ��͐��ɐH���Ă�����B����ƒ���͋t�サ�āA�M�����X�ɏ��ɒ@�����āA���킵�n�߂�B�����Ԋ����E��ł����ޏ��́A���ɓ{��������A��r��U�肩�����ĕv�ɔ���A�Ƃ��Ƃ��v��ǂ��o���Ă��܂��B�ނ͂ӂĂ�����āA���̂Ƃ���֍s���Ă��܂��B�ޏ��͖���������߂ċ����B �@�u�_�͈�����҂����炵�߂�v�B����ɐ����o���Ă���ޏ��̕����ցA�ׂ̏����Ȏq��������ė��āA�f�V�т����Ă��邤���ɁA�����痎�������ɂȂ�B����������悤�Ƃ����ޏ��́A�M������ꂽ�傫�Ȑ����A����ĂĂЂ�����Ԃ��A��Ώ������Ă��܂��B���ѐ������ߏ��̐l�����������ɗ��āA�ޏ���Q���ɉ^�ԁB�����ď��ƈꏏ�ɐQ�Ă����ޏ��̕v��T���āA�A��߂��B��҂���������A�����������͂���Ǝ��̏��̍ȂɊ��Y���B�������X�ŕa���Ă����ʂł���B����������������鎞�v�̊[�����A���̎���������B�v�͂������Ȃ̖ڂ���Ă�邱�Ƃ��o���������ł���B �@�u�K���Ȃ邩�ȕn�����ҁA�V���͂��̐l�̂��̂Ȃ�v�B�l�X�͍s�������Ė����ɍs���B�_���̂��o�A�������ɉ��낳��A�v���y��������B���ׂČ^�ʂ�ł���B�������ς�A�Q��҂͕n���X�̈�����ɍs���āA�R�[�q�[�Ƃ��َq�ŁA���V�̉����J���B���߂ė܂ɕ���V�k�̊�ɂ́A�ߘJ�ƐS�J�����ݍ��܂�Ă���B���̎��̌������A�����������̂����ł��Ȃ���A���l�̎q�����h���Ă��܂������̂����ł��A�M���̂����ł��Ȃ��B�{���̌����͔ޏ��̐l�����̂��̂������B�����x�[�g�[�x���̑����s�i�Ȃ��s�A�m�őt�ł��钆���A�x�������ς܂��ė��������čs���Q��̗אl�����́A���S���l�Ƃ��������̎��҂̈�l�ł���ޏ������A�u�p�Y�v�̑����ɂӂ��킵���������Ƃ������Ă����B �y����z�g�[�L�[����ɏ��x��āA�v���n�ŕ����A�悤�₭�x�������Ō��J���ꂽ���� �T�C�����g�f��́A�`�F�R�̒��ł��h�C�c�l���Z�҂����������Y�f�[�e���n���o�g�̃J�[���E�����O�n���X�ē����삵���A�h�C�c�E�`�F�R����f��ŁA�v���n�̕n���X��Ƃ��Ă���B�����̃h�C�c�̃W���[�i���X�g�����������O�n���X�́A���̐��̔ߌ����f�扻���悤�Ƃ����}�ɁA�h�C�c�ł͉��̎x���������Ȃ������B�������ނ̊�ĂɁA�L���ȃ`�F�R�̔o�D�e�I�h���E�r�V���`�F�N���S�������A�ނ̂��߂ɂS���}���N�B���Ă��ꂽ�B�������ĂP�X�Q�O�N��v���n�̘J���ҊK���̐������A�����Ƃ����A���ɕ`�����f�悪�a�������B�����O�n���X���P�X�Q�T�N�ɃV�i���I�������グ�����ɂ́A����͖{���̓h�C�c�̃h���X�f���ɐݒ肳��Ă����̂�����A���䂪�v���n�Ɉڂ����̂́A�܂������r�V���`�F�N�̗U���ɉ��������ʂł���B �@�����O�n���X�̓`����Ƃ���ł́A�ŏ��u�v�����g�C�X�f��v�Ђ��S���}���N�o�����ƂɂȂ��Ă������A���̍ۊK�������I�ȃX���[�K����t�����u�m��I�v�Ȍ����ɂ��邱�Ƃ���]���A�ނ���������ނƃL�����Z�����Ă��܂����B�u�K�������ɂƂ��ĐϋɓI�Ȍ����v�Ƃ����̂́A�����̍����̌Œ�ϔO�������B�L�����Z�����ꂽ�������ł��̉f��́A�������Ă��������Ԃ����Ƃ���̂Ȃ����A���Y���ŁA�[��������^���Ă����B�����ɕ`���o���ꂽ���퐶���́A���I�ɔ�������Ă����Ȃ����A�A�W�e�[�V�����p�Ɉ��p����Ă����Ȃ��B �@�o���o�D�́A�r�V���`�F�N������V�ŏo�������̂ɂȂ�����B����̃��F���E�o���m�t�X�J���́A�v�h�t�L���́w��x�i1926�j�̎�����������o�D�ł���B�B�e�͂P�X�Q�X�N�ɁA���T�ԂŊ������Ă����B�������z���Ǝ҂�������Ȃ������B�E�[�t�@�f��Ђ�����ƈ����āA1930�N5���ɂ���ƌ��J���ꂽ���ɂ́A�����g�[�L�[���オ�n�܂��Ă����B�ϋq�̓T�C�����g�f��ɂ͊S���������A���̉f��͂��̋]���ƂȂ��āA�قƂ�ǒm���Ȃ��܂܂ɂȂ��Ă��܂����B���̈Ӗ��ł��̉f��́A�`�F�R�E�T�C�����g�f��̔����̉̂������B�����ɂ���̓v���n�̃v���_�N�V�����́A�|�p�I���n���ؖ�������̂������B�܂�1920�N�㖖�̃h�C�c�f��̌X���A�x������������̉�ƃc�B���ɂ��Ȃu�c�B���f��v�Ƃ́A���ڂȊW���ǂݎ�邱�Ƃ��ł���B�������䂪�`�F�R�̃v���n�Ɉڂ��ꂽ���߂ɁA�����O�n���X���Ō�Ɏc����120���[�g���̃t�B�������g���āA�͂�3���ԂŎB�����v���n�̕n���X�̃��P�[�V�����́A�����̊ϋq�ɁA1920�N��v���n�̊X�́A�Ɠ��̃��[�J���E�J���[��X�������͋C��`���Ă���Ă���B �@�f��̃N���C�}�b�N�X�́A���̒a�����̏j���̏�ʂƁA�����̍ς�̕n������H�̏�ʂł���B�a�����̏j���Ƃ������������̍K�����A�������Ď�l���̐����̕n�������A�����̉��ɖ\�I����B�ɂ�������炸�p���m�t�X�J������������̎p�́A�Â��ȕi�ʂ�X���Ă���B�p���m�t�X�J�̂����ꂽ���Z�̗͂ł���B���������b�e�E�A�C�X�i�[�́w��x�ł̉��Z�قǂɂ͔����Ă��Ȃ��B�ޏ��́u�V�`���G�[�V���������܂�ɊG��I�ł���B�l���͐�ɂ����̔@���ł͂Ȃ��v�ƁA�ے�I�ɕ]�����Ă���B �@�J�[���E�����O�n���X�͂��̉f��ȊO�ɂ́A�d�v�ȍ�i�͉������Ȃ������B�����ăi�`����ɃA�����J�ɖS�������B1964�N�ɔނ́A���̉f��̃T�E���h�ł���������A���y�Ɖ����������ꂽ�����ł���B 1929.1���͂��� ���V�A�f��w�A�W�A�̗� Potomak Tchings-Khan�x �y����z���V�A�̃v�h�t�L���ēo�Ȃ̉��ŁA�x�������ŏ�f�B 1929.1.7 �w���l�A����ɃL�b�X�� Ihre Hand,Madame�x ���[�x���g�E�����g�ēA �y����z�n���[�E���[�g�P�̃t�@�������f��A�x�������́u�^�E�G���c�B�[���p���X�g�v�ŕ���B�q�b�g�Ȃč��ە��f��B�i�u�x�������R�v��113�j 1929.1.18 �w��O�w�N���̐킢 Der Kampf der Tertia�x �y����z���q�̔L��߂炦�ĊF�E���ɂ���̂�W�Q���悤��Ă��w�Z���Ԃ̏��N�����́A�z���[���X�I�ȋ~���푈��`������i�ŁA�����ɂ͎v�t���̏�ɑ��镨�킩��̂悢������������Ă���B�����L���E���X�̏��N�����������āA��Җ�������ɂ����B�i�r�E�N���J�E�A�[s159�j 1929.2.9�i���{����1930.2.13�j �w�p���h���̔� Die Büchse der Pandora�x �Q�I���N�E���B���w�����E�p�v�X�g�ēA�V�i���I�F���f�B�X���t�E�E�@�C�_�i�t�����N�E���F�[�f�L���g�̋Y�ȁw�n��x�i1895�j�Ɓw�p���h���̔��x�i1929�j�ɂ��A�B�e�F�O���^�[�E�N�����v́A���u�F�A���h���C�E�A���h���C�G�t�A�S�b�g���[�v�E�w�b�V���A����F�l���f�� �y�L���X�g�z���C�[�Y�E�u���b�N�X�i�����j�A�t���b�c�E�R���g�i�[�i�V�F�[�����m�j�A�t�����c�E���[�f���[�i�A�����@�E�V�F�[���j�A�J�[���E�Q�b�cGoetz�i�V�S���q�j�A�A���X�E���x�[���i�Q�V�����B�b�c���ݕv�l�j�A�N���t�g�E���b�V���i���h���S�E�N���@�X�g�j�A�O�X�^�t�E�f�B�[�[��Gustav Diesel�i��W���b�N�j�A�f�[�W�B�E�h�[���i�V�F�[�����m�̍���ҁj�A�~�q���G���E�t�H���E�l�t�����X�L�[�i�J�X�e�B�[�s�A�[�j��݁j�A�W�[�N�t���[�g�E�A���m �y���炷���z�q���C���̃����͐��܂ꂽ�ꏊ���f�����s���́A��σZ�N�V�[�ł͂��邪�A�j�B���݂Ȕj�ł����閂���̏��ł���B���͐V���Ў�ŁA���郌�����[����̋����o���҂̃V�F�[�����m���A�ޏ������l�ɂ��Ă���B�ޏ��͂���G���K���g�ȃA�p�[�g�ɏZ��ł��邪�A�W���l�ɋ����Ă���Ƃ���ցA���Ă̗{���V�S���q���K�˂Ă���B�ނ̓��������S����������A�ޏ��̕ی�҂ł���A�t���������B�ޏ��͔ނ��ɓ���A�ĉ���y���ށB�V�S���q�͔ޏ����V�F�[���̈��l�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A���₩�ɔ��A�V���[�K�[���������̂ɖ߂�悤�ɂƒ�������B�����Ă���ɂ͂��傤�Ǘǂ��p�[�g�i�[������A�������̒ʂ�ő҂��Ă���Ƃ����B���̗͎����̒j���h���S�́A�u��|����ȃ��@���C�G�e�B�E�V���[�ŁA�ޏ��ƈꏏ�ɃX�e�[�W�ɗ����Ƃ���]���Ă���v�̂ł���B �@�Ƃ��낪�����֎v���������V�F�[����������K�˂Ă���B�V�S���q�͎p���B���B�V�F�[���̓����ɁA�����͓�����b�̖��ƍ����Ƒł������A�ʂ�b�������o���B�����������͏��m�����A���߂Ĕނ�U�f����B�V�F�[�����o�Ă����ƃV�S���q�́A�ʂ�ő҂��Ă��郍�h���S�ɁA�オ���Ă���悤�ɂƌ����B���h���S�̓����ɁA�������ǂ�Ȃɋ������������B�����͏��Ȃ���ނ̋ؓ��̗͂��^������B �@����V�F�[���̉Ƃł͑��q����ȉƂ̃A�����@�ƁA�R�X�`���[���E�f�U�C�i�[�̎Ⴂ���ݕv�l�Q�V�����B�b�c���A�V�����������[�����d�������Ă���B����ƃ���������Ă��āA���h���S�ƈꏏ�Ƀ��@���C�G�e�B�E�V���[�ɏo������̂��ƁA�ւ炵���ɘb���B���̍ۃ������A�����@�ɓ��ʂɍ���ȍD�ӂ������ƁA���̃V�F�[�����m�ƃ����Ƀ��X�r�A���I�Ȉ��������Ă��锌�ݕv�l�Ƃ��A���i����B�������s���Ă��܂��ƁB�A�����@�͕��ɁA�Ȃ��ދ��ȑ�b�̖��̑���ɁA�����ƌ������Ȃ��̂��Ɛq�˂�B�V�F�[���͑��q�Ɂu�j�͂���ȏ��Ƃ͌������Ȃ��B����͎��E�s�ׂ��v�Ɠ�����B�ނ̓A�����@�ɁA�����Ɗւ��Ȃƌx������B�����ă��������h���S�ƈꏏ�ɏo������v���b���ƁA�V�F�[���̓A�����@�ƃQ�V�����B�b�c������Ă���V�����������[�ɁA��l�ŏo��悤�Ɋ��߂�B �@�������[�̏����̎��A�V�F�[���͕��䗠�ŁA�ނ̌���̃����o�[�������̎Ⴂ����҂ɏЉ��B�����͂�������J���Ɗ����āA����ɏo�邱�Ƃ����ށB�y���ŃV�F�[���́A�����̍l����ς������悤�Ƃ���B�����͂��̋@��𗘗p���Ĕނ�U�f����B�����փV�F�[���̍���҂�����ė���B�����͌ւ炵���ɕ���ɏo�āA����҂͎S�߂ȋC�����ł����ۂ������B��b�̖��Ƃ̌����͂��j�Z�ɂȂ�A���̑���ɃV�F�[���̓����ƌ������鑼�͂Ȃ��Ȃ�B �@�������̃��Z�v�V�����ł̈�ԗz�C�ȋq�́A�V�S���q�ƃ��h���S�ł���B����������������Ƃ����āA�����͒�i�ɂȂ�����͂��Ȃ��B�ޏ��̓Q�V�����B�b�c���ݕv�l�Ƒ�ϐe���ɗx���Ă݂���B�V�F�[���Ƃ��q�B�͕��S����B��x�������ς�����V�S���q�ƃ��h���S�������ƈꏏ�ɐV���̃x�b�h���Ԃŏ����Ă���Ƃ���ցA�A�����@������Ă���B�����Ĕނ��ޏ��̗��ƂȂ�B�V�F�[�����Q���ɓ����Ă������ɂ��傤�ǁA�A�����@�������Ɉ����������悤�Ƃ��Ă����B�V�F�[���̓V�S���q�ƃ��h���S�Ƀs�X�g����˂����āA�Ƃ���ǂ��o���B�Q���ɋA���Ă݂�ƁA���荞�A�����@�̓����������G�ɍڂ��Ă���B�A�����@���s���Ă��܂�����ŁA�V�F�[���̓����Ƀs�X�g����n���A���E�����v����B�����āu���O�͂�����l�ԂɁA�Ђ��������炳�Ȃ��v�A���z���s�����ƌ����B�����ɂȂ�A�����́u����ł��܂��A���ꂪ��������l���~���B��̓���v�ƁA�V�F�[���Ɍ������ăs�X�g���˂���B�V�F�[���̓����ɂ����݂����A��������ē|���B�����ĉ������A�����@�ɁA�u�C��t����A���͂��O�����v�Ƌ���ŁA���ʁB �@�����͖@��Ɉ����o�����B�����V�S���q��A�����@�́A�ޏ��������B�����āu���̕s�K�ȏ����͐l�E���ł͂���܂���B�ޏ��͌����Ȃ̂ł�����A�ߕ�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���v�ƌ����B����ɑ��Č����́u�M���V���̐_�X�͏����[�[�p���h�������܂����B�ޏ��͔������A�h���I�ł����B�������_�X�͔ޏ��ɁA���̐��̂����鈫�����߂�������^���܂����B���̕s���ӂȏ���������J���A�Ж�����ɏP�����������̂ł��B���͎��Y�����Y���܂��v�ƌ����B�����������͔ޏ��̖��͂ōٔ����⌟�������f�킵�A�����͎E�l�߂łT�N�̒����Ƃ������ƂɂȂ�B �@������������Ă���ԂɁA�����̗F�l�B�͉Е�m�@��炷�B�����č����ɕ���āA������E�o������B�A�����@�A�V�S���q�A���h���S�����ăQ�V�����B�b�c�́A�ޏ��ƈꏏ�Ƀp���ɓ�����B�����r���D�Ԃ̒��ŁA�Ђ��ŏ��������Ǝ҃J�X�e�B�E�s�A�[�j��݂��A�ނ�̎ʐ^����̐V���L������A�ނ�̐��̂�\���B�ނ̓A�����@�ɍ��Y�̑啔��������āA���ق������Ȃ킹��B�����Ĕނ̓�����s���A����`���́A�q����ɉ������ꂽ�D�ɘA��Ă����B�����ł��Г�d�Ȃ�B�A�����@�͂������ܓq���ŕ߂܂�B�����̓��h���S�ɔ����A��p�i�Ƃ��ăQ�V�����B�b�c��ނɂ䂾�˂�B�������Q�V�����B�b�c�͔ނɐg��C���悤�Ƃ͂����A�ނ��E���Ă��܂��B�J�X�e�B=�s���[�j�̓������A�G�W�v�g�̃J�t�F�̏��L�҂Ƀ_���T�[�Ƃ��Ĕ������B�������̑����́A�x�@���q���D�Ɏ������������ƂŏI����������B�j�����Ĕ��X�̑̂œ����o���������́A�V�S���q�A�A�����@�Ƌ��ɁA�{�[�g�Ń����h���ɍ���т���B �@�����h���ł̐����́A�����Ԃ�ĉ����������ŕ�炷�S�߂Ȑ����ł���B�����ăp���������Ȃ��قNj������������́A���ɐg��B�N���X�}�X�̖�ޏ��͊X�p�ɗ��B�����ɂ͋~���R���n�����l�X�̂��߂ɐ��b�����Ă���B�����āu�����h���̏����ւ̒��Ӂv�Ƃ����f�����o�Ă���B�u�Ⴂ�������l�l�E����Ă���̂ŁA�w���q�͂��ׂāA�ی�Ȃ��ɖ�͊O�o���Ȃ��悤���ӂ��ꂽ���v�B�����֖��̒�����J�T�Ȓj�̎p�������B�~���R�̏������ނɁA�N���X�}�X�̃��h���M�̎}��^����B�ނ͔��t�w���E���đS�g�����A����������W���b�N�������B�q��{���Ă��������́A�ނ̎������ĉƂɘA�ꍞ�ށB�u���͂Ȃ��v�ƌ������ɂ�������炸�A�ޏ��́u�C�ɓ���������v�ƁA�ނ�U�����̂ł���B�����̒��œ�l�͕��i����B����ƃW���b�N�̖ڂ́A�e�[�u���̏�̔R���Ă���X�C�̑��ɂ���i�C�t��������B�W���b�N�̕\��ς��A�i�C�t������ă������h���B�~���R���N���X�}�X�̉̂��̂��Ȃ���A��̖��̒����s�i���čs���B�W���b�N�͈Èł̒��Ɏp�������B�����ċ~���R�̍s�i���������Ă���l�g�̒��ŁA�A�����@�������鋃���Ă���B �y����z�i�q���C���ɕ��������C�[�Y�E�u���b�N�X�̊�ՂƂ��Ēm���Ă���j�B �@���̉f��̊�b�ƂȂ��Ă���̂́A�t�����N�E���F�[�f�L���g�̃h���}�w�n��x�Ɓw�p���h���̔��x�ł���B���������ۂɂ͂���́A�p�v�X�g�ɂ���āA�f�����̂��̂͂���߂ė⍓�ȃ��A���Y���ł͂��邪�A�S�̂Ƃ��Ă͍r�����m�Ȉُ�ȍ�i�ɍ��ւ����Ă���B�X�N���[����ɂ͌����Ɍv�Z���ꂽ���Y���ŁA�V�S���q�A�V�F�[�����m�A�Q�V�����B�b�c���ݕv�l�̊炪�J��Ԃ�����A���̊ԂɃ����̔M�a�̂悤�Ȑ������f���o�����B �@�p�v�X�g�͂���߂ē��قȃ��A���Y���f��̊ēł���B�w��тȂ��X�x�i1925�j�A�w�������̔b���[�W�����k�E�l�C�̗��x�i1927�j�ɂ����ẮA�ꉞ�܂��Љ�h�I���A���Y���̘g���ێ�����Ă������A�P�X�Q�X�N�́w�p���h���̔��x�Ɓw�ϊy�̏��̓��L�x�Ɏ����āA�͂�����Ɣނ̃��A���Y���̓����ł���A�ُ�ȃZ�b�N�X�̘c�݂̖\�I�ɑ������B���̂����̋����̂��߂ɍ����Ɏ���܂ŁA�^�ۗ��_�ɂ킩�ꂽ�]�����Ȃ���Ă���B���������b�e�E�A�C�X�i�[�́w�p���h���̔��x���A�p�v�X�g�̉f�搻��̒��_�ł���Ƃ��āA�قƂ�Ǖs��������������قǂɖL���ɕω�����A���̍�i�̕��͋C���w�E���Ă���B �@�����Ă����������قȉf�����\�ɂ����̂��A�q���C���ɕ������A�����J���D���C�[�Y�E�u���b�N�X�̕s�C���Ȃ܂łɔ����ȉA�e�̗^�����ۂł���B���蓖���̊ϋq�́A��������Z�͂̕s���Ƃ������Ȃ��������A�����̉f�揗�D�ɉ߂��Ȃ������u���b�N�X����A�u���C�[�Y�E�u���b�N�X�̊�Ձv�ƌĂ��s�v�c�Ȗ��������o�����Ƃ���ɁA�p�v�X�g�̃p�v�X�g����䂦�������B �@���łȂ��炱�̉f��́A�u�l���f��v��Ђ�������l�[�x���c�@�[�������삵���Ō�̃T�C�����g�f�悾�����B�g�[�L�[����ɓ������u�l���f��v�Ђ͉���������}���邪�A�w�p���h���̔��x�̂悤�ȉf��͂������Ȃ������B �y�ē����z1887�N�ɃI�[�X�g���A�ɐ��܂�A�͂��߂͕���o�D�����o�ƂƂ��āA���[���b�p�ƃA�����J������Ă����B��ꎟ���E����x�������ɏo�āA�f��ɓ]���A1923�N�A���F���i�[�E�N���E�X�剉�̉f��w����x��������B�������ނ����ȃ��A���Y���̉f���ƃ����h���}�������˔��������قȃX�^�C�����m������̂́A�w��тȂ��X�x�i1925�j����ł���B���̃X�^�C���́w�������̔b���x�ɂ����Ċ������A�Ȍ�w�p���h���̔��x�A�w�d���̏��̓��L�x�ُ̈�Ȗ\�I�f��A�w�S�̕s�v�c�x�i1927�j�̐��I���_���͉f��A�w�������1918�N�x�i1930�j�̍r�������ꕗ�i�̏Ռ��I����f��A�����h���}�I�X���Ɩ\�I�I�X���̌�������w�O���I�y���x�i1931�j�A�F���̕��a��`���̂��グ���w�Y�B�x�i1931�j�ƁA����߂đ��ʂȌ�����c�����B �@������1932�N�ɂ́A�������������I���g�����]���āA������`�I�ȁw�A�g�����e�B�[�h�x�����A�i�`����Ƀt�����X�A�A�����J�ɓ���Ă���͖}�삵�����Ȃ������B������1939�N�Ƀ��B�[���Ɉڂ�A�w�쌀���ҁx�i1941�j�A�w�p���P���X�X�x�i1943�j�A�w���[�x���g�E�R�b�z�x�i1939�j�Ȃǂ�������B����E����̓��_���l���Q���������w�R���x�i1948�j�ɂ���āA���F�j�X�f��ՍŗD�G�ē܂��B 1929.2.14 �w������r Das lebende Leichnam�x �g���X�g�C����A�t���H�[�h���E�I�c�F�b�v�ē� 1929.2.16 �w�ܔM�̐S Das Brennende Herz�x ���[�g���B�q�E�x���K�[�ē� �y����z�x�������̉f��فu�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H �[�v�ŕ���B 1929.3.7 �w�ߏ�G���[ Fräulein Else�x �A���g�D�[���E�V���j�b�c���[����A�p�E���E�c�B���i�[�ēA�V�i���I�F�p�E���E�c�B���i�[�i�A���g�D�[���E�V���j�b�c���[�̏����ɂ��j�A�B�e�F�J�[���E�t���C���g �y�L���X�g�z�G���[�U�x�g�E�x���N�i�[�A�A���x���g�E�o�b�T�[�}���A�A���x���g�E�V���^�C�������b�N �y����z���̕��������悤�Ƃ��āA���̂��߂ɔj�ł�����������̔ߌ��B 1929.3.11�i���{����1930.1.25�j �w�A�X�t�@���g Asphalt�x �W���[�E�}�C�ē� �y�L���X�g�zGustav Frohlich�ABetty Amann �y����z�x������ΓD�_�̏��ɗU�f����A�E�l�̌��^����B�����h���}�Ƃ��Ă̒ʑ������B�A�X�t�@���g�̕ܓ������S���`�[�t�ƂȂ����V�����X�H�f��B 1929.3.12�i���{����1931.3.13�j �w���E�̃����f�B�[ Melodie der Welt�x ���@���^�[�E���b�g�}���ē� �y����z�h�C�c�ŏ��̒��҃g�[�L�[�f��B�����y�Ƃ��Ă̑D���B 1929.3.15 �w���@���f���u���N�̋Q�� Hunger in Waldenburg�x �s�[���E���b�c�B�ēA�V�i���I�F���I�E���[�j�A�i�z�����X�E�c�B���}�[�}���Ɩ����̒j���̘J���҂����̊֗^�j �y����z�E�H�v�Ȃ̑��q�����Ƃ��A���ɏo�Ă��K�������������Ȃ��ɂ��ẮA�h�L�������^���[�I���f��B 1929.4.3 �w�ł�����Polizeibericht Überfall�x �y����z�G���l�E���b�c�i�[�̒Z�҉f��A�f�挟�{���ŋ֎~�B���̗��R�́u�f���Ŕƍ߂̕\�������ȖړI�v�B�������ꂽ�V���̏��L���Ƃ��Č���B 1929.4.15�i���{����1930.9.17�j �w�j�[�i�E�y�g�����i Die wunderbare Lüge der Nina Petrowna�x �n���X�E�V�����@���c�ēA�V�i���I�F�n���X�E�N���[���A�B�e�F�J�[���E�z�t�}�� �y�L���X�g�z�u���M�b�e�E�w�����A�t�����c�E���[�f���[�A���@�����B�b�N�E���@���g �y����z�낤�������������Ǝ��ɏI��郁���h���}�B 1929.4.28 �w�Z�� Brüder�x ���F���i�[�E�z�b�z�}���ēA�V�i���I�F���F���i�[�E�z�b�z�}���A�B�e�F�O�X�^�t�E�x���K�[ �y�L���X�g�z�f�l�o�D�����B �y����z1896�N�̃n���u���N�ł̍`�p�J���҂̃X�g���C�L�ŁA��l�͘J���ҁA��l�͌x���Ƃ����Z�킪�G���镨��B 1929.4.28 �w����̏��� Die Frau�Anach der man sich sehnt�x �N���g�E�x�����n���g�ēA�V�i���I�F���f�B�X���t�E���C�_�i�}�b�N�X�E�u���[�g�̏����̃��e�B�[�t�ɂ��j�A�B�e�F�N���g�E�N�����g�A�n���X�E�V���C�v�A���u�F���[�x���g�E�l�p�b�n �y�L���X�g�z�}���[�l�E�f�B�[�g���q�A�t���b�c�E�R���g�i�[�A�E�[�m�E�w�j���O �y����z���f�I�ȏ������߂���S�����I�����h���}�f��B 1929.5�� ���{�f��w�\���H�x �ߊ}��V���ē� �y����z�x�������Łw���V�����̉e Im Schatten des Yoshiwara�x�̃^�C�g���Ō��J�B ���{�f�揉�̊C�O���J�B 1929.6.3 �w�V���M���O�E�t�[�� THE SINGING FOOL�x �y�L���X�g�z�A���E�W�����X�� �y����z�g�[�L�[����A�f��فu�O�����A�E�p���X�g�v�ŕ���B�u�T�j�[�E�{�[�C�̉́v�����́B�i�x�������Ap141�j 1929.8.30 �w�X�^���u�[���̎��l Strafling von Stanbul�x �O�X�^�t�E�E�`�b�L�ē� �y�L���X�g�z�n�C�����q�E�Q�I���Q�A�p�E���E�w���r�K�[�A���B���[�E�t�H���X�g�A�g���[�f�E�w�X�^�[�x���N �y����z�x�������̉f��فu�E�[�t�@�E�E�j���F���Y���v�ŕ��� 1929.9.13 �w�ɖk�̌Ăѐ� Der Ruf des Nordens�x ���C�X�E�g�����J�[�ē� �y����z�x�������̉f��فu�E�j���F���Y���v�ŕ���A�R�x�f��B 1929.10.8 �w�t�̂���߂� Fruhlingsrauschen�x ���B���w�����E�f�B�[�e�����ēE�剉 �y����z�x�������̉f��فu�e�B�^�j�A���p���X�g�v�ł̉f�敕��B 1929.10.10 �w�X�H�̌������� Jenseits der Strase�x ���I�E�~���[�ēA�V�i���I�F�����E�t�F�[�g�P�A���B���[�E�f���A�B�e�F�t���[�f���E�x�[�����O�����g �y�L���X�g�z���V�[�E�A���i�A�p�E���E���[�R�b�v�A�t���b�c�E�Q���V���[�A�W�[�N�t���[�g�E�A���m �y����z�`�̊��̒��ł̓��퐶���̔ߌ��B���Ɩ��������������̍�i�B�n���u���N�̒��̔��������P�B�e���܂ށB 1929.10.14�i���{����30.4.24�j �w�˗��̏��̓��LTagebuch einer Verlorenen�x �Q�I���N�E���B���w�����E�p�v�X�g�ēA�V�i���I�F���h���t�E���I���n���g�i�}���K���[�e�E�x�[���̏����w�˗��̏��̓��L�x�ɂ��j�A�B�e�F�[�b�v�E�A���K�C���[�A���u�F�G���l�E���b�c�i�[�A�G�~�[���E�n�X���[�A����F�p�v�X�g�f�� �y�L���X�g�z���C�[�Y�E�u���b�N�X Louise Brooks�i�e���[�~�A���j�A�A���h���E���A���k�i�I�X�h���t���݁j�A�t���b�c�E���X�v Fritz Rasp�i�}�C�l���g�F�U�f�ҁj�A�A���h���A�X�E�G���Q���}�� Andrews Engelmann�i����@���j�A���@���X�J�E�Q���g Valeska Gert�i����@���v�l�j�A���[�[�t�E�����F���X�L�[�i�w�j���O�j�A���F�[���E�p�������@�i�t���[�_����j�A�t�����c�B�X�J�E�L���c�i���[�^�j�A�A���m���g�E�R���t�i�V���݁j�A�G�f�B�b�g�E�}�C���n���g�i�G���J�j�A�W�[�N�t���[�g�E�A���m�[�i�q�j�A�N���g�E�Q�����i���B�^���X���m�j�A�W�r���E�V���~�b�c�i�G���[�U�x�g�F�Ɛ��w�j�A�l�E�J�T�X�J���A�V���y�[�f�B�E�V�����q�^�[�A�W�����B�A�E�g���t�A�G���}�E���B�[�_�A�~�q���G���E�t�H���E�l�t�����X�L�[�A���[���E�t�����g�A�n���X�E�J�X�p���E�X �y���炷���z����߂ɂȂ�����t�̃w�j���O�́A�Ɛ��w�̃G���[�U�x�g�����ق���B�����ޏ����A��Ǐ���̃}�C�l���g�ɗU�f���ꂽ����ł���B�|���m�t���̎��W�Ɉꐶ�����ɂȂ��Ă���}�C�l���g�́A16�ɂȂ��l�̖��e���[�~�A���Ɍ������B�ޏ��͎���ɂ���ɉ�����悤�ɂȂ�B �@���ăe���[�~�A���͌��M����邱�ƂɂȂ�B���̋V���́A���炩�Ƀw�j���O�ɔ��ȉe���͂������Ă���e�ʑS�����ɂ��₩�ɎQ�����āA�j���邱�ƂɂȂ�B���̎��e���[�~�A���͏f��̈�l����A���L���v���[���g�����B���L�͂₪�Ĕޏ��̈�ԑ�ȕƂȂ�B�ޏ��̐��q�҂ł���Ⴂ�I�X�h���t���݂́A�I�X�h���t�Ƃ̖�͓���̃��P�b�g���v���[���g����B�����₢�����j���̕��͋C�́A�G���[�U�x�g�̎��̂��^�э��܂ꂽ���߂ɁA�ˑR���f�����B���ق��ꂽ�Ɛ��w�͎��E�����̂ł���B�e���[�~�A�����������̎��E�ɜ��R�Ƃ��āA���_����B �@���̓��̗[���ޏ��́A����������������������}�C�l���g�ɍ��������āA�Ƃ��Ƃ��������������m����B�����ă}�C�l���g�͔ޏ���U�f����B���̌��ʔޏ��͔D�P���A�q�����ł���B���e�̃w�j���O�͂��̊ԂɐV�����Ɛ��w���ق��A�Ԃ��Ȃ��������邱�ƂɂȂ��Ă����B�e���[�~�A���̔D�P�ɋV�����e�ʂƃ��[�^�́A�w�j���O��������āA���܂ꂽ�q�������Y�w�ɂ������A�e���[�~�A���͋���@�ɓ���錈�S��������B �@����@�Ɏ��e���ꂽ���������́A�@���v�Ȃ̓|���I�ŃT�f�B�X�`�b�N�Ȃ��������Î����Ă���B�H���̂Ƃ���N���̂Ƃ��A�@���v�l�͓��t��@���Ďw������B���̃q�X�e���b�N�ȃe���|�ɍ��킹�āA���������͊�ȑ̑�����������B�e���[�~�A���͍ŏ�����A���̔�l�ԓI�Ȏx�z�ɔ��R����B�ޏ��͓����ꂵ�݂𖡂���Ă���G���J�ƒ��ǂ��ɂȂ�B�@���v�l������Ӌ����Q���ŁA�e���[�~�A���̓��L�����グ�悤�Ƃ������A�T�ς��Ă������������̓{�肪��������B�����̒��Ńe���[�~�A���ƃG���J�́A����@����E�����邱�Ƃɐ�������B �@�G���J�̓e���[�~�A���𐒔q���Ă���I�X�h���t���݂̂Ƃ���ɓ������ށB�e���[�~�A�������̐��q����T���ɍs���B�����q���������Ƃ�m��ƁA�ޏ��͂ق��Ƃ���B�e���[�~�A���ƃG���J�ƃI�X�h���t���݂́A����y���V�����ōĉ�邪�A�����͖{���͍������t�h�ł���B�ޏ��͗U�f����邪�A������ނ����ԁB�ŏ��͋q���������邱�Ƃ����ނ��A���ǔޏ��͂������C�ɓ����āA�₪�Č��Ƃ��v��Ȃ��Ȃ���������������B����������A�ޏ��̓i�C�g�N���u�ŁA�\�����Ȃ��ĉ������B���e�̃w�j���O�Ɣނ̐V�����ȃ��[�^�A�����ă}�C�l���g�����Ă����̂ł���B�ނ�͍���u�˗��̏��v�ƂȂ����ޏ����A�Ԗ��E�̒j���̐^�ɂ���p��������B���������������ւ������̒��ŁA���Ɩ��͈��A���邱�Ƃ��A���t�����킷���Ƃ������ɕʂ��B���̑��ɐ�]�������e�͎��ʁB��ǂ̓}�C�l���g�̂��̂ƂȂ�B���������Y�̑啔���́A�e���[�~�A���Ɉ�Y�Ƃ��Ďc�����B �@�ޏ��ɂ������������ƒm��ƁA�I�X�h���t���݂͍Ăуe���[�~�A���ɋ����������B�������e�̖�ǂ�K�˂��e���[�~�A���́A���[�^�Ɣޏ��̓�l�̎q�����A�w�j���O�̎�������u�ŁA��������n�R�ɂȂ����̂�m��ƁA�����Ɏc���ꂽ��Y�Ⴂ�̖������ɗ^���Ă��܂��B�e���[�~�A���Ƃ̌������v�悵�Ă����I�X�h���t���݂́A�����m��ƁA�������莸�]���āA���E���Ă��܂��B �@�����̎��ޏ��́A�e�ʂ�}�C�l���g�̋U�P�I�Ȃ�����݂̌��t�ɓf���C���Â����A�I�X�h���t���݂̔����̘V�I�X�h���t���݂̂˂�Ȉ����̎d���ɂ͊�������B�����Ă܂��ނ̏��F�B�ƂȂ�A�����ň��l�A���ǍȂƂȂ�B�������ăI�X�h���t���ݕv�l�ƂȂ����e���[�~�A���́A�㗬�Љ�̋M�w�l�Ƃ��āA�g���ɂӂ��킵�����܂��܂ȋ`�����ʂ������ƂɂȂ�B�����ċ����K�v�Ƃ��鏭�������̐��b������ψ���̃����o�[�ƂȂ�B �@�����Ŕޏ��͂�����A���������Ď��e����Ă�������@�����@���ɍs���B�@���͔ޏ����N�ł��邩�ɋC�Â������A�m��ʊ�����Ă���B�����čĂы���@�ɋt�߂肵�Ă����G���J���A�ψ���̂����X�ɁA�����I�ɑ������̓��ʂɈ����ȗ�Ƃ��ďЉ��B����ƃe���[�~�A���̗͐̂F�ɖ������A�V���Ă���M�w�l������O�ɂ��āA���̂悤�ȋ���@�Ƃ��̂悤�Ȉ����������Ă���Љ�̎c�����ƋU�P������������B�Ō�ɘV���݂́A�u����������������A�N������ȏ��ɗ�������͂��Ȃ��̂��v�ƌ����B �y����z�����̏�ʂ����t�h�ʼn�����ꂽ�̂ŁA�f�挟�{���ɂƂ��Ă͎���ƂȂ�A�J�b�g����āA855���[�g�����J�b�g����Ď���ꂽ�B �@���̍�i�̓p�v�X�g���w�p���h���̔��x�ɑ����āA�A�����J�̏��D���C�[�Y�E�u���b�N�X���g���ĎB������ڂ̉f��ł���B����ɂ��ău���b�N�X���g�A�w�n���E�b�h�̃����x�̒��ŁA���������Ă���B�u�p�v�X�g�́w�p���h���̔��x�Ő�W���b�N�̖��ɃO�X�^�t�E�f�B�[�Z����z�������A�����悤�ɒ��ړI�ȓ|�����ɂ���āA�ނ́w�˗��̏��̓��L�x�̒��݂̂���Ȗ�ǂ̏���ɂ́A�t���b�c�E���X�v��A��Ă����B�f�B�[�Z���ƃ��X�v�͂��̓�̉f��̒��ŁA���ɂƂ��Ĕ��Ɛ��I���͂������Ă����B��̔o�D�������B��W���b�N�̃V�[�������o����p�v�X�g�̂����́A�܂������P���������B����͒P�ɏ�̂���������ł����Ȃ������B�f�B�[�Z�����X�C�̌���ɂ҂����ƌ���i�C�t����Ɍ��鋰�낵���u�ԂɂȂ�܂ł́B����ɔ����āA����l�̐S��������e���[�~�A���̖��Ɏg�����w�˗��̏��̓��L�x�̒��ł̗U�f�̃V�[�����A�ނ̓o���[�Ƃ��č\�z�����B�����Ă�����u���C�ȁv�Ⴂ�����Ƃ�������炵�̍D�F���Ƃ̊Ԃ́A��A�̖����̐ڐG��ʂƂ悤�ɉ��o�����B�ނ��t���b�c�E���X�v��I�̂́A���X�v���J���J�`���A�ɋ߂��l�����������邱�Ƃ̂ł��鉉�Z�͂������Ă������߂����ł͂Ȃ��A�ނ̐g�̗̂͂ƗD�����̂��߂ł��������B�ނɕ��i����Ď����C�������Ƃ��A�ނ͎������̃l�O���W�G�̏d�������Ȃ����̂悤�ɁA�y�X�Ǝ����グ�A�x�b�h�ɉ^�v�B �@�Ƃ���ł悭�m���Ă���悤�ɁA���C�[�Y�E�u���b�N�X�̓N�����E�{�E�ɑ�\����铖���̃n���E�b�h�́u�t���b�p�[�v���D�̈�l�������B1920�N��A�����J�̏����̐V�����������\����f���̃t���b�p�[�����́A1929�N�̑勰�Q�܂ŁA�����w�a�m�͋��������D���x��f��w�Z�u���E�`�����X�x�ȂǁA�A�����J��O�����̐�D�̑ΏۂƂȂ��Ă����B�������u���b�N�X�͂��̉f��ŁA���������u�t���b�p�[�v���z���閣�͂����鑶�݂ƂȂ����B�u���C�[�Y�E�u���b�N�X�̊�Ձv�ƌ����鏊�Ȃł���B �@�f���̃{�[�C�b�V���ȁA�ϑ��������N�̂悤�ȐV���������Ƃ��������Ȃ�A�A�����J�����łȂ��A�h�C�c�̉f��E�����̐��E�ł��A���ł��ɃG���[�U�x�g�E�x���N�i�[���o�ꂵ�A�V�����^�̏����Ƃ��āA�u�����̎���ő�̏��D�v�Ƒ�����Ă����B�������x���N�i�[�͂����܂ł����������B����ɑ��ă��C�[�Y�E�u���b�N�X�͖��C�ł͂��邪�A���قȑ��݂������B �@���������u���b�N�X���g���āA�p�v�X�g�́w�˗��̏��̓��L�x�ɂ����Ă��A���`�I�ȉf�����N�����B�c�����̐��E�ɑ���V�j�J���Ȏp���Ɛ��̐ԗ��X�Ȗ\�I�ł���B����͓�����ނɂ�郊�q�����g�E�I�Y�����g�ḗw�˗��̏��̓��L�x�ɂ́A�����Ȃ������ł���B�I�Y�����g�̓h�C�c�f��j��ł́A�����鐫����f��̌��c�Ƃ����Ȃ߂��Ă��邪�A�ނ���r�̗ǂ��E�l�I�f��l�Ƃ��āA���̑�ނ��u�h���}�`�b�N�ȗ͂ɖ������A�قƂ�ǎ��I�ȑ̌��v�ƕ]����郁���h���}�Ɏd���ďグ�Ă����B��ꎟ���E���I���̒��O�A1918�N10��29���ɕ���ꂽ���̍�i�ł́A�G���i�E�����i���e���[�~�A���ɕ����A�A���C���z���g�E�V�����c�F���̃I�X�h���t���݁A���F���i�[�E�N���E�X�̃}�C�l���g�A�����ĉf��Ɏn�߂ăf�r���[�����R�����[�g�E�t�@�C�g�������E�X���m�ɕ����Ă����B�ނ�͉f��o�D�Ƃ��Ă̘r���Ă���r���������Ƃ͂����A����̉f�扻�Ƃ��ẮA���̕������R�������B �@�p�v�X�g�̉f�扻��1929�N�Ƃ����]�@�̎��������Y�Ƃ��āA�ނ���A���`�E�����h���}�ƂȂ��Ă���B�q���̎���m���Ă��A�e���[�~�A���͒Q���߂���͂��Ȃ��B�ق��Ƃ��Ĕ�����B���t�A�ɔ������߂Ă��A�ǐS�̒ɂ݂͂Ȃ��B�V�R�Ƃ��Ĉ����ɐg���܂�����B�����h���}�ɕ��ʂ̃������ȂǁA�ޏ��ɂ͉��̈Ӗ����Ȃ��B�{���̌����ł͔ޏ��́A������u���W���A�I���K�ɔw�������āA���甄�t�A�̏���l�ɂȂ�͂��������B���́u�{���̌����v�͌��{�ɂ���Ė��E���ꂽ�B �@�p�v�X�g�̎Љ�ᔻ��������v�`�u���E���W�J���Y���ɉ߂��Ȃ����ǂ����͖₤�Ƃ���ł͂Ȃ��B�f�������ׂĂł���B�u���W���A������̌���������@�̘c�p��\�I���A�t�ɔ��t�A���m�肷��A�i�[�L�Y���I��������Βu����Ƃ����\�����A�Ռ��͂������Ă��邩�ǂ��������ł���B�p�v�X�g�̉f��ɑ��ĕK�������m��I�Ȍ��������Ă��Ȃ��W�[�N�t���[�g�E�N���J�E�A�[���A���̍�i�̓��ِ��͔F�����Ă����B�u�p�v�X�g�͒��Y�K���I���̕s���������J��Ԃ��ċ�������̂ŁA���t�A�͂��̔��ɂ܂�ŕۗ{�n�̂悤�Ɍ�����B�����Ƃ��뎩���̎Љ��]�̊܂݂���\�����ڒ��ɁA�p�v�X�g�͑ޔp���̂��̂�O����ɓW�J����B�ނ��ޔp�ƃT�f�B�Y���Ƃ̊Ԃ̐e�ߐ����悭�m���Ă������Ƃ́A�e���[�~�A�������荞�܂�鋳��@�ُ̈�ȃG�s�\�[�h�������Ă���B�v�h�t�L���̂悤�Ƀp�v�X�g�́A���̎Љ�I�R���e�N�X�g�̒��ŁA�Z�b�N�X������������ɋC�Â��Ă���v�B �@���@���X�J�E�Q���g�̕����鋳��@���v�l���A�܂�œ|�������������ł���̂ɁA���t�A�̏������p���V�����̑P�ǂȃz�X�e�X�̂悤�Ɍ����闝�R���A�����ɂ���B���C�[�Y�E�u���b�N�X�́A�|���I�}���̒��ɂ����āA�i�C�[���ȋP��������Ȃ��B����͌����p�v�X�g�̃C���[�W�̒��ɂ���A�A��d�����������e���[�~�A������\�����邽�߂̐��i�`���������B�i�`����Ƒ���E�����o�������ł́A�Љ�I���ۂ̒��Ő�߂鐫�I�Ȃ��̂̈Ӗ��́A�\���ɔF������Ă���B������������������̊J�n��������P�X�Q�X�N�Ƃ������_�ł́A���������F���͂܂����n���Ă��Ȃ������B�r���ł͂��邪�p�v�X�g���������������́A�P�Ɂu���C�[�Y�E�u���b�N�X�̊�Ձv�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�����̖ڂōĕ]������K�v�����낤�B �@���łȂ��狳��@���v�l�̃��@���X�J�E�Q���g�́A��ꎟ���E����̃h�C�c�ŁA���t�w�̐��Ԃ�ԗ��X�ɖ\�I���邱�ƂŃu���W���A�Љ��ᔻ����\�����x�̑n�n�҂Ƃ��āA�Ռ���^�������݂������B���̔ޏ��Ƀp�v�X�g�́A�t�ɗv���쏭�����s�҂���T�f�B�Y���I�������������������킯�ł���B�X�ɃG���[�U�x�g���������W�r���B�V���~�b�c�́A���̔N�G���l�E���b�c�i�[�́w�ł����Ɓx�ƁA���̉f��Ƃɂ���ăf�r���[���A�P�X�R�Q�N�A�b�E�s�E�h���C���[�́w�z���S�x�Ń��I�[�k���������āA�傢�ɒ��ڂ��ꂽ�B�������ޏ��́u���Ă��Ȃ������v�B�����̂��i�`���ゾ�������߁A���͂�������Y�ꋎ���A���ɓM��Ď��E�����B�u�j���[�E�W���[�}���E�V�l�}�v�̊���t�@�X�r���_�[�́A�ޏ������f���ɂ��āA�Y�ꋎ���Ĕj�ł��鉝�N�̑受�D�̕���w���F���j�J�E�t�H�X�̂�������x��������B�A 1929.10.15�i���{����1931.1.7�j �w�����E�̏� Frau im Mond�x �t���b�c�E�����O�ēA�V�i���I�F�e�A�E�t�H���E�n���u�i�ޏ����g�̏����ɂ��j�A�B�e�F�N���g�E�N�[�����g�A�I�X�J�[�E�t�B�b�V���K�[�A�I�b�g�[�E�J���g���b�N�A������ʁF�R���X�^���e�B���E�`�F�b�g���F���R�t�A�|�p�E�w�p�ږ�F�O�X�^�t�E���H���t�����A���[�[�t�E�_�j�����@�b�c�A�w���}���E�I�[�x���g�����i���P�b�g�Ɋւ��āj�A���u�F�G�~�[���E�n�X���[�A�I�b�g�[�E�t���e�A�J�[���E�t�H���u���q�g�A����F�E�[�t�@�f��� �y�L���X�g�z�N���E�X�E�|�[���i�Q�I���N�E�}���t�F���g�����j�A���B���[�E�t���b�`���i���H���t�E�w���E�X�j�A�O�X�^�t�E�t�H���E���@���Q���n�C���i�n���X�E���B�f�b�K�[�F�Z�t�j�A�Q���_�E�}�E���X�i�t���[�f�E���F���e���F�V���w�̊w���j�A�O�X�g���E�V���^���N���O�X�e�b�e���o�E�A�[�i�O�X�^�t�j�A�t���b�c�E���X�v�i�������@���g�E�g�D���i�[�Ə̂��Ă����j�j�A�e�B���E�f�������^�w���}���E�t�@�����e�B���^�}�b�N�X�E�c�B���c�@�[�^�}�[���[�g�E�e�����E�o�C�^�{�����B���E���@���g�^�i���]�Ə��؎�����ܐl�A�}���K���[�e�E�N�b�p�[�i�q�b�|���g�v�l�F�w���E�X��̉Ɛ��w�j�A�}�b�N�X�E�}�N�X�~���A���i�O���[�g�����F�w���E�X�̉^�]��j�A�A���N�T�E�t�H���E�|�e���u�X�L�[�i�X�~������j�A�Q���n���g�E�_�}���i�E�H���j�A�n�C�����q�E�S�[�g�i�R�K�̊Ԏ�l�j�A�J�[���E�v���[�e���i�}�C�N�̒j�j�A�A���t�e�[�g�E�����b�g�A�G�h�K�[�E�p�E���i��l�̓z��j�A�˂��݁E���[�t�B�[�l�B �y����z�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H �[�̃t�@�T�[�h�͐�`���`�[�t�̃��[�f�B�E�t�F���g�ɂ���ċP�������C�����~�l�[�V��������A�������P�b�g�ő������ꂽ�B�����O���l�̃��P�b�g���ƃw���}���E�I�[�x���g�ƃ��B���[�E���C���A�h���@�C�X�B �x�������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H�[�v�ŕ���B�N���J�E�A�[155 1929.10.22�i���{����1930.2.14�j �w���̋�� Die weisse Hölle vom Piz Palu�x �A���m���g�E�t�@���N�A�Q�I���N�E���B���w�����E�p�v�X�g�ēA�V�i���I�F�A���m���g�E�t�@���N�A���f�B�X���E�X�E���C�_�A�B�e�F�[�b�v�E�A���K�C���[�A���q�����g�E�A���O�X�g�A�n���X�E�V���l�[�x���K�[�A���u�F�G���l�E���b�c�i�[�A���y�F���B���[�E�V���~�b�g���Q���g�i�[�B����F�g�E�q�E�]�[�J���f�� �y�L���X�g�z�O�X�^�t�E�f�B�[�X���i���n�l�X�E�N���t�g���m�j�A���j�E���[�t�F���V���^�[���i�}���A�j�A�G�����X�g�E�y�[�^�[�[���i�J�[���E�V���e�����j�A�I�b�g�[�E�V���v�����O�i�N���X�`�����E�N���b�J�[�A�R�x�K�C�h�j�A�G�����X�g�E�E�[�f�g�i��s�m�j �y���炷���z�s�c�E�p�����R�̎R���A�C��2977���[�g���ɂ���A�o�R�҂̂��߂̔����ɁA��l�̃J�b�v���A�J�[���E�V���e�����i�G�����X�g�E�y�[�^�[�[���j�ƃ}���A�i���j�E���[�t�F���V���^�[���j���A�n�l���[���Ƀs�c�E�p�����ɓo�肽���v���ė��Ă���B��l���e�[�u���Ƀ��E�\�N�𗧂āA�J�[�����u�����͌N�̒a�������A�}���A�A�����Ėl���̃s�c�E�p�����֓o��n�l�[�����̓����v�����āA�}���A��������߂Ă���Ƃ���ցA�����̌˂��J���ĕs�C���Ȓj�������Ă���B����͐��N�O�s�c�E�p�����ɓo�����ہA�K�C�h�̃N���X�`�����̌x�������Ė����ȓo�R�����A�����鍥��҂�[���N���o�X�ɓ]�������Ď��Ɏ��炵�߂����n�l�X�E�N���t�g���m�i�O�X�^�t�E�f�B�[�X���j�������B����ȗ��ނ͔ޏ��̖S�[��T���āA���N�ޏ��̎��̓��ɎR�ɓo���ė���̂������B���ꂪ���N�́A���܂��R�����Ń}���A�ƃJ�[���̃J�b�v���ɏo������̂ł���B�N���t�g�̒��T�Ȏp�ɋ���ł��ꂽ�}���A�́A�J�[�����R�[�q�[�������߂̐������߂ď����̊O�ɏo���Ƃ��A�N���t�g�Ɂu���͂��Ȃ��̂��Ƃ��A���Ȃ��̋C�����𗝉����܂����B����ǂ�ȕ��ɋN�����̂��A�b���Ă��������v�Ɗ肤�B �@�N���t�g�͂���ɓ����āA����ɓۂݍ��܂ꂽ����҂��~�����ƁA�K���ɃN���o�X���~���������A�U�C�����I���ɂȂ��Ă���m��ʐ[���������A��������Đg���������鑼�͂Ȃ������ƌ���āA�����̊O�ɏo�Ă����B�����փJ�[�����A��ƈꏏ�ɖ߂��Ă��āA�ޏ��Ɂu���ꂪ�N���X�`�����N�i�I�b�g�[�E�V���v�����O�j���A�s�c�E�p�����̈�Ԃ̃K�C�h���v�ƏЉ��B�N���X�`�����́u�����͍r��͗l���A���͑��ɂ���ė����w���B�ɖ����͓o�R���T����悤�x�������A�N�ɂ��x�����Ă����v�ƌ����B �@���������N�����N���t�g���m�͎��ЂɁu��N�ԃg���C������Ŏ��́A�k�ǂ������m���ɐ����ł���Ɗ����Ă���A������l�Łv�Ə����ďo�|���悤�Ƃ���B�����J�[�����o�Ă��āu�҂��Ă���A�������ƈꏏ�ɍs���v�ƌ����B�����Ď��ЂɁu�e���̓}���A�A�l�̓N���t�g���m�ƈꏏ�ɖk�ǂ𐪕����ɍs���A�l�ɂ͂ł���v�Ə����A�N���t�g�̖��O�̉��Ɏ����̖��O�����������āA���V��̒����R���ڎw���ďo������B�Ԃ��Ȃ��ڂ��o�܂����}���A�͂�������āA���ЂɎ����̖��O�����������A�X�L�[�œ�l�̌��ǂ��B�ǂ������ޏ��ɃJ�[���́u�s�c�E�p�����͏����̂��߂̎R�ł͂Ȃ��A���ɖk�ǂ́v�Ɖ��߂邪�A�}���A�͌������Ƃ��������A�O�l�œo��n�߂�B �@�����V�������A�ނ�͐���Ɋ������܂�A�N���t�g���m�͋r��܂��Ă��܂��B���̎p���w���B���o�ዾ�Ō����A�u�N���t�g���m������Ă���A�ނ�͎R�̈�Ԋ댯�ȏꏊ�ɂ���v�ƁA�~���Ɍ������B�������ނ�������Ɋ������܂�ē]������B���낤���Ċ�I�ɔ����オ�����N���t�g�̓}���A�����������J�[��������āA�[�Ɍ������ċ~�������߂āA�u���b�z�[�v�Ƌ��ё�����B���̋��т����N���X�`�����͋}���ŎR��o��B�����J�Ԃ̑��ł�����̏����炳��A�N���t�g���m��s�Ɗw���B��T���āA�铹���~�������o������B �@������I�ł́A��������Ă���J�[����������̕X����܂Ƃ��ɎāA�������蓪�����������Ȃ�A�}���A�͂Ƃ��Ƃ��ނ��U�C���Ŕ����Ă��܂��B�邪������ƁA�ȏ���s�m�̃E�[�f�g����s�@�Œ�@���āA�ނ�̋��ꏊ��T���ɗ���B�R����D���Ĕނ��{�����Ă���E�[�f�g�̔�s�@���������N���t�g�ƃ}���A�́A������������B�E�[�f�g�̓p���V���[�g�ŐH���𗎂Ƃ����A�J�Ԃɗ����Ă��܂��B������x���ē�l�̎p���m�F�����ނ́A�R����o���Ă���~�����Ƀp���V���[�g�𗎂Ƃ��A�u���͔ނ�������B�������ނ�ɐH����͂��邱�Ƃ͕s�\�v�ƒm�点��B�E�[�f�g�̃��������Č��C�Â���ꂽ�~�������A����ɃN���X�`���������シ��B �@��������I�ł͔���ꂽ�J�[�����A�X���̂悤�ɗ��������Ă���B�}���A���N���t�g���m�Ɂu�J�[���������������Ă���v�Ƌ��ԁB����ƃN���t�g�͎����̃��b�P�E���ŃJ�[���ɒ����A�}���A�ɂ͎����̖X�q�����Ԃ���B���E�̑��ł͑��l������ɏW�܂��āA����҂̖������F���Ă���B���ɋ~���������ǂ蒅���A�}���A��S�����낷�B����̏�����A���l���u�ނ炪�A���ė����v�ƏW�܂��Ă���B�u��l���������ĎR�����ɒ������v �@�C�������}���A���ׂɐQ�Ă���J�[���̎p�����āA�u����Łc�c���n�l�X���m�́v�Ɛq�˂�B����ƃN���X�`���������m�̏����u����������B����ɂ́u�e���ȃN���X�`�����A���������悤�Ƃ͂��Ȃ��ł���[�[���̎҂��~���Ă���B���͍���҂ƎR�ƈꏏ�ɂȂ�v�Ə�����Ă����B��l�͉i�v�Ɉꏏ�ɂȂ����[�[�s�c�E�p�����̒n���ŁB �y����z�x�������́u�E�[�t�@�E�p���X�g�E�A���E�c�H �[�v�ŕ���B���j�E���[�t�F���V���^�[�����o�����A�E�[�f�b�g�̋ȏ���s���]���ƂȂ�A�u�|�p�I�ɉ��l�L��v�̕]�_�i�v���f�B�J�[�g�j���B 1929.10.28 �w�A�g�����e�B�b�N Atlantic�x E.A.�f���|���ēA�V�i���I�FE.A.�f���|���ēA�B�e�F�`���[���Y�E���V���[ �y�L���X�g�z�t���b�c�E�R���g�i�[�A�G���U�E���@�[�O�i�[�A���[�c�B�G�E�}���n�C���A�t�����c�E���[�f���[ �y����z�p�Ƌ����g�[�L�[�f��B�����q�C�Œ��v�����p�����؋q�D�u�^�C�^�j�b�N�v�������f���ɂ�����i�B 1929.11.13 �w�ŃK�X Giftgas�x �y����z�x�������̉f��فu�}�������n�E�X�v�ŁA�y�[�^�[�E�}���e�B���E�����y������́A�f��Ƃ��ĕ��� 1929.11.22 �w�N�������� Dich hab'ich geliebt�x �y����z�x�������̉f��فu�J�s�g���v�ŁA�h�C�c�ŏ��̊��S�g�[�L�[�f�敕��B 1929.12.16�i���{����1930.11.21�j �w�߉́i�S�̃����f�B�[�jMelodie des Herzens�x �n���X�E�V�����@���c�ēA�V�i���I�F�n���X�E�X�c�F�[�P���A�B�e�F�M�����^�[�E���b�^�E�A�n���X�E�V���l�[�x���K�[�A���y�F���F���i�[�E���q�����g�E�n�C�}�� �y�L���X�g�z�f�B�[�^�E�p���� Dita Parlo�A���B���[�E�t���b�`�� Willy Fritsch �y����z�̉��y�t���̃����h���}�B�E�[�t�@�ŏ��̒��҃g�[�L�[�f��v���~�A�B�h�C�c��ŁA�p��ŁA�t�����X��ŁA�n���K���[��ł����삳�ꂽ�B 1929.12.19 �w��͎������̂��� Die Nacht gehört uns�x �J�[���E�t���[���q�ē� �y�L���X�g�z�n���X�E�A���o�[�X�A�V�������b�e�E�A���f�� �y����z�h�C�c�ŎO�Ԗڂ́A�����Ă͂��߂Č|�p�I�ɐ��������g�[�L�[�f��B 1929.12.30 �w�N���E�X���ꂳ��̍K�� Mutter Krausens Fahrt ins Glück�x �s�[���E���b�c�B�ēA�V�i���I�F�����E�t�F�[�g�P�A���B���[�E�f���i�n�C�����q�E�c�B���̕���ɂ��j�A�B�e�F�s�[���E���b�c�B�A���u�F���[�x���g�E�V�����t�F���x���N�A�J�[���E�n�[�J�[�A���y�F�p�E���E�f�b�T�E�A����F�v�����e�E�X�f�� �y�L���X�g�z�A���N�T���h���E�V���~�b�g�i�N���E�[���ꂳ��j�A�z�����X�E�c�B���}�[�}���i�p�E���j�A�C���[�E�g���E�g�V�����g�i�G���i�j�A�Q���n���g�E�r�[�l���g�i�Ԏ�l�j�A���F���E�U�n�����i���t�w�j�A�t���[�h���q�E�O�i�X�i�}�b�N�X�j�A�t�F�[�E���@�b�N�X���[�g�i�q���j �y���炷���z�i�P�X�Q�X�N�W���X���Ŗv���N�ƂȂ��ƃn�C�����q�E�c�C�����`�����x�����������̊�����ᔻ�I�ɉf���������f��j�B �@���łɐ��l������l�̎q���G���i�ƃp�E���ƈꏏ�ɁA�x�������k��̕n���X�E�F�f�B���O�́A����ɖʂ����Z���Ő������Ă���N���E�[���ꂳ��́A�X�ɋ��ԂƑ䏊��f���̂͂����肵�Ȃ��Ԏ�l�ƁA���̍Ȃ̔��t�w�A�c�����̎q���ƁA�����Ŏg���Ă���B�����ĐV���z�B�����Đ��v���x���Ă���B���q�̃p�E���Ɩ��̃G���i�͂ǂ���̎��ƒ��ł���B �@�G���i�͊K���ӎ��ɖڊo�߂����H�H�v�̃}�b�N�X�Ɛe�����B�����Ŕޏ��̓}�b�N�X�ƈꏏ�Ƀv�[���ɍs�����Ƃ��Ă���B�����ŃN���E�[���ꂳ��͂�ނ��p�E���ɁA�����A�G���i�̑���ɐV���̔z�B����`���Ă���Ɨ��ށB�p�E���͏W�߂�����V���Ђ̏o�����ɓn�����A�S������ł��܂��B�N���E�[���ꂳ��͔ނ�����ŁA�x���x���ɐ����ς���Ă���̂�������B�ޏ��͖����Ȃ���20�}���N�����Ԃ����Ƃ��邪�A�ʖڂł���B �@�p�E���͂��͂�ƂA��E�C���Ȃ��B��������K�i�Ɏp�������A��e������Ɠ����Ă����Ă��܂��B�Ƃ���ŊԎ�l�̂ق��́A���l���܂Ƃ��Ȑl�Ԃɂ��傤�Ƃ��āA�������������Ȃ��B�����_���X�̂Ƃ��A�ނ͑O����̏K���ʂ�G���i�ɓ���ꂵ������B���̂��ߔނƃ}�b�N�X�Ƃ̊Ԃɑ������N����B�Ƃ��Ƃ��Ԏ�l�́u���͂��O�����O�ɁA�������̏��Ɏ�����Ă����v�Ƌ��ԁB�u����͖{�����v�Ƃ����}�b�N�X�̖�ɑ��āA�G���i�͒p���Ă����ڂ��邾���Ȃ̂ŁA�}�b�N�X�͓f���C���Â��āA���������Ă��܂��B�Ԏ�l���]������ƍ�����B �@�������N���E�[���ꂳ��͑䏊�̌˒I����A�S�v�̏ё�����̃u���[�`����肾���A�����Ɏ����čs���B�������ق�̐��O���b�V�F���ɂ����Ȃ�Ȃ��B�ޏ��͐V���̏o�����ł����̐��Z�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���������肪����Ȃ��̂ŁA�ߌ�܂łɂ����������ė��Ȃ���A�N�r�ɂ��č�������Ƌ��������B�ޏ��͋���ɋ삯��邪�A���ʂł���B�Ԏ�l���u�����������炩��v�Ȃ̂ŁA�������Ȃ��B�������ނ͊K�i�̂Ƃ���Ńp�E���ɏo��B�ނ̓p�E����������āA�ꏏ�Ɏ����ɉ����������ɍs���A����ŕ�e�������Ă�낤����Ȃ����ƁA����������B �@�����G���i�͊Ԏ�l�̍Ȃ̔��t�w�ɉe������āA�u���ɉ\�Ȃ����Łv��e�������悤�Ƃ��邪�A�Ō�̏u�Ԃɓ��݂Ƃǂ܂��āA���������Ŕ������Ƃ��ăv���[�{�[�C�̖��肩�瓦���o���B �@�G���i�̓}�b�N�X�̂Ƃ���֑����čs�����A�ނ͂��Ȃ��B�ׂ̏�����}�b�N�X�̓f���ɍs�����ƕ������ꂽ�ޏ��́A�ʂ�ɏo�Ă����A�}�b�N�X�������āA�ꏏ�Ƀf���ɉ����B�����ă}�b�N�X�̕����ŁA��l�͘a������B��l�́u�J���҉����A���̃K�[�f���p�[�e�B�v�ɍs���ėx��A�A���Ă��Ă����e�ɁA���������͌����������ƍ�����B �@�����p�E���͊Ԏ�l�ƈꏏ�Ɏ����ɉ�������A�X��Ɗi�����āA�s�X�g����\������B�x�����ʂ�ł�������āA�삯����B�Ԏ�l�͑ߕ߂���邪�A�p�E���͂��̑O�ɓ����Ă��܂��B�����Ă������苻�������l�q�ŁA�䏊�ɂ����e�̂Ƃ���֎p�������B���q���߂��ė��Ă��ꂽ�ƁA�N���E�[���ꂳ��͓V�ɂ�����C�����ŁA�ނ��}����B�����������Ɍx�@������ė��āA���q��ߕ߂��čs���B �@��������C���������N���E�[���ꂳ��́A����܂ł̐����̎d���Ɠ����悤�ɁA�܂�ŋV���̂悤�ɔO����ɁA�u�K���ւ̎��o�̗��H�v�ւ̏���������B�����Ĉ�ԗǂ����𒅂āA�Ō�̃R�[�q�[���킩���A���ꂩ�玩���K�X���u�ɂQ�O���b�V�F������āA�����J���B�����Ă��������Ă��鏩�w�̗c���q�����A�ꏏ�ɓ��A��ɂ���B�u���O�̂悤�Ȉ���Ȏq�́A���̐��ʼn����������̂����낤�H�v �@�}�b�N�X�ƃG���i�͈ꏏ�Ƀp�[�e�B����A���Ă������ɂ́A�������h�������Ă����B�}�b�N�X�͋��������G���i���Ԃ߂Ȃ���A��������B�Ō�ɓ�l�͂�����x�f���ɏo�čs���B �y����z1925�N�ɃE�[�t�@�f��Ђ́u�p���t�@���g����v�����сA�n���E�b�h�̃A�����J���{�̎P���ɓ������B�����N�Ƀ��B���[�E�~�����c�F���x���N�́A�u�v�����e�E�X�f��Ёv��ݗ������B����̓E�[�t�@�Ɣ��ɁA�\���B�G�g�ƌ��Ԃ��̂������B���̌��ʃx�������́A���ۓI�ȉf��̊p����ƂȂ����B�v�����e�E�X�f��Ђ́A���Y�}�̍���c���ŐN�C���^�[�̃��[�_�[�������~�����c�F���x���N���ݗ����������̊�Ƃ̈�������B�����ăv�����e�E�X�Ђ̓\���B�G�g�f��̃h�C�c�ւ̗A���������Ȃ������A���̒��ɂ̓h�C�c�̉f��s��ŏ��������ʁA���E�ɍL�܂����w��̓|�`�����L���x��w�A�W�A�̗��x���������B �@�����Ă��́w��̓|�`�����L���x�̃h�C�c��ō쐬�ɗ͂�s�������̂��A�w�N���E�[���ꂳ��̍K���x���ē����s�[���E���b�c�B�������B����͓����̃h�C�c�̉f��K��ɂ���āA�w��̓|�`�����L���x���ւ̗A�������̌��Ԃ�Ƃ��Đ��삳�ꂽ���̂������B����ɂ͉�Ƃ̃P�[�e�E�R�����B�b�c�A�n���X�E�o���V�F�N��A�n�C�����q�E�c�B���̗F�l�Łu���ۘJ���ҋ~���g�D�v�iIAH�j�̈����������ƃI�b�g�[�E�i�[�Q�����̎x�������B �x�����������̕�����n�����l�X�̗��ꂩ��`�������y��ƃc�B���́A�����x�������s���ɐe���܂�Ă��邪�A���̉f��͂��̃c�B���̕`�����x�����������́u�~�����[�v��Ƃ��āA�Ӑ}�I�Ƀc�B���̎u���ɏ]�����f��ł���B�����������̂�����u�c�B���f��v�́A�v�����^���A�����̐w�c�����ĂȂ��A�u���W���A�����̐w�c�ł����s�ɂȂ��Ă����B�x�������k��̕n���X�u�E�F�f�B���O�v�̐��E�̕�����A�K���ɂ��Ď����͂����֗������܂��ɂ��x�������s�����y����Ō����̂������B���̌��ʁu�c�B���f��v�͊m���ȏ����ƂȂ�A�w��܊K���x�i1925�j��w��ӂ̐l�X�x�i1926�j�Ȃǂ�����Ă����B�����āu�v�����e�E�X�f��Ёv����̂��̉f��́A���������u���W���A�I�u�c�B���f��v�Ƃ͒������قȂ�A���^�����́u�c�B���f��v�ƂȂ����B�������c�B���̊G���̂́A�u���W���A�W�[�v�����^���A�[�g�Ƃ����Η��}���ɉ������̂ł͂Ȃ������B����䂦�c�B���̍Ō�̒a�����Ɍ���ăA�C�f�A�Ɋ�Â���{�́A��{�I�ɂ̓����h���}�������B���������́u�c�B���f��v�̊�Ղ̕����I���i�̂��߂ɁA�f���̃��b�Z�[�]�͈�`�I�ł͂Ȃ��B����ɂ�������炸�����̕]���̓C�f�I���M�[���D�悵�āA�^�ʂ�̔�]�������Ȃ�ꂽ�B�Ⴆ��1930�N�́u�Ԋ��v�́A������]���Ă���B�u�G���i�͂��ǂ������̂��߂ɐ키�v���I�J���ҊK���̐��ɉ����B�f��͖��Ăɂ����₢������B���N�n�������͉���]�ނ��A�K�X��������Ƃ��������v�B �@����ɑ��ăW�[�N�t���[�g�E�N���J�E�A�[�́A�����ᔻ���Ă���B�u���̓}�b�N�X�̍K�����A�N���E�[���ꂳ��̍K���ςɂ܂��邩�ǂ����ł���B�ޏ��̎��E�ɗ͓_���u����Ă��邱�Ƃ�������o�����Ƃ̂ł��錋�_�́A������ł���B���Ȃ킿�A���̉f��͎Љ��`�I�ȗv�����]�𐄐i������́A�ނ��냁�����R���b�N�ɂ�����͂��邱�Ƃ��Ӑ}���Ă���̂ł���v�B����ɓ���1929�N�ɍ��ꂽ�A�����e�[�}�̉f��w�l���͂����̔@���x�̊ēJ�[���E�����O�n���X�́A���̉f��̊����u�v�����e�E�X�Ёv�Ɏ��������A�f���̏�ʂ��������Ƃ𗝗R�ɁA���Ƃ��ꂽ�ƌ���Ă���B�N���E�[���ꂳ��̎��E�̌�ɁA�f���s�i�̑��̃V�[�����t���������Ă���̂́A�܂��ɂ��̗v�]�ɓY�������̂��������A���ꂪ�����������ƌ����āA�f��S�̂̈Ӗ������̏�ʂɎ��ʂ��ꂤ�邩�ǂ����́A���ł���B���̓_�ɂ��ẮA���������u�c�B���f��v�́A���̂悤�Ȉ�`�I�Ӗ��Â�����ՂƂ���f��ł͂Ȃ��ƌ������Ƃ��ł��悤�B �@�ނ��낱�̉f��̉��l�́A�����̑��̑�s�s�f�擯�l�A�n���X�u�E�F�f�B���O�v�́u�~�����[�v�̃��|���^�[�W���f���Ƃ��Ắu�^�����v�ɂ���B�܂�c�B���I�~�����[�̉f���I�蒅�ɐ������Ă���_�ɂ���B���ꂪ�c�B���L�O�f��ƂȂ����̂́A�s�v�c�ł͂Ȃ��B �Ȃ����̉f��ɏo�������̂́A��������{���̃E�F�f�B���O�̏Z���̑f�l���A���邢�͍����̉����̃O���[�v�̃����o�[�������B�p�E�����������z�����X�E�c�B���}�[�}���́A���Ȃ�O����s�[���E���b�c�B�̋��͎҂ł����āA���b�c�B��1928�N�ɍ�����w����̓����̃p���[�[���@���f���u���N�̋Q���x�ɂ��o�������B�C���[�E�g���E�g�V�����g�ƃt���[�h���q�E�O�i�X�́A�Q���n���g�E�r�[�l���g���l�A�s�X�J�[�g�����䂩�獶�������^���ɉ�����Ă����B���F���E�U�n�����́A��ƃI�b�g�[�E�f�B�b�N�X�̃��f���Ƃ��ē����Ă����B������ɂ��Ă����̉f��́A�ɓx�ɏ��Ȃ������̂��߂ɁA�o���҂̋]���I��d�ɂ���āA�h�����ĎB�e���I�����邱�Ƃ��ł����B |