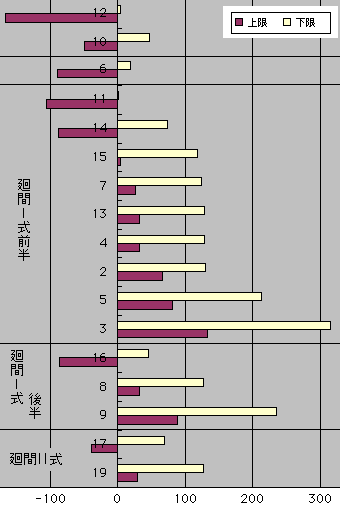| 番号 | 型式 | C14(BP) | 較正年代
| | 12 | 古宮II式 | 2076±40 | BC166( )126, 124(89,77,57)42, 7( )4
| | 10 | 古宮II式 | 2019±38 | BC49(38,30,21,11,1)AD26, 43( )47
| | 6 | 山中I式 | 2034±39 | BC89( )78, 57(42,7,4)AD4, 10( )19
| | 11 | 廻間I−0 | 2050±40 | BC105()104, 95(46)35, 35()17, 13()AD2
| | 14 | 廻間I式前半 | 2002±69 | BC88()80, 55(15,15,AD2)74
| | 15 | 廻間I式前半 | 1947±41 | AD4()8, 21(65)84, 103()119
| | 7 | 廻間I式前半 | 1933±38 | AD27()42, 49(73)89, 99()125
| | 13 | 廻間I−0 | 1917±40 | AD32()38, 53(80)129
| | 4 | 廻間I式前半 | 1914±41 | AD32()37, 54(81)129
| | 2 | 廻間I式前半 | 1903±38 | AD67(85,103,120,)131
| | 5 | 廻間I式前半 | 1873±38 | AD81(129)179, 190()214
| | 3 | 廻間I式前半 | 1809±37 | AD133(236)253, 305()316
| | 16 | 廻間I−4 | 2025±40 | BC86( )83,53(39,28,23,9,2)AD24, 44( )46
| | 8 | 廻間I式後半 | 1917±38 | AD32( )37, 54(80)128
| | 9 | 廻間I−4〜II−1 | 1852±37 | AD89( )99, 125(132)235
| | 17 | 廻間II−1 | 1981±40 | BC39()28, 22( )10, 2(AD25,44,47)69
| | 19 | 廻間II式後半 | 1921±40 | AD30( ), 52(78)128 |
|
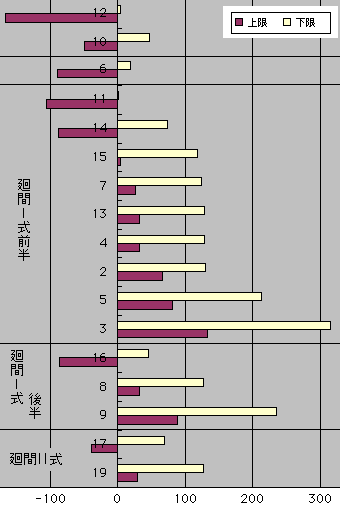
|