

「HONDA GB400TT」
GB400TT改良乗って不満があった部分等を少しづつ変更しています。 足回りに関しては既製品が少ないので、他車用をベースに加工しているものが多いです。 |
|
|
点火系をいじり始めたきっかけは走行中の失火でした。その後の調査で、メインスイッチの接触不良で失火することが大部分であることが分かったのですが、一度手をつけてしまったので、コイル交換までやってしまいました、でも、エンブレ後の燃焼状況の悪さから失火する場合が今でもあるようです まず手始めに走行距離不明で、だいぶ劣化していると思われた点火コードと点火コイルを交換しました。コードとコイルは最近多いハンダ付けされているものなので個別には交換できません。(ケース割るなり、無理すれば可能ですが。。。実際は後でやっちゃいました(笑)) 効果は、体感できる程の変化はありませんでしたが、数万ボルトを通している点火コードはずっと使い続けていて酸化していたことは確かだと思います。(エンジンの性能を維持する為、10000km交換を推奨しているショップもあるようですね)
次に巷では、賛否両論のsplitfireプラグ(以前XLR250Rに装着して良い印象をうけていました)とコードを装着しました。コードは太いし、純正コードはハンダづけされている為、点火コイルケースの先を少し割って強引に純正コードを外し加工して直接接続しました。 次に、点火コイルをDYNAのものに交換しました。(以前純正コイルのケースを加工して無理やり装着していたためコードが外れる不安もあったので) このコイル、純正と比較して圧倒的に大きい為、適当な装着場所が無く悩んだのですが、GB400にはダウンチューブにMarkII用のカウルステー用ネジ穴があったため、そこに手元にあったNSR88用バンクセンサーのアルミパイプと、GB400ハンドルウエイト装着用ネジとステンの汎用ステーを使って装着しました。 配線は汎用の端子と線を使って延長しています。装着して、純正コイル&コード、DYNAコイル&spritfireコード装着とで同一日同一場所で比較試乗した結果では、明らかにDYNAコイルの方が一回の爆発が強くなりアクセルを開けるのが楽しくなる結果となりました。 ただし純正コイルとはオーム数が違う為、ただ装着すると同じ場所からパルスを拾っているタコメータが暴走します。これには、タコメータの配線に抵抗を入れて解決しました。 デメリットとしては、おそらくただでもライフが短いと言われているspritfireプラグのライフが一段と短くなることでしょう。あと、エンジンの始動をセルでした場合、エンジンがかかるまでセルを回している時間が長くなりました。(コイルのオーム数が違うから?それとも容量の違いから?) DYNAコイル装着時に雨に降られた時、リークして点火が安定しなくなったことが ありました。装着時にはリーク対策にも気を使った方が良いと思います.
その後、バイク屋さんに低回転域での点火にふらつきがあり、低回転のセッティングが出ないと言われ、コイルとコードを元に戻し、
NGKの「DP8EVX-9」プラグや、DENSOの「IRIDIUM POWER IX24B」、NGKの「IRIDIUM IX」を装着してみました. この中ではデンソーのイリジウムプラグがアイドリング時の回転数が一番上がりアイドリングも 安定していましたが、走ると体感的には違いを感じることはありませんでした.鈍感なだけ?(^_^;
川越のGB乗りの方から、「「CRM250AR」の点火コイルが希薄燃焼対策の為に強化した点火コイルを
装着しているらしい.」というメールを頂き、99年10月に、CRM250ARの点火コイルを注文して装着してみました.
価格は\3,000-でした.
2003/03/21 デンソーイリジウムレーシングプラグ装着
タイヤは風邪をひいていた今では売っていないTT700GP!が装着されていて、あまりにひどいけど、ハイグリップタイプで装着するサイズあまりないなーーなんて考えていたら、懐かしいTT100GPが復刻されたため装着しました。 特性はとんがりおむすび形状のため、スッとバンクして、一定のところでバンク角固定って感じで自分では好みのタイヤです。その代わり切り返しはGBは重心が若干高いこともあって、ヨイショって感じでやります(笑)今回使っているGPコンパウンドはあまり温度依存していないそうなので、以前のように冬にすってんころりんは無いようで寒い日も安心!?
99年夏に、TT900GPのフロント90/90−18、リア120/80−18(リアは110/90−18のサイズがラインナップに無い為)を装着しました.
本当はリアのリムはワンサイズ上げた方が良いと思いますが、タイヤ屋さんの話しですと「このタイヤは形が出やすい為このリムでも大丈夫でしょう」
ということでした.
ずっと、TT900GPを履き続けていたのですが、GB400TT乗りの樋口さんから、是非装着してみて欲しいと実験の依頼!(笑)
私は体重が約55kg(98年当時(笑))なのですが、自分の体重だとダンパーが弱いのかスプリングが固いのかリバウンドが少な過ぎるのか、とにかくリアがよく跳ねてしまいました。(その後にリアのスイングアームをばらして 判ったのですがスイングアームの動きが悪かった為に跳ねていたのでした)高いサスだとwp製や、DYNAMIC製があるのですが、所帯を持っている身には手が届きません。。ぶらっとバイク用品店によったところ、KYB製の「HGS−330」というGB400/500用サスが目に止まりました。 これは、スプリングイニシャルは無断階調整で、伸びのダンピングが4段に調整でき値段も¥36,000のガスショックで、一度だけGB400TTMarkIIに装着しているのを見たことがあり、どうしても装着してみたくなりました。手頃な価格のものには、他にHEIGON製やKONI(SR400用),DAYTONA(SR400)用があります。 結局2カ月おこずかいをためて(泣けるでしょ(笑))購入しました。外観はメッキを多用したノーマルに比べるとガンメタ色のスプリングに銀塗装のダンパー部となり、若干地味な感じとなります。 装着は2本サスの為簡単ですがノーマルより自由長が若干長い為、センタースタンドをかけた後ノーマルサスを2本と外した後交換した方が楽にできます。
装着後、ノーマルサスと1Gの長さを合わせてみたのですが、イニシャルはまったくかけない状態で合いました。(FCR装着後、イニシャルを5mmかけています)
現在ダンパーは”2”や”3”で使用しています。”2”だと私が乗ると高速コーナーで落ち着きが無いようです。
走行した感じは、サスの動きが良いことと、リバウンドが長くとられているためか、跳ねることがなくなり、ダンピングも効いている感じで、全体的にしっとりしっかりした感じになりました。 その後、フロントサスの加工とリアサスのピボットの分解掃除を行った後、同じタイヤでイニシャル7mmダンパー”1”のセッティングになりました. 2年程度このサスを使用していたのですが加工したフロントサスとのバランスが悪いのか3kg太ってしまった私が 悪いのか、設定されたスプリングレートが低い為、高速域になるとリアが沈み込みすぎるようで、乗り方を変えてもフロントまわりの暴れが納まらないようになり(装着当初も高速コーナーで発生していたのですが乗り方で対処してました)現在はノーマルに戻しています.標準体重の方や飛ばす人には向かないかも
KYBサスをベースに、ましもさんプロデュースの「MassimoKYB」サスが登場しました。
2001/11/24 使用していた「MassimoKYB」リアサスのダンパーの動きが悪くなってきたので、中古のOHLINSを購入して
装着しました。
2002/12/30 スイングアームのピボットのニードルベアリング化
ノーマルベースで、オリフィスの加工とノーマルスプリングを切りイニシャルをかける加工をしています
組み込んでみると突っ張り感があったので、イニシャルを弱め、ゴールドバルブのイニシャルも弱めたら自然な感じとなり、
荒れた高速コーナーでフロントも暴れなくなり、リアとのマッチングが良くなりました。
2002/05/25 キャリパーをAPのCP3369に変更したところ、圧減衰を下げた(といってもノーマルより全然効いているのですが)
すこん!とオイルロック(笑) 結果的にゴールドバルブのスプリングのレート上げ、フォークオイル粘度上げ、スロントフォークスプリングのレート上げをするはめになりました。やっと落ち着きました。
2002/02
ゴールドバルブのスプリングを柔らかいものに変更しセッティング変更、シートパイプは減衰を上げるよう加工した
ものを使用し、自然な感じにしています。
2001/02/11 他社種用のイニシャルアジャスターをGBに装着できるよう加工してもらい取り付けています。
装着には、バネのイニシャルを調整しているカラーも加工が必要です。
2001/07/09 サンセイのハンドルに交換しました。
2002/02/10 フロントフォークスタビライザーを製作しました。
リム幅を広げたことによりグリップが上がったため、以前から感じていたフロントフォークの剛性不足が
顕著に現れてしまいました。
コワース製スタビライザーの真ん中の板は中心部に削りが入っているため、左右の幅を詰めると穴の位置が削りの部分にかかって
しまいそうな為、ましもさんのアイデアでかなり剛性のあるドライカーボン素材を使用し切り出して製作してみようことになりました。
製作ですが、まず寸法を測定した上でやわらかいプラ板を切り出し現物合わせをしながら型紙を製作し、それを元にカーボン素材
に書き写し糸鋸で切り出しました。そして現物合わせをしながらヤスリで形を整え(中心の板は長手方向が曲線で出来ています(^_^;)、
最後にある程度自由になる穴を開け(これがなかなか時間がかかりました)2枚作成し中心部を組み付け完成です。
近所を走ったのみなのですが、装着感はブレーキング時に安定度が増し(商品も直訳で安定装置ですね)、
交差点を曲がる時に今までよりインに切り込む感じが出ました。今までフォークがねじれて穏やかさが出ていた
部分が無くなりシャープになったのだと理解しました。
2003/01/11 ステアリングステムベアリングのテーパーローラーベアリング化
作業が淡々と進んだので、グリスまみれの手で途中経過の写真を撮ってみました。
箱根に初めてGB400を持ち込んだ私は椿ラインを2往復したら、軟弱な私の腕は(笑)現代レベルと比較して効きの甘い&フェードにより握力を失い腕が上がってしまうのでした。
そこで、効くパッドが欲しい!!衝動にかられ(今までのバイクではレプリカバイクの純正に充分満足していたため、社外品のパッドを使うの初めて)聞き込みにより(笑)フェロードのパッドを装着しました
結果、食いつきがすごく良くなり安心して走れるようになりました。装着したのが寒くなってからの為、峠を走っていないのでフェード性については未確認です。でも、このパッドって元々強力なブレーキに装着したら結構過激かもしれないですね。
ブレーキホースは現代のものより膨張していると思われるので、テフロンホースのものに交換しました.ノーマルよりダイレクト感が出て山道ではコントロールしやすくなりました.
レバーは、NSR250R等のものを使用して、握りしろを調整できるよう変更しています.
純正流用でナイトホーク用の316Φディスクをサポートを作って装着しました.
2002/3/9 AP製CP3369キャリパーを装着しました。
<ホイール>
2002/01/20 takasago RK EXCELのリム F:2.15 R:3.00を装着しました。
タイヤは、腕が良いという鶴見の国道1号沿いのタイヤ屋さん「ポイント・ワン」にタイヤ組み換えをしてもらいました。
噂通り丁寧な扱いでした。
走行感ですが、タイヤの展開が広がったので粘りが強い感じとなり、安心感が増しました。
高速では安定性が出て開けて行ける気になるのですが、今まで持っていた鋭さは影をひそめました。
何キロの走行距離か分からないし、恐らく前オーナは直キャブ仕様にしていたようで、私のキャブはダイアフラム部の動きが悪く磨耗と傷が入っていたダイアフラム部&ジェットニードル交換と奮発し、キャブ本体の傷もならしたのですが、走行中の動きは良くなったのですが、エンジン始動し暖気後走り始めた直後のダイアフラムの張りつきは未解決。。
交換して予備部品となっていたダイアフラム部の下部の穴を、バイクの機種によって大きくするというダイノジェットの例にならって実験してみましたが、見事ダイアフラム部が負圧で動作しなくなりました。大失敗です(笑)
エアクリーナは、K&Nからキャブ直付けタイプが出ています。
その後、エンジンを加工したのと同時にK&Nのパワーフィルターを装着しました.ノーマルエアクリーナ用のアダプターがあるので、ノーマルキャブに合う大型のタイプを購入しました.
バイクは中古で買ったのですが、エンジンをばらした時、圧縮時もバルブはずるずるでガスが抜ける状態でした.もう1X年もたっているので、中古で購入すればこんな状態のものが多いのだと思います.新車時のパワーってどれくらだったのでしょうか.メーターも戻されていたのでいったい何キロ走っていたのでしょう
オーバーホールを兼ねて吸入バルブ拡大、ポート加工、ハイオク燃料使用を前提に圧縮比UP等を行っています。クラッチ板交換時にGB500用のスプリングを入れて強化しましたが、少しクラッチが重くなりました。
2002/05/01 以前入手していた、XR600RヘッドとHRCのXR630キットのカムを使用してヘッドから上を組み直しました。
今までのピークは6000rpm程度だったのですが、カム交換と排気バルブ拡大の効果でピークが7000rpmあたりになり、実質7500rpmあたりまで伸びるようになりました。峠ではパワーゾーンが狭いエンジンとなり苦労していたので、これで楽に走れる
ようになりそうです。 |



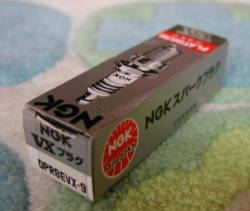
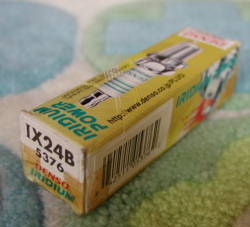


























 装着前
装着前
 装着後
装着後


 こんな感じで作業です。
こんな感じで作業です。 ノーマルベアリングのレース(打ち抜いた後、上に載せてます)
ノーマルベアリングのレース(打ち抜いた後、上に載せてます) ノーマルベアリングのレースを打ち抜いた後
ノーマルベアリングのレースを打ち抜いた後 テーパーローラーベアリングのレースを打ち込んだところ
テーパーローラーベアリングのレースを打ち込んだところ アンダーブラケットのベアリングレースを抜き取るところ
アンダーブラケットのベアリングレースを抜き取るところ テーパーローラーベアリング(グリスアップ前)
テーパーローラーベアリング(グリスアップ前)


 GB純正
GB純正 NSR純正
NSR純正




 XLR/XR250R用 FCR35Φ
XLR/XR250R用 FCR35Φ GB400/500用 FCR39Φ
GB400/500用 FCR39Φ








 OVERマフラー
OVERマフラー (参考)HARRISマフラー
(参考)HARRISマフラー












 カーボンチェーンケース
カーボンチェーンケース XR600Rスプロケットカバー
XR600Rスプロケットカバー ノーマルリアフェンダーと純正オプションアルミリアフェンダー
ノーマルリアフェンダーと純正オプションアルミリアフェンダー 製作した部品
製作した部品
 純正フェンダーと純正オプションアルミフェンダー
純正フェンダーと純正オプションアルミフェンダー



