 大分県本匠村の山腹にある聖嶽(ひじりだき)洞穴は、更新世人類化石と、細石刃が共伴した洞穴遺跡として、日本列島における旧石器時代末期の最も貴重な遺跡と目されていました。しかし最初に調査が行なわれたのは1962年と古いことであり、最近の技術やセンスを以て遺跡を再調査することで、より確かな学術資料として位置付けたいと考えられました。これは、以前から続いている「科学研究費特定領域研究:日本人および日本文化の起源に関する学際的研究」(通称:尾本プロジェクト)の一環として計画されたものです。
大分県本匠村の山腹にある聖嶽(ひじりだき)洞穴は、更新世人類化石と、細石刃が共伴した洞穴遺跡として、日本列島における旧石器時代末期の最も貴重な遺跡と目されていました。しかし最初に調査が行なわれたのは1962年と古いことであり、最近の技術やセンスを以て遺跡を再調査することで、より確かな学術資料として位置付けたいと考えられました。これは、以前から続いている「科学研究費特定領域研究:日本人および日本文化の起源に関する学際的研究」(通称:尾本プロジェクト)の一環として計画されたものです。
 大分県本匠村の山腹にある聖嶽(ひじりだき)洞穴は、更新世人類化石と、細石刃が共伴した洞穴遺跡として、日本列島における旧石器時代末期の最も貴重な遺跡と目されていました。しかし最初に調査が行なわれたのは1962年と古いことであり、最近の技術やセンスを以て遺跡を再調査することで、より確かな学術資料として位置付けたいと考えられました。これは、以前から続いている「科学研究費特定領域研究:日本人および日本文化の起源に関する学際的研究」(通称:尾本プロジェクト)の一環として計画されたものです。
大分県本匠村の山腹にある聖嶽(ひじりだき)洞穴は、更新世人類化石と、細石刃が共伴した洞穴遺跡として、日本列島における旧石器時代末期の最も貴重な遺跡と目されていました。しかし最初に調査が行なわれたのは1962年と古いことであり、最近の技術やセンスを以て遺跡を再調査することで、より確かな学術資料として位置付けたいと考えられました。これは、以前から続いている「科学研究費特定領域研究:日本人および日本文化の起源に関する学際的研究」(通称:尾本プロジェクト)の一環として計画されたものです。
マクロに見た場合、この背景には、日本列島における更新世人類化石が非常に限られたものであり、再検討が進む毎に、かつて資料と考えられていたものが、資料のリストからはずされるようになってきたことがあります。厳密な検証は進行中ですが、少なくとも積極的な資料として支持できないものが、次々に明らかになってきました。ただし沖縄本島南部出土の港川人や沖縄県内の資料は確実なものですが、石器や人工遺物が確認されておらず、文化的位置付けが出来ない状況でした。その点、聖嶽の貴重性が際立ってきます。とはいえ、聖嶽洞穴遺跡には幾つかの問題点がありました。特に、遺物が黒曜石に限られ、内容的にも周辺地域の文脈上特異であるという点が、解せなかったところです。黒曜石は概ね長崎県腰岳産と推定されていました。また古い後頭骨が見つかったのは第3地点の第III層(落盤の下)ですが、細石刃を含む石器は出土地点が異なり、第III層上面(II層との漸移層)とされていますが、後頭骨出土層位より上位のようで、層準としては不一致だったのです(洞穴内の層序認定の難しさもあると思われますが)。
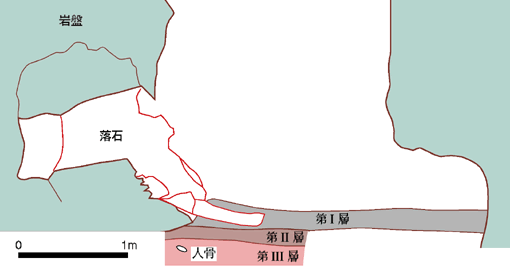 なお同洞穴は中近世に葬送の場となっていたことが推定され、前回調査でも表層(第I層)に大量の人骨片が散布したような状況で見つかっているようです。聖嶽(ひじりだき)という名称にも、何らかの意味があると考える方が自然でしょう。
なお同洞穴は中近世に葬送の場となっていたことが推定され、前回調査でも表層(第I層)に大量の人骨片が散布したような状況で見つかっているようです。聖嶽(ひじりだき)という名称にも、何らかの意味があると考える方が自然でしょう。
後頭骨出土地点の断面図
![]()
(1962年調査)
1999年の再調査で確認されたのは、1962年調査で人骨が包含されていたIII層(3層)が意外と新しい年代値を示したことでした。2000年8月24日付で公開されたデータは以下の通りです[公開URL](較正前の年代。但し本来の放射性炭素年代のBPは1950年起点なので、単純に50年を加えて2000年起点に換算してあります→yaと表記)。
| 1 | 1トレンチ(洞窟最奥) | 2層 | 木炭No.9 | 130±40ya. | |
| 2 | 10トレンチ(前回発掘の後頭骨付近の通路際) | 3層最上部 | 木炭No.3 | 100±40ya | |
| 3 | 13トレンチ(入口の人骨付近) | 3層対応…2〜3層漸移 | 木炭(No.なし) | 260±40ya | |
| 4 | 10トレンチ(前回発掘した後頭骨付近) | 3層最上部 | 木炭No.7 | 380±30ya | |
| 5 | 前回発掘時の排土 | 人骨 | 550±40ya | フッ素含量0.158% | |
| 6 | 前回発掘時の耕土 | 動物の肩甲骨 | 9,990±60ya | フッ素含量1.08% | |
| 7 | 10トレンチ | 3層 | 人骨(指骨) | (小さすぎて未測定) | フッ素含量0.529% |
試料2の木炭3は撹乱と考えて除外すると、試料3・4のデータから、III層(3層)最上部は(誤差を考慮すると)220〜410年前という年代値が与えられていることになります。試料5は旧排土中出土ながら放射性炭素とフッ素のデータが出されており、かなり新しい試料であることは確かです。試料6は約1万年前ですから単純に考えると縄文草創期の後半に相当します。試料7の人骨のフッ素含量は試料5と6の中間なので、年代は概ね縄文時代(あえて言えば前期〜晩期)と推定されます。
ここで重要なことは、フッ素年代は、同一遺跡・同一環境下での相対年代だということです。明らかになってきた聖嶽洞穴資料のフッ素含量は3群に分けられます(なお1962年出土骨のフッ素含量は当時の測定値)。
| 群 | 資料 | フッ素含量 | 放射性炭素年代 |
| A群 | 試料5(人骨)、1962年調査第I層人骨 | 0.158、0.20 | 500±40BP(試料5) |
| B群 | 試料7(指骨)、1962年調査後頭部、1962年調査第III層人骨 | 0.529、0.55、0.56 | ? |
| C群 | 試料6(動物の肩甲骨) | 1.08 | 9,940±60BP |
B群の年代は、A群とC群のほぼ中間に位置付けられ、よくまとまっていることが明らかです。これが新しい調査の成果といっていいでしょう。こうして見ると、およそ数千年前といったオーダーの縄文時代の包含層(B群が属する)があることは確かなようです。なお新しく発掘された石器は黒曜石製が2点ですが、撹乱中の出土で層準は不明です。
1962年調査で出土した後頭骨についての再検証は、予備的な調査しか行なわれておりませんが、レプリカの精査では、周口店上洞人101との類似は言われるほどでもなく、縄文人的でないことは認められるもの、異常に厚い骨厚を含め、江戸時代骨標本と比較すると、似たものが存在することが分かってきました(注1)。
問題なのは、平行して実施された1962年調査分の資料精査の過程で、次々に不可解な状況が露呈してきたことです。出土した石器資料の数が、特定できないことが最たるものでした。結局2001年3月6日の別府大学における記者会見で明らかになった所では、1981年報告書では26点が掲載されているのですが、正しくは14点だったようです(1961年の別府大による予備調査で6点、1962年本調査で8点:修正01.3.28)。しかも14点の内2点は現在行方不明、残りの過半数は縄文石器だというのです。単に縄文時代の石器が含まれているだけなら、新しい調査成果の年代観と矛盾しないのですが、26点が報告されたこと、実際には資料の特定も難しいなど、全体に整理が悪いというレベルを越えており、常軌を逸しているというべきです。また台形様のナイフ形石器と、細石刃、細石核の年代観も、かなりのずれがあります。一番の問題は、実測図にも記録されていたように、遺物に「がじり」が見られることでしょう(追加01.3.28)。今のところ真相は不明であり、聖嶽洞穴の石器遺物については全てペンディングの状態になったようです。
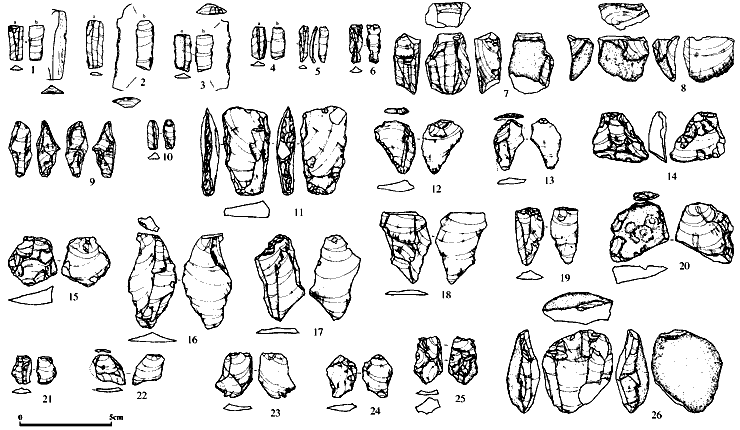
※なお本稿は本サイト独自の見解である。