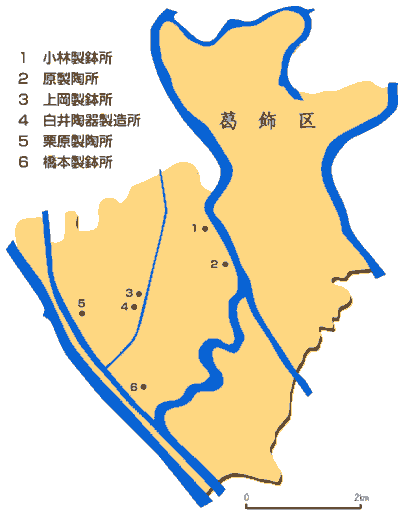
葛飾区における往時の窯元分布
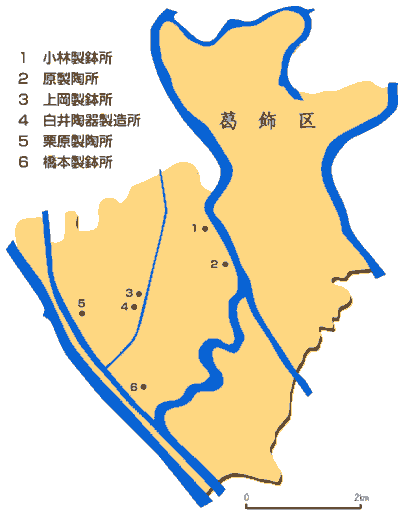
葛飾区における往時の窯元分布 |
今戸焼は、浅草の東北にあたる今戸や橋場、あるいは周辺地域で焼かれていた素焼系の日常雑器や土人形(今戸人形)等いわゆる江戸在地系土器のブランドである。瓦も達磨窯(だるま窯)で生産されていた(昭和37年の青戸における達磨窯−周囲に瓦が並べられている−の写真が残っている)。江戸時代において、今戸焼は隅田川の川辺の風物詩として浮世絵にも取り上げられてきたが、天保年間の江戸名所図会「長昌寺宗論芝」(橋場)には、どうやら二口焚と一口焚の地上窯が描かれている。二口焚はおそらく達磨窯に相当し、燻瓦(いぶし瓦)を製造していたと考えられる。。
今戸焼の土器窯については、桶窯、煙管窯(きせる窯)とも言われるが、少なくとも桶窯は(焚口の突き出し部はともかく)燃焼室と焼成室が一体化しているものを指すようである。煙管窯は燃焼室と焼成室が分離しているが、焼成室天井部が開口している構造をイメージさせる。実際、橋本2号窯はそうだし、同様の構造でさらに小型窯の写真も残っている(人形を焼いていた尾張窯)。橋本窯では天井の有無を問わず「ドロ窯」と呼ばれていたが、表面が泥製(スサ等を混ぜた粘土)の窯という事であり、フォークタームとしてはともかく、構造を指す用語ではない。なお、橋本窯はかつて今戸で操業していたが、関東大震災の後、葛飾に移転したという事である。そうした都市周縁への移転は、今戸焼ではよく語られているところである。

江戸名所図会 長昌寺宗論芝(部分) |
発掘された橋本1号窯は全長3.68m、幅2.3m。高さは確認できないが、往時の写真で見ると2号窯(高さ2.5m)より一回り大きく、3m以上あったと思われる。2号窯は天井が開口しているが、1号窯は天井を有していた。天井の有無は規模の大小によるとされ、製品の出し入れの都合のようだ(2号窯も後方が開いており、要するに中で人が立てるかどうかの違いのようだ)。前出の尾張窯はもっと小型で、上面の大きな開口部から製品を出し入れしていた。1号窯の内部構造は(2号窯と殆ど同様と思われるが)、焔の立ち上がり部にあたる「峠」に至る傾斜ははっきりしないが、達磨窯を一口焚きにしたような構造をなしている(とも受け取れるが、その関連性は詳らかではない)。
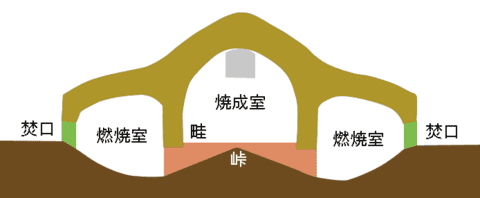
達磨窯の構造概念図(藤原学他 1997よりトレース) |
こうした伝統的で家内製手工業的な小型地上窯は、昭和40年代に急速に廃れていったが、今や日本中で操業の終焉を迎えつつあり、消え去ろうとしている。地域の産業遺産ないし文化財として保護の必要性が増しつつある。