24年ぶりの群馬の田舎
24年ぶりに、両親の実家に行ってみた。
両親が健在なうち、親戚の方々が健在なうちに、会っておきたかったからだ。
その他に、子供の頃、夏を過ごした“田舎”が、今はどうなっているのか確認したかった。
いや、個人的レベルでは、こちらの方の気持ちが大きい。
両親の田舎は、群馬県の藤岡市。
関東平野が終わりに差しかかり、小高い丘が裏にあるという場所だ。
そこで亡くなった祖父母は、農業を営んでいた。
夏休みというと、私達兄弟は、この田舎に預けられたのだ。
 |
|
| 父の実家の母屋。外見は戸袋だけ新しくなった。 |
|
 |
|
| 別の角度から。フェニックスもそのままだ。 |
|
 |
|
| 仏壇の前の襖。他にその外側に1枚ずつ。 |
|
 |
|
| 庚申山の全景。建物が明らかに増えている。 |
|
 |
|
| 田んぼ。 |
|
 |
|
| 用水路。右側は新たに作られた道。 |
|
 |
|
| 母の実家の門。結構立派だった。 |
|
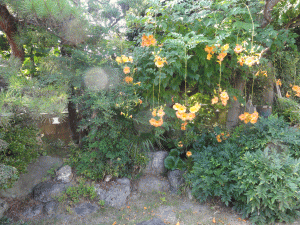 |
|
| 庭ののうぜんかづら。 |
|
子供の頃の記憶として“田舎”がある。
その後を追体験したいというのは、断片化した記憶をつなげたい気持ちからである。
果たして、“田舎”は変わっていた。
私が小学生の頃と現在の違いは、関越自動車道の開通が最たるものだろう。
以前は川越街道をひたすら進んでいたため、時間がかかったし、遠い所へ出掛ける感が大きかった。
それが、時間は短縮、道が整備されてて、簡単に行けるようになった。
それだけではない、高速の出口付近の道が新規に作られ、郊外型の量販店や飲食店がたくさんできていた。
この“都市化”の波が、インターチェンジからも駅からも離れた“田舎”にも押し寄せていた。
広々とした田んぼの中に、住宅が1軒また1軒と建てられていた。
田んぼのあぜ道が舗装され、自動車が入れるようになっていた。
それと、桑畑のあったところが、他の作物の畑となっていた。
群馬と言えば養蚕だが、もう養蚕をする家は皆無なのだろうか?
⇒子供の頃の記憶
蚕小屋と呼ばれる納屋の他に、座敷にまでお蚕を育てていて、茶の間と寝室以外はお蚕がいた。
そのため、お蚕からわずか1mくらいの距離で食事をしていた。
シンシンシンと、雨音のような食む音と共に食事。おいしいはずがない。
おまけに、私は足のない虫が大嫌い!
乳牛も兎も飼っていたのに、こちらもいない。
おかげさまで、食事時のハエに悩まされることもなくなったが。。
田んぼの真ん中を貫く用水路が、コンクリ造りになっていたのも、大きな変化だ。
おまけに、あぜ道よりも断然広い道が並行して走っている。
もはや用水路とは呼べない。
さらにこの道の存在で、宅地造成はなされるだろう。
⇒子供の頃の記憶
ここは、すすきやボケの木が生えてて、とんぼがたくさん飛んできていた。
手で簡単に捕まえられるため、バカみたいに取っていた。
また、川の淵がよくわからず、そばに寄ると落ちるという恐怖感があった。
子供の頃見た大きな建物は、大きくなってから見ると大したことないと言うが、私も感じた。
それは、父の実家と母の実家の間の距離感だ。
子供の足で15分はあったから、1km離れていると思っていた。
それがどうだろう。
背が高くなったため、なんと向こうの県道を走る車が見えるではないか!
それによると、ざっと600m。
曲がりくねってるあぜ道を考慮しても、700mくらいだ。
そんなもんなのか。自宅から駅よりも近いかも知れない。
また、裏の庚申山も、すっかり公園化して市民のものになっていた。
スポーツ施設もある様子。
⇒子供の頃の記憶
登って、草花を採取した。それを押し花にして、夏休みの課題にしていた。
また、真冬にはひょうたん池が氷結したので、上に乗って遊んだ。
遊歩道はあったものの、本当に何もない山(丘)だった。
が、変わらないものもある。
何と言っても、父の実家の母屋だ。
外のトイレはなくなり、裏の竹藪は枯れ、裏の畑がなくなっても、母屋だけはしっかりとあった。
蔵もあった。
近所の家もそのままだ。
それと、襖の墨絵。
桂林を思わせる、丸くてこんもりした山と川の流れ。
これが、父の記憶に無意識的に強く印象づけ、ついには父の桂林行きを促した。
父の幼少時からの異国への憧れや、心に根強く染みついたものの正体を確認したかったのだと思う。
私でさえ、あの墨絵の印象度は強烈で、桂林の写真を見た際、すぐにフラッシュバックした。
ましてや、毎日見ていた父にとっては。。
母の家の庭に咲くのうぜんかづらも、そのままだった。
子供心に、あそこだけ南国調だと思ったものだ。
それと、田んぼだ。
多少形は変わろうと、田んぼは田んぼ。
青々と天に向かってすくすくと育っていた。
子供の頃は、「田んぼしかない、何もない」とうんざりしていたが、今では癒しだ。
田んぼがあることで、安心する。
自給率を下げないためにも、農業を廃れさせてはいけない。
それを担っている農家の人々には、頭が下がる思いだ。
親戚の人達が、病気もなく元気にしていたことが、一番だった。
私のことも、よく覚えてくれていた。
皆、70代〜80代になり、今会わずしたら、お葬式の日に会うことになってしまう。
それだけは避けたかった。
取りとめもない世間話だったが、楽しい時間が送れたと思う。
暑い群馬で、その日は36℃は超えたことだろう。
息子が帰省する、娘も都合を合わせて帰って来るという日だったが、ドタキャンしてでも行った価値が十分にあった。
家族・・・親戚関係も含めて、人との繋がりを深く考えさせられる田舎だった。
特に今年は、東日本大震災が発生して、何が起きるかわからない、
今会える人には会っておかなければ、あとで後悔するだろうという強迫観念が働いていたのかもしれない。
でも、強迫観念にしろ何にしろ、日頃不義理の人と接するのは重要だ。
いいきっかけになった。
兄も田舎に行きたいと言ってくれたおかげだ。
私一人じゃ、押し切られていた。
それも、節電対策があって、夏休みが多く取れていたおかげなのだ。。
いずれにせよ、タイミングがぴったり合っていた。
行くべくして行ったのだ。
この“田舎行き”が、後に大きな意味合いを持つだろうと確信している。