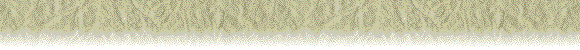 |
|
|
|
|
チェスキー・クルムロフ城の最も低い位置にある第一の中庭から城の探勝に出発しよう。 城内への入場は自由で、城の塔やガイデッド・ツアー、美術館等のみチケットが必要だ。
この第一の広い中庭には3つの入り口がある。 1つはラトラーン通りに面した東側のチェルヴェナー・ブラーナ、赤い門。 そして2つ目は南側のラゼブニツキー橋近くから続く城の階段
Zámecke schody、そしてもう一つは西からプラーシュチョヴィー橋の北側をフラードゥニ通り
Hradni からの第一の中庭の西の奥まったところの入り口だ。
右上写真は第一の中庭からチェルヴェナー・ブラーナを眺めたものだ。 この道がかなりの傾斜を持っていることがお分かりいただけるだろうか。
この第一の中庭は荘園形態をとっており、城の従僕や職人が住み、家畜が飼われていた部分だ。 写真右側の建物は厩舎だったもの、その西隣が古い執事長の家。 ここには執事長のほか書記や徴税人が居住していた。 チェルヴェナー・ブラーナの左側の建物はソルニツェ
Solnice と呼ばれるかつての塩の貯蔵庫。 広場の北側には奥まったところから病院、醸造所、鍜治場、氷蔵庫、そして東に折れて薬局があった。
|

チェルヴェナー・ブラーナからまっすぐ坂をあがったところにはかなり深い堀が切られている。 かつてここに1647年に建造された木製の跳ね橋があり、城を堅固に守っていたが、現在は石橋となっている。 その石橋の両側の掘割には16世紀から熊が飼われていて、2002年10月現在向かって左側に1頭(左写真)、右側につがいと合計3頭が飼われている。
石橋を渡り城館をくりぬいた通路を出るとそこが円形の噴水のある第二の中庭(下写真)。 ここは下層部の城、英語ではロワー・キャッスルと呼ばれている。 まず左手奥に南側に張り出し、その一部が第一の中庭に面しているフラデーク Hrádek =小さな城。 優美な塔を持った建物だ。
そして中庭の南側が造幣局 Mincovna の建物だ。 バロック・スタイルのこの建物はヨハン・クリスチャンの時代の1680年代に建築されたもので、1702年に皇帝のコイン発行禁止令が出るまでの期間エンゲンベルク・コインの鋳造をしていた。 現在この建物にチケット・オフィスとミュージアム・ショップが入っている。 この第二の中庭に達したらまずここへ行き、城内の3つのガイドつきのツアーの時間を確認してチケットを購入しておこう。 ここではガイドつきツアーがあるだけで、個人的に城館の見学をすることはできない。 ツアーはチェコ語のものと、ド イツ語および英語のものがあり、ドイツ語、英語のものとチェコ語のものでは料金に大きな差がある。 2002年10月のルート1の英語のツアーの料金は140コルナだった。 イツ語および英語のものがあり、ドイツ語、英語のものとチェコ語のものでは料金に大きな差がある。 2002年10月のルート1の英語のツアーの料金は140コルナだった。
北西の角は酪農場でバターやチーズの製造を行っていた。
北側からこの広場への入り口のある東側に連なるのが新執事長の家(右写真右側の建物)。 この建物はフラデークにもつながっており、建物前には現在4門の大砲が据えられている。 この建物の1階は1742年から1948年の間は城を警護するための衛兵詰め所になっていた。 現在1階と2階は城の図書館となっており、過去4世紀の間に収蔵された書物が所蔵されている。
第二の中庭は上層の城館へといざなう(右写真中央坂を登ったところが入り口)。
|
|
先へ進む前に、ガイディッド・ツアーの開始時間までに時間があればフラデークにある城の塔
Zàmeckà vez に登ってみよう。
フラデークは石橋を渡って第二の中庭に入った左側の奥にある。 塔へは階段を登っていくが、入場券売り場はその途中にあり、1人30コルナであった。
13世紀の中ごろにまでその起源をさかのぼることのできるこのフラデークと塔であるが、ロジェムベルク家のヴィルヘルムの時代、16世紀後半にイタリアの建築家アローニャのバルタサーレ・マッギー
Bardassare Maggi of Arogna によって質素なゴシック様式からルネッサンス様式へと大きくその外観は変えられた。 その際フラデークと塔とには壁面装飾が施され、現在見られるような優雅な外観となった。 また塔の上層部にはトランペット吹きの部屋と19のアーケードを持つギャラリーと呼ばれる部分が設けられた。 塔の最上部には時を知らせる鐘が設置されており、その下には円形の時計がはめ込まれている。
この多色が施された優美であったフラデークも時の経過とともにその美しさも減じ、それに伴いやがて倉庫や城の庸人の住居となり、ついに1760年からは時計のねじを巻く見張り人のみが使用するようになった。 その後時報はギャラリーからトランペットを用いて行うことになった。
フラデークと塔はその後19世紀と20世紀に修復が行われ、ルネッサンス様式の美しさを取り戻し、チェスキー・クルムロフのシンボルとしてよみがえった。
塔の160段と言われる階段を上りその360度の眺望を楽しもう。 上は第二の中庭から上層部の城館、中はヴルタヴァ川に島のようにせり出すオストロフとプラーシュチョヴィー橋方面にわたる狭い木橋。 下は第一の中庭とチェルヴェナー・ブラーナ、そしてその背後の旧フランシスコ派の修道院とエッゲンベルク家醸造所。
下右は同じくギャラリーから見た聖ヴィート教会方面。

城の塔。 アーケードと呼ばれる回廊部分まで登れる。
|
 |
|
|
第二の中庭からかなり長い地下通路を経て第三の中庭(右写真)に達する。 この小さな第三とそれに続く第四の中庭に面して建つ上層の城館
Horni zámek がこのチェスキー・クルムロフ城の宮殿部分で、ルート1とルート2のツアーはこの部分を巡る。
この第三の中庭にはベンチが置いてあり、2つのガイド・ツアーは右写真の建物の下の通路部分から出発する。 ちなみにルート1は左側すぐのところで、表示が出ているので心配はない。 その反対側はガイドの詰め所だ。
この宮殿の建物は14世紀中ごろから18世紀にかけて歳月をかけて建設され、徐々に貴族の館としての体裁を整えていった。 この2つの中庭から見る限り何の変哲もない宮殿のように見えるが、この岩山の上の宮殿工事は困難なものだった。 まず14世紀はじめにこの部分を平らにする工事から始めねばならなかった。 ことに第四の中庭の部分はヴルタヴァ川に向かって急峻な斜面となっていたため、3層の地下蔵がこの上層の宮殿部分の地下に作られている。 これらの一部は洞窟ギャラリーで見ることができる。
|
|
城内ツアーは2つあり、ルート1とルート2と呼ばれている。 それぞれ第三の中庭を出発点として下写真の赤線および青線の上層の宮殿部分を見学する。 ルート1は主に宮殿の部屋部屋を、ルート2はインテリアや肖像画ギャラリーなどを巡る。 この2つのコースによって、ロジェムベルク家、エッゲンベルク家そしてシュワルツェンベルク家の人々が生活した場所を見学することができる。 私の参加できたルート1のみを説明しよう。 なお城内ツアーで訪れる部屋部屋は写真撮影が禁じられているので、文章だけの説明となる。

ルート1の集合場所は第三の中庭の西南の隅の部屋で、その表示は第四の中庭へのトンネルを入ったところにありわかりやすい。 入り口からツアー・ガイドに従って階段を下に下りると聖イジー礼拝堂
kaple sv. Jirí だ。 この礼拝堂は当初の中世の城館部分の一部であったものを上層の宮殿を建築する際に移築したものだが、その際に各種の変更が施された。 現在の礼拝堂は1750年から1753年のウィーンの画家マティアス・アンドレー
Mathias André がロココ・スタイルのスタッコ(化粧漆喰)で壁面の装飾を施して完成されたものである。
次に訪れるのが一連のルネッサンス様式の部屋である。 第一の部屋は儀式用のもので、現在ダイニング・ルームとなっている第二の部屋とかつては一体だった。 第三の部屋は豪華に装飾され、しかも最も保存の良い部屋である。 壁の上半分には旧約聖書やギリシャ/ローマ神話の題材で描かれており、格間の天井には五弁のバラが描かれている。 壁はガブリエル・デ・ブロンデ
Gabriel de Blonde によって1577年より描かれたものである。 第四の部屋も同じく格間天井を持っているが、第三の部屋に比べると壁に直接絵が描かれていないだけシンプルだ。 ここには「パリスの審判」や「金の羊毛を持つヴィーレム・ロジェムベルクの肖像」等の絵画が飾られている。
 バロック様式の階段を登った所はこのルート1城内ツアーで唯一写真撮影の許された場所だ。 ただし窓からの屋外撮影だけだ。 右写真がその窓から撮ったものだ。 バロック様式の階段を登った所はこのルート1城内ツアーで唯一写真撮影の許された場所だ。 ただし窓からの屋外撮影だけだ。 右写真がその窓から撮ったものだ。
階段に面しているのがアンテカメラ Antecamera だ。 ここはその名前が示すようにこの城館の主に目通りを願う人々がまず通される部屋だ。
隣のエッゲンベルク・サロンには黄金の馬車が人目を引く。 これはエッゲンベルク家のヤン・アントニーン一世が外交使節の一員としてバチカンのウルバヌス8世を訪問した際に使われたもので、その時の従者の金モールで装飾された黒のヴェルベットの制服もこの部屋に展示されている。
次に訪れるのがシュヴァルツェンベルク・アパートメントまたはバロック・アパートメントと呼ばれる部分である。 バロック・ダイニングルームにあるタペストリーはルーベンスの原画をもとに17世紀中ごろにブリュッセルで織られたすばらしいものだ。 次はバルダヒン・サロンと呼ばれる部屋で、リラックスして談話やゲームに興じる場所であった。 その次は天蓋つきのベッドのある寝室だ。
このツアーの最後に訪れるのがマスカルニ・ザール Maskarni Sál、仮面舞踏会の間だ。 この広大な部屋は建築家アントモルテ
A. Antomolte によるものと推定され、その四囲の壁はレーデラー Josef Lederer
によって1748年に描かれたフレスコ画である。 このフレスコには、着飾った貴族たち、イタリアやフランスのコメディーの登場人物、中国人やトルコ人など多彩な人々が思い思いの衣装、そして表情や立ち居振る舞いで描かれており、また色彩も驚くほど豊かだ。 ルート1の最後の部屋と言うことで時間をかけて見られるのもうれしい。 このマスカルニ・ザールはチェスキー・クルムロフ国際音楽祭等のコンサート会場としても使われる。
|
|
第3の中庭から第4の中庭に移動しよう。 この広場の右側に有料トイレがあることを覚えておこう。 ここから先にはトイレはない。
第4の中庭からさらに進むと右側に洞窟ギャラリー Mezinárodní
Galerie Keramické Tvorby の入り口がある。 入場料30コルナを払って下へ下って行こう。 ここは第4の中庭の下の3層に建造されたゴシック様式の地下室である。 伝説によればチェコ王バーツラフ四世
Václav IV が1394年にロジェムベルク家により幽閉された場所だと言う。
上層の城館の項で述べたように、ここに城館を建てるためにまず土地を平坦にしかも強固なものにしなければならなかった。 複雑な地形にアーチを積み重ねていくと言う方法を取り、強度を確保するとともに労力を軽減したのであろう。 アーチ型のトンネルが複雑に張り巡らされている。
1990年代に入りここはアート・ギャラリーとして開放された。 ほの暗い照明の中に世界各地の美術品がディスプレイされている(右写真)。
|
|
 第4の中庭から洞窟ギャラリーの前のトンネルをくぐるとプラーシュチョヴィー橋の上に出る。 この橋は単に城の橋
most na plásti とも呼ばれ、城の上層部と城の庭園をつなぐ橋だ。 右写真が第五の中庭からプラーシュチョヴィー橋と上層の城館方向を眺めた写真だが、これを見るとポルティコの上に三層の回廊が乗っているだけのように見える。 第4の中庭から洞窟ギャラリーの前のトンネルをくぐるとプラーシュチョヴィー橋の上に出る。 この橋は単に城の橋
most na plásti とも呼ばれ、城の上層部と城の庭園をつなぐ橋だ。 右写真が第五の中庭からプラーシュチョヴィー橋と上層の城館方向を眺めた写真だが、これを見るとポルティコの上に三層の回廊が乗っているだけのように見える。
しかし実はこの下は深い谷となっており上層の城館部分と第四の中庭、城の劇場、城の庭園とはこの谷によって分断されている。 ここに木造の跳ね橋が最初にかけられたのは1686年で、その後何回か架け替えられた。
|

その後3層のアーチを持った石橋となり今日に至っている。 左の写真が城の北側のイェレニー庭園方面から見たプラーシュチョヴィー橋の全景だ。 この橋からのヴルタヴァ川と市街地の眺めもすばらしいことは言うまでもない。 石橋の上はごらんのようにいわゆる下駄履きの4階建てだ。 その最上階の回廊は城の庭園に通じ、下の回廊はマスカルニ・ザールと城の劇場を結んでいる。
第五の中庭に面してかつては防御施設や倉庫が建っていたが、エッゲンベルク家のヨハン・クリスチャンがここに1682年に劇場を建設させた。 その後1766年にシュヴァルツェンベルク家のヨーゼフ・アダムが当時の最新舞台装置を装備した劇場に大改造させた。
これらの舞台装置は手動ではあるが基本的には現代のものと変わらないすぐれたもので、また約300に及ぶ背景に使われたパーツも残っていて、13の基本的な情景とその組み合わせを今日でも再現できるということだ。 約600着の当時の衣装やその他小物類も現存すると言うのには驚かされる。
客席はベンチ形式の平土間と、中央にロイヤル・ボックスを持つ馬蹄形の2階バルコニー席とからなり、狭いがオーケストラ・ピットを有する。 客席の内部装飾は劇場建築に名をはせたジュセッペ・ガッリ・ビビエーナ
Giuseppe Galli Bibiena 派のハンス・ヴェッチェル Hans Wetschel とレオ・メルケル
Leo Märkel の作である。 舞台装置は大工のロレンツォ・マコー Lorenze
Makho の作で、情景を10から12秒で変えることができ、またろうそくとオイル・ランプによる照明装置も秀でたものであるという。 舞台後方には広大なバックステージがあり、さらに着替え部屋やランドリーまであるという本格的な劇場だ。
このバロック劇場は世界に2ヶ所しか現存しない18世紀後半のオリジナルな舞台装置を有する劇場の一つで、このチェスキー・クルムロフ城中最も価値のある場所だと言われる。 なおもう一つの劇場と言うのはスエーデンのドゥロッティングホルム
Drottingholm と言う場所にあるそうだ。
なお私たちは残念ながらここを見学することはできなかった。 したがってこのバロック劇場の項はもっぱら文献による。
|
|
劇場につらなるルネッサンス・ハウスと呼ばれる建物にそって右手に回廊の下をくぐって城の北側へ通ずる道がある。 ここでは右には曲がらずまっすぐ進む。 やがて両側に建物が現れる。 その先右側が城の庭園の入り口だ。
ヨハン・クリスチャンが17世紀後半に作らせたこの庭園は縦750m横150mと広大で、大きく4つの部分からなっていると言えよう。 それらは下からフランス庭園、イギリス庭園の幾何学模様部分、林、そして池だ。
 今入ってきた入り口から反対側の入り口へ通ずる道がこの庭園を大きく2分している。 城側の一番低い部分はフランス様式の庭園で、対称形の幾何学模様が美しい。 庭園を上下に分けるその道に隣接してカスケード噴水(上写真)がある。 今入ってきた入り口から反対側の入り口へ通ずる道がこの庭園を大きく2分している。 城側の一番低い部分はフランス様式の庭園で、対称形の幾何学模様が美しい。 庭園を上下に分けるその道に隣接してカスケード噴水(上写真)がある。
庭園の上層部分はイギリス庭園でこの噴水の位置からさらに500mも続く。 まず対称形の庭園があり、その先は左写真のような林だ。
この林の中に巨大な観客席が突然現れる。 おそらく悠に1000名は収容できようと言うスタンドだが、これが何と回転するそうだ。 最初のものは1956年に作られ、現在のものは1993年製の二代目。 夏の夜にはこれを用いたショーが催されると言う。
このスタンドの前には優雅なべラリー夏宮殿 Letohrádek Bellarie。 この建物の起源は1692年までさかのぼるが、その後何回か改修が行われた。 18世紀後半にアンドレアス・アルトモンテ
Andreas Altomonte によってロココ様式に変えられ今日に至っている。
さらにこの林を先に進むと島のある幅も150m近い池にぶつかり、庭園はここで終わりだ。
帰りは第五の中庭からずっと続く道側の塀に沿った道を落ち葉を踏みしめながら入り口のところまで戻った。 その道が下右の写真だ。
この上下に庭園を分ける道の反対側の出口の外には塀に沿って17世紀後半に建てられた庭師頭の住居がある。 ここは現在大きな暖炉のある 酒場となっている。 酒場となっている。
そこからフランス庭園を下り、左手の冬の乗馬学校の前を通り下へ降りていくとプラーシュチョヴィー橋の最上段の回廊が庭園に通じていることがはっきりと理解できる(下写真)。
|
|
 チェスキー・クルムロフ 旧市街 のページへ チェスキー・クルムロフ 旧市街 のページへ |
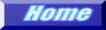  |
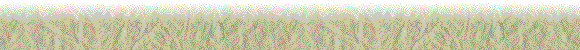 |
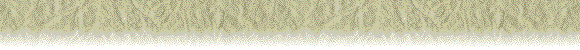


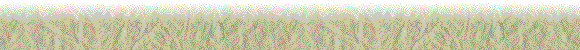

 イツ語および英語のものがあり、ドイツ語、英語のものとチェコ語のものでは料金に大きな差がある。 2002年10月のルート1の英語のツアーの料金は140コルナだった。
イツ語および英語のものがあり、ドイツ語、英語のものとチェコ語のものでは料金に大きな差がある。 2002年10月のルート1の英語のツアーの料金は140コルナだった。






 バロック様式の階段を登った所はこのルート1城内ツアーで唯一写真撮影の許された場所だ。 ただし窓からの屋外撮影だけだ。 右写真がその窓から撮ったものだ。
バロック様式の階段を登った所はこのルート1城内ツアーで唯一写真撮影の許された場所だ。 ただし窓からの屋外撮影だけだ。 右写真がその窓から撮ったものだ。 第4の広場と洞窟ギャラリー
第4の広場と洞窟ギャラリー 第4の中庭から洞窟ギャラリーの前のトンネルをくぐるとプラーシュチョヴィー橋の上に出る。 この橋は単に城の橋
most na plásti とも呼ばれ、城の上層部と城の庭園をつなぐ橋だ。 右写真が第五の中庭からプラーシュチョヴィー橋と上層の城館方向を眺めた写真だが、これを見るとポルティコの上に三層の回廊が乗っているだけのように見える。
第4の中庭から洞窟ギャラリーの前のトンネルをくぐるとプラーシュチョヴィー橋の上に出る。 この橋は単に城の橋
most na plásti とも呼ばれ、城の上層部と城の庭園をつなぐ橋だ。 右写真が第五の中庭からプラーシュチョヴィー橋と上層の城館方向を眺めた写真だが、これを見るとポルティコの上に三層の回廊が乗っているだけのように見える。 城の庭園
城の庭園 今入ってきた入り口から反対側の入り口へ通ずる道がこの庭園を大きく2分している。 城側の一番低い部分はフランス様式の庭園で、対称形の幾何学模様が美しい。 庭園を上下に分けるその道に隣接してカスケード噴水(上写真)がある。
今入ってきた入り口から反対側の入り口へ通ずる道がこの庭園を大きく2分している。 城側の一番低い部分はフランス様式の庭園で、対称形の幾何学模様が美しい。 庭園を上下に分けるその道に隣接してカスケード噴水(上写真)がある。  酒場となっている。
酒場となっている。