 じゃぱにぃず・びんてぃじ
じゃぱにぃず・びんてぃじ
GB楽器博物館
その他の楽器類/ウクレレ:13
伝説との遭遇

 お友達、Kさんが実家で発掘した、と言うウクレレを見せて頂いた。
お友達、Kさんが実家で発掘した、と言うウクレレを見せて頂いた。
なんと、フリクション・ペグ(木ペグ)のYAMAHA総単板No.80と言う代物。
今を去ること40年以上昔…
私が生まれて初めて両親にねだって買って貰ったウクレレも…
もっともっとずっと安物だったが、フリクション・ペグだった。
 YAMAHAサイトの旧製品カタログに型番・価格一覧だけが載っているが、その他のデータはない。
YAMAHAサイトの旧製品カタログに型番・価格一覧だけが載っているが、その他のデータはない。
また、どういう訳か、No.60の次は90で80と言う型番が、その記録にはない。
ググるとオークション出品モノや、現に使っているという方の記事はかなりの数出てくるのだが…
謎だ…
もっとも、YAMAHAサイトが公開しているデータはどうやら発売1963年03月以降のようなので、もしかしたら、これはもっと古いモノなのかも知れない…
| No.60A | 1,200円 | 発売1963年03月 |
| No.60C | 1,200円 | 発売1963年03月 |
| No.90 | 2,000円 | 発売1963年03月 |
| No.170 | 1,700円 | 発売1963年03月 |
| No.220 | 2,200円 | 発売1963年03月 |
| No.300 | 3,000円 | 発売1963年03月 |
| No.400 | 4,000円 | 発売1963年03月 |
| No.1000 | 10,000円 | 発売1963年03月 |
No.170以降、YAMAHA特有の「定価を表す型番」が付与されているので、この年に型番整理やきちんとした記録を始めたと言うことも考えられる。
オーナーの方のページを見つけた。
詳しい計測結果も記載されていた。
TOP: えぞ松単板
SIDE: メイプル単板
BACK: メイプル単版
NECK: マホガニー
F.Board: ローズウッド
Fret: 13(12fret joint) Craft: Japan(1960's)
Weight: 280g
Others: ウッドフリクションペグ
 その方の話だと
その方の話だと
母親の荷物から、フォーククルセーダースの“おらは死んじまっただ(帰ってきたヨッパライ)”とか、“モンキーズのテーマ”等のドーナツ盤と一緒に出てきて、母親が結婚前に働いていたときに買ったもので、このウクレレもその頃に買ったもの。
だそうである。
“帰ってきたヨッパライ”の大ヒットが1968年、モンキーズの方も、日本でも、TVシリーズが開始されたのが1967年10月、“モンキーズのテーマ”の大ヒットで爆発的な人気を呼び、武道館でコンサートを行ったのが1968年10月2日なので、YAMAHAサイトの資料とは5年ほどタイムラグがある。
この方は、No.80を
「このウクレレはNo.80という名前がついているが、これはどうやら当時の値段で安易にネーミングされていたらしい。80ってのは800円だか、8000円で売っていたということのようだ。」
と書かれているが、8,000円は高すぎるし、800円も1968年頃の製品としては少々安すぎる気がしないでもない。
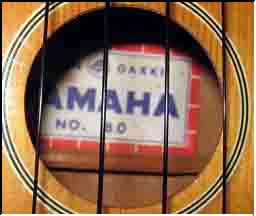
KさんのNo.80はブランドマークに現在の「音叉マーク」ではなく、「ピアノマーク」が使われている。
調べてみたのだが、YAMAHAが「ピアノマーク」を廃止した年代は判らなかった。
YAMAHAサイトの資料では1963年03月の時点ではNo.80はラインナップされていないようなので、もしかしたらこの方は、デッドストック…というか、当時はいくらでもあったと思われる、仕入れたが店頭に吊しっぱなしだった商品を入手したのかも知れない。
 KさんのNo.80はもの凄く小さく感じるが、多分これはMartinウクレレのサイズをそのまま模したモノだと思われる。
KさんのNo.80はもの凄く小さく感じるが、多分これはMartinウクレレのサイズをそのまま模したモノだと思われる。
若干のネック順反りとブリッジ前の窪みはあるが、楽器として致命的な狂いではない。
但し、ナット溝が浅すぎて、1フレット押弦で音程が♯してしまうのと、フリクション・ペグの乾きすぎでチューニングが出来ないのはどうにも…
しかし、ナット溝は調整でどうにでもなるし、フリクション・ペグはバイオリン・ペグ専用のクレヨンとかチョーク(正式には「ペグソープ」「ペグドープ」、商品名はCOMPOSITION FOR PEGSと言うらしい。1,000円位)とか言われる物を使えば何とかなるのではないだろうか?
(普通のクレヨンや白墨は使っちゃイカンぞ、多分)
 Gotohのペグに交換してしまうのが一番手っ取り早いのだが、木ペグの楽器は貴重だし、美しいので、これは是非このまま使って欲しい。
Gotohのペグに交換してしまうのが一番手っ取り早いのだが、木ペグの楽器は貴重だし、美しいので、これは是非このまま使って欲しい。
「売ってしまえ!」
との御意見もあった様だが…
売ったところでせいぜいつり上げて、当時の定価の10倍程度にしかならんだろう。
買ってくれる人が愛してくれる人なら良いんだけどね…
ちゃんと「楽器に戻して」あげて、ガシガシ使った方がよいのではないかと。
Kさんは、全く売るつもりはなく、木ペグも気に入っているので当然このまま、とのこと。
 Kさんは、知り合いから「松ヤニでもいいんじゃない?」と言われらしい。
Kさんは、知り合いから「松ヤニでもいいんじゃない?」と言われらしい。
冷静に考えれば、「ペグソープ」「ペグドープ」とか呼ばれるフリクション・ペグ用の塗布剤(コンポジション)…
これ、ほぼバイオリン(ビオラ、チェロ含む)専用である。
現在、他にこれを使うような楽器はない。
(コントラバスは現在全てが機械式ペグなので必要ない。)
で、これが必要な楽器はみんな擦弦楽器で、必ず松脂を携行している楽器なのである。
その人達が手持ちの松脂を使わないで結構お高い専用薬剤を使うと言うことは…
松脂は何らかの理由で使えないと判断して良いと思う。
実際には「その場しのぎ」として、時折使われるという画材のクレヨンや蝋燭(これは潤滑剤)、白墨(これは摩擦材)で一時は良くなると思うが…
一旦これらを付けてしまうとペグとヘッドの当たり面が駄目になってしまうのではないか?
チョークなどは摩擦は増えるが、あの粉末はかなり粒子が大きいので穴もペグも磨り減ってしまうはずである。
多分、松脂にもそう言った副作用があるのではないか、と…
写真はKさんが入手して手当てに使った「ペグ・ドープ」
 さて、調整である。
さて、調整である。
順反りと腹歪みは若干あるが、演奏上支障が出るほどではない。
順反りと腹歪みについては経年変化で仕方がないレベルで、これはこのまま使うべきだろう。
ウクレレを…特に弾き語り歌伴に使うなら、ローポジションがちゃんと出ればいいわけで、Kさんの用途としては問題はないと判断。
ペグはKさんの手当てが、上手く効いている様で、実用的には何とか問題ない様だ。ナット調整で蘇るだろう。
 サドル調整をしようと思ったら、木製サドルで、塗装仕上げ。
サドル調整をしようと思ったら、木製サドルで、塗装仕上げ。
溝切りで弦の半径分程下げるが、これ以上やってしまうと弦振動に影響が出そうなのでここまで。
今回はナット調整で何とかする。
サドルが異常に高いのでハイポジション側の音程は宜しくないが、唄伴様にローポジ専用と割り切れば、この音はかなり使えると思う。
昔の楽器って、なんだか最初から弦高が高いものが多い様な気がする。
ナット側でギリギリ限界までアクションを下げてみた。
これで行けるんじゃないだろうか?
 サドルは調整しろが少ない、と言うかほとんど無い。
サドルは調整しろが少ない、と言うかほとんど無い。
木製サドルの上塗装してあるので出来れば表に出るところ削りたくないし。
(自分のものだったら、一旦外してブリッジの方削っちゃうが…)
何となくね、このブリッジ寸法、大昔のサドルレス・ブリッジのサイズを踏襲しているのではないかという気もする。
今回はブリッジには手を付けないでサドルに弦溝を掘ることで気持ちだけ弦高を下げる。
こうして、不精者に預けられて半年放置状態にあったジャパニーズビンテージは持ち主の元へ帰っていった。
これで持ち主の音楽の幅が広がってくれれば、それは嬉しいことである。
 GB楽器博物館 目次へ戻る
GB楽器博物館 目次へ戻る
 トップページへ戻る
トップページへ戻る

 じゃぱにぃず・びんてぃじ
じゃぱにぃず・びんてぃじ
お友達、Kさんが実家で発掘した、と言うウクレレを見せて頂いた。
YAMAHAサイトの旧製品カタログに型番・価格一覧だけが載っているが、その他のデータはない。
その方の話だと
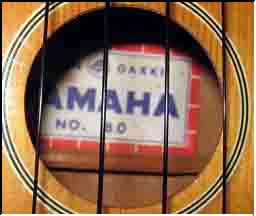
KさんのNo.80はもの凄く小さく感じるが、多分これはMartinウクレレのサイズをそのまま模したモノだと思われる。
Gotohのペグに交換してしまうのが一番手っ取り早いのだが、木ペグの楽器は貴重だし、美しいので、これは是非このまま使って欲しい。
Kさんは、知り合いから「松ヤニでもいいんじゃない?」と言われらしい。
さて、調整である。
サドル調整をしようと思ったら、木製サドルで、塗装仕上げ。
サドルは調整しろが少ない、と言うかほとんど無い。
 GB楽器博物館 目次へ戻る
GB楽器博物館 目次へ戻る トップページへ戻る
トップページへ戻る